もちろん暦は様々な性格を持ち、様々な働きをしているので、一概には言えないのは承知です。そして、この多面性ゆえに暦論議があるように私には思えます。そこで、暦論議を、基礎から整理することができないものかと考えて、このトピを設定しました。
まず、社会生活においては、“人々のスケジュールを管理するための規範”として暦は存在していると思います。いわば、時の権力体制による強制される規則としての性格であり、現在「グレゴリオ暦」が獲得している通りです。これは権力によって人々に共通の暦が強制されているという単なる“権威”であり、暦の内容に直接には関係のない性格です。?
次に、“ある暦日の同一性を確定するという働き”やその時点からの年月といった“経過時間の長さを知る目安”という働きがあると思います。いわば“時間のモノサシ”的な働きであり、暦に対して多くの人が抱くイメージではないでしょうか。現代の都市文化では、パソコンのファイルに刻まれるグレゴリオ暦+時刻などはこの目的で用いられていると言えます。この日付、つまりキリスト生誕紀元年(西紀)+グレゴリオ暦は?の理由によって広く用いられています。西紀という「紀年法」は近年内だけを考えるには十分に古く便利です。が、変則的なグレゴリオ暦月日の方は、私たちが単にこの変則性に慣れてしまっているというだけのように思えます。むしろ「元日または立春起点の通算日」あるいは「ユリウス通日」の方が便利に思われます。また、“歴史上の暦日の同一性を確定するという働き”のためには「年干支」や「日干支」や「曜日」が役に立ちよく使われます。?
さらに、暦には“時の道理や意味を知る道標”という働きがあると思います。実は暦の歴史において最も重要視されて来ながら現在は最もないがしろにされているものではないかという気が私にはします。例えば十二支は本当は時刻と暦月への配当が本質であり、陰と陽あるいは明と暗を循環するサイクルの位相を知る標識ですし、日付とは本来月齢を表し電気の無い時代の夜間照明や海の潮汐に対応したものであったはずです。八十八夜なども百姓にとって遅霜の目安として活用されてきたはずです。たくさんの暦註や占断や年中行事には、暦のこの働きから展開してきたものが多いように思います。西洋では新しい季節の始まりを告げる春分と満月と日曜の三つの条件で復活祭を行うこの日取りも、暦のこの働きによるものととらえることができます。?
まず、社会生活においては、“人々のスケジュールを管理するための規範”として暦は存在していると思います。いわば、時の権力体制による強制される規則としての性格であり、現在「グレゴリオ暦」が獲得している通りです。これは権力によって人々に共通の暦が強制されているという単なる“権威”であり、暦の内容に直接には関係のない性格です。?
次に、“ある暦日の同一性を確定するという働き”やその時点からの年月といった“経過時間の長さを知る目安”という働きがあると思います。いわば“時間のモノサシ”的な働きであり、暦に対して多くの人が抱くイメージではないでしょうか。現代の都市文化では、パソコンのファイルに刻まれるグレゴリオ暦+時刻などはこの目的で用いられていると言えます。この日付、つまりキリスト生誕紀元年(西紀)+グレゴリオ暦は?の理由によって広く用いられています。西紀という「紀年法」は近年内だけを考えるには十分に古く便利です。が、変則的なグレゴリオ暦月日の方は、私たちが単にこの変則性に慣れてしまっているというだけのように思えます。むしろ「元日または立春起点の通算日」あるいは「ユリウス通日」の方が便利に思われます。また、“歴史上の暦日の同一性を確定するという働き”のためには「年干支」や「日干支」や「曜日」が役に立ちよく使われます。?
さらに、暦には“時の道理や意味を知る道標”という働きがあると思います。実は暦の歴史において最も重要視されて来ながら現在は最もないがしろにされているものではないかという気が私にはします。例えば十二支は本当は時刻と暦月への配当が本質であり、陰と陽あるいは明と暗を循環するサイクルの位相を知る標識ですし、日付とは本来月齢を表し電気の無い時代の夜間照明や海の潮汐に対応したものであったはずです。八十八夜なども百姓にとって遅霜の目安として活用されてきたはずです。たくさんの暦註や占断や年中行事には、暦のこの働きから展開してきたものが多いように思います。西洋では新しい季節の始まりを告げる春分と満月と日曜の三つの条件で復活祭を行うこの日取りも、暦のこの働きによるものととらえることができます。?
|
|
|
|
コメント(2)
ところで、旧暦ブームの昨今、新暦vs旧暦の話題が時々起こっていますよね。この議論において、グレゴリオ暦は一般的あるいは国際的だから正しいというような意見は私には体制的?な権威主義に思えて仕方ありません。
また、グレゴリオ暦の方が季節のズレが無いという意見は、旧暦が太陰と太陽との複合暦であるという点を切り捨て陰暦という点ばかりに注目しすぎているように思えます。純太陽暦である二十四節気は、グレゴリオ暦ではなくまぎれもなく旧暦です。現に書籍の図版等にある古暦の写真などでも暦の中に二十四節気が記載されているのが確認できます。例えば、天保暦(1842)よりも古い貞享六年(元禄二年)(1689)の貞享暦の図版が『暦を知る事典』(東京堂出版)にはありますが、正月十五日のところに立春が記載されているのが判ります。季節の目安として信頼できる二十四節気によって正確な季節推移は読み取ったことが想像できます。季節の正確さを必要とする場合の日付は立春起算の八十八夜や二百十日もありましたし。だから、旧暦の月日だけを取り上げて季節のズレを非難するのはおかしいと思います。むしろ、季節の目安としてはグレゴリオ暦月日は歪んでいると思います。西洋的な季節区分は3/1が春の初日、同様に6/1、9/1、12/1がそれぞれ夏秋冬の初日ですがこれらの日に一体どんな意味があるでしょうか。一ヶ月の長さは暦の支配者の都合ででたらめに歪められており、月日の数字には日々を区別する以上の意味はありません。新暦時代の現在、単なる数字の語呂合わせだけで記念日が作られる理由もそのためではないでしょうか。新暦では、潮干狩り(上巳の節供)や夜空(七夕)に関係する旧暦節供のようなものは不可能です。
それから、グレゴリオ暦はルールが単純だが旧暦は全く不規則だから一般人が計算して構成することが困難という意見もありますよね。確かに10年後、20年後のスケジュールを立てようという時に旧暦だと月日と曜日の対応あるいはユリウス通日で何日かが簡単には分からないということになります。でも、どうなのでしょう? 旧暦時代の日本は毎月一日、六日、十一日、十六日、二十一日、二十六日の六回が休日だったようです。旧暦の中にも古くから曜日(月火水木金土日)はありましたが、日の吉凶要素だったようで、曜日に基いて休日を設定するのはもともと、7日ごとの安息や礼拝を義務付けるユダヤ教・キリスト教の習慣です。キリスト教国でもない国がどうしてそれに従わなければならないのでしょうか?
世界を見渡すとき、暦というものはその土地の風土に合ったものが一番良いと思うので、私が旧暦支持者であろうと旧暦が一番と言うことはできません。しかし、グレゴリオ暦が素晴らしいとか、旧暦より良いとか全然思えません。グレゴリオ暦は、一年の長さを変則的な12ヶ月の合計日数で上手く合わせているだけで、途切れない7日ごとの安息日を守る生活サイクルを強制する暦であるように思えます。暦において本当は非常に重要である“時の節目”を全く無意味化してしまっています。暦を“時間のモノサシ”とだけ考える機械的な発想はそこから出ているのではないでしょうか。そしてこれは、人間を自然から切り離し人工的で機械的な時間に人間を適応させる結果を導いているのではないでしょうか?
また、グレゴリオ暦の方が季節のズレが無いという意見は、旧暦が太陰と太陽との複合暦であるという点を切り捨て陰暦という点ばかりに注目しすぎているように思えます。純太陽暦である二十四節気は、グレゴリオ暦ではなくまぎれもなく旧暦です。現に書籍の図版等にある古暦の写真などでも暦の中に二十四節気が記載されているのが確認できます。例えば、天保暦(1842)よりも古い貞享六年(元禄二年)(1689)の貞享暦の図版が『暦を知る事典』(東京堂出版)にはありますが、正月十五日のところに立春が記載されているのが判ります。季節の目安として信頼できる二十四節気によって正確な季節推移は読み取ったことが想像できます。季節の正確さを必要とする場合の日付は立春起算の八十八夜や二百十日もありましたし。だから、旧暦の月日だけを取り上げて季節のズレを非難するのはおかしいと思います。むしろ、季節の目安としてはグレゴリオ暦月日は歪んでいると思います。西洋的な季節区分は3/1が春の初日、同様に6/1、9/1、12/1がそれぞれ夏秋冬の初日ですがこれらの日に一体どんな意味があるでしょうか。一ヶ月の長さは暦の支配者の都合ででたらめに歪められており、月日の数字には日々を区別する以上の意味はありません。新暦時代の現在、単なる数字の語呂合わせだけで記念日が作られる理由もそのためではないでしょうか。新暦では、潮干狩り(上巳の節供)や夜空(七夕)に関係する旧暦節供のようなものは不可能です。
それから、グレゴリオ暦はルールが単純だが旧暦は全く不規則だから一般人が計算して構成することが困難という意見もありますよね。確かに10年後、20年後のスケジュールを立てようという時に旧暦だと月日と曜日の対応あるいはユリウス通日で何日かが簡単には分からないということになります。でも、どうなのでしょう? 旧暦時代の日本は毎月一日、六日、十一日、十六日、二十一日、二十六日の六回が休日だったようです。旧暦の中にも古くから曜日(月火水木金土日)はありましたが、日の吉凶要素だったようで、曜日に基いて休日を設定するのはもともと、7日ごとの安息や礼拝を義務付けるユダヤ教・キリスト教の習慣です。キリスト教国でもない国がどうしてそれに従わなければならないのでしょうか?
世界を見渡すとき、暦というものはその土地の風土に合ったものが一番良いと思うので、私が旧暦支持者であろうと旧暦が一番と言うことはできません。しかし、グレゴリオ暦が素晴らしいとか、旧暦より良いとか全然思えません。グレゴリオ暦は、一年の長さを変則的な12ヶ月の合計日数で上手く合わせているだけで、途切れない7日ごとの安息日を守る生活サイクルを強制する暦であるように思えます。暦において本当は非常に重要である“時の節目”を全く無意味化してしまっています。暦を“時間のモノサシ”とだけ考える機械的な発想はそこから出ているのではないでしょうか。そしてこれは、人間を自然から切り離し人工的で機械的な時間に人間を適応させる結果を導いているのではないでしょうか?
たびたび指摘していることでもあるのですが、暦には天文の周期を近似的な数値で月日にまとめるという数理的な性格と、天文の現象に従うという天文的な性格とがあります。現在の新暦(グレゴリオ暦)とは前者の性格を優先した暦法の代表であり、一方西洋天文学に裏付けられた旧暦はいわば後者を優先した暦の代表といえると思います。
これは、太陽暦か太陰太陽暦かという問題とは全く別次元の話です。西洋においては太陽暦を使用する前の陰暦時代から月々の日数というものを正確な新月にではなく人間の都合で決定してきているのです。これは、天文現象よりも人工的な数理を優先するという西洋思想の現れ方の一つなのです。日本の旧暦にも似た太陰太陽暦であるユダヤ暦においても、天象の正確な時刻にではなく近似された周期に基づいた数理に従っています。一方、東洋の旧暦においては、グレゴリオ暦と同様な太陽暦である二十四節気がありますが、二十四節気の日取りは一年を24等分した切れ目を含む日を節または中気の入り日にするという考え方からして天象に準拠しようとする思想が窺われます。この思想は、弘化一年(1844)施行の西洋天文学の計算を導入した天保暦以降はさらに二十四節気が恒気(常気)法から定気法へ切り替わることで洗練されて現在の旧暦に至っています。
つまり、暦法が太陽暦だとか太陰太陽暦だとか言う以前の問題として、暦が人工的な数理論でなければならないという西洋思想的な発想に基づくか、自然の摂理ともいえる天象に忠実であることを尊重すべきだとする東洋思想的な発想に基づくか、という違いの問題があると思うのです。暦の計算をする人々はよく「ルールがシンプルで季節のずれが少ないグレゴリオ暦が優れている」という趣旨の意見を言われますが、これは太陽暦賞賛である以前に西洋思想の表明であるように思います。(明治・大正・昭和時代の暦の権威達はそういう意味でみんな“西洋思想かぶれ”と言えるかもしれません・・・)
この問題に関して私の意見としては、東洋思想的な態度を支持したいということです。そもそも暦は数理である以前に天象であると考えているからです。いくら厳密に数理で暦法を組み立てようと、絶対に永久暦にはならないでしょう。必ず、ある時点で矛盾が生じてイレギュラーな閏や変更をせざるをえなくなるのです。
例えば、現在の時間は「グレゴリオ暦&定時法」によって決められていますが、しばしば挿入されている“うるう秒”の挿入には周期が定まっているでしょうか? 太陽の運行による1日(平均太陽時による24時間)と(セシウム原子時計による)86400秒とのずれが1秒に近づいたら日和見的にうるう秒を挿入するのでしょうか? このように、時法においても西洋思想と東洋思想の違いが定時法と不定時法という形で現れてきます。西洋思想らしく原子秒によって厳格に一日の長さを確定するわけですが、結局天象とのずれが生じるので閏秒で天象に合わせるわけです。太陽の高さや方角で時刻が決まる不定時法にはうるう秒などという厄介な問題はそもそも無いでしょう。
もう一つ、グレゴリオ暦は季節のずれがいくら少ないといっても全くずれないわけではありません。2621年毎に1日ずつ季節がずれていくようです。しかしグレゴリオ暦にはこのずれを補正するルールはありません。歴史を見ても、数理で決まっている暦というものは、西紀1582年に10日間の日付が削除されたり、紀元前46年に閏日が90日間も挿入されたりといった大規模な閏による修正や改暦が必要になる宿命にあるのです。つまり、数理は天象を支配できないのです。
暦を数理で決定するということは、天文学と暦学とが一緒に天象の周期や法則を見つけていくという段階にこそふさわしいものだと私は思います。ですが、天文学が著しく発達し天文計算が精密に行うことが可能になった現代においては、数理だけで暦法、時法を決定出来なければならないという思想はもはや保守的であり時代遅れではないかと私は思います。
結局、天象に従っている定朔(正確な新月の瞬間を尊重すること)と定気(太陽黄経を季節の指標にすること)によりずれの補正を恒常的に行っていく現在の旧暦は永久使用のできる暦法だと思います。
これは、太陽暦か太陰太陽暦かという問題とは全く別次元の話です。西洋においては太陽暦を使用する前の陰暦時代から月々の日数というものを正確な新月にではなく人間の都合で決定してきているのです。これは、天文現象よりも人工的な数理を優先するという西洋思想の現れ方の一つなのです。日本の旧暦にも似た太陰太陽暦であるユダヤ暦においても、天象の正確な時刻にではなく近似された周期に基づいた数理に従っています。一方、東洋の旧暦においては、グレゴリオ暦と同様な太陽暦である二十四節気がありますが、二十四節気の日取りは一年を24等分した切れ目を含む日を節または中気の入り日にするという考え方からして天象に準拠しようとする思想が窺われます。この思想は、弘化一年(1844)施行の西洋天文学の計算を導入した天保暦以降はさらに二十四節気が恒気(常気)法から定気法へ切り替わることで洗練されて現在の旧暦に至っています。
つまり、暦法が太陽暦だとか太陰太陽暦だとか言う以前の問題として、暦が人工的な数理論でなければならないという西洋思想的な発想に基づくか、自然の摂理ともいえる天象に忠実であることを尊重すべきだとする東洋思想的な発想に基づくか、という違いの問題があると思うのです。暦の計算をする人々はよく「ルールがシンプルで季節のずれが少ないグレゴリオ暦が優れている」という趣旨の意見を言われますが、これは太陽暦賞賛である以前に西洋思想の表明であるように思います。(明治・大正・昭和時代の暦の権威達はそういう意味でみんな“西洋思想かぶれ”と言えるかもしれません・・・)
この問題に関して私の意見としては、東洋思想的な態度を支持したいということです。そもそも暦は数理である以前に天象であると考えているからです。いくら厳密に数理で暦法を組み立てようと、絶対に永久暦にはならないでしょう。必ず、ある時点で矛盾が生じてイレギュラーな閏や変更をせざるをえなくなるのです。
例えば、現在の時間は「グレゴリオ暦&定時法」によって決められていますが、しばしば挿入されている“うるう秒”の挿入には周期が定まっているでしょうか? 太陽の運行による1日(平均太陽時による24時間)と(セシウム原子時計による)86400秒とのずれが1秒に近づいたら日和見的にうるう秒を挿入するのでしょうか? このように、時法においても西洋思想と東洋思想の違いが定時法と不定時法という形で現れてきます。西洋思想らしく原子秒によって厳格に一日の長さを確定するわけですが、結局天象とのずれが生じるので閏秒で天象に合わせるわけです。太陽の高さや方角で時刻が決まる不定時法にはうるう秒などという厄介な問題はそもそも無いでしょう。
もう一つ、グレゴリオ暦は季節のずれがいくら少ないといっても全くずれないわけではありません。2621年毎に1日ずつ季節がずれていくようです。しかしグレゴリオ暦にはこのずれを補正するルールはありません。歴史を見ても、数理で決まっている暦というものは、西紀1582年に10日間の日付が削除されたり、紀元前46年に閏日が90日間も挿入されたりといった大規模な閏による修正や改暦が必要になる宿命にあるのです。つまり、数理は天象を支配できないのです。
暦を数理で決定するということは、天文学と暦学とが一緒に天象の周期や法則を見つけていくという段階にこそふさわしいものだと私は思います。ですが、天文学が著しく発達し天文計算が精密に行うことが可能になった現代においては、数理だけで暦法、時法を決定出来なければならないという思想はもはや保守的であり時代遅れではないかと私は思います。
結局、天象に従っている定朔(正確な新月の瞬間を尊重すること)と定気(太陽黄経を季節の指標にすること)によりずれの補正を恒常的に行っていく現在の旧暦は永久使用のできる暦法だと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
暦 こよみ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
暦 こよみのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
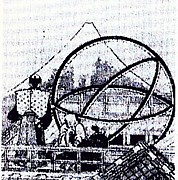


![月夜見 [ツクヨミ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/3/72/1110372_2s.gif)



















