グレゴリオ暦とは、西洋化された現代の多くの国において一般的に用いられている暦法(月日の割り当て方)の固有名です。日本においては、明治の文明開化(伝統破壊)において廃止された伝統的な陰暦(旧暦)に対して、新暦とか太陽暦とも呼ばれているものです。現在の政府、役所等で公式に使う日付であり、カレンダーやスケジュール帳、PCの内蔵時計などで一般的に用いられており、私たちに最も馴染み深い暦法です。
私たちの時間尺度の基準にさえなっており、あまりにも当たり前すぎて疑問を持つことさえ少ないこの“グレゴリオ暦”という暦法について語り合ってみましょう。例えば、2月だけが28日なのはどうしてなのかとか、元日(年始の起日つまり1月1日)はどうして北半球が冬の寒の入りの頃なのかとか、そもそも季節の狂いが少ない「太陽暦」だと言われるグレゴリオ暦にとっての季節とは何かとか…
私たちの時間尺度の基準にさえなっており、あまりにも当たり前すぎて疑問を持つことさえ少ないこの“グレゴリオ暦”という暦法について語り合ってみましょう。例えば、2月だけが28日なのはどうしてなのかとか、元日(年始の起日つまり1月1日)はどうして北半球が冬の寒の入りの頃なのかとか、そもそも季節の狂いが少ない「太陽暦」だと言われるグレゴリオ暦にとっての季節とは何かとか…
|
|
|
|
コメント(4)
週の起源はいま一つ判然としない。ユダヤ教では天地創造に6日を費やし神は7日目である土曜日に安息日(ヨム・シャバット)を取ったから、神が休んだこの7日めを休日とし、このサイクルを守ることが宗教上の絶対的な掟として守られている。それは、紀元前6世紀頃かららしい。そして、このシャッバトSabbathという語からラテン系語圏での土曜日を意味するサバトという語になっている(ちなみに、英語のSaturdayは別語源)。ところが、日々に7日周期の暦註を付けることは古代メソポタミア文明のカルデア人(B.C.7c後半〜B.C.538)が肉眼観測できる5惑星に月と太陽を加えた7天体による運勢を時間や日々に配当したことが基になっているとも言われる。はたして、ユダヤ教とカルデア人の天文占星学とのどちらの方が古いのか、という問題になってくる。どこかの本には、ユダヤ教の天地創造+安息日という7日の周期はカルデア人が作ったこの7日周期を基にしたのかもしれないと言うことが書いてあった気がする。うろ覚えだが、ユダヤ人はカルデア人の子孫ということもどこかの本でちらっと見たことがある。ということは、やっぱりカルデア人が作った7日周期の曜日配当が先で、この7日周期を基に『旧約聖書』の「創世記」が書かれ、そしてユダヤ人がそれを厳格に守り、そしてキリスト教を導入した古代ローマ帝国が紀元前1〜2世紀から暦に取り入れ定着させたということになるだろうか? いずれにせよ紀元前7〜6世紀頃の歴史問題だ。
ともあれ、安息日を定めるこの7日周期はユダヤ教からキリスト教にも安息する曜日を変更しながらも受け継がれ、イスラム教にもまた同様に安息する曜日を変更して受け継がれている。だらら、7日周期を正確に連続させることは、たとえそれが天象的には全く意味のない人為的な周期あるとしても、これら三大一神教が世界的に支配的である限り変えることが許されないことだろう。だから、曜日を持たない日を一年に1日(閏年には2日)設けて1年52週の曜日固定“世界暦”構想も実現は不可能なのだ。三大一神教が支配的である限り曜日の連続性を崩すことは不可能だろう。そうして、週の連続性は守られていく。ユダヤ教国でもキリスト教国でもイスラム教国でもない日本が週制度に従って休日を設定しなければならない理由は全然ないが、日本にも大同元年(806)に弘法大師(空海)が唐から『宿曜経』として持ってきて以来暦註として存在する7日周期の曜日は、国際的に暦を考える場合に必須だろう。
ところで、曜日の順番は土日を一般に週末と言うのに、ほとんどのカレンダーにおいて週の頭は日曜日になっている。これは生活のサイクルはキリスト教(日曜が休日)なのにカレンダーの方はユダヤ教(土曜が7日目の安息日)になっているということが言える。どうして日本人が国内で使うカレンダーまでユダヤ教に従わなければならないのか?
ともあれ、安息日を定めるこの7日周期はユダヤ教からキリスト教にも安息する曜日を変更しながらも受け継がれ、イスラム教にもまた同様に安息する曜日を変更して受け継がれている。だらら、7日周期を正確に連続させることは、たとえそれが天象的には全く意味のない人為的な周期あるとしても、これら三大一神教が世界的に支配的である限り変えることが許されないことだろう。だから、曜日を持たない日を一年に1日(閏年には2日)設けて1年52週の曜日固定“世界暦”構想も実現は不可能なのだ。三大一神教が支配的である限り曜日の連続性を崩すことは不可能だろう。そうして、週の連続性は守られていく。ユダヤ教国でもキリスト教国でもイスラム教国でもない日本が週制度に従って休日を設定しなければならない理由は全然ないが、日本にも大同元年(806)に弘法大師(空海)が唐から『宿曜経』として持ってきて以来暦註として存在する7日周期の曜日は、国際的に暦を考える場合に必須だろう。
ところで、曜日の順番は土日を一般に週末と言うのに、ほとんどのカレンダーにおいて週の頭は日曜日になっている。これは生活のサイクルはキリスト教(日曜が休日)なのにカレンダーの方はユダヤ教(土曜が7日目の安息日)になっているということが言える。どうして日本人が国内で使うカレンダーまでユダヤ教に従わなければならないのか?
>日本語の俗語「サボる」の語源もヘブライ語の休息シャバットに関係があるのでしょう。
関係なさそうです。
下記のような見解が一般的と思われます。
-----------------------------------------------------
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
サボるとは、仕事などを怠けること。フランス語で労働争議の一種である「怠業」を表すサボタージュ(sabotage)の日本語の略語「サボ」にラ行五段活用を付して動詞とした、造語。類似の造語に「ダブる」がある。
フランス語のサボタージュという言葉は木靴を示すサボ(sabot)から来ている。木靴を履いて仕事をすると仕事の効率が落ちるためであるとか、木靴で機械を蹴って仕事をしなかったとか、逆に機械がうまく動かなくて仕事の効率が上がらないときに木靴で叩いたからであるなどの説がある。
日本語の「サボる」は仕事などをちょっと怠けたり休んだりする程度の意味に使われるが、フランス語や英語の"sabotage"は「破壊活動」「妨害工作」といった本当の争議の場合に用いられる言葉であり、日本語の外来語の「サボタージュ」も同様に使われる。
日本では大正時代に既にサボるという言葉が使われていた。怠業などによる労働争議は大正時代を象徴する出来事だったのである。サボタージュという言葉が日本で怠業の意味として流行し始めたのは、1920年(大正9年)に村嶋歸之により書かれた『サボタージユ—川崎造船所怠業の真相』(ISBN 4-7601-2614-7) によったとする説がある。[1]
1970年代から1990年代にかけては、学生を中心として、サボるの代わりに「ふける」という言葉がよく使われていた。もともと「ふける」は「逃げる」という意味の言葉であったが、授業などから逃げることから転じてサボると同義の言葉として用いられた。
関係なさそうです。
下記のような見解が一般的と思われます。
-----------------------------------------------------
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
サボるとは、仕事などを怠けること。フランス語で労働争議の一種である「怠業」を表すサボタージュ(sabotage)の日本語の略語「サボ」にラ行五段活用を付して動詞とした、造語。類似の造語に「ダブる」がある。
フランス語のサボタージュという言葉は木靴を示すサボ(sabot)から来ている。木靴を履いて仕事をすると仕事の効率が落ちるためであるとか、木靴で機械を蹴って仕事をしなかったとか、逆に機械がうまく動かなくて仕事の効率が上がらないときに木靴で叩いたからであるなどの説がある。
日本語の「サボる」は仕事などをちょっと怠けたり休んだりする程度の意味に使われるが、フランス語や英語の"sabotage"は「破壊活動」「妨害工作」といった本当の争議の場合に用いられる言葉であり、日本語の外来語の「サボタージュ」も同様に使われる。
日本では大正時代に既にサボるという言葉が使われていた。怠業などによる労働争議は大正時代を象徴する出来事だったのである。サボタージュという言葉が日本で怠業の意味として流行し始めたのは、1920年(大正9年)に村嶋歸之により書かれた『サボタージユ—川崎造船所怠業の真相』(ISBN 4-7601-2614-7) によったとする説がある。[1]
1970年代から1990年代にかけては、学生を中心として、サボるの代わりに「ふける」という言葉がよく使われていた。もともと「ふける」は「逃げる」という意味の言葉であったが、授業などから逃げることから転じてサボると同義の言葉として用いられた。
ご指摘ありがとうございます。いいかげんな発言を反省いたします。読んでくださっている方がいらっしゃることが分かって嬉しいです。実は書き込んだ直後にサボタージュを辞書で確認していたのですが、訂正を放置してしまって失礼しました。すでに暦の話からは離れてしまいますが、フランス語の安息日がbからmに変化している背景や、フランス語の木靴サボ(sabot)の語源にも興味が湧いてきました。
ご指摘ありがとうございました。また勉強してきます。(投稿コメントにも編集機能があるなら誤った記述箇所を直接に訂正したいところなのですが、放置or削除の選択しかないんですよね・・・)今後ともよろしくお願いいたします。
ご指摘ありがとうございました。また勉強してきます。(投稿コメントにも編集機能があるなら誤った記述箇所を直接に訂正したいところなのですが、放置or削除の選択しかないんですよね・・・)今後ともよろしくお願いいたします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
暦 こよみ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
暦 こよみのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31946人
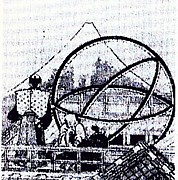


![月夜見 [ツクヨミ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/3/72/1110372_2s.gif)



















