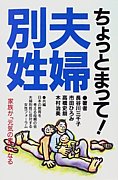|
|
|
|
コメント(164)
また、夫婦別姓とは直接の関係はありませんが、
現在の法務大臣の江田五月氏の性格を示す記事を紹介します。
「死刑、当面命じない意向 江田法相「議論が必要」と」
(2011年(平成23年)8月7日 47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011080601000555.html
『江田五月法相が6日までに共同通信のインタビューに応じ、昨年7月の執行を最後に1年以上行われていない死刑について「より深い議論が必要」「今は執行ということを考えられるほど自分の勉強が煮詰まっていない」などとして、当面は執行を命じる考えがないことを明らかにした。』
事実上の死刑廃止を、その地位による権限行使の不作為により行っています。
このような事実上の法の停止という事態は「死刑制度」が象徴的なのですが、法に対する考え方が透けて見えます。
現法制に「より深い議論が必要」と考えるのは良い事です。
しかし、「今は執行ということを考えられるほど自分の勉強が煮詰まっていない」
というのは、法の執行を担当する行政のトップとして如何なものでしょう。
超法規的な行動を、いとも簡単に実行・表明できてしまうところを危惧します。
現在の法務大臣の江田五月氏の性格を示す記事を紹介します。
「死刑、当面命じない意向 江田法相「議論が必要」と」
(2011年(平成23年)8月7日 47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011080601000555.html
『江田五月法相が6日までに共同通信のインタビューに応じ、昨年7月の執行を最後に1年以上行われていない死刑について「より深い議論が必要」「今は執行ということを考えられるほど自分の勉強が煮詰まっていない」などとして、当面は執行を命じる考えがないことを明らかにした。』
事実上の死刑廃止を、その地位による権限行使の不作為により行っています。
このような事実上の法の停止という事態は「死刑制度」が象徴的なのですが、法に対する考え方が透けて見えます。
現法制に「より深い議論が必要」と考えるのは良い事です。
しかし、「今は執行ということを考えられるほど自分の勉強が煮詰まっていない」
というのは、法の執行を担当する行政のトップとして如何なものでしょう。
超法規的な行動を、いとも簡単に実行・表明できてしまうところを危惧します。
野田新内閣についての論評を紹介します。
「【安倍晋三の突破する政治】新政権は“適材不適所”内閣」(2011.09.07)
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110907/plt1109071348004-n1.htm
『厚労相に小宮山洋子氏をあてたことも理解できない。彼女は、家族の価値を認めないジェンダーフリー論者であり、夫婦別姓推進論者である。そんな人物が、子育て政策の責任者になるなど、おかしい。
平岡秀夫氏の法相起用は異常だ。彼は民主党左派を自任し、光市母子殺人事件の加害者弁護団の奇妙な主張を支持しただけでなく、息子を少年に暴行死させられた母親に対して、「彼らにも罪を犯す事情があったんですよ」と言い放った人物である。』
引き続き、注意するべき内閣の布陣のようです。
「【安倍晋三の突破する政治】新政権は“適材不適所”内閣」(2011.09.07)
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110907/plt1109071348004-n1.htm
『厚労相に小宮山洋子氏をあてたことも理解できない。彼女は、家族の価値を認めないジェンダーフリー論者であり、夫婦別姓推進論者である。そんな人物が、子育て政策の責任者になるなど、おかしい。
平岡秀夫氏の法相起用は異常だ。彼は民主党左派を自任し、光市母子殺人事件の加害者弁護団の奇妙な主張を支持しただけでなく、息子を少年に暴行死させられた母親に対して、「彼らにも罪を犯す事情があったんですよ」と言い放った人物である。』
引き続き、注意するべき内閣の布陣のようです。
かなり時間が経ちましたが、野田政権の法務大臣をチェックしてみましょう。
「平岡秀夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B2%A1%E7%A7%80%E5%A4%AB
『平岡 秀夫(ひらおか ひでお、1954年1月14日 - )は、日本の大蔵官僚、弁護士、政治家。衆議院議員(5期)、法務大臣(第88代)、リベラルの会代表世話人。
内閣法制局第三部参事官、国税庁課税部法人税課課長、内閣府副大臣、総務副大臣などを歴任した。』
『政策・主張
法務・検察
東京大学法学部在学中に司法試験に合格しており、内閣法制局での勤務経験を持つなど、司法行政に明るい。 刑事事件の捜査について「取り調べの可視化」の推進を主張している。また死刑執行については、人の命を奪う重大刑ゆえ慎重であるべきというスタンスである。
外交・安全保障
日本の外交は「どの国も敵国視しない。」という平和主義を掲げ、国連を主導とした集団安全保障に頼るべきで、国際問題の解決はできる限り平和的手段で解決していくべきとしている。 2006年11月15日、朝鮮大学校創立50周年記念祝賀宴に参加。2007年10月3日、緊急集会「東北アジアの平和と日朝国交正常化―制裁をやめ対話と人道支援へ」(主催=緊急集会実行委員会、呼びかけ=東北アジアに非核、平和の確立を!日朝国交正常化を求める連絡会)に社民党所属の国会議員らとともに参加。その後、2008年に、北朝鮮との対話路線外交を推進する朝鮮半島問題研究会を立ち上げた。 2009年6月19日、ソマリア沖の海賊から日本の船舶を保護するために自衛隊が海上警備行動を行うことやODAを活用してソマリア情勢の安定を目指す海賊対処法案[12]について、衆院本会議で「自衛隊の海外派遣は認められない」とする反対答弁を行った。また、「海賊のいない平和な海をもたらす努力を自公政権にはうかがえないとして、速やかに解散・総選挙を行うべきだとした。
外国人献金問題
2011年9月6日の会見で平岡は、日本の政治家に対する外国人献金問題について「ほかの先進国と比べて、日本はかなり厳しい」「金を受けてしまうことで、影響を受けてしまうのかが問題。そういう懸念をどこまで制度化していくかが問題の基本ではないか」と述べた。
パチンコ換金問題
パチンコ換金合法化を訴えている。』
(フリー百科事典ウィキペディア(wikipedia))
「夫婦別姓」には目立った発言はないようですが、容認する立場なのだろうと想像します。
「平岡秀夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B2%A1%E7%A7%80%E5%A4%AB
『平岡 秀夫(ひらおか ひでお、1954年1月14日 - )は、日本の大蔵官僚、弁護士、政治家。衆議院議員(5期)、法務大臣(第88代)、リベラルの会代表世話人。
内閣法制局第三部参事官、国税庁課税部法人税課課長、内閣府副大臣、総務副大臣などを歴任した。』
『政策・主張
法務・検察
東京大学法学部在学中に司法試験に合格しており、内閣法制局での勤務経験を持つなど、司法行政に明るい。 刑事事件の捜査について「取り調べの可視化」の推進を主張している。また死刑執行については、人の命を奪う重大刑ゆえ慎重であるべきというスタンスである。
外交・安全保障
日本の外交は「どの国も敵国視しない。」という平和主義を掲げ、国連を主導とした集団安全保障に頼るべきで、国際問題の解決はできる限り平和的手段で解決していくべきとしている。 2006年11月15日、朝鮮大学校創立50周年記念祝賀宴に参加。2007年10月3日、緊急集会「東北アジアの平和と日朝国交正常化―制裁をやめ対話と人道支援へ」(主催=緊急集会実行委員会、呼びかけ=東北アジアに非核、平和の確立を!日朝国交正常化を求める連絡会)に社民党所属の国会議員らとともに参加。その後、2008年に、北朝鮮との対話路線外交を推進する朝鮮半島問題研究会を立ち上げた。 2009年6月19日、ソマリア沖の海賊から日本の船舶を保護するために自衛隊が海上警備行動を行うことやODAを活用してソマリア情勢の安定を目指す海賊対処法案[12]について、衆院本会議で「自衛隊の海外派遣は認められない」とする反対答弁を行った。また、「海賊のいない平和な海をもたらす努力を自公政権にはうかがえないとして、速やかに解散・総選挙を行うべきだとした。
外国人献金問題
2011年9月6日の会見で平岡は、日本の政治家に対する外国人献金問題について「ほかの先進国と比べて、日本はかなり厳しい」「金を受けてしまうことで、影響を受けてしまうのかが問題。そういう懸念をどこまで制度化していくかが問題の基本ではないか」と述べた。
パチンコ換金問題
パチンコ換金合法化を訴えている。』
(フリー百科事典ウィキペディア(wikipedia))
「夫婦別姓」には目立った発言はないようですが、容認する立場なのだろうと想像します。
上記コメント132のニュースを確認しました。
「別姓の婚姻届不受理問題、控訴を棄却」(2011年11月24日18時39分 ニッカンスポーツ)
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20111124-867956.html
『結婚で同一の姓にしなければならない民法の規定は「両性の平等」を定めた憲法に違反するとして、夫婦別姓で暮らす事実婚の2人が、婚姻届を受理しなかった東京都荒川区の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、訴えを却下した一審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。
青柳馨裁判長は一審同様「戸籍に関する争いは家裁の家事審判手続きで判断されるべきだ」と指摘。仮に民法の規定が違憲だとしても、関係法令が立法で是正されない限り婚姻届の受理を命じることはできないとした。』
当然の結果が出ましたね。
それにしても、
『婚姻届の不受理処分の取消訴訟(控訴審)の判決が次のとおり言い渡 されます。』
などと表現をする、「別姓訴訟を考える会」というのは下劣です。
弁護士等の法の専門家が多くいながら何を考えているのか?
東京高等裁判所が今回、示した判決は、“婚姻届の不受理処分”の内容を判断すものではありません。
“婚姻届の不受理処分”に対する“取り消しを求めた訴え”を東京地方裁判所が却下したことに対する、裁判手続きの適正を争ったものです。
だから「東京地裁の請求却下訴訟の判決」と表現するのが適切でしょう。
訴訟は門前払いされて、門前払いへの異議も敗訴したということです。
【参考】
「判決」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA
『控訴審の判決
控訴認容判決
控訴裁判所は、原判決が不当であるとき(305条)及び第1審の判決の手続が法律に違反したとき(306条)は、控訴に理由があるから、原判決を取り消さなければならない。控訴を認容する本案判決である。 その上で、控訴裁判所は、原則として自ら訴えに対する判断をする(自判)。 ただし、原判決が訴え却下判決であった場合は、事件を原裁判所に差し戻さなければならず(307条)、その他、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所に差し戻すことができる(308条1項)。
控訴棄却判決
原判決が相当であって、控訴に理由がないときは、控訴を棄却する判決をする(302条)。本案判決である。
控訴却下判決
控訴の要件が欠け、控訴が不適法な場合は、控訴を却下する判決をする(290条)。訴訟判決である。』
(フリー百科事典ウィキペディア(wikipedia))
「別姓の婚姻届不受理問題、控訴を棄却」(2011年11月24日18時39分 ニッカンスポーツ)
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20111124-867956.html
『結婚で同一の姓にしなければならない民法の規定は「両性の平等」を定めた憲法に違反するとして、夫婦別姓で暮らす事実婚の2人が、婚姻届を受理しなかった東京都荒川区の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、訴えを却下した一審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。
青柳馨裁判長は一審同様「戸籍に関する争いは家裁の家事審判手続きで判断されるべきだ」と指摘。仮に民法の規定が違憲だとしても、関係法令が立法で是正されない限り婚姻届の受理を命じることはできないとした。』
当然の結果が出ましたね。
それにしても、
『婚姻届の不受理処分の取消訴訟(控訴審)の判決が次のとおり言い渡 されます。』
などと表現をする、「別姓訴訟を考える会」というのは下劣です。
弁護士等の法の専門家が多くいながら何を考えているのか?
東京高等裁判所が今回、示した判決は、“婚姻届の不受理処分”の内容を判断すものではありません。
“婚姻届の不受理処分”に対する“取り消しを求めた訴え”を東京地方裁判所が却下したことに対する、裁判手続きの適正を争ったものです。
だから「東京地裁の請求却下訴訟の判決」と表現するのが適切でしょう。
訴訟は門前払いされて、門前払いへの異議も敗訴したということです。
【参考】
「判決」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA
『控訴審の判決
控訴認容判決
控訴裁判所は、原判決が不当であるとき(305条)及び第1審の判決の手続が法律に違反したとき(306条)は、控訴に理由があるから、原判決を取り消さなければならない。控訴を認容する本案判決である。 その上で、控訴裁判所は、原則として自ら訴えに対する判断をする(自判)。 ただし、原判決が訴え却下判決であった場合は、事件を原裁判所に差し戻さなければならず(307条)、その他、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所に差し戻すことができる(308条1項)。
控訴棄却判決
原判決が相当であって、控訴に理由がないときは、控訴を棄却する判決をする(302条)。本案判決である。
控訴却下判決
控訴の要件が欠け、控訴が不適法な場合は、控訴を却下する判決をする(290条)。訴訟判決である。』
(フリー百科事典ウィキペディア(wikipedia))
さて、「婚姻届の不受理処分の取消訴訟(控訴審)」の判決を、下記のサイトはどのように紹介しているのでしょうか?
「別姓訴訟を考える会」
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/tusin.html
『【行政訴訟の控訴審判決で、行政訴訟はできないと再度判断 11月24日】 弁護団 小島延夫
前略
東 京高裁は、戸籍の受理は形式的審査であり、公開の法廷での審査を認め なくとも憲法違反とならないとしました。同判決は、末尾で、夫婦同一 姓を定めている民法750条を違憲とすると、婚姻制度や戸籍制度全般 に影響が及ぶので、立法によることなく、裁判所が是正することはでき ないと述べており、この点が今回の判断の実質的な理由のようです。
しかし、登記手続のように、形式的審査でも訴訟できるのは広く認め られており、東京高裁の判断には理由がありません。そもそも夫婦別姓 のような重要な問題について、国家賠償という形態でなく、直接に、公 開の法廷で争う手段がなければなりません。最高裁も、法律上の実体的 権利義務自体につき争がある場合には公開の法廷における審理が保障さ れるべきとしています(憲法32条、82条)。これからは、最高裁に 上告し、最高裁の判断を求めることになります。』
上告するようです。
「別姓訴訟を考える会」
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/tusin.html
『【行政訴訟の控訴審判決で、行政訴訟はできないと再度判断 11月24日】 弁護団 小島延夫
前略
東 京高裁は、戸籍の受理は形式的審査であり、公開の法廷での審査を認め なくとも憲法違反とならないとしました。同判決は、末尾で、夫婦同一 姓を定めている民法750条を違憲とすると、婚姻制度や戸籍制度全般 に影響が及ぶので、立法によることなく、裁判所が是正することはでき ないと述べており、この点が今回の判断の実質的な理由のようです。
しかし、登記手続のように、形式的審査でも訴訟できるのは広く認め られており、東京高裁の判断には理由がありません。そもそも夫婦別姓 のような重要な問題について、国家賠償という形態でなく、直接に、公 開の法廷で争う手段がなければなりません。最高裁も、法律上の実体的 権利義務自体につき争がある場合には公開の法廷における審理が保障さ れるべきとしています(憲法32条、82条)。これからは、最高裁に 上告し、最高裁の判断を求めることになります。』
上告するようです。
また法務大臣が変わりました。
「法相に小川敏夫氏の起用固まる」(1月13日10時19分 NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120113/t10015236441000.html
『これまでの調整の結果、野田総理大臣は、去年の臨時国会で問責決議が可決された一川防衛大臣と山岡国家公安委員長兼消費者担当大臣のほか、平岡法務大臣、中川文部科学大臣、蓮舫行政刷新担当大臣の合わせて5人を退任させる意向を固めました。そのうえで野田総理大臣は、新しい法務大臣には民主党の小川敏夫参議院幹事長を起用する意向を固めました。小川氏は、参議院東京選挙区選出の当選3回で、63歳。裁判官や検察官を経て弁護士になり、平成10年の参議院選挙で初当選しました。そして、小川氏は菅内閣で法務副大臣を務め、現在は党の参議院幹事長です。野田総理大臣としては、小川氏が法務行政に精通していることを踏まえ、法務大臣に起用することにしたものとみられます。』
さてどんな考えを持っているのでしょうか?
夫婦別姓に直接関係する部分はスグには見つかりそうにありません。
以下はあくまで参考。
「小川俊夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E6%95%8F%E5%A4%AB
『従軍慰安婦問題
アメリカ合衆国下院で決議されたアメリカ合衆国下院121号決議に異議を唱える安倍晋三首相に対して、「謝らなければいけない立場なのに 『(慰安婦の)証言は事実無根』と言っても国際世論は賛同しない」 と批判をしている。この批判を受けて、安倍が「戦後六十年、日本は自由と民主主義、基本的な人権を守って歩んでまいりました。そのことは国際社会から高く私は評価されているところであろうと、このように思います」「(小川は)殊更そういう日本の歩みをおとしめようとしているんではないか」と述べたことに対し「大変な暴言」「今度は下院、院全体で決議が出るかもしれないと。そのことによって生ずる我が国のこの国際的な評価、これが低下することを憂えて言っているんですよ」と反論した。
永住外国人への地方選挙権付与
2008年1月に、在日韓国人等に参政権を付与することを目的とする在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟に参加した。
2009年3月1日のビートたけしのTVタックルの外国人参政権特集において、1995年(平成7年)の最高裁判決「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」を、「参政権は国民が本来的に持っている権利である。しかし、それは国民から参政権を奪うことはできないということであって、許される範囲で立法の裁量によって国民ではない者に与えることも許される」と解説し、主文に「外国人にはその権利は及ばない」と書いていることについては「認める法律がないからそうなっただけで、認める法律があればいい」と述べ、外国人参政権付与法案の必要性を訴えた。また、外国人参政権の付与に反対する日本人に対しては「日本っていう国が海外から尊敬される国になるのも大きな国益なんじゃないでしょうか。日本が日本だけで、こうして外国人を排除する、人権無視をやればですね、評価が下がる」と指摘した。
2009年11月26日に、衆議院第1議員会館で、在日本大韓民国青年会や在日本大韓民国民団が主催する「永住外国人の地方参政権法案の早期立法化を求める11・26緊急院内集会」に、末松義規・渡辺浩一郎・手塚仁雄・初鹿明博・白真勲らと参加し、在日外国人の参政権法案を成立させる決意表明をした。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
「法相に小川敏夫氏の起用固まる」(1月13日10時19分 NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120113/t10015236441000.html
『これまでの調整の結果、野田総理大臣は、去年の臨時国会で問責決議が可決された一川防衛大臣と山岡国家公安委員長兼消費者担当大臣のほか、平岡法務大臣、中川文部科学大臣、蓮舫行政刷新担当大臣の合わせて5人を退任させる意向を固めました。そのうえで野田総理大臣は、新しい法務大臣には民主党の小川敏夫参議院幹事長を起用する意向を固めました。小川氏は、参議院東京選挙区選出の当選3回で、63歳。裁判官や検察官を経て弁護士になり、平成10年の参議院選挙で初当選しました。そして、小川氏は菅内閣で法務副大臣を務め、現在は党の参議院幹事長です。野田総理大臣としては、小川氏が法務行政に精通していることを踏まえ、法務大臣に起用することにしたものとみられます。』
さてどんな考えを持っているのでしょうか?
夫婦別姓に直接関係する部分はスグには見つかりそうにありません。
以下はあくまで参考。
「小川俊夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E6%95%8F%E5%A4%AB
『従軍慰安婦問題
アメリカ合衆国下院で決議されたアメリカ合衆国下院121号決議に異議を唱える安倍晋三首相に対して、「謝らなければいけない立場なのに 『(慰安婦の)証言は事実無根』と言っても国際世論は賛同しない」 と批判をしている。この批判を受けて、安倍が「戦後六十年、日本は自由と民主主義、基本的な人権を守って歩んでまいりました。そのことは国際社会から高く私は評価されているところであろうと、このように思います」「(小川は)殊更そういう日本の歩みをおとしめようとしているんではないか」と述べたことに対し「大変な暴言」「今度は下院、院全体で決議が出るかもしれないと。そのことによって生ずる我が国のこの国際的な評価、これが低下することを憂えて言っているんですよ」と反論した。
永住外国人への地方選挙権付与
2008年1月に、在日韓国人等に参政権を付与することを目的とする在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟に参加した。
2009年3月1日のビートたけしのTVタックルの外国人参政権特集において、1995年(平成7年)の最高裁判決「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」を、「参政権は国民が本来的に持っている権利である。しかし、それは国民から参政権を奪うことはできないということであって、許される範囲で立法の裁量によって国民ではない者に与えることも許される」と解説し、主文に「外国人にはその権利は及ばない」と書いていることについては「認める法律がないからそうなっただけで、認める法律があればいい」と述べ、外国人参政権付与法案の必要性を訴えた。また、外国人参政権の付与に反対する日本人に対しては「日本っていう国が海外から尊敬される国になるのも大きな国益なんじゃないでしょうか。日本が日本だけで、こうして外国人を排除する、人権無視をやればですね、評価が下がる」と指摘した。
2009年11月26日に、衆議院第1議員会館で、在日本大韓民国青年会や在日本大韓民国民団が主催する「永住外国人の地方参政権法案の早期立法化を求める11・26緊急院内集会」に、末松義規・渡辺浩一郎・手塚仁雄・初鹿明博・白真勲らと参加し、在日外国人の参政権法案を成立させる決意表明をした。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
ご無沙汰してます^^;
夫婦別姓に反対の立場です。
民主党政権に反対の立場でもあります。
内閣改造があったりしたのに、新しく就任した方の素性を理解していませんでした。
暫く見ていない間に、これまたとんでもない改造があったのですね。
ようやく菅が降りたかと思ったけど、野田も韓国飲みをする様ですし
本当に民主党にはろくな人材がいないと改めて思いました。
首相がどうのじゃないんですよね。
もう民主党が政権を持っている限り、中国韓国の中華思想のもと、属国化していきそうで嫌ですね。
孔子の像を世界中に建てまくってる中国。
その孔子が夫婦別姓を作った張本人。
なぜ夫の姓を名乗らせなかったか?
女は夫の子供を産むだけの存在だから
夫の家に入れなかった。
これこそ男尊女卑の思想の賜物なのに、世の新進的な女性たちは
男尊女卑を自ら推進してると気づかないのでしょうかw
夫婦別姓に反対の立場です。
民主党政権に反対の立場でもあります。
内閣改造があったりしたのに、新しく就任した方の素性を理解していませんでした。
暫く見ていない間に、これまたとんでもない改造があったのですね。
ようやく菅が降りたかと思ったけど、野田も韓国飲みをする様ですし
本当に民主党にはろくな人材がいないと改めて思いました。
首相がどうのじゃないんですよね。
もう民主党が政権を持っている限り、中国韓国の中華思想のもと、属国化していきそうで嫌ですね。
孔子の像を世界中に建てまくってる中国。
その孔子が夫婦別姓を作った張本人。
なぜ夫の姓を名乗らせなかったか?
女は夫の子供を産むだけの存在だから
夫の家に入れなかった。
これこそ男尊女卑の思想の賜物なのに、世の新進的な女性たちは
男尊女卑を自ら推進してると気づかないのでしょうかw
136■かつみゆかり さん
ご無沙汰しています。また、墓の問題やアメリカの状況等、宜しくお願いします。
137■まっちゃんCR-Zさん
貴重な情報ありがとうございます。
野田政権では、民法の改変に手を付ける余裕はない事でしょう。
それでも、世の中は静かに動いています。奇妙な啓蒙活動が進行する事を憂慮します。
「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日 閣議決定 )
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/
「第2分野男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」
(URLが直接入手できないので、上記URLから入って下さい。)
『1 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
エ 家族に関する法制の整備等
・夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、婚姻適齢の
男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進める。
また、再婚の増加等に伴う家族の在り方の多様化、少子化など時代の変化等に応じ、
家族法制の在り方等について広く課題の検討を行う。』
ご無沙汰しています。また、墓の問題やアメリカの状況等、宜しくお願いします。
137■まっちゃんCR-Zさん
貴重な情報ありがとうございます。
野田政権では、民法の改変に手を付ける余裕はない事でしょう。
それでも、世の中は静かに動いています。奇妙な啓蒙活動が進行する事を憂慮します。
「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日 閣議決定 )
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/
「第2分野男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」
(URLが直接入手できないので、上記URLから入って下さい。)
『1 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
エ 家族に関する法制の整備等
・夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、婚姻適齢の
男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進める。
また、再婚の増加等に伴う家族の在り方の多様化、少子化など時代の変化等に応じ、
家族法制の在り方等について広く課題の検討を行う。』
「女性の政治参画もっと
比例中心の制度に
婦団連が政府要望」 (2012年2月11日(土) 赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-11/2012021104_04_1.html
『日本婦人団体連合会(婦団連)は9日、内閣府で園田康博内閣府大臣政務官に岡田克也少子化対策・男女共同参画担当大臣あての要請書を手わたし、民法改正と比例代表制を中心にする選挙制度への改定を申し入れました。
堀江ゆり婦団連会長があいさつ。全労連の柴田真佐子副議長は、「選択制の夫婦別姓を政府としてもっとアピールするべきだ。民法改正を早急に閣議決定してほしい」と訴えました。全教の長尾ゆり副委員長は、「小選挙区制を導入してから女性の政治参画がさらに難しくなった。能力も意欲もある女性議員が増えるように比例代表を中心にする選挙制度にしてほしい」と語りました。』
どういう訳か、随分と古臭く感じます。
本当に、今年のニュースなのでしょうか?
比例中心の制度に
婦団連が政府要望」 (2012年2月11日(土) 赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-11/2012021104_04_1.html
『日本婦人団体連合会(婦団連)は9日、内閣府で園田康博内閣府大臣政務官に岡田克也少子化対策・男女共同参画担当大臣あての要請書を手わたし、民法改正と比例代表制を中心にする選挙制度への改定を申し入れました。
堀江ゆり婦団連会長があいさつ。全労連の柴田真佐子副議長は、「選択制の夫婦別姓を政府としてもっとアピールするべきだ。民法改正を早急に閣議決定してほしい」と訴えました。全教の長尾ゆり副委員長は、「小選挙区制を導入してから女性の政治参画がさらに難しくなった。能力も意欲もある女性議員が増えるように比例代表を中心にする選挙制度にしてほしい」と語りました。』
どういう訳か、随分と古臭く感じます。
本当に、今年のニュースなのでしょうか?
「公明は女性の人権守る:松副代表 民法改正集会で訴え 」(公明新聞:2012年3月9日付)
http://www.komei.or.jp/news/detail/20120309_7520
『席上、松副代表は、結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度の導入などを盛り込んだ民法改正について「1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が答申して以来、公明党は一貫して取り組んできた」と強調。自公政権時代には、公明党が独自の法案を提出したことにも言及し「公明党は女性の人権を守るために闘っている」と訴えた。』
実を言うと、「選択的夫婦別姓」問題だけに関して考えると、民主党以上に積極的なのは公明党だと思っています。
そして、この公明党の副代表には情けなく思うことがあります。
「松あきら」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E3%81%82%E3%81%8D%E3%82%89
『発言
擬似科学 似非科学と批判の強い[3][4][5]江本勝の『水からの伝言』説を信奉しており、国会審議において江本の著書に対し肯定的な発言を度々行っている。
2000年11月2日、第150回国会の参議院文教・科学委員会にて、質問に立った松は、江本の著書『水は語る――Water, it tells us precious things』の実験内容を詳細に語り、持参した水の結晶の写真を委員会室で回覧させ、「やはり水も言葉がわかる」「私もこのお水の実験を実際してみたいなと思う」「授業の中で子供たちに、こういう人がいてこういう実験をしたらこうなったんだってよと、水でもわかるのかしら、このクラスでも一遍やってみようかとか、そういうことも子供たちが心というものを考える、あるいは命というものを考える一つの手助け」と発言している。答弁に立った文部大臣(兼科学技術庁長官)の大島理森は「写真でございますが、拝見してみて、これはボトルに張るだけでこういうふうに変わるというのは……」と発言したが、松はさらに科学技術庁に対し「ぜひ実験してみてください」と要請した。
2001年3月22日、第151回国会の参議院文教科学委員会にて、松は江本を「何十年も研究なさっていらっしゃる方」と評している。そして、江本の著書『水は語る--Water, it tells us precious things』の内容について実験内容を再び詳細に語っている。そのうえで、松は「水にも心がわかる」と発言し「人間の体、70%が水分であると。ですから、そういうことも含めて」「環境ホルモン等々、ダイオキシンの問題もありますけれども、心の面と、そして科学的な面、両方の面からこの教育というのをしっかり考えていただきたい」との主張を文部科学大臣の町村信孝に対し要望した。なお、実際に、江本の説を日本の一部小学校が道徳教材として取り上げたため、「非科学的なことが『事実』として教えられている」として「疑似科学の拡大助長」との議論が起こっている。』
(「フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
http://www.komei.or.jp/news/detail/20120309_7520
『席上、松副代表は、結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度の導入などを盛り込んだ民法改正について「1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が答申して以来、公明党は一貫して取り組んできた」と強調。自公政権時代には、公明党が独自の法案を提出したことにも言及し「公明党は女性の人権を守るために闘っている」と訴えた。』
実を言うと、「選択的夫婦別姓」問題だけに関して考えると、民主党以上に積極的なのは公明党だと思っています。
そして、この公明党の副代表には情けなく思うことがあります。
「松あきら」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E3%81%82%E3%81%8D%E3%82%89
『発言
擬似科学 似非科学と批判の強い[3][4][5]江本勝の『水からの伝言』説を信奉しており、国会審議において江本の著書に対し肯定的な発言を度々行っている。
2000年11月2日、第150回国会の参議院文教・科学委員会にて、質問に立った松は、江本の著書『水は語る――Water, it tells us precious things』の実験内容を詳細に語り、持参した水の結晶の写真を委員会室で回覧させ、「やはり水も言葉がわかる」「私もこのお水の実験を実際してみたいなと思う」「授業の中で子供たちに、こういう人がいてこういう実験をしたらこうなったんだってよと、水でもわかるのかしら、このクラスでも一遍やってみようかとか、そういうことも子供たちが心というものを考える、あるいは命というものを考える一つの手助け」と発言している。答弁に立った文部大臣(兼科学技術庁長官)の大島理森は「写真でございますが、拝見してみて、これはボトルに張るだけでこういうふうに変わるというのは……」と発言したが、松はさらに科学技術庁に対し「ぜひ実験してみてください」と要請した。
2001年3月22日、第151回国会の参議院文教科学委員会にて、松は江本を「何十年も研究なさっていらっしゃる方」と評している。そして、江本の著書『水は語る--Water, it tells us precious things』の内容について実験内容を再び詳細に語っている。そのうえで、松は「水にも心がわかる」と発言し「人間の体、70%が水分であると。ですから、そういうことも含めて」「環境ホルモン等々、ダイオキシンの問題もありますけれども、心の面と、そして科学的な面、両方の面からこの教育というのをしっかり考えていただきたい」との主張を文部科学大臣の町村信孝に対し要望した。なお、実際に、江本の説を日本の一部小学校が道徳教材として取り上げたため、「非科学的なことが『事実』として教えられている」として「疑似科学の拡大助長」との議論が起こっている。』
(「フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
少々、マニアックな動きを紹介します。
「第180回国会 法務委員会 第8号
平成二十四年六月十九日(火曜日) 午前十時十五分開会」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0003/18006190003008c.html
丸山 和也 議員の発言
『 それでは、時間の関係で次に移りますが、いわゆる法務大臣がころころ替わるということで、なかなか法務行政が進まないということはあるんですけれども、それは別にしまして、個々の問題について大臣が幾ら替わろうと、民主党政権あるいはマニフェストでうたっていることいろいろ含めて、やっぱりいい施策も、法案というのも幾つかあると思うんですね。そういうのがなかなか進まないということについて、ある意味では失望もしているんですけれども。
それで、一つは相続差別問題ですね。
相続での婚外子の相続分の差別、民法九百条四号ただし書というのがありますね。非嫡出子の相続分は嫡出子の二分の一だとかね。こういうことは、辛うじてまだ今裁判上合憲が保たれていますけれども、もうほとんど時間の問題で、違憲だという裁判官が多くなってきています。こういうのは、もう法律をきちっと出して、早く民法の改正をするとか、当然おっしゃっているとは思うんだけれども、なかなか進まない。
それから、もう一つは夫婦別姓ですね。
これは、別姓と言うかどうかは別にして、これも民主党政権ではやると言っておられたようだけれども、法案もなかなか出ないと。これは、なかなか議論がございます、夫婦別姓に関しては。しかし、これは前提として私の思想的理想を言うんですけれども、やっぱり強い国家というか国と自由な市民社会という、この一見矛盾するようなことをやっぱり達成するべきだと私は思っているんですね。
それで、婚姻したら夫婦が同一姓になるというのは明治になってからなんですよ、日本の歴史を見ても。恐らく、明治二十九年ですかね、民法が制定されて、三十一年施行、このときからなんですよね。姓がなかった人も明治以前はたくさんいたんですけれども、少なくとも夫婦結婚したら同一姓にするというのは、これは民法ができて初めてできているんですよ。そんなに日本的伝統でも何でもないんですよね、よく考えてみると。
それで、当時はやっぱり明治政府の富国強兵策の下に強い国家をつくるんだと、そのための家族というのは家制度の下で強くするんだと。それで強い家族、強い家制度、それが強い国家になっていくんだみたいな、一つのやっぱり国策なんですね、思想的に。それは、その時点になって初めて法的に整備されたということを見てもよく分かる。片や、アジアの諸国を見ても全然違う、中国、韓国にしてもですね。やっぱり生まれた自分の姓というのは結婚したぐらいでは変わらないんですよ。
こういうことも、だからどういう形で強い国をつくっていくかというのは時代によって変わっていくと僕は思うんですね。家制度によって強い国をつくっていくというような時代から、やっぱりそれぞれの個人のいろんな形態を、多様な形態を認めて、強い個人同士のきずなによって、自由なつながりによって強い社会をつくっていくんだという、やっぱり時代は変わっているんですよね。
そういう中で、やはり僕は、民主党さんがおっしゃっている中で、これはいろいろ賛否両論ありますけれども、少なくとも歴史的な、あるいは哲学的な観点に立ったこういう議論を堂々と進めていかないとやっぱり駄目だと思うんですね。それで、ちょっと世論がこう反対と言うとすぐやめてしまうとか、もう何というか、ポピュリズムというか、信念がない政治というのは一番駄目だと思うんですね。
特に、法務行政なんていうのは、そういう意味では非常にぶこつで質実剛健で、世論がどう言おうとかなり啓蒙していくような姿勢がないと法務行政というのはなかなか前に進まない。そうしないと、また法務行政も他の省庁の政治と比べても、さっき言葉ありましたけれども、なめられるというのは変ですけれども、軽く見られてしまう側面あると思うんですね。
そういう意味で、今、婚外子の相続分の問題、夫婦の姓の問題、こういう非常に市民社会の根幹にかかわる骨太のところを、単に世論の賛否あるいは声だけを気にしながら進めるんじゃなくて、堂々と検討してもらいたい。どういう結論になろうと堂々と議論をするということが大事だと思うんですけれども、大臣はどういうお考えですか。』
イロイロと書きたいことはありますが、まずは紹介に留めます。
「第180回国会 法務委員会 第8号
平成二十四年六月十九日(火曜日) 午前十時十五分開会」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0003/18006190003008c.html
丸山 和也 議員の発言
『 それでは、時間の関係で次に移りますが、いわゆる法務大臣がころころ替わるということで、なかなか法務行政が進まないということはあるんですけれども、それは別にしまして、個々の問題について大臣が幾ら替わろうと、民主党政権あるいはマニフェストでうたっていることいろいろ含めて、やっぱりいい施策も、法案というのも幾つかあると思うんですね。そういうのがなかなか進まないということについて、ある意味では失望もしているんですけれども。
それで、一つは相続差別問題ですね。
相続での婚外子の相続分の差別、民法九百条四号ただし書というのがありますね。非嫡出子の相続分は嫡出子の二分の一だとかね。こういうことは、辛うじてまだ今裁判上合憲が保たれていますけれども、もうほとんど時間の問題で、違憲だという裁判官が多くなってきています。こういうのは、もう法律をきちっと出して、早く民法の改正をするとか、当然おっしゃっているとは思うんだけれども、なかなか進まない。
それから、もう一つは夫婦別姓ですね。
これは、別姓と言うかどうかは別にして、これも民主党政権ではやると言っておられたようだけれども、法案もなかなか出ないと。これは、なかなか議論がございます、夫婦別姓に関しては。しかし、これは前提として私の思想的理想を言うんですけれども、やっぱり強い国家というか国と自由な市民社会という、この一見矛盾するようなことをやっぱり達成するべきだと私は思っているんですね。
それで、婚姻したら夫婦が同一姓になるというのは明治になってからなんですよ、日本の歴史を見ても。恐らく、明治二十九年ですかね、民法が制定されて、三十一年施行、このときからなんですよね。姓がなかった人も明治以前はたくさんいたんですけれども、少なくとも夫婦結婚したら同一姓にするというのは、これは民法ができて初めてできているんですよ。そんなに日本的伝統でも何でもないんですよね、よく考えてみると。
それで、当時はやっぱり明治政府の富国強兵策の下に強い国家をつくるんだと、そのための家族というのは家制度の下で強くするんだと。それで強い家族、強い家制度、それが強い国家になっていくんだみたいな、一つのやっぱり国策なんですね、思想的に。それは、その時点になって初めて法的に整備されたということを見てもよく分かる。片や、アジアの諸国を見ても全然違う、中国、韓国にしてもですね。やっぱり生まれた自分の姓というのは結婚したぐらいでは変わらないんですよ。
こういうことも、だからどういう形で強い国をつくっていくかというのは時代によって変わっていくと僕は思うんですね。家制度によって強い国をつくっていくというような時代から、やっぱりそれぞれの個人のいろんな形態を、多様な形態を認めて、強い個人同士のきずなによって、自由なつながりによって強い社会をつくっていくんだという、やっぱり時代は変わっているんですよね。
そういう中で、やはり僕は、民主党さんがおっしゃっている中で、これはいろいろ賛否両論ありますけれども、少なくとも歴史的な、あるいは哲学的な観点に立ったこういう議論を堂々と進めていかないとやっぱり駄目だと思うんですね。それで、ちょっと世論がこう反対と言うとすぐやめてしまうとか、もう何というか、ポピュリズムというか、信念がない政治というのは一番駄目だと思うんですね。
特に、法務行政なんていうのは、そういう意味では非常にぶこつで質実剛健で、世論がどう言おうとかなり啓蒙していくような姿勢がないと法務行政というのはなかなか前に進まない。そうしないと、また法務行政も他の省庁の政治と比べても、さっき言葉ありましたけれども、なめられるというのは変ですけれども、軽く見られてしまう側面あると思うんですね。
そういう意味で、今、婚外子の相続分の問題、夫婦の姓の問題、こういう非常に市民社会の根幹にかかわる骨太のところを、単に世論の賛否あるいは声だけを気にしながら進めるんじゃなくて、堂々と検討してもらいたい。どういう結論になろうと堂々と議論をするということが大事だと思うんですけれども、大臣はどういうお考えですか。』
イロイロと書きたいことはありますが、まずは紹介に留めます。
かなり間を開けてしまいました。
丸山 和也 議員の発言に対して、少々指摘をしましょう。
 『少なくとも夫婦結婚したら同一姓にするというのは、これは民法ができて初めてできているんですよ。そんなに日本的伝統でも何でもないんですよね、よく考えてみると。』
『少なくとも夫婦結婚したら同一姓にするというのは、これは民法ができて初めてできているんですよ。そんなに日本的伝統でも何でもないんですよね、よく考えてみると。』
その通りです。肝心な事は、“日本的伝統である。”ということが、反対意見の本質ではないという事です。
恥ずかしながら、このコミュニティが開始された当初、私は、“夫婦同姓が日本的伝統である。”という認識でした。
それは過ちです。かといって、反対に、“夫婦別姓が日本的伝統である。”かという言うと、それも過ちです。
明治期以前は「姓」というもの自体が今とは相違するのです。
 『それで、当時はやっぱり明治政府の富国強兵策の下に強い国家をつくるんだと、そのための家族というのは家制度の下で強くするんだと。』
『それで、当時はやっぱり明治政府の富国強兵策の下に強い国家をつくるんだと、そのための家族というのは家制度の下で強くするんだと。』
明治期の「国家意思」又は「施政者の意図」の本質は何であったのか?
この事自体で膨大な議論ができます。
一応、「富国強兵」という方向性が主要な課題であったことには同意します。
但し、丸山 和也 議員の発言には、その課題の元で、
「国民の家族の在り方が、国家目標に合致するように、後から形づけられた。」
というニュアンスを感じます。
つまり、「富国強兵」を推進する道具として「家制度」が制度かされ、「夫婦同姓」という原則が作られたという発想です。
「支配」と「被支配」の発想ですね。
私は事実に相違すると考えます。
この事に関して、コメントを分けて説明します。
丸山 和也 議員の発言に対して、少々指摘をしましょう。
その通りです。肝心な事は、“日本的伝統である。”ということが、反対意見の本質ではないという事です。
恥ずかしながら、このコミュニティが開始された当初、私は、“夫婦同姓が日本的伝統である。”という認識でした。
それは過ちです。かといって、反対に、“夫婦別姓が日本的伝統である。”かという言うと、それも過ちです。
明治期以前は「姓」というもの自体が今とは相違するのです。
明治期の「国家意思」又は「施政者の意図」の本質は何であったのか?
この事自体で膨大な議論ができます。
一応、「富国強兵」という方向性が主要な課題であったことには同意します。
但し、丸山 和也 議員の発言には、その課題の元で、
「国民の家族の在り方が、国家目標に合致するように、後から形づけられた。」
というニュアンスを感じます。
つまり、「富国強兵」を推進する道具として「家制度」が制度かされ、「夫婦同姓」という原則が作られたという発想です。
「支配」と「被支配」の発想ですね。
私は事実に相違すると考えます。
この事に関して、コメントを分けて説明します。
コメント143の続きです。
「夫婦別姓に関する法律問題・質問2(民法中心)」トピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=51531093&comm_id=4570870&page=1&from=first_page
の最初の方を読むば、民法で「夫婦同姓」の制度が法制化されるまでの、明治政府の「姓」に関する指示が、多少詳しく書いてあります。
――――――――――――――――――――――――
《明治民法制定までの姓に関する簡略法制史》
1.明治3年9月19日太政官布告第608号「自今平民苗氏被差許候事」
(苗字使用許可)
2.明治8年2月13日太政官布告第22号「平民苗字必称令」
(苗字使用義務化)
3.明治9年3月17日太政官指令(明治8年11月9日内務省伺への回答)
(妻は生来の氏を名乗るべき。)
4.明治31年6月21日法律第9号 明治民法施行
(家族同姓)
――――――――――――――――――――――――
まずは、明治3年に「苗字使用許可」という、禁止されていた行為の解放が為されています。
(所謂、江戸期に大多数の民衆に「姓」が無かったは誤りです。公的な使用が禁止されていただけです。)
つまりは、国民の権利を認め、特権階級のみに許された権利を解放するものです。
「富国」の前提に、国民一人一人の地位向上があるのです。
次に明治8年には、「苗字使用義務化」が為されます。
「許可」はあくまで、「使用したいものが使用する。」なので、使用しなくとも別に良かったと考えられます。
少数ではあっても、「姓」が無い人物や、「姓」が忘れられた人物もいたことでしょう。又は、女子に「姓」を使用させない家族もいたかもしれません。
国民一人一人の地位向上に、啓蒙的な処置だったと考えます。
明治9年には、いよいよ「姓」に関する統一制度の方針が出されます。
国民国家としての統一を、より強固にする為に、基本的な民政制度の統一化を図るは素直な施策です。
肝心なことは、この時期に明治政府は「夫婦別姓」を指令していたことです。
そうして、明治31年に民法が施行されました。ここで制度化された「家制度」には、「富国強兵」を推進する「意図」があったと解釈されても違和感はありません。
但し、明治期の「家制度」が必ず「夫婦同姓」であることを必要としてしていたとは思えません。
「家制度」にとって、「夫婦別姓」であっても良く、明治政府は「夫婦別姓」を最初は考えていたと思われます。
それがなぜ、明治9年「夫婦別姓」から明治31年「夫婦同姓」の間に変化したのか?
それは、「武家」や「公家」等の人々 と 「農民」や「商人」の人々で、「姓」に関する慣習と考え方が相違していたからだと考えます。
当初、明治政府の施政者が馴染む制度を指向したが、多数を占める国民からは支持されなかった、実情に馴染まなかったという結果だと考えます。
「富国強制」を推進する「家制度」の設計として「夫婦別姓」を採用しようとしたが、多数の国民の実情を前にして「夫婦同姓」が採用されたという事です。
「夫婦別姓に関する法律問題・質問2(民法中心)」トピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=51531093&comm_id=4570870&page=1&from=first_page
の最初の方を読むば、民法で「夫婦同姓」の制度が法制化されるまでの、明治政府の「姓」に関する指示が、多少詳しく書いてあります。
――――――――――――――――――――――――
《明治民法制定までの姓に関する簡略法制史》
1.明治3年9月19日太政官布告第608号「自今平民苗氏被差許候事」
(苗字使用許可)
2.明治8年2月13日太政官布告第22号「平民苗字必称令」
(苗字使用義務化)
3.明治9年3月17日太政官指令(明治8年11月9日内務省伺への回答)
(妻は生来の氏を名乗るべき。)
4.明治31年6月21日法律第9号 明治民法施行
(家族同姓)
――――――――――――――――――――――――
まずは、明治3年に「苗字使用許可」という、禁止されていた行為の解放が為されています。
(所謂、江戸期に大多数の民衆に「姓」が無かったは誤りです。公的な使用が禁止されていただけです。)
つまりは、国民の権利を認め、特権階級のみに許された権利を解放するものです。
「富国」の前提に、国民一人一人の地位向上があるのです。
次に明治8年には、「苗字使用義務化」が為されます。
「許可」はあくまで、「使用したいものが使用する。」なので、使用しなくとも別に良かったと考えられます。
少数ではあっても、「姓」が無い人物や、「姓」が忘れられた人物もいたことでしょう。又は、女子に「姓」を使用させない家族もいたかもしれません。
国民一人一人の地位向上に、啓蒙的な処置だったと考えます。
明治9年には、いよいよ「姓」に関する統一制度の方針が出されます。
国民国家としての統一を、より強固にする為に、基本的な民政制度の統一化を図るは素直な施策です。
肝心なことは、この時期に明治政府は「夫婦別姓」を指令していたことです。
そうして、明治31年に民法が施行されました。ここで制度化された「家制度」には、「富国強兵」を推進する「意図」があったと解釈されても違和感はありません。
但し、明治期の「家制度」が必ず「夫婦同姓」であることを必要としてしていたとは思えません。
「家制度」にとって、「夫婦別姓」であっても良く、明治政府は「夫婦別姓」を最初は考えていたと思われます。
それがなぜ、明治9年「夫婦別姓」から明治31年「夫婦同姓」の間に変化したのか?
それは、「武家」や「公家」等の人々 と 「農民」や「商人」の人々で、「姓」に関する慣習と考え方が相違していたからだと考えます。
当初、明治政府の施政者が馴染む制度を指向したが、多数を占める国民からは支持されなかった、実情に馴染まなかったという結果だと考えます。
「富国強制」を推進する「家制度」の設計として「夫婦別姓」を採用しようとしたが、多数の国民の実情を前にして「夫婦同姓」が採用されたという事です。
夫婦別姓問題に関わらず、日本の政治に大きな動きが生じようとしています。
衆議院選挙です。
大方の見方として、政権交代が生じる結果となる見込みです。
現実は、不確実ですので、予想はあくまで予想です。
当コミュニティの参加者は、ほとんどの人が日本国の選挙権を持っていると思います。
面白いアンケート結果を見つけましたの紹介します。
間際の提示ですが、参考にでもなれば、コムニュティの副管理人として嬉しいです。
「みどりの一期一会」
http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/d3955e48143f59076a2dc0a1cb7d49c1
『「ジェンダー平等政策」全政党公開アンケートの結果のご報告/<私たちの手で>政策疑問ぶつける 公約
(2012-12-09 17:12:09 | ジェンダー/上野千鶴子)』
各政党の「夫婦別姓問題」に対する姿勢が少しわかります。
衆議院選挙です。
大方の見方として、政権交代が生じる結果となる見込みです。
現実は、不確実ですので、予想はあくまで予想です。
当コミュニティの参加者は、ほとんどの人が日本国の選挙権を持っていると思います。
面白いアンケート結果を見つけましたの紹介します。
間際の提示ですが、参考にでもなれば、コムニュティの副管理人として嬉しいです。
「みどりの一期一会」
http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/d3955e48143f59076a2dc0a1cb7d49c1
『「ジェンダー平等政策」全政党公開アンケートの結果のご報告/<私たちの手で>政策疑問ぶつける 公約
(2012-12-09 17:12:09 | ジェンダー/上野千鶴子)』
各政党の「夫婦別姓問題」に対する姿勢が少しわかります。
2012年衆議院選挙で、自民党が安定過半数を大幅に超える国会議員を当選させました。
政権交代です。
巷では、新内閣の顔ぶれ予想が盛んです。
「安倍内閣・・閣僚の顔ぶれ予想」(2012/12/20 13:03)
http://sibaryou55.iza.ne.jp/blog/entry/2958486/
『麻生太郎・・財務・・平成の高橋是清で決まり。
谷垣禎一・・外務?法務?
山本一太・・総務?
山谷えり子・・拉致担当
石原伸晃・・環境?
茂木敏充・・経産
甘利明・・経済再生担当相・・決まり
下村博文・・文部
林芳正・・金融?
稲田朋美・・法務
小渕優子・・少子化
高市早苗・・厚生労
浜田靖一・・防衛相』
稲田朋美議員の法務大臣には大賛成です。
ところで、
「夫婦別姓待つ身の溜息」
http://fb-hint.tea-nifty.com/
私の記憶では、最近、丸山和也議員の法務大臣就任予測の事が書かれていたと思ったのですが、……
ま、どでもいいか。
政権交代です。
巷では、新内閣の顔ぶれ予想が盛んです。
「安倍内閣・・閣僚の顔ぶれ予想」(2012/12/20 13:03)
http://sibaryou55.iza.ne.jp/blog/entry/2958486/
『麻生太郎・・財務・・平成の高橋是清で決まり。
谷垣禎一・・外務?法務?
山本一太・・総務?
山谷えり子・・拉致担当
石原伸晃・・環境?
茂木敏充・・経産
甘利明・・経済再生担当相・・決まり
下村博文・・文部
林芳正・・金融?
稲田朋美・・法務
小渕優子・・少子化
高市早苗・・厚生労
浜田靖一・・防衛相』
稲田朋美議員の法務大臣には大賛成です。
ところで、
「夫婦別姓待つ身の溜息」
http://fb-hint.tea-nifty.com/
私の記憶では、最近、丸山和也議員の法務大臣就任予測の事が書かれていたと思ったのですが、……
ま、どでもいいか。
政権交代がされて、やっと巻き返しの動きが出始めました。
「男女共同参画会議に教育学者の高橋史朗氏 伝統的家族観へ是正も」(産経ニュース 2013.1.11 01:45)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130111/plc13011101460004-n1.htm
『安倍晋三首相は10日、政府の男女共同参画会議(議長・菅義偉官房長官)のメンバーに、教育学者の高橋史朗明星大教授を起用する方針を固めた。高橋氏の起用は、「男女共同参画」に名を借りた行き過ぎた性教育を容認するようなジェンダーフリー(男女の性差否定)や夫婦別姓制度をめぐり、民主党政権下で相次いだ伝統的家族観を崩す方向への動きを是正する狙いがありそうだ。』
「男女共同参画会議に教育学者の高橋史朗氏 伝統的家族観へ是正も」(産経ニュース 2013.1.11 01:45)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130111/plc13011101460004-n1.htm
『安倍晋三首相は10日、政府の男女共同参画会議(議長・菅義偉官房長官)のメンバーに、教育学者の高橋史朗明星大教授を起用する方針を固めた。高橋氏の起用は、「男女共同参画」に名を借りた行き過ぎた性教育を容認するようなジェンダーフリー(男女の性差否定)や夫婦別姓制度をめぐり、民主党政権下で相次いだ伝統的家族観を崩す方向への動きを是正する狙いがありそうだ。』
「婚外子相続差別規定を削除する民法改正案を3党共同で参院に提出」(2013年04月26日 民主党広報委員会)
http://www.dpj.or.jp/article/102390/%E5%A9%9A%E5%A4%96%E5%AD%90%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%EF%BC%93%E5%85%9A%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%A7%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
『民主党は26日、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めている民法の婚外子差別規定の削除を内容とする法案をみんなの党、社民党と共同で参院に提出した。
民主党は選択的夫婦別姓制度の導入などの内容と一体の民法改正案を1998年以来過去16回、野党共同で衆参両院に提出してきたが、最高裁第一小法廷が2月、婚外子相続差別について争われている上告事件の審理を大法廷に回付する決定を行ったことから、婚外子相続差別を合憲としてきた過去の判例を変更して違憲判決を出す可能性が高まっているとして、立法府としても違憲判決を待たずに婚外子相続差別規定の早期改正に取り組むべきとの考えで3党が一致した。3党の提出者らは記者会見で、各党に呼びかけて参院での可決を目指す考えを表明した。』
私は、みんなの党 を警戒しています。
ほとんど存在感のなくなった社民党、ボロボロ状態の民主党、
この2党を見限って、ヨカラヌ輩が向かう先は みんなの党 だと予測しています。
http://www.dpj.or.jp/article/102390/%E5%A9%9A%E5%A4%96%E5%AD%90%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%EF%BC%93%E5%85%9A%E5%85%B1%E5%90%8C%E3%81%A7%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
『民主党は26日、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めている民法の婚外子差別規定の削除を内容とする法案をみんなの党、社民党と共同で参院に提出した。
民主党は選択的夫婦別姓制度の導入などの内容と一体の民法改正案を1998年以来過去16回、野党共同で衆参両院に提出してきたが、最高裁第一小法廷が2月、婚外子相続差別について争われている上告事件の審理を大法廷に回付する決定を行ったことから、婚外子相続差別を合憲としてきた過去の判例を変更して違憲判決を出す可能性が高まっているとして、立法府としても違憲判決を待たずに婚外子相続差別規定の早期改正に取り組むべきとの考えで3党が一致した。3党の提出者らは記者会見で、各党に呼びかけて参院での可決を目指す考えを表明した。』
私は、みんなの党 を警戒しています。
ほとんど存在感のなくなった社民党、ボロボロ状態の民主党、
この2党を見限って、ヨカラヌ輩が向かう先は みんなの党 だと予測しています。
残念ながら、子の相続割合に関する民法規定の改正(気分は改悪)は国会で可決されました。
その改正内容を報告します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
≪平成25年法律第94号抄(民法の改正)≫
民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/min/h25-094.htm
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
『第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。』
≪平成25年法律第94号附則≫
民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/sup/h25-094.htm
附 則
(施行期日)
『1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。』
≪民法 新旧対照表 7≫
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min/r007.htm
【改正前】
(法定相続分)
第九百条 〔略〕
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
【改正後】
第九百条 〔略〕
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
その改正内容を報告します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
≪平成25年法律第94号抄(民法の改正)≫
民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/min/h25-094.htm
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
『第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。』
≪平成25年法律第94号附則≫
民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/sup/h25-094.htm
附 則
(施行期日)
『1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。』
≪民法 新旧対照表 7≫
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min/r007.htm
【改正前】
(法定相続分)
第九百条 〔略〕
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
【改正後】
第九百条 〔略〕
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
だいぶ、古いネタを拾ってきました。
松島みどり法相が、平成26年10月8日の参院予算委員会で、このように答弁したらしいです。
「法務省としては現在、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入はできないと考えている」
ソリャソーでしょうね。選択的夫婦別姓に反対、若しくは慎重な意見の国会議員の方が多いいのです。
選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案が可決されると考える方がどうかしています。
でも、この答弁を問題視する人がいるようです。現実を無視した考えをする議員もいるのですね。
日本共産党:仁比聡平議員のようです。
法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を提言する答申を出した経緯などを示し、
「こうした積み重ねをご破算にするというのか。」と質したとようです。
松島法相の答弁:「現時点での状況判断で、できないと説明した。」
アッタリ前の事です。ことばを補足して繰り返し説明しないと解らない内容ではありません。
すると、
姓は憲法が保障する人格権であり、国連人権機関からも繰り返し日本への是正勧告が出ている内容の説明をした上で、
「(選択的夫婦別姓が)基本的人権にかかわる問題だとの認識はあるのか。」と、更に質したようです。
ウワー、どうやら正義らしきものを振りかざして、現実がどうであろうと、選択的夫婦別姓制度は導入されないといけないと考えているようですね。
導入できるかどうか、政府に頼らず、立法府を構成員たる議員として、議員立法を目指せばいいじゃないかな?
他力本願な正義漢です。
松島法相の考えは、次の答弁のようなものだったようです。
「選択的夫婦別姓を導入するか否かは、基本的人権にかかわる問題ではなく立法政策上の問題だ。」
ホー。ただ単に現実問題として「選択的夫婦別姓制度の導入ができない。」だけではなく、
「基本的人権の問題では無い。」という点を明らかにしましたね。
妥当な見解です。「基本的人権」という美辞麗句を濫用する人々にはショックなことでしょう。
「選択的夫婦別姓 人権の問題ではない」(赤旗 2014年10月19日(日))
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-10-19/2014101902_05_1.html
『仁比氏は「これまでの(議論の)積み重ねに背を向けるものだ」「頭を冷やしてよく考えるべきだ」と批判しました。』
仁比聡平議員は自分自身へ自問自答した方が良いですね。
因みに、
「松島みどり」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A#.E9.81.B8.E6.8A.9E.E7.9A.84.E5.A4.AB.E5.A9.A6.E5.88.A5.E5.A7.93
『選択的夫婦別姓
選択的夫婦別姓制度の導入に賛成しており、2014年9月5日、閣議後の記者会見において「旧姓では銀行口座を開設できないなど、女性が働く中で不便を感じる人が増えている」と述べ、民法改正への言及は避けつつも、「現実的な運用について議論したい」と改善の方法を検討する意向を示した。また2001年3月15日に、「国会では通称使用しているが、戸籍名の当選証書を手にしたときのショックは忘れられない。選択制なのだから、別姓にしたい人は好きにさせてほしい。」と述べている。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
選択的夫婦別姓に好意的な意見を持っている大臣だったに……、
先鋭的な理想論者の偏狂さを再認識したことでしょう。
松島みどり法相が、平成26年10月8日の参院予算委員会で、このように答弁したらしいです。
「法務省としては現在、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入はできないと考えている」
ソリャソーでしょうね。選択的夫婦別姓に反対、若しくは慎重な意見の国会議員の方が多いいのです。
選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案が可決されると考える方がどうかしています。
でも、この答弁を問題視する人がいるようです。現実を無視した考えをする議員もいるのですね。
日本共産党:仁比聡平議員のようです。
法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を提言する答申を出した経緯などを示し、
「こうした積み重ねをご破算にするというのか。」と質したとようです。
松島法相の答弁:「現時点での状況判断で、できないと説明した。」
アッタリ前の事です。ことばを補足して繰り返し説明しないと解らない内容ではありません。
すると、
姓は憲法が保障する人格権であり、国連人権機関からも繰り返し日本への是正勧告が出ている内容の説明をした上で、
「(選択的夫婦別姓が)基本的人権にかかわる問題だとの認識はあるのか。」と、更に質したようです。
ウワー、どうやら正義らしきものを振りかざして、現実がどうであろうと、選択的夫婦別姓制度は導入されないといけないと考えているようですね。
導入できるかどうか、政府に頼らず、立法府を構成員たる議員として、議員立法を目指せばいいじゃないかな?
他力本願な正義漢です。
松島法相の考えは、次の答弁のようなものだったようです。
「選択的夫婦別姓を導入するか否かは、基本的人権にかかわる問題ではなく立法政策上の問題だ。」
ホー。ただ単に現実問題として「選択的夫婦別姓制度の導入ができない。」だけではなく、
「基本的人権の問題では無い。」という点を明らかにしましたね。
妥当な見解です。「基本的人権」という美辞麗句を濫用する人々にはショックなことでしょう。
「選択的夫婦別姓 人権の問題ではない」(赤旗 2014年10月19日(日))
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-10-19/2014101902_05_1.html
『仁比氏は「これまでの(議論の)積み重ねに背を向けるものだ」「頭を冷やしてよく考えるべきだ」と批判しました。』
仁比聡平議員は自分自身へ自問自答した方が良いですね。
因みに、
「松島みどり」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A#.E9.81.B8.E6.8A.9E.E7.9A.84.E5.A4.AB.E5.A9.A6.E5.88.A5.E5.A7.93
『選択的夫婦別姓
選択的夫婦別姓制度の導入に賛成しており、2014年9月5日、閣議後の記者会見において「旧姓では銀行口座を開設できないなど、女性が働く中で不便を感じる人が増えている」と述べ、民法改正への言及は避けつつも、「現実的な運用について議論したい」と改善の方法を検討する意向を示した。また2001年3月15日に、「国会では通称使用しているが、戸籍名の当選証書を手にしたときのショックは忘れられない。選択制なのだから、別姓にしたい人は好きにさせてほしい。」と述べている。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
選択的夫婦別姓に好意的な意見を持っている大臣だったに……、
先鋭的な理想論者の偏狂さを再認識したことでしょう。
気になったので、現(平成27年1月6日現在)法務大臣の「選択的夫婦別姓」に対する意見を、少しだけ調べてみました。
「上川陽子」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B7%9D%E9%99%BD%E5%AD%90
『選択的夫婦別姓制度の導入に賛成。「日常生活の中で女性が活躍する際に壁になっていることはできるだけ避けていくように努力していきたいという思いの中で取り組んできたこと」「(夫婦同姓を強制する制度が人権問題であり、人権を制約し、その解決が問題になっている)といったことも総合的に勘案しながら考えていくべきこと」、と述べる。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
ウーン。どうしたものでしょう。
「上川陽子」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B7%9D%E9%99%BD%E5%AD%90
『選択的夫婦別姓制度の導入に賛成。「日常生活の中で女性が活躍する際に壁になっていることはできるだけ避けていくように努力していきたいという思いの中で取り組んできたこと」「(夫婦同姓を強制する制度が人権問題であり、人権を制約し、その解決が問題になっている)といったことも総合的に勘案しながら考えていくべきこと」、と述べる。』
(フリー百科事典ウィキペディア(WIKIPEDIA))
ウーン。どうしたものでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00002703-bengocom-soci
夫婦別姓」最高裁が憲法判断へ「結婚前の姓を使うためペーパー離婚した」原告も期待
「夫婦別姓」をめぐる訴訟が2月18日、最高裁判所の第3小法廷(大橋正春裁判長)から大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付された。最高裁の大法廷は、長官を含む15人の裁判官全員で、憲法問題や判例変更などの重要問題を審理する。今回は、夫婦同姓制度を定めた民法750条について、憲法判断が行われるとみられる。
これを受け、訴訟の原告と弁護団が同日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。榊原富士子弁護団長は「最高裁大法廷に回すということは、憲法判断をするということだ。まず一歩。とてもうれしい。最高裁の積極的な姿勢を感じている。最高裁には、明確に『憲法違反である』と書いていただきたい。それが、私たちの切なる思いだ」と話した。
●「夫婦同姓を定めた民法750条は憲法違反」
この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償を求めて2011年に起こした。だが、原告たちが本当に求めているのは「夫婦別姓を選べる制度」を実現すること。つまり、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することだ。
榊原弁護団長は「いまの制度は、名前か、結婚かの二者択一状態だ。結婚前の姓を使えなくなることは、憲法13条の人格権を侵害する。結婚できなくなることは、憲法24条で認められている結婚する権利を侵害することになる」と述べ、民法750条が憲法違反だと強調した。
弁護団の大谷美紀子弁護士は「国連の女性差別撤廃委員会も、民法750条を改正するよう日本政府に勧告している」とつけ加えた。
夫婦別姓を求める背景について、弁護団は、結婚後も元の名前を使いたいというニーズが高まり、「通称」を使える場面が増えているが、通称では結局2つの姓を使い分けなければならず、解決にはならないと説明。夫婦別姓制度へ向けた機運は十分に醸成されたとしている。
●「自分の名前が本物じゃなくなってしまった」
原告の1人であるフリーライターの加山恵美さん(43)は、2000年に結婚し、夫の姓に合わせた。その際、加山さんは「それまでずっと『加山』でいたのに、それが通称になってしまったり、ペンネームになってしまった。住民票の姓が取り消し線で消されたのを見て、自分の名前が本物じゃなくなってしまったかのような、残念な気持ちになった」という。
結局、加山さん夫婦は2004年、もとの姓を使うために「ペーパー離婚」をすることにした。現在は事実婚状態だという。仕事中に連絡を受けて、会見に駆けつけたという加山さんは「ペーパー離婚をしたときには、すぐに夫婦別姓が認められ、また結婚できると思っていたが、10年経ってもそのままだ」と話した。
最高裁大法廷に回付されたことについては、「いまはまだ半信半疑で、過度な期待はしないようにと思っている」と述べつつも、「夫婦別姓が認められていないことで、多くの夫婦が困っている。最高裁にはよく考えて判断してもらいたい」と希望を語っていた。
>民法750条が憲法違反だと強調した。
法で妻が夫の姓になることを強制などしていない。
法律的婚姻関係になること、同一の戸籍に入ることも強制などしていない。
別姓に拘るなら法律的婚姻になる必要などないではないか。
なぜ国が慰謝料まで払う必要がある?
夫婦別姓」最高裁が憲法判断へ「結婚前の姓を使うためペーパー離婚した」原告も期待
「夫婦別姓」をめぐる訴訟が2月18日、最高裁判所の第3小法廷(大橋正春裁判長)から大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付された。最高裁の大法廷は、長官を含む15人の裁判官全員で、憲法問題や判例変更などの重要問題を審理する。今回は、夫婦同姓制度を定めた民法750条について、憲法判断が行われるとみられる。
これを受け、訴訟の原告と弁護団が同日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。榊原富士子弁護団長は「最高裁大法廷に回すということは、憲法判断をするということだ。まず一歩。とてもうれしい。最高裁の積極的な姿勢を感じている。最高裁には、明確に『憲法違反である』と書いていただきたい。それが、私たちの切なる思いだ」と話した。
●「夫婦同姓を定めた民法750条は憲法違反」
この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償を求めて2011年に起こした。だが、原告たちが本当に求めているのは「夫婦別姓を選べる制度」を実現すること。つまり、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することだ。
榊原弁護団長は「いまの制度は、名前か、結婚かの二者択一状態だ。結婚前の姓を使えなくなることは、憲法13条の人格権を侵害する。結婚できなくなることは、憲法24条で認められている結婚する権利を侵害することになる」と述べ、民法750条が憲法違反だと強調した。
弁護団の大谷美紀子弁護士は「国連の女性差別撤廃委員会も、民法750条を改正するよう日本政府に勧告している」とつけ加えた。
夫婦別姓を求める背景について、弁護団は、結婚後も元の名前を使いたいというニーズが高まり、「通称」を使える場面が増えているが、通称では結局2つの姓を使い分けなければならず、解決にはならないと説明。夫婦別姓制度へ向けた機運は十分に醸成されたとしている。
●「自分の名前が本物じゃなくなってしまった」
原告の1人であるフリーライターの加山恵美さん(43)は、2000年に結婚し、夫の姓に合わせた。その際、加山さんは「それまでずっと『加山』でいたのに、それが通称になってしまったり、ペンネームになってしまった。住民票の姓が取り消し線で消されたのを見て、自分の名前が本物じゃなくなってしまったかのような、残念な気持ちになった」という。
結局、加山さん夫婦は2004年、もとの姓を使うために「ペーパー離婚」をすることにした。現在は事実婚状態だという。仕事中に連絡を受けて、会見に駆けつけたという加山さんは「ペーパー離婚をしたときには、すぐに夫婦別姓が認められ、また結婚できると思っていたが、10年経ってもそのままだ」と話した。
最高裁大法廷に回付されたことについては、「いまはまだ半信半疑で、過度な期待はしないようにと思っている」と述べつつも、「夫婦別姓が認められていないことで、多くの夫婦が困っている。最高裁にはよく考えて判断してもらいたい」と希望を語っていた。
>民法750条が憲法違反だと強調した。
法で妻が夫の姓になることを強制などしていない。
法律的婚姻関係になること、同一の戸籍に入ることも強制などしていない。
別姓に拘るなら法律的婚姻になる必要などないではないか。
なぜ国が慰謝料まで払う必要がある?
夫婦別姓―多様な家族認めるとき
2015年2月20日(金)付:朝日新聞社説
夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や男女平等などの憲法の理念に沿うのか。最高裁が判断することになった。地裁、高裁で退けられた事実婚の夫婦ら5人の訴えが、最高裁で大法廷に回された。判決はまだ先だが、最高裁は、高裁の判断をそのまま追認するわけではない姿勢を示唆している。
生き方や、家族の形が多様化するなか、例外なく夫婦の一方に姓を変えさせる民法は、もはや時代にそぐわず、柔軟さを欠いている。最高裁は現実をつぶさにみて、考えてほしい。
法制審議会は19年も前に「結婚しても姓を変えない利益を保護する必要がある」として、別姓を選べる民法改正要綱案を答申した。法務省が法案を準備し、是正の道筋をつけた。実現していないのは保守系議員が「家族の崩壊を招く」などと反対してきたからだ。
必要な人に選択肢を与える改正なのに、それを許さない一部議員の姿勢は頑迷というほかない。12年の政府の世論調査では、「夫婦は同姓にすべきだ」と「希望すれば旧姓を名乗れるよう法改正していい」が拮抗(きっこう)するが、年代別では20〜50代で「別姓許容」が上回る。今後の社会を担う世代の意識を重んじていくべきだろう。
結婚で姓を変える96%は妻の側で、負担は女性に集中する。「女性の活躍を阻むあらゆる課題に挑戦する」と安倍政権は宣言している。ならばまず、選択的別姓を阻んできた自民党の姿勢を顧み、改めるべきだ。最高裁から言われる前に、国会自らが実行すべき問題である。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11610852.html
2015年2月20日(金)付:朝日新聞社説
夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や男女平等などの憲法の理念に沿うのか。最高裁が判断することになった。地裁、高裁で退けられた事実婚の夫婦ら5人の訴えが、最高裁で大法廷に回された。判決はまだ先だが、最高裁は、高裁の判断をそのまま追認するわけではない姿勢を示唆している。
生き方や、家族の形が多様化するなか、例外なく夫婦の一方に姓を変えさせる民法は、もはや時代にそぐわず、柔軟さを欠いている。最高裁は現実をつぶさにみて、考えてほしい。
法制審議会は19年も前に「結婚しても姓を変えない利益を保護する必要がある」として、別姓を選べる民法改正要綱案を答申した。法務省が法案を準備し、是正の道筋をつけた。実現していないのは保守系議員が「家族の崩壊を招く」などと反対してきたからだ。
必要な人に選択肢を与える改正なのに、それを許さない一部議員の姿勢は頑迷というほかない。12年の政府の世論調査では、「夫婦は同姓にすべきだ」と「希望すれば旧姓を名乗れるよう法改正していい」が拮抗(きっこう)するが、年代別では20〜50代で「別姓許容」が上回る。今後の社会を担う世代の意識を重んじていくべきだろう。
結婚で姓を変える96%は妻の側で、負担は女性に集中する。「女性の活躍を阻むあらゆる課題に挑戦する」と安倍政権は宣言している。ならばまず、選択的別姓を阻んできた自民党の姿勢を顧み、改めるべきだ。最高裁から言われる前に、国会自らが実行すべき問題である。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11610852.html
>>[159]
賛同します。ほんとに、同感です。
ちなみに、
『生き方や、家族の形が多様化するなか、例外なく夫婦の一方に姓を変えさせる民法は、もはや時代にそぐわず、柔軟さを欠いている。最高裁は現実をつぶさにみて、考えてほしい。』
こういう、時代に即しているかどうかという論旨であれば、それは立法府の判断するところ、選択の問題です。
最高裁判所が現憲法条文に照らして判断すべき、合憲・違憲の問題ではありません。
朝日新聞等が、過去・現在の立法府に在籍した
『一部議員の姿勢は頑迷』
に不満を感じて、論難するのは構いませんが、司法の判断を期待するのは筋違いでしょう。
こういった論理展開には、独善的な権力を指向する、不気味さを感じてしまいます。
賛同します。ほんとに、同感です。
ちなみに、
『生き方や、家族の形が多様化するなか、例外なく夫婦の一方に姓を変えさせる民法は、もはや時代にそぐわず、柔軟さを欠いている。最高裁は現実をつぶさにみて、考えてほしい。』
こういう、時代に即しているかどうかという論旨であれば、それは立法府の判断するところ、選択の問題です。
最高裁判所が現憲法条文に照らして判断すべき、合憲・違憲の問題ではありません。
朝日新聞等が、過去・現在の立法府に在籍した
『一部議員の姿勢は頑迷』
に不満を感じて、論難するのは構いませんが、司法の判断を期待するのは筋違いでしょう。
こういった論理展開には、独善的な権力を指向する、不気味さを感じてしまいます。
「野党6党派、選択的夫婦別姓法案を共同提出 野田聖子総務相は距離置く姿勢」
(産経新聞 2018.6.14 18:02)
https://www.sankei.com/politics/news/180614/plt1806140028-n1.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
立憲民主、国民民主、共産、自由、社民各党と衆院会派「無所属の会」は14日、選択的夫婦別姓を認める民法改正案を衆院に共同提出した。
別姓の夫婦に生まれた子供については、出生時に父母が協議して姓を決める。法施行後2年間に限り、すでに結婚している夫婦でも婚姻前の姓に戻すことができる経過措置を設ける。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
半年も前の報道ですが、法案の提出がされています。
おそらく、今も継続審議中でしょう。
テーマは違いますが、次のような対談も行われています。
「国会の空気も変わってきた」——山尾志桜里×青野慶久が振り返る「2017年の政治・働き方改革」
https://www.businessinsider.jp/post-108356
(産経新聞 2018.6.14 18:02)
https://www.sankei.com/politics/news/180614/plt1806140028-n1.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
立憲民主、国民民主、共産、自由、社民各党と衆院会派「無所属の会」は14日、選択的夫婦別姓を認める民法改正案を衆院に共同提出した。
別姓の夫婦に生まれた子供については、出生時に父母が協議して姓を決める。法施行後2年間に限り、すでに結婚している夫婦でも婚姻前の姓に戻すことができる経過措置を設ける。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
半年も前の報道ですが、法案の提出がされています。
おそらく、今も継続審議中でしょう。
テーマは違いますが、次のような対談も行われています。
「国会の空気も変わってきた」——山尾志桜里×青野慶久が振り返る「2017年の政治・働き方改革」
https://www.businessinsider.jp/post-108356
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
選択的夫婦別姓制度法制化反対 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-