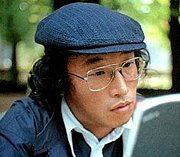<1周目にお世話になった書籍への謝意>
チャンピオン
★ホフマイヤー『生命記号論』
パースの3項関係を深く取り上げます。
<パースの3項関係は、進化トピの基本です!>
自己流にこう言い換えました。
記号→解釈(観測)→意味
ホフマイヤーのパース解釈の深さは最高レベルです。
その3項関係が水平方向に連鎖しているのが世界です。
私は層(上下)を重視しません。水平方向(横)の関係重視。
意識は、身体の上位項と見るのではなく、意味と記号の間を行き来する記号過程と見ます。
「私たちは徹底的に血と肉であり、この惑星の記号圏である地位を占めており、他の全ての生物と共にある基本的な関係の中に組み込まれている」
私もそれに共感します。この本が提示している問題は深く大きいです。
読んで損無し!(旧トピ#657〜で掲載しました)
追加
訳者:松野 孝一郎が書いた「あとがき」が本文より気合い入ってます。
★生命を記述する新しい方法論としての「内部観測」!惚れた
(郡司ペギオ‐幸夫、オットー・E. レスラーと共著で『内部観測』という題の本を出されてます)
★郡司ペギオー幸夫
『生命壱号』
これは2周目の教科書としたい。
郡司ペギオは、パースの3項関係をこう変形します。
トークン(個物)、タイプ(類)、2項を調停するもの
「調停」とは観測者。「調停」はシステムや境界そのもの、またはエンジンと言えるでしょう。
★下條信輔
『サブリミナル・マインド: 潜在的人間観のゆくえ』中公新書、1996
『「意識」とは何だろうか 脳の来歴、知覚の錯誤』講談社現代新書、1999
『サブリミナル・インパクト 情動と潜在認知の現代』ちくま新書、2008
どれも素晴らしい!新刊が出たら絶対買う!
「自分は自分で思っているほど自分のことを知らない」
その通りだと思います。「私」=精神は初めから在るのではなく、コストを掛けて構成されているのだと感じます。「時間」も同様。
「私」を構成するコスト=「時間」を構成するコスト
生命=時間
★内田樹
『寝ながら学べる構造主義』
これが内田樹の一番の名作だと思います。皆さんもぜひ読んで欲しい。平易で含蓄に富みます。
トピでほとんどやってないけど(笑)、私の潜在的思想背景になっています。
★下條信輔の認知科学と内田樹の構造主義を合わせると、「私」=精神は事後的に措定されるものとなります。つまり社会的文脈が「私」=精神です。(宇宙的文脈と言っていいかもしれません)
他者との関係から事後的に構成されるものが「私」=精神。
「私」=精神を初めから在る実在と考えず、コストを掛けて構成された存在と考えたい。
精神の特殊性を強調しない。精神の素材とされる「もの」をモノ扱いしない。
むしろ「もの」は精神に参加・関与している。
「もの」は原理に積極的にコミットしている、
と考えたいのです。
★池田清彦
『構造主義科学論の冒険』
全体的に分かりやすくお薦め。第五章は特に支持。
でも「私の観念、経験」も疑う余地があると私は考えます。(第二章)よって、自明なる「私」を、科学の基底に据えることは不可能と考えます。
★福岡伸一
『生物と無生物のあいだ』
1周目序盤に世話になりました。
代謝回転(ターンオーバー)、「内部の内部は外部」
また2周目にも復活の予感です。
★清水博(&西田幾多郎の絶対矛盾的自己同一哲学)
『生命と場所――創造する生命の原理』(新装版, NTT出版, 1999年)
「場所」という考えは重要だと思います。
矛盾した表現を持つ哲学も、生命を語るに有効です。なぜなら、
哲学が実装された具体的な形が生命だと思うからです。
★宮台真司(&速水由紀子)
『サイファ覚醒せよ!』
学問の臨界点に言及します。
その学問の臨界点(=特異点)をむしろ積極的に転換します。すなわち、
サイファ=特異点(名状しがたいもの)を媒介としてより良い「生」を模索します。学問の統一理論にもなってる。名著。
☆竹内薫
主にブルーバックス。めざせ!ポスト都筑卓司!
☆大野乾
『生命の誕生と進化』
専門用語満載だが、専門用語は読み飛ばしても趣旨は分かります。図書館でどうぞ。
遺伝暗号・コドンの単位がなぜ3個なのかを見事に説明します。
生命は遺伝子重複によって進化してきた。この遺伝子重複説は有名。
【一創造百盗作】
世界は、(めったに起こらない)発明と、その発明の盗作的繰り返しである。
(私は最近、“繰り返し”も創造に繋がっていると感じるようになった。既にある何かの反復と、それが固有の何かであることは矛盾しない)
★動画
郡司ペギオー幸夫
http://
浅田彰
http://
http://
http://
「機械論的世界と有機体論的世界という2分対立は19世紀に捏造されたフィクションである」
2周目のテーマは2項対立の齟齬の調停です。
________________
<進化トピ2周目のキーワード>
これからの進化トピのキーワードは、
「内部観測」
「境界」
「同一性」の懐疑→「ズレ・齟齬」の重視
「ズレ・齟齬」の「調停」→これが思考・論理を構成
「媒介」
「インターフェイス」
です。
★素材と原理を分離する考えでは拙いと思います。
「もの」を、新たな原理を創造する「インターフェイス」と考えたいのです。
そうしなければ“創発”を導けません。
素材と原理が分離できるのは、あくまで“創発”が起こった後に限られます。
★生命とは、両義性を持ち、かつ矛盾する2項の境界運動と考えます。
その境界は制御不能です。その境界制御不能性が生命のエンジンであり、進化を保証していると考えます。
2項とはすなわち、
郡司ペギオならトークン(個物)とタイプ(類)、
暗黙知理論なら(全体従属的)細目と(包括的)全体です。
2項を矛盾に陥らせることなく、齟齬を「調停」する「媒介」項を考えます。
つまり、
★細目と全体を結び付けてるものは何だろうと考えるのです。
それはXの「コミットメント」ですね。
何か(X)のコミットメントによって、記号が意味に昇華し、細目から全体に至るのだと考えます。
★X=「もの」と考えます。「もの」はモノではありません。
「もの」がコミットして、「存在」が構成されると考えます。「もの」に「人格」の地位を与えたいのです。
この唯物論者め!と言うなかれ。
「もの」と精神が分離したままでは、精神の特殊性ばかりが強調されるばかりで、逆に精神が衰退すると思うのです。
★「もの」は、存在にコミットする「中心」です。
「もの」=「中心」がコミットする「場所」が生命です。
「場所」とは、「もの」=「中心」が幻視するイメージと考えます。
進化とは、幻視=イメージが変容することで起きると考えます。
★私は、生命を複数の「中心」から構成される“民主主義”のようなものと考えています。
よって生命は大雑把に統合されているだけで、反逆は日常茶飯事です。生命が安定するには強い幻=イメージ(→権力)が必要と考えます。
★暗黙知を「もの」の理と考えます。「もの」は同一性があるものではなく、各々「ズレ」ている。「ズレ」ているからこそ齟齬が生まれ、その調停として論理が発生すると考えます。
「もの」の理と物理(自然科学)を統合し、「拡張された自然法則」(by M.ポランニー)を完成させましょう。
★宇宙(世界)は、法則(外部観測)に従事しているのではないと考えます。
世界に「同一性」は存在しません。法則ではなく行為(内部観測)として世界を見たい。
「もの」は、法則に隷属(workやlabor)なのではありません。
「もの」の本質は、活動(action)だと考えます。
宇宙(世界)は法則ではなく活動です。
宇宙(世界)の運動は、人間の活動(芸術、科学、発明、文明)と同じです。
宇宙(世界)はアートです。哲学です。
チャンピオン
★ホフマイヤー『生命記号論』
パースの3項関係を深く取り上げます。
<パースの3項関係は、進化トピの基本です!>
自己流にこう言い換えました。
記号→解釈(観測)→意味
ホフマイヤーのパース解釈の深さは最高レベルです。
その3項関係が水平方向に連鎖しているのが世界です。
私は層(上下)を重視しません。水平方向(横)の関係重視。
意識は、身体の上位項と見るのではなく、意味と記号の間を行き来する記号過程と見ます。
「私たちは徹底的に血と肉であり、この惑星の記号圏である地位を占めており、他の全ての生物と共にある基本的な関係の中に組み込まれている」
私もそれに共感します。この本が提示している問題は深く大きいです。
読んで損無し!(旧トピ#657〜で掲載しました)
追加
訳者:松野 孝一郎が書いた「あとがき」が本文より気合い入ってます。
★生命を記述する新しい方法論としての「内部観測」!惚れた
(郡司ペギオ‐幸夫、オットー・E. レスラーと共著で『内部観測』という題の本を出されてます)
★郡司ペギオー幸夫
『生命壱号』
これは2周目の教科書としたい。
郡司ペギオは、パースの3項関係をこう変形します。
トークン(個物)、タイプ(類)、2項を調停するもの
「調停」とは観測者。「調停」はシステムや境界そのもの、またはエンジンと言えるでしょう。
★下條信輔
『サブリミナル・マインド: 潜在的人間観のゆくえ』中公新書、1996
『「意識」とは何だろうか 脳の来歴、知覚の錯誤』講談社現代新書、1999
『サブリミナル・インパクト 情動と潜在認知の現代』ちくま新書、2008
どれも素晴らしい!新刊が出たら絶対買う!
「自分は自分で思っているほど自分のことを知らない」
その通りだと思います。「私」=精神は初めから在るのではなく、コストを掛けて構成されているのだと感じます。「時間」も同様。
「私」を構成するコスト=「時間」を構成するコスト
生命=時間
★内田樹
『寝ながら学べる構造主義』
これが内田樹の一番の名作だと思います。皆さんもぜひ読んで欲しい。平易で含蓄に富みます。
トピでほとんどやってないけど(笑)、私の潜在的思想背景になっています。
★下條信輔の認知科学と内田樹の構造主義を合わせると、「私」=精神は事後的に措定されるものとなります。つまり社会的文脈が「私」=精神です。(宇宙的文脈と言っていいかもしれません)
他者との関係から事後的に構成されるものが「私」=精神。
「私」=精神を初めから在る実在と考えず、コストを掛けて構成された存在と考えたい。
精神の特殊性を強調しない。精神の素材とされる「もの」をモノ扱いしない。
むしろ「もの」は精神に参加・関与している。
「もの」は原理に積極的にコミットしている、
と考えたいのです。
★池田清彦
『構造主義科学論の冒険』
全体的に分かりやすくお薦め。第五章は特に支持。
でも「私の観念、経験」も疑う余地があると私は考えます。(第二章)よって、自明なる「私」を、科学の基底に据えることは不可能と考えます。
★福岡伸一
『生物と無生物のあいだ』
1周目序盤に世話になりました。
代謝回転(ターンオーバー)、「内部の内部は外部」
また2周目にも復活の予感です。
★清水博(&西田幾多郎の絶対矛盾的自己同一哲学)
『生命と場所――創造する生命の原理』(新装版, NTT出版, 1999年)
「場所」という考えは重要だと思います。
矛盾した表現を持つ哲学も、生命を語るに有効です。なぜなら、
哲学が実装された具体的な形が生命だと思うからです。
★宮台真司(&速水由紀子)
『サイファ覚醒せよ!』
学問の臨界点に言及します。
その学問の臨界点(=特異点)をむしろ積極的に転換します。すなわち、
サイファ=特異点(名状しがたいもの)を媒介としてより良い「生」を模索します。学問の統一理論にもなってる。名著。
☆竹内薫
主にブルーバックス。めざせ!ポスト都筑卓司!
☆大野乾
『生命の誕生と進化』
専門用語満載だが、専門用語は読み飛ばしても趣旨は分かります。図書館でどうぞ。
遺伝暗号・コドンの単位がなぜ3個なのかを見事に説明します。
生命は遺伝子重複によって進化してきた。この遺伝子重複説は有名。
【一創造百盗作】
世界は、(めったに起こらない)発明と、その発明の盗作的繰り返しである。
(私は最近、“繰り返し”も創造に繋がっていると感じるようになった。既にある何かの反復と、それが固有の何かであることは矛盾しない)
★動画
郡司ペギオー幸夫
http://
浅田彰
http://
http://
http://
「機械論的世界と有機体論的世界という2分対立は19世紀に捏造されたフィクションである」
2周目のテーマは2項対立の齟齬の調停です。
________________
<進化トピ2周目のキーワード>
これからの進化トピのキーワードは、
「内部観測」
「境界」
「同一性」の懐疑→「ズレ・齟齬」の重視
「ズレ・齟齬」の「調停」→これが思考・論理を構成
「媒介」
「インターフェイス」
です。
★素材と原理を分離する考えでは拙いと思います。
「もの」を、新たな原理を創造する「インターフェイス」と考えたいのです。
そうしなければ“創発”を導けません。
素材と原理が分離できるのは、あくまで“創発”が起こった後に限られます。
★生命とは、両義性を持ち、かつ矛盾する2項の境界運動と考えます。
その境界は制御不能です。その境界制御不能性が生命のエンジンであり、進化を保証していると考えます。
2項とはすなわち、
郡司ペギオならトークン(個物)とタイプ(類)、
暗黙知理論なら(全体従属的)細目と(包括的)全体です。
2項を矛盾に陥らせることなく、齟齬を「調停」する「媒介」項を考えます。
つまり、
★細目と全体を結び付けてるものは何だろうと考えるのです。
それはXの「コミットメント」ですね。
何か(X)のコミットメントによって、記号が意味に昇華し、細目から全体に至るのだと考えます。
★X=「もの」と考えます。「もの」はモノではありません。
「もの」がコミットして、「存在」が構成されると考えます。「もの」に「人格」の地位を与えたいのです。
この唯物論者め!と言うなかれ。
「もの」と精神が分離したままでは、精神の特殊性ばかりが強調されるばかりで、逆に精神が衰退すると思うのです。
★「もの」は、存在にコミットする「中心」です。
「もの」=「中心」がコミットする「場所」が生命です。
「場所」とは、「もの」=「中心」が幻視するイメージと考えます。
進化とは、幻視=イメージが変容することで起きると考えます。
★私は、生命を複数の「中心」から構成される“民主主義”のようなものと考えています。
よって生命は大雑把に統合されているだけで、反逆は日常茶飯事です。生命が安定するには強い幻=イメージ(→権力)が必要と考えます。
★暗黙知を「もの」の理と考えます。「もの」は同一性があるものではなく、各々「ズレ」ている。「ズレ」ているからこそ齟齬が生まれ、その調停として論理が発生すると考えます。
「もの」の理と物理(自然科学)を統合し、「拡張された自然法則」(by M.ポランニー)を完成させましょう。
★宇宙(世界)は、法則(外部観測)に従事しているのではないと考えます。
世界に「同一性」は存在しません。法則ではなく行為(内部観測)として世界を見たい。
「もの」は、法則に隷属(workやlabor)なのではありません。
「もの」の本質は、活動(action)だと考えます。
宇宙(世界)は法則ではなく活動です。
宇宙(世界)の運動は、人間の活動(芸術、科学、発明、文明)と同じです。
宇宙(世界)はアートです。哲学です。
|
|
|
|
コメント(740)
【量子経済人類学に向けて】その1
久しぶりに創作意欲が湧く!(コミュ人数も198人と最多記録)
9月28日放送のEテレ・サイエンスZEROを見て触発された。
量子コンピューターがついに実用化されたのだ!
見逃した方も、NHKオンデマンドで108円で見ることができる。
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
=================
★世界は「借金」「自転車操業」から成り立っている。
私は、NHK番組を見て「量子経済人類学」というものを書いてみたくなった。もちろん、今までの話と同じ流れを汲む。
経済人類学における「貨幣」の解説は素晴らしい。貨幣は「弁済しなければならない義務」から始まっている。貨幣は喜ばしいものではない。むしろ「呪い」である。
貨幣(富)を持つ者は、常に他者に対して贈与返礼義務が生じている不安定な状態にいる。
贈与は贈与を生み、世界は自転車操業的に回転する。
生は、貨幣と同じである。生を受けた者は、何者かに「弁済しなければならない義務」が発生している。生は喜ばしいものではない。むしろ「呪い」である。
最終的には、誰かに食われることがゴールである。そうして生物界は自転車操業的に輪廻(回転)する。
☆世界を「借金」「自転車操業」をキーワードに語ろうと思う。
「借金」とは、常に「弁済しなければならない義務」に苛まれている状態だ。世界は、そういう負の状態を互いに擦り付け合う「自転車操業」だと考える。
このキーワードは生物だけに当て嵌まるものではない。量子の性質を理解すると、「借金」「自転車操業」は、「存在するもの全て」に当て嵌まるキーワードだと確信する。
ここからが本編である。
久しぶりに創作意欲が湧く!(コミュ人数も198人と最多記録)
9月28日放送のEテレ・サイエンスZEROを見て触発された。
量子コンピューターがついに実用化されたのだ!
見逃した方も、NHKオンデマンドで108円で見ることができる。
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
=================
★世界は「借金」「自転車操業」から成り立っている。
私は、NHK番組を見て「量子経済人類学」というものを書いてみたくなった。もちろん、今までの話と同じ流れを汲む。
経済人類学における「貨幣」の解説は素晴らしい。貨幣は「弁済しなければならない義務」から始まっている。貨幣は喜ばしいものではない。むしろ「呪い」である。
貨幣(富)を持つ者は、常に他者に対して贈与返礼義務が生じている不安定な状態にいる。
贈与は贈与を生み、世界は自転車操業的に回転する。
生は、貨幣と同じである。生を受けた者は、何者かに「弁済しなければならない義務」が発生している。生は喜ばしいものではない。むしろ「呪い」である。
最終的には、誰かに食われることがゴールである。そうして生物界は自転車操業的に輪廻(回転)する。
☆世界を「借金」「自転車操業」をキーワードに語ろうと思う。
「借金」とは、常に「弁済しなければならない義務」に苛まれている状態だ。世界は、そういう負の状態を互いに擦り付け合う「自転車操業」だと考える。
このキーワードは生物だけに当て嵌まるものではない。量子の性質を理解すると、「借金」「自転車操業」は、「存在するもの全て」に当て嵌まるキーワードだと確信する。
ここからが本編である。
【量子経済人類学に向けて】その2
9月28日放送のEテレ・サイエンスZERO『ついに出た!?夢の“量子コンピューター”』
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
一番重要なことをまず書こう!
《自然界は、エネルギーをなるべく低くしようと働く。》
この性質は非常に重要だ。
エネルギーがあるということは有毒なのだ。過剰。
存在するということは、エネルギーがあるということなので、自然の摂理から見れば有毒なのだ。
生命(存在)は本当は喜ばしいものではないかもしれない。本当はもっと楽に生きられる方法があると思う。解脱。涅槃。
人間は涅槃と逆の生き方をしている。回転かごを猛烈に回し続けるネズミのように。
前回、貨幣は「喜ばしいものではない」と書いた。近代は、本来蕩尽すべき貨幣を、あろうことかずっと溜め込んでいる状況だ。これでは病になってもしかたがない。
生についても同様だ。自分の生は、他人に贈与し続けて“軽く”なることが最も楽な生き方である。生は、単独では喜ばしいものにはなれない。生の過剰な倒錯が、生き辛さを発生させている。
=================
番組での竹内薫の解説は見事だった。
株価のグラフのような無数に上下する放物線をイメージしよう。下図は株価変動の典型例である。(竹内薫の解説に株価の喩えはない。私が言い換えたのだ)
株価は上下し、所々“底値”があるわけだ。その底値周辺をUと表記しよう。
U字の底が一番エネルギーが低い。自然界においては、そこが最適値なのだ。
しかし、無数にU字があるわけだ。
果たして、そのU字の底が、世界で一番の“底=最適値”かどうか分からない。
U
U
U U U
U U
U
↑
ミクシィでグラフを書けないが、脳内で補完して欲しい。飛び飛びのU字を、株価が上下するように線で結んで欲しい。
量子コンピューターの凄いところは状態の重ね合わせができることだ。
番組は、代表的な難問「巡回サラリーマン問題」を解く方法を解説している。
下図では、縦軸がエネルギー(コスト)、横軸が(サラリーマンの)経路となる。
最適値候補であるU字の底を全て重ね合わせる。↑の位置のU字が最適値(答え)だと一発で分かる。
U字一個一個を見ていたら「井の中の蛙大海を知らず」で、そこが一番“底”なのかが分からない。
単体一個ついてどうのこうの言っていたのが従来の科学だ。それは哲学でもそうだった。
「状態の重ね合わせ」(=無数のU字を俯瞰できる観測)によって
エネルギーの低い状態が「何か」が決定できる。
その「何か」を目指して形態が再編成される。無数に連なった一群が、ダイナミックに変動する。
これが進化=世界の運動だと考えるのだ。
量子コンピューターの登場によって、難攻不落の「進化」をついに語ることができるようになった、ということ確信する!
9月28日放送のEテレ・サイエンスZERO『ついに出た!?夢の“量子コンピューター”』
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
一番重要なことをまず書こう!
《自然界は、エネルギーをなるべく低くしようと働く。》
この性質は非常に重要だ。
エネルギーがあるということは有毒なのだ。過剰。
存在するということは、エネルギーがあるということなので、自然の摂理から見れば有毒なのだ。
生命(存在)は本当は喜ばしいものではないかもしれない。本当はもっと楽に生きられる方法があると思う。解脱。涅槃。
人間は涅槃と逆の生き方をしている。回転かごを猛烈に回し続けるネズミのように。
前回、貨幣は「喜ばしいものではない」と書いた。近代は、本来蕩尽すべき貨幣を、あろうことかずっと溜め込んでいる状況だ。これでは病になってもしかたがない。
生についても同様だ。自分の生は、他人に贈与し続けて“軽く”なることが最も楽な生き方である。生は、単独では喜ばしいものにはなれない。生の過剰な倒錯が、生き辛さを発生させている。
=================
番組での竹内薫の解説は見事だった。
株価のグラフのような無数に上下する放物線をイメージしよう。下図は株価変動の典型例である。(竹内薫の解説に株価の喩えはない。私が言い換えたのだ)
株価は上下し、所々“底値”があるわけだ。その底値周辺をUと表記しよう。
U字の底が一番エネルギーが低い。自然界においては、そこが最適値なのだ。
しかし、無数にU字があるわけだ。
果たして、そのU字の底が、世界で一番の“底=最適値”かどうか分からない。
U
U
U U U
U U
U
↑
ミクシィでグラフを書けないが、脳内で補完して欲しい。飛び飛びのU字を、株価が上下するように線で結んで欲しい。
量子コンピューターの凄いところは状態の重ね合わせができることだ。
番組は、代表的な難問「巡回サラリーマン問題」を解く方法を解説している。
下図では、縦軸がエネルギー(コスト)、横軸が(サラリーマンの)経路となる。
最適値候補であるU字の底を全て重ね合わせる。↑の位置のU字が最適値(答え)だと一発で分かる。
U字一個一個を見ていたら「井の中の蛙大海を知らず」で、そこが一番“底”なのかが分からない。
単体一個ついてどうのこうの言っていたのが従来の科学だ。それは哲学でもそうだった。
「状態の重ね合わせ」(=無数のU字を俯瞰できる観測)によって
エネルギーの低い状態が「何か」が決定できる。
その「何か」を目指して形態が再編成される。無数に連なった一群が、ダイナミックに変動する。
これが進化=世界の運動だと考えるのだ。
量子コンピューターの登場によって、難攻不落の「進化」をついに語ることができるようになった、ということ確信する!
【量子経済人類学に向けて】その3
★「ぱっと見て分かる」が鍵
ぜひ番組を見て頂きたい。私の駄文よりも明白に分かる。量子コンピューターの問題解法が、従来の方法と根本的に「違う」ということを!
9月28日放送のEテレ・サイエンスZERO『ついに出た!?夢の“量子コンピューター”』
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
次回は、停滞する暗黙知論者の典型的な人工知能批判を取り上げる。また、ペンローズの人工知能批判も紹介する。
要するにこういうことだ。コンピューターでは「ぱっと見て分かる」を創り出すことが出来ない。人間(生命)の知能の作用原理とコンピューターとは完全に異質なものである。だから、機械の原理だけでは、人間精神を決して語れないと結論付ける。(※)
***
量子コンピューターの実用化によって、「ぱっと見て分かる」が実現可能となった!
今回実用化されたのは、今までの量子コンピューターの主流であった「万能ゲート方式」とは《違う》ということ強調しておく。誰も注目しなかった「量子アニーリング方式」が採用されている。Googleが大金をはたいて研究しているので、「量子アニーリング方式」が世界を席巻する日は近いだろう。
「万能ゲート方式」は石の上に石を積み重ねるような不安定なものなのだ。「万能ゲート方式」は、従来のコンピューターのビット(0か1)を量子ビットに置き換えただけであり、原理的にはさほど革新性を感じない。
番組を見ると気づくだろう。「量子アニーリング方式」は、コンピューターの“プログラム性”を全く感じないのだ。いわゆる“プログラム”とは異質なもので計算されている。
四色問題や巡回サラリーマン問題の解法は、状態を重ね合わせて、一番コストが低いところを一瞬ではじき出す。エネルギー(コスト)が高いところから低いところへ目指すという方式は、自然界の「理」そのものなので実に【安定】しているのだ。
☆こう言いたい!
知性・思考というものは実はかなり【安定】していると考える。だから普遍的に存在する。
そして知性・思考を実現する原理は極めてシンプルなものなのだ。
(量子アニーリング方式の問題解決法は、実にシンプルなものである)
=================
アニーリングとは(金属の)焼なましのことである。金属は、原子が綺麗に整列している状態が一番エネルギーが低い。実際には整列が乱れて、内部にひずみが生じてエネルギーが高い状態になっている。それに熱を加えることで、原子の整列を綺麗に揃えエネルギーを低くして、安定した金属を作り出すのだ。
この場合、金属は外部から熱を「借り」受けたのだ。
全ての存在は、少しでもエネルギーを低くしようと外部(=隣接する他者)から借金していると考える。「借金」がないと内部にひずみが生じて存在することができない。
「借金」によって、外部(=隣接する他者)に対して贈与返礼義務が生じる。そして贈与の連鎖によって、この世が成り立っていると考える。まさに自転車操業だ。
量子は我々生命と遠い存在ではなく、全く同じ原理(=借金と自転車操業)によって運動している。
経済人類学の最重要概念にトランザクション(交換)があるが、交換とはエネルギーを最小にしようとする自然界の大原則から導かれるものだと思うのだ。
_______________
註釈(※)
私は、現行のノイマン型コンピューターですら、人工知能と呼べるものを創り出せる可能性があると思っている。もちろん、人間の知能とは違うかたちにはなるだろう。
現在のコンピューターのソフトは、バリバリの古典理論によって構成されている。我々の知性とはほど遠いものに思えるだろう。しかし、コンピューターのハードは意外や意外!実は「非論理的なもの」で構成されているのだ。これはコンピューターを組んで生活している人の話だから信用できる。
人間の古典的な理論を、具体的なモノで実現しようと思うと「非論理的なもの」にならざるを得ないのだろう。理論(概念)と現実的具体物とは、必ずズレが生じる。そのズレを埋め合わせる調停作業が、コンピューターという存在の中に非明示的に隠れている。そのズレ及びズレの調停によって、人工知能と呼べるものを創り出せる可能性があると考えるのだ。
★「ぱっと見て分かる」が鍵
ぜひ番組を見て頂きたい。私の駄文よりも明白に分かる。量子コンピューターの問題解法が、従来の方法と根本的に「違う」ということを!
9月28日放送のEテレ・サイエンスZERO『ついに出た!?夢の“量子コンピューター”』
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2014055542SA000/
次回は、停滞する暗黙知論者の典型的な人工知能批判を取り上げる。また、ペンローズの人工知能批判も紹介する。
要するにこういうことだ。コンピューターでは「ぱっと見て分かる」を創り出すことが出来ない。人間(生命)の知能の作用原理とコンピューターとは完全に異質なものである。だから、機械の原理だけでは、人間精神を決して語れないと結論付ける。(※)
***
量子コンピューターの実用化によって、「ぱっと見て分かる」が実現可能となった!
今回実用化されたのは、今までの量子コンピューターの主流であった「万能ゲート方式」とは《違う》ということ強調しておく。誰も注目しなかった「量子アニーリング方式」が採用されている。Googleが大金をはたいて研究しているので、「量子アニーリング方式」が世界を席巻する日は近いだろう。
「万能ゲート方式」は石の上に石を積み重ねるような不安定なものなのだ。「万能ゲート方式」は、従来のコンピューターのビット(0か1)を量子ビットに置き換えただけであり、原理的にはさほど革新性を感じない。
番組を見ると気づくだろう。「量子アニーリング方式」は、コンピューターの“プログラム性”を全く感じないのだ。いわゆる“プログラム”とは異質なもので計算されている。
四色問題や巡回サラリーマン問題の解法は、状態を重ね合わせて、一番コストが低いところを一瞬ではじき出す。エネルギー(コスト)が高いところから低いところへ目指すという方式は、自然界の「理」そのものなので実に【安定】しているのだ。
☆こう言いたい!
知性・思考というものは実はかなり【安定】していると考える。だから普遍的に存在する。
そして知性・思考を実現する原理は極めてシンプルなものなのだ。
(量子アニーリング方式の問題解決法は、実にシンプルなものである)
=================
アニーリングとは(金属の)焼なましのことである。金属は、原子が綺麗に整列している状態が一番エネルギーが低い。実際には整列が乱れて、内部にひずみが生じてエネルギーが高い状態になっている。それに熱を加えることで、原子の整列を綺麗に揃えエネルギーを低くして、安定した金属を作り出すのだ。
この場合、金属は外部から熱を「借り」受けたのだ。
全ての存在は、少しでもエネルギーを低くしようと外部(=隣接する他者)から借金していると考える。「借金」がないと内部にひずみが生じて存在することができない。
「借金」によって、外部(=隣接する他者)に対して贈与返礼義務が生じる。そして贈与の連鎖によって、この世が成り立っていると考える。まさに自転車操業だ。
量子は我々生命と遠い存在ではなく、全く同じ原理(=借金と自転車操業)によって運動している。
経済人類学の最重要概念にトランザクション(交換)があるが、交換とはエネルギーを最小にしようとする自然界の大原則から導かれるものだと思うのだ。
_______________
註釈(※)
私は、現行のノイマン型コンピューターですら、人工知能と呼べるものを創り出せる可能性があると思っている。もちろん、人間の知能とは違うかたちにはなるだろう。
現在のコンピューターのソフトは、バリバリの古典理論によって構成されている。我々の知性とはほど遠いものに思えるだろう。しかし、コンピューターのハードは意外や意外!実は「非論理的なもの」で構成されているのだ。これはコンピューターを組んで生活している人の話だから信用できる。
人間の古典的な理論を、具体的なモノで実現しようと思うと「非論理的なもの」にならざるを得ないのだろう。理論(概念)と現実的具体物とは、必ずズレが生じる。そのズレを埋め合わせる調停作業が、コンピューターという存在の中に非明示的に隠れている。そのズレ及びズレの調停によって、人工知能と呼べるものを創り出せる可能性があると考えるのだ。
【緊急】
ひっそりと栗本慎一郎コミュに帰ってます。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=43561&id=74955907&comment_count=20
「進化を語ろう!2周目」に書いても良かった内容です。ぜひご覧下さい。(読まないと流れが分かりません)
「ここ」に帰ってこようと思ったことは3回ありました。
 物理の標準理論の正しさが証明されました。CERNによってヒッグス機構が証明されましたのです。重力を除く3つの「力」の統一理論の完成です。科学者はその証明を慎重にやりました。これが覆ることはないでしょう。CERNによってボロが出ると言ってた暗黙知信者は節穴です。
物理の標準理論の正しさが証明されました。CERNによってヒッグス機構が証明されましたのです。重力を除く3つの「力」の統一理論の完成です。科学者はその証明を慎重にやりました。これが覆ることはないでしょう。CERNによってボロが出ると言ってた暗黙知信者は節穴です。
 小保方晴子のSTAP細胞「発見」。科学は、「正しい」と思う信念だけではダメだということです。ただ、「STAP細胞はある」という信念告白だけなら価値があったでしょう。進化トピでは賭けに似た“信念告白”を続けようと思います。
小保方晴子のSTAP細胞「発見」。科学は、「正しい」と思う信念だけではダメだということです。ただ、「STAP細胞はある」という信念告白だけなら価値があったでしょう。進化トピでは賭けに似た“信念告白”を続けようと思います。
そして、
 CyberRebeat -The Fifth Domain of Warfare-
CyberRebeat -The Fifth Domain of Warfare-
副題は、サイバー空間が陸海空そして宇宙に次ぐ5番目の戦争領域だということ。
CyberRebeatは、サイバー戦争で、何度も何度も敵を出し抜き合う状況でしょう。
http://www.ennach.sakura.ne.jp/CyberRebeat/
無料の電子小説です。ぜひ読んで下さい!
最先端のハッキングはここまで進んでいるのか!と感銘を受けました。
面白くてぜひ紹介したかったのです。
生命論にも関係あります!
ハッキングやウイルスが存在できるのは、いかなるシステムも必ずバグ(想定外)を孕むからです。世界は想定された設計原理そのままで運行されている訳ではありません。必ず「もの」によって具現されます。セイキュリティーの穴は、「想定」と「もの」のズレによって必ず生じます。そのズレをついたものがハッキングやウイルスです。
ウイルスは、「層の原理」のどこにも存在しません。下の階層は上の階層の素材(細目)であり、上の階層は下の階層を象る意味(全体)であり、上下の細目と意味の関係が、無限に入れ替わり連鎖する体系を「層の原理」と言います(私は反抗します)。が、ウイルスは「想定外」なので「層の原理」のどこにも位置づけられません。
経済人類学に「病」という概念はありますが、それは受動的なものに感じます。ハッキングは「やろう」と思わないとできないものです。ウイルスは「病」を引き起こす外部じゃなく、システムの内部にある積極的に変革をもたらす装置だと考えます。
ウイルスを「もの」の可能性を拡張する「想定外」発生装置と考える生命論は後日にやります。
今日は、サイバー戦争の現状が緊急レベルで脅威だということを分かって下さい。
↓ ↓ ↓
ひっそりと栗本慎一郎コミュに帰ってます。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=43561&id=74955907&comment_count=20
「進化を語ろう!2周目」に書いても良かった内容です。ぜひご覧下さい。(読まないと流れが分かりません)
「ここ」に帰ってこようと思ったことは3回ありました。
そして、
副題は、サイバー空間が陸海空そして宇宙に次ぐ5番目の戦争領域だということ。
CyberRebeatは、サイバー戦争で、何度も何度も敵を出し抜き合う状況でしょう。
http://www.ennach.sakura.ne.jp/CyberRebeat/
無料の電子小説です。ぜひ読んで下さい!
最先端のハッキングはここまで進んでいるのか!と感銘を受けました。
面白くてぜひ紹介したかったのです。
生命論にも関係あります!
ハッキングやウイルスが存在できるのは、いかなるシステムも必ずバグ(想定外)を孕むからです。世界は想定された設計原理そのままで運行されている訳ではありません。必ず「もの」によって具現されます。セイキュリティーの穴は、「想定」と「もの」のズレによって必ず生じます。そのズレをついたものがハッキングやウイルスです。
ウイルスは、「層の原理」のどこにも存在しません。下の階層は上の階層の素材(細目)であり、上の階層は下の階層を象る意味(全体)であり、上下の細目と意味の関係が、無限に入れ替わり連鎖する体系を「層の原理」と言います(私は反抗します)。が、ウイルスは「想定外」なので「層の原理」のどこにも位置づけられません。
経済人類学に「病」という概念はありますが、それは受動的なものに感じます。ハッキングは「やろう」と思わないとできないものです。ウイルスは「病」を引き起こす外部じゃなく、システムの内部にある積極的に変革をもたらす装置だと考えます。
ウイルスを「もの」の可能性を拡張する「想定外」発生装置と考える生命論は後日にやります。
今日は、サイバー戦争の現状が緊急レベルで脅威だということを分かって下さい。
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
次にこの動画を見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=8E1LmGZXxFI
苫米地英人最新刊『日本人だけが知らない戦争論』とは?
日本が戦争になるとき、3つの攻撃が同時に行われます。サイバー攻撃によるインフラ停止、特殊部隊の工作、無人機による空爆。
電気が止まれば証券取引、銀行、ATMが使えなくなり経済が死にます。日本の個人情報管理は杜撰で、年金情報漏洩の例のように「した」方も「された」方も何とも思ってないでしょう。「またか」と思う程度のレベル。外国から見たらザルで情報を抜き放題、工作し放題。既にあらゆる分野で細工は完了しているでしょう。細工は巧妙で、OSを再インストールすれば良いというレベルではないでしょう。HDDの書き換えできない領域にウイルスは潜んでいるでしょう。
(SSDは使っているうちに速度が遅くなります。Trimという機能でそれを防止します。Macの場合、純正SSD搭載ならば自動的にTrimがOnになります。他社製の場合は自動的なサポートはありません。「Mac製」という情報はSSDの見えない領域に書き込まれているのです。そういう仕様は一般に知られてません。MacのTrimは自動的に発動する善意の機能ですが、書き換えの出来ない記憶媒体に悪意のある機能を潜ませることは、やろうと思えば簡単だということです)
3つの同時攻撃で日本は壊滅です。兵隊が入る段階は「占領」を意味します。他国によるサイバー攻撃の準備は既に完了しているでしょう。日本はいつ滅んでもおかしくない状況にあるでしょう。
そういう状況下では、通常の兵器の意味が著しく減退します。自衛隊そのものの価値が薄いのです。日本はサイバー防疫、またはサイバー攻撃部隊を持つべきでしょう。
◆今日の要点
サイバー攻撃の脅威を知って下さい。
苫米地英人の本を読むか動画を見て下さい。
CyberRebeat という(読むだけ)のゲームをやって下さい。
最後は、読者に物語全体を俯瞰させ、この作品自体を自己言及させます。押井守が好むメタ手法です。とにかく面白いです。
無料なので、取りあえずダウンロードして一日少しずつでもやって欲しいです。
専門用語が乱発されますが無視して先に進めた方がストレスがありません。
次回は危機的状況下にある日本はどうしたら良いかということを語ります。
(生命論より先にサイバー攻撃の現状をお伝えするのは、日本がまさに危機だからです。自分自身がなんと平和ボケしていたものだと反省するからです)
次にこの動画を見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=8E1LmGZXxFI
苫米地英人最新刊『日本人だけが知らない戦争論』とは?
日本が戦争になるとき、3つの攻撃が同時に行われます。サイバー攻撃によるインフラ停止、特殊部隊の工作、無人機による空爆。
電気が止まれば証券取引、銀行、ATMが使えなくなり経済が死にます。日本の個人情報管理は杜撰で、年金情報漏洩の例のように「した」方も「された」方も何とも思ってないでしょう。「またか」と思う程度のレベル。外国から見たらザルで情報を抜き放題、工作し放題。既にあらゆる分野で細工は完了しているでしょう。細工は巧妙で、OSを再インストールすれば良いというレベルではないでしょう。HDDの書き換えできない領域にウイルスは潜んでいるでしょう。
(SSDは使っているうちに速度が遅くなります。Trimという機能でそれを防止します。Macの場合、純正SSD搭載ならば自動的にTrimがOnになります。他社製の場合は自動的なサポートはありません。「Mac製」という情報はSSDの見えない領域に書き込まれているのです。そういう仕様は一般に知られてません。MacのTrimは自動的に発動する善意の機能ですが、書き換えの出来ない記憶媒体に悪意のある機能を潜ませることは、やろうと思えば簡単だということです)
3つの同時攻撃で日本は壊滅です。兵隊が入る段階は「占領」を意味します。他国によるサイバー攻撃の準備は既に完了しているでしょう。日本はいつ滅んでもおかしくない状況にあるでしょう。
そういう状況下では、通常の兵器の意味が著しく減退します。自衛隊そのものの価値が薄いのです。日本はサイバー防疫、またはサイバー攻撃部隊を持つべきでしょう。
◆今日の要点
サイバー攻撃の脅威を知って下さい。
苫米地英人の本を読むか動画を見て下さい。
CyberRebeat という(読むだけ)のゲームをやって下さい。
最後は、読者に物語全体を俯瞰させ、この作品自体を自己言及させます。押井守が好むメタ手法です。とにかく面白いです。
無料なので、取りあえずダウンロードして一日少しずつでもやって欲しいです。
専門用語が乱発されますが無視して先に進めた方がストレスがありません。
次回は危機的状況下にある日本はどうしたら良いかということを語ります。
(生命論より先にサイバー攻撃の現状をお伝えするのは、日本がまさに危機だからです。自分自身がなんと平和ボケしていたものだと反省するからです)
前回からの続き
ひっそりと栗本慎一郎コミュに復帰しています。
「栗本氏の問題意識・テーマを継ぐ著者」トピ#18#19#20をご覧下さい。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=43561&id=74955907&comment_count=20
《『日本人だけが知らない戦争論』読者限定無料プレゼント!》は、
『パンツを脱いだサル』巻末のテーマである貨幣の猛毒・国際金融資本とどう戦って行くかの答えになっています。
「読者限定無料プレゼント」はフォレスト出版のURLをいじると見ることができますが、公開するとルール違反だと思うので自分で買って下さい。要約だけ書きます。
◆抑止力としてのサイバー武装
日本の伝統的な平和の具現方法は「抑止力」だと言います。
武家社会における「守り」は互いにスカスカです。西洋のような堅固な城があった訳ではありません。殿様の首を取ろうと思えばいつでもできた訳です。自分からは攻め込まないけど、「やったら絶対やり返すよ」という論理が抑止力となって平和を築いてきました。核の抑止力と同じ論理です。
日本もサイバー武装せよ、というのが苫米地の結論です。いざとなったら、敵国の首都機能を停止させます。それくらいのサイバー攻撃ができる特殊部隊を日本は持つべきだと言うのです。【サイバー抑止力】による平和の実現です。
(自衛隊の)通常兵器の価値は下がっていると前回述べました。日本が生き残るにはサイバー武装しかありません。
所詮はオマケ動画なので問題点はあります。
もう既に日本の要所に、他国による工作が施されている状況でしょう。いざとなったら首都機能を麻痺させる「練習」を、実際に他国からやられていると感じます。今から日本がサイバー武装した所で他国にかなり遅れを取ってます。
ハッキング技術は日々進歩しています。サイバー武装をするにしても、その技術を常に最新にする必要があります。つまり実際の仮想敵国相手に「練習」をする必要があります。他国が脅威に思ってくれないと「抑止力」になりません。敵国の地方のインフラを部分的に停止させるくらいの実戦演習がなければ、いざとなったときに敵国の首都機能を止められません。(日本は、この「練習」をまさに他国からされているでしょう!)
日本にこんな度胸はないでしょうし、かなり狡猾で日本人の美意識に反します。
☆日本のサイバー武装は非現実的なものでしょうか?
(国会でサイバー攻撃に対する強固な防衛をすべきだという発言がありました。ただ「防衛」では「抑止力」になりません。)
その答えはお薦めしたゲームの中にあります。
『CyberRebeat』(同人ゲーム・ゲームと言ってもただ読むだけ)
http://www.ennach.sakura.ne.jp/CyberRebeat/
◆ハッカーを殺すハニーポット
ハッキングを受けることを前提に、わざと怪しい場所を容易します。そこを踏ませることで、ハッカーに対して逆にウイルス感染させることも可能です。
相手が「ウイルス感染」したとすぐに分かってしまっては効果がないですが、相手に「ウイルス感染」の自覚がなければ絶大な効果があります。
ゲーム中のシナリオはこうです。ハニーポットを踏むと、モニターに水滴が落ちる映像が現れます。一見なんでもないような映像なのでハッカーは気にも留めませんが、実は高度な催眠効果のある映像だったのです。ハッカーを知らず知らずのうちに催眠状態にして、その後ハードディスク・PC本体を異常発熱させハッカーを焼死させます。
(発熱するPCの種明かしはこうでしょう。通常使用なら問題が出ず、ある使い方をしたときだけ「欠陥」が現れます。「意図者」によってその欠陥は操作できます。そういうPCが密かに流通していたという隠れ設定でしょう。作品では種明かしはありません)
ハッカーを殺す!
このアイデアは優秀です。サイバー攻撃された相手にだけ仇をなすというのであれば報復の原理(=抑止力)に叶います。
↓ ↓ ↓
ひっそりと栗本慎一郎コミュに復帰しています。
「栗本氏の問題意識・テーマを継ぐ著者」トピ#18#19#20をご覧下さい。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=43561&id=74955907&comment_count=20
《『日本人だけが知らない戦争論』読者限定無料プレゼント!》は、
『パンツを脱いだサル』巻末のテーマである貨幣の猛毒・国際金融資本とどう戦って行くかの答えになっています。
「読者限定無料プレゼント」はフォレスト出版のURLをいじると見ることができますが、公開するとルール違反だと思うので自分で買って下さい。要約だけ書きます。
◆抑止力としてのサイバー武装
日本の伝統的な平和の具現方法は「抑止力」だと言います。
武家社会における「守り」は互いにスカスカです。西洋のような堅固な城があった訳ではありません。殿様の首を取ろうと思えばいつでもできた訳です。自分からは攻め込まないけど、「やったら絶対やり返すよ」という論理が抑止力となって平和を築いてきました。核の抑止力と同じ論理です。
日本もサイバー武装せよ、というのが苫米地の結論です。いざとなったら、敵国の首都機能を停止させます。それくらいのサイバー攻撃ができる特殊部隊を日本は持つべきだと言うのです。【サイバー抑止力】による平和の実現です。
(自衛隊の)通常兵器の価値は下がっていると前回述べました。日本が生き残るにはサイバー武装しかありません。
所詮はオマケ動画なので問題点はあります。
もう既に日本の要所に、他国による工作が施されている状況でしょう。いざとなったら首都機能を麻痺させる「練習」を、実際に他国からやられていると感じます。今から日本がサイバー武装した所で他国にかなり遅れを取ってます。
ハッキング技術は日々進歩しています。サイバー武装をするにしても、その技術を常に最新にする必要があります。つまり実際の仮想敵国相手に「練習」をする必要があります。他国が脅威に思ってくれないと「抑止力」になりません。敵国の地方のインフラを部分的に停止させるくらいの実戦演習がなければ、いざとなったときに敵国の首都機能を止められません。(日本は、この「練習」をまさに他国からされているでしょう!)
日本にこんな度胸はないでしょうし、かなり狡猾で日本人の美意識に反します。
☆日本のサイバー武装は非現実的なものでしょうか?
(国会でサイバー攻撃に対する強固な防衛をすべきだという発言がありました。ただ「防衛」では「抑止力」になりません。)
その答えはお薦めしたゲームの中にあります。
『CyberRebeat』(同人ゲーム・ゲームと言ってもただ読むだけ)
http://www.ennach.sakura.ne.jp/CyberRebeat/
◆ハッカーを殺すハニーポット
ハッキングを受けることを前提に、わざと怪しい場所を容易します。そこを踏ませることで、ハッカーに対して逆にウイルス感染させることも可能です。
相手が「ウイルス感染」したとすぐに分かってしまっては効果がないですが、相手に「ウイルス感染」の自覚がなければ絶大な効果があります。
ゲーム中のシナリオはこうです。ハニーポットを踏むと、モニターに水滴が落ちる映像が現れます。一見なんでもないような映像なのでハッカーは気にも留めませんが、実は高度な催眠効果のある映像だったのです。ハッカーを知らず知らずのうちに催眠状態にして、その後ハードディスク・PC本体を異常発熱させハッカーを焼死させます。
(発熱するPCの種明かしはこうでしょう。通常使用なら問題が出ず、ある使い方をしたときだけ「欠陥」が現れます。「意図者」によってその欠陥は操作できます。そういうPCが密かに流通していたという隠れ設定でしょう。作品では種明かしはありません)
ハッカーを殺す!
このアイデアは優秀です。サイバー攻撃された相手にだけ仇をなすというのであれば報復の原理(=抑止力)に叶います。
↓ ↓ ↓
=================
まとめ
ハッキングがなぜ可能なのか?
システムには、設計者が思いも寄らなかった「想定外」が必ず具現化します。システムの穴=「想定外」を突く行為がハッキングです。
『日本人だけが知らない戦争論』では、世界中のPCが細工済みだと書かれています。そういう状況下で、日本がサイバー武装した所で意味があるでしょうか?あります!
「世界中のPCをいざとなったら操作できる」という意図全体もシステムと見ることができます。つまりそこには、よくよく調べると意図者が思いも寄らなかった「想定外」が潜んでいると考えます。
日本人は優秀です。サイバー攻撃側の欠陥(想定外)を見つけましょう。
日本は既に「サイバー攻撃を受けている」という状況を利用しましょう。
巧妙なハニーポットを作って、攻撃者を罠に嵌めましょう。すぐにバレるようなものではダメです。日本人にしか作れない高度なウイルス、サイバー攻撃した相手にだけ感染するウイルスを開発しましょう。ウイルスはすぐに「症状」を現さず、じっと敵の深部に潜伏するものが良いです。
日本の情報が盗まれているなら、ハニーポッドに仕掛けたウイルスは逆のルートを辿って「意図者」の元まで運ばれて行きます。日本が仕掛けたウイルスはいずれバレるでしょうが、敵側が「何かされた」という意識を持つことこそが「このウイルスの狙い」です。こちらのウイルスが巧妙であればあるほど効果は絶大です。
敵側が仕掛けた「意図」に対してのウイルスなのですから、計画(想定)を一から見直さなければいけません。
「世界中のPCをいざとなったら操作できる」という意図さえ怪しくなります。逆に「何かされている」のではないか?と疑心暗鬼になってもらえれば成功です。
*******************
◆「何かされた?」
名作『カイジ』で、カイジと利根川との名勝負がありました。(利根川の「金は命より重い」は名言です)
カイジは土壇場の勝負で何か細工をしたようなフリをします。利根川は疑心暗鬼に落ち、カイジが「何かした」という前提で行動し、結果敗北してしまいます。実際にはカイジは何もしていません。
◆敵側が「何かされた」と思ってくれることが「抑止力」になるということです。
日本がハニーポッドに仕掛けるウイルスは、特に何もしなくてもいいのです。潜伏するだけでいい。敵側が怪しいと思ってくれるだけで効果があるのです。
=================
『CyberRebeat』の“Rebeat” に生命進化の歴史を感じます。
食って食われる「たたき合い」の歴史。
私が2大の謎だと言った「生命はなぜ他の生命を食うのか?」「性はなぜあるのか?」
は根源は同じなのでしょう。
性(遺伝子)の交換は、想定外を生む装置でしょう。
生命のエンジン・本質は「想定外」です!
ならばウイルスすらもシステムに組み込まれた「内部」だと思えるのです。(栗本先生が言うように「外部」じゃないです)
※次回予定
遺伝子のシステムにはSCADAのようなメタシステムがあるでしょう。
まとめ
ハッキングがなぜ可能なのか?
システムには、設計者が思いも寄らなかった「想定外」が必ず具現化します。システムの穴=「想定外」を突く行為がハッキングです。
『日本人だけが知らない戦争論』では、世界中のPCが細工済みだと書かれています。そういう状況下で、日本がサイバー武装した所で意味があるでしょうか?あります!
「世界中のPCをいざとなったら操作できる」という意図全体もシステムと見ることができます。つまりそこには、よくよく調べると意図者が思いも寄らなかった「想定外」が潜んでいると考えます。
日本人は優秀です。サイバー攻撃側の欠陥(想定外)を見つけましょう。
日本は既に「サイバー攻撃を受けている」という状況を利用しましょう。
巧妙なハニーポットを作って、攻撃者を罠に嵌めましょう。すぐにバレるようなものではダメです。日本人にしか作れない高度なウイルス、サイバー攻撃した相手にだけ感染するウイルスを開発しましょう。ウイルスはすぐに「症状」を現さず、じっと敵の深部に潜伏するものが良いです。
日本の情報が盗まれているなら、ハニーポッドに仕掛けたウイルスは逆のルートを辿って「意図者」の元まで運ばれて行きます。日本が仕掛けたウイルスはいずれバレるでしょうが、敵側が「何かされた」という意識を持つことこそが「このウイルスの狙い」です。こちらのウイルスが巧妙であればあるほど効果は絶大です。
敵側が仕掛けた「意図」に対してのウイルスなのですから、計画(想定)を一から見直さなければいけません。
「世界中のPCをいざとなったら操作できる」という意図さえ怪しくなります。逆に「何かされている」のではないか?と疑心暗鬼になってもらえれば成功です。
*******************
◆「何かされた?」
名作『カイジ』で、カイジと利根川との名勝負がありました。(利根川の「金は命より重い」は名言です)
カイジは土壇場の勝負で何か細工をしたようなフリをします。利根川は疑心暗鬼に落ち、カイジが「何かした」という前提で行動し、結果敗北してしまいます。実際にはカイジは何もしていません。
◆敵側が「何かされた」と思ってくれることが「抑止力」になるということです。
日本がハニーポッドに仕掛けるウイルスは、特に何もしなくてもいいのです。潜伏するだけでいい。敵側が怪しいと思ってくれるだけで効果があるのです。
=================
『CyberRebeat』の“Rebeat” に生命進化の歴史を感じます。
食って食われる「たたき合い」の歴史。
私が2大の謎だと言った「生命はなぜ他の生命を食うのか?」「性はなぜあるのか?」
は根源は同じなのでしょう。
性(遺伝子)の交換は、想定外を生む装置でしょう。
生命のエンジン・本質は「想定外」です!
ならばウイルスすらもシステムに組み込まれた「内部」だと思えるのです。(栗本先生が言うように「外部」じゃないです)
※次回予定
遺伝子のシステムにはSCADAのようなメタシステムがあるでしょう。
NHK・Eテレ11月13日23時〜23時55分放送の感想。
カリフォルニァ大学のフレンケル教授による「数学ミステリー白熱教室」(全4回)
http://www.nhk.or.jp/hakunetsu/math/
おおお!
「数学の大統一理論」の番組を見ました。
★数の数え方
まず、具体的な(例えばリンゴのような)事物を1個2個…と数える方法が思いつきます。
これは誰でも思いつく明示的な方法です。
それでは、ソラリスのように知的生命が「1個」しか存在しない場合、数という概念・延いては我々と同じ数学を持つことができるでしょうか?
講師は「巻きつけ」という手法を提示します。
ソラリスに生命は1個しかありませんが、自らを紐のようなもので「巻きつける」ことは想像できるでしょう。
円(球)を1周「巻きつける」ごとに、1・2・3…と数えることが可能です。
さらに、「巻きつけ」の数え方の優秀性は、マイナスの概念を容易に表せます。
時計回りの「巻きつけ」方をプラスとすると、反時計回りはマイナスとなります。
具体的な事物を数える手法では、マイナスの概念は決して導けません。さらに、1個と2個の中間はなく、整数しか数えることができません。
「巻きつけ」の数え方では、1(周)と2(周)の間は連続しているので、実数すべをカバーできます。
★発展(講師が直接話したことではありません)
「巻きつけ」の数え方の【過程】と【軌跡】を考えると、図形や波が現れます。
講師が最終的に行いたいのは、これまで互いに全く無関係だと思われてきた数学の様々な分野(数論、幾何学、調和解析など)を“統一”することです。
「巻きつき」は円と考えられます。円上の点は、数を数える【過程】です。円上の点を結ぶと図形になります。数から図形=幾何学へは容易に橋渡しできます。
√2のような無理数も、πのような超越数も、「数を数える」というシンプルな営為から導けます。
円を平面上に置きます。x軸を実数、y軸を虚数(i)とすると、複素数全体をカバーできます。
「巻きつき」は円運動です。【過程】=円上の点をずっとなぞって行くと、その【軌跡】は波になります。
波の合成を考える学問が「調和解析」なので、見事に「数を数えること」と「音楽(波の合成)の美しさ」がつながります!
「数を数えること」を考えるだけで、数学を統一する見通しが立ちます。わくわくしますね。
↓ ↓ ↓
カリフォルニァ大学のフレンケル教授による「数学ミステリー白熱教室」(全4回)
http://www.nhk.or.jp/hakunetsu/math/
おおお!
「数学の大統一理論」の番組を見ました。
★数の数え方
まず、具体的な(例えばリンゴのような)事物を1個2個…と数える方法が思いつきます。
これは誰でも思いつく明示的な方法です。
それでは、ソラリスのように知的生命が「1個」しか存在しない場合、数という概念・延いては我々と同じ数学を持つことができるでしょうか?
講師は「巻きつけ」という手法を提示します。
ソラリスに生命は1個しかありませんが、自らを紐のようなもので「巻きつける」ことは想像できるでしょう。
円(球)を1周「巻きつける」ごとに、1・2・3…と数えることが可能です。
さらに、「巻きつけ」の数え方の優秀性は、マイナスの概念を容易に表せます。
時計回りの「巻きつけ」方をプラスとすると、反時計回りはマイナスとなります。
具体的な事物を数える手法では、マイナスの概念は決して導けません。さらに、1個と2個の中間はなく、整数しか数えることができません。
「巻きつけ」の数え方では、1(周)と2(周)の間は連続しているので、実数すべをカバーできます。
★発展(講師が直接話したことではありません)
「巻きつけ」の数え方の【過程】と【軌跡】を考えると、図形や波が現れます。
講師が最終的に行いたいのは、これまで互いに全く無関係だと思われてきた数学の様々な分野(数論、幾何学、調和解析など)を“統一”することです。
「巻きつき」は円と考えられます。円上の点は、数を数える【過程】です。円上の点を結ぶと図形になります。数から図形=幾何学へは容易に橋渡しできます。
√2のような無理数も、πのような超越数も、「数を数える」というシンプルな営為から導けます。
円を平面上に置きます。x軸を実数、y軸を虚数(i)とすると、複素数全体をカバーできます。
「巻きつき」は円運動です。【過程】=円上の点をずっとなぞって行くと、その【軌跡】は波になります。
波の合成を考える学問が「調和解析」なので、見事に「数を数えること」と「音楽(波の合成)の美しさ」がつながります!
「数を数えること」を考えるだけで、数学を統一する見通しが立ちます。わくわくしますね。
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
★超発展(もう講師の言ったことから外れています)
【忘却=情報の消失】の保険としての「対象性の破れ」と「目印」
対象性は私の好きな概念で、物理の統一理論でも大活躍します。
講師は、底が丸いペットボトルと四角いペットボトルではどちらが対象性が高いかを受講者に問いました。
受講者はほとんど正解しました。答えは底が丸いペットボトルです。
しかし今私が語りたいのは、対象性の低い方です。【情報の消失】に強いからです。
まさに"実際に”、「巻きつき」によって数を数えている最中だとしましょう。
底が丸いペットボトルの場合を考えます。
何かの拍子にペットボトルが回転したとしましょう。円は対象性が高く目印がありません。なので、もうどこまで巻きつければ1周するのかという情報が【忘却】してしまいます。
何回巻きつけたかを覚えていても、その端数が分かりません。"過程”は0から2πのどこかにあるとしか言えません。そこで大量の誤差を生んでしまします。
今度は、底が四角いペットボトルの場合を考えます。
これには4つの点という目印があります。通過点さえ覚えておけば、思わぬペットボトルが回転しまう事故にも少ない誤差ですみます。
※それを踏まえて遺伝子のことを語りましょう。
「巻きつき」と聞いたときに、遺伝子の二重螺旋構造を思い浮かべました。
らせん構造は、何かの過程が具象化したものでしょう。何度も反復される運動がです。
しかし、何かの拍子にどの過程をやっていたか分からなくなることが頻繁に起こったと思うのです。
(それも進化の契機のひとつでしょう)
そういう時のために、遺伝子は目印をつけていると思うのです。実際に、DNAのメチル化というものが存在します。遺伝子に修飾をつけるのです。メチル化は細胞分裂を経ても保存されます。
***
我々が論理を構築するとき、いったんは紙に書かないと無理です。書いたものを手がかりにすることで、さらに深い論理を構築できるのです。「紙に書いたもの」が目印です。
生命の体系は、最初は「巻きつき」のような単純な営為しかなかったと思います。無限の反復。
その反復の中で、いくつか発明をしたと考えます。その発明を書いた目印が遺伝子でしょう。
遺伝子の目印を見て次の過程が分かる仕組みです。
その目印は数学的な美しさ=対象性を破るものです。対象性の高いものは事故に弱いからです。
だから生命進化が進むにつれ、形態がいびつになっていきます。
人類はやがて数学的大統一理論、、さらに物理をも統合した理論を手に入れるでしょう。
その次は生命論との統合です。生命は一見数学的美で構築されているように見えます。
一方で、今の数学では語れない醜さももっています。その醜さこそ、生命が発明した実践的な知恵だと考えます。
つまり、理系の統一理論=美だけでは生命は語れないでしょう。生命は、美+醜でもって語られることになるでしょう。かなり先の未来でしょうが。
数学は抽象学問なので「忘れる」という概念はありませんが、生命は具体的事物でできています。
「忘れる」ことも「壊れる」こともあるのです。忘れたり壊れたりしても生命は存在し続けます。
抽象(理系の学問)を統べた後は、具体的事物でしかあり得ない事象との統合が必要だということです。
万物の統一理論は、抽象(数学・物理)と具体物(生命)の融合によって創めて可能になるでしょう。
【結び】
「巻きつけ」という数え方は、思いつきにくく、言われてみればなるほどと思う『隠れている知恵』です。
これこそ非明示的知識と言えるでしょう。
非明示的知識を発見をして、学問の境界を取り払いましょう!
★超発展(もう講師の言ったことから外れています)
【忘却=情報の消失】の保険としての「対象性の破れ」と「目印」
対象性は私の好きな概念で、物理の統一理論でも大活躍します。
講師は、底が丸いペットボトルと四角いペットボトルではどちらが対象性が高いかを受講者に問いました。
受講者はほとんど正解しました。答えは底が丸いペットボトルです。
しかし今私が語りたいのは、対象性の低い方です。【情報の消失】に強いからです。
まさに"実際に”、「巻きつき」によって数を数えている最中だとしましょう。
底が丸いペットボトルの場合を考えます。
何かの拍子にペットボトルが回転したとしましょう。円は対象性が高く目印がありません。なので、もうどこまで巻きつければ1周するのかという情報が【忘却】してしまいます。
何回巻きつけたかを覚えていても、その端数が分かりません。"過程”は0から2πのどこかにあるとしか言えません。そこで大量の誤差を生んでしまします。
今度は、底が四角いペットボトルの場合を考えます。
これには4つの点という目印があります。通過点さえ覚えておけば、思わぬペットボトルが回転しまう事故にも少ない誤差ですみます。
※それを踏まえて遺伝子のことを語りましょう。
「巻きつき」と聞いたときに、遺伝子の二重螺旋構造を思い浮かべました。
らせん構造は、何かの過程が具象化したものでしょう。何度も反復される運動がです。
しかし、何かの拍子にどの過程をやっていたか分からなくなることが頻繁に起こったと思うのです。
(それも進化の契機のひとつでしょう)
そういう時のために、遺伝子は目印をつけていると思うのです。実際に、DNAのメチル化というものが存在します。遺伝子に修飾をつけるのです。メチル化は細胞分裂を経ても保存されます。
***
我々が論理を構築するとき、いったんは紙に書かないと無理です。書いたものを手がかりにすることで、さらに深い論理を構築できるのです。「紙に書いたもの」が目印です。
生命の体系は、最初は「巻きつき」のような単純な営為しかなかったと思います。無限の反復。
その反復の中で、いくつか発明をしたと考えます。その発明を書いた目印が遺伝子でしょう。
遺伝子の目印を見て次の過程が分かる仕組みです。
その目印は数学的な美しさ=対象性を破るものです。対象性の高いものは事故に弱いからです。
だから生命進化が進むにつれ、形態がいびつになっていきます。
人類はやがて数学的大統一理論、、さらに物理をも統合した理論を手に入れるでしょう。
その次は生命論との統合です。生命は一見数学的美で構築されているように見えます。
一方で、今の数学では語れない醜さももっています。その醜さこそ、生命が発明した実践的な知恵だと考えます。
つまり、理系の統一理論=美だけでは生命は語れないでしょう。生命は、美+醜でもって語られることになるでしょう。かなり先の未来でしょうが。
数学は抽象学問なので「忘れる」という概念はありませんが、生命は具体的事物でできています。
「忘れる」ことも「壊れる」こともあるのです。忘れたり壊れたりしても生命は存在し続けます。
抽象(理系の学問)を統べた後は、具体的事物でしかあり得ない事象との統合が必要だということです。
万物の統一理論は、抽象(数学・物理)と具体物(生命)の融合によって創めて可能になるでしょう。
【結び】
「巻きつけ」という数え方は、思いつきにくく、言われてみればなるほどと思う『隠れている知恵』です。
これこそ非明示的知識と言えるでしょう。
非明示的知識を発見をして、学問の境界を取り払いましょう!
◆新・暗黙知大統一理論
NHK・Eテレ11月20日23時〜23時55分放送
「数学ミステリー白熱教室」(第2回)を見ました。
↓ちなみに第1回目の動画
https://www.youtube.com/watch?v=ZB0CFXzQK2o&index=2&list=FLrD80BBE3TrGZZNOQ6w3jvA
東洋経済の記事(これを読むと<糸巻き法>が何か分かります)
http://toyokeizai.net/articles/-/92682?page=2
方程式の解と対称性の話はタメになりました。5次以上の方程式に、一般的な代数的解法は存在しないことは知ってましたが、そういうカラクリだと知りませんでした。
「タメ」にはなりましたが、自分の空想を羽ばたかせる力は圧倒的に第1回の方が上です。
==================================
第1回目の白眉
<糸巻き法>による数の数え方!
教授の本を買いましたが、<糸巻き>の話は一切ありません。放送2回目以降、<糸巻き法>は重要ではなくなるような気がしてました。実際そうでした。「対称性」にこそ焦点が移ります。
しかし、経済人類学が理数系と融合するには<糸巻き法>しかないと考えます。
前回の放送で、「数」は普遍的なものだと分かりました。
私は、「数」は個物と対応したものが発祥ではなく、<糸巻き>のような回転が始原だと考えます。
1回転するごとに、123…と数えます。
私は、円ではなく、【楕円】の<巻きつけ>こそ生命の基底単位だと主張します。
ずばりキーワードは【楕円】になります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%95%E5%86%86
上のウィキペディアの「作図」を参照していただくとイメージしやすいです。
【楕円】の1回の<巻きつけ>が、「1」という単位です。
宇宙のすべての生命体は惑星上で誕生したorするでしょう。惑星は円ではなく、楕円運動をしています。(ケプラーの法則)
きれいな円運動をしている惑星など無いと考えられますので、楕円運動は生命にとって普遍的な運動だと考えます。(銀河自体の形状も楕円です)
楕円は2つの焦点をもちます。
【2つの焦点(中心)】
生命は、2つの中心(焦点)を持つ<糸巻き運動>だと考えます。
生命は<糸巻き運動>で数えられた【暦】を共有しています。その独自の【暦】を、伝達・継承する営為が性です。性は端的に遺伝子の交換なのですが、なぜわざわざオスとメスが半分ずつ交換しあうのか、今の科学ではさっぱり分かりません。しかし、隠された数学的な根拠があって、将来きっと解明されると考えます。
1ではなく2つの焦点(中心)を持つことが生命進化のミソです。
ハレとケ。過剰と蕩尽。ヒトが2つの時間を使い分ける根拠は、<糸巻き運動>が正円ではなく、歪んだ楕円だからでしょう。(月(こちらは円運度)の影響もあって、実際はもっと複雑な【暦】を作ります)
栗本慎一郎先生が得意のブダペストの話。光の都市・闇の都市。(『都市は、発狂する。』など)
ひとつの体系に、2系統の異質な文化が恒常的に交わると経済活動が飛躍的に発展する、という論。
日本が近代になった理由も、農耕文化と山岳文化の恒常的な交わりがあったから。
(遺伝子も、ひとつの体系に、2系統の異質な恒常的な交換ですね)
こういった栗本説は、ことの始まりから生命が2つの焦点(中心)を持ってなければ説明できません。
だからこそ、楕円による<巻きつけ>を単位とする生命論を構築する必要があります。
その後、理系の統一理論(=対称性)と融合することが可能になるでしょう。
NHK・Eテレ11月20日23時〜23時55分放送
「数学ミステリー白熱教室」(第2回)を見ました。
↓ちなみに第1回目の動画
https://www.youtube.com/watch?v=ZB0CFXzQK2o&index=2&list=FLrD80BBE3TrGZZNOQ6w3jvA
東洋経済の記事(これを読むと<糸巻き法>が何か分かります)
http://toyokeizai.net/articles/-/92682?page=2
方程式の解と対称性の話はタメになりました。5次以上の方程式に、一般的な代数的解法は存在しないことは知ってましたが、そういうカラクリだと知りませんでした。
「タメ」にはなりましたが、自分の空想を羽ばたかせる力は圧倒的に第1回の方が上です。
==================================
第1回目の白眉
<糸巻き法>による数の数え方!
教授の本を買いましたが、<糸巻き>の話は一切ありません。放送2回目以降、<糸巻き法>は重要ではなくなるような気がしてました。実際そうでした。「対称性」にこそ焦点が移ります。
しかし、経済人類学が理数系と融合するには<糸巻き法>しかないと考えます。
前回の放送で、「数」は普遍的なものだと分かりました。
私は、「数」は個物と対応したものが発祥ではなく、<糸巻き>のような回転が始原だと考えます。
1回転するごとに、123…と数えます。
私は、円ではなく、【楕円】の<巻きつけ>こそ生命の基底単位だと主張します。
ずばりキーワードは【楕円】になります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%95%E5%86%86
上のウィキペディアの「作図」を参照していただくとイメージしやすいです。
【楕円】の1回の<巻きつけ>が、「1」という単位です。
宇宙のすべての生命体は惑星上で誕生したorするでしょう。惑星は円ではなく、楕円運動をしています。(ケプラーの法則)
きれいな円運動をしている惑星など無いと考えられますので、楕円運動は生命にとって普遍的な運動だと考えます。(銀河自体の形状も楕円です)
楕円は2つの焦点をもちます。
【2つの焦点(中心)】
生命は、2つの中心(焦点)を持つ<糸巻き運動>だと考えます。
生命は<糸巻き運動>で数えられた【暦】を共有しています。その独自の【暦】を、伝達・継承する営為が性です。性は端的に遺伝子の交換なのですが、なぜわざわざオスとメスが半分ずつ交換しあうのか、今の科学ではさっぱり分かりません。しかし、隠された数学的な根拠があって、将来きっと解明されると考えます。
1ではなく2つの焦点(中心)を持つことが生命進化のミソです。
ハレとケ。過剰と蕩尽。ヒトが2つの時間を使い分ける根拠は、<糸巻き運動>が正円ではなく、歪んだ楕円だからでしょう。(月(こちらは円運度)の影響もあって、実際はもっと複雑な【暦】を作ります)
栗本慎一郎先生が得意のブダペストの話。光の都市・闇の都市。(『都市は、発狂する。』など)
ひとつの体系に、2系統の異質な文化が恒常的に交わると経済活動が飛躍的に発展する、という論。
日本が近代になった理由も、農耕文化と山岳文化の恒常的な交わりがあったから。
(遺伝子も、ひとつの体系に、2系統の異質な恒常的な交換ですね)
こういった栗本説は、ことの始まりから生命が2つの焦点(中心)を持ってなければ説明できません。
だからこそ、楕円による<巻きつけ>を単位とする生命論を構築する必要があります。
その後、理系の統一理論(=対称性)と融合することが可能になるでしょう。
《365.2422を法とするカレンダー》
NHK・Eテレ11月27日23時〜23時55分放送「数学ミステリー白熱教室」(第3回目)の感想文
ん?いっきに難しくなりましたね(笑)。
大学時代を思い出しました。良い教授の講義はあんな感じです。無駄話が多く、内容はもっと圧縮できます。しかし「教える」のが本意ではなく、学生自らが勉強するように誘導することにこそ本意があります。
大事なことは、「教わる」のではなく「自ら学ぶ」のです。名教授は一から十まで教えません。「いかに興味を持たせるか」に力を注ぎます。
学生に、ただ単位が欲しいのか、本気で勉強したいのかを問う訳です。
講義の内容は大雑把でしたが、本気で勉強したいと思いました。そういう意味で名講義でしょう。
フェルマーの定理の解説は、一般的なものじゃないので新鮮でした。
一般的な解説では「谷山・志村・ヴェイユ予想」は迂回されがちですが、教授はガチでその秘めた美しさを伝えようとしました。
時計のように1周する算術が鍵のようです。アナログの時計は12を法とする算術です。
1時から35時間経過すると12時を示します。
角度は360を法とする算術です。450度の回転は90度の回転に等しいのです。
(見なかった人へ)
(数日後に、Youtubeで「数学ミステリー白熱教室」と検索するとアップされていると思います)
==================================
数=<巻き>=回転・循環
教授が1回目の講義で話した<糸巻き法>は、この世の「答え」でしょう。
(教授にとっては、単にその時だけのお話だったかもしれませんが)
講義内容は、「対称性」という尺度で、数学…そして物理までを統一して語れるというお話です。
そもそも、数の起源が「1回転」にあるならば、その軌跡は極めて対称性の高い「円」になります。
数論と他の分野に共通点が見つかるのは、むしろ当然でしょう。
我々生命は、暦に忠実に生きています。
もうすぐ1月1日です。(なにがめでたいのか意味不明でも)すべての人が「おめでとう」と言います。
セミは忠実に周期を繰り返して、生まれ鳴いて死んでいきます。セミじゃなくてもすべての生命がそうですね。
「生命は、Nを法とする算術である」と言えるでしょう。
Nは複数あります。太陽、自転、月…さまざまな周期を持っています。
公転の周期が、約365.2422日という「汚い数字」なのも進化の原動力と考えます。
複数のNは、微妙にズレます。ところどころで微調整(時計合せ)をしなければなりません。その力が進化の源でしょう。
何回巡り巡っても、1月1日は1月1日と呼ばれます。誰も疑問に思わないでしょうが、並々ならぬ力が陰で働いているのです。
我々は、時計(=1周すると同じものと看做す体系)です。
【1周すると同じ】…これがキーワードです。
modulo=法
35 mod 12 = 11 こんな【余り】を求める計算も意味があります。
アンサイクロペディアでは皮肉られていますが…
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AD
【余り】の重要性は、結城 浩『数学ガール フェルマーの最終定理』を読むとよく分かります。
【余り】は、実世界で「暗号」として大活躍しています。
http://www.maitou.gr.jp/rsa/rsa09.php
NHK・Eテレ11月27日23時〜23時55分放送「数学ミステリー白熱教室」(第3回目)の感想文
ん?いっきに難しくなりましたね(笑)。
大学時代を思い出しました。良い教授の講義はあんな感じです。無駄話が多く、内容はもっと圧縮できます。しかし「教える」のが本意ではなく、学生自らが勉強するように誘導することにこそ本意があります。
大事なことは、「教わる」のではなく「自ら学ぶ」のです。名教授は一から十まで教えません。「いかに興味を持たせるか」に力を注ぎます。
学生に、ただ単位が欲しいのか、本気で勉強したいのかを問う訳です。
講義の内容は大雑把でしたが、本気で勉強したいと思いました。そういう意味で名講義でしょう。
フェルマーの定理の解説は、一般的なものじゃないので新鮮でした。
一般的な解説では「谷山・志村・ヴェイユ予想」は迂回されがちですが、教授はガチでその秘めた美しさを伝えようとしました。
時計のように1周する算術が鍵のようです。アナログの時計は12を法とする算術です。
1時から35時間経過すると12時を示します。
角度は360を法とする算術です。450度の回転は90度の回転に等しいのです。
(見なかった人へ)
(数日後に、Youtubeで「数学ミステリー白熱教室」と検索するとアップされていると思います)
==================================
数=<巻き>=回転・循環
教授が1回目の講義で話した<糸巻き法>は、この世の「答え」でしょう。
(教授にとっては、単にその時だけのお話だったかもしれませんが)
講義内容は、「対称性」という尺度で、数学…そして物理までを統一して語れるというお話です。
そもそも、数の起源が「1回転」にあるならば、その軌跡は極めて対称性の高い「円」になります。
数論と他の分野に共通点が見つかるのは、むしろ当然でしょう。
我々生命は、暦に忠実に生きています。
もうすぐ1月1日です。(なにがめでたいのか意味不明でも)すべての人が「おめでとう」と言います。
セミは忠実に周期を繰り返して、生まれ鳴いて死んでいきます。セミじゃなくてもすべての生命がそうですね。
「生命は、Nを法とする算術である」と言えるでしょう。
Nは複数あります。太陽、自転、月…さまざまな周期を持っています。
公転の周期が、約365.2422日という「汚い数字」なのも進化の原動力と考えます。
複数のNは、微妙にズレます。ところどころで微調整(時計合せ)をしなければなりません。その力が進化の源でしょう。
何回巡り巡っても、1月1日は1月1日と呼ばれます。誰も疑問に思わないでしょうが、並々ならぬ力が陰で働いているのです。
我々は、時計(=1周すると同じものと看做す体系)です。
【1周すると同じ】…これがキーワードです。
modulo=法
35 mod 12 = 11 こんな【余り】を求める計算も意味があります。
アンサイクロペディアでは皮肉られていますが…
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AD
【余り】の重要性は、結城 浩『数学ガール フェルマーの最終定理』を読むとよく分かります。
【余り】は、実世界で「暗号」として大活躍しています。
http://www.maitou.gr.jp/rsa/rsa09.php
>>[723] YUJIさん
身体論については、
『身体化された心―仏教思想からのエナクティブ・アプローチ』
フランシスコ・ヴァレラ, エレノア・ロッシュ, エヴァン・トンプソン
(工作舎 2001)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=4746
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4875023545
この本など、いかがでしょう?
YUJIさんは、
・ジェームズL. オシュマンの生物物理学=エネルギー医学説(バックミンスター・フラーの「テンセグリティ」にも着目)
http://www.shamogoloparvaneh.com/Ener._Medicine.pdf
・「X‐信号系(間中善雄『体の中の原始信号』
http://mixi.jp/view_item.pl?id=757126)」説
・「チャクラと心の関係」説
一例:ニューエイジ流の図式的解釈
http://rouma.ocnk.net/page/14
あたりには心理的抵抗があるかもしれませんが、この本は面白く感じられるかも。
チベット仏教も学んだ認知科学者ヴァレラは、生命システムに関する「オートポイエーシス」論(河本英夫 http://mixi.jp/view_community.pl?id=5638985 も)の創始者の1人でしたし。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A9
僕には難解過ぎてよく分からないんですが、郡司ペギオ-幸夫らの「内部観測」論も、「オートポイエーシス」論に分類されるんでしょうか?
余談ですが
身体論で、バックミンスター・フラーの「テンセグリティ」に着目している人には、古武術家の甲野善紀氏もいます。
>■■テンセグリティー (Tensegrity)
>・バックミンスター・フラーにより提唱された概念。Tension(張力)とIntegrity(統合)の造語。
>・テンセグリティは構造システムが破綻しない範囲で、部材を極限まで減らしていったときの最適形状の一種とも考えられている。
>人体のテンセグリティモデル・・・ロルフィングなど
甲野善紀、小池弘人『武術と医術 人を活かすメソッド』(集英社新書 2013年)
http://blog.goo.ne.jp/usmle1789/e/289ff3bb3a7f83fb0e7bf0b17631fc3e
http://mixi.jp/view_item.pl?id=2406447
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087206939
http://blog.livedoor.jp/suchan4wd6/archives/2291564.html
http://kobujyutu.blog.fc2.com/blog-date-201310-3.html
テンセグリティ構造調整法・・・機能解剖学・運動学に基づいた整体の技術
http://bodycareseminar.simdif.com/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%B3%95.html
生命科学・生命論との関わりでは
『斎の舞へ』清水 宣明, 甲野 善紀(仮立舎 2006年)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=426664
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/499026570X
>生命研究にフラーのシナジー幾何学を応用できないか
【読書メモ】吉本隆明『新・書物の解体学』メタローグ 1992年 より<書評>を引用
<書評>I・プリゴジン/I・スタンジェール『混沌からの秩序』伏見康治ほか訳 みすず書房
著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。
<書評>I・プリゴジン/I・スタンジェール『混沌からの秩序』伏見康治ほか訳 みすず書房
著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。
吉本隆明「異常論」:『母型論』学研 1995年刊 所収
乳(胎)児にとって性の欲動を表象する乳首を吸う行為は、同時に栄養を摂取する食の行為と未分化のまま共時性の起源の状態にある。そしてこの共時性は成長して食と性が分離したあともなくならず、二重の層になって対応している。この性と栄養摂取とのいつまでもなくならない共時性は、内臓系からやってくる心の働きと体壁系につながる感覚の作用からできた織物に、いわば普遍的な性の意味を与えることになる。別の言い方をすればヒトという類の性と栄養摂取の共時性が、すべての内臓系の植物神経的な動きと動物系の知覚作用とに性的な意味を与えている素因だということになる。
たとえば窃視症と露出症は、眼の知覚作用に共時的に重なった眼の器官にまつわるエロス覚が過剰に不均質に充当されたものとみることができる。またサディズムとマゾヒズムは、体壁系に属する皮膚の痛圧感覚が、エロスとして過当な備給をうけたものとみなせることになる。これは内臓系についてもいえる。たとえば広義のヒステリー症を思いうかべてみれば、口(腔)や肛門のような鰓腸の上下の開口部にたいして性的な器官の役割を過剰に背負わせる傾向が、ある閾値を越えたばあいにおこるとかんがえることができる。もっとこの言い方をおしすすめれば愛と憎しみの情念や、他者への親和と敵意の感情は、内臓系とくに心臓の高まりから生れる心の動きに、対象にむかってゆく性の欲動が重なった形とみることができよう。
乳(胎)児にとって性の欲動を表象する乳首を吸う行為は、同時に栄養を摂取する食の行為と未分化のまま共時性の起源の状態にある。そしてこの共時性は成長して食と性が分離したあともなくならず、二重の層になって対応している。この性と栄養摂取とのいつまでもなくならない共時性は、内臓系からやってくる心の働きと体壁系につながる感覚の作用からできた織物に、いわば普遍的な性の意味を与えることになる。別の言い方をすればヒトという類の性と栄養摂取の共時性が、すべての内臓系の植物神経的な動きと動物系の知覚作用とに性的な意味を与えている素因だということになる。
たとえば窃視症と露出症は、眼の知覚作用に共時的に重なった眼の器官にまつわるエロス覚が過剰に不均質に充当されたものとみることができる。またサディズムとマゾヒズムは、体壁系に属する皮膚の痛圧感覚が、エロスとして過当な備給をうけたものとみなせることになる。これは内臓系についてもいえる。たとえば広義のヒステリー症を思いうかべてみれば、口(腔)や肛門のような鰓腸の上下の開口部にたいして性的な器官の役割を過剰に背負わせる傾向が、ある閾値を越えたばあいにおこるとかんがえることができる。もっとこの言い方をおしすすめれば愛と憎しみの情念や、他者への親和と敵意の感情は、内臓系とくに心臓の高まりから生れる心の動きに、対象にむかってゆく性の欲動が重なった形とみることができよう。
岸田秀「〔小谷野敦宛て書簡〕「江戸の性愛」幻想を斬る」:『ものぐさ性愛論』青土社 所収
わたしが「学問的なデュー・プロセスを踏んでいない」とのことですが、それはそうかもしれません。しかし、あなたは正しい普遍的な「学問的なデュー・プロセス」が存在するという幻想をもっているのではないかと、わたしには思えます。
性倒錯の一種としてのサディズム、すなわち、相手を傷つけ苦しめることと、性的興奮と満足とが結びついたもの、加虐行為と結び付いた性欲は近代に始まるのではないかと、わたしは考えています。サド公爵以前にサディストはいなかったというのはそういう意味です。ネロはキリスト教徒などを迫害して面白がっていたようですが、それで性的に興奮していたということはなかったと思います。
「好きな女とセックスしない男も近代に新しく現れた」ということに「確固たる根拠を示せと言われても困る」と書いたところ、「確固たる根拠を示してください」と迫られましたが、「確固たる根拠を示せと言われると困る」というのは一種のレトリックで、実は、わたしはどんなことについても「確固たる根拠」というようなものはめったにあるものではないと思っているのです。
女を性欲の対象にすることが加虐(身体的、精神的)の意味を帯び、その結果、「好きな女とセックスしない男」が新しく現れたというわけで、言わば、社会現象としての性も一種の論理構造を成しており、その論理構造にもとづいて、性に関してもいろいろなことが言い得ると、わたしは考えており、わたしとしては、そういう論理構造にもとづく判断のほうが、文学作品などを根拠とする判断よりも、あくまで相対的な意味においてですが、「確固たる」根拠にもとづく判断だと言えるのではなかろうかと思っているわけです。
自然科学の場合なら、論理にもとづく推測は、言わば、仮説の段階にあって、その仮説を証明するか、覆すかは実験によるわけですが(実験によって証明されればその仮説は正しい、という仮説そのものは実験によって正しいと証明できないと、養老孟司はわたしに言っていましたが)、人間に関して、歴史や社会現象に関して、実験は不可能なので、文学作品とか、臨床例とか、東西古今のいろいろな事件とか、自分の個人的経験とか、人から聞いた話とかの、言わば傍証に頼るしかなく、傍証をいくら集めても、厳密な意味での確証にはならないと思います。…そのうちいつか真理に到達するということはないのではないでしょうか。
わたしが「学問的なデュー・プロセスを踏んでいない」とのことですが、それはそうかもしれません。しかし、あなたは正しい普遍的な「学問的なデュー・プロセス」が存在するという幻想をもっているのではないかと、わたしには思えます。
性倒錯の一種としてのサディズム、すなわち、相手を傷つけ苦しめることと、性的興奮と満足とが結びついたもの、加虐行為と結び付いた性欲は近代に始まるのではないかと、わたしは考えています。サド公爵以前にサディストはいなかったというのはそういう意味です。ネロはキリスト教徒などを迫害して面白がっていたようですが、それで性的に興奮していたということはなかったと思います。
「好きな女とセックスしない男も近代に新しく現れた」ということに「確固たる根拠を示せと言われても困る」と書いたところ、「確固たる根拠を示してください」と迫られましたが、「確固たる根拠を示せと言われると困る」というのは一種のレトリックで、実は、わたしはどんなことについても「確固たる根拠」というようなものはめったにあるものではないと思っているのです。
女を性欲の対象にすることが加虐(身体的、精神的)の意味を帯び、その結果、「好きな女とセックスしない男」が新しく現れたというわけで、言わば、社会現象としての性も一種の論理構造を成しており、その論理構造にもとづいて、性に関してもいろいろなことが言い得ると、わたしは考えており、わたしとしては、そういう論理構造にもとづく判断のほうが、文学作品などを根拠とする判断よりも、あくまで相対的な意味においてですが、「確固たる」根拠にもとづく判断だと言えるのではなかろうかと思っているわけです。
自然科学の場合なら、論理にもとづく推測は、言わば、仮説の段階にあって、その仮説を証明するか、覆すかは実験によるわけですが(実験によって証明されればその仮説は正しい、という仮説そのものは実験によって正しいと証明できないと、養老孟司はわたしに言っていましたが)、人間に関して、歴史や社会現象に関して、実験は不可能なので、文学作品とか、臨床例とか、東西古今のいろいろな事件とか、自分の個人的経験とか、人から聞いた話とかの、言わば傍証に頼るしかなく、傍証をいくら集めても、厳密な意味での確証にはならないと思います。…そのうちいつか真理に到達するということはないのではないでしょうか。
内田樹『邪悪なものの鎮め方』(株)バジリコ
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。数値をもって示すことのできない「知」は知としては認知されない。…〔十九世紀末、イワノフスキーは〕「見えないもの」〔ウイルス〕が存在すると仮定しないと、「話のつじつまが会わない」ということを証明したのである。このような態度を「科学的」と呼ぶのだろうと私は思う。そこに「何か、私たちの手持ちの度量衡では考量できないもの」が存在すると想定しないと、「話のつじつまが合わない」場合には、「そういうものがある」と推論する。「存在する」と想定した方が話のつじつまが合うものについては、それを仮定的に想定して、いずれ「話のつじつまが次に合わなくなるまで」使い続ける、というのが自然科学のルールである。そうやって分子も、電子も、素粒子も「発見」されてきた。ところが、いま私たちに取り憑いている「数値主義」という病態では「私たちの手持ちの度量衡で考量できないもの」は「存在しないもの」とみなされなければならない。…なぜ、ある種の人は時間を「フライング」〔予見〕することができるのかを〔私たちはいま〕問うべきではないのか。
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。数値をもって示すことのできない「知」は知としては認知されない。…〔十九世紀末、イワノフスキーは〕「見えないもの」〔ウイルス〕が存在すると仮定しないと、「話のつじつまが会わない」ということを証明したのである。このような態度を「科学的」と呼ぶのだろうと私は思う。そこに「何か、私たちの手持ちの度量衡では考量できないもの」が存在すると想定しないと、「話のつじつまが合わない」場合には、「そういうものがある」と推論する。「存在する」と想定した方が話のつじつまが合うものについては、それを仮定的に想定して、いずれ「話のつじつまが次に合わなくなるまで」使い続ける、というのが自然科学のルールである。そうやって分子も、電子も、素粒子も「発見」されてきた。ところが、いま私たちに取り憑いている「数値主義」という病態では「私たちの手持ちの度量衡で考量できないもの」は「存在しないもの」とみなされなければならない。…なぜ、ある種の人は時間を「フライング」〔予見〕することができるのかを〔私たちはいま〕問うべきではないのか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
栗本慎一郎 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート