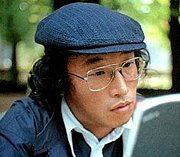|
|
|
|
コメント(42)
そうそう、イヤですよね(笑)。
まあそれはそれとして、栗本を語る上では、
「意味と生命」は避けられている傾向が強いと思います。
まあそれは栗本に限った話ではなくて、
たとえばフィリップ・K・ディックを語る上で、
「ヴァリス」は避けて通れない作品ですが、
みんなそれについては難解だとか神秘的だとか言って敬遠して、
テーマのわかりやすい短編ばかり論じている、というのがディック論の主流でした。
同じようにみんなより理解しやすい「パンツをはいたサル」などの論評に流れる、という感じで。
僕の知る限りで最も栗本について言及している評論家は、
多分浅羽通明だと思うのですが、
彼も基本的にニューアカブームへの影響について論じるのが主で、
思想に関して立ち入ったことは述べていないように思えます。
これを読んでいる方で興味を持った方には、
「天使の王国」(幻冬舎文庫)あたりがおすすめです。
あとは「ニセ学生マニュアル」というのもありましたが、今は入手困難かも。
まあつまるところ、
彼の仕事を総括し受け継ぐのは、
我々の使命である、ということでしょうかね(笑)
まあそれはそれとして、栗本を語る上では、
「意味と生命」は避けられている傾向が強いと思います。
まあそれは栗本に限った話ではなくて、
たとえばフィリップ・K・ディックを語る上で、
「ヴァリス」は避けて通れない作品ですが、
みんなそれについては難解だとか神秘的だとか言って敬遠して、
テーマのわかりやすい短編ばかり論じている、というのがディック論の主流でした。
同じようにみんなより理解しやすい「パンツをはいたサル」などの論評に流れる、という感じで。
僕の知る限りで最も栗本について言及している評論家は、
多分浅羽通明だと思うのですが、
彼も基本的にニューアカブームへの影響について論じるのが主で、
思想に関して立ち入ったことは述べていないように思えます。
これを読んでいる方で興味を持った方には、
「天使の王国」(幻冬舎文庫)あたりがおすすめです。
あとは「ニセ学生マニュアル」というのもありましたが、今は入手困難かも。
まあつまるところ、
彼の仕事を総括し受け継ぐのは、
我々の使命である、ということでしょうかね(笑)
浅羽通明の『ニセ学生マニュアル』って、たしか3冊出てたと思うんですが、最初は「縄文夢通信から目が離せない!」みたいに言ってたのに、2冊目から急に、現代思想批判という立場から、批判してるんですよね
詳しいところは忘れましたが。
最近は、仲正昌樹が『集中講義!日本の現代思想―ポストモダンとは何だったのか』 (NHKブックス)で、初期栗本を評価していました。
でも、後期の『意味と生命』は上手くスルーしています(笑)
『人類新世紀 終局の選択』は、彼の人生論として読めば面白いですね。
精神世界の「自ら選んだ」というシンプルな言説が根本原理主義に陥る危険性を指摘したところは、大きく頷きました。
「想念が形になる」という主張は、神智学やニューソート(アメリカ流成功哲学などのルーツ)みたいだ、と思いましたが、その後、東條真人氏と交流されたらしいことが『シリウスの都 飛鳥』で分かります。
近代エソテリシズム概論:ミトラ教と神智学・人智学(東條真人)
http://homepage2.nifty.com/Mithra/Mihrijja_Mithraism_and_Theosophy.html
http://homepage2.nifty.com/Mithra/Mihrijja_Mithraism_and_Theosophy2.html
http://home2.highway.ne.jp/miiboat/HP_Theosophy_Trans-himalaya.html
「脳の側坐核に人類の記憶(前世の記憶?)がある」という主張は、この本でしか見たことがありません
情報源は、何だったんでしょう?
詳しいところは忘れましたが。
最近は、仲正昌樹が『集中講義!日本の現代思想―ポストモダンとは何だったのか』 (NHKブックス)で、初期栗本を評価していました。
でも、後期の『意味と生命』は上手くスルーしています(笑)
『人類新世紀 終局の選択』は、彼の人生論として読めば面白いですね。
精神世界の「自ら選んだ」というシンプルな言説が根本原理主義に陥る危険性を指摘したところは、大きく頷きました。
「想念が形になる」という主張は、神智学やニューソート(アメリカ流成功哲学などのルーツ)みたいだ、と思いましたが、その後、東條真人氏と交流されたらしいことが『シリウスの都 飛鳥』で分かります。
近代エソテリシズム概論:ミトラ教と神智学・人智学(東條真人)
http://homepage2.nifty.com/Mithra/Mihrijja_Mithraism_and_Theosophy.html
http://homepage2.nifty.com/Mithra/Mihrijja_Mithraism_and_Theosophy2.html
http://home2.highway.ne.jp/miiboat/HP_Theosophy_Trans-himalaya.html
「脳の側坐核に人類の記憶(前世の記憶?)がある」という主張は、この本でしか見たことがありません
情報源は、何だったんでしょう?
まず栗本さんの時間論の枢要な部分の1つは、「意味と生命」P210の「さて空間は時間なしには成立し得ないとして〜」以後のその段落の部分です。
「空間の基礎は時間」というのは他の思想でもほぼそうだと思いますが、そこから先の議論は栗本さん独自だと思われます。
栗本さんの言っている事は、
時間は空間の基礎ではあるが、時間単体では存在し得ない。
時間というものは変容によって関連づけられるからである。
変容によって関連づけられるから、時間論の所でエントロピーだとか熱力学・統計力学の話が出てくるわけです。
ところが「変容」というものは明らかに「空間」に関する概念を含んでいますよね。
つまり結局の所、空間は時間によって基礎づけられ、時間は空間によって定義されるみたいな循環論になる。
これは西洋的な科学では甚だまずい事なのですが、経済人類学的には全く構わないと言っています(^_^;)
つまりそれを包括する全体があるからなのですが、その概念がまだ見つかってないというだけという事だと思います。
んでこの事を前提としてP214の3行目「ともあれ、時間と空間は〜」あたりの訳の解らぬ議論になっていきます(^_^;)
やっぱり経済人類学を知らない人間から見ると、その人が如何に頭の良い人でも、ここの議論は「ワケ解らん」となると思うなぁ(^_^;)
「空間の基礎は時間」というのは他の思想でもほぼそうだと思いますが、そこから先の議論は栗本さん独自だと思われます。
栗本さんの言っている事は、
時間は空間の基礎ではあるが、時間単体では存在し得ない。
時間というものは変容によって関連づけられるからである。
変容によって関連づけられるから、時間論の所でエントロピーだとか熱力学・統計力学の話が出てくるわけです。
ところが「変容」というものは明らかに「空間」に関する概念を含んでいますよね。
つまり結局の所、空間は時間によって基礎づけられ、時間は空間によって定義されるみたいな循環論になる。
これは西洋的な科学では甚だまずい事なのですが、経済人類学的には全く構わないと言っています(^_^;)
つまりそれを包括する全体があるからなのですが、その概念がまだ見つかってないというだけという事だと思います。
んでこの事を前提としてP214の3行目「ともあれ、時間と空間は〜」あたりの訳の解らぬ議論になっていきます(^_^;)
やっぱり経済人類学を知らない人間から見ると、その人が如何に頭の良い人でも、ここの議論は「ワケ解らん」となると思うなぁ(^_^;)
少しは、大和雅之さんなどに任せてたんじゃないですか?
相対性理論といえば、ホワイトヘッドが独自の代替論を出していたようですが、もうまったく、考慮に値しないものなんでしょうか?
当時理解して、代替論を発表するって、すごいことですよね!
今では、「アンチ相対論」を唱える人は、即「トンデモ」扱いされているのに
この人の議論など、麗奈さんからみて、どうですか?
以前から気になっていたんです。
マックスの科学館
http://home7.highway.ne.jp/max-1998/science.html
あと数年前、
ジョアオ・マゲイジョ
『光速より速い光〜アインシュタインに挑む若き科学者の物語』
という本が話題になったんですけど、その後、どうなっているんでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4140808411
常温核融合も、必ずしも「トンデモ」「病的科学」とは言えないらしいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88
水野忠彦、山口栄一氏などが研究されています。
反証されたのかな?
相対性理論といえば、ホワイトヘッドが独自の代替論を出していたようですが、もうまったく、考慮に値しないものなんでしょうか?
当時理解して、代替論を発表するって、すごいことですよね!
今では、「アンチ相対論」を唱える人は、即「トンデモ」扱いされているのに
この人の議論など、麗奈さんからみて、どうですか?
以前から気になっていたんです。
マックスの科学館
http://home7.highway.ne.jp/max-1998/science.html
あと数年前、
ジョアオ・マゲイジョ
『光速より速い光〜アインシュタインに挑む若き科学者の物語』
という本が話題になったんですけど、その後、どうなっているんでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4140808411
常温核融合も、必ずしも「トンデモ」「病的科学」とは言えないらしいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%B8%A9%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88
水野忠彦、山口栄一氏などが研究されています。
反証されたのかな?
>シナジーさん
「マックスの科学館 」の内容だけについて書きますが、それは貴方も持ってくる他のものにも適合する内容だと思います。
だから他のものには言及しないかもしれません。
>マックスの科学館
これの「相対性理論の異論を唱える科学者たち」
についてお答えします。
まずエーテルについて。
エーテルというのは電磁波の媒質で、電磁波の速さは静止したエーテルに対してのものと定義されていました。
座標軸がエーテルに対して動いているならば、その分だけ電磁波の速さが変わる筈です。
これは自動車から見た景色が動くのと同じ「原理」です。
地面は静止していても、車が動いている訳ですから車から見た景色は逆に動いて見えますよね。
ところが電磁波はどの動いている座標系から見ても、同じ速さなんです。
これは大変不思議な話で、光速度不変の原理と言って相対性理論の基本原理です。
実はこの根拠は既に古典物理の中にあるんです。
電磁方程式の中に真空の誘電率と真空の透磁率の積が出てくるのですが、これが光の速さです。
そしてこの値は時間に依存しないんです。
時間に依存しないって事は、如何なる座標系を取っても「不変」という事です。
光速は速さなんだから時間で微分したものでは?
と思うかもしれませんが、ここで電磁方程式で用いている真空の誘電率と真空の透磁率はどちらも当然定数です。だから当時はこれが光速だと誰も思わなかったかもしれません。ただの物理定数だという事にしてたかもしれない。
とにかく実はエーテルを想定するよりも、こちらの方がずっと超常現象的な筈です。
当時光速度不変が中々受け入れられなかったのは、想像に難しくありません。
だから未だに「エーテル」だとか騒ぐ人は、逆の逆を取ってしまって、凡庸に陥ってるというわけです。
因みに光は電磁波のある周波数帯の現象です。
光速度が不変だと逆に時間も空間も「相対的」でなければならなくなります。
栗本先生が時間や空間より、「速度」や「変容」がそれらの基軸となっていると考えるのはこの事からも自然なわけですね。
さて、これが言えてしまうと、ある絶対空間(つまりエーテルが静止している状態を基軸に取った空間)というものが否定されてしまいます。
どちらが「正しい」のかなのですが、実験データも大切ですが、むしろエーテルが採用されなかったのはエーテルを想定すると色々な現象の説明が大変難しくなってしまうからなんです。
科学を解ってない人は、常に「実体」を考えがちなのですが、科学にとって大切なのはむしろその説明法なんです。
エーテルが存在するかどうかではなくて、エーテルが存在すると想定すると、理論構築が大変困難になってしまうと考えるべきなんです。
だから偶々何かの実験でエーテルの存在を示唆するものがあっても、それだけでは駄目だという事です。
物理現象で目視できる現象なんてむしろ僅かなんですね。
特に素粒子物理学は電子顕微鏡でも見えない現象ですから、全て人間が勝手に「想像」してると言っても良いです。
例えば重力は皆さんにとって馴染み深いものでしょうが、これらの力の媒介に物質が介入してると思いますか?
実はしてるんです。重力子という「量子」が媒介してると考えられてます。
多分本当は無い記述をしたいと思ってるのですが、現在の科学水準ではそういう記述の仕方はまだできないんです。
つまりは重力子の存在そのものを議論するのがナンセンスなのはお解かりでしょうか。
基本的に科学というのはこういうものなんです。
「マックスの科学館 」の内容だけについて書きますが、それは貴方も持ってくる他のものにも適合する内容だと思います。
だから他のものには言及しないかもしれません。
>マックスの科学館
これの「相対性理論の異論を唱える科学者たち」
についてお答えします。
まずエーテルについて。
エーテルというのは電磁波の媒質で、電磁波の速さは静止したエーテルに対してのものと定義されていました。
座標軸がエーテルに対して動いているならば、その分だけ電磁波の速さが変わる筈です。
これは自動車から見た景色が動くのと同じ「原理」です。
地面は静止していても、車が動いている訳ですから車から見た景色は逆に動いて見えますよね。
ところが電磁波はどの動いている座標系から見ても、同じ速さなんです。
これは大変不思議な話で、光速度不変の原理と言って相対性理論の基本原理です。
実はこの根拠は既に古典物理の中にあるんです。
電磁方程式の中に真空の誘電率と真空の透磁率の積が出てくるのですが、これが光の速さです。
そしてこの値は時間に依存しないんです。
時間に依存しないって事は、如何なる座標系を取っても「不変」という事です。
光速は速さなんだから時間で微分したものでは?
と思うかもしれませんが、ここで電磁方程式で用いている真空の誘電率と真空の透磁率はどちらも当然定数です。だから当時はこれが光速だと誰も思わなかったかもしれません。ただの物理定数だという事にしてたかもしれない。
とにかく実はエーテルを想定するよりも、こちらの方がずっと超常現象的な筈です。
当時光速度不変が中々受け入れられなかったのは、想像に難しくありません。
だから未だに「エーテル」だとか騒ぐ人は、逆の逆を取ってしまって、凡庸に陥ってるというわけです。
因みに光は電磁波のある周波数帯の現象です。
光速度が不変だと逆に時間も空間も「相対的」でなければならなくなります。
栗本先生が時間や空間より、「速度」や「変容」がそれらの基軸となっていると考えるのはこの事からも自然なわけですね。
さて、これが言えてしまうと、ある絶対空間(つまりエーテルが静止している状態を基軸に取った空間)というものが否定されてしまいます。
どちらが「正しい」のかなのですが、実験データも大切ですが、むしろエーテルが採用されなかったのはエーテルを想定すると色々な現象の説明が大変難しくなってしまうからなんです。
科学を解ってない人は、常に「実体」を考えがちなのですが、科学にとって大切なのはむしろその説明法なんです。
エーテルが存在するかどうかではなくて、エーテルが存在すると想定すると、理論構築が大変困難になってしまうと考えるべきなんです。
だから偶々何かの実験でエーテルの存在を示唆するものがあっても、それだけでは駄目だという事です。
物理現象で目視できる現象なんてむしろ僅かなんですね。
特に素粒子物理学は電子顕微鏡でも見えない現象ですから、全て人間が勝手に「想像」してると言っても良いです。
例えば重力は皆さんにとって馴染み深いものでしょうが、これらの力の媒介に物質が介入してると思いますか?
実はしてるんです。重力子という「量子」が媒介してると考えられてます。
多分本当は無い記述をしたいと思ってるのですが、現在の科学水準ではそういう記述の仕方はまだできないんです。
つまりは重力子の存在そのものを議論するのがナンセンスなのはお解かりでしょうか。
基本的に科学というのはこういうものなんです。
上記のつづき
因みに上記の「マックスの科学館」の「相対性理論を否定する科学者たち」の内容はあまり高くは評価しません。
マイケルソン・モーレーの実験だけで何か言えないのは当たり前です。
マイケルソン・モーレーの実験の結果だけでは、地球に対してエーテルが静止していると考えれば良いだけの話ですからね。
ただ物理の教科書にはそれだけが載っていますが、他の膨大な実験データを載せてたら紙数も膨大になるからです。
この方の
>その他、現代の科学教育では「マイケルソン・モーレーの実験が相対性理論の証明」とされていますが〜
あたりのくだりを読んだだけで、読むに値しないのを見抜かなければなりません。
ある科学的に確実だとされているものが、本当にそうなのか実際に検証できる人は僅かです。
多くの学者も他人の業績を「前提」として仕事をしています。
その1つ1つが確かなものか実際に検証なんてしていません。
その為に科学的権威があり、マイケルポランニーもその重要性を指摘しています。
まずこれを受け入れる事(固執するという意味ではありません)が、科学をする「前提」なんです。
上記を書いた方は、恐らくこの辺の事が全く解っていません。
ところでこの人の「エーテルドリフト実験」については何も言えません。
このHPを見ただけでは、実験「原理」が解らないからです。
もしかすると実験装置に問題があるか、理論値の考え方が間違ってるかもしれません。
だからと言って、相対論に反するからと言って、例えばこんなものを一々読むのは大変です。
多分厳密に批判する為には、膨大な時間がかかる筈。
それらは過去の物理学者が「した」として現在があるのだと考えるんです。
現在の物理学界に残らなかったものは、他の人々が追試をしても同じ結果が得られなかったとか、理論的に煩雑でとても一般性を持たないとかで採用されなかったという事です。
それでも中には凄い発見もあるかもしれません。
ただ99%は多分やっぱり没だと思います。
物理学の論文は一年でも膨大なんです。一年分でも10年かけても読みきれない位です。
だから物理学に採用されなかった過去の論文を持ち出してきても無意味なんです。
というより、きちんとご自分で精読もしないで、「相対性理論が揺らいだ」的な事を持ち出されても、むしろ弊害の方が大きいです。
ある理論や実験の正当性を言う為に、膨大な物理学者が検証や追試をするんです。
その蓄積に対して、既に検証された可能性のある過去の論文を引っ張りだしてきて、云々するのはやはり学問に対して失礼でしょうね。
因みに上記の「マックスの科学館」の「相対性理論を否定する科学者たち」の内容はあまり高くは評価しません。
マイケルソン・モーレーの実験だけで何か言えないのは当たり前です。
マイケルソン・モーレーの実験の結果だけでは、地球に対してエーテルが静止していると考えれば良いだけの話ですからね。
ただ物理の教科書にはそれだけが載っていますが、他の膨大な実験データを載せてたら紙数も膨大になるからです。
この方の
>その他、現代の科学教育では「マイケルソン・モーレーの実験が相対性理論の証明」とされていますが〜
あたりのくだりを読んだだけで、読むに値しないのを見抜かなければなりません。
ある科学的に確実だとされているものが、本当にそうなのか実際に検証できる人は僅かです。
多くの学者も他人の業績を「前提」として仕事をしています。
その1つ1つが確かなものか実際に検証なんてしていません。
その為に科学的権威があり、マイケルポランニーもその重要性を指摘しています。
まずこれを受け入れる事(固執するという意味ではありません)が、科学をする「前提」なんです。
上記を書いた方は、恐らくこの辺の事が全く解っていません。
ところでこの人の「エーテルドリフト実験」については何も言えません。
このHPを見ただけでは、実験「原理」が解らないからです。
もしかすると実験装置に問題があるか、理論値の考え方が間違ってるかもしれません。
だからと言って、相対論に反するからと言って、例えばこんなものを一々読むのは大変です。
多分厳密に批判する為には、膨大な時間がかかる筈。
それらは過去の物理学者が「した」として現在があるのだと考えるんです。
現在の物理学界に残らなかったものは、他の人々が追試をしても同じ結果が得られなかったとか、理論的に煩雑でとても一般性を持たないとかで採用されなかったという事です。
それでも中には凄い発見もあるかもしれません。
ただ99%は多分やっぱり没だと思います。
物理学の論文は一年でも膨大なんです。一年分でも10年かけても読みきれない位です。
だから物理学に採用されなかった過去の論文を持ち出してきても無意味なんです。
というより、きちんとご自分で精読もしないで、「相対性理論が揺らいだ」的な事を持ち出されても、むしろ弊害の方が大きいです。
ある理論や実験の正当性を言う為に、膨大な物理学者が検証や追試をするんです。
その蓄積に対して、既に検証された可能性のある過去の論文を引っ張りだしてきて、云々するのはやはり学問に対して失礼でしょうね。
栗本さんは異端的な学説を引用してる半面、スタンダードなものも引用します。
アインシュタインやメルロポンティもそうだし、学者の名前こそあまり出さないけど構造主義や記号論的な手法も多用しています。
ただこういうのを云々するのは本質ではありません。
社会科学でも自然科学でも大切なのは、まず正統的に考える事だと思います。
それはつまり過去の学説にのっとって考えていく。
いきなり面白いからとか目立つからとかの理由で、逆を取ってはいけないと。
それはむしろ凡庸な姿勢だと思うんですね。
これは思考もそうなんだけど、正統的に考えるというのは実はとても難しいんです。
間違った考え方の方がずっと楽です。
言ってみれば、正解は1つに対して不正解はそれ以外ですから。
学問というものは1つの正解を探す作業に似ています。
ここが普通の人の世間話とは違うんです。
多くの人間に吟味されて、認められたものだけが生き残る。
それだけで絶対正しいとは言えませんが、残るものはそれなりに優れているものがあるのが通常です。
だからまず過去の学者の業績を生かすのが正道です。
こういう勉強をしっかりしない人、それを軽視する人は絶対に優れた業績はあげられないと思います。
しかし既存のスタンダードな学説でも、説明不能な事や不合理な点は幾らでも出てくると思います。
そこまで突き詰めて、新しい解決法を考えるのが栗本センセのしている事です。
彼は決して最初から異端になろうなんて考えてはいません。
既存の学説を吟味したプロセスを経ないで単に新しいものと、栗本先生のとは全然違います。
某掲示板でたまたま栗本スレがあったんですが、そこでの意見で
「パンサルを出した当時はその論理の奇抜さが新鮮で面白かったが、今はもう古いし当時の精彩はないな〜」
というのがありましたが、何も解っていないと思います。
ただこういう人を説得する自信は自分には無いので何も言いませんが(^_^;)
他の方は知りませんが、自分は栗本先生の学説が「面白い」から支持しているのでは全くありません。
彼が自分の言説で対象としている範囲の広さや、言語体系としての完成度に可能性があると思ってるからずっと支持し続けてるんです。
暗黙知理論の懐の深さは、凄まじいものがあります。
この気持ちは色々勉強して更に深まりましたね(^_^;)
アインシュタインやメルロポンティもそうだし、学者の名前こそあまり出さないけど構造主義や記号論的な手法も多用しています。
ただこういうのを云々するのは本質ではありません。
社会科学でも自然科学でも大切なのは、まず正統的に考える事だと思います。
それはつまり過去の学説にのっとって考えていく。
いきなり面白いからとか目立つからとかの理由で、逆を取ってはいけないと。
それはむしろ凡庸な姿勢だと思うんですね。
これは思考もそうなんだけど、正統的に考えるというのは実はとても難しいんです。
間違った考え方の方がずっと楽です。
言ってみれば、正解は1つに対して不正解はそれ以外ですから。
学問というものは1つの正解を探す作業に似ています。
ここが普通の人の世間話とは違うんです。
多くの人間に吟味されて、認められたものだけが生き残る。
それだけで絶対正しいとは言えませんが、残るものはそれなりに優れているものがあるのが通常です。
だからまず過去の学者の業績を生かすのが正道です。
こういう勉強をしっかりしない人、それを軽視する人は絶対に優れた業績はあげられないと思います。
しかし既存のスタンダードな学説でも、説明不能な事や不合理な点は幾らでも出てくると思います。
そこまで突き詰めて、新しい解決法を考えるのが栗本センセのしている事です。
彼は決して最初から異端になろうなんて考えてはいません。
既存の学説を吟味したプロセスを経ないで単に新しいものと、栗本先生のとは全然違います。
某掲示板でたまたま栗本スレがあったんですが、そこでの意見で
「パンサルを出した当時はその論理の奇抜さが新鮮で面白かったが、今はもう古いし当時の精彩はないな〜」
というのがありましたが、何も解っていないと思います。
ただこういう人を説得する自信は自分には無いので何も言いませんが(^_^;)
他の方は知りませんが、自分は栗本先生の学説が「面白い」から支持しているのでは全くありません。
彼が自分の言説で対象としている範囲の広さや、言語体系としての完成度に可能性があると思ってるからずっと支持し続けてるんです。
暗黙知理論の懐の深さは、凄まじいものがあります。
この気持ちは色々勉強して更に深まりましたね(^_^;)
>きちんとご自分で精読もしないで、「相対性理論が揺らいだ」的な事を持ち出されても、むしろ弊害の方が大きいです。
きちんと精読できないのは、私の勉強不足ですから陳謝しますが、理数系の知識を充分にマスターする自由な時間がなかなか取れないので、ここで理数系に詳しい方々にお尋ねしています。
エントロピーに関しても、熱力学と情報理論のものを同じに扱ってよいのか、理学系の人の間でも議論(槌田敦は否定)していますから、ご意見を聞いてみたいです。
地球温暖化も、専門家の間で見解が別れているじゃありませんか?
私自身は「想念が形になる(メルロ=ポンティから)」という栗本氏の説を敷衍していけば、「共振」「形(ゲーテ形態学など)」のテーマを追究するのは自然だと思っています。
奇をてらっているつもりは、全くありません。
ニコラ・テスラに注目したのも「共振」が重要な発想になっているからです。
多湖敬彦氏・井出治氏には直接お会いして、研究姿勢のしっかりされた「悪玉トンデモ」でない方だと考えています(それでも彼の仮説が間違っている可能性はもちろんあります)。
きちんと精読できないのは、私の勉強不足ですから陳謝しますが、理数系の知識を充分にマスターする自由な時間がなかなか取れないので、ここで理数系に詳しい方々にお尋ねしています。
エントロピーに関しても、熱力学と情報理論のものを同じに扱ってよいのか、理学系の人の間でも議論(槌田敦は否定)していますから、ご意見を聞いてみたいです。
地球温暖化も、専門家の間で見解が別れているじゃありませんか?
私自身は「想念が形になる(メルロ=ポンティから)」という栗本氏の説を敷衍していけば、「共振」「形(ゲーテ形態学など)」のテーマを追究するのは自然だと思っています。
奇をてらっているつもりは、全くありません。
ニコラ・テスラに注目したのも「共振」が重要な発想になっているからです。
多湖敬彦氏・井出治氏には直接お会いして、研究姿勢のしっかりされた「悪玉トンデモ」でない方だと考えています(それでも彼の仮説が間違っている可能性はもちろんあります)。
「熱力学エントロピーと情報エントロピーを同一視して良いか」という問題は、槌田敦派が徹底的にこれらを分けるべきとしていて、物理学者の間でも判断が分かれている状況らしいです(基本的に同一視して良いというのが主流ですが)。
エントロピー学会
http://entropy.ac/
なぜ、いまエントロピー学会なのか
http://entropy.ac/download/E1/E-3.pdf
汚れとは何か
http://www.teamrenzan.com/archives/writer/nagai/pollution.html
1982年の「理研において開催されたシンポジウム」において河宮信郎は、いわゆる「情報エントロピー」を熱学エントロピーと直接結びつけることによってエントロピーの統一的理解をはかる、という立場を示したが、1983年夏の「ラスティグ氏を囲むエントロピー・シンポジウム」以降、そうした理解の仕方の危険性を明確に指摘する立場へと転換
した。
こうしてエントロピー学会は、「情報や知識の増大を通じてのエントロピー問題の克服」という命題を分析・批判する力量をも次第に備えてきているように思われるのである。
もう20年は経っているのに、未だに専門家の間でも見解が分かれているんですかね?
「情報化が進めば、エントロピー増大は防げる」という議論が流布することを警戒しているのかな?
エントロピー学会
http://entropy.ac/
なぜ、いまエントロピー学会なのか
http://entropy.ac/download/E1/E-3.pdf
汚れとは何か
http://www.teamrenzan.com/archives/writer/nagai/pollution.html
1982年の「理研において開催されたシンポジウム」において河宮信郎は、いわゆる「情報エントロピー」を熱学エントロピーと直接結びつけることによってエントロピーの統一的理解をはかる、という立場を示したが、1983年夏の「ラスティグ氏を囲むエントロピー・シンポジウム」以降、そうした理解の仕方の危険性を明確に指摘する立場へと転換
した。
こうしてエントロピー学会は、「情報や知識の増大を通じてのエントロピー問題の克服」という命題を分析・批判する力量をも次第に備えてきているように思われるのである。
もう20年は経っているのに、未だに専門家の間でも見解が分かれているんですかね?
「情報化が進めば、エントロピー増大は防げる」という議論が流布することを警戒しているのかな?
栗本さんの時間論の、個人的に注目するところあげてみます。
時間はあるときエネルギーとして存在している。(P221)
エネルギーとは結局、無秩序の増加を生み出すものだ。(P222)
無秩序、あるいはもっと具体的にエントロピーを、”世界”を説明または解釈するときの基準に採ることは、更に別のはっきりしたメリットをわれわれに供給する。それは生命、あるいは簡単に、生体の化学機構の考察との単純で明快なブリッジを持つということである。(P223)
無秩序が、結局は秩序を支えることがあるという逆接が、空間から時間へという幼児の意識の発達の中でも働いている。(P225)
ということは、時間=エネルギー=エントロピー=無秩序が、システムの境界を形成させる原動力になっている。そして、これは、過剰蕩尽理論とつながってくると思いますが、いかがでしょうか?
時間はあるときエネルギーとして存在している。(P221)
エネルギーとは結局、無秩序の増加を生み出すものだ。(P222)
無秩序、あるいはもっと具体的にエントロピーを、”世界”を説明または解釈するときの基準に採ることは、更に別のはっきりしたメリットをわれわれに供給する。それは生命、あるいは簡単に、生体の化学機構の考察との単純で明快なブリッジを持つということである。(P223)
無秩序が、結局は秩序を支えることがあるという逆接が、空間から時間へという幼児の意識の発達の中でも働いている。(P225)
ということは、時間=エネルギー=エントロピー=無秩序が、システムの境界を形成させる原動力になっている。そして、これは、過剰蕩尽理論とつながってくると思いますが、いかがでしょうか?
テクノロジーの彼方 栗本慎一郎×田中三彦
雑誌「オルガン」6号 鉄腕アトムの涙 1989.
1989年7月29日深夜「朝まで生テレビ 原発特集」の後に行なわれた対談。
●新しいエネルギーの可能性
栗本
結論を言うと、ポランニーとぼくの意見は同じなんだけれども、
「シンプルなライフ、シンプルであってエネルギーをキープしうる生活はある」
という考えです。
このことはじつは、最終的な結論は、近々新しいエネルギーをぼくらはひょっとしてみつけられるんじゃないか。
「〔ジェフェリー・チューの〕ブーツ・ストラップでいくのか、クォークをつきぬけたデジタルでいくのか」という、じつはそのあたりに、狙っている新しいエネルギーがあるんじゃないか という感じがあるんじゃないですか。
田中
今までとは関係のない、想像もしなかったようなという意味でですか。
栗本
「言葉の上では想像もしなかったような」ですね。
たぶん、あると思うんですが。
田中
具体的に言うと?
栗本
今言ってしまうとチャネリングのようになります。
田中
ああ、チャネリングですか。
栗本
いやいや、「チャネリングのように」です(笑)。
今言うとね。
『意味と生命』という本の中で言っていますが、あれでもこれまでの既成のものに対して、1歩ぐらいでいいのに2、3歩行き過ぎているのかもしれませんけど、あるんだと思うんです。
そうすれば基本的に解決するというか、原子力というものを世間の人は「すごい大変なものだ」と思っているけれども、原理的にはきわめて簡単なものでしょう。
田中
原理は簡単ですね。
栗本
粗いものであるが、それが化石燃料より次元的に1つ超えたものを持っていたので、人類は喜んじゃってる。
田中
おっしゃっているのは、すると微細なエネルギーですね。
精妙なサトルなエナジーというような。
栗本
そう。
だから、「力が物体なり人体なりに対してどのように効くか」というのを、もう1つ見直してみなければならないと思っているんですね。
田中
それはサイキックなことですか。
栗本
そうですね。
体重70キロの人間を動かすのに、物理的な力で動かすんじゃなくて、動かすようにエネルギーを情報として伝達すればいいわけでしょう。
その情報の一貫性みたいなものがあり得るのではないか。
今のところそれはサイキックなエネルギーだとか、そういったところで論じられているし、いわゆるまともな大学内部の自然科学者なんかは疑わしいと言ったりしているような部分が、もう少し出てほしい。
そろそろ「いかがわしくないようなものなんだ」というふうに目を向けて出て行くということが可能だと思いませんか。
[p.25-26]
雑誌「オルガン」6号 鉄腕アトムの涙 1989.
1989年7月29日深夜「朝まで生テレビ 原発特集」の後に行なわれた対談。
●新しいエネルギーの可能性
栗本
結論を言うと、ポランニーとぼくの意見は同じなんだけれども、
「シンプルなライフ、シンプルであってエネルギーをキープしうる生活はある」
という考えです。
このことはじつは、最終的な結論は、近々新しいエネルギーをぼくらはひょっとしてみつけられるんじゃないか。
「〔ジェフェリー・チューの〕ブーツ・ストラップでいくのか、クォークをつきぬけたデジタルでいくのか」という、じつはそのあたりに、狙っている新しいエネルギーがあるんじゃないか という感じがあるんじゃないですか。
田中
今までとは関係のない、想像もしなかったようなという意味でですか。
栗本
「言葉の上では想像もしなかったような」ですね。
たぶん、あると思うんですが。
田中
具体的に言うと?
栗本
今言ってしまうとチャネリングのようになります。
田中
ああ、チャネリングですか。
栗本
いやいや、「チャネリングのように」です(笑)。
今言うとね。
『意味と生命』という本の中で言っていますが、あれでもこれまでの既成のものに対して、1歩ぐらいでいいのに2、3歩行き過ぎているのかもしれませんけど、あるんだと思うんです。
そうすれば基本的に解決するというか、原子力というものを世間の人は「すごい大変なものだ」と思っているけれども、原理的にはきわめて簡単なものでしょう。
田中
原理は簡単ですね。
栗本
粗いものであるが、それが化石燃料より次元的に1つ超えたものを持っていたので、人類は喜んじゃってる。
田中
おっしゃっているのは、すると微細なエネルギーですね。
精妙なサトルなエナジーというような。
栗本
そう。
だから、「力が物体なり人体なりに対してどのように効くか」というのを、もう1つ見直してみなければならないと思っているんですね。
田中
それはサイキックなことですか。
栗本
そうですね。
体重70キロの人間を動かすのに、物理的な力で動かすんじゃなくて、動かすようにエネルギーを情報として伝達すればいいわけでしょう。
その情報の一貫性みたいなものがあり得るのではないか。
今のところそれはサイキックなエネルギーだとか、そういったところで論じられているし、いわゆるまともな大学内部の自然科学者なんかは疑わしいと言ったりしているような部分が、もう少し出てほしい。
そろそろ「いかがわしくないようなものなんだ」というふうに目を向けて出て行くということが可能だと思いませんか。
[p.25-26]
●振動・波動・超常現象
栗本
エネルギーというものをどう考えるか。
重いものを運ぶこと、持ち上げるとか、明りをつけるということでいいわけですよね。
それがどういうふうに起きているかというと、今日の物理学の最尖端のことで言っても、たとえば、「振動の共振とか共鳴とか引き込み」という言葉はすでに使われておりますね。
そういうかっこうで伝達すればいいわけですね。
たとえば、目の前に100トンの鉄の塊があって、これを動かすには日常感覚から言えば、巨大なエネルギーがいるけれども、これがたとえば、金属内部の振動を共振させることができて、1メートル向こうに動けばいいわけでしょう。
「振動の働きをつきつめて、あともう1つか2つバリヤーを越したところで、そういうものが現在の科学から飛躍しないで、ブリッジしたままでできるんじゃないか」
というのが、今言えるあまり危険じゃない、バカと言われない範囲で(笑)、言えることなんですね。
振動とか波動とかそういうところです。
ついでに言ってしまえば、
「テレパシーであるとかそういった種類の、超常現象と言われていることは、それの部分的表現なんだ」
とぼくは思ってます。
すると、もとの振動の最初の部分は小さくていいわけですよ。
大きなものを極端に動かすようなものでなくていいわけであって、システムが分かれば、あるいは数字が分かるぐらいでいいかもしれません。
その関係を一応暫定的にでも、振動や周波数のデジタルな組み合わせで、たとえば、ブーツ・ストラップでもいいんですが、それを言えればいいんじゃないか、と考えているんです。
田中
そういう科学者がいるんですか。
栗本
大学ではいないでしょうね。
「今部分的に役立つものがあるかどうか」ということは、それはいつもの私のやりかたで、そういうものはいつも見てまして『パンツを捨てるサル』とかにまとめてますけれども。
今言えるのはそういうことですね。
超常現象についても、大学という職をしょってても部分的に参加している方がいくらでもおられますよね。
いくらでも見てるんです。
[p.36-37]
(続く)
栗本
エネルギーというものをどう考えるか。
重いものを運ぶこと、持ち上げるとか、明りをつけるということでいいわけですよね。
それがどういうふうに起きているかというと、今日の物理学の最尖端のことで言っても、たとえば、「振動の共振とか共鳴とか引き込み」という言葉はすでに使われておりますね。
そういうかっこうで伝達すればいいわけですね。
たとえば、目の前に100トンの鉄の塊があって、これを動かすには日常感覚から言えば、巨大なエネルギーがいるけれども、これがたとえば、金属内部の振動を共振させることができて、1メートル向こうに動けばいいわけでしょう。
「振動の働きをつきつめて、あともう1つか2つバリヤーを越したところで、そういうものが現在の科学から飛躍しないで、ブリッジしたままでできるんじゃないか」
というのが、今言えるあまり危険じゃない、バカと言われない範囲で(笑)、言えることなんですね。
振動とか波動とかそういうところです。
ついでに言ってしまえば、
「テレパシーであるとかそういった種類の、超常現象と言われていることは、それの部分的表現なんだ」
とぼくは思ってます。
すると、もとの振動の最初の部分は小さくていいわけですよ。
大きなものを極端に動かすようなものでなくていいわけであって、システムが分かれば、あるいは数字が分かるぐらいでいいかもしれません。
その関係を一応暫定的にでも、振動や周波数のデジタルな組み合わせで、たとえば、ブーツ・ストラップでもいいんですが、それを言えればいいんじゃないか、と考えているんです。
田中
そういう科学者がいるんですか。
栗本
大学ではいないでしょうね。
「今部分的に役立つものがあるかどうか」ということは、それはいつもの私のやりかたで、そういうものはいつも見てまして『パンツを捨てるサル』とかにまとめてますけれども。
今言えるのはそういうことですね。
超常現象についても、大学という職をしょってても部分的に参加している方がいくらでもおられますよね。
いくらでも見てるんです。
[p.36-37]
(続く)
田中
ぼくも非常に好き「だった」んです。
ぼくは何にも籍を置いていないから、超常現象についてしゃべってもいいんですが、そういう意味では気軽に見たし、うちの娘だってスプーンの2、3本平気で折るわけです。
そういうことを言うと、いろいろ批判を浴びますが、ぼくはどうしても「科学に見落としがあった」と思って、それに興味を持ったわけです。
エネルギー論として超常的なことに興味を持ったんじゃなくて、どっちかというと、
「科学の流儀だとか自然認識の基本において大きな違いがあるのかな」
という意味で、超常現象に興味を持ったんです。
でも、結局ぼくが思ったことは、「自然科学のテーマとしてはあまり重大なものでない」と思ったんです。
「DNAの螺旋1つ見ても、あのことが本当に偶然なのか」
ということのほうが大事で、今の普通の科学がやっていることは、
「結果論としては非常に分析ができているけれども、原因論としては非常になさけない状態にある」
と思うんです。
栗本
ぼくは「科学は結果論でいい」と思うんですよ。
最近読んでいて気がついたのは、超常現象に賛意を表して、そちらのほうから既成科学を批判している人が、よくそういうことを言うんですが、
「科学というのは結果論の経済的記述でいい」
と思うんです。
それともう1つ、スプーンが曲がる曲がらないというのは、金属の中を電子が飛んでいるから、そういうことができてもあまりに小さい。
けれども、具体的にギゼーのピラミッドのようなことがあるわけで、あれは明らかにエネルギーという概念に到達していた。
そうすれば、そのことについてわれわれの見落としがあるのは事実だろうと思っています。
そうすると、ピラミッド1個解読できるだけで、われわれが今つきあたっているぐらいのエネルギー問題は、と言うと怒られるけれども。
田中
するとエネルギー的に超常現象を見ているというわけですね。
そういうものが、そんなに今の科学とは不連続でないところで、新しいエネルギー論が近未来の中で登場してくる可能性があると。
栗本
あと1歩というと何ですが、あと2歩くらいじゃないですかねえ。
クォークと言っても、振動とかそういうことをもうちょっと調べたいというか、東大の清水博さんがやっているあたりを、もっと厚くカバーして、それでもまだ不足ですがね。
[p.37-38]
ぼくも非常に好き「だった」んです。
ぼくは何にも籍を置いていないから、超常現象についてしゃべってもいいんですが、そういう意味では気軽に見たし、うちの娘だってスプーンの2、3本平気で折るわけです。
そういうことを言うと、いろいろ批判を浴びますが、ぼくはどうしても「科学に見落としがあった」と思って、それに興味を持ったわけです。
エネルギー論として超常的なことに興味を持ったんじゃなくて、どっちかというと、
「科学の流儀だとか自然認識の基本において大きな違いがあるのかな」
という意味で、超常現象に興味を持ったんです。
でも、結局ぼくが思ったことは、「自然科学のテーマとしてはあまり重大なものでない」と思ったんです。
「DNAの螺旋1つ見ても、あのことが本当に偶然なのか」
ということのほうが大事で、今の普通の科学がやっていることは、
「結果論としては非常に分析ができているけれども、原因論としては非常になさけない状態にある」
と思うんです。
栗本
ぼくは「科学は結果論でいい」と思うんですよ。
最近読んでいて気がついたのは、超常現象に賛意を表して、そちらのほうから既成科学を批判している人が、よくそういうことを言うんですが、
「科学というのは結果論の経済的記述でいい」
と思うんです。
それともう1つ、スプーンが曲がる曲がらないというのは、金属の中を電子が飛んでいるから、そういうことができてもあまりに小さい。
けれども、具体的にギゼーのピラミッドのようなことがあるわけで、あれは明らかにエネルギーという概念に到達していた。
そうすれば、そのことについてわれわれの見落としがあるのは事実だろうと思っています。
そうすると、ピラミッド1個解読できるだけで、われわれが今つきあたっているぐらいのエネルギー問題は、と言うと怒られるけれども。
田中
するとエネルギー的に超常現象を見ているというわけですね。
そういうものが、そんなに今の科学とは不連続でないところで、新しいエネルギー論が近未来の中で登場してくる可能性があると。
栗本
あと1歩というと何ですが、あと2歩くらいじゃないですかねえ。
クォークと言っても、振動とかそういうことをもうちょっと調べたいというか、東大の清水博さんがやっているあたりを、もっと厚くカバーして、それでもまだ不足ですがね。
[p.37-38]
【振動の共振とか共鳴とか引き込み】
そういうかっこうで伝達すればいい。
【振動の働きをつきつめて、あともう1つか2つバリヤーを越したところで、そういうものが現在の科学から飛躍しないで、ブリッジしたままでできるんじゃないか】
【テレパシーであるとかそういった種類の、超常現象と言われていることは、それの部分的表現なんだ】
もとの振動の最初の部分は小さくていい。
大きなものを極端に動かすようなものでなくていいわけであって、システムが分かれば、あるいは数字が分かるぐらいでいいかもしれない。
その関係を一応暫定的にでも、
【振動や周波数のデジタルな組み合わせ】
で、それを言えればいいんじゃないか。
----------------------------------------------------------------
栗本氏はここまで発言していて、なぜ、東欧出身の天才科学者ニコラ・テスラには触れなかったのだろう?
----------------------------------------------------------------
1882(明治15)年2月のある遅い午後のことだった。
テスラは友人とブダペスト市内の公園に散歩に出かけた。
詩を暗誦しながら園内を歩いていると、大好きなゲーテの『ファウスト』の一節がふと浮かんだ。
日はだんだんいざって逃げる。きょう一日も葬られる。
日はあそこを駆けて行って、新しい生活を促す。
このからだに羽がはえて、あの跡を
どこまでも追って行かれたら! (高橋健二 訳)
するとたちまち啓示が訪れた。
テスラは落ちていた小枝を拾い上げると、泥道に図を描き始めた。
「見てみろ、これがぼくのモーターだ。さあ、逆転させてみるぞ」
テスラは子どものように興奮して叫んだ。
このときテスラが発見した原理は「回転磁界」と呼ばれ、交流システムの基本原理となった。
これを応用したのが世界最初の実用的な交流モーターとなった「二相誘導モーター」である。
『天才の発想力 エジソンとテスラ、発明の神に学ぶ』新戸雅章
(サイエンス・アイ新書 53) ソフトバンククリエイティブ
http://mixi.jp/view_item.pl?id=977925
『自然は脈動する―ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察』
アリック・バーソロミュー(日本教文社)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1028856
『SYNC』スティーヴン・ストロガッツ(早川書房)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=137075
ニコラ・テスラも、マイケル・ポランニーと同じく【東欧思考】【ブダペスト思考】の持ち主だった。
「共振、イメージ・象徴とアナロジー、身体性」という発想でつながっていくはずだ。
そういうかっこうで伝達すればいい。
【振動の働きをつきつめて、あともう1つか2つバリヤーを越したところで、そういうものが現在の科学から飛躍しないで、ブリッジしたままでできるんじゃないか】
【テレパシーであるとかそういった種類の、超常現象と言われていることは、それの部分的表現なんだ】
もとの振動の最初の部分は小さくていい。
大きなものを極端に動かすようなものでなくていいわけであって、システムが分かれば、あるいは数字が分かるぐらいでいいかもしれない。
その関係を一応暫定的にでも、
【振動や周波数のデジタルな組み合わせ】
で、それを言えればいいんじゃないか。
----------------------------------------------------------------
栗本氏はここまで発言していて、なぜ、東欧出身の天才科学者ニコラ・テスラには触れなかったのだろう?
----------------------------------------------------------------
1882(明治15)年2月のある遅い午後のことだった。
テスラは友人とブダペスト市内の公園に散歩に出かけた。
詩を暗誦しながら園内を歩いていると、大好きなゲーテの『ファウスト』の一節がふと浮かんだ。
日はだんだんいざって逃げる。きょう一日も葬られる。
日はあそこを駆けて行って、新しい生活を促す。
このからだに羽がはえて、あの跡を
どこまでも追って行かれたら! (高橋健二 訳)
するとたちまち啓示が訪れた。
テスラは落ちていた小枝を拾い上げると、泥道に図を描き始めた。
「見てみろ、これがぼくのモーターだ。さあ、逆転させてみるぞ」
テスラは子どものように興奮して叫んだ。
このときテスラが発見した原理は「回転磁界」と呼ばれ、交流システムの基本原理となった。
これを応用したのが世界最初の実用的な交流モーターとなった「二相誘導モーター」である。
『天才の発想力 エジソンとテスラ、発明の神に学ぶ』新戸雅章
(サイエンス・アイ新書 53) ソフトバンククリエイティブ
http://mixi.jp/view_item.pl?id=977925
『自然は脈動する―ヴィクトル・シャウベルガーの驚くべき洞察』
アリック・バーソロミュー(日本教文社)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1028856
『SYNC』スティーヴン・ストロガッツ(早川書房)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=137075
ニコラ・テスラも、マイケル・ポランニーと同じく【東欧思考】【ブダペスト思考】の持ち主だった。
「共振、イメージ・象徴とアナロジー、身体性」という発想でつながっていくはずだ。
『テスラ―発明的想像力の謎』新戸 雅章(工学社)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1014890
より引用。
http://nikola-tesla.sakura.ne.jp/
http://nikola-tesla.sakura.ne.jp/links.html
http://www.yurope.com/org/tesla/muzeje.htm
http://x51.org/x/03/04/2641.php
http://www.benedict.co.jp/Smalltalk/talk-12.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9
テスラの発明のキーワードは、一般にアイデアとか直観、インスピレーションだと見なされている。
回転磁界のアイデアを啓示として授かったとか、電気的共振の原理から世界的な無線システムを構想したといったエピソードがこうした見方を支えている。
この見方は間違いではないが、彼の発明を理解するためにはさらにキーワードを追加する必要がある。
それは【イメージ・シンボル・身体性・魔術性】といった言葉である。
テスラの特許には複雑な数式はほとんど出てこない。
そのかわり、多くの特許にイマジネーションを喚起するような概念図が添えられている。
これは彼の数学に対する能力不足というよりも、彼の発明の多くが頭の中でイメージやシンボルの助けを借りて成し遂げられたことに対応している。
とりわけ交流システムに関しては100%そうだった。
発想をふくらませる上では【アナロジー(類推)】の助けを借りることも多かった。
研究所の小さな高周波装置を地球的な規模の無線システムに拡大するといった技は彼の十八番だったし、電気推進の航空機や垂直離着陸機などもその奔放なイメージの中から飛び出したものだった。
また実験の積み重ねから生まれた発明もイメージやシンボルに満ちている。
無線システムが若いころの感覚過敏症による超知覚体験とつながり、テスラコイルによる放電が性〔エロス〕的なイメージにつながっていることは、テスラ研究者もつとに指摘しているところである。
また身体的な浮揚感覚が垂直離着陸機の発想につながったことは彼自身の言からも推測し得る。
それらを含めてテスラの発明家としてのありかたを「魔術的」と言うことが許されるのではないか。
「魔術的」という表現は誤解されやすいが、ここでは
【近代科学が切り捨ててきたイメージやシンボルの体系、身体性などを排除していない】
という意味である。
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1014890
より引用。
http://nikola-tesla.sakura.ne.jp/
http://nikola-tesla.sakura.ne.jp/links.html
http://www.yurope.com/org/tesla/muzeje.htm
http://x51.org/x/03/04/2641.php
http://www.benedict.co.jp/Smalltalk/talk-12.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9
テスラの発明のキーワードは、一般にアイデアとか直観、インスピレーションだと見なされている。
回転磁界のアイデアを啓示として授かったとか、電気的共振の原理から世界的な無線システムを構想したといったエピソードがこうした見方を支えている。
この見方は間違いではないが、彼の発明を理解するためにはさらにキーワードを追加する必要がある。
それは【イメージ・シンボル・身体性・魔術性】といった言葉である。
テスラの特許には複雑な数式はほとんど出てこない。
そのかわり、多くの特許にイマジネーションを喚起するような概念図が添えられている。
これは彼の数学に対する能力不足というよりも、彼の発明の多くが頭の中でイメージやシンボルの助けを借りて成し遂げられたことに対応している。
とりわけ交流システムに関しては100%そうだった。
発想をふくらませる上では【アナロジー(類推)】の助けを借りることも多かった。
研究所の小さな高周波装置を地球的な規模の無線システムに拡大するといった技は彼の十八番だったし、電気推進の航空機や垂直離着陸機などもその奔放なイメージの中から飛び出したものだった。
また実験の積み重ねから生まれた発明もイメージやシンボルに満ちている。
無線システムが若いころの感覚過敏症による超知覚体験とつながり、テスラコイルによる放電が性〔エロス〕的なイメージにつながっていることは、テスラ研究者もつとに指摘しているところである。
また身体的な浮揚感覚が垂直離着陸機の発想につながったことは彼自身の言からも推測し得る。
それらを含めてテスラの発明家としてのありかたを「魔術的」と言うことが許されるのではないか。
「魔術的」という表現は誤解されやすいが、ここでは
【近代科学が切り捨ててきたイメージやシンボルの体系、身体性などを排除していない】
という意味である。
現代の技術者が依拠する研究手段は、数学に基づく理論(数理)、実験、計算(コンピュータ)といったものである。
しかし、こうした方法が成立したのは、近代的な技術者(エンジニア)が成立した19世紀後半以降のことである。
それ以前の職人的な技術者は大なり小なり、イメージやシンボルの力を重視し、活用していた。
たとえば機械仕掛けの自動人形(オートマトン)を製作していた見世物師や時計職人たちは、おのれの技術を魔術的なものと自認し、単なる技術を超えた生命原理を追求していた。
しかしこうした知は、近代技術が形成されるにつれて捨てられ、あるいはエンジニア的な知に再編されていった。
独学者の常として、テスラはアカデミーが重視する科学的方法にこだわらなかった。
それどころかアナロジーによるイメージの横滑りや増殖、シンボル操作といった魔術的方法を駆使して、独創的なアイデアを開拓していったのである。
具体的にはアナロジーを多用しつつ、ミクロとマクロ、内と外、遠いものと近いものなどを交換して、思いがけないアイデアに到達する。
かつてはへロンやアルキメデス、レオナルド・ダ・ヴィンチといった技術的天才たちも利用したもので、広く創造性という観点からは現代でもその有効性は失われていないだろう。
その発明法は、テスラにおいては個々の発明を超えて1つの世界観にまで昇華されていた。
そのイメージに満ちた発明のあり方を、ひとまず【テスラ的】と呼ぶことにしたい。
【テスラ的】な発明法が、イメージやシンボル・言語・身体性などを駆使するといっても、数理や実験、計算をおろそかにするわけではない。
実際、テスラの高周波の研究は実験と同義語である。
地球規模の無線システムを開発する際も、まずマンハッタンの研究所で綿密な実験を重ね、その後コロラドスプリングズに大規模な実験施設を建設して、8ヶ月に及ぶ実験を行なったものである。
しかし同時に、彼の実験の傍らには、放電のシンボル的イメージや、共振原理によるミクロコスモスとマクロコスモスの照応といった魔術的世界観が常に寄り添っていた。
こうした世界観と厳密な科学実験が想像力の中で衝突し、火花を散らしながら、優れたアイデアに結晶化していくところにテスラの発明の真骨頂があった。
だから前人未踏の業績を達成することもできたのである。
もちろんテスラ的発明法は万能ではないし、アナロジーを多用するその方法は彼が活躍した19世紀末ですら時代遅れになろうとしていた。
そこを起点にして現代技術のあり方を批判するつもりはない。
それは近代科学の成果を否定して、魔術の時代に逆戻りせよと叫ぶようなものだからである。
ただ、数理科学万能の現代エンジニアリングにおいてもイメージの果たす役割は決してなくならない。
とりわけ、アイデアの生成や社会における技術の問題を考える場合はそうである。
テスラは研究室の実験を地球規模で考えると同時に、それらを自らの【身体性】において探求した。
また【共振】という概念を通じて環境とのかかわりを常に意識してきた。
言い換えれば、彼の発明は、人間と環境の【界面】において成し遂げられたものだった。
だからこそ、その発明的想像力は現代技術のあり方を問い直す契機ともなり得るのである。
詩的ともいえる奔放なイマジネーションゆえに、テスラの思考はしばしば正統科学から逸脱し、魔術的な世界をさ迷った。
彼の後半生の過小評価はそこに一因がある。
しかし技術的想像力にかぎらず、観念の歴史はそのような枝道や回り道にこそ大いなる発見の喜びがひそんでいるのではないだろうか。
しかし、こうした方法が成立したのは、近代的な技術者(エンジニア)が成立した19世紀後半以降のことである。
それ以前の職人的な技術者は大なり小なり、イメージやシンボルの力を重視し、活用していた。
たとえば機械仕掛けの自動人形(オートマトン)を製作していた見世物師や時計職人たちは、おのれの技術を魔術的なものと自認し、単なる技術を超えた生命原理を追求していた。
しかしこうした知は、近代技術が形成されるにつれて捨てられ、あるいはエンジニア的な知に再編されていった。
独学者の常として、テスラはアカデミーが重視する科学的方法にこだわらなかった。
それどころかアナロジーによるイメージの横滑りや増殖、シンボル操作といった魔術的方法を駆使して、独創的なアイデアを開拓していったのである。
具体的にはアナロジーを多用しつつ、ミクロとマクロ、内と外、遠いものと近いものなどを交換して、思いがけないアイデアに到達する。
かつてはへロンやアルキメデス、レオナルド・ダ・ヴィンチといった技術的天才たちも利用したもので、広く創造性という観点からは現代でもその有効性は失われていないだろう。
その発明法は、テスラにおいては個々の発明を超えて1つの世界観にまで昇華されていた。
そのイメージに満ちた発明のあり方を、ひとまず【テスラ的】と呼ぶことにしたい。
【テスラ的】な発明法が、イメージやシンボル・言語・身体性などを駆使するといっても、数理や実験、計算をおろそかにするわけではない。
実際、テスラの高周波の研究は実験と同義語である。
地球規模の無線システムを開発する際も、まずマンハッタンの研究所で綿密な実験を重ね、その後コロラドスプリングズに大規模な実験施設を建設して、8ヶ月に及ぶ実験を行なったものである。
しかし同時に、彼の実験の傍らには、放電のシンボル的イメージや、共振原理によるミクロコスモスとマクロコスモスの照応といった魔術的世界観が常に寄り添っていた。
こうした世界観と厳密な科学実験が想像力の中で衝突し、火花を散らしながら、優れたアイデアに結晶化していくところにテスラの発明の真骨頂があった。
だから前人未踏の業績を達成することもできたのである。
もちろんテスラ的発明法は万能ではないし、アナロジーを多用するその方法は彼が活躍した19世紀末ですら時代遅れになろうとしていた。
そこを起点にして現代技術のあり方を批判するつもりはない。
それは近代科学の成果を否定して、魔術の時代に逆戻りせよと叫ぶようなものだからである。
ただ、数理科学万能の現代エンジニアリングにおいてもイメージの果たす役割は決してなくならない。
とりわけ、アイデアの生成や社会における技術の問題を考える場合はそうである。
テスラは研究室の実験を地球規模で考えると同時に、それらを自らの【身体性】において探求した。
また【共振】という概念を通じて環境とのかかわりを常に意識してきた。
言い換えれば、彼の発明は、人間と環境の【界面】において成し遂げられたものだった。
だからこそ、その発明的想像力は現代技術のあり方を問い直す契機ともなり得るのである。
詩的ともいえる奔放なイマジネーションゆえに、テスラの思考はしばしば正統科学から逸脱し、魔術的な世界をさ迷った。
彼の後半生の過小評価はそこに一因がある。
しかし技術的想像力にかぎらず、観念の歴史はそのような枝道や回り道にこそ大いなる発見の喜びがひそんでいるのではないだろうか。
・・・
18世紀フランスの啓蒙主義者たちは「理性の光によって闇を駆逐し得る」と信じたが、実際にはそれは不可能な試みだった。
なぜなら、この闇は啓蒙的理性を支えた西欧形而上学が、その理性ゆえに内部に抱えてしまった闇にほかならないからである。
そこでなお理性の光を貫徹しようとすれば、空洞の原因たる理性自体を捨てなければならない。
啓蒙主義者はこうした光の逆説に対してあまりに無頓着だったが、近代の神秘思想家たちもその点では変わらない。
彼らが謳った太古の闇も、現実には啓蒙の光に支えられた近代の闇であり、空洞の闇に過ぎなかった。
しかしそのことに無自覚だったため、空疎な闇にあるはずのない豊かさを見出そうとしたあげく、科学的客観性の罠に落ち込んでいったのである〔「科学的」と名乗る宗教など〕。
西欧における光と闇の探求は、デカルト、カント、ヘーゲルといった合理主義の立場(光の立場)からも、ニーチェ、ヤスパース、ハイデガーといった非合理的主義(闇の立場)からもなされ、20世紀の思想的潮流をかたちづくっていった。
必要なのは、光か闇かを選択することではなく、両者の関係をまるごと問うことなのである。
テスラは1881年、20代半ばでハンガリーの首都ブダペストにおもむき、ここで電話局の技師として勤務した。
当時のブダペストはロンドンやパリと並ぶ世界都市のひとつで、電信や電話といった最新テクノロジーの中継点でもあった。
いわばそれは、モダンな「光の都市」だった。
しかし一方では、吸血鬼伝説などに彩られた中世以来の闇がまだ息づいている「闇の都市」でもあった。
『異星人伝説―20世紀を創ったハンガリー人』ジョルジュ・マルクス(日本評論社)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1233185
光を求めすぎた西欧近代が招き入れた闇は中世以来の闇を放逐し、その結果、闇は2つに引き裂かれることになった。
輝ける都市ニューヨークに住み、光(蛍光管)の発明家となったテスラの中にも両様の闇が存在した。
すなわち、マンハッタンの照明がつくりだす闇と故郷ユーゴスラヴィアにつながる闇である。
栗本 慎一郎
『光の都市 闇の都市』青土社 1981
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4791750314
『都市は、発狂する。―そして、ヒトはどこに行くのか』1983
http://mixi.jp/view_item.pl?id=997841
18世紀フランスの啓蒙主義者たちは「理性の光によって闇を駆逐し得る」と信じたが、実際にはそれは不可能な試みだった。
なぜなら、この闇は啓蒙的理性を支えた西欧形而上学が、その理性ゆえに内部に抱えてしまった闇にほかならないからである。
そこでなお理性の光を貫徹しようとすれば、空洞の原因たる理性自体を捨てなければならない。
啓蒙主義者はこうした光の逆説に対してあまりに無頓着だったが、近代の神秘思想家たちもその点では変わらない。
彼らが謳った太古の闇も、現実には啓蒙の光に支えられた近代の闇であり、空洞の闇に過ぎなかった。
しかしそのことに無自覚だったため、空疎な闇にあるはずのない豊かさを見出そうとしたあげく、科学的客観性の罠に落ち込んでいったのである〔「科学的」と名乗る宗教など〕。
西欧における光と闇の探求は、デカルト、カント、ヘーゲルといった合理主義の立場(光の立場)からも、ニーチェ、ヤスパース、ハイデガーといった非合理的主義(闇の立場)からもなされ、20世紀の思想的潮流をかたちづくっていった。
必要なのは、光か闇かを選択することではなく、両者の関係をまるごと問うことなのである。
テスラは1881年、20代半ばでハンガリーの首都ブダペストにおもむき、ここで電話局の技師として勤務した。
当時のブダペストはロンドンやパリと並ぶ世界都市のひとつで、電信や電話といった最新テクノロジーの中継点でもあった。
いわばそれは、モダンな「光の都市」だった。
しかし一方では、吸血鬼伝説などに彩られた中世以来の闇がまだ息づいている「闇の都市」でもあった。
『異星人伝説―20世紀を創ったハンガリー人』ジョルジュ・マルクス(日本評論社)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1233185
光を求めすぎた西欧近代が招き入れた闇は中世以来の闇を放逐し、その結果、闇は2つに引き裂かれることになった。
輝ける都市ニューヨークに住み、光(蛍光管)の発明家となったテスラの中にも両様の闇が存在した。
すなわち、マンハッタンの照明がつくりだす闇と故郷ユーゴスラヴィアにつながる闇である。
栗本 慎一郎
『光の都市 闇の都市』青土社 1981
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4791750314
『都市は、発狂する。―そして、ヒトはどこに行くのか』1983
http://mixi.jp/view_item.pl?id=997841
電磁波と人間の関係を歴史的にたどってみると、初期には人体に悪影響を与えるものだといった発想はまったくなかった。
それは電信やラジオの実用化に先駆けて、高周波の熱効果が医療・健康の分野で利用されたことからもわかる。
第2次世界大戦前には流行した高周波療法は現代でも医療や美容・マッサージなどに用いられているし、ガンの治療法にも応用されている。
そしてこの分野を開拓したのもまたテスラだった。
テスラの提案は多くの医療関係者に強烈なインパクトを与え、高周波療法は世界的な流行となった。
万能療法としてもてはやされた過去の反動から、とかくうさんくさい目で見られがちな高周波療法だが、最先端医療にも応用し得る、優れた治療法であることは再認識されてよいだろう。
テスラの研究が当時、どれほど進んでいたかを示すエピソードに、「アメリカ最初のレントゲン写真撮影者はテスラだった」という説がある。
レントゲンの発表前、テスラはガイスラー管の下で親友マーク・トウェインの写真を撮った。
撮影後、出来上がった写真を見た発明家はカメラレンズの調整ネジが鮮明に映っていたのに気付いた。
この写真が事実上、アメリカで最初のX写真だったというのである。
テスラがレントゲンに先駆けて真空放電による透過効果を知っていたことは、多くのテスラ研究者が指摘しているところである。
しかし、知っていたことと、理解していたことはまた別である。
結局、彼はその知識を未知の放射線発見に結びつけることはできなかった。
ちなみに、旧ソ連の技術者セミョーン・キルリアンが1930年代に発見した「キルリアン写真」(生体エネルギー、オーラを写したものと主張されることがある)も、1890年代にテスラがコロナ放電を撮影した高圧放電写真と同じものであることを、キルリアン自身が認めている。
テスラと高周波の関わりを理解するキーワードは【共振】にある。
共振とは、一般に外部からの力で振動させられた物体の振動数が、物体の固有振動数(物体ごとに決まっている1秒間の振動回数)と一致して大きな振動が起こる現象をいう。
同じ現象は音波でも起こるが、その場合は共振ではなく【共鳴】と呼ばれる。
ギターやバイオリンなどの楽器は、共鳴現象をうまく利用して小さな楽器で大きな音を出しているのである。
テスラの電気的な発明にはこの共振現象を利用したものが多い。
無線電力輸送システムや宇宙からエネルギーを取り出す無限エネルギー装置といった壮大なアイデアも、もとを正せば共振回路(ラジオの同調回路など)を地球的、宇宙的規模に拡大したものと見なせるだろう。
またそれは、機械的共振を利用した通信システムや、共振を利用して地球を真っ二つにする(「地球2分割法」)といったユニークなアイデアとも重なっている。
「テロートマトン(tel-automaton)」と名付けた遠隔操縦ロボットも、人間を宇宙的な共振機械とみなすところから発想されたものだった。
無線操縦のテロートマトンは、太陽電池を動力に無線操縦されるNASAの全翼無人ソーラー機「ヘリオス」に受け継がれている。
また2001年、ソニーから発売された無線操縦で動くAIBO(アイボ)も、テロートマトンの発展型であることは言うまでもない。
垂直離着陸機もフォークランド紛争で活躍した米軍のAV8ハリアー戦闘機(開発したのはイギリス)として実用化されている。
テスラが心血を注いだ無線送電も、マイクロ波を利用した太陽発電衛星構想とかたちを変えてNASAや宇宙科学研究所で研究が進められている。
それは電信やラジオの実用化に先駆けて、高周波の熱効果が医療・健康の分野で利用されたことからもわかる。
第2次世界大戦前には流行した高周波療法は現代でも医療や美容・マッサージなどに用いられているし、ガンの治療法にも応用されている。
そしてこの分野を開拓したのもまたテスラだった。
テスラの提案は多くの医療関係者に強烈なインパクトを与え、高周波療法は世界的な流行となった。
万能療法としてもてはやされた過去の反動から、とかくうさんくさい目で見られがちな高周波療法だが、最先端医療にも応用し得る、優れた治療法であることは再認識されてよいだろう。
テスラの研究が当時、どれほど進んでいたかを示すエピソードに、「アメリカ最初のレントゲン写真撮影者はテスラだった」という説がある。
レントゲンの発表前、テスラはガイスラー管の下で親友マーク・トウェインの写真を撮った。
撮影後、出来上がった写真を見た発明家はカメラレンズの調整ネジが鮮明に映っていたのに気付いた。
この写真が事実上、アメリカで最初のX写真だったというのである。
テスラがレントゲンに先駆けて真空放電による透過効果を知っていたことは、多くのテスラ研究者が指摘しているところである。
しかし、知っていたことと、理解していたことはまた別である。
結局、彼はその知識を未知の放射線発見に結びつけることはできなかった。
ちなみに、旧ソ連の技術者セミョーン・キルリアンが1930年代に発見した「キルリアン写真」(生体エネルギー、オーラを写したものと主張されることがある)も、1890年代にテスラがコロナ放電を撮影した高圧放電写真と同じものであることを、キルリアン自身が認めている。
テスラと高周波の関わりを理解するキーワードは【共振】にある。
共振とは、一般に外部からの力で振動させられた物体の振動数が、物体の固有振動数(物体ごとに決まっている1秒間の振動回数)と一致して大きな振動が起こる現象をいう。
同じ現象は音波でも起こるが、その場合は共振ではなく【共鳴】と呼ばれる。
ギターやバイオリンなどの楽器は、共鳴現象をうまく利用して小さな楽器で大きな音を出しているのである。
テスラの電気的な発明にはこの共振現象を利用したものが多い。
無線電力輸送システムや宇宙からエネルギーを取り出す無限エネルギー装置といった壮大なアイデアも、もとを正せば共振回路(ラジオの同調回路など)を地球的、宇宙的規模に拡大したものと見なせるだろう。
またそれは、機械的共振を利用した通信システムや、共振を利用して地球を真っ二つにする(「地球2分割法」)といったユニークなアイデアとも重なっている。
「テロートマトン(tel-automaton)」と名付けた遠隔操縦ロボットも、人間を宇宙的な共振機械とみなすところから発想されたものだった。
無線操縦のテロートマトンは、太陽電池を動力に無線操縦されるNASAの全翼無人ソーラー機「ヘリオス」に受け継がれている。
また2001年、ソニーから発売された無線操縦で動くAIBO(アイボ)も、テロートマトンの発展型であることは言うまでもない。
垂直離着陸機もフォークランド紛争で活躍した米軍のAV8ハリアー戦闘機(開発したのはイギリス)として実用化されている。
テスラが心血を注いだ無線送電も、マイクロ波を利用した太陽発電衛星構想とかたちを変えてNASAや宇宙科学研究所で研究が進められている。
テスラの身体(共振的身体)は、生涯を通して外界と共振し続けた。
〔電磁波が世界を駆け巡る〕「世界システム」においては、それはもはや地球身体とか世界身体というべきものに拡張されていた。
いや、テスラが主張するがごとく人間の肉体が宇宙の歯車に組み込まれた機械であるとすれば、それは宇宙的身体でもあった。
マーガレット・チェニーは、「テスラが多様な周波数の電磁波が織りなす宇宙的ハーモニーに魅了されながら、電磁波の探求に邁進したのだ」と指摘している。
『テスラ―発明王エジソンを超えた偉才』マーガレット・チェニー(工作舎)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=655506
鋭い指摘だが、それは彼がこの宇宙音楽の指揮者や演奏者だったことを意味するだけではない。
なにより彼自身が宇宙的ハーモニーの共鳴器、すなわち楽器としてその音楽の一部となっていたのである。
この過剰な身体性によってテスラは自分を取り巻く環境と、自分自身の観念や肉体の関係について考えざるを得なかった。
彼の発明が「技術―発明的な」想像力の宝庫である理由はここにある。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー・ボックスセット』[DVD]
http://mixi.jp/view_item.pl?id=18855
『プレステージ スタンダード・エディション 』[DVD]
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1206310
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの天才科学者ドクのモデルはテスラであり、彼へのリスペクトが隠されていると考えられるのは、火花放電・遠隔操縦(リモコン、ラジコン)・ロボットの基礎を作ったのが実はテスラであり、アメリカSFの祖ヒューゴー・ガーンズバック(→ヒューゴー賞)も彼の崇拝者でした。
ガーンズバックはテスラが亡くなった際、デスマスクの制作を彫刻家に依頼しているほどです。
第1作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開は1985(昭和60)年でレーガン政権のもとにSDI構想が進められていた時期なので、レーザーのアイディアを残しているテスラを表に出すことは避けられたのかもしれません。
彼の晩年の発明構想は軍事機密になっているようで、現在も謎に包まれたままです(レーダー、レーザー、プラズマ、高エネルギー粒子ビーム兵器などに関する研究の基にされたと言われる)。
私たちが現在、空気のように使っている電気交流システムのほとんどを完成させ、今日の世界の産業の基礎を築いた天才発明家ですから、もっと知られていいと思いますね。
ちなみに、大槻義彦教授専攻のプラズマ(球電)を人工的に作り出した最初の人物もテスラで、携帯電話の基礎も無線電話技術に支えられていますから、彼の発明が原型と言えます。
〔電磁波が世界を駆け巡る〕「世界システム」においては、それはもはや地球身体とか世界身体というべきものに拡張されていた。
いや、テスラが主張するがごとく人間の肉体が宇宙の歯車に組み込まれた機械であるとすれば、それは宇宙的身体でもあった。
マーガレット・チェニーは、「テスラが多様な周波数の電磁波が織りなす宇宙的ハーモニーに魅了されながら、電磁波の探求に邁進したのだ」と指摘している。
『テスラ―発明王エジソンを超えた偉才』マーガレット・チェニー(工作舎)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=655506
鋭い指摘だが、それは彼がこの宇宙音楽の指揮者や演奏者だったことを意味するだけではない。
なにより彼自身が宇宙的ハーモニーの共鳴器、すなわち楽器としてその音楽の一部となっていたのである。
この過剰な身体性によってテスラは自分を取り巻く環境と、自分自身の観念や肉体の関係について考えざるを得なかった。
彼の発明が「技術―発明的な」想像力の宝庫である理由はここにある。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー・ボックスセット』[DVD]
http://mixi.jp/view_item.pl?id=18855
『プレステージ スタンダード・エディション 』[DVD]
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1206310
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの天才科学者ドクのモデルはテスラであり、彼へのリスペクトが隠されていると考えられるのは、火花放電・遠隔操縦(リモコン、ラジコン)・ロボットの基礎を作ったのが実はテスラであり、アメリカSFの祖ヒューゴー・ガーンズバック(→ヒューゴー賞)も彼の崇拝者でした。
ガーンズバックはテスラが亡くなった際、デスマスクの制作を彫刻家に依頼しているほどです。
第1作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開は1985(昭和60)年でレーガン政権のもとにSDI構想が進められていた時期なので、レーザーのアイディアを残しているテスラを表に出すことは避けられたのかもしれません。
彼の晩年の発明構想は軍事機密になっているようで、現在も謎に包まれたままです(レーダー、レーザー、プラズマ、高エネルギー粒子ビーム兵器などに関する研究の基にされたと言われる)。
私たちが現在、空気のように使っている電気交流システムのほとんどを完成させ、今日の世界の産業の基礎を築いた天才発明家ですから、もっと知られていいと思いますね。
ちなみに、大槻義彦教授専攻のプラズマ(球電)を人工的に作り出した最初の人物もテスラで、携帯電話の基礎も無線電話技術に支えられていますから、彼の発明が原型と言えます。
それから栗本氏がたまに言及している、エドガー・ケイシーのリーディングによるエネルギー関連情報は
エドガー・エヴァンズ・ケイシー
『アトランティス物語―「失われた帝国」の全貌』
http://mixi.jp/view_item.pl?id=665570
『アトランティス』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4813602215
( まったく同じ内容の2冊)
まったく同じ内容の2冊)
『波動療法』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=348402
に詳しいですが、内容の評価は各自にお任せします
エドガー・エヴァンズ・ケイシー
『アトランティス物語―「失われた帝国」の全貌』
http://mixi.jp/view_item.pl?id=665570
『アトランティス』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4813602215
(
『波動療法』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=348402
に詳しいですが、内容の評価は各自にお任せします
『アトランティス物語―「失われた帝国」の全貌』
http://mixi.jp/view_item.pl?id=665570
『アトランティス』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4813602215
【内容】
プラトンは、およそ9000年前に大西洋に巨大な島が沈没したことを紹介している。
以後、多くの研究者が伝説の大陸を究明するためにさまざまな角度から論議を重ねてきたが、いまだ、決定的な結論には至っていない。
エドガー・ケイシーのリーディングをもとに研究を進めた本書は、想像の範囲を超え、アトランティス大陸の輪郭を明らかに浮き上がらせている。
さらにリーディングは、地球の未来についても言及する。
現存する地球上の大陸は、アトランティスと同じ運命をたどるのだろうか。
本書は、ひとつの解答を明示した、他に類書を見ない秀逸の名著である。
2002年刊『アトランティス物語』の改題、全面改訳新版。
【著者略歴】
ケイシー,エドガー・エバンズ
1918年米アラバマ州セルマ生まれ。
故エドガー・ケイシーの次男。
1925年、家族とともにバージニア州バージニアビーチに移る。
超心理学の学部を置くことで名高いデューク大学(J.B.ラインが創始)に学び、電子工学の学位取得。
第2次大戦で四年間米兵役に従事。
のち、バージニア州の公認エンジニアとなる。
現在、エドガー・ケイシー財団広報教育機関AREの保管委員長を努めている。
林 陽
1953年千葉県生まれ。独協大学外国語学部で英文学専攻。作家。雑誌ライター。出版翻訳家。
在学中にエドガー・ケイシー研究会を始めて、多数の著書を翻訳。
【目次】
第1章 アトランティス伝説
第2章 ライフ・リーディングと転生
第3章 紀元前5万年のアトランティス大陸
第4章 紀元前5万年から紀元前一万年までのアトランティス
第5章 アトランティス大陸最後の崩壊
第6章 アトランティス大陸の痕跡
第7章 補遺 ツーオイ石の謎

チャネリング本などでよく出てくる「アトランティス話」は、このエドガー・ケイシーのリーディングと近代神智学・人智学の宇宙論・根源人種論が「元ネタ」だと思われます。
「第7章 補遺 ツーオイ石の謎」には、複雑な数式まで出てきていますが(変換できないのでここには載せられません)、原著が書かれたのはかなり昔ですし、私には理数系素養が不足しているため正否が分かりません(苦笑)
誰か勇気のある理数系の方がいましたら、判断をお願いします(メッセージでも結構です)。
「エドガー・ケイシーのリーディングから発想のヒントを得ました」と明言することは、栗本慎一郎氏以外、日本(おそらく欧米でも)の学術系ではタブーだと思います(あ、小室直樹氏なら許されるかもしれない)。
得たとしても論文には書かないでしょう。
シャーリー・マクレーンが紹介していたチャネラーのうち、ケビン・ライヤーソンはARE出身でした。
http://www.asahi-net.or.jp/~df7t-ymd/kr.html
公平を期すため、懐疑派の見解なども貼っておきます。
http://www.genpaku.org/skepticj/channeling.html
http://www.genpaku.org/skepticj/cayce.html
http://mimizun.com/2chlog/psy/mentai.2ch.net/psy/kako/996/996009371.html
http://mimizun.com/2chlog/psy/life.2ch.net/psy/kako/1043/10431/1043188893.html
http://mixi.jp/view_item.pl?id=665570
『アトランティス』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4813602215
【内容】
プラトンは、およそ9000年前に大西洋に巨大な島が沈没したことを紹介している。
以後、多くの研究者が伝説の大陸を究明するためにさまざまな角度から論議を重ねてきたが、いまだ、決定的な結論には至っていない。
エドガー・ケイシーのリーディングをもとに研究を進めた本書は、想像の範囲を超え、アトランティス大陸の輪郭を明らかに浮き上がらせている。
さらにリーディングは、地球の未来についても言及する。
現存する地球上の大陸は、アトランティスと同じ運命をたどるのだろうか。
本書は、ひとつの解答を明示した、他に類書を見ない秀逸の名著である。
2002年刊『アトランティス物語』の改題、全面改訳新版。
【著者略歴】
ケイシー,エドガー・エバンズ
1918年米アラバマ州セルマ生まれ。
故エドガー・ケイシーの次男。
1925年、家族とともにバージニア州バージニアビーチに移る。
超心理学の学部を置くことで名高いデューク大学(J.B.ラインが創始)に学び、電子工学の学位取得。
第2次大戦で四年間米兵役に従事。
のち、バージニア州の公認エンジニアとなる。
現在、エドガー・ケイシー財団広報教育機関AREの保管委員長を努めている。
林 陽
1953年千葉県生まれ。独協大学外国語学部で英文学専攻。作家。雑誌ライター。出版翻訳家。
在学中にエドガー・ケイシー研究会を始めて、多数の著書を翻訳。
【目次】
第1章 アトランティス伝説
第2章 ライフ・リーディングと転生
第3章 紀元前5万年のアトランティス大陸
第4章 紀元前5万年から紀元前一万年までのアトランティス
第5章 アトランティス大陸最後の崩壊
第6章 アトランティス大陸の痕跡
第7章 補遺 ツーオイ石の謎
チャネリング本などでよく出てくる「アトランティス話」は、このエドガー・ケイシーのリーディングと近代神智学・人智学の宇宙論・根源人種論が「元ネタ」だと思われます。
「第7章 補遺 ツーオイ石の謎」には、複雑な数式まで出てきていますが(変換できないのでここには載せられません)、原著が書かれたのはかなり昔ですし、私には理数系素養が不足しているため正否が分かりません(苦笑)
誰か勇気のある理数系の方がいましたら、判断をお願いします(メッセージでも結構です)。
「エドガー・ケイシーのリーディングから発想のヒントを得ました」と明言することは、栗本慎一郎氏以外、日本(おそらく欧米でも)の学術系ではタブーだと思います(あ、小室直樹氏なら許されるかもしれない)。
得たとしても論文には書かないでしょう。
シャーリー・マクレーンが紹介していたチャネラーのうち、ケビン・ライヤーソンはARE出身でした。
http://www.asahi-net.or.jp/~df7t-ymd/kr.html
公平を期すため、懐疑派の見解なども貼っておきます。
http://www.genpaku.org/skepticj/channeling.html
http://www.genpaku.org/skepticj/cayce.html
http://mimizun.com/2chlog/psy/mentai.2ch.net/psy/kako/996/996009371.html
http://mimizun.com/2chlog/psy/life.2ch.net/psy/kako/1043/10431/1043188893.html
『波動療法』 (エドガー・ケイシー文庫)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=348402
【内容】
生命の源とも言われる水。
その水が、私たち人間にどのような作用を与えているか、水治療法、水浄化法、飲水健康法など、水の神秘力を解説。
また、電気、色、音の太陽エネルギーによってもたらされる三大波動についての概説がなされ、それぞれの波動による詳細な治療法が、リーディングを通じて紹介される。
波動の調整を行えば、人間本来の治癒力が活性化すると言う。
近年注目の波動療法の草分けとも言える書。
『エドガー・ケイシー驚異の波動健康法』の全面改訳新版。
【著者略歴】
バラード,ジュリエット・ブルック
ランドルフ・メーコン女子大学卒、ウィリアム&メリー大学大学院で文学の修士号を取得、「アメリカ淑女録」にも名を連ねている女流作家である。
1959年より、エドガー・ケイシー・リーディングを研究、1966年から1970年まで、エドガー・ケイシー財団広報教育機関AREが発行する専門誌「AREジャーナル」の共同編集者、1971年から1973年にかけて雑誌「トレジャー・トローブ」の編集長をつとめる。
【目次】
第1章 水の神秘な治療力
第2章 太陽エネルギーの謎を解く
第3章 電気とその治療パワー
第4章 色とオーラの治療力
第5章 サウンド・ヒーリング
第6章 周期
またしても「水」と「波動(振動)」「リズム(周期)」なんですね。
ちなみにルドルフ・シュタイナーにも「振動エネルギー機関」に関する記述があるそうです。
せいぜい私自身が言えることは
「この辺りに主流科学のアプローチが見逃している<何か>があるのではないか」
ということです。
中村雄二郎氏の「汎リズム論」までが岩波書店などで出せる範囲でしょう(それでもアカデミズムからの反発はかなりあるのではないかな?)
で、アカデミズムと直接関係ない私は、こういう話は「好き」ですが、疑問点を言えば、
「結局、白人中心主義・キリスト教の発想を超えてないんじゃないか?」
ということです(グノーシスをめぐる問題)。
近代神智学・人智学の宇宙論・根源人種論は、ニーチェの超人思想と同じく1つ間違えれば、ナチスなどの優生学と繋がりかねません。
紙一重です。
実証主義アプローチを重んじるアカデミズムからの反発は、結局、ここに由来する部分も大きいと思います。
「血液型と性格の相関性」の研究がなかなか進まないのも、優生学の問題が絡んでいるからでしょう。
こういう厄介な問題は、アニメで『機動戦士ガンダム』が表現しちゃってますね。
「ニュータイプ」とか「ジオニズム」「強化人間」「サイコガンダム」という用語で。
●「ケイシー療法」コミュ トピック
水の神秘な治療力
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38793838&comm_id=3972099
●『水の神秘 科学を超えた不思議な世界』ウェスト・マリン(河出書房新社 2006)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=514454
【内容】
もっとも謎めいて、根源的な物質「水」の本質とは何か?
水そのものの神秘と謎を、古代文明から神話、さらに現代科学などの様々な角度から検証。
水のすべてとその魅力がわかる究極の「水の大全」。
【著者略歴】
マリン,ウェスト
本名はDonn Louis Marrin。
アリゾナ大学で水資源学の博士号を、カリフォルニア大学で生物学と環境科学の学位を取得。
現在は、サンディエゴ州立大学の非常勤教授として水文学と生物地球化学を教え、さらにカリフォルニア大学サンディエゴ校でも環境化学などを中心に講義をしている。
そのほか、水に関わる広範なプロジェクトについて資源関係機関や環境グループと意見交換をするなど、さまざまなかたちで活躍している。
ハワイのカウアイ島在住。
【目次】
第1部 古代の知恵
(古代神話/神聖な混沌/現代のナチュラリズム)
第2部 水の科学
(水の起源/謎めいた分子/生命と水/ガイアの循環システム)
第3部 古代と現代の出会い
(波と渦の科学/生きている水を求めて/宇宙の仲介者)
●『水とセクシュアリティ』ミシェル・オダン(青土社 1995)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=133762
【内容】
「ヒトはなぜ水に魅かれるのだろう?」
生殖のプロセスのなかに、からだの特徴のなかに、免疫系、神経系、ホルモン系のしくみのなかに、痕跡を残す「かつて水中生活に適応していた」ことの証し。
水中出産のパイオニア、M・オダンが、忘れられたヒトと水との結びつきに科学の眼をむけ、環境と調和した未来の人間像を描きだす。
【目次】
1 水をもちいる出産
2 出産のプロセスを理解する
3 水の力
4 水のエロティシズム
5 タオの医学
6 水と宗教
7 ヒトとイルカ
8 水に棲まうヒト―ホモ・アクアティクス
9 狂ったヒト―ホモ・デメンス
10 「感情=本能」理論
11 叡知のヒト―ホモ・サピエンス
水の神秘な治療力
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38793838&comm_id=3972099
●『水の神秘 科学を超えた不思議な世界』ウェスト・マリン(河出書房新社 2006)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=514454
【内容】
もっとも謎めいて、根源的な物質「水」の本質とは何か?
水そのものの神秘と謎を、古代文明から神話、さらに現代科学などの様々な角度から検証。
水のすべてとその魅力がわかる究極の「水の大全」。
【著者略歴】
マリン,ウェスト
本名はDonn Louis Marrin。
アリゾナ大学で水資源学の博士号を、カリフォルニア大学で生物学と環境科学の学位を取得。
現在は、サンディエゴ州立大学の非常勤教授として水文学と生物地球化学を教え、さらにカリフォルニア大学サンディエゴ校でも環境化学などを中心に講義をしている。
そのほか、水に関わる広範なプロジェクトについて資源関係機関や環境グループと意見交換をするなど、さまざまなかたちで活躍している。
ハワイのカウアイ島在住。
【目次】
第1部 古代の知恵
(古代神話/神聖な混沌/現代のナチュラリズム)
第2部 水の科学
(水の起源/謎めいた分子/生命と水/ガイアの循環システム)
第3部 古代と現代の出会い
(波と渦の科学/生きている水を求めて/宇宙の仲介者)
●『水とセクシュアリティ』ミシェル・オダン(青土社 1995)
http://mixi.jp/view_item.pl?id=133762
【内容】
「ヒトはなぜ水に魅かれるのだろう?」
生殖のプロセスのなかに、からだの特徴のなかに、免疫系、神経系、ホルモン系のしくみのなかに、痕跡を残す「かつて水中生活に適応していた」ことの証し。
水中出産のパイオニア、M・オダンが、忘れられたヒトと水との結びつきに科学の眼をむけ、環境と調和した未来の人間像を描きだす。
【目次】
1 水をもちいる出産
2 出産のプロセスを理解する
3 水の力
4 水のエロティシズム
5 タオの医学
6 水と宗教
7 ヒトとイルカ
8 水に棲まうヒト―ホモ・アクアティクス
9 狂ったヒト―ホモ・デメンス
10 「感情=本能」理論
11 叡知のヒト―ホモ・サピエンス
ルドルフ・シュタイナーの人智学から、ヨハネの黙示録を読み解くと、666は、将来現れるソラトという悪魔の名だそうです。
ソラトは、シュタイナーの説く悪魔アーリマンのなかでも最も邪悪な悪霊だという。
ソラト、つまり邪悪なアーリマンは、地球を太陽系、及び宇宙体系から切り離し、自らの砦とするために、
人類を誘惑し、堕落させ、獣化し、奴隷化しようと目論んでいるという。
ソラトが地球にもたらした最も邪悪なものは、666年の周期で行われ、いままで、333年(666/2)と666年と1332年(666×2)にあったという。
333年には、キリスト教カトリックにおいて、アリウス派とアタナシオス派の論争が起こり、アタナシオス派が勝ち、それが元で、カトリックはローマ帝国のように権威化し、キリスト教は堕落の道を辿っていったという。
とくに、初期キリスト教において重要な教えである、
【キリストが太陽霊の使者である】という見解を見失ってしまったという。
666年には、ゴンデイシャプールにおいて、当時の哲学者を集め、学院を開き、人類に、時期尚早な太陽の叡智を3つ授けたという。
1つは、遺伝による優生学、
2つめは、精神による予防医学
3つめは【波動による律動学】だといわれている。
これらの世界中への伝播は、ムハンマドのイスラムの教えにより阻止されたが、キリスト教カトリックの堕落した教えの権威化により呼応して、唯物観として広まっていき、ロジャー・ベーコンを介して、西洋において、唯物的科学として誕生したという。
1332年には、聖堂騎士団の撲滅を行なったという。
聖堂騎士団は、テンプル騎士団として有名で、人類に聖杯の教えをもたらすものであったが、ソラトの「人類を太陽という霊性に向けさせないように、地球に閉じ込める企み」のために、巧妙に、唯物論により滅ぼされたという。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215565907
ソラトは、シュタイナーの説く悪魔アーリマンのなかでも最も邪悪な悪霊だという。
ソラト、つまり邪悪なアーリマンは、地球を太陽系、及び宇宙体系から切り離し、自らの砦とするために、
人類を誘惑し、堕落させ、獣化し、奴隷化しようと目論んでいるという。
ソラトが地球にもたらした最も邪悪なものは、666年の周期で行われ、いままで、333年(666/2)と666年と1332年(666×2)にあったという。
333年には、キリスト教カトリックにおいて、アリウス派とアタナシオス派の論争が起こり、アタナシオス派が勝ち、それが元で、カトリックはローマ帝国のように権威化し、キリスト教は堕落の道を辿っていったという。
とくに、初期キリスト教において重要な教えである、
【キリストが太陽霊の使者である】という見解を見失ってしまったという。
666年には、ゴンデイシャプールにおいて、当時の哲学者を集め、学院を開き、人類に、時期尚早な太陽の叡智を3つ授けたという。
1つは、遺伝による優生学、
2つめは、精神による予防医学
3つめは【波動による律動学】だといわれている。
これらの世界中への伝播は、ムハンマドのイスラムの教えにより阻止されたが、キリスト教カトリックの堕落した教えの権威化により呼応して、唯物観として広まっていき、ロジャー・ベーコンを介して、西洋において、唯物的科学として誕生したという。
1332年には、聖堂騎士団の撲滅を行なったという。
聖堂騎士団は、テンプル騎士団として有名で、人類に聖杯の教えをもたらすものであったが、ソラトの「人類を太陽という霊性に向けさせないように、地球に閉じ込める企み」のために、巧妙に、唯物論により滅ぼされたという。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215565907
●666は獣の数字か?
獣の数字は、『新約聖書』の『ヨハネの黙示録』に記述されている。
以下に引用すると、
「ここに知恵が必要である。思慮のある者は、獣の数字を解くがよい。その数字とは、人間をさすものである。そして、その数字は666である」(13章18節)
この数字の意味については、古来より様々に解釈されてきたが、今日の聖書学では、ローマ皇帝ネロを指すという説が最も支持を得ている。
即ち、皇帝ネロ(Nero Caesar)のギリシア語表記(Νέρων Καίσαρ, Nerōn Kaisar)をヘブライ文字に置き換え(נרון קסר, Nrwn Ksr)、これを数値化し(ゲマトリア)、その和が666になるというもの。
ヘブライ文字はギリシア文字のように、それぞれの文字が数値を持っており、これによって数記が可能である。
写本によっては、獣の数字は666でなく、616と記されているものもある。
この場合は、本来のラテン語式に「ネロン」ではなく「ネロ」(נרו קסר Nrw Ksr)と発音を正したものと解釈できる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8D%A3%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%97
これも原義は違ったのだけど、次第に拡大解釈されて「獣の数字」という俗信になってしまったのでしょう。
■キリスト教と仏教の666を考察する。
http://bloom.at.webry.info/200609/article_2.html
日本では、映画『オーメン』シリーズの影響が大きいのかもしれません。
ちなみに、666×3=1998年となり、これはエドガー・ケイシーの予言とも重なる年でしたが、「目に見える世界」では大きな出来事は別段無かったように思います。
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha801.html
http://roseandcross.kakurezato.com/page074.html
----------------------------------------------------------------
●エドガー・ケイシー
日本の海への没入(1958年から1998年の間に日本の大部分が沈没する」という予言が有名であり、ハラリエルという「警告」の天使が語った特殊な例とされる)といった予言の類は、外れているものも多い。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%BC
獣の数字は、『新約聖書』の『ヨハネの黙示録』に記述されている。
以下に引用すると、
「ここに知恵が必要である。思慮のある者は、獣の数字を解くがよい。その数字とは、人間をさすものである。そして、その数字は666である」(13章18節)
この数字の意味については、古来より様々に解釈されてきたが、今日の聖書学では、ローマ皇帝ネロを指すという説が最も支持を得ている。
即ち、皇帝ネロ(Nero Caesar)のギリシア語表記(Νέρων Καίσαρ, Nerōn Kaisar)をヘブライ文字に置き換え(נרון קסר, Nrwn Ksr)、これを数値化し(ゲマトリア)、その和が666になるというもの。
ヘブライ文字はギリシア文字のように、それぞれの文字が数値を持っており、これによって数記が可能である。
写本によっては、獣の数字は666でなく、616と記されているものもある。
この場合は、本来のラテン語式に「ネロン」ではなく「ネロ」(נרו קסר Nrw Ksr)と発音を正したものと解釈できる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8D%A3%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%97
これも原義は違ったのだけど、次第に拡大解釈されて「獣の数字」という俗信になってしまったのでしょう。
■キリスト教と仏教の666を考察する。
http://bloom.at.webry.info/200609/article_2.html
日本では、映画『オーメン』シリーズの影響が大きいのかもしれません。
ちなみに、666×3=1998年となり、これはエドガー・ケイシーの予言とも重なる年でしたが、「目に見える世界」では大きな出来事は別段無かったように思います。
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha801.html
http://roseandcross.kakurezato.com/page074.html
----------------------------------------------------------------
●エドガー・ケイシー
日本の海への没入(1958年から1998年の間に日本の大部分が沈没する」という予言が有名であり、ハラリエルという「警告」の天使が語った特殊な例とされる)といった予言の類は、外れているものも多い。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%BC
橋元淳一郎 『時空と生命 ― 物理学思考で読み解く主体と世界』(技術評論社 2009年) http://bit.ly/LXnb7x
【内容紹介】
私とは何か。時間とは、空間とは……。
これらは、古来、哲学者たちが何千年もの間考え続けてきた謎である。
近代科学の登場、そして19世紀から20世紀にかけての科学革命(進化論・相対論・量子論・分子生物学など)が、時間・空間・生命についてのわれわれの常識を覆した。
「『私』は時間と空間の中に生きている」という事実への問いは、そういった意味で、きわめて現代的なテーマとして浮かびあがってくる。
本書では、これらの謎に迫るべく、時間・空間・生命の関係を、物理学・生命科学・哲学の知見からときほぐしていく。
【目次】
第一章 ミンコフスキー時空を読む
1. 虚数iの発見
2. ミンコフスキー時空
3. ピタゴラスの定理と時空長
4. 時空長の計算
5. 縮退した時空
6. ヒッグス場と時空
7. 進行波と後退波
8. 非局所性の問題
9. 夢と時空
10. 非因果領域に隠れていく未来
第二章 主体的意思としての生命――動物について
1. 主観の科学的記述の困難さ
2. ツバメの歓喜
3. 進化の階層
4. 言語は主体的意思の担い手たりうるか
5. 自己意識の進化と大脳のモジュール群
6. 自己意識は主体的意思の担い手たりうるか
7. すべての動物は主体的意思を持つ
8. 快・不快を基準に行為する主体的意思
第三章 主体的意思としての生命――バクテリアについて
1. 生命の歴史的階層性
2. 五つの王国
3. 生命の代表としてのバクテリア
4. 自然選択と自由経済
5. プログラムされた死
6. 植物の主体的意思について
7. 主体的意思と快・不快
第四章 非平衡熱力学系と主体的意思
1. 熱力学
2. 平衡系とエントロピー増大の法則
3. オンサーガーの相反定理
4. 非平衡熱力学系
5. 生命は主体的意思を持つ非平衡熱力学系である
6. 生命誕生の困難さと必然性
7. 散逸構造・複雑系・オートポイエーシス
8. 複雑系システムから主体的意思へ
第五章 主体的生命原理と創造的宇宙
1. 有時――道元の悟り
2. グラディエント・ベクトルとしての主体的意思
3. ミンコフスキー時空の時間軸に沿った「動き」
4. 三すくみのジレンマ
5. 最小作用の原理と経路積分
6. 最大傾斜の原理
7. 主体的な生命原理と自由意思宇宙の創造
【著者インタビュー】
http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/100603.shtml
http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/100801.shtml
【内容紹介】
私とは何か。時間とは、空間とは……。
これらは、古来、哲学者たちが何千年もの間考え続けてきた謎である。
近代科学の登場、そして19世紀から20世紀にかけての科学革命(進化論・相対論・量子論・分子生物学など)が、時間・空間・生命についてのわれわれの常識を覆した。
「『私』は時間と空間の中に生きている」という事実への問いは、そういった意味で、きわめて現代的なテーマとして浮かびあがってくる。
本書では、これらの謎に迫るべく、時間・空間・生命の関係を、物理学・生命科学・哲学の知見からときほぐしていく。
【目次】
第一章 ミンコフスキー時空を読む
1. 虚数iの発見
2. ミンコフスキー時空
3. ピタゴラスの定理と時空長
4. 時空長の計算
5. 縮退した時空
6. ヒッグス場と時空
7. 進行波と後退波
8. 非局所性の問題
9. 夢と時空
10. 非因果領域に隠れていく未来
第二章 主体的意思としての生命――動物について
1. 主観の科学的記述の困難さ
2. ツバメの歓喜
3. 進化の階層
4. 言語は主体的意思の担い手たりうるか
5. 自己意識の進化と大脳のモジュール群
6. 自己意識は主体的意思の担い手たりうるか
7. すべての動物は主体的意思を持つ
8. 快・不快を基準に行為する主体的意思
第三章 主体的意思としての生命――バクテリアについて
1. 生命の歴史的階層性
2. 五つの王国
3. 生命の代表としてのバクテリア
4. 自然選択と自由経済
5. プログラムされた死
6. 植物の主体的意思について
7. 主体的意思と快・不快
第四章 非平衡熱力学系と主体的意思
1. 熱力学
2. 平衡系とエントロピー増大の法則
3. オンサーガーの相反定理
4. 非平衡熱力学系
5. 生命は主体的意思を持つ非平衡熱力学系である
6. 生命誕生の困難さと必然性
7. 散逸構造・複雑系・オートポイエーシス
8. 複雑系システムから主体的意思へ
第五章 主体的生命原理と創造的宇宙
1. 有時――道元の悟り
2. グラディエント・ベクトルとしての主体的意思
3. ミンコフスキー時空の時間軸に沿った「動き」
4. 三すくみのジレンマ
5. 最小作用の原理と経路積分
6. 最大傾斜の原理
7. 主体的な生命原理と自由意思宇宙の創造
【著者インタビュー】
http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/100603.shtml
http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/100801.shtml
リンクが切れているもので、復活できたものを載せておきます。
>>[7]
マックスの科学館
https://web.archive.org/web/20080210155018/http://home7.highway.ne.jp/max-1998/science.html
>>[19]
汚れとは何か
https://web.archive.org/web/20081210070345/http://www.teamrenzan.com/archives/writer/nagai/pollution.html
>>[32]
ケビン・ライヤーソン
https://web.archive.org/web/20010818150814/http://www.asahi-net.or.jp/~df7t-ymd/kr.html
>>[7]
マックスの科学館
https://web.archive.org/web/20080210155018/http://home7.highway.ne.jp/max-1998/science.html
>>[19]
汚れとは何か
https://web.archive.org/web/20081210070345/http://www.teamrenzan.com/archives/writer/nagai/pollution.html
>>[32]
ケビン・ライヤーソン
https://web.archive.org/web/20010818150814/http://www.asahi-net.or.jp/~df7t-ymd/kr.html
>>[33] >>[34] の、水に関する科学ニュースです。
東京大学 が水の特異性の起源を解明|大学ジャーナル オンライン 2018/04/03
http://univ-journal.jp/20095/
東京大学の田中肇教授らの研究グループは、さまざまな正四面体構造を形成する傾向を持つ液体の中で、水が極めて特異的である物理的な起源を解明するとともに、温度・圧力相図と特異性の関係を明らかにすることに成功した。
4℃で密度の最大を示し結晶化の際に体積が膨張するなど、他の液体にない極めて特異な性質を持つ水は、気象現象、地球物理現象、生命現象などに大きな影響を与える。
このような異常性は水に限らずシリコン、ゲルマニウム、炭素、シリカなど正四面体的な局所的な構造を形成する傾向を持つ液体に共通してみられる。
これらの液体は、水素結合、共有結合などの方向性の結合を持ち、それが局所的に正四面体的対称性を好むことがその起源であることは知られていた。
しかし、正四面体形成能や温度・圧力相図の形とこれらの液体の示す特異性との間の関係は不明であった。
研究グループは、正四面体構造を形成する傾向の強さを系統的に変えられるシミュレーションモデルを用いて、これらの関係の解明に初めて成功した。
まず、シミュレーションで得られたさまざまな特異性と同グループが以前提案した理論モデルの予測との比較により、これらの異常性のすべてが、局所的に安定な構造の形成に起因していることを明らかにした。
また、その比較をもとにこれらの特異性を支配している物理因子を特定し、水がこれらの液体の中で最も特異的(密度の異常性が最大など)である理由の物理的な起源を明らかにした。
今回の研究成果は、人類にとって最も重要な物質群の示す特異的な性質の系統的理解に大きく貢献するものと期待され、生命科学、地球科学など広範な分野に波及効果が期待される。
論文情報:【Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America】Water-like anomalies as a function of tetrahedrality
東京大学 が水の特異性の起源を解明|大学ジャーナル オンライン 2018/04/03
http://univ-journal.jp/20095/
東京大学の田中肇教授らの研究グループは、さまざまな正四面体構造を形成する傾向を持つ液体の中で、水が極めて特異的である物理的な起源を解明するとともに、温度・圧力相図と特異性の関係を明らかにすることに成功した。
4℃で密度の最大を示し結晶化の際に体積が膨張するなど、他の液体にない極めて特異な性質を持つ水は、気象現象、地球物理現象、生命現象などに大きな影響を与える。
このような異常性は水に限らずシリコン、ゲルマニウム、炭素、シリカなど正四面体的な局所的な構造を形成する傾向を持つ液体に共通してみられる。
これらの液体は、水素結合、共有結合などの方向性の結合を持ち、それが局所的に正四面体的対称性を好むことがその起源であることは知られていた。
しかし、正四面体形成能や温度・圧力相図の形とこれらの液体の示す特異性との間の関係は不明であった。
研究グループは、正四面体構造を形成する傾向の強さを系統的に変えられるシミュレーションモデルを用いて、これらの関係の解明に初めて成功した。
まず、シミュレーションで得られたさまざまな特異性と同グループが以前提案した理論モデルの予測との比較により、これらの異常性のすべてが、局所的に安定な構造の形成に起因していることを明らかにした。
また、その比較をもとにこれらの特異性を支配している物理因子を特定し、水がこれらの液体の中で最も特異的(密度の異常性が最大など)である理由の物理的な起源を明らかにした。
今回の研究成果は、人類にとって最も重要な物質群の示す特異的な性質の系統的理解に大きく貢献するものと期待され、生命科学、地球科学など広範な分野に波及効果が期待される。
論文情報:【Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America】Water-like anomalies as a function of tetrahedrality
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
栗本慎一郎 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート