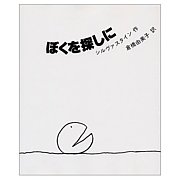本なんて読んだところで頭が良くなる訳でも心が豊かになる訳でもなく目が悪くなるばかりだから(当社調べ)、そんなことをするくらいならジョギングか内職でもやってたほうが体も懐も温かくなると思うのですが、私はどういう訳かそういうことはあまりしたくないので、ここで本の事を書かせてもらおうと思いました。
1.「ポスト・オフィス」 チャールズ・ブコウスキー著 坂口緑:訳
本作は1970年からおよそ15年間に及ぶ、ブコウスキーの郵便局員時代のことを書いた半自伝的な小説です。
ブコウスキーは1980年頃からサルトル、ジュネといった著名人から「アメリカで一番の詩人」 と言われ、徐々に文壇にその名を知らせてきました。しかし、その生活は華々しい、とは到底言えず、低賃金で過酷な郵便局の仕事、まったく折り合わない上司との軋轢、悪循環を招くだけと解っていながらも飲まずにいられない暴飲、彼女の死、等々に苦しめられ、文字通り血を吐くような暮らしをしていました。
実際、当時のアメリカでは郵便局員といえばろくでなしのする仕事の代表のようなものだったらしく、こういう人はブコウスキー以外にも沢山いたのだと思いますが、ブコウスキーは本作でその当時の出来事を、乱雑で、口唇的な文体で笑い飛ばすように、だけどどこかペシミスティックに綴っています。
と、ここまで書いたところで本作の説明は書くことがなくなりましたので、私の感想を言いますが、先述のように、本作は今風にいうと「底辺、負け組、ホワイトトラッシュ」 を書いた小説で、ある意味アメリカ版蟹工船と言えないこともないのですが(それは無理がある、と言う人もいらっしゃるでしょうが、今は無視します)、蟹工船が反社会的であったのに対して、本作は非社会的なところが私はとても共感出来ました。反と非、それらの違いは何かというと、ようするにやる気です。私は、この本を読んで、確実に勤労意欲が減退したのを感じるのと同時に、人間、生きてる内はなにかして食っていかねばらならないなぁ、と思い、仕事を辞めるのを止めました(結局辞めたけど)。
1.「ポスト・オフィス」 チャールズ・ブコウスキー著 坂口緑:訳
本作は1970年からおよそ15年間に及ぶ、ブコウスキーの郵便局員時代のことを書いた半自伝的な小説です。
ブコウスキーは1980年頃からサルトル、ジュネといった著名人から「アメリカで一番の詩人」 と言われ、徐々に文壇にその名を知らせてきました。しかし、その生活は華々しい、とは到底言えず、低賃金で過酷な郵便局の仕事、まったく折り合わない上司との軋轢、悪循環を招くだけと解っていながらも飲まずにいられない暴飲、彼女の死、等々に苦しめられ、文字通り血を吐くような暮らしをしていました。
実際、当時のアメリカでは郵便局員といえばろくでなしのする仕事の代表のようなものだったらしく、こういう人はブコウスキー以外にも沢山いたのだと思いますが、ブコウスキーは本作でその当時の出来事を、乱雑で、口唇的な文体で笑い飛ばすように、だけどどこかペシミスティックに綴っています。
と、ここまで書いたところで本作の説明は書くことがなくなりましたので、私の感想を言いますが、先述のように、本作は今風にいうと「底辺、負け組、ホワイトトラッシュ」 を書いた小説で、ある意味アメリカ版蟹工船と言えないこともないのですが(それは無理がある、と言う人もいらっしゃるでしょうが、今は無視します)、蟹工船が反社会的であったのに対して、本作は非社会的なところが私はとても共感出来ました。反と非、それらの違いは何かというと、ようするにやる気です。私は、この本を読んで、確実に勤労意欲が減退したのを感じるのと同時に、人間、生きてる内はなにかして食っていかねばらならないなぁ、と思い、仕事を辞めるのを止めました(結局辞めたけど)。
|
|
|
|
コメント(7)
2冊目。
『ノヴァ急報』 ウィリアム・S・バロウズ著 諏訪優:訳
80年代頃からロックミュージシャンやサブカルチャー好きの連中に持ち上げられたおかげで良い意味でも悪い意味でも有名になったバロウズが、65年頃に薬物中毒の治療直後書いた(違ったかも知れないが手元に資料がないから、取り敢えずそういうことにしておく)、長編小説です。
さて、バロウズの名を雑誌や中島らものエッセイなどで見たときに、次に見えてくるのは、重度の薬物依存、おかま、ワケのワカラン実験小説、ウィリアムテルごっこで嫁を撃ち殺した……と、まことに碌でもないことばかりで、90年代の中頃にその存在を知った私は「まったくとんでもない爺だ。これは読まんとイカンだろう」 と決意し、古本屋を探して廻ったのですがなかなか手に入りません。そのうちにどうでもよくなってしまって探さなかったので、結局、初めてバロウズを読んだのはそれから何年か後でした。
初めて読んだ感想はご多分に漏れず、良く解らない、というもので、余りにも解らないものですから読むのが辛くなって、本棚で日焼けさせていたのですが、ある時、「じゃあ何が解らないのかを考えながら読んでみよう」 と思い立ち、読んでみると(暇だったんだと思う)、難解なのは、誰だか解らない奴がいきなり出てきて地の文が一人称に変わったり、カットアップによる、文意が不明瞭なセンテンツが頻出するためだと解りました。しかし、それが解っても話のスジが良く解らないのは相変わらずで、ノヴァ(超新星)から、ウイルス、悪霊、謎の昆虫等々が地球にやってきて、人類を崩壊に導いている……と粗筋を知ってから読んでもやはり良くわかりませんでした。
こう言ってしまうとアレですが、『ノヴァ急報』の面白さは、私には良く解りません。しかし、何かがずば抜けている、ということに変わりはなく、それは初期のトリスタン・ツァラやルーセルと何か通底している面白さであり、そういうモノは、私がどうのこうの言っても仕方がないし、言いたくもないのでもうこの辺で止めようと思いますが(読みたい人だけ読めばいい類の本なので……)、カットアップについて少しだけ補足すると、バロウズが言うにはそれは「よそ見のようなもの」 これを聞いて私はなるほどと得心したのでした。だって、普通に生活していても、視界に入るものって繋がりのないモノが結構ありますからね。ワケが解らなくなるのも納得。
『ノヴァ急報』 ウィリアム・S・バロウズ著 諏訪優:訳
80年代頃からロックミュージシャンやサブカルチャー好きの連中に持ち上げられたおかげで良い意味でも悪い意味でも有名になったバロウズが、65年頃に薬物中毒の治療直後書いた(違ったかも知れないが手元に資料がないから、取り敢えずそういうことにしておく)、長編小説です。
さて、バロウズの名を雑誌や中島らものエッセイなどで見たときに、次に見えてくるのは、重度の薬物依存、おかま、ワケのワカラン実験小説、ウィリアムテルごっこで嫁を撃ち殺した……と、まことに碌でもないことばかりで、90年代の中頃にその存在を知った私は「まったくとんでもない爺だ。これは読まんとイカンだろう」 と決意し、古本屋を探して廻ったのですがなかなか手に入りません。そのうちにどうでもよくなってしまって探さなかったので、結局、初めてバロウズを読んだのはそれから何年か後でした。
初めて読んだ感想はご多分に漏れず、良く解らない、というもので、余りにも解らないものですから読むのが辛くなって、本棚で日焼けさせていたのですが、ある時、「じゃあ何が解らないのかを考えながら読んでみよう」 と思い立ち、読んでみると(暇だったんだと思う)、難解なのは、誰だか解らない奴がいきなり出てきて地の文が一人称に変わったり、カットアップによる、文意が不明瞭なセンテンツが頻出するためだと解りました。しかし、それが解っても話のスジが良く解らないのは相変わらずで、ノヴァ(超新星)から、ウイルス、悪霊、謎の昆虫等々が地球にやってきて、人類を崩壊に導いている……と粗筋を知ってから読んでもやはり良くわかりませんでした。
こう言ってしまうとアレですが、『ノヴァ急報』の面白さは、私には良く解りません。しかし、何かがずば抜けている、ということに変わりはなく、それは初期のトリスタン・ツァラやルーセルと何か通底している面白さであり、そういうモノは、私がどうのこうの言っても仕方がないし、言いたくもないのでもうこの辺で止めようと思いますが(読みたい人だけ読めばいい類の本なので……)、カットアップについて少しだけ補足すると、バロウズが言うにはそれは「よそ見のようなもの」 これを聞いて私はなるほどと得心したのでした。だって、普通に生活していても、視界に入るものって繋がりのないモノが結構ありますからね。ワケが解らなくなるのも納得。
3冊目。
あまり書くと暇人だと思われてしまうのが心配ですが、暇なので書きます。
『変愛小説集』 岸本佐知子 編訳
現代の外国人作家が書いた、奇想天外奇妙奇天烈な恋愛小説を10編収めた本作は、そのスジの人達(ヤクザではない) なら、一冊は持っているという特殊なエッセイストとしても知られる翻訳家の岸本佐知子さんが編訳をした短編集です。私は本作の執筆陣ではニコルソン・ベイカーしか知りませんでしたが、他の方もそれなりに売れてるようです。
世界は広いですね! そして、そんな広い世界に触れることが出来るなんて近代文明の勝利としか言いようがありませんね! 日本でよかった(滝本晃司)。
まあ、それは良いとして、私がこの短編集の中で一番好きだったのはレイ・ヴクサヴィッチという作家の「僕らが冥王星に着くころ」 という作品で、これは、体の皮膚が宇宙服に変質してしまうという流行病が蔓延している世界を舞台にしたお話です。
なんだギャグ小説か。馬鹿馬鹿しい。
という向きの方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなのは私に言わせれば想像力の欠如したリアリスト気取りの腐れ……なんでもありません。
とにかく、全部が全部というわけではありませんが、本書に収められた作品はどれも甘く切なく、ちょっとだけ文学的(なんだそれ……)で、それでいて小難しいことは書かれていないので、普段は本を読まない人でも、フツーの小説として読める素晴らしい本だと思います。現代海外文学の入門編としても良いかと……。
あまり書くと暇人だと思われてしまうのが心配ですが、暇なので書きます。
『変愛小説集』 岸本佐知子 編訳
現代の外国人作家が書いた、奇想天外奇妙奇天烈な恋愛小説を10編収めた本作は、そのスジの人達(ヤクザではない) なら、一冊は持っているという特殊なエッセイストとしても知られる翻訳家の岸本佐知子さんが編訳をした短編集です。私は本作の執筆陣ではニコルソン・ベイカーしか知りませんでしたが、他の方もそれなりに売れてるようです。
世界は広いですね! そして、そんな広い世界に触れることが出来るなんて近代文明の勝利としか言いようがありませんね! 日本でよかった(滝本晃司)。
まあ、それは良いとして、私がこの短編集の中で一番好きだったのはレイ・ヴクサヴィッチという作家の「僕らが冥王星に着くころ」 という作品で、これは、体の皮膚が宇宙服に変質してしまうという流行病が蔓延している世界を舞台にしたお話です。
なんだギャグ小説か。馬鹿馬鹿しい。
という向きの方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなのは私に言わせれば想像力の欠如したリアリスト気取りの腐れ……なんでもありません。
とにかく、全部が全部というわけではありませんが、本書に収められた作品はどれも甘く切なく、ちょっとだけ文学的(なんだそれ……)で、それでいて小難しいことは書かれていないので、普段は本を読まない人でも、フツーの小説として読める素晴らしい本だと思います。現代海外文学の入門編としても良いかと……。
3冊目。
『ショック! 残酷! 切株映画の世界』 高橋ヨシキ:編纂
タイトルで使われている「切株映画」 とは、主にスプラッター映画、スラッシャー映画のことで、映画の中で行われる人体破壊、腕がもげたり首がチョンパとぶっ飛んだりしてできた人体の断面を切り株に見立てたところから発生した造語です。高橋ヨシキ氏は本書で、1900年代前半の芸術家がよくやっていたのを模倣して切株派宣言という宣言を行っています。それはどのようなマニフェストか、引用するのもアレなので端折って言うと、「切株派とは、映画を観る喜びの半分くらいは、切株表現にあると信じる人の集まり」 です。
そういった悪趣味極まりない思想で編まれた本書は、要するに気持ちの悪い残酷シーンがある映画の紹介と解説、それから論考がメインという構成になっています。執筆陣の中では特に高橋ヨシキ氏が素晴らしく、怒りと皮肉に満ちた文章で現在のピントの狂った倫理観に則った表現規制を(シェイクスピアだのグランギニョルまでを援用して) 痛烈に批判しています。若干、こじつけの感があるものの、頷けるところも多く、面白いです。
『ショック! 残酷! 切株映画の世界』 高橋ヨシキ:編纂
タイトルで使われている「切株映画」 とは、主にスプラッター映画、スラッシャー映画のことで、映画の中で行われる人体破壊、腕がもげたり首がチョンパとぶっ飛んだりしてできた人体の断面を切り株に見立てたところから発生した造語です。高橋ヨシキ氏は本書で、1900年代前半の芸術家がよくやっていたのを模倣して切株派宣言という宣言を行っています。それはどのようなマニフェストか、引用するのもアレなので端折って言うと、「切株派とは、映画を観る喜びの半分くらいは、切株表現にあると信じる人の集まり」 です。
そういった悪趣味極まりない思想で編まれた本書は、要するに気持ちの悪い残酷シーンがある映画の紹介と解説、それから論考がメインという構成になっています。執筆陣の中では特に高橋ヨシキ氏が素晴らしく、怒りと皮肉に満ちた文章で現在のピントの狂った倫理観に則った表現規制を(シェイクスピアだのグランギニョルまでを援用して) 痛烈に批判しています。若干、こじつけの感があるものの、頷けるところも多く、面白いです。
4冊目。
『ロクス・ソルス』 レーモン・ルーセル著 岡谷 公二:訳
レーモン・ルーセルが遺した二つの小説(なんかも一冊くらいあった気がするけど……)の内の一つ。
その内容は奇妙奇天烈もいいとこで、マッドな博士が造った、「なんでそんなの造るんだよっ」 といしかいいようのない奇抜かつ無意味な発明品(毛のない猫が泳ぐ水槽とか) の数々を招待客に見せ、それにどのようなカラクリが使われているかを博士が詳細に語っていくスタイルで話が進んでいきます。しかし、あまりにも説明が詳細なせいで、読んでいると面倒臭くなってくるのですが、そんなことをしては本書の魅力を堪能できないので我慢して読み進めていくと、その仕掛けの背後にある制作エピソードが激烈に面白いことが判明し、読み終わってからも日常生活でよく見る普段ならどうでもイイものの影に、楽しげなエピソードが隠されているような気がして三ヶ月に一度はお気に入りのシーンを拾い読みしたりしてしまうほどに影響されてしまいます。個人的にはアフリカの印象よりこっちのが好き。暇な時にしか読む気がしないのが唯一難点でしょうか。
『ロクス・ソルス』 レーモン・ルーセル著 岡谷 公二:訳
レーモン・ルーセルが遺した二つの小説(なんかも一冊くらいあった気がするけど……)の内の一つ。
その内容は奇妙奇天烈もいいとこで、マッドな博士が造った、「なんでそんなの造るんだよっ」 といしかいいようのない奇抜かつ無意味な発明品(毛のない猫が泳ぐ水槽とか) の数々を招待客に見せ、それにどのようなカラクリが使われているかを博士が詳細に語っていくスタイルで話が進んでいきます。しかし、あまりにも説明が詳細なせいで、読んでいると面倒臭くなってくるのですが、そんなことをしては本書の魅力を堪能できないので我慢して読み進めていくと、その仕掛けの背後にある制作エピソードが激烈に面白いことが判明し、読み終わってからも日常生活でよく見る普段ならどうでもイイものの影に、楽しげなエピソードが隠されているような気がして三ヶ月に一度はお気に入りのシーンを拾い読みしたりしてしまうほどに影響されてしまいます。個人的にはアフリカの印象よりこっちのが好き。暇な時にしか読む気がしないのが唯一難点でしょうか。
5冊目。
もう疲れてきた。このペースではとても30万冊なんて紹介できない……しかし暇なのでもう少し書いてみようと思います。
『空のオルゴール』 中島らも著
ロベール・ウーダンという奇術師を調査しにフランスに飛んだ大学生が、現地の奇術師と暗殺集団の血で血を洗うような抗争に巻き込まれる……という粗筋の本作は、晩年の中島らもが遺した長編小説。
本作は、抗鬱剤の副作用で著者の視力が低下した為に、著者と原稿の間に、著者の奥さんを挟んだ口述筆記で書かれています。そのせいか、文体もそれまでとはかなり違っていて、一見しただけだと平坦で軽い印象があります。内容も破綻スレスレで、主人公達は暗殺者に狙われているというのにしょっちゅう酒盛りをやったり、愚にもつかない下らない馬鹿話をしたりするばかりで、中島らもの作品を愛読してきた私も、最初は本作があまり好きになれず、「ああ、中島らもはアルコールと薬物で以前の才能を失ってしまったのだ」 と残念に思っていたのですが、しかしなんとなく味のある本作をたまに思い出してはパラパラと拾い読みしていました。そして、そうする内にふつふつと疑問が湧いてきました。
それは、これって激烈に面白いのではないか、という疑問です。
よく読むと文章の端正さは失われていないし、ストーリーも壊れていない(ロジカルな意味でも)。決してキチッとした、お手本になるような小説ではありませんが、だからこそゴミ屑のように死んでいく(メイン人物の10人中、6人が死ぬ)登場人物達が生き生きとして人間らしく見えるし、そして悲しさもぐっと前に出てくる。まるでふざけてるかのような軽い文体だからこそ、どうしようもないほど悲しいというのは、まったく体験したことのない読書経験でした。小説が物語である前に言語表現であるという事を考えると、これほどまでに優れた小説というのもなかなかないのではないでしょうか。
もう疲れてきた。このペースではとても30万冊なんて紹介できない……しかし暇なのでもう少し書いてみようと思います。
『空のオルゴール』 中島らも著
ロベール・ウーダンという奇術師を調査しにフランスに飛んだ大学生が、現地の奇術師と暗殺集団の血で血を洗うような抗争に巻き込まれる……という粗筋の本作は、晩年の中島らもが遺した長編小説。
本作は、抗鬱剤の副作用で著者の視力が低下した為に、著者と原稿の間に、著者の奥さんを挟んだ口述筆記で書かれています。そのせいか、文体もそれまでとはかなり違っていて、一見しただけだと平坦で軽い印象があります。内容も破綻スレスレで、主人公達は暗殺者に狙われているというのにしょっちゅう酒盛りをやったり、愚にもつかない下らない馬鹿話をしたりするばかりで、中島らもの作品を愛読してきた私も、最初は本作があまり好きになれず、「ああ、中島らもはアルコールと薬物で以前の才能を失ってしまったのだ」 と残念に思っていたのですが、しかしなんとなく味のある本作をたまに思い出してはパラパラと拾い読みしていました。そして、そうする内にふつふつと疑問が湧いてきました。
それは、これって激烈に面白いのではないか、という疑問です。
よく読むと文章の端正さは失われていないし、ストーリーも壊れていない(ロジカルな意味でも)。決してキチッとした、お手本になるような小説ではありませんが、だからこそゴミ屑のように死んでいく(メイン人物の10人中、6人が死ぬ)登場人物達が生き生きとして人間らしく見えるし、そして悲しさもぐっと前に出てくる。まるでふざけてるかのような軽い文体だからこそ、どうしようもないほど悲しいというのは、まったく体験したことのない読書経験でした。小説が物語である前に言語表現であるという事を考えると、これほどまでに優れた小説というのもなかなかないのではないでしょうか。
一つも反響のないままに書いていると、だんだんと虚しくなってくるのは当然ですが、まだ別に虚しくならないので
6冊目。
「たのしいムーミン一家」 ヤンソン:著 山村静:訳
ムーミンといえば、カバのようなルックスの可愛らしい妖精が谷をあっちに行ったりこっちに行ったりして、友達のスナフキンやスニフと一緒に冒険を繰り広げるのですが、よくよく考えてみると、そんなものを読んで何が面白いのか、カバがちょろちょろしたり、ニートがしたり顔でハーモニカ吹いてたりするだけで、別に面白くないんじゃないかと思ってしまいがちですが、そんなことはなく、すこぶる面白いのです。
なぜなら人生において、家族と過ごしたり、彼女と喧嘩したり、近所をウロウロしたり、ハーモニカを吹いたりすること以外に別にやることがないということが本書を読んでいるうちに解るからです。いちいち反論の仕様のない、身も蓋もない哲学を持つスナフキン、現金で俗物極まりないスナフ、常に何かに熱中していないと鬱状態に陥るヘムレン、何もかもをありのままに受け入れるムーミンママ、それらの人物をよくよく見てみると、普段我々が固執しているものはすべて無意味だと気付かされるのです。本書の際立って素晴らしい点はまさにそこで、どういう事かというと、ムーミン達の寿命等は明かされていませんが、祖先がいたということを仄めかす箇所もあることから不死の存在ではないことは明らかで、彼らもいずれはどこかへ還るのですが、それが解っていても何もしません。これは仏教でいう会者定離、生者必滅、色即是空、空即是色、を体現しているということで、まったくもって空虚な戯言に過ぎないのですが、しかし、これ以上に真理に迫った童話もなかなかなく、そういった空虚な生活を大事にすることが人間には何より大切なんだよと、そういうことなのではないでしょうが、ないでしょうか。
6冊目。
「たのしいムーミン一家」 ヤンソン:著 山村静:訳
ムーミンといえば、カバのようなルックスの可愛らしい妖精が谷をあっちに行ったりこっちに行ったりして、友達のスナフキンやスニフと一緒に冒険を繰り広げるのですが、よくよく考えてみると、そんなものを読んで何が面白いのか、カバがちょろちょろしたり、ニートがしたり顔でハーモニカ吹いてたりするだけで、別に面白くないんじゃないかと思ってしまいがちですが、そんなことはなく、すこぶる面白いのです。
なぜなら人生において、家族と過ごしたり、彼女と喧嘩したり、近所をウロウロしたり、ハーモニカを吹いたりすること以外に別にやることがないということが本書を読んでいるうちに解るからです。いちいち反論の仕様のない、身も蓋もない哲学を持つスナフキン、現金で俗物極まりないスナフ、常に何かに熱中していないと鬱状態に陥るヘムレン、何もかもをありのままに受け入れるムーミンママ、それらの人物をよくよく見てみると、普段我々が固執しているものはすべて無意味だと気付かされるのです。本書の際立って素晴らしい点はまさにそこで、どういう事かというと、ムーミン達の寿命等は明かされていませんが、祖先がいたということを仄めかす箇所もあることから不死の存在ではないことは明らかで、彼らもいずれはどこかへ還るのですが、それが解っていても何もしません。これは仏教でいう会者定離、生者必滅、色即是空、空即是色、を体現しているということで、まったくもって空虚な戯言に過ぎないのですが、しかし、これ以上に真理に迫った童話もなかなかなく、そういった空虚な生活を大事にすることが人間には何より大切なんだよと、そういうことなのではないでしょうが、ないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
わたしの選ぶ30冊 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
わたしの選ぶ30冊のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75479人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6435人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208285人