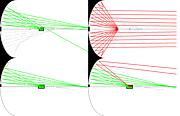と、偉そうなことをぶち上げてみましたが、スペクトル非連続な放電灯である、HIDというランプは従来の白熱電球などとはぜんぜん違う仕組みで発光してるので、色温度表記はあんまりアテにならないので、そこらへんの理論や仕組みについて理解を深めましょうというトピです。
以前からしつこく言っていましたが、放電灯では光が連続していないので、スペクトルグラフを載せるべきと主張しているのですが、これを載せてしまうとダメな球はダメダメさがはっきり露見してしまうせいか、どこもほとんど掲載していません。また、見る人が見ると企業秘密がわかったりしてしまう場合もあります。
このスペクトルという概念について解説していきたいと思います。
まず知っておいて欲しいのが、HIDは太陽光線やハロゲン電球のように満遍なく光が出ているわけではないと言う点。
満遍なく光が出ている場合は、たとえば青色のフィルターなり着色ガラスを通せばなだらかに赤方向の光を抑えて、カラーバランスが青に偏った連続な光を得ることができます。
こういう場合だと、青い光はシャープでクールだとか、普通のハロゲンと比べると赤みが押さえられて見やすいとかの評価になる場合もありますが、この考えをHIDにそのまま当てはめると非常に危険です。
HIDはハロゲン化金属の励起発光の原理を利用して光らせるので、特定の色しか出ません。
だいたいベースになる水銀の出す色プラス4つか5つのピークしかありません。
なので、簡単に覚えておくには、紫に近い青、水色、純緑、黄緑、黄色、赤あたりの単色が組み合わさって出てきて光っていると理解してください。
なので、光のピークは自然の光線やハロゲンと違ってギザギザでガタガタで変に鋭いグラフになります。
本来色温度表記は、スペクトル連続な光源に対して、色の傾向を評価する指針として存在するものなので、スペクトルが連続していない場合は正しい値が出てきません。傾向として換算するとだいたいこれぐらいの色温度だよと言う目安でしかないのです。
また、色温度表記で表すことができるのは、白色のみです。黄色やピンクや紫などの明らかに白ではなく色が付いた光色は白色ではなく「色」です。もちろん、色が付いた光源でも測定器にかければ何らかの色温度の数値は出てきます。真っ赤とかまっ黄色でも数値は出てきますが、それを色温度幾つとか呼ぶのはナンセンスです。
数値が色を表しているわけではないので、色温度が低いのは黄色と言う認識も販売する側が植え込んだ誤った認識です。あれはあくまでも黄色です。
数値の座標で色を表す方法もあります。おむすびのような形をしたCIEの色度図表と言うものがあり、座標で色を表すことができます。この表では白は左下から右上になだらかに曲がったカーブの座標の上にしか存在できません。それ以外は白ではなくて「色」ということになります。色温度が高くなると青っぽく見えてきますが、青色ではありません。快晴の空の色のような色の傾向になります。色温度が低いほうは黄色ではなく、アンバーというオレンジがかった方向に変化していきます。ローソクの色温度がだいたい2400Kぐらいです。あれは黄色ではないですね。
長くなったので、今回はこれぐらいで。後日に続きます。
以前からしつこく言っていましたが、放電灯では光が連続していないので、スペクトルグラフを載せるべきと主張しているのですが、これを載せてしまうとダメな球はダメダメさがはっきり露見してしまうせいか、どこもほとんど掲載していません。また、見る人が見ると企業秘密がわかったりしてしまう場合もあります。
このスペクトルという概念について解説していきたいと思います。
まず知っておいて欲しいのが、HIDは太陽光線やハロゲン電球のように満遍なく光が出ているわけではないと言う点。
満遍なく光が出ている場合は、たとえば青色のフィルターなり着色ガラスを通せばなだらかに赤方向の光を抑えて、カラーバランスが青に偏った連続な光を得ることができます。
こういう場合だと、青い光はシャープでクールだとか、普通のハロゲンと比べると赤みが押さえられて見やすいとかの評価になる場合もありますが、この考えをHIDにそのまま当てはめると非常に危険です。
HIDはハロゲン化金属の励起発光の原理を利用して光らせるので、特定の色しか出ません。
だいたいベースになる水銀の出す色プラス4つか5つのピークしかありません。
なので、簡単に覚えておくには、紫に近い青、水色、純緑、黄緑、黄色、赤あたりの単色が組み合わさって出てきて光っていると理解してください。
なので、光のピークは自然の光線やハロゲンと違ってギザギザでガタガタで変に鋭いグラフになります。
本来色温度表記は、スペクトル連続な光源に対して、色の傾向を評価する指針として存在するものなので、スペクトルが連続していない場合は正しい値が出てきません。傾向として換算するとだいたいこれぐらいの色温度だよと言う目安でしかないのです。
また、色温度表記で表すことができるのは、白色のみです。黄色やピンクや紫などの明らかに白ではなく色が付いた光色は白色ではなく「色」です。もちろん、色が付いた光源でも測定器にかければ何らかの色温度の数値は出てきます。真っ赤とかまっ黄色でも数値は出てきますが、それを色温度幾つとか呼ぶのはナンセンスです。
数値が色を表しているわけではないので、色温度が低いのは黄色と言う認識も販売する側が植え込んだ誤った認識です。あれはあくまでも黄色です。
数値の座標で色を表す方法もあります。おむすびのような形をしたCIEの色度図表と言うものがあり、座標で色を表すことができます。この表では白は左下から右上になだらかに曲がったカーブの座標の上にしか存在できません。それ以外は白ではなくて「色」ということになります。色温度が高くなると青っぽく見えてきますが、青色ではありません。快晴の空の色のような色の傾向になります。色温度が低いほうは黄色ではなく、アンバーというオレンジがかった方向に変化していきます。ローソクの色温度がだいたい2400Kぐらいです。あれは黄色ではないですね。
長くなったので、今回はこれぐらいで。後日に続きます。
|
|
|
|
コメント(24)
読んでいてなんとなくスペクトルのグラフの読み方がわかりました。
一枚目の写真の下半分のグラフがそうですよね?
これでゆうところの左のヤツと右のDL50なるモノが比べられてるワケですよね。
ドイツの技術屋のサイトを持ってこさせていただきました。
http://www.nuconverter.de/spectraldatapage.html
これでいえば、上から10個めのハロゲンと思われるグラフはスペクトルが連続していると捕らえていいのでしょうか?
なんか馬力表みたいに右肩上がりですね。
見比べると全く違いますね。発光という同じ仕事をしているとは思えないです。
こうなってくると有名メーカーから中華までいろんなのを持ってきて試したいですね。
もし営業妨害だというのなら情報提供不足だと逆に言いたいです。
一枚目の写真の下半分のグラフがそうですよね?
これでゆうところの左のヤツと右のDL50なるモノが比べられてるワケですよね。
ドイツの技術屋のサイトを持ってこさせていただきました。
http://www.nuconverter.de/spectraldatapage.html
これでいえば、上から10個めのハロゲンと思われるグラフはスペクトルが連続していると捕らえていいのでしょうか?
なんか馬力表みたいに右肩上がりですね。
見比べると全く違いますね。発光という同じ仕事をしているとは思えないです。
こうなってくると有名メーカーから中華までいろんなのを持ってきて試したいですね。
もし営業妨害だというのなら情報提供不足だと逆に言いたいです。
政 さん
10番目のはまさしくハロゲンH1のスペクトル曲線ですね。これが色温度表記3200Kのグラフです。でも今売ってる黄色いHIDで3200Kと言うのがあってもこれとは似ても似つかないグラフになりますので、色温度表記はHIDでは役に立たないと思ったほうがいいかもしれません。
右肩上がりなのは、青色がほとんど出ていなくて熱ばかり盛大に出ていると言うことです。だいたい700nm以上は人間にとっては見えなくて熱として感じる赤外線領域です。
だからハロゲンバルブは熱いんですね。逆にHIDではそこら辺がまったく出ていません。
11番目の白色LEDも不思議な分布ですよね。人によっては色が薄いとかなんか色が足らないと感じるかもしれません。
青いガラスのハロゲンはただでさえ出ていない青だけを透過させるために、盛大に出ている赤方向を一生懸命カットしているので当然暗くなります。
10番目のはまさしくハロゲンH1のスペクトル曲線ですね。これが色温度表記3200Kのグラフです。でも今売ってる黄色いHIDで3200Kと言うのがあってもこれとは似ても似つかないグラフになりますので、色温度表記はHIDでは役に立たないと思ったほうがいいかもしれません。
右肩上がりなのは、青色がほとんど出ていなくて熱ばかり盛大に出ていると言うことです。だいたい700nm以上は人間にとっては見えなくて熱として感じる赤外線領域です。
だからハロゲンバルブは熱いんですね。逆にHIDではそこら辺がまったく出ていません。
11番目の白色LEDも不思議な分布ですよね。人によっては色が薄いとかなんか色が足らないと感じるかもしれません。
青いガラスのハロゲンはただでさえ出ていない青だけを透過させるために、盛大に出ている赤方向を一生懸命カットしているので当然暗くなります。
トピ主さんやコメントされたみなさんのお話を読んで思ったのですが。
(以下拙い理解と重複ばかりで恐縮ですが。)
・色温度はスペクトル連続である光について傾向を表すもの
・HIDはそもそもスペクトル連続でない(複数の"特定色を放つ物質"をいっぺんに光らせる-->結果として白色に近い(時には黄や青みがかった)光を放つもの)
・よってHIDについて色温度表記は適切でない
スペクトルグラフについては何となくわかるような"気がします"が、CIEの色度図表は(この場以外の)他の資料を見てもピンときませんでした。(苦笑
CIE色度図表の上で白色が曲線で表現されるという点だけはやはり"何となく"わかるような気はしますけれども。
さて、作り手(売り手)にとってスペクトルグラフは公開したくないもの・・・となると、買い手は光の色合い(?)に関しては正確な製品仕様を"机上の資料として"入手することは現実的に無理がある、ということですね。
もっとも色温度に振り回されるのは、こう言っては何ですが自動車照明には疑問符がつくような極端な色合いを求める人であるようにも思いますが。
しかし、HIDの仕組みからすれば自動車照明に自然な色合い(何か変な表現ですよね(汗)の製品であっても色温度表記は必ずしもアテにならないわけで、となると何を基準に購入すれば良いものやらと。(苦笑
実際に購入を検討する製品が点灯している実例を見るか、作り手を信頼して購入する以外なさそうですね。
元より信用できない作り手の製品を購入する気など(個人的には)毛頭無いのですが。
HIDに限らず、自動車用品の類では信用ならないモノが山ほどあるので困ります。有名大手用品メーカーまでもが公取に排除命令をくらうようでは、一体どこを信用しろというのかと。(苦笑
駄文にて失礼しました。
(以下拙い理解と重複ばかりで恐縮ですが。)
・色温度はスペクトル連続である光について傾向を表すもの
・HIDはそもそもスペクトル連続でない(複数の"特定色を放つ物質"をいっぺんに光らせる-->結果として白色に近い(時には黄や青みがかった)光を放つもの)
・よってHIDについて色温度表記は適切でない
スペクトルグラフについては何となくわかるような"気がします"が、CIEの色度図表は(この場以外の)他の資料を見てもピンときませんでした。(苦笑
CIE色度図表の上で白色が曲線で表現されるという点だけはやはり"何となく"わかるような気はしますけれども。
さて、作り手(売り手)にとってスペクトルグラフは公開したくないもの・・・となると、買い手は光の色合い(?)に関しては正確な製品仕様を"机上の資料として"入手することは現実的に無理がある、ということですね。
もっとも色温度に振り回されるのは、こう言っては何ですが自動車照明には疑問符がつくような極端な色合いを求める人であるようにも思いますが。
しかし、HIDの仕組みからすれば自動車照明に自然な色合い(何か変な表現ですよね(汗)の製品であっても色温度表記は必ずしもアテにならないわけで、となると何を基準に購入すれば良いものやらと。(苦笑
実際に購入を検討する製品が点灯している実例を見るか、作り手を信頼して購入する以外なさそうですね。
元より信用できない作り手の製品を購入する気など(個人的には)毛頭無いのですが。
HIDに限らず、自動車用品の類では信用ならないモノが山ほどあるので困ります。有名大手用品メーカーまでもが公取に排除命令をくらうようでは、一体どこを信用しろというのかと。(苦笑
駄文にて失礼しました。
とりす さん
私の難解な文章を解りやすくまとめていただきましてありがとうございます。要約するとまさしくそんな感じですね。
車は物理現象で動いているはずですが、まことしやかなウソや、中途半端な知識がセールストークになっていてまんまと騙されてしまったり、騙されるところまでいかなくても勘違いしていたりわかった気分になって満足してしまうような事象はたくさんありますよね。オイルの話とかアーシングとかコンデンサチューンとか。
さて、続きを書きますといっていてなかなか進まず申し訳ないところですが、私が以前身につけた知識を整理して、忘れかかっていた点などをもう一度勉強しなおしていたりしますので、ちょっと間違っている点などもあると思いますが、そういう場合は容赦なく突っ込みを入れていただければ幸いです。
光や色の世界は学問としては体系的に理論がしっかり確立していますが、人間の視覚の特性を考慮するとなかなか理解が難しくなってくるように思います。また、光源としての色の評価と、染色などの光が反射して色を出す物の評価は基本理論は一緒ですが、また違った判断基準が必要なので、インターネット上にたくさんある参考になる資料や文献は、そのまま車のHID光源を考察する資料になるものは意外と少ないように感じました。
色温度については、理想黒体に熱をかけたときに発光する色味と言うことで、太陽光線やハロゲン電球のように熱で発光する連続スペクトルにしか本来は当てはまりませんが、便利な判断基準なのでよく使われているわけですね。スペクトル非連続のものはほんとは「相関色温度」と呼ぶべきかもしれません。
スペクトル非連続と言う光源は金属を励起すると鋭いピーク波長を持った光を出すと言う便利な特性を放電灯という技術を確立したときに実用になりました。非常に効率がいいですが、普段太陽光線のなかで生活している人間の視覚特性には自然に感じるわけがない人工的で偏った光なわけです。典型的なのはナトリウムランプですかね。
金属励起発光の物理的特性もいろいろ研究解明されてきたのと合わせて、人間の視覚特性も感覚から、数式ような計算式として定量化する研究も進んで現在ではほぼ理論で説明が付くレベルになりました。
私の難解な文章を解りやすくまとめていただきましてありがとうございます。要約するとまさしくそんな感じですね。
車は物理現象で動いているはずですが、まことしやかなウソや、中途半端な知識がセールストークになっていてまんまと騙されてしまったり、騙されるところまでいかなくても勘違いしていたりわかった気分になって満足してしまうような事象はたくさんありますよね。オイルの話とかアーシングとかコンデンサチューンとか。
さて、続きを書きますといっていてなかなか進まず申し訳ないところですが、私が以前身につけた知識を整理して、忘れかかっていた点などをもう一度勉強しなおしていたりしますので、ちょっと間違っている点などもあると思いますが、そういう場合は容赦なく突っ込みを入れていただければ幸いです。
光や色の世界は学問としては体系的に理論がしっかり確立していますが、人間の視覚の特性を考慮するとなかなか理解が難しくなってくるように思います。また、光源としての色の評価と、染色などの光が反射して色を出す物の評価は基本理論は一緒ですが、また違った判断基準が必要なので、インターネット上にたくさんある参考になる資料や文献は、そのまま車のHID光源を考察する資料になるものは意外と少ないように感じました。
色温度については、理想黒体に熱をかけたときに発光する色味と言うことで、太陽光線やハロゲン電球のように熱で発光する連続スペクトルにしか本来は当てはまりませんが、便利な判断基準なのでよく使われているわけですね。スペクトル非連続のものはほんとは「相関色温度」と呼ぶべきかもしれません。
スペクトル非連続と言う光源は金属を励起すると鋭いピーク波長を持った光を出すと言う便利な特性を放電灯という技術を確立したときに実用になりました。非常に効率がいいですが、普段太陽光線のなかで生活している人間の視覚特性には自然に感じるわけがない人工的で偏った光なわけです。典型的なのはナトリウムランプですかね。
金属励起発光の物理的特性もいろいろ研究解明されてきたのと合わせて、人間の視覚特性も感覚から、数式ような計算式として定量化する研究も進んで現在ではほぼ理論で説明が付くレベルになりました。
放電灯も約50年の歴史があり、まだまだ進化していますが、程よく枯れた安定した技術となっています。車用HIDは車で使うと言う特性を考えて、過酷な条件でも使えるように特化された仕様になっています。ので、性能的には究極ではなく、大雑把に言ってしまえば悪条件に強くするために多少性能を犠牲にしているところもあり、Philipsの球の特性を例にとって見ると見事としか言いようがない特性になっています。いまだとこれをもっと低コストで実現するとか、環境対策のために水銀を使わないでも同等の特性を実現するとか、そういうのはありますが、約20年前の技術でデビューしてから変更なしで現在でも通用していると言うのはすごいものです。多分これ以上劇的に向上することもないでしょう。
HIDは小型のものを作るのが難しく、35Wなんていう小さいものがほんとに実用レベルになるのか?とその昔は言われていたのですが、小型放電ランプの技術では進んでいたPhilipsがいち早く製品の実用化にこぎつけました。他社の管球メーカーでも大型のものは優秀なものはたくさんありますが、その技術で車用を作ることは非常に難しいのです。
車で要求されるHIDの要件としては、厳しい温度特性。マイナス20度の場所でも確実に点灯しないといけません。次にホットリスタート時の再点灯特性。昔体育館の水銀灯を一度消してからすぐつけると15分ぐらい点かなかったなんていう記憶がある人もいるかもしれませんがそれでは話にならないと言うことです。さらに耐振動性と点灯可能角度の特性。これはガラス管の保持で地味ながらいろいろな研究成果が詰まっていて、有名どころでは各社特許を取っていたりします。ここらへんはあちらのトピのおぎすけさんが詳しいかと思います。バラストのほうも、貧弱で電圧変動が激しい車の12Vで如何に安定して点灯させるかというのが課題です。
そして最後に演色性と色温度の問題。20年前の技術でも色温度は6500kでも8000kでも作ることはもちろん可能でしたが、CIEの研究成果をもとにいろいろなポイントが議論されてあの4300k付近と言う色温度と演色性が決まったと聞きます。
私が以前研究職として聞いた話では、ハロゲン電球の置き換えとなるものなので、やたら高い色温度は違和感を感じたり、他車のランプの色に違和感を覚えたり運転に支障が出ること。車の貧弱な電源で、ハロゲンの置き換えとして必要以上に明るさを出せるが、35Wという小型な球の光束では高い色温度は暗く感じること(クルーゾフ効果)、現在の都市の夜間は演色性が高い性能がいい街路灯がたくさんありますから、暗く感じることも少なくなりましたが、夜間の街路灯の色温度は一昔前はもっと低いものだったので色が違いすぎると疲労が増えることなどがあげられていました。そう考えると、現在の明るい都市部なら6500Kでもいいかもしれませんね。
では、また続きます。
HIDは小型のものを作るのが難しく、35Wなんていう小さいものがほんとに実用レベルになるのか?とその昔は言われていたのですが、小型放電ランプの技術では進んでいたPhilipsがいち早く製品の実用化にこぎつけました。他社の管球メーカーでも大型のものは優秀なものはたくさんありますが、その技術で車用を作ることは非常に難しいのです。
車で要求されるHIDの要件としては、厳しい温度特性。マイナス20度の場所でも確実に点灯しないといけません。次にホットリスタート時の再点灯特性。昔体育館の水銀灯を一度消してからすぐつけると15分ぐらい点かなかったなんていう記憶がある人もいるかもしれませんがそれでは話にならないと言うことです。さらに耐振動性と点灯可能角度の特性。これはガラス管の保持で地味ながらいろいろな研究成果が詰まっていて、有名どころでは各社特許を取っていたりします。ここらへんはあちらのトピのおぎすけさんが詳しいかと思います。バラストのほうも、貧弱で電圧変動が激しい車の12Vで如何に安定して点灯させるかというのが課題です。
そして最後に演色性と色温度の問題。20年前の技術でも色温度は6500kでも8000kでも作ることはもちろん可能でしたが、CIEの研究成果をもとにいろいろなポイントが議論されてあの4300k付近と言う色温度と演色性が決まったと聞きます。
私が以前研究職として聞いた話では、ハロゲン電球の置き換えとなるものなので、やたら高い色温度は違和感を感じたり、他車のランプの色に違和感を覚えたり運転に支障が出ること。車の貧弱な電源で、ハロゲンの置き換えとして必要以上に明るさを出せるが、35Wという小型な球の光束では高い色温度は暗く感じること(クルーゾフ効果)、現在の都市の夜間は演色性が高い性能がいい街路灯がたくさんありますから、暗く感じることも少なくなりましたが、夜間の街路灯の色温度は一昔前はもっと低いものだったので色が違いすぎると疲労が増えることなどがあげられていました。そう考えると、現在の明るい都市部なら6500Kでもいいかもしれませんね。
では、また続きます。
色についての続きです。左の図は欠落したスペクトルがない商業施設用の優秀な6500kのHIDの例。右はこれから説明する人の目の特性グラフ。黒の点線が白黒状態で明るさを感じる部分の特性。3枚目は例のドイツのバラスト屋さんから引用した白色LEDのスペクトルグラフ
満遍なく色が出てない光源はイカサマくさいとさんざん書いてきましたが、実は人間の目の特性は3種類の色と明るさレベルしか認識できないんです。3色しか認識できなくて、どうやってたくさんあるいろんな色を判断できるの?という理論はシンプルなのですが、理解するのがなかなか難しいかもしれません。
人間の目は420nmをピークとして両袖が比較的狭い範囲の青色を認識する部分と、両袖の範囲が比較的広い534nmをピークとする緑を認識する山と、グラフ表記した場合、それがそのまま右にずれた564nmをピークとする赤を認識する部分の3色を刺激の強さとして脳に伝えます。脳はこの3つのデータの強弱と明るさのデータを照合して見ているものの色として認識するわけです。
このとき例えば青の認識特性について考えてみると、一番感度が高いピーク波長は420mnですが、それより波長が低い紫外線に近い深い青紫のような色も、ピークより波長が長い水色のような青も、脳にいくデータは何種類もあるわけではなく、強弱だけで一種類なんですね。波長が低くても高くても感度が変わるだけで青紫も水色もまったく判断できていなくて、青成分の強さだけ感じることになります。
水色の場合、その上の緑成分を感じる部分がオーバーラップするような特性になっているので弱い青の刺激と弱い緑の刺激が同時に入ってくると水色と認識できるわけです。そして青紫から水色までの刺激の総量を積分した値が青の刺激は一種類として脳にいくわけです。
同様に緑と赤でもそのように刺激の強さで色を認識しますが、人類の進化の歴史上、もともと緑と赤は別々に認識できなかったのが進化して赤も認識できるように進化したという歴史があるため、赤の認識は緑の認識とオーバーラップしている部分が多いという特性があり、このため人間の目はある特定の色域で簡単に騙されることがあります。
例えば黄色がそうなんですが、緑の認識のピークと赤の認識のピークのオーバーラップしている中間が550nmあたりのオレンジがかった黄色なのですが、本物の黄色が入ってくる場合、緑の刺激と赤の刺激が同じく大きく入ってきた状態だと脳が黄色だと認識するのですが、ピークが鋭い純緑と純赤を同時に出す光源を見ると刺激が同じになるため、簡単に騙されて黄色に見えちゃいます。緑色のLEDと赤色のLEDが一緒に光るとオレンジに見えるのはそのためです。逆に現在主流の白色高輝度LEDは青と黄色の2色で人間の特性を利用してごまかして緑と赤もあるように見せかけてトータルで白く見えるようにするというなかなか巧みなことをやっています。HIDもそれに近いです。
と、まあ難しい理屈はいろいろあるんですが、人間の目は3色の刺激でしか色を判断できないということを覚えてください。なので、スペクトルアナライザが分析して出すグラフは人間がどうやったって判断して書いたり出来ないものなのです。どちらかというとパソコンのRGBの値で色を出すのと同じような感じでしか認識できてません。
じゃあ、複雑な色とか、連続したスペクトルなんて見えないんだから必要ないじゃん。と思ったアナタ、実はそのとおりなんですよ。条件付で。
次はそこら辺を説明していきます。
満遍なく色が出てない光源はイカサマくさいとさんざん書いてきましたが、実は人間の目の特性は3種類の色と明るさレベルしか認識できないんです。3色しか認識できなくて、どうやってたくさんあるいろんな色を判断できるの?という理論はシンプルなのですが、理解するのがなかなか難しいかもしれません。
人間の目は420nmをピークとして両袖が比較的狭い範囲の青色を認識する部分と、両袖の範囲が比較的広い534nmをピークとする緑を認識する山と、グラフ表記した場合、それがそのまま右にずれた564nmをピークとする赤を認識する部分の3色を刺激の強さとして脳に伝えます。脳はこの3つのデータの強弱と明るさのデータを照合して見ているものの色として認識するわけです。
このとき例えば青の認識特性について考えてみると、一番感度が高いピーク波長は420mnですが、それより波長が低い紫外線に近い深い青紫のような色も、ピークより波長が長い水色のような青も、脳にいくデータは何種類もあるわけではなく、強弱だけで一種類なんですね。波長が低くても高くても感度が変わるだけで青紫も水色もまったく判断できていなくて、青成分の強さだけ感じることになります。
水色の場合、その上の緑成分を感じる部分がオーバーラップするような特性になっているので弱い青の刺激と弱い緑の刺激が同時に入ってくると水色と認識できるわけです。そして青紫から水色までの刺激の総量を積分した値が青の刺激は一種類として脳にいくわけです。
同様に緑と赤でもそのように刺激の強さで色を認識しますが、人類の進化の歴史上、もともと緑と赤は別々に認識できなかったのが進化して赤も認識できるように進化したという歴史があるため、赤の認識は緑の認識とオーバーラップしている部分が多いという特性があり、このため人間の目はある特定の色域で簡単に騙されることがあります。
例えば黄色がそうなんですが、緑の認識のピークと赤の認識のピークのオーバーラップしている中間が550nmあたりのオレンジがかった黄色なのですが、本物の黄色が入ってくる場合、緑の刺激と赤の刺激が同じく大きく入ってきた状態だと脳が黄色だと認識するのですが、ピークが鋭い純緑と純赤を同時に出す光源を見ると刺激が同じになるため、簡単に騙されて黄色に見えちゃいます。緑色のLEDと赤色のLEDが一緒に光るとオレンジに見えるのはそのためです。逆に現在主流の白色高輝度LEDは青と黄色の2色で人間の特性を利用してごまかして緑と赤もあるように見せかけてトータルで白く見えるようにするというなかなか巧みなことをやっています。HIDもそれに近いです。
と、まあ難しい理屈はいろいろあるんですが、人間の目は3色の刺激でしか色を判断できないということを覚えてください。なので、スペクトルアナライザが分析して出すグラフは人間がどうやったって判断して書いたり出来ないものなのです。どちらかというとパソコンのRGBの値で色を出すのと同じような感じでしか認識できてません。
じゃあ、複雑な色とか、連続したスペクトルなんて見えないんだから必要ないじゃん。と思ったアナタ、実はそのとおりなんですよ。条件付で。
次はそこら辺を説明していきます。
複雑な色とか連続したスペクトルなんてなくてもいいという場合が条件付で存在します。
先ほど説明した人間の色認識特性のRGBそれぞれの山の一番高いところだけビシッと出てさえいれば、むしろその方が綺麗に見える条件。それは光源を直視する場合です。でもHID点灯中に裸眼でマジマジと覗き込んだりしないですよね。こういう条件の場合、目はRGBでしか判断できていないですから、人間の最大感度に近いところできつい波長のピークさえあればいいわけです。3つのピークのバランスを微妙に変えれば紫白だろうとピンクだろうと黄色だろうと、人の目で見た場合という条件においては自在に出すことが出来るわけです。ちょっと紫入っているならフォトレタッチソフトでR214 G214 B255とかそんなイメージです。
また、この条件というのはテレビやモニターディスプレイを見ているときがまさしくそうです。図はCRTディスプレイの蛍光体の発光特性のグラフですが、人間の目の特性に合わせた発光特性になるようになっています。Rがなめらかではなくガタガタですが、なかなか理想的な蛍光体材料がないため仕方ないところですが、これでも液晶モニタより特性がいいです。最近バックライトがLEDの液晶モニタが出てきましたが、ピークが鋭く色がにごらないので色の表現できる範囲が広くなります。
これが光源を直視する場合の目の特性です。
なので、カー用品屋さんで展示してある点灯可能な状態のHIDの見本を目を細めて直視して色を確認すると、結構いい色に見えたり、違いがわからなかったりしますし、RGBのデータとして写真を記録するデジカメでHID光源を直接撮影するしてモニタ上で見てみると、カラーバランスは別として結構綺麗な色に見えちゃったりします。だから写真でこんな色だよとアップしてくれる親切な人がいて、念のためにお店のサンプルを点灯させてきちんと目で確認したのに、車に装着してみるとなんか色が違うという悩みを抱える場合がある人もいるんじゃないかと思います。これは演色性Raが大きく関係してきます。
とりあえず、デジカメやモニターは人間の3色しか認識できないという特性に合わせてうまく特性をあわせて3つの色だけでさまざまな色があるように見せる技術で、HIDで照射した光はモニタ画面上や直視したときの色になるわけではない場合があるというのを覚えてください。
もうちょっと続きます
先ほど説明した人間の色認識特性のRGBそれぞれの山の一番高いところだけビシッと出てさえいれば、むしろその方が綺麗に見える条件。それは光源を直視する場合です。でもHID点灯中に裸眼でマジマジと覗き込んだりしないですよね。こういう条件の場合、目はRGBでしか判断できていないですから、人間の最大感度に近いところできつい波長のピークさえあればいいわけです。3つのピークのバランスを微妙に変えれば紫白だろうとピンクだろうと黄色だろうと、人の目で見た場合という条件においては自在に出すことが出来るわけです。ちょっと紫入っているならフォトレタッチソフトでR214 G214 B255とかそんなイメージです。
また、この条件というのはテレビやモニターディスプレイを見ているときがまさしくそうです。図はCRTディスプレイの蛍光体の発光特性のグラフですが、人間の目の特性に合わせた発光特性になるようになっています。Rがなめらかではなくガタガタですが、なかなか理想的な蛍光体材料がないため仕方ないところですが、これでも液晶モニタより特性がいいです。最近バックライトがLEDの液晶モニタが出てきましたが、ピークが鋭く色がにごらないので色の表現できる範囲が広くなります。
これが光源を直視する場合の目の特性です。
なので、カー用品屋さんで展示してある点灯可能な状態のHIDの見本を目を細めて直視して色を確認すると、結構いい色に見えたり、違いがわからなかったりしますし、RGBのデータとして写真を記録するデジカメでHID光源を直接撮影するしてモニタ上で見てみると、カラーバランスは別として結構綺麗な色に見えちゃったりします。だから写真でこんな色だよとアップしてくれる親切な人がいて、念のためにお店のサンプルを点灯させてきちんと目で確認したのに、車に装着してみるとなんか色が違うという悩みを抱える場合がある人もいるんじゃないかと思います。これは演色性Raが大きく関係してきます。
とりあえず、デジカメやモニターは人間の3色しか認識できないという特性に合わせてうまく特性をあわせて3つの色だけでさまざまな色があるように見せる技術で、HIDで照射した光はモニタ画面上や直視したときの色になるわけではない場合があるというのを覚えてください。
もうちょっと続きます
さて、車用HIDとは一見全然関係ない色の話をひたすら進めてきましたが、特別な興味がなければすべて覚える必要もないと思います。
理解しておいたほうがいいことを箇条書きにしてみると、
・HIDは放電ランプなので、スペクトルは連続していないのでガタガタギザギザである。
・なので、色温度表記で表すには不適当な部分が多いが、解り易いように相対色温度表記で表している。
・車用HIDは小型で苛酷な環境で使えるようにするため、あえて光の質は妥協してある。
・人間の目は3色の色しか認識できないので、強さのバランスを脳内で分析して色として認識している。
・そのため非常に多彩な色彩を認識できる反面、簡単に騙されたり錯覚するポイントがある。
・現在の蛍光灯や放電ランプやLEDはこの人間の目の特性を巧みに利用したものになっている
・光源を直視する場合、CRTや液晶モニタなどの自ら発光する表示装置を見る場合、3色あれば十分
と、こんな感じです。
私も理屈では解っていたのですが、仕事用車のライトがH3cのプロジェクターライトなので中華製HIDを装着しているのですが、どうも直視するとそれほど悪い色ではないんだけど、照射した光を見ると明らかに光が薄い、色が足らない感じが顕著に出るのです。
あまり乗らないんですが趣味車の旧車のほうはシビエの丸型ガラスレンズにD-H4Rなので、それと比べると中華性H3cはひどいものです。でも、発光しているところをデジカメでとっても両方そんなに変わらないんですね。で、考えてみると、片方はスペクトルが満遍なく出ていて、中華製はきついピークはあるけど、どうも欠損しているスペクトル領域がいくつかあるというようだという結論になったのです。
車のライトは運転席に座ってそこから見えるものを照らすわけで、見ているのは光源そのものではなく、光源が照らして反射してきたものを見ているわけです。このとき光源のスペクトルで欠損して光っていない領域があるとすると、光っていないわけですからその部分は反射した色が帰ってこないということになります。例えば赤い光がぜんぜん出ていない光源では、赤いものに照射しても光が返ってきませんから、黒とかグレーにしか見えません。最近は少なくなりましたが、高速道路のトンネルでナトリウムランプだけのところでは、カラフルな車の色が無彩色のグレーに見えたりなんていう例もそうですね。
これが如何に忠実に照射した光の色がきちんと返ってくるかという演色性という概念でRaいくつとあらわします。
理解しておいたほうがいいことを箇条書きにしてみると、
・HIDは放電ランプなので、スペクトルは連続していないのでガタガタギザギザである。
・なので、色温度表記で表すには不適当な部分が多いが、解り易いように相対色温度表記で表している。
・車用HIDは小型で苛酷な環境で使えるようにするため、あえて光の質は妥協してある。
・人間の目は3色の色しか認識できないので、強さのバランスを脳内で分析して色として認識している。
・そのため非常に多彩な色彩を認識できる反面、簡単に騙されたり錯覚するポイントがある。
・現在の蛍光灯や放電ランプやLEDはこの人間の目の特性を巧みに利用したものになっている
・光源を直視する場合、CRTや液晶モニタなどの自ら発光する表示装置を見る場合、3色あれば十分
と、こんな感じです。
私も理屈では解っていたのですが、仕事用車のライトがH3cのプロジェクターライトなので中華製HIDを装着しているのですが、どうも直視するとそれほど悪い色ではないんだけど、照射した光を見ると明らかに光が薄い、色が足らない感じが顕著に出るのです。
あまり乗らないんですが趣味車の旧車のほうはシビエの丸型ガラスレンズにD-H4Rなので、それと比べると中華性H3cはひどいものです。でも、発光しているところをデジカメでとっても両方そんなに変わらないんですね。で、考えてみると、片方はスペクトルが満遍なく出ていて、中華製はきついピークはあるけど、どうも欠損しているスペクトル領域がいくつかあるというようだという結論になったのです。
車のライトは運転席に座ってそこから見えるものを照らすわけで、見ているのは光源そのものではなく、光源が照らして反射してきたものを見ているわけです。このとき光源のスペクトルで欠損して光っていない領域があるとすると、光っていないわけですからその部分は反射した色が帰ってこないということになります。例えば赤い光がぜんぜん出ていない光源では、赤いものに照射しても光が返ってきませんから、黒とかグレーにしか見えません。最近は少なくなりましたが、高速道路のトンネルでナトリウムランプだけのところでは、カラフルな車の色が無彩色のグレーに見えたりなんていう例もそうですね。
これが如何に忠実に照射した光の色がきちんと返ってくるかという演色性という概念でRaいくつとあらわします。
ということで、お店のサンプルを直接見たとか、デジカメで撮影した光源を液晶モニターで見た場合、なかなかいい色に見えて、これはよさそうと思って購入してみると、思ったほど青くなかったとか、上品な紫が出ないとか、たくさん書き込みがある内容になってしまうのではないかという結論が自分のなかででました。たぶん、その状態でも、その車を外から見た場合には結構いい色でライトが光っているように見えていることでしょう。でも、照射光を見るとダメダメだと。
演色性Raは太陽光線やハロゲンランプの場合、スペクトルが連続していますから限りなく100に近い状態です。違和感を感じない程度の演色性の目安は使用するジャンルや環境によりますが、60以上あればまあ悪くない程度。80あれば普通は不満は出ないかなという感じです。過酷な条件で使用する車用HIDの場合、点灯性能重視なので標準的なPhilipsのMPXLで70弱ぐらいです。
演色性を測定する場合、JISで定められた色見本試料8種類に照射して色ずれを数値化して算出します。ただ、この8色は非常になんともいえない微妙な色で、逆に言うと、安物HIDでは結構しっかりした色を返してくる感じの色なので、それなりの演色性を出しているのかもしれません。印刷の世界なんかですと、この8色ではシビアな判断をするには足らないので、R9-R15という9番目から15番目までの特殊演色評価色を追加して判断します。この中には赤青緑の原色や、微妙な肌色という色が含まれるので、こちらのほうで判断したほうが自然で現実的な色の評価が出来ますが、こっちの基準を使ってしまうと家庭用蛍光灯などでもボロクソの評価が露見してしまうので、微妙な8色だけ測定して、その条件で好成績を出して公表している感じがあります。
で、この色評価色シートを使わなくても、スペクトルのグラフがあればどこは出ていてどこが出ていないかというのが一目瞭然なので、ぜひ載せるべきだと私は主張している次第です。
技術力がある管球メーカーはしっかり公表していますが、車用だったら載せたくないところの方が多いような気がします。載せたら私のようなウルサイのからツッコミが入るでしょうし(笑
で、バーナーを買おうと思って実物を点灯させて直接確認できる場合は、この演色評価色票を持っていって照射して確認すれば確実です。このときリファンレンスは昼間の屋外で太陽光線で見たときの色にしましょう。あれがだいたい6500Kから6700KぐらいでRa100の色です。その状態の色と比較して見え方がどの色がくすんで出にくくなるかによって傾向がわかります。紫っぽいのが好きな人は紫色がくすんで落ちないバーナーを探せばいいし、青いのがいい場合は青で、抜けるような白がいい場合は全色のバランスが良いものを選ぶと良いでしょう。ただし、点灯しているバーナーを直視しても人間の目やデジカメではまったく同じに見えたりしますので、反射した試料で判断しましょう。
また、演色評価色票はプリンタで出したものだと正確ではないので、可能なら本物を手にいれたほうがいいでしょう。画材屋さんとかで買えたと思います。プリンタで出したものは目安にはなりますが、これで断言するのは危険です。
光源から照射した光を演色評価色表に当てたものをデジカメで撮影したものはある程度判断するのに十分通用すると思いますので、Web上で判断する場合はそのような判断基準を使うのも有効な方法かもしれません。
次以降、やっと色温度の話に入ります。毎度長くてすみません。
演色性Raは太陽光線やハロゲンランプの場合、スペクトルが連続していますから限りなく100に近い状態です。違和感を感じない程度の演色性の目安は使用するジャンルや環境によりますが、60以上あればまあ悪くない程度。80あれば普通は不満は出ないかなという感じです。過酷な条件で使用する車用HIDの場合、点灯性能重視なので標準的なPhilipsのMPXLで70弱ぐらいです。
演色性を測定する場合、JISで定められた色見本試料8種類に照射して色ずれを数値化して算出します。ただ、この8色は非常になんともいえない微妙な色で、逆に言うと、安物HIDでは結構しっかりした色を返してくる感じの色なので、それなりの演色性を出しているのかもしれません。印刷の世界なんかですと、この8色ではシビアな判断をするには足らないので、R9-R15という9番目から15番目までの特殊演色評価色を追加して判断します。この中には赤青緑の原色や、微妙な肌色という色が含まれるので、こちらのほうで判断したほうが自然で現実的な色の評価が出来ますが、こっちの基準を使ってしまうと家庭用蛍光灯などでもボロクソの評価が露見してしまうので、微妙な8色だけ測定して、その条件で好成績を出して公表している感じがあります。
で、この色評価色シートを使わなくても、スペクトルのグラフがあればどこは出ていてどこが出ていないかというのが一目瞭然なので、ぜひ載せるべきだと私は主張している次第です。
技術力がある管球メーカーはしっかり公表していますが、車用だったら載せたくないところの方が多いような気がします。載せたら私のようなウルサイのからツッコミが入るでしょうし(笑
で、バーナーを買おうと思って実物を点灯させて直接確認できる場合は、この演色評価色票を持っていって照射して確認すれば確実です。このときリファンレンスは昼間の屋外で太陽光線で見たときの色にしましょう。あれがだいたい6500Kから6700KぐらいでRa100の色です。その状態の色と比較して見え方がどの色がくすんで出にくくなるかによって傾向がわかります。紫っぽいのが好きな人は紫色がくすんで落ちないバーナーを探せばいいし、青いのがいい場合は青で、抜けるような白がいい場合は全色のバランスが良いものを選ぶと良いでしょう。ただし、点灯しているバーナーを直視しても人間の目やデジカメではまったく同じに見えたりしますので、反射した試料で判断しましょう。
また、演色評価色票はプリンタで出したものだと正確ではないので、可能なら本物を手にいれたほうがいいでしょう。画材屋さんとかで買えたと思います。プリンタで出したものは目安にはなりますが、これで断言するのは危険です。
光源から照射した光を演色評価色表に当てたものをデジカメで撮影したものはある程度判断するのに十分通用すると思いますので、Web上で判断する場合はそのような判断基準を使うのも有効な方法かもしれません。
次以降、やっと色温度の話に入ります。毎度長くてすみません。
>政 さん
さすが車関係のお仕事をしていらっしゃるだけあって、鋭いですねw
仕事車はMC11ワゴンRです。ただし、RRではなくRX-T(右後ろにドアがない初期型の売れなかったタイプ)に熱に強いRR後期型プロ目を移植したものです。
金属リフレクタに魚眼レンズなのでUVの劣化は無視できてる感じですね。中華製バーナーはフィラメント位置がずれていて、カットラインが赤ボケになる(長い)のがちょっと気に入らないんですが。中華製自称55W、実際40Wちょっとのバラストです。
趣味車は旧型のほうのFIAT500です。CIBIEの丸型4灯タイプのガラスレンズで、こいつはグレアキャップがないんですが、ガラスレンズのおかげで強烈なグレアは出ていませんです。気力と時間があったら135φの丸に収まるバイキセノンを移植改造とか、Valeo(CIBIE)のSCモジュラー100mmを入れたいかなとか考えていますが、今の状態でも悪くないのでそのままになっちゃってます。
丸目はアウトビアンキのA112とかも好きですね。ほのぼの系が好きなのかも。
バラストは日産純正流用のValeoの薄型です。ヤフオクでもValeoは知名度が低いせいか、運がいいと2個で3000円程度で買えます。ので、PhilipsかOSRAM新品取りはずし品とセットにしても1万円で十分おつりが来ますね。
FIAT500は発電量が貧弱なので、とにかく無難に性能がよさそうなバラストでと選んでますので35Wタイプです。でもこっちのほうがワゴンRのプロ目より明るい気がします。
いらっしゃいませ。トピのほうに書いたほうがいい話題でしたね、すみません。
さすが車関係のお仕事をしていらっしゃるだけあって、鋭いですねw
仕事車はMC11ワゴンRです。ただし、RRではなくRX-T(右後ろにドアがない初期型の売れなかったタイプ)に熱に強いRR後期型プロ目を移植したものです。
金属リフレクタに魚眼レンズなのでUVの劣化は無視できてる感じですね。中華製バーナーはフィラメント位置がずれていて、カットラインが赤ボケになる(長い)のがちょっと気に入らないんですが。中華製自称55W、実際40Wちょっとのバラストです。
趣味車は旧型のほうのFIAT500です。CIBIEの丸型4灯タイプのガラスレンズで、こいつはグレアキャップがないんですが、ガラスレンズのおかげで強烈なグレアは出ていませんです。気力と時間があったら135φの丸に収まるバイキセノンを移植改造とか、Valeo(CIBIE)のSCモジュラー100mmを入れたいかなとか考えていますが、今の状態でも悪くないのでそのままになっちゃってます。
丸目はアウトビアンキのA112とかも好きですね。ほのぼの系が好きなのかも。
バラストは日産純正流用のValeoの薄型です。ヤフオクでもValeoは知名度が低いせいか、運がいいと2個で3000円程度で買えます。ので、PhilipsかOSRAM新品取りはずし品とセットにしても1万円で十分おつりが来ますね。
FIAT500は発電量が貧弱なので、とにかく無難に性能がよさそうなバラストでと選んでますので35Wタイプです。でもこっちのほうがワゴンRのプロ目より明るい気がします。
いらっしゃいませ。トピのほうに書いたほうがいい話題でしたね、すみません。
FIAT500だったんですね。
完全にヨミ違いでした。
ちなみに新型をこないだ見かけたんですが、
ノーマルはハロゲンと思われる灯体の中に単純にHIDをぶち込んでありまして、
何一つ遮光をしていないのでまぁこれが眩しいこと・・・
ハロゲンなら問題ないんでしょうが、HIDにするならこれは考えてほしいと思います。
トヨタやダイハツでよく見かけますが、
「トップグレードやオプションではHIDを採用しているが、?前期?廉価版?非オプション、などの理由でハロゲンを採用している車」が顕著な例です。
現行のFIAT500もこれだと思われます。
ハロゲンはH7でHIDはD2SやD2Rというヤツです。
アレにポン付けHIDが私は生まれつき勘弁してほしい症候群です。
自分がハイビームで走っているという実感はないもんなんでしょうか。
完全にヨミ違いでした。
ちなみに新型をこないだ見かけたんですが、
ノーマルはハロゲンと思われる灯体の中に単純にHIDをぶち込んでありまして、
何一つ遮光をしていないのでまぁこれが眩しいこと・・・
ハロゲンなら問題ないんでしょうが、HIDにするならこれは考えてほしいと思います。
トヨタやダイハツでよく見かけますが、
「トップグレードやオプションではHIDを採用しているが、?前期?廉価版?非オプション、などの理由でハロゲンを採用している車」が顕著な例です。
現行のFIAT500もこれだと思われます。
ハロゲンはH7でHIDはD2SやD2Rというヤツです。
アレにポン付けHIDが私は生まれつき勘弁してほしい症候群です。
自分がハイビームで走っているという実感はないもんなんでしょうか。
>政 さん
CIBIEにはグレアキャップが付いていないのですが、もともと付いていたキャレロは3点支持のキャップが付いています。まだハロゲンでなく、遮光がまったくできていないタングステン時代のランプユニットだからでしょうね。
ほんとはグレアキャップつきの小糸の丸型ランプユニットのほうがいいんでしょうけど、CIBIEのほうが配光が綺麗なんですよ。そのうち小糸のグレアキャップを移植してみます。
で、新型FIAT500はあまり興味なかったんで、てっきりプロジェクターランプだと思っていたのですが、そんな凶悪なランプだったのですか。日本に輸出されているのは日本特別仕様らしく、変に内装とか高級で値段も高いらしいので、ライトはヨーロッパ仕様と違うやっつけ左側通行仕様なのかもしれませんね。
ヨーロッパではグレアに対しては政さん以上に怒りに執念を燃やす国民性の国が多く、ドイツが一番過激にうるさいようです。下手するとテメエ眩しいんだよ!と暴力沙汰になりかねないぐらいらしいです。向こうでは不要な光を漏らしたり撒き散らすのを光害(こうがい)と呼んでいますから。逆に中国の北京あたりの夜の道路の光景はすごいのかもしれません。日本のDQNも真っ青なのかもという気がする(笑
ハロゲンむき出しランプユニットは、コストダウンとマルチリフレクターと、デザインの流れが昔のようなライトではなくなってきたのが原因かもしれませんね。
ボンネットの中に平べったく横長に収められるデザインから、ボンネットの横車の両端に縦長配置になって来てますからね。あと、消費者側がキラキラしたのが見えるライトを求めた結果こんなになっちゃったんじゃないかと言う意見もあります。だからそういうのが好きな層が好んで購入する普及価格帯の車に多いと。高級車は落ち着いたイメージが要求されるので、結構地味でランプユニットの性能もいいですよね。
CIBIEにはグレアキャップが付いていないのですが、もともと付いていたキャレロは3点支持のキャップが付いています。まだハロゲンでなく、遮光がまったくできていないタングステン時代のランプユニットだからでしょうね。
ほんとはグレアキャップつきの小糸の丸型ランプユニットのほうがいいんでしょうけど、CIBIEのほうが配光が綺麗なんですよ。そのうち小糸のグレアキャップを移植してみます。
で、新型FIAT500はあまり興味なかったんで、てっきりプロジェクターランプだと思っていたのですが、そんな凶悪なランプだったのですか。日本に輸出されているのは日本特別仕様らしく、変に内装とか高級で値段も高いらしいので、ライトはヨーロッパ仕様と違うやっつけ左側通行仕様なのかもしれませんね。
ヨーロッパではグレアに対しては政さん以上に怒りに執念を燃やす国民性の国が多く、ドイツが一番過激にうるさいようです。下手するとテメエ眩しいんだよ!と暴力沙汰になりかねないぐらいらしいです。向こうでは不要な光を漏らしたり撒き散らすのを光害(こうがい)と呼んでいますから。逆に中国の北京あたりの夜の道路の光景はすごいのかもしれません。日本のDQNも真っ青なのかもという気がする(笑
ハロゲンむき出しランプユニットは、コストダウンとマルチリフレクターと、デザインの流れが昔のようなライトではなくなってきたのが原因かもしれませんね。
ボンネットの中に平べったく横長に収められるデザインから、ボンネットの横車の両端に縦長配置になって来てますからね。あと、消費者側がキラキラしたのが見えるライトを求めた結果こんなになっちゃったんじゃないかと言う意見もあります。だからそういうのが好きな層が好んで購入する普及価格帯の車に多いと。高級車は落ち着いたイメージが要求されるので、結構地味でランプユニットの性能もいいですよね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
HID! HID! HID! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-