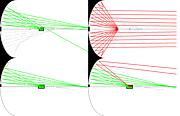|
|
|
|
コメント(34)
あ、質問トピできたんですね。
ここ質問トピないからどこで質問するんかな〜、わかんないからどこで質問したらいいんか質問トピで聞こうかな〜って思ったら質問トピがないな〜って思(以下ry
自作自演ソーリーです。
私が今まで組んできたHIDは、電源本体はトヨタ純正、ベロフ、コイトと様々なんですが、バーナーは頑なにフィリップスかオスラムのいわゆる純正バーナーばかりなんです。
ですがよく思うのはバーナーが同じタイプなのに灯色がバラストによって結構違ってて、白っぽいこともあればハロゲン臭いこともあるし。明るさはそんなに違わないです。
バラストによる色の違いって、もしあることとすれば何が原因なんでしょう?
或いは目の錯覚や気分の問題ですかね?
ここ質問トピないからどこで質問するんかな〜、わかんないからどこで質問したらいいんか質問トピで聞こうかな〜って思ったら質問トピがないな〜って思(以下ry
自作自演ソーリーです。
私が今まで組んできたHIDは、電源本体はトヨタ純正、ベロフ、コイトと様々なんですが、バーナーは頑なにフィリップスかオスラムのいわゆる純正バーナーばかりなんです。
ですがよく思うのはバーナーが同じタイプなのに灯色がバラストによって結構違ってて、白っぽいこともあればハロゲン臭いこともあるし。明るさはそんなに違わないです。
バラストによる色の違いって、もしあることとすれば何が原因なんでしょう?
或いは目の錯覚や気分の問題ですかね?
政さんこんにちは。私もこっちの仲間に入れてください。
で、すごく専門的で難しめの内容になってしまって恐縮なのですが、あっちのコミュではないので遠慮しないで書かせてもらいますね(笑
すけねるさんも答えてくれていますが、バラストによって色は結構変わります。
具体的には、車用HIDの場合、バーナーにかける電力波形は、四角い矩形波なんですが、共鳴による球の破裂を避けるため、あまり高周波にできないのですね。なので、最低100Hz程度から、最大でも400Hzぐらいまでの比較的低い周期の矩形波なのですが、この周波数によって、一番積極的に励起される金属の種類が変わってきます。これによって同じバーナーでも組み合わせるバラストによって、緑っぽい球があったり紫っぽくなったりなんていうことが起こるのがひとつ。
二つ目の要因は、上記の矩形波は理想では角が直角にスパッと切れた綺麗な波形が理想なのですが、バラスト電力供給の最終段の電力増幅素子はアナログ素子なので、そんな理想波形と比べると波形が崩れたり鈍ったりしてしまいます。この電力波形の崩れ具合、鈍り具合でも色味が左右され、中華製のような安物の場合、波形を測定してみるとダメダメ(普通に点灯するけど、理論値には程遠い)な物だらけです。一番初期型のバラストは金と手間がかかるアナログ発振回路を使っていましたが、現在では4ビットとか8ビット程度のマイクロプロセッサが正確な矩形波を出力し、それを電力増幅素子で増幅します。これがデジタルバラストと呼ばれているものですね。
きれいな矩形波を強力な電源回路で実現した上、スパッと切れるはずのところをわざと削ったり、鈍らせたり、オーバーシュートさせると色味を若干変えることが出来ます。見た目ではちょっと紫っぽくなったかなとかちょっとピンクっぽくなったかなとか判断できるのですが、色温度として測定器で測るとほとんど変化しません。しても200k程度だったり。スペクトルのグラフで見てみると、5つぐらいあるピークの最大値がちょっと変化しているのが判断できます。
なので、紫っぽいのが、とかピンクがとか言っている人は、4300kの球で、バラストの出力電力の波形の形をいじるといいのにねと思うのですが、あちらのコミュでは理解してもらえなさそうなので言ったことはありません。
三つ目はデューティー比です。四角い矩形波は標準的な場合デューティー比50のプラス出力半分、マイナス出力半分なんですが、これの比率を変えるとやはり色が変わります。
昔仕事をしていた職場は映画用にハロゲン化金属が25種類ぐらい入っていたHMIという特殊メタルハライドランプを作っていたところだったのですが、電力波形をいじると面白いように色が変わりました。
車用HIDはハロゲン化金属が5種類ほどだったと思うのですが、それでもそれぞれの金属の発光ピーク値が変わるので、見た目の色は変わります。
といことで、メーカーによって電力の周波数が違う、波形の精度がちがう(あえて色のためにチューニングしてる場合もあるかも)、デューティー比がちがうなどの複合要因によって、同じ球でも色が変わってくるわけです。で、中華製粗悪品はそこまでのレベルで考えられていないです。
余談ですが、青白いのが好きな人が追求する紫ぽいというのは、青の更に下の純紫のウルトラバイオレットが出ているわけではなく、水色と若干のピンクが強く出たラベンダー色が出たものですので、実はあまり色温度は高くなかったりします。測定器で測って高い色温度表記が出る場合は、赤を減量しているからです。だから当然暗くなるんですが、色温度が高いと暗いと言うのはこういう現象から起こっているわけです。
長文で難しい話ですみません。
で、すごく専門的で難しめの内容になってしまって恐縮なのですが、あっちのコミュではないので遠慮しないで書かせてもらいますね(笑
すけねるさんも答えてくれていますが、バラストによって色は結構変わります。
具体的には、車用HIDの場合、バーナーにかける電力波形は、四角い矩形波なんですが、共鳴による球の破裂を避けるため、あまり高周波にできないのですね。なので、最低100Hz程度から、最大でも400Hzぐらいまでの比較的低い周期の矩形波なのですが、この周波数によって、一番積極的に励起される金属の種類が変わってきます。これによって同じバーナーでも組み合わせるバラストによって、緑っぽい球があったり紫っぽくなったりなんていうことが起こるのがひとつ。
二つ目の要因は、上記の矩形波は理想では角が直角にスパッと切れた綺麗な波形が理想なのですが、バラスト電力供給の最終段の電力増幅素子はアナログ素子なので、そんな理想波形と比べると波形が崩れたり鈍ったりしてしまいます。この電力波形の崩れ具合、鈍り具合でも色味が左右され、中華製のような安物の場合、波形を測定してみるとダメダメ(普通に点灯するけど、理論値には程遠い)な物だらけです。一番初期型のバラストは金と手間がかかるアナログ発振回路を使っていましたが、現在では4ビットとか8ビット程度のマイクロプロセッサが正確な矩形波を出力し、それを電力増幅素子で増幅します。これがデジタルバラストと呼ばれているものですね。
きれいな矩形波を強力な電源回路で実現した上、スパッと切れるはずのところをわざと削ったり、鈍らせたり、オーバーシュートさせると色味を若干変えることが出来ます。見た目ではちょっと紫っぽくなったかなとかちょっとピンクっぽくなったかなとか判断できるのですが、色温度として測定器で測るとほとんど変化しません。しても200k程度だったり。スペクトルのグラフで見てみると、5つぐらいあるピークの最大値がちょっと変化しているのが判断できます。
なので、紫っぽいのが、とかピンクがとか言っている人は、4300kの球で、バラストの出力電力の波形の形をいじるといいのにねと思うのですが、あちらのコミュでは理解してもらえなさそうなので言ったことはありません。
三つ目はデューティー比です。四角い矩形波は標準的な場合デューティー比50のプラス出力半分、マイナス出力半分なんですが、これの比率を変えるとやはり色が変わります。
昔仕事をしていた職場は映画用にハロゲン化金属が25種類ぐらい入っていたHMIという特殊メタルハライドランプを作っていたところだったのですが、電力波形をいじると面白いように色が変わりました。
車用HIDはハロゲン化金属が5種類ほどだったと思うのですが、それでもそれぞれの金属の発光ピーク値が変わるので、見た目の色は変わります。
といことで、メーカーによって電力の周波数が違う、波形の精度がちがう(あえて色のためにチューニングしてる場合もあるかも)、デューティー比がちがうなどの複合要因によって、同じ球でも色が変わってくるわけです。で、中華製粗悪品はそこまでのレベルで考えられていないです。
余談ですが、青白いのが好きな人が追求する紫ぽいというのは、青の更に下の純紫のウルトラバイオレットが出ているわけではなく、水色と若干のピンクが強く出たラベンダー色が出たものですので、実はあまり色温度は高くなかったりします。測定器で測って高い色温度表記が出る場合は、赤を減量しているからです。だから当然暗くなるんですが、色温度が高いと暗いと言うのはこういう現象から起こっているわけです。
長文で難しい話ですみません。
とりす さん、好意的に解釈、理解していただきましてありがとうございます。
なるべく皆さんに理解していただきやすいように文章を書くように心がけているのですが、そうすると文章がやたら長くなってしまうのが私の能力不足なところです。もっと簡潔に書かないとダメだなあと反省したりすることもあるのですが、このコミュのほうではHID初心者の方は知らないような理論や知識をなるべく書いたり答えたりできるようにしようと思います。ので、回答できないような質問もあると思うのですが、仕組みや理論などについてならいろいろ聞いてください。逆に今売ってるやつではどのバーナーがいいですか?とか聞かれると、純正がいいよとしか答えられません(笑
なるべく皆さんに理解していただきやすいように文章を書くように心がけているのですが、そうすると文章がやたら長くなってしまうのが私の能力不足なところです。もっと簡潔に書かないとダメだなあと反省したりすることもあるのですが、このコミュのほうではHID初心者の方は知らないような理論や知識をなるべく書いたり答えたりできるようにしようと思います。ので、回答できないような質問もあると思うのですが、仕組みや理論などについてならいろいろ聞いてください。逆に今売ってるやつではどのバーナーがいいですか?とか聞かれると、純正がいいよとしか答えられません(笑
QK さん
デジタルバラストの心臓部分のマイクロプロセッサは、点灯時の電流制御も行っています。これも初期のころはアナログフィードバック式だったので部品点数や精度が大変でしたが、現在では点灯直後の、ほおっておくと短絡に近い大電流になってしまうところをしっかり監視し、適切な電流量を絞って流す役割をしています。
人によっては点灯時の立ち上がり促進のために電流を増量すると言う言い方をする人もいますが、実際のところは放っておくとショートしそうな状態なのを一生懸命押さえるので、最初はたくさん電流を流しているように見えるのです。球の状態が安定してくるとガス圧が上がり、電流値が安定してくるので、積極的に制御しなくても大丈夫な状態になりますが、マイクロプロセッサは常に電流を監視し、球の寿命が近づいてきたときには安定時も通常より電流が多めに流れるようになるので、そういうのを検知し破裂したりしないように安全に動作を停止して球切れ交換を知らせたりといろんな役目を負っています。
なので、それなりのマイクロプロセッサが必要になるのですね。現在世界中で何社かが専用プロセッサを作っています。
優秀な設計だと、再点灯時の監視もしっかりしていて、安全な範囲でイグナイタ電圧増量などもしっかり行いますが、安価ないい加減なつくりのバラストだとそこまでの回路構成になっていないため、ホットリスタートが失敗したりしますね。
デジタルバラストの心臓部分のマイクロプロセッサは、点灯時の電流制御も行っています。これも初期のころはアナログフィードバック式だったので部品点数や精度が大変でしたが、現在では点灯直後の、ほおっておくと短絡に近い大電流になってしまうところをしっかり監視し、適切な電流量を絞って流す役割をしています。
人によっては点灯時の立ち上がり促進のために電流を増量すると言う言い方をする人もいますが、実際のところは放っておくとショートしそうな状態なのを一生懸命押さえるので、最初はたくさん電流を流しているように見えるのです。球の状態が安定してくるとガス圧が上がり、電流値が安定してくるので、積極的に制御しなくても大丈夫な状態になりますが、マイクロプロセッサは常に電流を監視し、球の寿命が近づいてきたときには安定時も通常より電流が多めに流れるようになるので、そういうのを検知し破裂したりしないように安全に動作を停止して球切れ交換を知らせたりといろんな役目を負っています。
なので、それなりのマイクロプロセッサが必要になるのですね。現在世界中で何社かが専用プロセッサを作っています。
優秀な設計だと、再点灯時の監視もしっかりしていて、安全な範囲でイグナイタ電圧増量などもしっかり行いますが、安価ないい加減なつくりのバラストだとそこまでの回路構成になっていないため、ホットリスタートが失敗したりしますね。
いや〜みなさんのおかげでだいぶわかってきました。
何年か前に「HIDって明るいって印象もあるんだけど、なんか雨とか雪とかに乱反射するからとか、
そんなん以前にどうも光自体が薄い気がするんだよなぁ。ハロゲンのほうが光が太くて、
HIDは光が細い、確かに明るいけど細い。ハリセンボンのはるかとはるなみたい」
って思ってたんです。まぁ、はるな愛はみんなかわいいっていいますけど。同感です。
どうやら満更間違いでもなかったみたいですね。
実際いまの自分の車ではそれは感じないですし。
このバーナー、HIDにしては白くないですが、逆に「HID=白」という固定観念を捨てるとゆうか、
ハナからないものとすればどこにも問題はないですし、
逆にそれを補って余りあるメリットの方がありがたいです。
このバーナーの発色を見て、HIDが好きな人はきまって「HIDらしくないね」といいます。
そういう人はHIDが好きなんではなくて「白いHID」か「青いHID」が好きなんだと思います。
私は外見きれいな欠陥住宅よりも小汚いしっかりした家が好きです。
いまフツーにフィリップス品を部品屋から仕入れると1本13000円だったかな?
それぐらいしました。
ちなみにそれはもちろん4300kのハナシで、5000kぐらいになると確か20000円じゃぁくれなかったと思います。
それをなぜヤッホーでは1本4000円や3000円で売ってるのか、最初はカナリ謎でした。
純正ブランド力も値段に働いているということもわかりましたが、
それ以前にそれだけの開発をしていますよね。
実際20000円ポンと渡されて「おいお前、D2Rの4300k作れるもんなら作ってみれ」
って言われても絶対できませんから。
情報の対価といいますか、技術力万円って感じです。
だから4300Kでも日本国や独国のモノと中華国のモノで明るさがまったく違うのもわかりました。
そして電源の原産国でもこれだけの違いが生まれるんですね。
たしかに電源は大事ですよね。見過ごしてました。
こうなってくると商売としてあからさまに30000kを売るという行為がまったく信用できません。
ほんとに蒼く青くしたいだけなら青色LEDでも並べればいいと思うんですが。
あんだけ青いと夏は目の前とんだ蚊が死んでくれれば役に立つんだけどと思います。
ちなみに、
>逆に今売ってるやつではどのバーナーがいいですか?とか聞かれると、純正がいいよとしか答えられません(笑
は、今月の暫定トップです。
あとは「電力波形」の件と、某古巣で教えていただいた「スペクトルのグラフ」の読み方などは別トピで進めましょうかね。
あ、トピ立ててくださってありがとうございます。
どんどん進めちゃってください。助かります。
管理人なのに生徒の側ですから。
何年か前に「HIDって明るいって印象もあるんだけど、なんか雨とか雪とかに乱反射するからとか、
そんなん以前にどうも光自体が薄い気がするんだよなぁ。ハロゲンのほうが光が太くて、
HIDは光が細い、確かに明るいけど細い。ハリセンボンのはるかとはるなみたい」
って思ってたんです。まぁ、はるな愛はみんなかわいいっていいますけど。同感です。
どうやら満更間違いでもなかったみたいですね。
実際いまの自分の車ではそれは感じないですし。
このバーナー、HIDにしては白くないですが、逆に「HID=白」という固定観念を捨てるとゆうか、
ハナからないものとすればどこにも問題はないですし、
逆にそれを補って余りあるメリットの方がありがたいです。
このバーナーの発色を見て、HIDが好きな人はきまって「HIDらしくないね」といいます。
そういう人はHIDが好きなんではなくて「白いHID」か「青いHID」が好きなんだと思います。
私は外見きれいな欠陥住宅よりも小汚いしっかりした家が好きです。
いまフツーにフィリップス品を部品屋から仕入れると1本13000円だったかな?
それぐらいしました。
ちなみにそれはもちろん4300kのハナシで、5000kぐらいになると確か20000円じゃぁくれなかったと思います。
それをなぜヤッホーでは1本4000円や3000円で売ってるのか、最初はカナリ謎でした。
純正ブランド力も値段に働いているということもわかりましたが、
それ以前にそれだけの開発をしていますよね。
実際20000円ポンと渡されて「おいお前、D2Rの4300k作れるもんなら作ってみれ」
って言われても絶対できませんから。
情報の対価といいますか、技術力万円って感じです。
だから4300Kでも日本国や独国のモノと中華国のモノで明るさがまったく違うのもわかりました。
そして電源の原産国でもこれだけの違いが生まれるんですね。
たしかに電源は大事ですよね。見過ごしてました。
こうなってくると商売としてあからさまに30000kを売るという行為がまったく信用できません。
ほんとに蒼く青くしたいだけなら青色LEDでも並べればいいと思うんですが。
あんだけ青いと夏は目の前とんだ蚊が死んでくれれば役に立つんだけどと思います。
ちなみに、
>逆に今売ってるやつではどのバーナーがいいですか?とか聞かれると、純正がいいよとしか答えられません(笑
は、今月の暫定トップです。
あとは「電力波形」の件と、某古巣で教えていただいた「スペクトルのグラフ」の読み方などは別トピで進めましょうかね。
あ、トピ立ててくださってありがとうございます。
どんどん進めちゃってください。助かります。
管理人なのに生徒の側ですから。
国産車でHIDを採用した初期のアコードの青白い光は、私もそうでしたけどすごくセンセーショナルで、良くも悪くもあれがHIDのイメージとして定着しちゃったのかもしれないですね。他の車だとあそこまで青く出なくて、何でアコードだけあんなにクールな青色が出るんだ?と私の周りで話題になっていて、バーナーはそのころはD2しかなかったので4300kだったんですが、分解してみたらなんとリフレクターに薄い青色が付いていたと言う。なかなかやるなスタンレーの技術者!と思ったものですが、今はその方法は違反になっちゃうんですよねえ。
ヤフオクでPhilipsやOSRAM純正品が叩き売りなのは、新車取り外し品が多いと言う話を聞きました。納車時からPIAAやベロフのにしてくれと言って取り替えちゃうのだとか。だから出品者は高級外車を扱ってるところとか多い感じです。一番お得なので、実験用に買い占めるのもいいかもしれませんね。
技術やノウハウにお金を払えるかという点については人によって考えが違うかもしれないですねえ。安さ命みたいな人もいますから。
ただ、ヨーロッパの老舗企業のいやらしいところは、安価な生産能力では中国に勝ち目がないものだから、何でも特許特許ライセンスで縛りまくって、高い金を巻き上げることによって利益を得るのが当たり前のようになっているのがちょっとなあという感じです。
まあ、そういう生き残り方法を取るために基礎研究や開発にはきちんと金をかけているのでたしかにそれをそのままパクられる訳にはいかないというのは納得なんですが。
また年々規制を厳しくしてそんなの無理だよと言う規制をかけてきて海外製品を締め出すと言う政治的手法を取っているのもちょっといやらしい感じです。水銀規制とか電気製品のRoHS規制とか
、排気ガス規制とか。でも日本の技術者はがんばっちゃってヨーロッパ規制をクリアしちゃうから規制になっていないようですが。
15年ぐらい前だったかな、車用が出る前にMPXL-DL35と同型のD2Sと同じ評価用の球を実験用にPhilipsから調達したときの値段は2本で30000円でしたので、それを考えると今でも定価はほとんど変わっていないのね、ということになりますね。
ヤフオクでPhilipsやOSRAM純正品が叩き売りなのは、新車取り外し品が多いと言う話を聞きました。納車時からPIAAやベロフのにしてくれと言って取り替えちゃうのだとか。だから出品者は高級外車を扱ってるところとか多い感じです。一番お得なので、実験用に買い占めるのもいいかもしれませんね。
技術やノウハウにお金を払えるかという点については人によって考えが違うかもしれないですねえ。安さ命みたいな人もいますから。
ただ、ヨーロッパの老舗企業のいやらしいところは、安価な生産能力では中国に勝ち目がないものだから、何でも特許特許ライセンスで縛りまくって、高い金を巻き上げることによって利益を得るのが当たり前のようになっているのがちょっとなあという感じです。
まあ、そういう生き残り方法を取るために基礎研究や開発にはきちんと金をかけているのでたしかにそれをそのままパクられる訳にはいかないというのは納得なんですが。
また年々規制を厳しくしてそんなの無理だよと言う規制をかけてきて海外製品を締め出すと言う政治的手法を取っているのもちょっといやらしい感じです。水銀規制とか電気製品のRoHS規制とか
、排気ガス規制とか。でも日本の技術者はがんばっちゃってヨーロッパ規制をクリアしちゃうから規制になっていないようですが。
15年ぐらい前だったかな、車用が出る前にMPXL-DL35と同型のD2Sと同じ評価用の球を実験用にPhilipsから調達したときの値段は2本で30000円でしたので、それを考えると今でも定価はほとんど変わっていないのね、ということになりますね。
QK さん
おお、なつかしいですね。HIDはデビュー当時はPhilipsはたしかに マイクロパワー(キセノン)ライト と呼んでいました。なのでその当時から汎用品のほうの型番はMPXLなんですよ。
マイクロパワーライトと言う名前は一般的にならなかったですね。OSRAMのXENARCもぜんぜん聞かないですね。初期のころは通称メタハラと呼ばれることが多かった気がします。
探せば発売前のMPXLの資料が出てくるかもしれないので、見つかったらここにあげてみます。
D2と呼ばれているのは自動車のランプとしての規格で、ソケットの正式名称はP32dといいます。これはPhilipsとたしかOSRAMだったかにライセンス料払わないと使えないので、それで中華製のアフターマーケット品の球は中華型としてP32dを使っていないようです。まあ、そのおかげなのか多彩な純正形状置き換え型が出せるので、まあ、ありがたいと言えばありがたいですね。
政 さん
写真のアウターチューブなしの物は試作品とか初期のサンプル品だったと思います。何回かサンプル注文しましたが、私が個人的に分けてもらったときは、UVカット対策された車用のも出せるようになりましたけど、どっちにしますか?と聞かれた覚えがあります。私が入手したアウターチューブがついたものはMPXLではなくD2型番でした。発光特性はUVカット以外は一緒でした。
アウターチューブがない外見の球は、UVランプのMPXL-UVなんかは紫外線カットしないのでアウターチューブがないです。見た目貧弱で簡単に折れそうですけど。
おお、なつかしいですね。HIDはデビュー当時はPhilipsはたしかに マイクロパワー(キセノン)ライト と呼んでいました。なのでその当時から汎用品のほうの型番はMPXLなんですよ。
マイクロパワーライトと言う名前は一般的にならなかったですね。OSRAMのXENARCもぜんぜん聞かないですね。初期のころは通称メタハラと呼ばれることが多かった気がします。
探せば発売前のMPXLの資料が出てくるかもしれないので、見つかったらここにあげてみます。
D2と呼ばれているのは自動車のランプとしての規格で、ソケットの正式名称はP32dといいます。これはPhilipsとたしかOSRAMだったかにライセンス料払わないと使えないので、それで中華製のアフターマーケット品の球は中華型としてP32dを使っていないようです。まあ、そのおかげなのか多彩な純正形状置き換え型が出せるので、まあ、ありがたいと言えばありがたいですね。
政 さん
写真のアウターチューブなしの物は試作品とか初期のサンプル品だったと思います。何回かサンプル注文しましたが、私が個人的に分けてもらったときは、UVカット対策された車用のも出せるようになりましたけど、どっちにしますか?と聞かれた覚えがあります。私が入手したアウターチューブがついたものはMPXLではなくD2型番でした。発光特性はUVカット以外は一緒でした。
アウターチューブがない外見の球は、UVランプのMPXL-UVなんかは紫外線カットしないのでアウターチューブがないです。見た目貧弱で簡単に折れそうですけど。
>政 さん
写真貼るの忘れてました。これです。
http://www.lighting.philips.co.jp/jp/-/Portal?xml=catalogue/special_family&fldr_id=4926
ここに詳細が載っていますが、ドイツのバラスト屋さんのところに掲載されているDUVというモデルと一緒だと思います。
これだと盛大に紫外線と青までしか出さないですけど、それでも測定しても30000Kなんて値は出てこないと思います。いいところ15000Kぐらいなんじゃないかな。
440nmあたりが盛大に出ているので、測定器では存在しないはずの赤の入力レベルが上がってしまって、思ったほど青だけが強い特性にならない計測結果になっちゃうんですよ。
で、青いの大好きな人でも、このランプを装着して走るのは無理でしょう。車体下にアクセントランプとして装着するなら、誘蛾灯や殺菌灯にはなるかもしれません(笑
写真貼るの忘れてました。これです。
http://www.lighting.philips.co.jp/jp/-/Portal?xml=catalogue/special_family&fldr_id=4926
ここに詳細が載っていますが、ドイツのバラスト屋さんのところに掲載されているDUVというモデルと一緒だと思います。
これだと盛大に紫外線と青までしか出さないですけど、それでも測定しても30000Kなんて値は出てこないと思います。いいところ15000Kぐらいなんじゃないかな。
440nmあたりが盛大に出ているので、測定器では存在しないはずの赤の入力レベルが上がってしまって、思ったほど青だけが強い特性にならない計測結果になっちゃうんですよ。
で、青いの大好きな人でも、このランプを装着して走るのは無理でしょう。車体下にアクセントランプとして装着するなら、誘蛾灯や殺菌灯にはなるかもしれません(笑
単位っていっぱいあってめんどくさいですよね。いろいろ相関関係があるので、それを理解できちゃうとなんとなく納得になるかもしれません。
私の書いてるのがどんどん突っ走っちゃってるのでそういうのを説明するのをすっかりわすれてました。すみませんです。
「nm」はナノメートルと読みます。昔はオングストロームなんていわれていましたが、光の波長の長さの単位です。ナノだと10のマイナス6乗ですね。ようするにすごく小さい振幅の波ですよと。
音のグラフだと低音が左で100Hzとかで右側が高音で20kHzとかなりますが、光の場合左右逆で、波長が短い、音で言うと高音のほうが紫外線から青、波長が長い、音で言うと低音のほうが赤から赤外線領域となります。
人間の目で見えるのは個人差もありますが、だいたい380nmから780nmあたりと言われています。
演色性は「えんしょくせい」と読み、単位がRaとなり、表記は「Ra80」とかなります。
あっちのコミュでおぎすけさんが挙げてくれたグラフのデータの右端にも書いてありますね。数値は高いに越したことはありませんが、車用ならRa70程度でも問題ないと思います。
ケルビンは理想黒体という架空の物体を熱して出てくるであろう連続スペクトルの光線が出すカラーバランスを表します。0kはマイナス273℃でそれ以下の数値はマイナス側は存在しません。核融合で盛大に光っている太陽の表面温度が6000kぐらいです。ハロゲン電球の場合、フィラメントに電力をかけると熱が出て、それで連続スペクトルの光線が出てきます。なので、2800kのただの白熱電球より3200kのハロゲンのほうが熱いです。また最近の技術だと、ハリソン東芝やナショナル(今はパナソニックですが)が実用化にこぎつけた、フットボール型のガラスチューブに熱線反射コートを施して、一度放出された熱を再度フィラメントに跳ね返して再加熱し、さらにフィラメント温度を上げて色温度が高い発光ができるようにした高性能ハロゲンもあります。商品名だとHIRあたりが有名かな。この方法の限界はだいたい3900kあたりです。これ以上だと青く染色したガラスを通すしかありませんが暗くなりますね。
スペクトル非連続の光源の場合は正確に言うと相対色温度と言う名前になって、人間の目で見たときに換算するとこれぐらいという値です。演色性が高いと、白色のカーブ上に近いところに乗りますが、スペクトルの欠損が多いとか偏っている場合、カーブから変に外れた数値になります。だから15000kなんていうのも出てしまうんですね。どうも色温度高いものがめちゃくちゃな座標になりやすいようです。
私の書いてるのがどんどん突っ走っちゃってるのでそういうのを説明するのをすっかりわすれてました。すみませんです。
「nm」はナノメートルと読みます。昔はオングストロームなんていわれていましたが、光の波長の長さの単位です。ナノだと10のマイナス6乗ですね。ようするにすごく小さい振幅の波ですよと。
音のグラフだと低音が左で100Hzとかで右側が高音で20kHzとかなりますが、光の場合左右逆で、波長が短い、音で言うと高音のほうが紫外線から青、波長が長い、音で言うと低音のほうが赤から赤外線領域となります。
人間の目で見えるのは個人差もありますが、だいたい380nmから780nmあたりと言われています。
演色性は「えんしょくせい」と読み、単位がRaとなり、表記は「Ra80」とかなります。
あっちのコミュでおぎすけさんが挙げてくれたグラフのデータの右端にも書いてありますね。数値は高いに越したことはありませんが、車用ならRa70程度でも問題ないと思います。
ケルビンは理想黒体という架空の物体を熱して出てくるであろう連続スペクトルの光線が出すカラーバランスを表します。0kはマイナス273℃でそれ以下の数値はマイナス側は存在しません。核融合で盛大に光っている太陽の表面温度が6000kぐらいです。ハロゲン電球の場合、フィラメントに電力をかけると熱が出て、それで連続スペクトルの光線が出てきます。なので、2800kのただの白熱電球より3200kのハロゲンのほうが熱いです。また最近の技術だと、ハリソン東芝やナショナル(今はパナソニックですが)が実用化にこぎつけた、フットボール型のガラスチューブに熱線反射コートを施して、一度放出された熱を再度フィラメントに跳ね返して再加熱し、さらにフィラメント温度を上げて色温度が高い発光ができるようにした高性能ハロゲンもあります。商品名だとHIRあたりが有名かな。この方法の限界はだいたい3900kあたりです。これ以上だと青く染色したガラスを通すしかありませんが暗くなりますね。
スペクトル非連続の光源の場合は正確に言うと相対色温度と言う名前になって、人間の目で見たときに換算するとこれぐらいという値です。演色性が高いと、白色のカーブ上に近いところに乗りますが、スペクトルの欠損が多いとか偏っている場合、カーブから変に外れた数値になります。だから15000kなんていうのも出てしまうんですね。どうも色温度高いものがめちゃくちゃな座標になりやすいようです。
カンデラ「cd」ルーメン「lm」ルクス「lx」は明るさ関係の単位ですが、何で三つもあるの?って感じですよね。この三つはすべて相関関係があります。難しいことはwikipediaにいろいろ載っていますので、興味と時間が取れる方はじっくり見てみるのも面白いかもしれません。
cdは定義によると、放射強度683分の1ワット毎ステラジアンで540テラヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度 ということなんですが、これじゃ完全に宇宙人語ですね。要するに、人間の目の一番感度が高いと言われている540nmの波長の光(色は付いていなくていいんですが、540nmは緑色)が光源からどれだけ強く出ているかということを表す単位です。光度と言いますが、まあ、まぶしさの単位だと思ってもらうのが解りやすいでしょう。なので、cdの値が高いとまぶしいですが、これは全体の明るさとは関係ないんですね。LEDがまぶしいわりに明るくないと言うのがいい例です。
なので、単純に明るさと思うのはまずいです。一点からどれだけ強い光を出せるかという感じです。
ルーメンは、1カンデラの光源から1ステラジアン内に放射される光束 と定義される光束で、点ではなく、球体を切り取ったある角度と面積を持った平面にどれだけの明るさを照射できるかを表したものです。なので、これが実質のいちばんピンと来る明るさの単位になると思います。この電球の明るさは?と言う場合に3000lmだよとか言う答えになります。LEDのようにカンデラ値は高くてもルーメン値は低い物もあります。
ルクスは、1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度 と定義されます。照度です。机の上の明るさは何Lux以上が見えやすくていいですね。なんていう使い方になります。イメージ的には照らされた先の対象物の明るさだと思えばわかりやすいかと思います。
なので、この3つの単位は切っても切り離せないし、計算でお互いを出すこともできます。電流Vと電圧Iをかけると電力Wになるような関係ですね。
HIDの場合だと、点光源に近いので、バーナー単体の評価としてならcdはアリかもしれませんが、ランプハウジングに装着されているときはcdで評価することはできません。
また、ランプの発光性能としてlmは使いますが、ランプユニットとしてみた場合は、ある面積がある光源とみなしたほうが現実的です。
また、照射される先は、たとえば5m先の路面とか10m先の壁面に照射した場合何luxだよとかそういう評価の仕方になります。なので、米粒を縦に伸ばしたような照射ビームの照度データなんかがハロゲンなんかでも良く載っていますね。これは光源だけでなく、ランプユニット総合の性能として評価されるべきものになります。
あと、120Wクラスとか、あれは単位でも何でもありません。JISで定められた自動車用標準光源電球があって、それは今となってはすごくしょぼい明るさのD4タングステン電球なんですが(H4以前のハロゲンじゃないバージョンHIDのD4とは別物)それと比べてどれぐらいと言っているので、半分サギみたいなもんです。20年前のエアコンと比べて能力3割アップで消費電力半分とか言ってるのと同じです。ハロゲンの進化はそろそろ物理的な限界に差し掛かっていますのでこれ以上劇的な性能向上はないと思います。
また寿命を犠牲にすれば美人薄命のすごい明るい電球も可能なのですが、アフターマーケット品は最近その方向に走るようになっている傾向がありますね。また、熱をフィラメントにだけ確実に返せば、明るくて色温度高くて寿命も長い球が作れるので、HIRはそれを実現していますが、青く染色した球は赤方向の色をさえぎって熱にしてますので、バルブ全体が熱で劣化し、フィラメントが切れなくても付け根のタングステンリードのところからヒビが入って切れたりする物も少なくありません。
以前、明るいので有名なレークリとHIRの照度と電流値を測定してみたことがありましたが、ノーマルハロゲンの2割ちょっと増しぐらいの明るさでした。レークリは微ハイワッテージでしたし(笑
さらに頭混乱しちゃったかもしれませんが、明るさとしてはルーメンを、照らしている先の明るさはルクスを、何Wクラスはアテにならないと理解していただければいいと思います。
cdは定義によると、放射強度683分の1ワット毎ステラジアンで540テラヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度 ということなんですが、これじゃ完全に宇宙人語ですね。要するに、人間の目の一番感度が高いと言われている540nmの波長の光(色は付いていなくていいんですが、540nmは緑色)が光源からどれだけ強く出ているかということを表す単位です。光度と言いますが、まあ、まぶしさの単位だと思ってもらうのが解りやすいでしょう。なので、cdの値が高いとまぶしいですが、これは全体の明るさとは関係ないんですね。LEDがまぶしいわりに明るくないと言うのがいい例です。
なので、単純に明るさと思うのはまずいです。一点からどれだけ強い光を出せるかという感じです。
ルーメンは、1カンデラの光源から1ステラジアン内に放射される光束 と定義される光束で、点ではなく、球体を切り取ったある角度と面積を持った平面にどれだけの明るさを照射できるかを表したものです。なので、これが実質のいちばんピンと来る明るさの単位になると思います。この電球の明るさは?と言う場合に3000lmだよとか言う答えになります。LEDのようにカンデラ値は高くてもルーメン値は低い物もあります。
ルクスは、1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度 と定義されます。照度です。机の上の明るさは何Lux以上が見えやすくていいですね。なんていう使い方になります。イメージ的には照らされた先の対象物の明るさだと思えばわかりやすいかと思います。
なので、この3つの単位は切っても切り離せないし、計算でお互いを出すこともできます。電流Vと電圧Iをかけると電力Wになるような関係ですね。
HIDの場合だと、点光源に近いので、バーナー単体の評価としてならcdはアリかもしれませんが、ランプハウジングに装着されているときはcdで評価することはできません。
また、ランプの発光性能としてlmは使いますが、ランプユニットとしてみた場合は、ある面積がある光源とみなしたほうが現実的です。
また、照射される先は、たとえば5m先の路面とか10m先の壁面に照射した場合何luxだよとかそういう評価の仕方になります。なので、米粒を縦に伸ばしたような照射ビームの照度データなんかがハロゲンなんかでも良く載っていますね。これは光源だけでなく、ランプユニット総合の性能として評価されるべきものになります。
あと、120Wクラスとか、あれは単位でも何でもありません。JISで定められた自動車用標準光源電球があって、それは今となってはすごくしょぼい明るさのD4タングステン電球なんですが(H4以前のハロゲンじゃないバージョンHIDのD4とは別物)それと比べてどれぐらいと言っているので、半分サギみたいなもんです。20年前のエアコンと比べて能力3割アップで消費電力半分とか言ってるのと同じです。ハロゲンの進化はそろそろ物理的な限界に差し掛かっていますのでこれ以上劇的な性能向上はないと思います。
また寿命を犠牲にすれば美人薄命のすごい明るい電球も可能なのですが、アフターマーケット品は最近その方向に走るようになっている傾向がありますね。また、熱をフィラメントにだけ確実に返せば、明るくて色温度高くて寿命も長い球が作れるので、HIRはそれを実現していますが、青く染色した球は赤方向の色をさえぎって熱にしてますので、バルブ全体が熱で劣化し、フィラメントが切れなくても付け根のタングステンリードのところからヒビが入って切れたりする物も少なくありません。
以前、明るいので有名なレークリとHIRの照度と電流値を測定してみたことがありましたが、ノーマルハロゲンの2割ちょっと増しぐらいの明るさでした。レークリは微ハイワッテージでしたし(笑
さらに頭混乱しちゃったかもしれませんが、明るさとしてはルーメンを、照らしている先の明るさはルクスを、何Wクラスはアテにならないと理解していただければいいと思います。
単位の件、まことにありがとうございます。
毎度毎度日本一丁寧な説明に感謝します。
で、ひとつ車屋的に疑問に思うことが生まれてきまして・・・
いつもいつも質問ばかりなんですが、
車検のときに必要なヘッドライトの光量があるんですが、
確かハイビームで12000cdか、ロービームで8000cdのどちらか・・・(それぞれ要方向性)
ここで数値を計るときの単位がcdなんですよね。
これはテスターの方式が集光式だからなんですかね?
集光部分のサイズは大体300mm×400mmぐらいです。
車検のときはいやらしいぐらいこの数字を見て帰るんですが、
私のような人間にはいいオモチャです。
純正H4ハロゲンマルチリフレクターでハイビーム60000cd出る灯体があるとして、
ここにインチキ6000K130Wクラスwのハロゲンをぶち込むとだいたい半分の30000cdです。
ちなみに前述ロービームは12000cd〜14000cdでさらにインチキ球じゃぁ10000出ません。
どうりで暗いわけです。
そしてさらにさらにここにHIDを入れてもそんなに明るくならないモンなんです。
ハロゲンマルチリフレクター+HIDの相性の悪さを思い出しました。
しかも大概グレアが嵐のようにでます。
逆に金属リフ+ガラスレンズカットの方が明るかったり運転しやすかったりします。
今んとこ純正HID1位はエリシオンとEKスポーツのプロジェクタで20000でした。
たしかにかなり明るいですよね。
下手すると前を走る車のハロゲンハイビームより明るいこともあります。
逆にびっくりしたのがエスティマハイブリッドの40系の方で10000でした。
あれって純正はD4Sなんですかね?
だからといって半分ってのはナイと思ったんですが・・・
計測結果を山ほど見てて、ある結論にたどり着きそうなんですが、ワタクシ思いますに、
メーカーはHIDの光量を20000以上にするつもりはないんじゃないかと。
こんだけ光れば十分だろと。
ハイビームもあるわけだし。
昔はロービーム=すれ違い灯、ハイビーム=走行灯が当然で
たしか私のZはロー35Wハイ55Wのシールドでした。
今は大義名分こそ変わりませんがロービームで十分走れるようになりましたよね。
逆に純正ハロゲンレンズカットの灯体にHIDを入れると純正HIDを超えることがありました。
前述の金属リフ+ガラスレンズカットがそうです。
これはほんとに明るいです。
残念ながらグレアも凄まじいですが・・・
毎度毎度日本一丁寧な説明に感謝します。
で、ひとつ車屋的に疑問に思うことが生まれてきまして・・・
いつもいつも質問ばかりなんですが、
車検のときに必要なヘッドライトの光量があるんですが、
確かハイビームで12000cdか、ロービームで8000cdのどちらか・・・(それぞれ要方向性)
ここで数値を計るときの単位がcdなんですよね。
これはテスターの方式が集光式だからなんですかね?
集光部分のサイズは大体300mm×400mmぐらいです。
車検のときはいやらしいぐらいこの数字を見て帰るんですが、
私のような人間にはいいオモチャです。
純正H4ハロゲンマルチリフレクターでハイビーム60000cd出る灯体があるとして、
ここにインチキ6000K130Wクラスwのハロゲンをぶち込むとだいたい半分の30000cdです。
ちなみに前述ロービームは12000cd〜14000cdでさらにインチキ球じゃぁ10000出ません。
どうりで暗いわけです。
そしてさらにさらにここにHIDを入れてもそんなに明るくならないモンなんです。
ハロゲンマルチリフレクター+HIDの相性の悪さを思い出しました。
しかも大概グレアが嵐のようにでます。
逆に金属リフ+ガラスレンズカットの方が明るかったり運転しやすかったりします。
今んとこ純正HID1位はエリシオンとEKスポーツのプロジェクタで20000でした。
たしかにかなり明るいですよね。
下手すると前を走る車のハロゲンハイビームより明るいこともあります。
逆にびっくりしたのがエスティマハイブリッドの40系の方で10000でした。
あれって純正はD4Sなんですかね?
だからといって半分ってのはナイと思ったんですが・・・
計測結果を山ほど見てて、ある結論にたどり着きそうなんですが、ワタクシ思いますに、
メーカーはHIDの光量を20000以上にするつもりはないんじゃないかと。
こんだけ光れば十分だろと。
ハイビームもあるわけだし。
昔はロービーム=すれ違い灯、ハイビーム=走行灯が当然で
たしか私のZはロー35Wハイ55Wのシールドでした。
今は大義名分こそ変わりませんがロービームで十分走れるようになりましたよね。
逆に純正ハロゲンレンズカットの灯体にHIDを入れると純正HIDを超えることがありました。
前述の金属リフ+ガラスレンズカットがそうです。
これはほんとに明るいです。
残念ながらグレアも凄まじいですが・・・
>すけねる さん
いつも知的な書き込みですばらしいです。数字や単位が関係する物は積極的にすけねるさんに質問したほうがいいかもしれませんね。
車のヘッドライト測定器はcdで測るというのの話はあとで書きますね。
で、cdで測っているときは、RGBそれぞれではなく、540nmが中心感度の測定装置を使っていたのでしょう。今まではハロゲン電球の測定だったからそれで十分だったのでしょうね。青いフィルターがかかっていても、明るさは落ちますが、青色のせいで大幅に測定値が狂うということもないと思います。これが放電灯でUVとその周辺の青しか出ていない球だと、540nmよりはるかに低いところしか出ていないので、とんでもなく低い数値とかゼロcdとか出てきてしまうかもしれません。
優秀な球は540nm付近も青も赤も満遍なく出ていますので、人間の目でも測定器でもいい成績になると思いますが、540nm付近のスペクトルが欠落している場合だと、目で見たときには暗く見えなくても測定器での評価は低い値が出る可能性はあると思います。
そういう不都合を解消したり、とんでもない色が出てきたときに検査員の主観ではなしに客観的に数値でここまではオッケーだけど、ここからはダメという判定をするために、RGBで測定して、色座標を算出して、それで合否を決めるのが併用されるようになるんじゃないかと予想します。これだと、高価なスペクトルアナライザーよりもう少し安く、扱いやすいので判定が際どい場合はそれで測って数値を出して合否を判断するということになるのでしょう。
あっちのコミュでおぎすけさんが上げてくれたグラフのようなものが出てきて(グラフは出なくてもxy座標の数値だけでもいいんですが)判断になると思われますので、スペクトルまでいちいち見ないような気もします。
前に白色の合格ラインの座標をあっちで書きましたが、どうも6000kだと不合格ラインな感じ。赤のx軸座標の許容値が青方向にだいぶ厳しいようなんですよね。
実は人間の目の感度のピークのRGBとCIEで定められた測定器のRGBのピークが違うので、ちょっと変な現象やごまかし技があったりするので、そこら辺は次の色温度トピで書くつもりです。
いつも知的な書き込みですばらしいです。数字や単位が関係する物は積極的にすけねるさんに質問したほうがいいかもしれませんね。
車のヘッドライト測定器はcdで測るというのの話はあとで書きますね。
で、cdで測っているときは、RGBそれぞれではなく、540nmが中心感度の測定装置を使っていたのでしょう。今まではハロゲン電球の測定だったからそれで十分だったのでしょうね。青いフィルターがかかっていても、明るさは落ちますが、青色のせいで大幅に測定値が狂うということもないと思います。これが放電灯でUVとその周辺の青しか出ていない球だと、540nmよりはるかに低いところしか出ていないので、とんでもなく低い数値とかゼロcdとか出てきてしまうかもしれません。
優秀な球は540nm付近も青も赤も満遍なく出ていますので、人間の目でも測定器でもいい成績になると思いますが、540nm付近のスペクトルが欠落している場合だと、目で見たときには暗く見えなくても測定器での評価は低い値が出る可能性はあると思います。
そういう不都合を解消したり、とんでもない色が出てきたときに検査員の主観ではなしに客観的に数値でここまではオッケーだけど、ここからはダメという判定をするために、RGBで測定して、色座標を算出して、それで合否を決めるのが併用されるようになるんじゃないかと予想します。これだと、高価なスペクトルアナライザーよりもう少し安く、扱いやすいので判定が際どい場合はそれで測って数値を出して合否を判断するということになるのでしょう。
あっちのコミュでおぎすけさんが上げてくれたグラフのようなものが出てきて(グラフは出なくてもxy座標の数値だけでもいいんですが)判断になると思われますので、スペクトルまでいちいち見ないような気もします。
前に白色の合格ラインの座標をあっちで書きましたが、どうも6000kだと不合格ラインな感じ。赤のx軸座標の許容値が青方向にだいぶ厳しいようなんですよね。
実は人間の目の感度のピークのRGBとCIEで定められた測定器のRGBのピークが違うので、ちょっと変な現象やごまかし技があったりするので、そこら辺は次の色温度トピで書くつもりです。
政さんのコメントで思ったのですが、ホンダのプロジェクターやEKスポーツはやっぱり明るいんですね。
後続車の光がカットラインがはっきり解る程遠くまで飛んでいて確認したらEKスポーツだったなんてこともありました。プロジェクタの灯体は縦長で随分小さい(リフレクタ面積は案外あるのかな?)のにあれだけ遠くまで飛ばせるとは。。
ライトの灯体は反射、集光させるのが目的ですからリフレクタはメッキで全反射させていますが光の場合は全反射の面に対して入射角の違いによってロスなんて存在するんでしょうか?(臨界角なんてあるのか!?)レンズなら光は反射光と通過光に分かれますから屈折角の違いによってロスがあると思いますが。。
もし入射角によってロスがあるのならプロジェクターはマルチリフレクタと比較してリフレクタとレンズでコントロールするのにどれだけロスがあるのかちょっと疑問です。解ったからといっても灯体自体は方式の違いこそあれ設計の善し悪しで高効率かどうか決まってくるでしょうからどうだと言うわけではないのですがちょっと気になったので。
また、使用目的によっても照射角をどうするのか違いますから単にある照射された部分が明るいからといってそれが優れているとは言い切れないものですね。
自分的にはロービームはプロジェクタ単体としては現行セルシオが真横まで照らす勢いですんごいー!と感じています。サブリフレクタと併用しているものではLS600hが優れているようですね。この辺りは流用するにもなかなかできるものではないですが(^_^;
LEXUSで思い出しましたが明るい灯体は現在LS600hがトップでLS460のものも優れており、フーガの灯体に対抗して作られたとかなんとか。でも明るいって何を基準に明るいと言っているんでしょうね。基準となる測定器での結果であっても構いませんが見やすいのとはイコールでないところが難しいところかなと思ったり。
あ、いろいろ書きましたが政さんのコメントに対してどうこう言っているわけではありませんので悪しからず。政さんのコメントも読んでいて楽しいですよ。
(^^)
後続車の光がカットラインがはっきり解る程遠くまで飛んでいて確認したらEKスポーツだったなんてこともありました。プロジェクタの灯体は縦長で随分小さい(リフレクタ面積は案外あるのかな?)のにあれだけ遠くまで飛ばせるとは。。
ライトの灯体は反射、集光させるのが目的ですからリフレクタはメッキで全反射させていますが光の場合は全反射の面に対して入射角の違いによってロスなんて存在するんでしょうか?(臨界角なんてあるのか!?)レンズなら光は反射光と通過光に分かれますから屈折角の違いによってロスがあると思いますが。。
もし入射角によってロスがあるのならプロジェクターはマルチリフレクタと比較してリフレクタとレンズでコントロールするのにどれだけロスがあるのかちょっと疑問です。解ったからといっても灯体自体は方式の違いこそあれ設計の善し悪しで高効率かどうか決まってくるでしょうからどうだと言うわけではないのですがちょっと気になったので。
また、使用目的によっても照射角をどうするのか違いますから単にある照射された部分が明るいからといってそれが優れているとは言い切れないものですね。
自分的にはロービームはプロジェクタ単体としては現行セルシオが真横まで照らす勢いですんごいー!と感じています。サブリフレクタと併用しているものではLS600hが優れているようですね。この辺りは流用するにもなかなかできるものではないですが(^_^;
LEXUSで思い出しましたが明るい灯体は現在LS600hがトップでLS460のものも優れており、フーガの灯体に対抗して作られたとかなんとか。でも明るいって何を基準に明るいと言っているんでしょうね。基準となる測定器での結果であっても構いませんが見やすいのとはイコールでないところが難しいところかなと思ったり。
あ、いろいろ書きましたが政さんのコメントに対してどうこう言っているわけではありませんので悪しからず。政さんのコメントも読んでいて楽しいですよ。
(^^)
今、バーナーとバラストの組み合わせでバーナーとバラストを接続する1極の防水コネクタを探しています。FETのバーナー、バラストなのでこのコネクタなんですよね。。モノは下記です。
メーカー:住友電装
型 名 :6189-0145 http://swsct.sws.co.jp/components/jp/housing.asp?number_s=61890145tss
6188-0083 http://swsct.sws.co.jp/components/jp/housing.asp?number_s=61880083tss
バーナーとバラストを接続するコネクタは高電圧ですから中国製の細いコンタクトのものでなく、接触面積の大きいものを使いたいと思っています。
矢崎のコネクタならネット通販で見つけたのですが、住友電装のものはTSシリーズで090ならよく見かけるのですが、コンタクトのサイズが大きい187タイプは見つかりません。
どなたか個人客、少量での購入先をご存知ありませんか?
どうしても見つからないのなら矢崎のものを使うしかないと思ってはいるのですけどね。
メーカー:住友電装
型 名 :6189-0145 http://swsct.sws.co.jp/components/jp/housing.asp?number_s=61890145tss
6188-0083 http://swsct.sws.co.jp/components/jp/housing.asp?number_s=61880083tss
バーナーとバラストを接続するコネクタは高電圧ですから中国製の細いコンタクトのものでなく、接触面積の大きいものを使いたいと思っています。
矢崎のコネクタならネット通販で見つけたのですが、住友電装のものはTSシリーズで090ならよく見かけるのですが、コンタクトのサイズが大きい187タイプは見つかりません。
どなたか個人客、少量での購入先をご存知ありませんか?
どうしても見つからないのなら矢崎のものを使うしかないと思ってはいるのですけどね。
> こめ(よね)@not CR-Z さん
あちらのコミュではお世話になっておりますが、こちらではご無沙汰しております。
矢崎のはネット上で販売してるのを見かけますが、住友電装のものは確かに見かけないですね。
何万個なら購入できるんでしょうけど、趣味だと同士に頒布しても捌ききれないだろうし。
で、接触面積ですが、電圧が低いと影響が大きいので、12Vだと接点の状態次第では面積が大きいほうが安心というのがありますが、矩形波85Vだと、100VのACライン同等と考えてもいいと思いますので、187タイプより一回り小さいコネクタでも気分的な以外のところはまったく問題ないかもしれませんね。
最初の電撃も6000Vから20000Vなので、接触面積より酸化皮膜にやられないような良質な表面処理のほうが重要かもしれません。
個人的な感覚では、自分で企画設計して商品として売り出すなら、安心の品質のために意地でも探すと思いますが、自分の趣味の工作の場合だと必要充分性能で入手しやすい矢崎を使っちゃうと思います。
または、手持ちの余った怪しいハーネスをちょん切って適当に使っちゃうかなあ。
全然参考意見になってなくてすみません。
あちらのコミュではお世話になっておりますが、こちらではご無沙汰しております。
矢崎のはネット上で販売してるのを見かけますが、住友電装のものは確かに見かけないですね。
何万個なら購入できるんでしょうけど、趣味だと同士に頒布しても捌ききれないだろうし。
で、接触面積ですが、電圧が低いと影響が大きいので、12Vだと接点の状態次第では面積が大きいほうが安心というのがありますが、矩形波85Vだと、100VのACライン同等と考えてもいいと思いますので、187タイプより一回り小さいコネクタでも気分的な以外のところはまったく問題ないかもしれませんね。
最初の電撃も6000Vから20000Vなので、接触面積より酸化皮膜にやられないような良質な表面処理のほうが重要かもしれません。
個人的な感覚では、自分で企画設計して商品として売り出すなら、安心の品質のために意地でも探すと思いますが、自分の趣味の工作の場合だと必要充分性能で入手しやすい矢崎を使っちゃうと思います。
または、手持ちの余った怪しいハーネスをちょん切って適当に使っちゃうかなあ。
全然参考意見になってなくてすみません。
メーデーです。
特になにもなかったんですが、来てみました。
どうでしょうか最近の皆さんのHID事情は?
身近なところでは、
オクの55Wの中華が切れた!不良品やろ!?文句言ってくる!って言ってたので、事情を説明してなだめたり、
中華バラスト丸出しで、表のステッカーには、
□35W □55W
って書いてあって、思いっきり35Wの方にチェックしてあるヤシを買わされてて、「国産品で15000円って言われた。安いやろ?」って仰るので、それは中華を日本人が扱っているものだと淡々と説明したり、
もう段々となにが正しくてどうすればいいのかよくわからない感じになってきました。
なんなんでしょうね70Wとか。何のための装置なんでしょう?発火装置ですかね。もう効率の為のHIDという時代では無くなってしまったんでしょうか?
でも愚痴っててもしょうがないのですが。
特になにもなかったんですが、来てみました。
どうでしょうか最近の皆さんのHID事情は?
身近なところでは、
オクの55Wの中華が切れた!不良品やろ!?文句言ってくる!って言ってたので、事情を説明してなだめたり、
中華バラスト丸出しで、表のステッカーには、
□35W □55W
って書いてあって、思いっきり35Wの方にチェックしてあるヤシを買わされてて、「国産品で15000円って言われた。安いやろ?」って仰るので、それは中華を日本人が扱っているものだと淡々と説明したり、
もう段々となにが正しくてどうすればいいのかよくわからない感じになってきました。
なんなんでしょうね70Wとか。何のための装置なんでしょう?発火装置ですかね。もう効率の為のHIDという時代では無くなってしまったんでしょうか?
でも愚痴っててもしょうがないのですが。
こちらではご無沙汰しております。皆様お元気そうで何よりです。
メーデーは、議会の式典とさらにお子様むけヒーローショーの照明のお仕事などしてました。
今だと派遣社員の人には、メーデー?ナニソレ?みたいな状況みたいですが。
さてさて、ここにいらっしゃる方たちは流行に惑わされず、本質をしっかり悟ってしまった方々が多いと思うので、意外と純正バーナー流用だったり、バラストも国産35W品を使っていたりする割合も多いんじゃないかと思います。
どうも、HIDのDIY取り付けと言うのは、いじる要素がだんだんなくなってきてしまった車の中でも難易度が低めな作業で、ドレスアップとしてのアイテム価値が高めになっているんじゃないかと思うようになりました。
だから、実際はどうであれ、色温度表記が高いほうがかっこいいとか、出力は大きいほうがなんか気分良いとかそういう方向かと。
リレー取り付けに関しても、意味もわからず付いているとカッコいいからリレーを付けるんだと言う人もいるようで、ホット稲妻のようなアイテムと変わらないのでしょう。
一方、悪徳業者はリレー付きじゃないと売れなくなっているところをコストを削減したいために、リレーレスで高性能とか謳っているのはなかなか笑わせてくれるなあと感心します。
先日、友人のところから知り合いが付けてくれって言うからHIDつけてやったんだけど、そのときに大量にH4ハロゲン出たから要る?って聞かれまして、座金だけ欲しいから貰うよと貰ってきたら、ハロゲンはオスラムや小糸の一流品でした。なんかもったいないです。
しかし、発光効率だけで考えたら、今だとアイスクリーム型の電球型蛍光灯のほうが発光効率が高いんですよ。商用設備のライティングでは、HIDは廃れてしまって、ちょっと終わってしまった技術の感じになってたりします。蛍光灯のほうがメインですし、LEDが旬になってきてます。
車用HIDが出現したばかりの時期には蛍光灯ヘッドランプの研究もされていました。が、技術的なところより、未来的なイメージがないから流行らないんで却下と言う経緯がありました。実際、温度特性がシビアで、極寒だとすごく暗くなっちゃったりとか、配光的にフラッドに当てるのは向いてるが、スパッと切れないのでヘッドライトに使うにはどうなのよとか、そんな問題もあったんですが。
しかし、今だと70Wですか。球が35Wのままだと70Wは許容限界値だったりするんでそれで通常使うのは無理なはずなのですが、入力電力70Wで実際のところは55W程度でしょうから、これもただの詐称なんでしょうね。
気になるのが、封入部分のつくりがいい加減な球が多いので、35W球に55W掛けてガス圧が上がった場合、内部のガスがリークして寿命が大幅に縮んじゃうんじゃないかと言う点です。
バラストも無理して動くので寿命が短そうです。
信じられない安い値段の中華は、球の中の金属ケチって水銀といいところスカンジウムしか入っていないようなのも増えてるんじゃないかと推測します。暗くて水色っぽく見える奴はその線が濃厚です。点灯した瞬間だけやけに明るかったら間違い無しです。
次の高付加価値商品はLEDヘッドライトだと思いますが、LEDは現状中華クオリティーのものは安いのはあっても、超高輝度のはまだまだだと思うのですが、イーグルアイあたりの韓国製のものはいかがなものでしょうか?<おぎすけ さん
しかし、不思議なのが、中華中華言われてはいますが、なぜ具体的にどこの管球メーカーが作っていると明記してある物がほとんどないのでしょう?中華でも、この球のメーカーなら問題ないとかそういうブランドイメージ戦略で売っていくことも可能だと思うのですが、聞いたことがないですね。知られるといろいろマズイことだらけだからあえて出さないようにしてるのでしょうかね?
個人的には、以前調べて判明したPhilipsライセンスのTCなんかは破格でなくてもいいので、それなりに安く手に入れば悪くないかなあと思っているのですが。
おぎすけさんはここら辺の事情には非常に詳しいと思いますが、おおっぴらに出来ないこともたくさんあるような気もしますし。
なんかいろいろとりとめのない話で済みませんです。
メーデーは、議会の式典とさらにお子様むけヒーローショーの照明のお仕事などしてました。
今だと派遣社員の人には、メーデー?ナニソレ?みたいな状況みたいですが。
さてさて、ここにいらっしゃる方たちは流行に惑わされず、本質をしっかり悟ってしまった方々が多いと思うので、意外と純正バーナー流用だったり、バラストも国産35W品を使っていたりする割合も多いんじゃないかと思います。
どうも、HIDのDIY取り付けと言うのは、いじる要素がだんだんなくなってきてしまった車の中でも難易度が低めな作業で、ドレスアップとしてのアイテム価値が高めになっているんじゃないかと思うようになりました。
だから、実際はどうであれ、色温度表記が高いほうがかっこいいとか、出力は大きいほうがなんか気分良いとかそういう方向かと。
リレー取り付けに関しても、意味もわからず付いているとカッコいいからリレーを付けるんだと言う人もいるようで、ホット稲妻のようなアイテムと変わらないのでしょう。
一方、悪徳業者はリレー付きじゃないと売れなくなっているところをコストを削減したいために、リレーレスで高性能とか謳っているのはなかなか笑わせてくれるなあと感心します。
先日、友人のところから知り合いが付けてくれって言うからHIDつけてやったんだけど、そのときに大量にH4ハロゲン出たから要る?って聞かれまして、座金だけ欲しいから貰うよと貰ってきたら、ハロゲンはオスラムや小糸の一流品でした。なんかもったいないです。
しかし、発光効率だけで考えたら、今だとアイスクリーム型の電球型蛍光灯のほうが発光効率が高いんですよ。商用設備のライティングでは、HIDは廃れてしまって、ちょっと終わってしまった技術の感じになってたりします。蛍光灯のほうがメインですし、LEDが旬になってきてます。
車用HIDが出現したばかりの時期には蛍光灯ヘッドランプの研究もされていました。が、技術的なところより、未来的なイメージがないから流行らないんで却下と言う経緯がありました。実際、温度特性がシビアで、極寒だとすごく暗くなっちゃったりとか、配光的にフラッドに当てるのは向いてるが、スパッと切れないのでヘッドライトに使うにはどうなのよとか、そんな問題もあったんですが。
しかし、今だと70Wですか。球が35Wのままだと70Wは許容限界値だったりするんでそれで通常使うのは無理なはずなのですが、入力電力70Wで実際のところは55W程度でしょうから、これもただの詐称なんでしょうね。
気になるのが、封入部分のつくりがいい加減な球が多いので、35W球に55W掛けてガス圧が上がった場合、内部のガスがリークして寿命が大幅に縮んじゃうんじゃないかと言う点です。
バラストも無理して動くので寿命が短そうです。
信じられない安い値段の中華は、球の中の金属ケチって水銀といいところスカンジウムしか入っていないようなのも増えてるんじゃないかと推測します。暗くて水色っぽく見える奴はその線が濃厚です。点灯した瞬間だけやけに明るかったら間違い無しです。
次の高付加価値商品はLEDヘッドライトだと思いますが、LEDは現状中華クオリティーのものは安いのはあっても、超高輝度のはまだまだだと思うのですが、イーグルアイあたりの韓国製のものはいかがなものでしょうか?<おぎすけ さん
しかし、不思議なのが、中華中華言われてはいますが、なぜ具体的にどこの管球メーカーが作っていると明記してある物がほとんどないのでしょう?中華でも、この球のメーカーなら問題ないとかそういうブランドイメージ戦略で売っていくことも可能だと思うのですが、聞いたことがないですね。知られるといろいろマズイことだらけだからあえて出さないようにしてるのでしょうかね?
個人的には、以前調べて判明したPhilipsライセンスのTCなんかは破格でなくてもいいので、それなりに安く手に入れば悪くないかなあと思っているのですが。
おぎすけさんはここら辺の事情には非常に詳しいと思いますが、おおっぴらに出来ないこともたくさんあるような気もしますし。
なんかいろいろとりとめのない話で済みませんです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
HID! HID! HID! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-