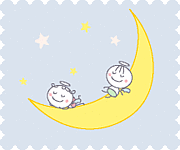「人身保護命令」と裁判官――暴走する司法
1 「人身保護命令」と「ヘビアス・コーパス」
昭和23年に制定・施行された「人身保護法」は、憲法第34条後段「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」という、英米の人身保護法を想起させる規定に基づくもので、人身保護令状についての詳細な手続法である。
英米の人身保護法は、人身保護令状(writ of habeas corpus )を中心として発達したものである。 habeasは haveを意味し、corpusはbodyを意味するもので、habeas corpusはyou have the body、すなわち「被拘束者の身柄を差出せ」との意味を有する。そして、人身保護令状は、他人を拘束した者に対し、令状を発する裁判所又は裁判官が被拘束者の利益のために考慮するいかなる事項をも実行し、服従し、受忍させるために、被拘束者の身柄を一定の日時、場所に、逮捕拘禁の月日及び事由を添えて、出頭させることを命ずる令状である。それは、法律中において最も有名な令状であり、幾世紀の間、個人の自由に対する違法な侵害を排除するために採用されて来たので、しばしば「自由の大令状」と称される。
ところが、日本では、人身保護命令が本来の意味するところに従って使われることは皆無である一方、専ら父母間における子の身柄争奪に濫用されている。しかも、人身保護法が「手続法」であることを理解しないから、人身保護法の手続は「子の身柄を父母間で移動させる」手段に堕して、ことごとく法が無視されるのである。したがって、裁判所は無法地帯と化している。
2 命令不服従の制裁――「裁判所侮辱罪」
人身保護法による救済の要諦は、被拘束者を審問期日に在廷させて、認容判決の言渡しによって「直ちに釈放する」(法16条3項)ことにある。人身保護法は二審制であるが、一審判決の言渡しによって効力を生じ、「釈放」が実現するのである。
そこで、被拘束者を審問期日に出頭させるために、拘束者に対して人身保護命令が発される(法12条2項)。人身保護命令を発して開く第1回審問期日に被拘束者が出頭しない場合、認容判決を言渡しても、現実の「釈放」はできないから、期日が延期される。
また、拘束者が人身保護命令に従わずに被拘束者を出頭させない場合、勾引や勾留の制裁を受けることがある(法18条、規則39条)。人身保護法の手続が英米のヘビアス・コーパスに由来するというものの、英米では、命令違反の制裁は裁判所侮辱罪で対処されるのに対し、官僚裁判官制度の日本では、裁判所侮辱罪の制度ができるまで、やむなく刑事訴訟法の勾引・勾留を準用したという。
しかるに、人身保護法制定から60年余経過してなお、裁判所侮辱罪は影も形もない。その理由を考えると、英米の裁判官が「一元判事」であるのに対し、日本の裁判官は、一人で裁判できない「判事補」までいて、昇進制の下におかれた官僚裁判官だということであろう。このような裁判官に、「自由の大令状」を発布する崇高な権限を付与することは不可能である。
3 弁護士会(子どもの権利委員会)の犯罪
ところで、父母間の幼い子どもの「身柄奪取」に人身保護法の手続が使われる際の最大の問題は、被拘束者である子どもの「人格」が完全に無視されることにある。
人身保護法における「請求者」は形式的当事者にすぎず、実質的当事者は「被拘束者」である。したがって、被拘束者は一切の訴訟行為をすることができ、それが請求者の訴訟行為と抵触する場合には、抵触する範囲において請求者の訴訟行為は効力を失うとされている(規則34条)。そして、「請求者」は誰でもなれるが、弁護士強制である(法3条)。また、被拘束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。
しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判所は弁護士会に推薦を依嘱し、弁護士会は「子どもの権利委員会」から推薦し、国選代理人が選任される。ところが、この国選代理人は、被拘束者の意思能力を認めないし、その主張さえしようとしない。そして、やることと言えば、家裁調査官のような調査であり、「請求者に引渡す」という認容判決に沿った意見を具申するのである。人身保護法の手続は、家事審判手続ではないのだから、これでは弁護士の役割を全く果たしていないし、被拘束者に対する背信行為である。
このような茶番劇が人身保護法の手続において繰り広げられるのは、裁判官も弁護士も、人身保護法の手続を、子の身柄奪取の手段としてしか念頭になく、法を侵害していることの自覚すらないからである。私は、平成20年4月に初めて拘束者代理人として事件受任して以来、人身保護法のイロハについて理解している法曹に出会ったことがない。そして、司法の暴虐により、この依頼者は、自殺してしまったのである。
「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母間の子の身柄争奪紛争について人身保護法による救済を抑制する最高裁判決(可部判決)も出ている。それにもかかわらず、弁護士会の「子どもの権利委員会」は、民法の離婚後単独親権制について疑問も持たず、家庭裁判所が「監護者指定」「親権者指定」の名目で、親権喪失事由のない親から親権・監護権を剥奪する不正義を疑わずに、「司法拉致」の方法として人身保護法の手続を用いることに邁進してきた。「子どもの権利」などと言いながら、親子を迫害することに加担している弁護士こそ、社会的に断罪されるべきである。
(2010,9,20 後藤富士子)
1 「人身保護命令」と「ヘビアス・コーパス」
昭和23年に制定・施行された「人身保護法」は、憲法第34条後段「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」という、英米の人身保護法を想起させる規定に基づくもので、人身保護令状についての詳細な手続法である。
英米の人身保護法は、人身保護令状(writ of habeas corpus )を中心として発達したものである。 habeasは haveを意味し、corpusはbodyを意味するもので、habeas corpusはyou have the body、すなわち「被拘束者の身柄を差出せ」との意味を有する。そして、人身保護令状は、他人を拘束した者に対し、令状を発する裁判所又は裁判官が被拘束者の利益のために考慮するいかなる事項をも実行し、服従し、受忍させるために、被拘束者の身柄を一定の日時、場所に、逮捕拘禁の月日及び事由を添えて、出頭させることを命ずる令状である。それは、法律中において最も有名な令状であり、幾世紀の間、個人の自由に対する違法な侵害を排除するために採用されて来たので、しばしば「自由の大令状」と称される。
ところが、日本では、人身保護命令が本来の意味するところに従って使われることは皆無である一方、専ら父母間における子の身柄争奪に濫用されている。しかも、人身保護法が「手続法」であることを理解しないから、人身保護法の手続は「子の身柄を父母間で移動させる」手段に堕して、ことごとく法が無視されるのである。したがって、裁判所は無法地帯と化している。
2 命令不服従の制裁――「裁判所侮辱罪」
人身保護法による救済の要諦は、被拘束者を審問期日に在廷させて、認容判決の言渡しによって「直ちに釈放する」(法16条3項)ことにある。人身保護法は二審制であるが、一審判決の言渡しによって効力を生じ、「釈放」が実現するのである。
そこで、被拘束者を審問期日に出頭させるために、拘束者に対して人身保護命令が発される(法12条2項)。人身保護命令を発して開く第1回審問期日に被拘束者が出頭しない場合、認容判決を言渡しても、現実の「釈放」はできないから、期日が延期される。
また、拘束者が人身保護命令に従わずに被拘束者を出頭させない場合、勾引や勾留の制裁を受けることがある(法18条、規則39条)。人身保護法の手続が英米のヘビアス・コーパスに由来するというものの、英米では、命令違反の制裁は裁判所侮辱罪で対処されるのに対し、官僚裁判官制度の日本では、裁判所侮辱罪の制度ができるまで、やむなく刑事訴訟法の勾引・勾留を準用したという。
しかるに、人身保護法制定から60年余経過してなお、裁判所侮辱罪は影も形もない。その理由を考えると、英米の裁判官が「一元判事」であるのに対し、日本の裁判官は、一人で裁判できない「判事補」までいて、昇進制の下におかれた官僚裁判官だということであろう。このような裁判官に、「自由の大令状」を発布する崇高な権限を付与することは不可能である。
3 弁護士会(子どもの権利委員会)の犯罪
ところで、父母間の幼い子どもの「身柄奪取」に人身保護法の手続が使われる際の最大の問題は、被拘束者である子どもの「人格」が完全に無視されることにある。
人身保護法における「請求者」は形式的当事者にすぎず、実質的当事者は「被拘束者」である。したがって、被拘束者は一切の訴訟行為をすることができ、それが請求者の訴訟行為と抵触する場合には、抵触する範囲において請求者の訴訟行為は効力を失うとされている(規則34条)。そして、「請求者」は誰でもなれるが、弁護士強制である(法3条)。また、被拘束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。
しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判所は弁護士会に推薦を依嘱し、弁護士会は「子どもの権利委員会」から推薦し、国選代理人が選任される。ところが、この国選代理人は、被拘束者の意思能力を認めないし、その主張さえしようとしない。そして、やることと言えば、家裁調査官のような調査であり、「請求者に引渡す」という認容判決に沿った意見を具申するのである。人身保護法の手続は、家事審判手続ではないのだから、これでは弁護士の役割を全く果たしていないし、被拘束者に対する背信行為である。
このような茶番劇が人身保護法の手続において繰り広げられるのは、裁判官も弁護士も、人身保護法の手続を、子の身柄奪取の手段としてしか念頭になく、法を侵害していることの自覚すらないからである。私は、平成20年4月に初めて拘束者代理人として事件受任して以来、人身保護法のイロハについて理解している法曹に出会ったことがない。そして、司法の暴虐により、この依頼者は、自殺してしまったのである。
「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母間の子の身柄争奪紛争について人身保護法による救済を抑制する最高裁判決(可部判決)も出ている。それにもかかわらず、弁護士会の「子どもの権利委員会」は、民法の離婚後単独親権制について疑問も持たず、家庭裁判所が「監護者指定」「親権者指定」の名目で、親権喪失事由のない親から親権・監護権を剥奪する不正義を疑わずに、「司法拉致」の方法として人身保護法の手続を用いることに邁進してきた。「子どもの権利」などと言いながら、親子を迫害することに加担している弁護士こそ、社会的に断罪されるべきである。
(2010,9,20 後藤富士子)
|
|
|
|
コメント(10)
「子育てする親の権利」を考える
「親権」という語彙が、「親の子に対する支配権」のように感じるということで、子どもの権利を尊重する立場から批判がある。これを法的に表現すると、「親権は子に対する義務(責任)であって、親の権利ではない」という。しかし、それは間違っていると思う。むしろ、声を大にして「親の権利」と叫びたい。
たとえば、「配偶者による子の拉致」事件では、親権を共同で行使する父母の一方が他方の親権行使を不可能にする。私は、こういう事態は、拉致した親による他方の親に対する不法行為(親権侵害)としか思えないが、それが司法の世界では通じない。また、離婚は親権喪失事由ではないのに、離婚により父母のどちらか一方が親権を喪失するし、非親権者と子の交流(親子の絆の構築)についても「面接交渉は親の権利ではない」として、「子の福祉」の名の下に監護親の意向次第と処理される。このように、理不尽に「子育て」から排除される私の依頼者は皆、「愛情深い親」である。その嘆き苦しみを見ているのも辛いが、こんなことして一体なにかよいことがあるのか、不思議でならない。
具体的事例でも、「単独親権」だから、家裁の調査官調査も「どちらがいいか」「現状が問題ないか」という枠組の中で「事実の調査」をした挙句、「子の福祉に適う」という規範的評価を下す。両親が別居すれば、子どもは一方の親と同居し、他方の親とは別居する。同居親と子の関係が良好だからといって、別居親を「子育て」から排除する論理必然性はない。「子育て」から排除しなければならないような親は、親権喪失宣告をすればいい。そうすると、「単独か共同か」という以前に、「親権の権利性」が理論上の大問題であることに思い至る。
ドイツでは、1979年の親権法全面改正で「親権」は「親の配慮」という用語に変更されたが、1997年の改正で「両親は、未成年の子を配慮する義務を負い、かつ権利を有する。親の配慮は、子の身上のための配慮と子の財産のための配慮を含む」という現行法になった。つまり、両親による共同性―父母間に婚姻関係がなくても共同配慮であることになったが、それ以上に「我が意を得たり」と思うのは、親の配慮は「最高の人格的権利」であり放棄できないとされ、また、子に対しては義務性をもつが第三者に対しては絶対的効力を有するとされていることである。したがって、国家が親に成り代わって「子の福祉」を実現すべく、単独親権者・単独監護者を指定することなどできないし、反対に、単独配慮や養子縁組の同意など親の配慮を自ら手放すときに親同士の同意では足りず、裁判所の司法判断を要する。つまり、日本の親権制度と正反対になっている。
ところで、児童虐待防止の観点から、民法に「親権の一時停止」条項を加える案が法制審議会から出ている。しかし、これは全く噴飯物である。まず指摘したいのは、「親権喪失」に期限がないことで児童相談所が躊躇するというが、親権喪失事由が消滅したときは取り消すことができる(民法836条)。だから、「一時停止」でなく「喪失」でも充分運用できる。より重大なのは、児童相談所の「子育て」理念で、「虐待する親」を排除して保護施設収容によって公的機関が子どもを育てるという発想である。しかしながら、これで子どもは幸せになるのであろうか?成人になるまで施設で暮すというのでいいのだろうか。成人になった途端放り出されるのも問題である。一方、親権者の内縁関係者など、親権を有さない者による虐待には対応できない。こう考えてくると、虐待に対処するには、親権制度よりも、児童福祉法や刑事法を適用することの方が遥かに効果的であろう。
ここに現れているように、日本の法律家は、「法の精神」というものに凄く鈍感だと思う。子を虐待などせず、慈しみ育てる能力も意欲も充分な親を、離婚や未婚で排除する「単独親権制」をそのままにして、離婚・未婚により単独親権下にある子の虐待を防止するために民法の親権規定を改正しようというのだから。父母間の婚姻関係の有無に関わらず共同親権とすれば、子が虐待の被害を受ける機会も減るだろうし、虐待があれば、「親権喪失宣告」など制度本来の趣旨に則して対応できる。すなわち、「虐待の防止」は、虐待があった際の事後的権力的対策を強化すること以上に、「親子の自然の情愛」を基礎にした親権制度―共同親権制度を充実させることによって「子育てする親」の自覚を促すことの方が遥かに建設的である。「子どもは社会が育てる」というよりも、「子育てできる親を社会が育てる」べきであろう。
(2010.12.23 後藤富士子)
「親権」という語彙が、「親の子に対する支配権」のように感じるということで、子どもの権利を尊重する立場から批判がある。これを法的に表現すると、「親権は子に対する義務(責任)であって、親の権利ではない」という。しかし、それは間違っていると思う。むしろ、声を大にして「親の権利」と叫びたい。
たとえば、「配偶者による子の拉致」事件では、親権を共同で行使する父母の一方が他方の親権行使を不可能にする。私は、こういう事態は、拉致した親による他方の親に対する不法行為(親権侵害)としか思えないが、それが司法の世界では通じない。また、離婚は親権喪失事由ではないのに、離婚により父母のどちらか一方が親権を喪失するし、非親権者と子の交流(親子の絆の構築)についても「面接交渉は親の権利ではない」として、「子の福祉」の名の下に監護親の意向次第と処理される。このように、理不尽に「子育て」から排除される私の依頼者は皆、「愛情深い親」である。その嘆き苦しみを見ているのも辛いが、こんなことして一体なにかよいことがあるのか、不思議でならない。
具体的事例でも、「単独親権」だから、家裁の調査官調査も「どちらがいいか」「現状が問題ないか」という枠組の中で「事実の調査」をした挙句、「子の福祉に適う」という規範的評価を下す。両親が別居すれば、子どもは一方の親と同居し、他方の親とは別居する。同居親と子の関係が良好だからといって、別居親を「子育て」から排除する論理必然性はない。「子育て」から排除しなければならないような親は、親権喪失宣告をすればいい。そうすると、「単独か共同か」という以前に、「親権の権利性」が理論上の大問題であることに思い至る。
ドイツでは、1979年の親権法全面改正で「親権」は「親の配慮」という用語に変更されたが、1997年の改正で「両親は、未成年の子を配慮する義務を負い、かつ権利を有する。親の配慮は、子の身上のための配慮と子の財産のための配慮を含む」という現行法になった。つまり、両親による共同性―父母間に婚姻関係がなくても共同配慮であることになったが、それ以上に「我が意を得たり」と思うのは、親の配慮は「最高の人格的権利」であり放棄できないとされ、また、子に対しては義務性をもつが第三者に対しては絶対的効力を有するとされていることである。したがって、国家が親に成り代わって「子の福祉」を実現すべく、単独親権者・単独監護者を指定することなどできないし、反対に、単独配慮や養子縁組の同意など親の配慮を自ら手放すときに親同士の同意では足りず、裁判所の司法判断を要する。つまり、日本の親権制度と正反対になっている。
ところで、児童虐待防止の観点から、民法に「親権の一時停止」条項を加える案が法制審議会から出ている。しかし、これは全く噴飯物である。まず指摘したいのは、「親権喪失」に期限がないことで児童相談所が躊躇するというが、親権喪失事由が消滅したときは取り消すことができる(民法836条)。だから、「一時停止」でなく「喪失」でも充分運用できる。より重大なのは、児童相談所の「子育て」理念で、「虐待する親」を排除して保護施設収容によって公的機関が子どもを育てるという発想である。しかしながら、これで子どもは幸せになるのであろうか?成人になるまで施設で暮すというのでいいのだろうか。成人になった途端放り出されるのも問題である。一方、親権者の内縁関係者など、親権を有さない者による虐待には対応できない。こう考えてくると、虐待に対処するには、親権制度よりも、児童福祉法や刑事法を適用することの方が遥かに効果的であろう。
ここに現れているように、日本の法律家は、「法の精神」というものに凄く鈍感だと思う。子を虐待などせず、慈しみ育てる能力も意欲も充分な親を、離婚や未婚で排除する「単独親権制」をそのままにして、離婚・未婚により単独親権下にある子の虐待を防止するために民法の親権規定を改正しようというのだから。父母間の婚姻関係の有無に関わらず共同親権とすれば、子が虐待の被害を受ける機会も減るだろうし、虐待があれば、「親権喪失宣告」など制度本来の趣旨に則して対応できる。すなわち、「虐待の防止」は、虐待があった際の事後的権力的対策を強化すること以上に、「親子の自然の情愛」を基礎にした親権制度―共同親権制度を充実させることによって「子育てする親」の自覚を促すことの方が遥かに建設的である。「子どもは社会が育てる」というよりも、「子育てできる親を社会が育てる」べきであろう。
(2010.12.23 後藤富士子)
単独親権制と共同監護―民法の趣旨
2011年5月10日 弁護士 後 藤 富 士 子
1 手続法と実体法の倒錯
「親権者を父母から父へ変更する」旨の審判国賠訴訟の第1審判決は、「親権者の指定又は変更の審判(家事審判法9条1項乙類7号)は、本来的に民事行政の性質を有する非訟手続においてされるものではあるが、対立する当事者間の紛争性が高く、家事審判官のした事実認定、法令の解釈適用及び具体的事案に対する判断について、不服申立制度を設けて当該手続において是正されることを予定していることなど争訟的な性質を有している。」と判示している。
しかしながら、家事審判法は手続法であり、実体法である民法よりも優位にあるはずはなく、親権者の指定又は変更の審判も、結局は民法の単独親権制の解釈問題に帰する。換言すると、単独親権制の解釈として、親権・監護権が親の固有の法的権利であることを否定する必然性があるのか、である。
また、婚姻中の共同親権を離婚に伴い単独親権にするのは「親権者指定」であって、「親権者変更」ではない。すなわち、「親権者変更」審判は、子が単独親権に服している場合に限って許されるのであり(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版47頁)、共同親権を単独親権に「親権者変更」することなどできない。
のみならず、「親権者指定」と「親権者変更」は、司法介入の性質において明確な差がある。すなわち、離婚の際の「単独親権者指定」は、一義的には父母の協議に委ねられているし、協議が調わない場合、審判にしろ、離婚判決にしろ、「協議に代わる」ものとしてされるのである(民法819条1項、5項)。これに対し、「親権者変更」は、父母間の協議・調停・審判・判決によって父母の一方が親権者と定められた後に、「子の利益のため必要がある」と認めるとき、家庭裁判所の審判(または調停)により、親権者を他の一方に変更するものであり、そもそも当事者間の協議だけによることはできず、「協議に代わる」ものとしてされるわけではないうえ、申立権者は「子の親族」に拡張されている(民法819条6項)。
そうすると、単独親権制が専ら親の親権を剥奪するだけのものとして運用されるなら、それが非訟手続によることは許されないことになるから、ここでも手続法と実体法の倒錯が問われるべきであろう。
2011年5月10日 弁護士 後 藤 富 士 子
1 手続法と実体法の倒錯
「親権者を父母から父へ変更する」旨の審判国賠訴訟の第1審判決は、「親権者の指定又は変更の審判(家事審判法9条1項乙類7号)は、本来的に民事行政の性質を有する非訟手続においてされるものではあるが、対立する当事者間の紛争性が高く、家事審判官のした事実認定、法令の解釈適用及び具体的事案に対する判断について、不服申立制度を設けて当該手続において是正されることを予定していることなど争訟的な性質を有している。」と判示している。
しかしながら、家事審判法は手続法であり、実体法である民法よりも優位にあるはずはなく、親権者の指定又は変更の審判も、結局は民法の単独親権制の解釈問題に帰する。換言すると、単独親権制の解釈として、親権・監護権が親の固有の法的権利であることを否定する必然性があるのか、である。
また、婚姻中の共同親権を離婚に伴い単独親権にするのは「親権者指定」であって、「親権者変更」ではない。すなわち、「親権者変更」審判は、子が単独親権に服している場合に限って許されるのであり(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版47頁)、共同親権を単独親権に「親権者変更」することなどできない。
のみならず、「親権者指定」と「親権者変更」は、司法介入の性質において明確な差がある。すなわち、離婚の際の「単独親権者指定」は、一義的には父母の協議に委ねられているし、協議が調わない場合、審判にしろ、離婚判決にしろ、「協議に代わる」ものとしてされるのである(民法819条1項、5項)。これに対し、「親権者変更」は、父母間の協議・調停・審判・判決によって父母の一方が親権者と定められた後に、「子の利益のため必要がある」と認めるとき、家庭裁判所の審判(または調停)により、親権者を他の一方に変更するものであり、そもそも当事者間の協議だけによることはできず、「協議に代わる」ものとしてされるわけではないうえ、申立権者は「子の親族」に拡張されている(民法819条6項)。
そうすると、単独親権制が専ら親の親権を剥奪するだけのものとして運用されるなら、それが非訟手続によることは許されないことになるから、ここでも手続法と実体法の倒錯が問われるべきであろう。
2 「親権」の法的権利性
「親権」の効力について、民法は、?監護教育の権利義務、?居所指定権、?懲戒権、?職業許可権、?財産管理権と代理権を定めている(820〜824条)。
本件で現実に問題となるのは、?と?だけである。そして、?については、婚姻中であっても父母の意見・見解が一致せずに共同行使ができないことがある一方、離婚・別居したからといって共同行使が不可能になるわけではない。現に、欧米では離婚後も共同親権・共同監護とする法制度に改正されており、共同監護について父母の合意があれば、原則として裁判所は介入しない。裁判所が介入するのは、単独親権・監護の主張がある場合や、合意が履行されない場合である(甲28参照)。また、?についても、父母が離婚して別居すると子どもの居所は父母のどちらかになるのが自然であるが、どちらと同居するかについて父母が合意することは十分可能である。現に9割を占める協議離婚で、その合意をしている。
そうすると、離婚後の単独親権制の趣旨は、片親を「子育て」から排除することにあるのではなく、子の地位の安定など専ら「子の利益のため」であることが明らかである。
そこで、離婚後の単独親権制がどのように運用されてきたかについて、アメリカ(カリフォルニア)とドイツを概観する。
まず、カリフォルニアで離婚後も共同養育とされたのは、1980年のことである。しかし、単独親権制の下でも100年に亘り、別居親には隔週末の面会交流権が法律で保護され、強制力をもつ権利として保障されていた(甲26)。
一方、ドイツでは、1979年に親権法の全面改正がされ、「親権」という用語は「親の配慮」という用語に変更されるなどしたが、離婚により共同配慮は現実的ではなくなり、子に明確な生活関係を確保すべきだとする見解に基づき、単独配慮制が維持された。そして、単独配慮制の下で、どちらを単独配慮親にするかという基準として、「主たる養育者の重視」理論が席巻した。これは、ゴールドシュタインらの『子の福祉を超えて―精神分析と良識による監護紛争の解決』で唱導された見解で、子にとっての特定の関係人との絆=心理的親子関係が重視され、面接交渉でさえ子の忠誠葛藤を引き起こすとされている。しかし、重要なことは、基本法第6条2項で「子の養育および教育は、両親の自然の権利であり、かつ、何よりもまず両親に課せられている義務である。その実行に対しては、国家共同社会がこれを監視する。」とされていることである。この条項に基づき、1982年11月3日、婚姻外の親の単独配慮規定について無効とする違憲判決が出されている(甲28/143〜144頁)。
このように、離婚後の単独親権制は、その前提として「親の固有の法的権利」を論理必然的に否定するものではないのであり、日本の民法だけが「親の固有の法的権利」を否定していると解釈すべき根拠は皆無である。むしろ、国民主権の下で、国家が親をさしおいて子の養育監護権をもつはずがない。また、「子の福祉」のためというパターナリズムによって「家族の自治」を否定して国家の管理下に家族を置くことは、全体主義に通じる危険なものがある。
結局、現行民法における親権・監護権につき、「親の固有の法的権利」であること否定する解釈は、法文上に根拠がなく、許されないというほかない。むしろ、単独親権制によって「親の固有の法的権利」であることを否定するのでは、本末転倒ではないか。
「親権」の効力について、民法は、?監護教育の権利義務、?居所指定権、?懲戒権、?職業許可権、?財産管理権と代理権を定めている(820〜824条)。
本件で現実に問題となるのは、?と?だけである。そして、?については、婚姻中であっても父母の意見・見解が一致せずに共同行使ができないことがある一方、離婚・別居したからといって共同行使が不可能になるわけではない。現に、欧米では離婚後も共同親権・共同監護とする法制度に改正されており、共同監護について父母の合意があれば、原則として裁判所は介入しない。裁判所が介入するのは、単独親権・監護の主張がある場合や、合意が履行されない場合である(甲28参照)。また、?についても、父母が離婚して別居すると子どもの居所は父母のどちらかになるのが自然であるが、どちらと同居するかについて父母が合意することは十分可能である。現に9割を占める協議離婚で、その合意をしている。
そうすると、離婚後の単独親権制の趣旨は、片親を「子育て」から排除することにあるのではなく、子の地位の安定など専ら「子の利益のため」であることが明らかである。
そこで、離婚後の単独親権制がどのように運用されてきたかについて、アメリカ(カリフォルニア)とドイツを概観する。
まず、カリフォルニアで離婚後も共同養育とされたのは、1980年のことである。しかし、単独親権制の下でも100年に亘り、別居親には隔週末の面会交流権が法律で保護され、強制力をもつ権利として保障されていた(甲26)。
一方、ドイツでは、1979年に親権法の全面改正がされ、「親権」という用語は「親の配慮」という用語に変更されるなどしたが、離婚により共同配慮は現実的ではなくなり、子に明確な生活関係を確保すべきだとする見解に基づき、単独配慮制が維持された。そして、単独配慮制の下で、どちらを単独配慮親にするかという基準として、「主たる養育者の重視」理論が席巻した。これは、ゴールドシュタインらの『子の福祉を超えて―精神分析と良識による監護紛争の解決』で唱導された見解で、子にとっての特定の関係人との絆=心理的親子関係が重視され、面接交渉でさえ子の忠誠葛藤を引き起こすとされている。しかし、重要なことは、基本法第6条2項で「子の養育および教育は、両親の自然の権利であり、かつ、何よりもまず両親に課せられている義務である。その実行に対しては、国家共同社会がこれを監視する。」とされていることである。この条項に基づき、1982年11月3日、婚姻外の親の単独配慮規定について無効とする違憲判決が出されている(甲28/143〜144頁)。
このように、離婚後の単独親権制は、その前提として「親の固有の法的権利」を論理必然的に否定するものではないのであり、日本の民法だけが「親の固有の法的権利」を否定していると解釈すべき根拠は皆無である。むしろ、国民主権の下で、国家が親をさしおいて子の養育監護権をもつはずがない。また、「子の福祉」のためというパターナリズムによって「家族の自治」を否定して国家の管理下に家族を置くことは、全体主義に通じる危険なものがある。
結局、現行民法における親権・監護権につき、「親の固有の法的権利」であること否定する解釈は、法文上に根拠がなく、許されないというほかない。むしろ、単独親権制によって「親の固有の法的権利」であることを否定するのでは、本末転倒ではないか。
3 現行民法の体系的・合理的解釈
前記したように、「親権」が親の固有の法的権利であることに鑑みると、単独親権制の運用が非訟手続でいいはずはなかろう。
そもそも、民法上、子どもの「親権者」は、父と母だけである。養子であっても、「親権者」は、養父と養母だけである。すなわち、片親の死亡により単独親権になったのならともかく、離婚後の単独親権者指定や単独親権者変更は、「親権者でない親」が実在する。そして、離婚後単独親権制についていえば、「単独親権者指定」によって「親権者でなくなった親」は、親権喪失事由がないのにもかかわらず、「民法がそうなっている」というだけで親権を剥奪されるのである。しかも、その立法趣旨は、「父母が婚姻関係にないときには、親権の共同行使は不可能ないしは困難である」というにすぎない(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版36頁)。
確かに、民法第819条が定める単独親権制は、離婚に際し母も親権者となりうる途を拓き、また、認知にかかわらず一応依然として母を親権者としている点で、旧法に比べれば、より進歩的であることは否めない。しかし、それが「子の福祉」の立場からみて妥当かは、頗る疑問である。離婚により夫婦の絆は断たれても、親子の監護の絆は断たれてはならない。同様に、父母の未婚(非婚)も親子の監護の絆を断つ理由とはならない。子は、いかなる場合にも、父母に対し、監護を求めることができるとしなければならない。近時、非親権者の法的地位が論ぜられ、また立法論として婚姻中でない父母の共同親権・共同監護が主張されているのも、現行単独親権制の「all or nothing」という硬直性への反省である(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版19頁)。
ところで、現行法でも、民法第819条の硬直さを緩和するものとして、離婚父母の「共同監護」を可能とする規定がある。民法第766条(同788条で認知に準用)がそれである。これによれば、親権と監護権を父母に分属させることもできる。とはいえ、「監護権」は「親権」に包摂されるものであるから、理論的には「監護権のない親権」というのも観念できようが、現実には「共同監護」にならざるを得ない。このことは、婚姻中でも片親が単身赴任や長時間労働のために「片親家庭」というべき実態でも「共同親権」であることと比較しても納得できる。
かように、民法第766条の存在は、親の固有の権利である「親権」を全面的に剥奪することを想定していないことを理解させる。すなわち、父母の協議が調わない場合でも、「単独親権者指定」と「監護に関する処分」をセットで行うことによって父母の「共同監護」を導くことは、現行民法上可能である。そして、その場合こそ、非訟手続が妥当するというのが、民法の趣旨であろう。
(以 上)
前記したように、「親権」が親の固有の法的権利であることに鑑みると、単独親権制の運用が非訟手続でいいはずはなかろう。
そもそも、民法上、子どもの「親権者」は、父と母だけである。養子であっても、「親権者」は、養父と養母だけである。すなわち、片親の死亡により単独親権になったのならともかく、離婚後の単独親権者指定や単独親権者変更は、「親権者でない親」が実在する。そして、離婚後単独親権制についていえば、「単独親権者指定」によって「親権者でなくなった親」は、親権喪失事由がないのにもかかわらず、「民法がそうなっている」というだけで親権を剥奪されるのである。しかも、その立法趣旨は、「父母が婚姻関係にないときには、親権の共同行使は不可能ないしは困難である」というにすぎない(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版36頁)。
確かに、民法第819条が定める単独親権制は、離婚に際し母も親権者となりうる途を拓き、また、認知にかかわらず一応依然として母を親権者としている点で、旧法に比べれば、より進歩的であることは否めない。しかし、それが「子の福祉」の立場からみて妥当かは、頗る疑問である。離婚により夫婦の絆は断たれても、親子の監護の絆は断たれてはならない。同様に、父母の未婚(非婚)も親子の監護の絆を断つ理由とはならない。子は、いかなる場合にも、父母に対し、監護を求めることができるとしなければならない。近時、非親権者の法的地位が論ぜられ、また立法論として婚姻中でない父母の共同親権・共同監護が主張されているのも、現行単独親権制の「all or nothing」という硬直性への反省である(新版注釈民法25巻親族(5)改訂版19頁)。
ところで、現行法でも、民法第819条の硬直さを緩和するものとして、離婚父母の「共同監護」を可能とする規定がある。民法第766条(同788条で認知に準用)がそれである。これによれば、親権と監護権を父母に分属させることもできる。とはいえ、「監護権」は「親権」に包摂されるものであるから、理論的には「監護権のない親権」というのも観念できようが、現実には「共同監護」にならざるを得ない。このことは、婚姻中でも片親が単身赴任や長時間労働のために「片親家庭」というべき実態でも「共同親権」であることと比較しても納得できる。
かように、民法第766条の存在は、親の固有の権利である「親権」を全面的に剥奪することを想定していないことを理解させる。すなわち、父母の協議が調わない場合でも、「単独親権者指定」と「監護に関する処分」をセットで行うことによって父母の「共同監護」を導くことは、現行民法上可能である。そして、その場合こそ、非訟手続が妥当するというのが、民法の趣旨であろう。
(以 上)
DV生活保護受給と婚姻費用分担請求
2011年5月18日 弁護士 後藤 富士子
第1 夫婦の婚姻共同生活保持義務について
1 夫婦の同居・協力義務
憲法第24条1項は、婚姻は夫婦相互の協力により維持されなければならない旨を定め、民法第752条は、夫婦の同居義務、協力義務および扶助義務を定めている。すなわち、同居義務、協力義務を一方的に怠った配偶者が、他方に扶助義務を要求することが信義に反することは、法文上自明である。
しかるに、本件のように、妻が「DV被害者」を装って、ある日突然子どもを連れて行方をくらまし、弁護士を盾にして、離婚請求と婚姻費用分担請求を同時にしてくる「事件」が多発している。婚姻を破壊する妻にとって、夫婦の同居・協力義務は存在しないものであり、ただ婚姻費用分担請求権だけが存在するのである。しかも、このような場合、子どもを連れて行かなければ、婚姻費用分担請求が認められないことも熟知しているから、父子から収奪するために子どもを連れ去るのである。
そこで、この文脈の中で婚姻費用分担義務について検討する。
2 婚姻費用分担における夫婦平等原則
明治民法のもとでは、夫(または女戸主)が妻(または夫)の財産に対して使用収益権を持つ(旧799条)反面、婚姻費用を夫が負担すると規定されており(旧798条)、この分担者が無資力の場合に、夫婦相互の扶養義務(旧790条)の適用があると解釈されていた。これに対し、憲法24条の夫婦平等の原則に基づき、妻の財産に対する夫の使用収益権が廃止されるとともに、民法760条は婚姻費用についても夫婦が分担するものと改め、夫婦が平等の立場で、婚姻生活の維持・確保に共同責任を負うことを明らかにした。
そして、婚姻共同生活の存在する限り、婚姻費用分担が生活保持義務であることに異論はみられないが、婚姻費用の分担義務が法的問題として登場するのは圧倒的に夫婦が別居している場合についてである。しかも、離婚紛争の前哨戦として、離婚を請求する夫に対して別居中の妻が婚姻費用を請求するという事例が多く、夫婦関係の回復が困難な破綻状態にあることが多い(別冊法学セミナー基本法コンメンタール『親族』74〜76頁参照)、というのがかつての実態であった。
しかるに、本件もその典型であるが、「ある日突然に妻が子を拉致して行方がわからない」状態で、弁護士を盾にして、離婚と婚姻費用を請求してくるという、全く法の想定外の事態である。夫にしてみれば、「何が何だか分からない」という状態で、離婚意思もなければ、別居の意思もない。妻子が戻ってくることを願っている。それが、善良な夫の姿である。ところが、そこにDV防止法が立ち塞がるのである。
すなわち、このような妻の行為は、その動機がどうであれ、婚姻を破壊するものにほかならない。したがって、夫婦が平等の立場で、婚姻生活の維持・確保に共同責任を負うとする婚姻費用の分担の前提を欠く。そして、婚姻破壊者である妻が無収入のため何ら婚姻費用を分担しないでおきながら、収入があるというだけの理由で無責の夫に婚姻費用を分担させるのは、夫婦平等を極端に逸脱している。
2011年5月18日 弁護士 後藤 富士子
第1 夫婦の婚姻共同生活保持義務について
1 夫婦の同居・協力義務
憲法第24条1項は、婚姻は夫婦相互の協力により維持されなければならない旨を定め、民法第752条は、夫婦の同居義務、協力義務および扶助義務を定めている。すなわち、同居義務、協力義務を一方的に怠った配偶者が、他方に扶助義務を要求することが信義に反することは、法文上自明である。
しかるに、本件のように、妻が「DV被害者」を装って、ある日突然子どもを連れて行方をくらまし、弁護士を盾にして、離婚請求と婚姻費用分担請求を同時にしてくる「事件」が多発している。婚姻を破壊する妻にとって、夫婦の同居・協力義務は存在しないものであり、ただ婚姻費用分担請求権だけが存在するのである。しかも、このような場合、子どもを連れて行かなければ、婚姻費用分担請求が認められないことも熟知しているから、父子から収奪するために子どもを連れ去るのである。
そこで、この文脈の中で婚姻費用分担義務について検討する。
2 婚姻費用分担における夫婦平等原則
明治民法のもとでは、夫(または女戸主)が妻(または夫)の財産に対して使用収益権を持つ(旧799条)反面、婚姻費用を夫が負担すると規定されており(旧798条)、この分担者が無資力の場合に、夫婦相互の扶養義務(旧790条)の適用があると解釈されていた。これに対し、憲法24条の夫婦平等の原則に基づき、妻の財産に対する夫の使用収益権が廃止されるとともに、民法760条は婚姻費用についても夫婦が分担するものと改め、夫婦が平等の立場で、婚姻生活の維持・確保に共同責任を負うことを明らかにした。
そして、婚姻共同生活の存在する限り、婚姻費用分担が生活保持義務であることに異論はみられないが、婚姻費用の分担義務が法的問題として登場するのは圧倒的に夫婦が別居している場合についてである。しかも、離婚紛争の前哨戦として、離婚を請求する夫に対して別居中の妻が婚姻費用を請求するという事例が多く、夫婦関係の回復が困難な破綻状態にあることが多い(別冊法学セミナー基本法コンメンタール『親族』74〜76頁参照)、というのがかつての実態であった。
しかるに、本件もその典型であるが、「ある日突然に妻が子を拉致して行方がわからない」状態で、弁護士を盾にして、離婚と婚姻費用を請求してくるという、全く法の想定外の事態である。夫にしてみれば、「何が何だか分からない」という状態で、離婚意思もなければ、別居の意思もない。妻子が戻ってくることを願っている。それが、善良な夫の姿である。ところが、そこにDV防止法が立ち塞がるのである。
すなわち、このような妻の行為は、その動機がどうであれ、婚姻を破壊するものにほかならない。したがって、夫婦が平等の立場で、婚姻生活の維持・確保に共同責任を負うとする婚姻費用の分担の前提を欠く。そして、婚姻破壊者である妻が無収入のため何ら婚姻費用を分担しないでおきながら、収入があるというだけの理由で無責の夫に婚姻費用を分担させるのは、夫婦平等を極端に逸脱している。
3 「扶養」と「婚姻費用の分担」
民法第752条は、夫婦の同居義務とともに、夫婦間の経済的義務として扶助義務(扶養義務)を定め、手続的には家事審判法第9条1項乙類1号審判の対象とされている。これに対し、民法第760条は、夫婦とその間に生まれた未成熟子を含めた婚姻生活の維持のための費用の分担義務を定め、手続的には家事審判法第9条1項乙類3号審判の対象とされている。
通説・判例は、両者は婚姻費用の分担と扶養というように概念的観念的には一応区別できるとしても、夫婦間扶養も未成熟子扶養も生活保持義務であるとして、本質的には同一であるとし、手続的にも差はないとしている。これに対し、両者を区別する見解があるが、なかでも、婚姻費用分担義務は婚姻共同生活の存在が前提であり、夫婦関係が破綻し、もはや婚姻共同生活の回復が期待できない場合は、婚姻費用の分担(生活保持義務)の問題ではなく、夫婦一方が生活に困窮しているならば、夫婦間の扶養(生活扶助義務=相手に最低生活費を保障すべき義務)の問題となるとの見解が比較的支持されている(別冊法学セミナー基本法コンメンタール『親族』74頁参照)。
また、未成熟子扶養についてみると、父母は親権の有無にかかわらず未成熟子(未成年者)に対して生活保持義務を負うので、未成熟子が自ら権利者(申立人)として(15歳未満であるときは法定代理人によって)、民法第877条以下・家事審判法第9条1項乙類8号「扶養に関する処分」事件の申立てにより扶養請求をすることができる。一方、民法第766条は、離婚後の子の監護に関する事項について規定しており、「子の監護について必要な事項」としては、監護者指定・変更、監護費用(養育費)分担、面接交渉、子の引渡などがあるが、いずれも家事審判法第9条1項乙類4号「子の監護に関する処分」事件とされている。
そうすると、「婚姻費用」は、夫婦間扶養と監護費用の合計となる。実務上、夫婦の一方が他方に対して行う生活費の請求に関して、婚姻費用分担審判の申立手続により処理することにほぼ統一されているのも、そのためである。
ところで、前記したように、本件では、妻が子どもを拉致同然に連れ去り、居所も秘匿し、父である夫を子どもにも会わせないで1年以上経過しているのであり、妻が失踪した時点で、いかなる意味でも婚姻関係は破綻していない。実在するのは、妻による婚姻関係・父子関係の破壊であり、妻は、夫婦同居義務を一方的に放棄して婚姻共同生活を破壊した配偶者である。
そこで、夫婦間扶養の問題として考えた場合、妻の夫に対する扶養請求が権利濫用であることは明白である。一方、妻によって拉致された子らの監護費用を妻から請求されることは、誘拐犯から「身代金」を請求されているに等しい。このように、夫婦間扶養と監護費用のどちらも「クリーン・ハンドの原則」に照らせば権利濫用であるのに、両方を合体させた「婚姻費用分担」になると、魔法のようにこの事情が消え去るのである。それは、家事審判官が、「破綻」の有無および「破綻」の原因について、実態を無視し、執務資料マニュアルにあてはめて行政処分をするからである。実際、本件のように、婚姻費用分担請求と離婚請求が同時に行われるケースでは、裁判上の離婚原因がない場合が多い。ちなみに、破綻主義を徹底させた平成8年の民法改正要綱では、破綻主義強制離婚がもたらすモラルハザードを予見しており、配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその離婚請求が信義に反すると認められるときには裁判所は離婚請求を棄却することができるとしている。
本件審判は、妻の背信性を全く無視して、通常の婚姻費用分担義務を夫に命じている点で、法解釈適用を誤っており、取り消されるべきである。
民法第752条は、夫婦の同居義務とともに、夫婦間の経済的義務として扶助義務(扶養義務)を定め、手続的には家事審判法第9条1項乙類1号審判の対象とされている。これに対し、民法第760条は、夫婦とその間に生まれた未成熟子を含めた婚姻生活の維持のための費用の分担義務を定め、手続的には家事審判法第9条1項乙類3号審判の対象とされている。
通説・判例は、両者は婚姻費用の分担と扶養というように概念的観念的には一応区別できるとしても、夫婦間扶養も未成熟子扶養も生活保持義務であるとして、本質的には同一であるとし、手続的にも差はないとしている。これに対し、両者を区別する見解があるが、なかでも、婚姻費用分担義務は婚姻共同生活の存在が前提であり、夫婦関係が破綻し、もはや婚姻共同生活の回復が期待できない場合は、婚姻費用の分担(生活保持義務)の問題ではなく、夫婦一方が生活に困窮しているならば、夫婦間の扶養(生活扶助義務=相手に最低生活費を保障すべき義務)の問題となるとの見解が比較的支持されている(別冊法学セミナー基本法コンメンタール『親族』74頁参照)。
また、未成熟子扶養についてみると、父母は親権の有無にかかわらず未成熟子(未成年者)に対して生活保持義務を負うので、未成熟子が自ら権利者(申立人)として(15歳未満であるときは法定代理人によって)、民法第877条以下・家事審判法第9条1項乙類8号「扶養に関する処分」事件の申立てにより扶養請求をすることができる。一方、民法第766条は、離婚後の子の監護に関する事項について規定しており、「子の監護について必要な事項」としては、監護者指定・変更、監護費用(養育費)分担、面接交渉、子の引渡などがあるが、いずれも家事審判法第9条1項乙類4号「子の監護に関する処分」事件とされている。
そうすると、「婚姻費用」は、夫婦間扶養と監護費用の合計となる。実務上、夫婦の一方が他方に対して行う生活費の請求に関して、婚姻費用分担審判の申立手続により処理することにほぼ統一されているのも、そのためである。
ところで、前記したように、本件では、妻が子どもを拉致同然に連れ去り、居所も秘匿し、父である夫を子どもにも会わせないで1年以上経過しているのであり、妻が失踪した時点で、いかなる意味でも婚姻関係は破綻していない。実在するのは、妻による婚姻関係・父子関係の破壊であり、妻は、夫婦同居義務を一方的に放棄して婚姻共同生活を破壊した配偶者である。
そこで、夫婦間扶養の問題として考えた場合、妻の夫に対する扶養請求が権利濫用であることは明白である。一方、妻によって拉致された子らの監護費用を妻から請求されることは、誘拐犯から「身代金」を請求されているに等しい。このように、夫婦間扶養と監護費用のどちらも「クリーン・ハンドの原則」に照らせば権利濫用であるのに、両方を合体させた「婚姻費用分担」になると、魔法のようにこの事情が消え去るのである。それは、家事審判官が、「破綻」の有無および「破綻」の原因について、実態を無視し、執務資料マニュアルにあてはめて行政処分をするからである。実際、本件のように、婚姻費用分担請求と離婚請求が同時に行われるケースでは、裁判上の離婚原因がない場合が多い。ちなみに、破綻主義を徹底させた平成8年の民法改正要綱では、破綻主義強制離婚がもたらすモラルハザードを予見しており、配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその離婚請求が信義に反すると認められるときには裁判所は離婚請求を棄却することができるとしている。
本件審判は、妻の背信性を全く無視して、通常の婚姻費用分担義務を夫に命じている点で、法解釈適用を誤っており、取り消されるべきである。
4 家事審判―裁判官の独裁
家事審判は、本質的に民事行政とされ、非訟手続で行われる。
しかしながら、本件をみれば分かるように、夫婦の婚姻共同生活保持義務や親の親権=養育監護権の保障など、家族生活全体を考慮して紛争を把握しないで、ただ婚姻費用分担義務をマニュアルに従って行政処分するなら、夫の財産権や生存権を侵害するにすぎない。そもそも、主権者たる国民に憲法で保障された権利を制限ないし剥奪する権限が、官僚裁判官に付与されているはずがない。裁判官は、非訟手続で「行政サービス」を提供しているつもりかもしれないが、実態は、官僚裁判官の行政処分であり、独裁である。
このように、本件審判は、憲法第29条および第25条に違反するだけでなく、憲法第31条および第32条に違反する。
なお、離婚と子どもをめぐる紛争をとってみても、家事審判と人事訴訟と手続的に分断されるために、当事者にとって「サービス」になどならない。むしろ、裁判官の独裁により確定された「紛争の断片」のせいで、どうにもならなくなるだけである。したがって、まずもって家事審判制度を廃止し、人事訴訟に一元化することである。また、調停前置主義が機能するように、単独親権制を廃止し、父母の婚姻関係の有無にかかわらず共同親権とする民法改正をすべきであろう。とはいえ、改正前でも、親権と監護権の分属など、家事審判のサービスを駆使して同じような解決が可能である。そういう働きを裁判官がしないから、家事審判制度は有害物に転化するのである。
第2 DV防止法による「自立支援」と婚姻費用分担請求
1 改正DV防止法の基本理念の欺瞞性―男女平等の実現?
法第2条の2(基本指針)に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(平成16年12月2日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号)において、「経済的自立が困難である女性に対する配偶者暴力は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げになっている」として、「人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要である。」という。そして、通報、相談、保護、自立支援等の体制が整備強化されている。
しかしながら、夫婦間の問題にすぎないことを、妻を保護することによって「男女平等の実現」が図られるはずがない。経済的自立の困難な妻を、生活保護などの「被害者の自立支援」策によって自立させることも、常識的には不可能と思われる。第一、職業を有する女性たちが賃金における男女差別と闘っており、それこそ男女平等社会の実現に必要なことである。
また、「男女共同参画」というなら、「共同子育て」こそが推進されるべき施策であるはずなのに、「DV防止法」では、子どもは母親の附属物扱いであり、父親を「DV加害者」として「子育て」から排除する。
このように、全く欺瞞的で非論理的な法令によって、子どもを拉致同然に連れ去る破壊的な離婚紛争が誘発されている。すなわち、経済的自立の困難な妻たちは、家庭破壊離婚を法律により教唆されているのである。そして、前記したように、未成熟子の「監護費用」は経済力のある父親と同等の生活が保障されるから、経済力のない妻にとって子どもが「金蔓」として重要な存在になるのである。子どもを拉致する所以である。
家事審判は、本質的に民事行政とされ、非訟手続で行われる。
しかしながら、本件をみれば分かるように、夫婦の婚姻共同生活保持義務や親の親権=養育監護権の保障など、家族生活全体を考慮して紛争を把握しないで、ただ婚姻費用分担義務をマニュアルに従って行政処分するなら、夫の財産権や生存権を侵害するにすぎない。そもそも、主権者たる国民に憲法で保障された権利を制限ないし剥奪する権限が、官僚裁判官に付与されているはずがない。裁判官は、非訟手続で「行政サービス」を提供しているつもりかもしれないが、実態は、官僚裁判官の行政処分であり、独裁である。
このように、本件審判は、憲法第29条および第25条に違反するだけでなく、憲法第31条および第32条に違反する。
なお、離婚と子どもをめぐる紛争をとってみても、家事審判と人事訴訟と手続的に分断されるために、当事者にとって「サービス」になどならない。むしろ、裁判官の独裁により確定された「紛争の断片」のせいで、どうにもならなくなるだけである。したがって、まずもって家事審判制度を廃止し、人事訴訟に一元化することである。また、調停前置主義が機能するように、単独親権制を廃止し、父母の婚姻関係の有無にかかわらず共同親権とする民法改正をすべきであろう。とはいえ、改正前でも、親権と監護権の分属など、家事審判のサービスを駆使して同じような解決が可能である。そういう働きを裁判官がしないから、家事審判制度は有害物に転化するのである。
第2 DV防止法による「自立支援」と婚姻費用分担請求
1 改正DV防止法の基本理念の欺瞞性―男女平等の実現?
法第2条の2(基本指針)に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(平成16年12月2日内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号)において、「経済的自立が困難である女性に対する配偶者暴力は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げになっている」として、「人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要である。」という。そして、通報、相談、保護、自立支援等の体制が整備強化されている。
しかしながら、夫婦間の問題にすぎないことを、妻を保護することによって「男女平等の実現」が図られるはずがない。経済的自立の困難な妻を、生活保護などの「被害者の自立支援」策によって自立させることも、常識的には不可能と思われる。第一、職業を有する女性たちが賃金における男女差別と闘っており、それこそ男女平等社会の実現に必要なことである。
また、「男女共同参画」というなら、「共同子育て」こそが推進されるべき施策であるはずなのに、「DV防止法」では、子どもは母親の附属物扱いであり、父親を「DV加害者」として「子育て」から排除する。
このように、全く欺瞞的で非論理的な法令によって、子どもを拉致同然に連れ去る破壊的な離婚紛争が誘発されている。すなわち、経済的自立の困難な妻たちは、家庭破壊離婚を法律により教唆されているのである。そして、前記したように、未成熟子の「監護費用」は経済力のある父親と同等の生活が保障されるから、経済力のない妻にとって子どもが「金蔓」として重要な存在になるのである。子どもを拉致する所以である。
2 DV防止法における「生活保護」と「配偶者扶養」の関係
DV防止法は、経済的に自立できない妻が夫からのDVから逃れること、つまり夫婦共同生活の破棄を前提とした「被害者支援」法である。そして、生活保護は、DV防止法の「援助」として位置づけられ、生活保護法の特例扱いがされている。DV防止法は、福祉事務所による自立支援を規定し(法第8条の3)、配偶者暴力の被害者の自立を支援するという趣旨で、通常の生活保護法による保護の実施要領の特例として、「扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者であって、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合」には、扶養能力の調査にあたって扶養義務者に直接照会することが真に適当でない場合として取扱われるのである。すなわち、DV防止法の「援助」としてされる生活保護は、配偶者から扶養を受けられないことを前提としている。
ところで、妻は、詳細を明らかにしないものの、生活保護を受給しているというのであり、これはDV防止法の「援助」としてされた生活保護にほかならない。すなわち、妻は夫から婚姻費用を得られない/請求しないことが前提なのである。したがって、仮に夫から婚姻費用分担金を受領すれば、生活費の二重取得になるはずである。
これについて、妻は、生活保護法を援用して、二重取得にならないと主張しているが、これはDV防止法を無視するものである。実際的に考えても、国庫に返還するために婚姻費用を請求するのは不自然であるし、妻に何のメリットもないと思われる。
しかるに、本件審判は、妻が受給している生活保護の全容を開示させることなく、婚姻費用が国庫に返還される前提でマニュアルに従って結論を導いており、取り消されるべきである。
(以 上)
DV防止法は、経済的に自立できない妻が夫からのDVから逃れること、つまり夫婦共同生活の破棄を前提とした「被害者支援」法である。そして、生活保護は、DV防止法の「援助」として位置づけられ、生活保護法の特例扱いがされている。DV防止法は、福祉事務所による自立支援を規定し(法第8条の3)、配偶者暴力の被害者の自立を支援するという趣旨で、通常の生活保護法による保護の実施要領の特例として、「扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者であって、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合」には、扶養能力の調査にあたって扶養義務者に直接照会することが真に適当でない場合として取扱われるのである。すなわち、DV防止法の「援助」としてされる生活保護は、配偶者から扶養を受けられないことを前提としている。
ところで、妻は、詳細を明らかにしないものの、生活保護を受給しているというのであり、これはDV防止法の「援助」としてされた生活保護にほかならない。すなわち、妻は夫から婚姻費用を得られない/請求しないことが前提なのである。したがって、仮に夫から婚姻費用分担金を受領すれば、生活費の二重取得になるはずである。
これについて、妻は、生活保護法を援用して、二重取得にならないと主張しているが、これはDV防止法を無視するものである。実際的に考えても、国庫に返還するために婚姻費用を請求するのは不自然であるし、妻に何のメリットもないと思われる。
しかるに、本件審判は、妻が受給している生活保護の全容を開示させることなく、婚姻費用が国庫に返還される前提でマニュアルに従って結論を導いており、取り消されるべきである。
(以 上)
人権としての「子育て」―性別役割分担と単独親権制 1/2
親は既に「出来上がった大人」として、「未熟な子ども」を養育するという前提は科学的に間違っている。大人も死ぬまで成長・発達するものであり、親自身が成長・発達することが、子どもの「育ち」にとって重要なことが証明されている。親の自己成長・発達は、親自身の幸福感と心理的安定の基盤であるだけでなく、子どものモデルとして重要である。それは、子どもが「有能な観察学習者」だからである。子どもは、親がどうふるまっているか、どう生きているかということを自分のモデルとして学ぶ。子の発達に対して親がなし得ることは、親自身が、どんなことであれ、自らが成長すべく努力し、精一杯生きている姿をみせることである。さらに、思春期になると、子どもは、親たちを「夫と妻」としてみるようになるし、親を職業人としても、家庭人としても観察する。両親が夫婦として調和せずに批判し合う対立関係にあることは、子どもにとっても不快で疎ましい。子どもは、その不快感を直接、親には言わないけれども、間接的な形で親に抗議し、批判する。親たちの発達は、子どもの心理的安定の基盤であると同時に、子どもの発達のモデルなのだ。
幼児の監護者として「母親が一番」という母性神話も科学的に間違っている。子どもや育児への態度や心理は、血縁や性の違いを超えて、養育責任と養育体験をもつことによって育まれる。人類は、育児本能をもつ動物とは違って、他者の心を理解し、他者を援助しようとする心が進化した人間ならではのこととして、小さく弱いものを慈しみ守り育てる心とスキルを持ちうる。父親が育児から降りてしまう状況は、人間ならではの心と力を無視している。人類の父親は、困難な育児をつつがなく成功させるために進化したものとも言える。日本における父親の育児不在状況は、子育て=繁殖成功の必需品として進化した機能が不全に陥っていることを意味している。ちなみに、脳科学の知見によれば、「ヒトを人間たらしめる」脳領域は前頭連合野であり、「社会の中でうまく生きて、最愛の配偶者を得て子どもをつくり、きちんとした成人に育てる」という目的で進化発達してきた知性群である。その脳機能を高めるには、「できるだけ多く他者と関わる臨床体験を重ねること」に尽きるが、8歳までが勝負という。
次へ
親は既に「出来上がった大人」として、「未熟な子ども」を養育するという前提は科学的に間違っている。大人も死ぬまで成長・発達するものであり、親自身が成長・発達することが、子どもの「育ち」にとって重要なことが証明されている。親の自己成長・発達は、親自身の幸福感と心理的安定の基盤であるだけでなく、子どものモデルとして重要である。それは、子どもが「有能な観察学習者」だからである。子どもは、親がどうふるまっているか、どう生きているかということを自分のモデルとして学ぶ。子の発達に対して親がなし得ることは、親自身が、どんなことであれ、自らが成長すべく努力し、精一杯生きている姿をみせることである。さらに、思春期になると、子どもは、親たちを「夫と妻」としてみるようになるし、親を職業人としても、家庭人としても観察する。両親が夫婦として調和せずに批判し合う対立関係にあることは、子どもにとっても不快で疎ましい。子どもは、その不快感を直接、親には言わないけれども、間接的な形で親に抗議し、批判する。親たちの発達は、子どもの心理的安定の基盤であると同時に、子どもの発達のモデルなのだ。
幼児の監護者として「母親が一番」という母性神話も科学的に間違っている。子どもや育児への態度や心理は、血縁や性の違いを超えて、養育責任と養育体験をもつことによって育まれる。人類は、育児本能をもつ動物とは違って、他者の心を理解し、他者を援助しようとする心が進化した人間ならではのこととして、小さく弱いものを慈しみ守り育てる心とスキルを持ちうる。父親が育児から降りてしまう状況は、人間ならではの心と力を無視している。人類の父親は、困難な育児をつつがなく成功させるために進化したものとも言える。日本における父親の育児不在状況は、子育て=繁殖成功の必需品として進化した機能が不全に陥っていることを意味している。ちなみに、脳科学の知見によれば、「ヒトを人間たらしめる」脳領域は前頭連合野であり、「社会の中でうまく生きて、最愛の配偶者を得て子どもをつくり、きちんとした成人に育てる」という目的で進化発達してきた知性群である。その脳機能を高めるには、「できるだけ多く他者と関わる臨床体験を重ねること」に尽きるが、8歳までが勝負という。
次へ
人権としての「子育て」―性別役割分担と単独親権制 2/2
ところで、男女を問わず、家族役割を担い家庭生活を享受することは、人間として当然の権利であり責任である。家庭(家族)責任および権利が男女労働者双方のものであることは、ILO条約第156号「家族責任をもつ男女労働者の権利」に明記されている。スウェーデンでは、男性もごく普通に育休をとっているが、それは、職業と家族役割を同じ比重で尊重する理念に基づき、育休をとることが職業上不利になるどころか有利になる制度的な裏付けがあり、男性の育児権が保障されているからである。
ところが、日本では、1999年6月、「男女共同参画社会」法が国の基本的政策の柱として成立したが、一向に進展がない。この目標を実現するために必要なことは、「ワーク・ライフ・バランス」の確立である。ここで「ライフ」というのは、家事・育児など家庭のことをすることではない。家事は生きるうえで必須の労働であり、「ワーク」である。ライフとは、勉強、教養、趣味、スポーツなど心身の成長・発達のための個人の活動である。こうした活動は、経済と家事・育児といった生きるうえでの安定、すなわちワークの基盤があってこそ成り立つ活動である。妻が専業主婦の場合、男性は職業のワークを、女性は家事・育児のワークを分担しているだけで、夫も妻も「ライフ」どころではないのが現状である。
しかし、「ワーク」だけとってみても、人間にとっての発達を考えた場合、複数役割に関与することで質的な展開がみられる。育児は、職業とは全く異質の活動で、育休をとった父親は「育児は育自」を実感し、仕事の価値を相対化できるようになる。発達の原則からみれば、一つのことだけに集中していることは、心理的健康を害し、能率的にも良くない。また、生活体験を欠いた企業の経済活動が、社会やそこに暮らす人々にとって良いはずがない。異質な体験が、それらの問題を修正することになるのである。そうすると、依然として仕事に偏りがちな日本の男性にとって、子育てという権利の保障は大切である。
こうしてみると、単独親権制は、人類のサバイバル戦略と背反するもので、親にとっても子にとっても、成長発達を疎外するものである。また、社会学的に見れば、単独親権制と「母親優先」の運用は、ジェンダー・バイアスとジェンダー・アンバランスの象徴にほかならない。さらに、審判だ訴訟だと権力・権威に解決を委ねるあり方/話合いによる解決を図ろうとしないことも、脳機能の劣化・退化を示唆している。
しかるに、日本国憲法は、このような人間の尊厳を冒涜する事象を克服する規範として存在しているのである。
参考文献:柏木惠子『子どもが育つ条件―家族心理学から考える』(岩波新書)
門脇厚司『社会力を育てる―新しい「学び」の構想』(岩波新書)
(2011.6.12 後藤富士子)
ところで、男女を問わず、家族役割を担い家庭生活を享受することは、人間として当然の権利であり責任である。家庭(家族)責任および権利が男女労働者双方のものであることは、ILO条約第156号「家族責任をもつ男女労働者の権利」に明記されている。スウェーデンでは、男性もごく普通に育休をとっているが、それは、職業と家族役割を同じ比重で尊重する理念に基づき、育休をとることが職業上不利になるどころか有利になる制度的な裏付けがあり、男性の育児権が保障されているからである。
ところが、日本では、1999年6月、「男女共同参画社会」法が国の基本的政策の柱として成立したが、一向に進展がない。この目標を実現するために必要なことは、「ワーク・ライフ・バランス」の確立である。ここで「ライフ」というのは、家事・育児など家庭のことをすることではない。家事は生きるうえで必須の労働であり、「ワーク」である。ライフとは、勉強、教養、趣味、スポーツなど心身の成長・発達のための個人の活動である。こうした活動は、経済と家事・育児といった生きるうえでの安定、すなわちワークの基盤があってこそ成り立つ活動である。妻が専業主婦の場合、男性は職業のワークを、女性は家事・育児のワークを分担しているだけで、夫も妻も「ライフ」どころではないのが現状である。
しかし、「ワーク」だけとってみても、人間にとっての発達を考えた場合、複数役割に関与することで質的な展開がみられる。育児は、職業とは全く異質の活動で、育休をとった父親は「育児は育自」を実感し、仕事の価値を相対化できるようになる。発達の原則からみれば、一つのことだけに集中していることは、心理的健康を害し、能率的にも良くない。また、生活体験を欠いた企業の経済活動が、社会やそこに暮らす人々にとって良いはずがない。異質な体験が、それらの問題を修正することになるのである。そうすると、依然として仕事に偏りがちな日本の男性にとって、子育てという権利の保障は大切である。
こうしてみると、単独親権制は、人類のサバイバル戦略と背反するもので、親にとっても子にとっても、成長発達を疎外するものである。また、社会学的に見れば、単独親権制と「母親優先」の運用は、ジェンダー・バイアスとジェンダー・アンバランスの象徴にほかならない。さらに、審判だ訴訟だと権力・権威に解決を委ねるあり方/話合いによる解決を図ろうとしないことも、脳機能の劣化・退化を示唆している。
しかるに、日本国憲法は、このような人間の尊厳を冒涜する事象を克服する規範として存在しているのである。
参考文献:柏木惠子『子どもが育つ条件―家族心理学から考える』(岩波新書)
門脇厚司『社会力を育てる―新しい「学び」の構想』(岩波新書)
(2011.6.12 後藤富士子)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
NPO 離婚後の子どもを守る会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO 離婚後の子どもを守る会 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89526人