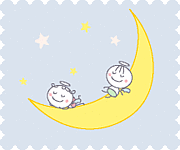ポールさま、XXXさま
こんなことを考えています。
自由法曹団通信に投稿しました。
後藤富士子
国家が家庭を破壊する契機
――親権と裁判所
1 「親権者指定」の決定権
民法818条3項は「婚姻中」のみ父母の共同親権としており、離婚後は父母どちらかの単独親権である(819条)。問題は、どちらを単独親権者とするかについて、父母の協議で決まらなければ、「裁判所が決める」とされていることである。そもそも単独親権制は、「両性の本質的平等」と両立しないのに、裁判所に「不平等」を実行させるのであるから、「おさまり」が悪いのも当然である。
ところで、裁判所が「両性の本質的平等」に反する決定をする際の基準は「子の福祉」の見地である。私の頭が単純なせいか、二人いる親を無理に一人にすること自体が「子の福祉」に反するとしか思えない。共同親権のまま、「共同監護」の具体的形態を調整する基準として「子の福祉」が言われるなら納得できる。つまり、裁判所は、両親に親権を保持させたまま、養育監護の共同責任の履行について介入するのである。
2 単独親権者の再婚相手と養子縁組した場合
「親権者変更」は、父母のどちらか一方の単独親権に服している子について、「子の利益のため必要がある」と認めるときは、子の親族(子自身は除く)の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更することができる(民法819条6項)。つまり、一旦、父母のどちらかが親権者と指定された以上、それが父母の協議で決まった場合でさえ、父母の合意だけでは親権者変更ができない。あくまで家庭裁判所の審判によるのである。
ところで、「親権者変更」が問題になる事例の一つは、単独親権者が死亡した場合に、非親権者である実親に親権者変更が許されるかという問題である。これについては、後見人が選任される前後を通じて、「子の福祉」に適う限り、許されるとするのが実務の趨勢である。
これに対し、単独親権者の再婚相手と養子縁組して実親と養親の共同親権に服している場合に、非親権者である実親への「親権者変更」は認められない。その理由とされるのは、もし親権者たる実親から非親権者である他方の実親への変更が認められると、「婚姻関係にない―あり得ない―2名の男性または2名の女性の親権者が同時に存在するという、民法の全く予想だにしなかった事態が生じることになる」からだという(昭和38年盛岡家審)。あるいは、共同親権から単独親権への変更に疑問があり、共同親権者の親権行使の方法等が子の利益を害するような場合は、民法834条以下の親権喪失宣告等の手続で処理すべきという(昭和48年東京高決)。なお、親権者変更の申立は許されるとする判例(昭和43年大阪高決)もある。
このように、単独親権者が再婚して、配偶者と養子縁組してしまった場合、そもそも非親権者には養子縁組を阻止する機会もないうえ、実親と養親の共同親権の前に「出る幕がない」状態に貶められる。これは、単独親権者が自分の両親と代諾養子縁組してしまった場合も同様である。すなわち、単独親権をめぐる紛争の後、非親権者をシャットアウトする方策として養子縁組がされるのであり、養子縁組がされた後は、非親権者は子との接触をもたないことが「子の福祉」に適うという考えが根底にあるようである。しかしながら、前述したように、単独親権者が死亡した後、非親権者に親権者変更することを考えると、非親権者と子の交流が保たれていなければ「子の福祉」が枯渇してしまうのである。
3 子をめぐる家族(親)と国家の関係
広渡清吾教授の「国家と家族―家族法における子の位置」(法と民主主義?447)によれば、ドイツ基本法6条2項は「子の養育および教育は両親の自然的権利であり、かつ、第一次的にかれらに課せられる義務である。国家は、両親の活動を監督する」と規定しているが、これはワイマール憲法に由来する。この規定は、まず親の自然的権利として国家に対する「責任領域」が設定され、義務の不履行があれば、国家がその領域を縮減して介入するシステムを予定するものであると解釈されている。
これに対し、日本の現行民法の解釈では、親権につき「親の自然的権利」と承認されておらず、国家に対する「責任領域」が設定されてもいない。「親権者指定」「監護者指定」「面会交流」と、ことごとく国家が両親の間に介入して、どちらか一方の肩を持ち、他方を叩きのめす。こうして家庭裁判所は「家庭破壊の先兵」になるのである。
しかしながら、日本国憲法は、子が個人として人間の尊厳の主体として位置づけ、家制度を解体し、人間の尊厳を担う個人が構成する共同体として、家族を確立することを要請した。現代日本では、核家族化した家族集団のなかで子の人間としての尊厳をいかに確保するかが深刻な問題となっている。親子関係が親の子に対する責任関係であることを軸にして国家・社会による支援体制の整備が求められている。子は、人間の尊厳を担い、自由で独立の存在に成熟する権利を有する主体として法のなかに位置づけられなければならないという。
なお、弁護士会の「両性の平等に関する委員会」の家族観では、「家からの個人の解放」が未だに主要課題と前提しているように見えるが、現代の「家」制度は「妻の実家」であり、実家依存症の妻に子を拉致された夫たちは、「種馬」「精子提供者」のごとき扱いを受けて、人間の尊厳を踏みにじられているのである。
(2010.6.12 後藤富士子)(無断転載厳禁)
こんなことを考えています。
自由法曹団通信に投稿しました。
後藤富士子
国家が家庭を破壊する契機
――親権と裁判所
1 「親権者指定」の決定権
民法818条3項は「婚姻中」のみ父母の共同親権としており、離婚後は父母どちらかの単独親権である(819条)。問題は、どちらを単独親権者とするかについて、父母の協議で決まらなければ、「裁判所が決める」とされていることである。そもそも単独親権制は、「両性の本質的平等」と両立しないのに、裁判所に「不平等」を実行させるのであるから、「おさまり」が悪いのも当然である。
ところで、裁判所が「両性の本質的平等」に反する決定をする際の基準は「子の福祉」の見地である。私の頭が単純なせいか、二人いる親を無理に一人にすること自体が「子の福祉」に反するとしか思えない。共同親権のまま、「共同監護」の具体的形態を調整する基準として「子の福祉」が言われるなら納得できる。つまり、裁判所は、両親に親権を保持させたまま、養育監護の共同責任の履行について介入するのである。
2 単独親権者の再婚相手と養子縁組した場合
「親権者変更」は、父母のどちらか一方の単独親権に服している子について、「子の利益のため必要がある」と認めるときは、子の親族(子自身は除く)の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更することができる(民法819条6項)。つまり、一旦、父母のどちらかが親権者と指定された以上、それが父母の協議で決まった場合でさえ、父母の合意だけでは親権者変更ができない。あくまで家庭裁判所の審判によるのである。
ところで、「親権者変更」が問題になる事例の一つは、単独親権者が死亡した場合に、非親権者である実親に親権者変更が許されるかという問題である。これについては、後見人が選任される前後を通じて、「子の福祉」に適う限り、許されるとするのが実務の趨勢である。
これに対し、単独親権者の再婚相手と養子縁組して実親と養親の共同親権に服している場合に、非親権者である実親への「親権者変更」は認められない。その理由とされるのは、もし親権者たる実親から非親権者である他方の実親への変更が認められると、「婚姻関係にない―あり得ない―2名の男性または2名の女性の親権者が同時に存在するという、民法の全く予想だにしなかった事態が生じることになる」からだという(昭和38年盛岡家審)。あるいは、共同親権から単独親権への変更に疑問があり、共同親権者の親権行使の方法等が子の利益を害するような場合は、民法834条以下の親権喪失宣告等の手続で処理すべきという(昭和48年東京高決)。なお、親権者変更の申立は許されるとする判例(昭和43年大阪高決)もある。
このように、単独親権者が再婚して、配偶者と養子縁組してしまった場合、そもそも非親権者には養子縁組を阻止する機会もないうえ、実親と養親の共同親権の前に「出る幕がない」状態に貶められる。これは、単独親権者が自分の両親と代諾養子縁組してしまった場合も同様である。すなわち、単独親権をめぐる紛争の後、非親権者をシャットアウトする方策として養子縁組がされるのであり、養子縁組がされた後は、非親権者は子との接触をもたないことが「子の福祉」に適うという考えが根底にあるようである。しかしながら、前述したように、単独親権者が死亡した後、非親権者に親権者変更することを考えると、非親権者と子の交流が保たれていなければ「子の福祉」が枯渇してしまうのである。
3 子をめぐる家族(親)と国家の関係
広渡清吾教授の「国家と家族―家族法における子の位置」(法と民主主義?447)によれば、ドイツ基本法6条2項は「子の養育および教育は両親の自然的権利であり、かつ、第一次的にかれらに課せられる義務である。国家は、両親の活動を監督する」と規定しているが、これはワイマール憲法に由来する。この規定は、まず親の自然的権利として国家に対する「責任領域」が設定され、義務の不履行があれば、国家がその領域を縮減して介入するシステムを予定するものであると解釈されている。
これに対し、日本の現行民法の解釈では、親権につき「親の自然的権利」と承認されておらず、国家に対する「責任領域」が設定されてもいない。「親権者指定」「監護者指定」「面会交流」と、ことごとく国家が両親の間に介入して、どちらか一方の肩を持ち、他方を叩きのめす。こうして家庭裁判所は「家庭破壊の先兵」になるのである。
しかしながら、日本国憲法は、子が個人として人間の尊厳の主体として位置づけ、家制度を解体し、人間の尊厳を担う個人が構成する共同体として、家族を確立することを要請した。現代日本では、核家族化した家族集団のなかで子の人間としての尊厳をいかに確保するかが深刻な問題となっている。親子関係が親の子に対する責任関係であることを軸にして国家・社会による支援体制の整備が求められている。子は、人間の尊厳を担い、自由で独立の存在に成熟する権利を有する主体として法のなかに位置づけられなければならないという。
なお、弁護士会の「両性の平等に関する委員会」の家族観では、「家からの個人の解放」が未だに主要課題と前提しているように見えるが、現代の「家」制度は「妻の実家」であり、実家依存症の妻に子を拉致された夫たちは、「種馬」「精子提供者」のごとき扱いを受けて、人間の尊厳を踏みにじられているのである。
(2010.6.12 後藤富士子)(無断転載厳禁)
|
|
|
|
|
|
|
|
NPO 離婚後の子どもを守る会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO 離婚後の子どもを守る会 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人