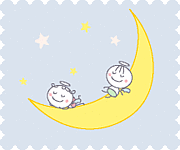自由法曹団通信より
1 人身保護法の「実務」
人身保護法は、昭和23年7月30日に制定された法律であり、その目的は「基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめること」とされている(同法第1条)。そして、同規則によれば、「拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい」(第3条)、また、請求の要件として「拘束がその権限なしにされていることが顕著である場合」で且つ「他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときは、その方法によって相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白」な場合に限るとされている(第4条)。さらに、「請求は、被拘束者の自由に表明した意思に反してこれをすることができない。」のである(第5条)。
この法律の本旨に照らせば、「拘束」とはいえない通常の監護状態下にある子の父母間における「身柄」争奪紛争に適用することはできないと思われる。ところが、たとえば未婚や離婚で単独親権の場合、あるいは、離婚前別居中に「監護者指定」や「引渡し」の本案審判や保全処分がなされた場合、「権限なしになされている」として、人身保護請求が認容されている。のみならず、請求認容の場合、審問手続(証拠調べ手続)は全く形骸化して、審問期日は事実上子の身柄を請求者に引渡す、執行手続になっていて、裁判所は「身柄引渡所」と化している。
本稿では、このような「実務」が、現実に著しい脱法行為の集積によっていることを明らかにする。と同時に、それがもたらしている人権侵害と家族破壊の惨状を告発する。
2 人身保護命令の暴虐――誘拐犯よりも迫害される親
人身保護法の規定による救済は、終局的には判決で実現されるのであるが、この救済を実現する人身保護手続は、通常の訴訟手続と異なり、人身保護命令を中心として構成されている(人身保護規則第2条)。すなわち、釈放その他適当であると認める処分を相手方たる拘束者が受忍し又は実行させるために判決前に特に必要的仮処分に準ずる人身保護命令という強力な手続を介在させたわけで、人身の自由の回復をより効果的にするための特別の制度である。決定でなされる人身保護命令は、独立した裁判でなく、判決手続の一部にすぎないもので、裁判所は釈放の状態を自ら形成するのである。そして、相手方にこの効果を受忍させるために、制裁の条件付で人身保護命令によって受忍義務を課するのである。
具体的には、拘束者が人身保護命令に従わないときに、「命令に従うまで勾留する」との制裁がある(人身保護法第12条3項)。これは、刑事訴訟法の勾留と異なり、裁判所の裁判、命令に従わないとき、その実行を促す秩序罰的なもので、本来は裁判所侮辱罪に対する制裁なのであるが、裁判所侮辱罪の制度が制定されるまで、やむなく準用したのである。そして、刑事訴訟法の勾留に関する規定の中、勾留の原由および期間は準用されず、期間について言えば、刑事訴訟法では「公訴の提起があった日から2箇月」とされているが(同第60条2項)、人身保護法による勾留は「命令に従うまで」とされ、無期限である。
拘束者が被拘束者を出頭させない場合の勾留の制裁は、拘束者を勾留したまま命令に従わせることはできないことであるから、命令に従う意思が認められたならば、拘束者を釈放して被拘束者の身柄を提出させることを意味している。すなわち、拘束者が父の場合、父は、勾留という重大な脅威を回避して自らの「人身の自由」を保持するには、母への引渡を拒絶している子(被拘束者)の意思に反して「子を差し出す」しかないのである。これが人倫に悖ることは多言を要しない。拘束者にとって「子を差し出す」ことは、「意に反する苦役」(憲法第18条)であり、「良心の自由の侵害」(同第19条)である。そして、このような勾留は、憲法第36条で禁止された「拷問」ないし「残虐な刑罰」というべきものである。
このことは、刑法第224条未成年者略取誘拐犯の場合と比較すれば、一層明らかになる。誘拐犯でさえ、適正手続が保障されるし、その刑罰も「3月以上7年以下の懲役」である。それに比べ、父親であるばかりに、拘束者は、無期限の勾留の脅しを受けたうえ、判決で親権・監護権を実質的に剥奪されるのである。一体いつから日本はこのように恐ろしい国になったのであろうか。しかも、人身保護制度の基となっているのが、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されない」という憲法第34条なのだから、悪夢というほかない。
3 人身保護請求認容判決の内容と執行力
人身保護法第16条1項は、「裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもってこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。」と定めている。これは、拘束者の拘束が正当であるなら、その拘束を継続させるために「引渡す」必要があるからである。
一方、同条3項は、「請求を理由ありとするときは、判決をもって被拘束者を直ちに釈放する。」と、単に「釈放」を定めるのみであるところ、同規則第37条は、「裁判所は、請求を理由があるとするときは、判決で、被拘束者を直ちに釈放し、又は被拘束者が幼児若しくは精神病者であるときその他被拘束者につき特別の事情があると認めるときは、被拘束者の利益のために適当であると認める処分をすることができる。」と定めている。すなわち、幼児や精神病者等の場合には、単に「釈放」するだけでは釈放の目的が達成されないので、釈放類似の、または釈放の性質を有する処分が認められる。しかし、それは被拘束者につき特別の事情があると認められること、また、被拘束者の利益のための処分でなければならない。
ところで、人身保護法の規定による救済は、終局的には判決で実現されるところ、その執行については、民事訴訟法による強制執行は親しまないと解されている。被拘束者が幼児の場合でも、引渡の強制執行はできないと解されているし、間接強制もできないとされている。すなわち、人身保護法の裁判の執行力は、家事審判および審判前の保全処分に比べると、格段に劣っている。裁判所が、審問期日を口実にして被拘束者を「別室」に出頭させ、形式的に審問期日を経て即日認容判決をし、請求者に被拘束者を事実上引渡してしまうのも、その執行力の不備を「補う」ために編み出された脱法行為である。そして、このような違法な実務の指南書になっているのは、昭和52年3月に発刊された「人身保護請求事件に関する実務的研究」(裁判所書記官実務報告書第13巻1号)なる、書記官丸投げマニュアルである。しかしながら、昭和55年家事審判法改正により審判前の保全処分が制度化される前の実務マニュアルを履行するなど狂気というほかなく、憲法第76条3項に違反することも明白である。
人身保護法の第1回審問期日は、憲法第34条後段に基づくものであり、刑事手続でいえば「勾留理由開示公判」(刑事訴訟法第82条〜86条)に比すべきもので、被拘束者こそが審問期日の主役である。しかるに、裁判所は、被拘束者らが「子ども」であることを理由に、意思無能力としてその人格を否認し、あたかも「家畜」か「物」のように扱っている。その必然的結果として、裁判所は、「審問のための公開の法廷」ではなく、「請求者のための子ども引渡所」に堕しているのであり、憲法第31条違反はあまりにも明白である。
これらのことは、人身保護法全26条、同規則全46条および昭和23年10月に最高裁事務局民事部が作成した「人身保護法解説」(民事裁判資料第8号)によれば、自明のことである。日本の裁判所の現行「実務」は、暗黒支配なのである。
1 人身保護法の「実務」
人身保護法は、昭和23年7月30日に制定された法律であり、その目的は「基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめること」とされている(同法第1条)。そして、同規則によれば、「拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい」(第3条)、また、請求の要件として「拘束がその権限なしにされていることが顕著である場合」で且つ「他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときは、その方法によって相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白」な場合に限るとされている(第4条)。さらに、「請求は、被拘束者の自由に表明した意思に反してこれをすることができない。」のである(第5条)。
この法律の本旨に照らせば、「拘束」とはいえない通常の監護状態下にある子の父母間における「身柄」争奪紛争に適用することはできないと思われる。ところが、たとえば未婚や離婚で単独親権の場合、あるいは、離婚前別居中に「監護者指定」や「引渡し」の本案審判や保全処分がなされた場合、「権限なしになされている」として、人身保護請求が認容されている。のみならず、請求認容の場合、審問手続(証拠調べ手続)は全く形骸化して、審問期日は事実上子の身柄を請求者に引渡す、執行手続になっていて、裁判所は「身柄引渡所」と化している。
本稿では、このような「実務」が、現実に著しい脱法行為の集積によっていることを明らかにする。と同時に、それがもたらしている人権侵害と家族破壊の惨状を告発する。
2 人身保護命令の暴虐――誘拐犯よりも迫害される親
人身保護法の規定による救済は、終局的には判決で実現されるのであるが、この救済を実現する人身保護手続は、通常の訴訟手続と異なり、人身保護命令を中心として構成されている(人身保護規則第2条)。すなわち、釈放その他適当であると認める処分を相手方たる拘束者が受忍し又は実行させるために判決前に特に必要的仮処分に準ずる人身保護命令という強力な手続を介在させたわけで、人身の自由の回復をより効果的にするための特別の制度である。決定でなされる人身保護命令は、独立した裁判でなく、判決手続の一部にすぎないもので、裁判所は釈放の状態を自ら形成するのである。そして、相手方にこの効果を受忍させるために、制裁の条件付で人身保護命令によって受忍義務を課するのである。
具体的には、拘束者が人身保護命令に従わないときに、「命令に従うまで勾留する」との制裁がある(人身保護法第12条3項)。これは、刑事訴訟法の勾留と異なり、裁判所の裁判、命令に従わないとき、その実行を促す秩序罰的なもので、本来は裁判所侮辱罪に対する制裁なのであるが、裁判所侮辱罪の制度が制定されるまで、やむなく準用したのである。そして、刑事訴訟法の勾留に関する規定の中、勾留の原由および期間は準用されず、期間について言えば、刑事訴訟法では「公訴の提起があった日から2箇月」とされているが(同第60条2項)、人身保護法による勾留は「命令に従うまで」とされ、無期限である。
拘束者が被拘束者を出頭させない場合の勾留の制裁は、拘束者を勾留したまま命令に従わせることはできないことであるから、命令に従う意思が認められたならば、拘束者を釈放して被拘束者の身柄を提出させることを意味している。すなわち、拘束者が父の場合、父は、勾留という重大な脅威を回避して自らの「人身の自由」を保持するには、母への引渡を拒絶している子(被拘束者)の意思に反して「子を差し出す」しかないのである。これが人倫に悖ることは多言を要しない。拘束者にとって「子を差し出す」ことは、「意に反する苦役」(憲法第18条)であり、「良心の自由の侵害」(同第19条)である。そして、このような勾留は、憲法第36条で禁止された「拷問」ないし「残虐な刑罰」というべきものである。
このことは、刑法第224条未成年者略取誘拐犯の場合と比較すれば、一層明らかになる。誘拐犯でさえ、適正手続が保障されるし、その刑罰も「3月以上7年以下の懲役」である。それに比べ、父親であるばかりに、拘束者は、無期限の勾留の脅しを受けたうえ、判決で親権・監護権を実質的に剥奪されるのである。一体いつから日本はこのように恐ろしい国になったのであろうか。しかも、人身保護制度の基となっているのが、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されない」という憲法第34条なのだから、悪夢というほかない。
3 人身保護請求認容判決の内容と執行力
人身保護法第16条1項は、「裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもってこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。」と定めている。これは、拘束者の拘束が正当であるなら、その拘束を継続させるために「引渡す」必要があるからである。
一方、同条3項は、「請求を理由ありとするときは、判決をもって被拘束者を直ちに釈放する。」と、単に「釈放」を定めるのみであるところ、同規則第37条は、「裁判所は、請求を理由があるとするときは、判決で、被拘束者を直ちに釈放し、又は被拘束者が幼児若しくは精神病者であるときその他被拘束者につき特別の事情があると認めるときは、被拘束者の利益のために適当であると認める処分をすることができる。」と定めている。すなわち、幼児や精神病者等の場合には、単に「釈放」するだけでは釈放の目的が達成されないので、釈放類似の、または釈放の性質を有する処分が認められる。しかし、それは被拘束者につき特別の事情があると認められること、また、被拘束者の利益のための処分でなければならない。
ところで、人身保護法の規定による救済は、終局的には判決で実現されるところ、その執行については、民事訴訟法による強制執行は親しまないと解されている。被拘束者が幼児の場合でも、引渡の強制執行はできないと解されているし、間接強制もできないとされている。すなわち、人身保護法の裁判の執行力は、家事審判および審判前の保全処分に比べると、格段に劣っている。裁判所が、審問期日を口実にして被拘束者を「別室」に出頭させ、形式的に審問期日を経て即日認容判決をし、請求者に被拘束者を事実上引渡してしまうのも、その執行力の不備を「補う」ために編み出された脱法行為である。そして、このような違法な実務の指南書になっているのは、昭和52年3月に発刊された「人身保護請求事件に関する実務的研究」(裁判所書記官実務報告書第13巻1号)なる、書記官丸投げマニュアルである。しかしながら、昭和55年家事審判法改正により審判前の保全処分が制度化される前の実務マニュアルを履行するなど狂気というほかなく、憲法第76条3項に違反することも明白である。
人身保護法の第1回審問期日は、憲法第34条後段に基づくものであり、刑事手続でいえば「勾留理由開示公判」(刑事訴訟法第82条〜86条)に比すべきもので、被拘束者こそが審問期日の主役である。しかるに、裁判所は、被拘束者らが「子ども」であることを理由に、意思無能力としてその人格を否認し、あたかも「家畜」か「物」のように扱っている。その必然的結果として、裁判所は、「審問のための公開の法廷」ではなく、「請求者のための子ども引渡所」に堕しているのであり、憲法第31条違反はあまりにも明白である。
これらのことは、人身保護法全26条、同規則全46条および昭和23年10月に最高裁事務局民事部が作成した「人身保護法解説」(民事裁判資料第8号)によれば、自明のことである。日本の裁判所の現行「実務」は、暗黒支配なのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
NPO 離婚後の子どもを守る会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO 離婚後の子どもを守る会 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人