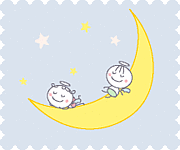谷岡参議院議員を通じて質問主意書↓を提出しました。 近近参議院のホームページにアップされます。 ご注意下さい。
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年五月○○日
谷 岡 郁 子
参議院議長 江 田 五 月 殿
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとつて最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准しいている国連子供の権利条約第九条第3項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。
ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方の親と面接交渉できない子が少なくない。
特に、離婚後の親権者、あるいは、その配偶者(内縁を含む)を加害者とする児童虐待事件によって、子の命が奪われるケースも多々見られている。面接交渉についての明確な規定に基づき、子供と同居していない親が子供と定期的に会って、子供の身体面、心理面についての変化を目にしていれば、こうした事件は、相当程度防げるはずである。
よって、以下質問する。
1. 現行の民法第八一九条は、離婚の場合、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している。このことが、親権者をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。
2. 離婚の際の、親権者をめぐる争いにおいて、調停や裁判の実務では現状追認の傾向が強く、現に子を占有する親が親権者となりやすいと認識されている。このため、離婚係争中の一方の親による子の連れ去りや、逆にこれを防ぐための相手方配偶者からの子の隠ぺいがしばしば問題となっている。こうした現状は、子の最善の利益に著しく反するものとして問題であると考えるが、どのように考えるか。
3. 現行の民法第八一九条は単独親権を強制し、また、裁判実務は、親権者ではない親と子との面接交渉を十分に確保することに他の先進国に比べ消極的である。さらに、離婚前後に生じた相手方への不信感を払拭できない多くの元夫婦の間では、子と元配偶者との間の不十分な面接交渉すら妨害される事例が少なくない。
多くの先進国において、両親が離婚した場合、子は双方の親と関わりを続けることが健全な成長を促す上で望ましいとされており、単に監護に関する決定をするだけでなく、監護調整を行うペアレンティング・コーディネーター(監護調整人)という職種を導入する例もあると言われる。わが国でも、離婚後の両親の紛争を抑え、子が双方の親との関わりを適切に続けるための継続的サポートの提供がますます必要となること考えられるが、どのように考えるか。
4. わが国の民法では、面接交渉などの離婚後の親子の交流について明確な規定がない。こうした不備が、離婚後の元夫婦間のトラブルや、子の双方の親との適切な関わりを困難にしているとの指摘がある。この指摘を、どのように考えるか。
5. わが国は一九九四年五月、いわゆる『国連子どもの権利条約』を批准した。同条約第九条第三項では、親の離婚後でも、子どもの権利として親とは分離されないことが明示されている。わが国は、同条約を批准したにもかかわらず、非親権者・非監護者の親と子との適切な交流がなされないケースが多々認められる。政府は条約を厳密に解釈し、日本の法制度は条約に違反していないと弁明するのではなく、子の利益をより確実に保障し、よりよい親子関係及び家族関係を築くことができるように法制度を整備すべきと考えるが、どのように考えるか。
6. 『国連子どもの権利条約』第十二条に「締約国は、自己の意見をもつ能力のある児童には、 その児童に影響を与える問題のすべてに関して自己の意見を自由に表明する権利を保障しなければならない・・・・」とされている。親の離婚問題について十五歳未満子どもの意思や希望はほとんど無視されている日本の状況は、上記権利条約の趣旨から逸脱していると言わざるを得ない。今後は国連子どもの権利条約に基づき、子の監護に関して子の人権尊重の立場から権利の主体であるばかりか権利行使の主体である子の意見を代理人を付けることにより聴く必要があると考えられ、また、幼少の子どもに関しては、代わって判断できる第三者の介入・援助も必要であると考えられるが、どのように考えるか。
7. 最高裁判所のHPに公開された司法統計によると、面接交渉・子の監護者指定・引き渡しなど子の監護をめぐる問題が乙類審判事件新授件数の34.5%を占めている。このうち、面接交渉が問題とされた案件はどのくらいあり、面接交渉を命じた事例、禁止した事例はどの程度あるかを示す司法統計はあるか。また、取り下げにより終結した事例のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立した事案、解決が困難なため取り下げとなり事実上あきらめざるをえなくなった事案がそれぞれどの程度存在するかを示す司法統計はあるか。
もし、かかる司法統計が存在しない場合、今後司法統計をとる考えはあるか。
8. 平成8年2月26日に法務省法制審議会総会決定した『民法の一部を改正する法律案要綱』では、第六の一で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」とされている。この改正は、元夫婦の離婚後の不毛なトラブルを防ぎ、子と双方の親との適切な関わりを継続して、子の福祉を増進する上で、緊急に実現すべきであるが、どう考えるか。
9. 現在、多くの教育の現場では、非親権者の親は、親権者の同意が無ければ子の学校の記録の入手や学校行事への参加を事実上拒まれている。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していると考えられるが、どう考えるか。
10. 離婚後親権親による児童虐待事案で、児童相談所が虐待された子を保護した場合、現状では非親権親にはなんら情報提供もなされていない。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していることはもとより、更なる児童虐待を抑止する観点からも、児童相談所は、非親権者に虐待された実子の情報を与え、非親権者も児童虐待事案に対し実親としてかかわるような運用をすることが子の最善の利益を守る事であると考えるが、どう考えるか。
右質問する。
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年五月○○日
谷 岡 郁 子
参議院議長 江 田 五 月 殿
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとつて最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准しいている国連子供の権利条約第九条第3項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。
ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方の親と面接交渉できない子が少なくない。
特に、離婚後の親権者、あるいは、その配偶者(内縁を含む)を加害者とする児童虐待事件によって、子の命が奪われるケースも多々見られている。面接交渉についての明確な規定に基づき、子供と同居していない親が子供と定期的に会って、子供の身体面、心理面についての変化を目にしていれば、こうした事件は、相当程度防げるはずである。
よって、以下質問する。
1. 現行の民法第八一九条は、離婚の場合、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している。このことが、親権者をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。
2. 離婚の際の、親権者をめぐる争いにおいて、調停や裁判の実務では現状追認の傾向が強く、現に子を占有する親が親権者となりやすいと認識されている。このため、離婚係争中の一方の親による子の連れ去りや、逆にこれを防ぐための相手方配偶者からの子の隠ぺいがしばしば問題となっている。こうした現状は、子の最善の利益に著しく反するものとして問題であると考えるが、どのように考えるか。
3. 現行の民法第八一九条は単独親権を強制し、また、裁判実務は、親権者ではない親と子との面接交渉を十分に確保することに他の先進国に比べ消極的である。さらに、離婚前後に生じた相手方への不信感を払拭できない多くの元夫婦の間では、子と元配偶者との間の不十分な面接交渉すら妨害される事例が少なくない。
多くの先進国において、両親が離婚した場合、子は双方の親と関わりを続けることが健全な成長を促す上で望ましいとされており、単に監護に関する決定をするだけでなく、監護調整を行うペアレンティング・コーディネーター(監護調整人)という職種を導入する例もあると言われる。わが国でも、離婚後の両親の紛争を抑え、子が双方の親との関わりを適切に続けるための継続的サポートの提供がますます必要となること考えられるが、どのように考えるか。
4. わが国の民法では、面接交渉などの離婚後の親子の交流について明確な規定がない。こうした不備が、離婚後の元夫婦間のトラブルや、子の双方の親との適切な関わりを困難にしているとの指摘がある。この指摘を、どのように考えるか。
5. わが国は一九九四年五月、いわゆる『国連子どもの権利条約』を批准した。同条約第九条第三項では、親の離婚後でも、子どもの権利として親とは分離されないことが明示されている。わが国は、同条約を批准したにもかかわらず、非親権者・非監護者の親と子との適切な交流がなされないケースが多々認められる。政府は条約を厳密に解釈し、日本の法制度は条約に違反していないと弁明するのではなく、子の利益をより確実に保障し、よりよい親子関係及び家族関係を築くことができるように法制度を整備すべきと考えるが、どのように考えるか。
6. 『国連子どもの権利条約』第十二条に「締約国は、自己の意見をもつ能力のある児童には、 その児童に影響を与える問題のすべてに関して自己の意見を自由に表明する権利を保障しなければならない・・・・」とされている。親の離婚問題について十五歳未満子どもの意思や希望はほとんど無視されている日本の状況は、上記権利条約の趣旨から逸脱していると言わざるを得ない。今後は国連子どもの権利条約に基づき、子の監護に関して子の人権尊重の立場から権利の主体であるばかりか権利行使の主体である子の意見を代理人を付けることにより聴く必要があると考えられ、また、幼少の子どもに関しては、代わって判断できる第三者の介入・援助も必要であると考えられるが、どのように考えるか。
7. 最高裁判所のHPに公開された司法統計によると、面接交渉・子の監護者指定・引き渡しなど子の監護をめぐる問題が乙類審判事件新授件数の34.5%を占めている。このうち、面接交渉が問題とされた案件はどのくらいあり、面接交渉を命じた事例、禁止した事例はどの程度あるかを示す司法統計はあるか。また、取り下げにより終結した事例のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立した事案、解決が困難なため取り下げとなり事実上あきらめざるをえなくなった事案がそれぞれどの程度存在するかを示す司法統計はあるか。
もし、かかる司法統計が存在しない場合、今後司法統計をとる考えはあるか。
8. 平成8年2月26日に法務省法制審議会総会決定した『民法の一部を改正する法律案要綱』では、第六の一で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」とされている。この改正は、元夫婦の離婚後の不毛なトラブルを防ぎ、子と双方の親との適切な関わりを継続して、子の福祉を増進する上で、緊急に実現すべきであるが、どう考えるか。
9. 現在、多くの教育の現場では、非親権者の親は、親権者の同意が無ければ子の学校の記録の入手や学校行事への参加を事実上拒まれている。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していると考えられるが、どう考えるか。
10. 離婚後親権親による児童虐待事案で、児童相談所が虐待された子を保護した場合、現状では非親権親にはなんら情報提供もなされていない。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していることはもとより、更なる児童虐待を抑止する観点からも、児童相談所は、非親権者に虐待された実子の情報を与え、非親権者も児童虐待事案に対し実親としてかかわるような運用をすることが子の最善の利益を守る事であると考えるが、どう考えるか。
右質問する。
|
|
|
|
コメント(5)
参議院に出した質問主意書が質問事項が多いので皆さんにはこちらを参照いただければと思っています。 以下が答弁書です。
答弁書
答弁書第一二五号
内閣参質一六九第一二五号
平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。
二について
親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。
三について
父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。
御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。
四について
三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。
続く
答弁書
答弁書第一二五号
内閣参質一六九第一二五号
平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。
二について
親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。
三について
父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。
御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。
四について
三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。
続く
五について
我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。
三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。したがって、法務省としては、御指摘の法制度の整備については、これを行う必要性は乏しいものと考えている。
六について
我が国の親の離婚に関する人事訴訟、家事審判、家事調停の各手続においては、制度上、十五歳未満の子も、意見や希望を述べることを制限されておらず、また、家庭裁判所は、個別の事案に応じて、必要と認められる場合には、子の意見を適切に考慮しているものと承知しており、児童の権利に関する条約の趣旨を逸脱した状況にあるものとは考えていない。
御指摘のような「代理人」による意見聴取や「第三者の介入・援助」の制度を導入することについては、このような我が国の現状を前提としつつ、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。
七について
最高裁判所が公表している司法統計中、家事審判事件に関する統計には、乙類審判事件である子の監護者の指定その他の処分事件のうち、面接交渉に関する審判の申立てがあるものの件数を示す統計があるものと承知している。また、そのような事件のうち、申立てを認容したものの件数と申立てを却下したものの件数を示す統計があるものと承知している。
他方、取下げにより終局した事件のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立したものや、解決が困難なため取下げとなり事実上あきらめざるを得なくなったものの件数を示す司法統計はないものと承知している。家事審判は、裁判所において行われるものであることから、法務省としてこのような統計をとることは考えていない。
八について
法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、三についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。
九について
御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
十について
児童相談所が、親権者である親に虐待された子の情報を親権者でない親に提供すること等の運用を行うことについては、必ずしも当該親権者でない親の支援を期待することが適当でない場合も想定されるため、各児童相談所において、個別・具体の事例に応じて、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。
三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。したがって、法務省としては、御指摘の法制度の整備については、これを行う必要性は乏しいものと考えている。
六について
我が国の親の離婚に関する人事訴訟、家事審判、家事調停の各手続においては、制度上、十五歳未満の子も、意見や希望を述べることを制限されておらず、また、家庭裁判所は、個別の事案に応じて、必要と認められる場合には、子の意見を適切に考慮しているものと承知しており、児童の権利に関する条約の趣旨を逸脱した状況にあるものとは考えていない。
御指摘のような「代理人」による意見聴取や「第三者の介入・援助」の制度を導入することについては、このような我が国の現状を前提としつつ、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。
七について
最高裁判所が公表している司法統計中、家事審判事件に関する統計には、乙類審判事件である子の監護者の指定その他の処分事件のうち、面接交渉に関する審判の申立てがあるものの件数を示す統計があるものと承知している。また、そのような事件のうち、申立てを認容したものの件数と申立てを却下したものの件数を示す統計があるものと承知している。
他方、取下げにより終局した事件のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立したものや、解決が困難なため取下げとなり事実上あきらめざるを得なくなったものの件数を示す司法統計はないものと承知している。家事審判は、裁判所において行われるものであることから、法務省としてこのような統計をとることは考えていない。
八について
法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、三についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。
九について
御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
十について
児童相談所が、親権者である親に虐待された子の情報を親権者でない親に提供すること等の運用を行うことについては、必ずしも当該親権者でない親の支援を期待することが適当でない場合も想定されるため、各児童相談所において、個別・具体の事例に応じて、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
NPO 離婚後の子どもを守る会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO 離婚後の子どもを守る会 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人