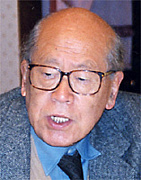オンリーワンロード:埼玉ひと物語 俳人・金子兜太さん/1 /埼玉
<Only One Road>
◇「知的野性」へのあこがれ 句会で評判「こりゃおもしれえな」
「私自身が五七五の塊です。きどったことを言えば、俳句が私のアイデンティティーです」。俳人、金子兜太さん(91)は、「熊猫荘(ゆうびょうそう)」と呼ぶ熊谷市内の自宅で語った。
「五七五を使っている間は、自分が自由に振る舞っている。表現の自由っていうのを堪能してる。そんな思いがあります」。照れたように笑った。土や草花を見つめてきた目は温かかった。
□ □
1919年、母の実家である小川町で生まれた。俳句を身近な存在にしたのは、父の元春さんだった。国神村(現在の皆野町)で医院を開業した元春さんは、秩父郡内の若者を集めて句会を始めた。
当時、元春さんの学生時代の同級生だった水原秋桜子(しゅうおうし)が俳誌「馬酔木(あしび)」を始めていた。叙情性を取り入れた新しい俳句に挑戦していた。
「友達の秋桜子が一旗揚げるというから、おやじは俳句がうまくもないくせに、協力したいと思ったんだろう。いなかっぺというのは義理堅いんだよ」
句会には来るのは、秩父の山で養蚕や畑仕事をする30〜40代の元気のいい男たち。
「みんな知的な欲求に飢えていた。学校に行きたいが長男じゃないから行けない。新鮮な気分で俳句をやっていました」
句会の後は、酒や食事が振る舞われた。批評が高じると、しばしば殴り合いになった。金子さんの弟、千侍さん(82)は「わいわいといつもにぎやかな家だった」と笑う。
伊昔紅(いせきこう)の俳号を持つ元春さんは、秩父音頭の歌詞も手掛けた。今も地元の人々に愛される名調子だ。
♪花の長瀞 あの岩畳 誰をまつやら おぼろ月
10代だった金子さんは、夢うつつの枕元で元春さんがつぶやく詞を聞いて育った。
「毎晩聞かされているうちに、七七七五の歌詞は私の体に染み込んでいきました」
□ □
俳句を初めて詠んだのは、旧制水戸高校2年生の時だった。先輩に誘われた句会でだった。それまで俳句を詠んだことがなかったのは、母はるさんが反対していたからだ。
「父の句会に集まっては騒ぐ男たちを見てきた母は、『お前は俳句なんかやるんじゃない。すぐけんかする。ろくなもんじゃねえ』ってよく言っていました」
白梅や老子無心の旅に住む
参加した句会で、水戸の名所、偕楽園の鮮やかな白梅を詠んだ。北原白秋が書いた「老子は無心の旅に出た」という内容の詩に「住む」という独自の言葉を加えた。
「その句が評判良くてえらい点が入った。こりゃおもしれえなと思ったよ」。それから毎回句会に行くようになった。俳句雑誌にも投稿した。
俳句にのめりこむようになって気付いたという。「結局、おやじの句会に集まった男たちにあこがれていたんだ。知的で野性的なあの武骨な雰囲気が好きだったんです」
知的野性。金子さんはこの言葉をよく使う。「私自身もそういう人間になっているのかもしれません」
□ □
「オンリーワンロード−−埼玉ひと物語」の第9回は俳人、金子兜太さん。俳句に触れた幼少時代、死と直面した戦争体験、そして改めて五七五の魅力を聞きます。【西田真季子】=つづく
==============
■人物略歴
◇かねこ・とうた
1919年小川町生まれ、皆野町で育つ。東京大学卒業後、日本銀行に入行し定年まで勤務する。加藤楸邨に師事し、秩父の自然や人間の本能的な思いを表す前衛俳句の旗手として活躍。俳誌「海程」主宰、第1句集「少年」、代表句集は「両神」「東国抄」など。紫綬褒章。現代俳句協会名誉会長。熊谷市在住
<Only One Road>
◇「知的野性」へのあこがれ 句会で評判「こりゃおもしれえな」
「私自身が五七五の塊です。きどったことを言えば、俳句が私のアイデンティティーです」。俳人、金子兜太さん(91)は、「熊猫荘(ゆうびょうそう)」と呼ぶ熊谷市内の自宅で語った。
「五七五を使っている間は、自分が自由に振る舞っている。表現の自由っていうのを堪能してる。そんな思いがあります」。照れたように笑った。土や草花を見つめてきた目は温かかった。
□ □
1919年、母の実家である小川町で生まれた。俳句を身近な存在にしたのは、父の元春さんだった。国神村(現在の皆野町)で医院を開業した元春さんは、秩父郡内の若者を集めて句会を始めた。
当時、元春さんの学生時代の同級生だった水原秋桜子(しゅうおうし)が俳誌「馬酔木(あしび)」を始めていた。叙情性を取り入れた新しい俳句に挑戦していた。
「友達の秋桜子が一旗揚げるというから、おやじは俳句がうまくもないくせに、協力したいと思ったんだろう。いなかっぺというのは義理堅いんだよ」
句会には来るのは、秩父の山で養蚕や畑仕事をする30〜40代の元気のいい男たち。
「みんな知的な欲求に飢えていた。学校に行きたいが長男じゃないから行けない。新鮮な気分で俳句をやっていました」
句会の後は、酒や食事が振る舞われた。批評が高じると、しばしば殴り合いになった。金子さんの弟、千侍さん(82)は「わいわいといつもにぎやかな家だった」と笑う。
伊昔紅(いせきこう)の俳号を持つ元春さんは、秩父音頭の歌詞も手掛けた。今も地元の人々に愛される名調子だ。
♪花の長瀞 あの岩畳 誰をまつやら おぼろ月
10代だった金子さんは、夢うつつの枕元で元春さんがつぶやく詞を聞いて育った。
「毎晩聞かされているうちに、七七七五の歌詞は私の体に染み込んでいきました」
□ □
俳句を初めて詠んだのは、旧制水戸高校2年生の時だった。先輩に誘われた句会でだった。それまで俳句を詠んだことがなかったのは、母はるさんが反対していたからだ。
「父の句会に集まっては騒ぐ男たちを見てきた母は、『お前は俳句なんかやるんじゃない。すぐけんかする。ろくなもんじゃねえ』ってよく言っていました」
白梅や老子無心の旅に住む
参加した句会で、水戸の名所、偕楽園の鮮やかな白梅を詠んだ。北原白秋が書いた「老子は無心の旅に出た」という内容の詩に「住む」という独自の言葉を加えた。
「その句が評判良くてえらい点が入った。こりゃおもしれえなと思ったよ」。それから毎回句会に行くようになった。俳句雑誌にも投稿した。
俳句にのめりこむようになって気付いたという。「結局、おやじの句会に集まった男たちにあこがれていたんだ。知的で野性的なあの武骨な雰囲気が好きだったんです」
知的野性。金子さんはこの言葉をよく使う。「私自身もそういう人間になっているのかもしれません」
□ □
「オンリーワンロード−−埼玉ひと物語」の第9回は俳人、金子兜太さん。俳句に触れた幼少時代、死と直面した戦争体験、そして改めて五七五の魅力を聞きます。【西田真季子】=つづく
==============
■人物略歴
◇かねこ・とうた
1919年小川町生まれ、皆野町で育つ。東京大学卒業後、日本銀行に入行し定年まで勤務する。加藤楸邨に師事し、秩父の自然や人間の本能的な思いを表す前衛俳句の旗手として活躍。俳誌「海程」主宰、第1句集「少年」、代表句集は「両神」「東国抄」など。紫綬褒章。現代俳句協会名誉会長。熊谷市在住
|
|
|
|
コメント(3)
オンリーワンロード:埼玉ひと物語 俳人・金子兜太さん/2 /埼玉
毎日新聞 9月25日(土)12時6分配信
<Only One Road>
◇戦争の罪滅ぼししたい 目の前で死んだ仲間思い
目に強い光が宿った。俳人、金子兜太さん(91)は、それまでの柔和な表情を一変させた。
「人間が目の前で吹っ飛んで死んだ。もう、考えるなんてできなくなるんだよ」
1944年3月、西太平洋のミクロネシア・トラック島。主計中尉として第4海軍施設部に配属された。戦況は悪化の一途だった。7月にサイパンが陥落すると、食糧や武器の補給が断たれた。
部隊は武器を手作りすることを考え、仲間の男性が試作品の手りゅう弾を投げた。
爆発の瞬間−−。
男性の右手が吹っ飛び背中の肉がえぐれた。金子さんたちは、即死した男性を病院に運んだ。
「数人で担ぎ上げた。私は周りを『わっしょい、わっしょい』と言って囲んで走った。もう死んでいるんだから病院に運んでもしょうがない、無駄だなんて思わない。勝手に体が動いていた」
兵士を志し、日銀を3日で辞めて海軍経理学校に入った。卒業の時には、希望地に「南方第一線」と書くほど血気盛んだった。
「生産力で圧倒的に劣る日本は負けるだろう」と冷静な半面、「どっちみち戦争に行くんだったら勝つしかない。勝つために全力投球でやってやろう」という思いもあった。
その行き着いた先が、仲間の残酷な死だった。
「死というものが理屈なく自分に迫ってきた。死ぬということがいかに重大なことか。戦争はいかに残酷か、悲惨か。それ以来、死ちゅうものを非常に重く考えるようになりました」
□ □
1945年、25歳の時に島で終戦を迎えた。心にわいたのは安堵(あんど)でなくむなしさだった。食糧調達の責任者だった自分の前で餓死していく仲間。そして、手りゅう弾の実験。
「自分が非常に軽薄な人間に思えた。なんてくだらねえ野郎なんだ。今までの罪滅ぼしをしなくてはいかん。出直さなくちゃいかん」。島で書いた日記やメモなどを全部焼き捨てた。
俳句も、軽薄さの代表のように思えた。「もうつくるまい」と決心した。ところが、句は体の中に自然にわいてきた。終戦後、1年3カ月の島での米軍捕虜生活でも俳句が浮かんでくる自分をとめられなかった。「やめようと思ってもできてしまう」
引き揚げ船で日本へ帰る時、頭の中に俳句がたまっていた。「このまま忘れるのももったいない気がした」。薄い紙に句を書き留めると、配給されたせっけんに小さな穴を開けて詰め込んだ。
「うちに帰って紙を開いてみたら、せっけんのにおいがしばらくしてました」。作った俳句は日銀に復職後、ノートに書き写した。その記録からできた初めての句集「少年」(1955年刊)は、現代俳句協会賞を受賞した。
戦争の体験は作品に強くにじむ。
彎曲(わんきょく)し火傷(かしょう)し爆心地のマラソン
被爆地、長崎に赴任した際に詠んだ。「戦争に対する罪償いをしたい」。戦後65年たってもあせることのない思いだ。【西田真季子】=つづく
………………………………………………………………………………………………………
■人物略歴
◇かねこ・とうた
1919年小川町生まれ、皆野町で育つ。東京大学卒業後、日本銀行に入行し定年まで勤務する。加藤楸邨に師事し、秩父の自然や人間の本能的な思いを表す前衛俳句の旗手として活躍。俳誌「海程」主宰、第1句集「少年」、代表句集は「両神」「東国抄」など。紫綬褒章。現代俳句協会名誉会長。熊谷市在住。
9月25日朝刊
毎日新聞 9月25日(土)12時6分配信
<Only One Road>
◇戦争の罪滅ぼししたい 目の前で死んだ仲間思い
目に強い光が宿った。俳人、金子兜太さん(91)は、それまでの柔和な表情を一変させた。
「人間が目の前で吹っ飛んで死んだ。もう、考えるなんてできなくなるんだよ」
1944年3月、西太平洋のミクロネシア・トラック島。主計中尉として第4海軍施設部に配属された。戦況は悪化の一途だった。7月にサイパンが陥落すると、食糧や武器の補給が断たれた。
部隊は武器を手作りすることを考え、仲間の男性が試作品の手りゅう弾を投げた。
爆発の瞬間−−。
男性の右手が吹っ飛び背中の肉がえぐれた。金子さんたちは、即死した男性を病院に運んだ。
「数人で担ぎ上げた。私は周りを『わっしょい、わっしょい』と言って囲んで走った。もう死んでいるんだから病院に運んでもしょうがない、無駄だなんて思わない。勝手に体が動いていた」
兵士を志し、日銀を3日で辞めて海軍経理学校に入った。卒業の時には、希望地に「南方第一線」と書くほど血気盛んだった。
「生産力で圧倒的に劣る日本は負けるだろう」と冷静な半面、「どっちみち戦争に行くんだったら勝つしかない。勝つために全力投球でやってやろう」という思いもあった。
その行き着いた先が、仲間の残酷な死だった。
「死というものが理屈なく自分に迫ってきた。死ぬということがいかに重大なことか。戦争はいかに残酷か、悲惨か。それ以来、死ちゅうものを非常に重く考えるようになりました」
□ □
1945年、25歳の時に島で終戦を迎えた。心にわいたのは安堵(あんど)でなくむなしさだった。食糧調達の責任者だった自分の前で餓死していく仲間。そして、手りゅう弾の実験。
「自分が非常に軽薄な人間に思えた。なんてくだらねえ野郎なんだ。今までの罪滅ぼしをしなくてはいかん。出直さなくちゃいかん」。島で書いた日記やメモなどを全部焼き捨てた。
俳句も、軽薄さの代表のように思えた。「もうつくるまい」と決心した。ところが、句は体の中に自然にわいてきた。終戦後、1年3カ月の島での米軍捕虜生活でも俳句が浮かんでくる自分をとめられなかった。「やめようと思ってもできてしまう」
引き揚げ船で日本へ帰る時、頭の中に俳句がたまっていた。「このまま忘れるのももったいない気がした」。薄い紙に句を書き留めると、配給されたせっけんに小さな穴を開けて詰め込んだ。
「うちに帰って紙を開いてみたら、せっけんのにおいがしばらくしてました」。作った俳句は日銀に復職後、ノートに書き写した。その記録からできた初めての句集「少年」(1955年刊)は、現代俳句協会賞を受賞した。
戦争の体験は作品に強くにじむ。
彎曲(わんきょく)し火傷(かしょう)し爆心地のマラソン
被爆地、長崎に赴任した際に詠んだ。「戦争に対する罪償いをしたい」。戦後65年たってもあせることのない思いだ。【西田真季子】=つづく
………………………………………………………………………………………………………
■人物略歴
◇かねこ・とうた
1919年小川町生まれ、皆野町で育つ。東京大学卒業後、日本銀行に入行し定年まで勤務する。加藤楸邨に師事し、秩父の自然や人間の本能的な思いを表す前衛俳句の旗手として活躍。俳誌「海程」主宰、第1句集「少年」、代表句集は「両神」「東国抄」など。紫綬褒章。現代俳句協会名誉会長。熊谷市在住。
9月25日朝刊
オンリーワンロード:埼玉ひと物語 俳人・金子兜太さん/3 /埼玉
毎日新聞 9月26日(日)11時15分配信
<Only One Road>
◇古里・秩父の土が原点 生き物への愛情あふれ
加須市にある龍蔵寺の境内に5月、一つの句碑がお目見えした。金子兜太さん(91)が昨年秋に寺で講演をした縁で、由木義文住職が建立した。
檀家(だんか)らが集まった除幕式で、金子さんは「私の句碑はたくさんあるが、ばかでかいのは食傷気味です。この句碑に満足しています」と話し、高さ40センチほどの石造りの碑に優しく手を置いた。
おおかみに蛍が一つ付いていた
刻まれた句は、金子さんの「生き物感覚」を代表する作品とされている。
「すべての生き物が同じ命の固まり。人間も、オオカミも、蛍も、咲いている庭の花々もみんな同じ友達」
生きとし生けるものはみんな平等で、どんな命もいとおしい。そんな思いが伝わる。
□ □
「人間というものを一度見直して見なければ」。金子さんがそう考えたのは1960年代後半だった。戦前の発言や態度をがらりと変えた人々。高度成長で豊かさを謳歌(おうか)する人々。「偉そうなことを言っている人間というのは何なんだろう」
言葉がするすると続いた。
「人間は非常に純粋なものを持っている。森の中に住んでいたと言われる原始の人間は樹木のにおいを嗅(か)いだり、他の生き物たちと関係し合って生きていた。そういう命のおおもと、生き物感覚が身についている。金銭や名誉など欲の塊である人間でも、この生き物感覚を失わなければましな生活ができる」
金子さんにとって、生き物感覚の基本となったのは、古里・秩父であったことにも思いが至った。「うぶすな」と呼ぶ秩父の土が草花や樹木を育て、虫や獣を生みだし、人間さえも養ってくれた。
「(秩父音頭の)七七七五を体に染み込ませてもらったし、野性っていうことの良さに気付かせてくれたのも秩父。私の生き物感覚もそこが基本となって養われてきていると今思っています。秩父っていうのは、私の原点なんです」
□ □
飾らない金子さんの周囲には人が集まる。
句碑の除幕式にも参加し、約10年間師事する吉川渓美さん(70)=加須市=は「先生の魅力は俳句だけではない。あるがまま、むき出しの人間くささがあって、でも温かい気持ちが通っている」と話す。
「金子先生のファンです」と話すのは、30年以上師事している伊藤淳子さん(78)=東京都練馬区。
「こんな句を出すくらいなら、せんべいでも食べて寝てらっしゃい」と金子さんに批評されたことがある。その後に「でも真剣に俳句を学ぶつもりなら、不肖金子が胸を貸します」と声をかけられたという。
東京都内での俳句講座の後、にぎやかな雑談が始まった。一見すると、誰が先生で生徒か分からないほど和やかな雰囲気だ。金子さんのユーモアを交えた辛口の言葉の裏には、人や生き物すべてへの愛情がある。その根底には「生き物感覚」が流れている。【西田真季子】=つづく
毎日新聞 9月26日(日)11時15分配信
<Only One Road>
◇古里・秩父の土が原点 生き物への愛情あふれ
加須市にある龍蔵寺の境内に5月、一つの句碑がお目見えした。金子兜太さん(91)が昨年秋に寺で講演をした縁で、由木義文住職が建立した。
檀家(だんか)らが集まった除幕式で、金子さんは「私の句碑はたくさんあるが、ばかでかいのは食傷気味です。この句碑に満足しています」と話し、高さ40センチほどの石造りの碑に優しく手を置いた。
おおかみに蛍が一つ付いていた
刻まれた句は、金子さんの「生き物感覚」を代表する作品とされている。
「すべての生き物が同じ命の固まり。人間も、オオカミも、蛍も、咲いている庭の花々もみんな同じ友達」
生きとし生けるものはみんな平等で、どんな命もいとおしい。そんな思いが伝わる。
□ □
「人間というものを一度見直して見なければ」。金子さんがそう考えたのは1960年代後半だった。戦前の発言や態度をがらりと変えた人々。高度成長で豊かさを謳歌(おうか)する人々。「偉そうなことを言っている人間というのは何なんだろう」
言葉がするすると続いた。
「人間は非常に純粋なものを持っている。森の中に住んでいたと言われる原始の人間は樹木のにおいを嗅(か)いだり、他の生き物たちと関係し合って生きていた。そういう命のおおもと、生き物感覚が身についている。金銭や名誉など欲の塊である人間でも、この生き物感覚を失わなければましな生活ができる」
金子さんにとって、生き物感覚の基本となったのは、古里・秩父であったことにも思いが至った。「うぶすな」と呼ぶ秩父の土が草花や樹木を育て、虫や獣を生みだし、人間さえも養ってくれた。
「(秩父音頭の)七七七五を体に染み込ませてもらったし、野性っていうことの良さに気付かせてくれたのも秩父。私の生き物感覚もそこが基本となって養われてきていると今思っています。秩父っていうのは、私の原点なんです」
□ □
飾らない金子さんの周囲には人が集まる。
句碑の除幕式にも参加し、約10年間師事する吉川渓美さん(70)=加須市=は「先生の魅力は俳句だけではない。あるがまま、むき出しの人間くささがあって、でも温かい気持ちが通っている」と話す。
「金子先生のファンです」と話すのは、30年以上師事している伊藤淳子さん(78)=東京都練馬区。
「こんな句を出すくらいなら、せんべいでも食べて寝てらっしゃい」と金子さんに批評されたことがある。その後に「でも真剣に俳句を学ぶつもりなら、不肖金子が胸を貸します」と声をかけられたという。
東京都内での俳句講座の後、にぎやかな雑談が始まった。一見すると、誰が先生で生徒か分からないほど和やかな雰囲気だ。金子さんのユーモアを交えた辛口の言葉の裏には、人や生き物すべてへの愛情がある。その根底には「生き物感覚」が流れている。【西田真季子】=つづく
オンリーワンロード:埼玉ひと物語 俳人・金子兜太さん/4止 /埼玉
毎日新聞 9月27日(月)10時56分配信
<Only One Road>
◇「わたしはまだ過程にある」 91歳の今も毎日俳句作り
金子兜太さん(91)が熊谷市に住んで40年余りになる。東京都内からこの地に引っ越すには、妻みな子さんの助言があった。
「あんたは土の上に住まないと駄目な人間になる」
普段は淡々としたみな子さんは毅然(きぜん)とそう言うと、家も見つけてきた。金子さんが、あらゆる生き物へ平等な目を向ける「生き物感覚」を意識したころと重なる。
結婚は1947年。終戦後にトラック島から戻って、知人から紹介された。「非常に感性が澄んだ女の子で、こっちがほれたんですよ」。半年ほどで一緒になった。
朝日けぶる手中の蚕妻に示す
「いい句でしょう」珍しく自作をほめながら紹介した。結婚直後、秩父の畑をみな子さんと散歩した際の俳句だ。山あいの秩父では、生糸を生み出す蚕は「蚕さま」と呼ばれる特別な存在だ。「蚕を示すことが妻への親しみの証しだった」
手のひらに蚕を載せ優しい表情で、みな子さんに見せる姿が浮かぶ。みな子さんも結婚後に俳句(俳号・皆子)を始め、現代俳句協会賞を受賞した。
06年、みな子さんは他界した。「4年たった今でも、いろんな瞬間にみな子がこんなこと言っていた、していたということが浮かぶ。アオダモの花が咲けば、花を見てこういう表情してたなとか。(記憶が)薄れていくだろうと思ったら全然変わらない。時には困るくらい切実に思い出すんです」
□ □
前衛俳句の旗手として、俳句の伝統や決まりは最短定型の五七五で書くことだけだ、と考える。
「季語などそれ以外の約束は、五七五が生み出した属性に過ぎない。五七五は古事記以来の日本語の叙情形式で、体の中に染みついたこのリズムにのっかって、感情や訴えたいことを言えばいい」
五七五で十分に表現しきるため、言葉の使い方を大切にしている。「本当の俳人、歌人は言葉の扱いが深くなる。中でも俳句は短い分、よりデリケートに扱う。妥協しない。助詞一つで全体の印象が変わる」
座右の銘は小林一茶が自らを称した「荒凡夫(あらぼんぶ)」。煩悩から抜けられない平凡な自分、それでもこのまま自由に生かしてほしい。その根底には、生き物感覚がある。「自分もそうでありたい」
□ □
91歳になった今も毎日俳句を作る。朝、目が覚めて布団で浮かんだことが俳句になる。「ほとんど苦労しない。大便をするみたいにすーっとできちゃう。これしか能がない」と笑う。
01年に発表した句集「東国抄」のあとがきで「わたしはまだ過程にある」と記した。「痛風になって体質改造にも取り組んで、むしろ元気になった」
酒止(や)めようかどの本能と遊ぼうか
荒凡夫の旅は続く。【西田真季子】=おわり
………………………………………………………………………………………………………
毎日新聞 9月27日(月)10時56分配信
<Only One Road>
◇「わたしはまだ過程にある」 91歳の今も毎日俳句作り
金子兜太さん(91)が熊谷市に住んで40年余りになる。東京都内からこの地に引っ越すには、妻みな子さんの助言があった。
「あんたは土の上に住まないと駄目な人間になる」
普段は淡々としたみな子さんは毅然(きぜん)とそう言うと、家も見つけてきた。金子さんが、あらゆる生き物へ平等な目を向ける「生き物感覚」を意識したころと重なる。
結婚は1947年。終戦後にトラック島から戻って、知人から紹介された。「非常に感性が澄んだ女の子で、こっちがほれたんですよ」。半年ほどで一緒になった。
朝日けぶる手中の蚕妻に示す
「いい句でしょう」珍しく自作をほめながら紹介した。結婚直後、秩父の畑をみな子さんと散歩した際の俳句だ。山あいの秩父では、生糸を生み出す蚕は「蚕さま」と呼ばれる特別な存在だ。「蚕を示すことが妻への親しみの証しだった」
手のひらに蚕を載せ優しい表情で、みな子さんに見せる姿が浮かぶ。みな子さんも結婚後に俳句(俳号・皆子)を始め、現代俳句協会賞を受賞した。
06年、みな子さんは他界した。「4年たった今でも、いろんな瞬間にみな子がこんなこと言っていた、していたということが浮かぶ。アオダモの花が咲けば、花を見てこういう表情してたなとか。(記憶が)薄れていくだろうと思ったら全然変わらない。時には困るくらい切実に思い出すんです」
□ □
前衛俳句の旗手として、俳句の伝統や決まりは最短定型の五七五で書くことだけだ、と考える。
「季語などそれ以外の約束は、五七五が生み出した属性に過ぎない。五七五は古事記以来の日本語の叙情形式で、体の中に染みついたこのリズムにのっかって、感情や訴えたいことを言えばいい」
五七五で十分に表現しきるため、言葉の使い方を大切にしている。「本当の俳人、歌人は言葉の扱いが深くなる。中でも俳句は短い分、よりデリケートに扱う。妥協しない。助詞一つで全体の印象が変わる」
座右の銘は小林一茶が自らを称した「荒凡夫(あらぼんぶ)」。煩悩から抜けられない平凡な自分、それでもこのまま自由に生かしてほしい。その根底には、生き物感覚がある。「自分もそうでありたい」
□ □
91歳になった今も毎日俳句を作る。朝、目が覚めて布団で浮かんだことが俳句になる。「ほとんど苦労しない。大便をするみたいにすーっとできちゃう。これしか能がない」と笑う。
01年に発表した句集「東国抄」のあとがきで「わたしはまだ過程にある」と記した。「痛風になって体質改造にも取り組んで、むしろ元気になった」
酒止(や)めようかどの本能と遊ぼうか
荒凡夫の旅は続く。【西田真季子】=おわり
………………………………………………………………………………………………………
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
金子兜太 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
金子兜太のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75503人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208297人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人