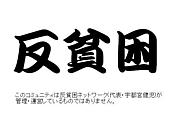毎日新聞 http://
「最低限の読み書き計算ができない子が増えているのではないか」。日本の子供たちに必要な「学力」とは何か。第4回は、多重債務者、子供の貧困問題などに取り組む弁護士の宇都宮健児さんに聞いた。
−−社会に出るまでに、必要な「学力」とは何でしょうか。
いろいろ考えたが、(答えるのは)なかなか難しいね。日本の社会で生きていくために、よく言われる「読み書き計算」は、最低限の基礎学力として必要じゃないか。戦後生まれの僕たちと比べて、特に算数ができないまま、社会に出ている人が増えているという印象があります。そのうえで、他人を思いやる想像力、他人の痛みが分かる力が、ほかの雑多な知識より重要だと思います。
−−算数の力が落ちていますか?
約30年、多重債務問題に取り組んできましたが、被害の大きな原因の一つは高金利です。借りたお金に対して何割の金利がついて、自分の収入から毎月いくらを返済にあてなければならないのか、基本的な計算ができない人が増えていると感じます。家計をきちんと管理するにも、そういった計算力がないとだめでしょう。闇金融が増えた時、10日で4割、5割の金利をとる業者がかなり横行しました。実は、取材に来たテレビ局のスタッフも、10日で4割が1年でどのくらいになるのか、スムーズに計算できなかった。
−−学校で教わっても身についていないのでしょうか。
学校では「無駄遣いをやめましょう」といった抽象的なことは教えますが、社会で必要なのは具体的な知識です。例えば、派遣労働のように非正規で働く人が安易にローンを利用して、多重債務者になってしまった時に相談する先や、解決法についてはほとんど教えられていない。教員自身が多重債務に陥って、どうすればいいか分からないケースも多いのです。
また、憲法には、健康で文化的な最低限度の生活を認めた生存権の規定(25条)があり、これは学校で教えるし、入試にも出ます。でも、生活保護の具体的なことについては教えていない。厚生労働省によると、生活保護水準に満たない家庭で、生活保護を受給しているのは約3割です。あとの7割は権利を行使していない。労働基本権についても同じで、働いている人が自分の権利を行使できない場合、どのように苦情申し立てをすればよいのか教わっていない。基礎的な読み書き計算の力がないと、こういった情報にコンタクトすることも、なかなかできない。
−−どうやって学べばよいでしょうか。
学校によっては、子供たちが畑で野菜や米を作って販売し、費用を計算して、利益を分配するといった経験をさせています。また、生活保護家庭が多くて、生徒の多くがアルバイトをしている高校で、アルバイト先から労働契約書をもらってこさせて、労働基準法を教えている先生もいます。生徒自身が働いているから、体験と結びついて、いろいろ考える。分かりやすいのではないかと思います。
−−若者にお薦めの本を紹介してください。
推薦したいのは、僕が大学時代に読んで、弁護士になることを決断した本。「わたしゃそれでも生きてきた 部落からの告発」(東上高志編、部落問題研究所)と、「小さな胸は燃えている 産炭地児童の生活記録集」(芝竹夫編、文理書院)の2冊で、絶版になっているんだけど、古本で買えたら読んでみてほしい。
「わたしゃ〜」は部落で育った女性12人の手記です。この中に、52歳の女性がひらがなで書いた文章があります。この人は貧しくて学校に行けなかったんですね。字を知らなかった。載っているのは「あいうえお」を教わって最初に書いた文章です。当時の僕の両親と同じくらいの年齢で、両親も貧しかったけど、字は書けた。世の中に字が書けない人がいることを初めて知りました。
もう1冊の「小さな〜」は、炭鉱の子供の作文や詩をまとめた本です。エネルギー政策の転換で、炭鉱が縮小、閉山した時代、炭鉱労働者の子供たちの生活がすさんでくる。そんな生活で感じたことをありのままに書かせた。例えば、小学校5年生の「どろぼう」という詩では、学校の先生はどろぼうはいけないと教えているのに、自分の父親はどろぼうしてこいという。銅線を盗んでこいと。でも、やりたくないと訴えている。僕の家も、漁村で開拓農家で苦しかったので、将来は官僚になるか、大企業に入って、なんとか貧乏から脱出しようと思っていたんですが、自分以外にも苦しんでいる人がたくさんいる。自分だけが抜け出すのではなく、そういう人たちのためになる仕事がないかと思って、弁護士になった。そう決めたのはこの2冊を読んだからです。【聞き手・岡礼子】
◇略歴
1946年愛媛県生まれ。68年、司法試験に合格し、東大法学部を中退。71年弁護士登録。2010年4月から日本弁護士連合会会長。全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長、「反貧困ネットワーク」代表などを務め、長年、多重債務や暴力団対策問題などに取り組む。著書に「弁護士、闘う 宇都宮健児の事件帖」(岩波書店)、共著に「反貧困の学校−−貧困をどう伝えるか、どう学ぶか」(明石書店)など。
「最低限の読み書き計算ができない子が増えているのではないか」。日本の子供たちに必要な「学力」とは何か。第4回は、多重債務者、子供の貧困問題などに取り組む弁護士の宇都宮健児さんに聞いた。
−−社会に出るまでに、必要な「学力」とは何でしょうか。
いろいろ考えたが、(答えるのは)なかなか難しいね。日本の社会で生きていくために、よく言われる「読み書き計算」は、最低限の基礎学力として必要じゃないか。戦後生まれの僕たちと比べて、特に算数ができないまま、社会に出ている人が増えているという印象があります。そのうえで、他人を思いやる想像力、他人の痛みが分かる力が、ほかの雑多な知識より重要だと思います。
−−算数の力が落ちていますか?
約30年、多重債務問題に取り組んできましたが、被害の大きな原因の一つは高金利です。借りたお金に対して何割の金利がついて、自分の収入から毎月いくらを返済にあてなければならないのか、基本的な計算ができない人が増えていると感じます。家計をきちんと管理するにも、そういった計算力がないとだめでしょう。闇金融が増えた時、10日で4割、5割の金利をとる業者がかなり横行しました。実は、取材に来たテレビ局のスタッフも、10日で4割が1年でどのくらいになるのか、スムーズに計算できなかった。
−−学校で教わっても身についていないのでしょうか。
学校では「無駄遣いをやめましょう」といった抽象的なことは教えますが、社会で必要なのは具体的な知識です。例えば、派遣労働のように非正規で働く人が安易にローンを利用して、多重債務者になってしまった時に相談する先や、解決法についてはほとんど教えられていない。教員自身が多重債務に陥って、どうすればいいか分からないケースも多いのです。
また、憲法には、健康で文化的な最低限度の生活を認めた生存権の規定(25条)があり、これは学校で教えるし、入試にも出ます。でも、生活保護の具体的なことについては教えていない。厚生労働省によると、生活保護水準に満たない家庭で、生活保護を受給しているのは約3割です。あとの7割は権利を行使していない。労働基本権についても同じで、働いている人が自分の権利を行使できない場合、どのように苦情申し立てをすればよいのか教わっていない。基礎的な読み書き計算の力がないと、こういった情報にコンタクトすることも、なかなかできない。
−−どうやって学べばよいでしょうか。
学校によっては、子供たちが畑で野菜や米を作って販売し、費用を計算して、利益を分配するといった経験をさせています。また、生活保護家庭が多くて、生徒の多くがアルバイトをしている高校で、アルバイト先から労働契約書をもらってこさせて、労働基準法を教えている先生もいます。生徒自身が働いているから、体験と結びついて、いろいろ考える。分かりやすいのではないかと思います。
−−若者にお薦めの本を紹介してください。
推薦したいのは、僕が大学時代に読んで、弁護士になることを決断した本。「わたしゃそれでも生きてきた 部落からの告発」(東上高志編、部落問題研究所)と、「小さな胸は燃えている 産炭地児童の生活記録集」(芝竹夫編、文理書院)の2冊で、絶版になっているんだけど、古本で買えたら読んでみてほしい。
「わたしゃ〜」は部落で育った女性12人の手記です。この中に、52歳の女性がひらがなで書いた文章があります。この人は貧しくて学校に行けなかったんですね。字を知らなかった。載っているのは「あいうえお」を教わって最初に書いた文章です。当時の僕の両親と同じくらいの年齢で、両親も貧しかったけど、字は書けた。世の中に字が書けない人がいることを初めて知りました。
もう1冊の「小さな〜」は、炭鉱の子供の作文や詩をまとめた本です。エネルギー政策の転換で、炭鉱が縮小、閉山した時代、炭鉱労働者の子供たちの生活がすさんでくる。そんな生活で感じたことをありのままに書かせた。例えば、小学校5年生の「どろぼう」という詩では、学校の先生はどろぼうはいけないと教えているのに、自分の父親はどろぼうしてこいという。銅線を盗んでこいと。でも、やりたくないと訴えている。僕の家も、漁村で開拓農家で苦しかったので、将来は官僚になるか、大企業に入って、なんとか貧乏から脱出しようと思っていたんですが、自分以外にも苦しんでいる人がたくさんいる。自分だけが抜け出すのではなく、そういう人たちのためになる仕事がないかと思って、弁護士になった。そう決めたのはこの2冊を読んだからです。【聞き手・岡礼子】
◇略歴
1946年愛媛県生まれ。68年、司法試験に合格し、東大法学部を中退。71年弁護士登録。2010年4月から日本弁護士連合会会長。全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長、「反貧困ネットワーク」代表などを務め、長年、多重債務や暴力団対策問題などに取り組む。著書に「弁護士、闘う 宇都宮健児の事件帖」(岩波書店)、共著に「反貧困の学校−−貧困をどう伝えるか、どう学ぶか」(明石書店)など。
|
|
|
|
|
|
|
|
反貧困 更新情報
-
最新のアンケート
反貧困のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6464人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19245人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208301人