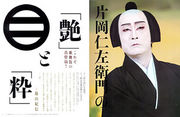|
|
|
|
コメント(5)
夜の部は、「夏祭」の通し狂言。七月の歌舞伎の時、劇場で職員から聞いた話では、今回は上方のやり方でやります、と言うので期待していた。お鯛茶屋、住吉鳥居前、上本町道具屋、三婦内・長屋町裏、田島町団七内・同大屋根と文楽でも出ない場が出た。
結果は、期待通りが半分、期待外れが半分。
一番の欠点は、季節の設定である。「住吉鳥居前の場」は春である。浄瑠璃の本文を読めば一目瞭然。それを江戸演出と同じように夏にしてしまった。それ以上に、最初から最後まで夏にしてしまった。江戸の演出では、「住吉鳥居前の場」「釣船三婦の場」「長屋町裏の場」しか出ないのなら、強引に全部を夏にしてしまう事も可能であろう。しかし、今回は通しである。首抜きの浴衣が着たいから、と住吉鳥居前の場を夏にするのは江戸役者のわがままである。なにもそれを見習う事はない。
期待通りは歌舞伎では通常上演されない、文楽でもあまり上演されない段を上演してくれたことにある。これだけ、出ていると話がわかりやすい。これまでの上演で疑問が残る部分が解消された。どうして、団七や徳兵衛が磯之丞にこれだけ、つくそうとするのかが、よくわかった。それに、釈放されてから真面目に暮らしていた団七がやむにやまれず人を殺してしまう、と言う悲劇であるのがよくわかった。
まずはお鯛茶屋。団七女房のお梶が壱太郎。磯之丞を騙す役なので役が重すぎるかと心配したが、以外に検討している。磯之丞は薪車、この場ではちょっと堅い。琴浦の尾上右近は、色気に乏しい。事件はこの女の色香に磯之丞が迷ったから起こるのだが、教えて貰った事をちゃんとやってます、と言う程度に留まる。それにこの場は、磯之丞を騙して色町から家に帰らせようとするのだが、これではちょっと騙されそうもない。
次いで鳥居前。前述した通り、期待外れに終わった。ただ、三婦が褌を出すところが面白い。それに、首抜きの衣装で出てくる愛之助の団七がとてもきれいである。
次いで、内本町道具屋の段。ここからが面白くなる。この場があるから、次の三婦内の場で磯之丞が三婦の家にかくまわれている理由、琴浦が怒っている理由がわかる。薪車の磯之丞はこの場が一番似合っている。色男でありながら、きりっとしたとこがあり、薪車がいい。それに良いのは、番頭伝八の猿弥である。元々関西の人でないから、変な東京訛りは仕方が無いが、なかなか面白い。義平次の 橘三郎が好演。磯之丞は清七と名前を変え、道具屋で奉公している。その清七に惚れる娘お仲の新悟が、これも色気に欠ける。通り一遍、教えて貰った事をそのままやってます、と言うことがまるわかり。本文でも、この芝居でも、住吉の場からすくなくとも3月はたっている。それなのに、登場人物の着物が薄物あり、袷あり、とまちまち。それに、全部を夏にしているので無理が出てくる。次に横堀番小屋の場が出るが、本文では道具屋の場に含まれる。それを独立した場として出し、後半をだんまりにしたのが面白いアイデアだと思った。しかし、そのおもしろさが十分生かし切れていない。それに幕を締めて道具を替えるので芝居の流れが途切れる。もともと一つの場なのだから、幕を開けたままでで道具を替えてもいいのではないか。
ここで幕間となる。
結果は、期待通りが半分、期待外れが半分。
一番の欠点は、季節の設定である。「住吉鳥居前の場」は春である。浄瑠璃の本文を読めば一目瞭然。それを江戸演出と同じように夏にしてしまった。それ以上に、最初から最後まで夏にしてしまった。江戸の演出では、「住吉鳥居前の場」「釣船三婦の場」「長屋町裏の場」しか出ないのなら、強引に全部を夏にしてしまう事も可能であろう。しかし、今回は通しである。首抜きの浴衣が着たいから、と住吉鳥居前の場を夏にするのは江戸役者のわがままである。なにもそれを見習う事はない。
期待通りは歌舞伎では通常上演されない、文楽でもあまり上演されない段を上演してくれたことにある。これだけ、出ていると話がわかりやすい。これまでの上演で疑問が残る部分が解消された。どうして、団七や徳兵衛が磯之丞にこれだけ、つくそうとするのかが、よくわかった。それに、釈放されてから真面目に暮らしていた団七がやむにやまれず人を殺してしまう、と言う悲劇であるのがよくわかった。
まずはお鯛茶屋。団七女房のお梶が壱太郎。磯之丞を騙す役なので役が重すぎるかと心配したが、以外に検討している。磯之丞は薪車、この場ではちょっと堅い。琴浦の尾上右近は、色気に乏しい。事件はこの女の色香に磯之丞が迷ったから起こるのだが、教えて貰った事をちゃんとやってます、と言う程度に留まる。それにこの場は、磯之丞を騙して色町から家に帰らせようとするのだが、これではちょっと騙されそうもない。
次いで鳥居前。前述した通り、期待外れに終わった。ただ、三婦が褌を出すところが面白い。それに、首抜きの衣装で出てくる愛之助の団七がとてもきれいである。
次いで、内本町道具屋の段。ここからが面白くなる。この場があるから、次の三婦内の場で磯之丞が三婦の家にかくまわれている理由、琴浦が怒っている理由がわかる。薪車の磯之丞はこの場が一番似合っている。色男でありながら、きりっとしたとこがあり、薪車がいい。それに良いのは、番頭伝八の猿弥である。元々関西の人でないから、変な東京訛りは仕方が無いが、なかなか面白い。義平次の 橘三郎が好演。磯之丞は清七と名前を変え、道具屋で奉公している。その清七に惚れる娘お仲の新悟が、これも色気に欠ける。通り一遍、教えて貰った事をそのままやってます、と言うことがまるわかり。本文でも、この芝居でも、住吉の場からすくなくとも3月はたっている。それなのに、登場人物の着物が薄物あり、袷あり、とまちまち。それに、全部を夏にしているので無理が出てくる。次に横堀番小屋の場が出るが、本文では道具屋の場に含まれる。それを独立した場として出し、後半をだんまりにしたのが面白いアイデアだと思った。しかし、そのおもしろさが十分生かし切れていない。それに幕を締めて道具を替えるので芝居の流れが途切れる。もともと一つの場なのだから、幕を開けたままでで道具を替えてもいいのではないか。
ここで幕間となる。
釣船三婦内の場。この場が一番面白かった。最初からだんじり囃子が聞こえ夏の感じがよく出ている。三婦女房おつぎに扇乃丞。この年齢設定が良い。おつぎは老けの役だがおばあさんではない。人形では、老女形の頭を使う。だから、徳兵衛女房お辰が訪ねて来たとき、焼き餅を焼くのがもっともらしくなる。
お辰の吉弥が良い。本文通りの「二十六七な」感じで、鉄火な感じが無い。極普通な女房と言う感じで出てくる。そのすっとしたところが良い。その普通の女が、顔に色気があると言われ、焼きごてを顔に当てる。そんな極普通と思っていた女の中の異常さがよく出ている。
お辰がひっこんでから、からみの二人が出てきて、三婦にけんかを売るところ、そのけんかを三婦が買って着物を着替えるが、そこでちょっと手間取るのが惜しい。それに、翫雀の三婦は、あまりにも人が良すぎて、侠客らしい所に欠けるところが惜しい。
それから、お辰が磯之丞を連れて花道から引っ込む。それを見送るのはおつぎである。いつもは、お辰と磯之丞を見送るのは三婦だが、こちらの方が本文通りである。お辰の、こちの人が惚れたのはここでござんす、と胸をたたく所で余計な事思い入れをは一切しない。そこが快く潔くて良い。もっとも、ここは本文にはない入れごとだが。
段七・徳兵衛が三婦と出てきて、段七が、義平次が琴浦を連れて行ったと聞いて、引っ込む所が面白い。そして、長町裏の段。ここでの義平次と段七とのやりとりが面白い。ただ、後半立ち回りになると、どこか冗長な所がある。それに、三婦内とこの長町裏は返しなのに、幕を締めて場面展開するので芝居の流れが途切れる。それから、段七の着物が脱げるところが、上手く段取りが出来ていて、良かった。今までやり方だと、芝居だから着物を脱ぎます、とばかりに脱いでいるのだが、このやり方だと、自然に着物が脱げる、と言うのがよくわかる。一番良かったのは、最後、だれもいなくなった舞台に一寸徳兵衛の亀鶴が残って、段七の残した雪駄を見つける所。その亀鶴がなかなか良かった。
幕間の後は田島町団七内の場。ここでの亀鶴の徳兵衛がなかなか良かった。お梶の壱太郎はちょっと色気に欠ける。それにもう一つ練れていない感じが脱ぐえない。最後の大屋根は立ち回りを見せるだけの場だが、これもちょっと冗長である。
色々、不満なところがあるが、全体として面白かった。それに、上方の型と言うのが良い。愛之助が熱演なのは勿論、亀鶴、吉弥、薪車と皆頑張って芝居していてとても楽しめた。
お辰の吉弥が良い。本文通りの「二十六七な」感じで、鉄火な感じが無い。極普通な女房と言う感じで出てくる。そのすっとしたところが良い。その普通の女が、顔に色気があると言われ、焼きごてを顔に当てる。そんな極普通と思っていた女の中の異常さがよく出ている。
お辰がひっこんでから、からみの二人が出てきて、三婦にけんかを売るところ、そのけんかを三婦が買って着物を着替えるが、そこでちょっと手間取るのが惜しい。それに、翫雀の三婦は、あまりにも人が良すぎて、侠客らしい所に欠けるところが惜しい。
それから、お辰が磯之丞を連れて花道から引っ込む。それを見送るのはおつぎである。いつもは、お辰と磯之丞を見送るのは三婦だが、こちらの方が本文通りである。お辰の、こちの人が惚れたのはここでござんす、と胸をたたく所で余計な事思い入れをは一切しない。そこが快く潔くて良い。もっとも、ここは本文にはない入れごとだが。
段七・徳兵衛が三婦と出てきて、段七が、義平次が琴浦を連れて行ったと聞いて、引っ込む所が面白い。そして、長町裏の段。ここでの義平次と段七とのやりとりが面白い。ただ、後半立ち回りになると、どこか冗長な所がある。それに、三婦内とこの長町裏は返しなのに、幕を締めて場面展開するので芝居の流れが途切れる。それから、段七の着物が脱げるところが、上手く段取りが出来ていて、良かった。今までやり方だと、芝居だから着物を脱ぎます、とばかりに脱いでいるのだが、このやり方だと、自然に着物が脱げる、と言うのがよくわかる。一番良かったのは、最後、だれもいなくなった舞台に一寸徳兵衛の亀鶴が残って、段七の残した雪駄を見つける所。その亀鶴がなかなか良かった。
幕間の後は田島町団七内の場。ここでの亀鶴の徳兵衛がなかなか良かった。お梶の壱太郎はちょっと色気に欠ける。それにもう一つ練れていない感じが脱ぐえない。最後の大屋根は立ち回りを見せるだけの場だが、これもちょっと冗長である。
色々、不満なところがあるが、全体として面白かった。それに、上方の型と言うのが良い。愛之助が熱演なのは勿論、亀鶴、吉弥、薪車と皆頑張って芝居していてとても楽しめた。
昼の部と夜の部を見てきました。
新・油地獄『大阪純情伝』
近松門左衛門の「女殺油地獄」に、新たな解釈を加えた新作だったけれど、古典の部分はしっかりふまえていて大変けっこうでした。愛之助の色悪は当代仁左衛門ゆずりで最高ですね。
そうそう、壱太郎がしっかりしてきましたね。
市川猿弥も、いい役者ですね!
『夏祭浪花鑑』
故・中村勘三郎丈の当たり狂言として有名になりましたが、もともと関西歌舞伎の演目。
大阪が舞台なので当然セリフも大阪弁です。愛之助が良く演じてくれました。このお芝居はやはり流ちょうな大阪弁でないとあきません。
ただ、勘三郎のスケールの大きさに近づくためには、さらに精進が必要かな。
上村吉弥さすがにベテラン、いい味でした。花形はワキが若手が多いので、よけい上手さが際だちますね。
私は、じつは実川延若の「夏祭り」を中座で見ているんです(歳がバレる)。
生前、勘三郎丈は、延若丈から「夏祭り」を習ったとおっしゃっていました。同じく勘三郎丈が延若丈から習った「乳房の榎」。もういちど観たかったですね。
新・油地獄『大阪純情伝』
近松門左衛門の「女殺油地獄」に、新たな解釈を加えた新作だったけれど、古典の部分はしっかりふまえていて大変けっこうでした。愛之助の色悪は当代仁左衛門ゆずりで最高ですね。
そうそう、壱太郎がしっかりしてきましたね。
市川猿弥も、いい役者ですね!
『夏祭浪花鑑』
故・中村勘三郎丈の当たり狂言として有名になりましたが、もともと関西歌舞伎の演目。
大阪が舞台なので当然セリフも大阪弁です。愛之助が良く演じてくれました。このお芝居はやはり流ちょうな大阪弁でないとあきません。
ただ、勘三郎のスケールの大きさに近づくためには、さらに精進が必要かな。
上村吉弥さすがにベテラン、いい味でした。花形はワキが若手が多いので、よけい上手さが際だちますね。
私は、じつは実川延若の「夏祭り」を中座で見ているんです(歳がバレる)。
生前、勘三郎丈は、延若丈から「夏祭り」を習ったとおっしゃっていました。同じく勘三郎丈が延若丈から習った「乳房の榎」。もういちど観たかったですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
上方歌舞伎 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-