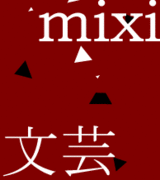【写真を焼く】
S医師から胃ガンを宣告されたとき洋介はすぐさま余命のことを訊いた。
「もって一年、早ければ半年ちょっと……」と申しわけなさそうに言うS医師に洋介は「わかりました。ありがとうございました」と答えた。S医師は患者の思いもかけぬ明るさに救われたような表情をした。洋介は自分でも声が場違いなほど明るいのではないかと思った。洋介は父も同様の症状でガンであったので自分もそうにちがいないと覚悟していた。
五年前死別したサチのことを思った。サチは大腸ガンで死んだ。死ぬ三ヶ月前に洋介と撮った写真や手紙をすべて始末したと言った。サチには夫も子どももいた。洋介は写真のことがずっと気がかりであったが、サチはなかなか始末しようとしなかった。「だって手紙や写真を見るとあなたが一緒だと思って力が出るの。それに夫は家を探したりしないわ」と言われると、洋介は返す言葉がなかった。「私死んじゃうんだからあとどうなってもいいし…」と自暴自棄になったこともあったが、結局、手紙、写真はきれいに始末してこの世を去った。
サチと同じ問題を洋介はここ二三年ずっと感じてきた。最近真昼の秋葉原で突然見も知らぬ異常者に何人もが殺された事件はショックだった。死病にかからなくても人はある日突然命を断たれることがある。歩く数歩先に死が待っているかもしれない。
いま自分が死んだら写真が残る。それが洋介の最大の懸念であった。しかし写真は処分できずにいた。いやむしろ撮影直後よりもっと頻繁に見るようになっていた。
この写真を妻が見たらどうなるのだろう。洋介はぞっとした。千恵は勘の鋭い女で夫の浮気はほとんど知っている。知っていて見ぬふりをする賢さを併せ持つ。男の生理、心理というものを長年の起き伏しを通じて理解したのか、それとも悲しみのはてに諦めたのか。いま千恵は夫を永遠の駄々っ子として真綿でくるむように対処している。
夫の健康を支えるべく朝夕、手塩にかけた料理をつくりつづけてきた。妻になんの非もない。洋介がよその女と関係をつづけてきたのは全く洋介の都合である。
この写真だけは見られてはいけない……結婚し子をなし家をともに育んできた相手への最低限の礼儀である。自分が生きていて不実を詰られるのはしかたない。千恵は夫にたぎる気持ちぶつけることでいくぶん憂さを晴らせるかもしれない。夫を無視して食事をつくらないという態度で抗議もできる。
しかし、夫が死んでしまってから生前の情事のあかしを、燃えたぎる溶岩をガラス器の中に閉じ込めたような形で見せられてどう思うだろう。爆発する思いをぶっつける的がないほど切なくつらいことはない。千恵はもちろん洋介にとってもそれは泥水をすするような残酷のものである。
しかしサチを撮ったヌード写真は絶品。発表するとすれば会員制のSМ雑誌しかないが、そんな気は洋介にはさらさらない。はじめはカメラを向けられて警戒していたサチだが洋介の嗜好を徐々に理解した。
「この人は自分の愉しみのためだけに私を写している、まるでガラスの瓶の中に蝶を閉じ込めるように」
絶頂に達しひらききった身体をサチは自分でどうすることもできなかった。そんな配慮ができないのが女に生れたしあわせ…身体は意思を失ってただただ雲の海に漂っていて、カメラのフラッシュに多少身体が揺らぐくらいのもの。無防備のサチをさまざまな角度から撮った写真をあまた洋介は持っている。それをときどき宝石箱をあけて光を確かめるように一人いつくしんでいる。
しかし写真は自宅へ置いておけなかった。
洋介は地元の銀行に貸し金庫を設けようとした。しかし本人が死んだときその管理などの権限はやはり配偶者に移行することを知り、写真の保管場所に窮した。墓に特別な保管場所をあつらえようとも思ったが、墓はまだ本籍地の八戸にある。東京への墓の移転もしなければならない。洋介はおさななじみの順平に写真の保管を頼んでいた。
洋介と順平は青森県八戸に生れ高校までずっと同じ教室で過ごした。高校を卒業して二人とも東京の大学へ入った。
洋介は大学時代に小説を書き同人誌を作って作家を夢見たがすぐその無謀さに気づき、出版社に入った。順平はカメラマンになった。企業が売り出す商品をカタログに載せるための写真を実直に撮っている。
「まさか、ヨーがこんなことになるとはな…」順平は小さな声で言った。
「医者に言われたときは真っ暗になったよ。膝がくがくしてさ…みっともなかったな」
「そりゃ誰だって…」
順平はおそるおそる洋介のコップにビールをついだ。
「あまり飲めんけどな。ときどき胃がギューンと差し込んでな…」
二人は軽くコップを合わせた。
ガンを告知された洋介は千恵についで順平に知らせた。順平は写真を持って居酒屋「バズーカ」に来て洋介と落ち合った。
「写真を始末する気になったのは最高によかったな」洋介は笑った。
「死ぬと言われてそんなこと思う奴、いるか?」順平も笑った。
「実はこの二三年どうしたら写真始末できるか考えててさ。いまのこの事態がいちばんだと思ってた…」
洋介はガンが高い確率で命を奪うこと、ただし死にいたるのに一定の時間がかかるのでこの世の懸案をある程度処理するゆとりがあることなど話した。「ガンっていい病気よ、老醜をさらさないで確実に死なせてもらえるんだから」と千恵が常々言っていたことが下敷きにあり、この事態でも心の平安をなんとか保っていられるのかもしれない。サチの闘病と二年じっくり向き合ったことも死の恐怖に対する免疫になっているのだろう。
「この写真ともサヨナラか」順平はほっとしたような、名残惜しそうな顔をして写真の入った袋を卓に置いた。順平は洋介が先に死んだら写真を処分するように言われていた。順平が先に死んだ場合がちょっと厄介だが、千恵に見つかるより順平の娘や母に見つかるほうがまだしも対処しやすかった。順平は妻をはやく亡くしていていて一人暮し。娘二人はすでに結婚している。
洋介は自分の撮った写真を袋から出して眺めた。
ソファに仰向けになった全裸のサチを足のほうから撮った写真である。サチは痩せていた。顔はのけぞっていて見えない。顎の輪郭は蹄鉄のように際立ち、鎖骨は尖り悲鳴を上げているかのようだ。胸は平板だが乳首が苺のように充血している。骨盤は皮膚を破りそうなほど突き出て腹部に落ち込み陰影をなしている。手の窪が吸い寄せられるような恥骨のふくらみ。痩せた女の恥骨はいじらしいほどふくらみ頬擦りしたくなる。それを中心に左右にうねるスロープは、小人になってスキーをしたいような愛らしさ。恥骨の下は黒々とした絶壁の中、滝のように割れて光っている。
いくたびも抱いた女だが写真を見てもなまなましい。痩せているのにしなやかでやわらかかった。写真に映っている身体は物でしかないが、さまざまな想念を呼び起こす。写真が呼び起こす記憶の量は膨大で、夏の野が草いきれを発するようにサチの息や言葉を伝えてくる。これに比べるとストリッパーが撮らせる一枚千円のポラロイド写真は、物語がなく砂漠のように乾いている。
「ヨーの写真っていいよ。女がこれ以上もう望まないというところまで突きつめた感じが全面に出ている。写真がいいというかそこまで素材を持ってきているのがすごいよ」順平はこの世でもう一人の閲覧者である。写真の背後に膨大に広がる洋介とサチの物語も知っている。「ヨーがカメラマンになってたらコマーシャルでなくて飯が食えたかも」
「やけに褒めるなあ。ジュンが趣味で撮る写真、すごいじゃん。プロはやはり違うよ」洋介は順平が密かに撮る写真に影響を受けていた。
順平は商品をクライアントが望むようにきちんとした露光とアングルで実直に撮ってきた。しかし仕事を離れるとアナーキーであった。妻に死なれてから女との関係は洋介同様絶間がなかったが、裸は撮らない。順平はカタツムリに異様な関心を示した。「かたつむりつるめば肉の食ひ入るや」という永田耕衣の俳句を知ったとき「文字に映像を越えられた」と悔しがった。以来、カタツムリにのめり込み、カタツムリ料理の本場フランスへ数回行っている。はじめは耕衣の俳句を越えようとしたのだが、次第に肉をレンズを通して活写することにのめり込んでいった。
順平はカタツムリを透明のガラスの上に置いて下から撮るようになった。ガラスに密着するとカタツムリは肉そのもの。これが動くとぞくぞくするほど訴えてくる。これはもう裏ビデオを見るよりも性的で猥褻……いいや、むしろあらゆる猥雑を除外した肉そのものの動きは神聖の領域へ入り込んでいる。順平が女を撮らないわけを洋介は深く理解していた。
洋介は順平と会った翌日の土曜日、奥多摩の高岩山へ向った。一月前シロヤシオを見にここへ来たとき道に迷った。繁茂した薮を抜けようとしたとき肩や首に毛虫がいくつかついた。そばに松の大木が四五本あって枯れかけていた。そのときはそこをすばやく通り過ぎたが、写真を始末しようと決意したときその場所がまほろばのように甘美によみがえった。
毛虫と一緒に写真を燃やす。
その考えが雷のように全身を走った。
前回うじゃうじゃいたと思った毛虫は今日見ると松の根元に十数匹いるにすぎない。燃やすという目的を持つとその数は多くない。サチの写真は五十枚ある。それに見合う毛虫が欲しい。見上げると幹にとりついてかなりうごめいている。棒で叩き落とすと毛虫は毬栗のようにおもしろいほど落ちてきた。どれも元気で放っておくとどこかへ行ってしまうので洋介はひとまず帽子の中に入れた。
一枚目の写真に火をつける。炎はときに青くときに緑がかってサチをつつむ。炎がサチの股間へ迫ると泣きたくなる。写真は一枚一枚微妙に異なりそれぞれがサチの違う声を伝える。五枚までは写真のみ静かに焼きサチとの感傷に浸っていたが、六枚目の写真を焼くとき毛虫一匹を載せてみた。火に触れて毛虫が反転してチリチリ音をたてる。その音は次の毛虫を燃やせという。二三匹毛虫を加えるとなんともいえぬ匂いがする。サチも燃えている。
洋介はサチの体臭を感じた。特に生理時のどうしようもない生臭さが鼻の奥をついた。毛虫の燃える匂いは女の生臭さとは全然ちがい食欲をかきたてるのだが、ふたつの匂いは渾然一体となった。洋介はたびたび胸を抑えて興奮に耐えた。
自分ももうじきこのように燃えてこの世を去ってゆく。サチはとうにこの世にいないが、その残像がいま消えてゆく。そしてサチを狂おしく抱いた自分もこのように煙になってゆく。洋介はすがすがしい思いで煙を吸っていた。
S医師から胃ガンを宣告されたとき洋介はすぐさま余命のことを訊いた。
「もって一年、早ければ半年ちょっと……」と申しわけなさそうに言うS医師に洋介は「わかりました。ありがとうございました」と答えた。S医師は患者の思いもかけぬ明るさに救われたような表情をした。洋介は自分でも声が場違いなほど明るいのではないかと思った。洋介は父も同様の症状でガンであったので自分もそうにちがいないと覚悟していた。
五年前死別したサチのことを思った。サチは大腸ガンで死んだ。死ぬ三ヶ月前に洋介と撮った写真や手紙をすべて始末したと言った。サチには夫も子どももいた。洋介は写真のことがずっと気がかりであったが、サチはなかなか始末しようとしなかった。「だって手紙や写真を見るとあなたが一緒だと思って力が出るの。それに夫は家を探したりしないわ」と言われると、洋介は返す言葉がなかった。「私死んじゃうんだからあとどうなってもいいし…」と自暴自棄になったこともあったが、結局、手紙、写真はきれいに始末してこの世を去った。
サチと同じ問題を洋介はここ二三年ずっと感じてきた。最近真昼の秋葉原で突然見も知らぬ異常者に何人もが殺された事件はショックだった。死病にかからなくても人はある日突然命を断たれることがある。歩く数歩先に死が待っているかもしれない。
いま自分が死んだら写真が残る。それが洋介の最大の懸念であった。しかし写真は処分できずにいた。いやむしろ撮影直後よりもっと頻繁に見るようになっていた。
この写真を妻が見たらどうなるのだろう。洋介はぞっとした。千恵は勘の鋭い女で夫の浮気はほとんど知っている。知っていて見ぬふりをする賢さを併せ持つ。男の生理、心理というものを長年の起き伏しを通じて理解したのか、それとも悲しみのはてに諦めたのか。いま千恵は夫を永遠の駄々っ子として真綿でくるむように対処している。
夫の健康を支えるべく朝夕、手塩にかけた料理をつくりつづけてきた。妻になんの非もない。洋介がよその女と関係をつづけてきたのは全く洋介の都合である。
この写真だけは見られてはいけない……結婚し子をなし家をともに育んできた相手への最低限の礼儀である。自分が生きていて不実を詰られるのはしかたない。千恵は夫にたぎる気持ちぶつけることでいくぶん憂さを晴らせるかもしれない。夫を無視して食事をつくらないという態度で抗議もできる。
しかし、夫が死んでしまってから生前の情事のあかしを、燃えたぎる溶岩をガラス器の中に閉じ込めたような形で見せられてどう思うだろう。爆発する思いをぶっつける的がないほど切なくつらいことはない。千恵はもちろん洋介にとってもそれは泥水をすするような残酷のものである。
しかしサチを撮ったヌード写真は絶品。発表するとすれば会員制のSМ雑誌しかないが、そんな気は洋介にはさらさらない。はじめはカメラを向けられて警戒していたサチだが洋介の嗜好を徐々に理解した。
「この人は自分の愉しみのためだけに私を写している、まるでガラスの瓶の中に蝶を閉じ込めるように」
絶頂に達しひらききった身体をサチは自分でどうすることもできなかった。そんな配慮ができないのが女に生れたしあわせ…身体は意思を失ってただただ雲の海に漂っていて、カメラのフラッシュに多少身体が揺らぐくらいのもの。無防備のサチをさまざまな角度から撮った写真をあまた洋介は持っている。それをときどき宝石箱をあけて光を確かめるように一人いつくしんでいる。
しかし写真は自宅へ置いておけなかった。
洋介は地元の銀行に貸し金庫を設けようとした。しかし本人が死んだときその管理などの権限はやはり配偶者に移行することを知り、写真の保管場所に窮した。墓に特別な保管場所をあつらえようとも思ったが、墓はまだ本籍地の八戸にある。東京への墓の移転もしなければならない。洋介はおさななじみの順平に写真の保管を頼んでいた。
洋介と順平は青森県八戸に生れ高校までずっと同じ教室で過ごした。高校を卒業して二人とも東京の大学へ入った。
洋介は大学時代に小説を書き同人誌を作って作家を夢見たがすぐその無謀さに気づき、出版社に入った。順平はカメラマンになった。企業が売り出す商品をカタログに載せるための写真を実直に撮っている。
「まさか、ヨーがこんなことになるとはな…」順平は小さな声で言った。
「医者に言われたときは真っ暗になったよ。膝がくがくしてさ…みっともなかったな」
「そりゃ誰だって…」
順平はおそるおそる洋介のコップにビールをついだ。
「あまり飲めんけどな。ときどき胃がギューンと差し込んでな…」
二人は軽くコップを合わせた。
ガンを告知された洋介は千恵についで順平に知らせた。順平は写真を持って居酒屋「バズーカ」に来て洋介と落ち合った。
「写真を始末する気になったのは最高によかったな」洋介は笑った。
「死ぬと言われてそんなこと思う奴、いるか?」順平も笑った。
「実はこの二三年どうしたら写真始末できるか考えててさ。いまのこの事態がいちばんだと思ってた…」
洋介はガンが高い確率で命を奪うこと、ただし死にいたるのに一定の時間がかかるのでこの世の懸案をある程度処理するゆとりがあることなど話した。「ガンっていい病気よ、老醜をさらさないで確実に死なせてもらえるんだから」と千恵が常々言っていたことが下敷きにあり、この事態でも心の平安をなんとか保っていられるのかもしれない。サチの闘病と二年じっくり向き合ったことも死の恐怖に対する免疫になっているのだろう。
「この写真ともサヨナラか」順平はほっとしたような、名残惜しそうな顔をして写真の入った袋を卓に置いた。順平は洋介が先に死んだら写真を処分するように言われていた。順平が先に死んだ場合がちょっと厄介だが、千恵に見つかるより順平の娘や母に見つかるほうがまだしも対処しやすかった。順平は妻をはやく亡くしていていて一人暮し。娘二人はすでに結婚している。
洋介は自分の撮った写真を袋から出して眺めた。
ソファに仰向けになった全裸のサチを足のほうから撮った写真である。サチは痩せていた。顔はのけぞっていて見えない。顎の輪郭は蹄鉄のように際立ち、鎖骨は尖り悲鳴を上げているかのようだ。胸は平板だが乳首が苺のように充血している。骨盤は皮膚を破りそうなほど突き出て腹部に落ち込み陰影をなしている。手の窪が吸い寄せられるような恥骨のふくらみ。痩せた女の恥骨はいじらしいほどふくらみ頬擦りしたくなる。それを中心に左右にうねるスロープは、小人になってスキーをしたいような愛らしさ。恥骨の下は黒々とした絶壁の中、滝のように割れて光っている。
いくたびも抱いた女だが写真を見てもなまなましい。痩せているのにしなやかでやわらかかった。写真に映っている身体は物でしかないが、さまざまな想念を呼び起こす。写真が呼び起こす記憶の量は膨大で、夏の野が草いきれを発するようにサチの息や言葉を伝えてくる。これに比べるとストリッパーが撮らせる一枚千円のポラロイド写真は、物語がなく砂漠のように乾いている。
「ヨーの写真っていいよ。女がこれ以上もう望まないというところまで突きつめた感じが全面に出ている。写真がいいというかそこまで素材を持ってきているのがすごいよ」順平はこの世でもう一人の閲覧者である。写真の背後に膨大に広がる洋介とサチの物語も知っている。「ヨーがカメラマンになってたらコマーシャルでなくて飯が食えたかも」
「やけに褒めるなあ。ジュンが趣味で撮る写真、すごいじゃん。プロはやはり違うよ」洋介は順平が密かに撮る写真に影響を受けていた。
順平は商品をクライアントが望むようにきちんとした露光とアングルで実直に撮ってきた。しかし仕事を離れるとアナーキーであった。妻に死なれてから女との関係は洋介同様絶間がなかったが、裸は撮らない。順平はカタツムリに異様な関心を示した。「かたつむりつるめば肉の食ひ入るや」という永田耕衣の俳句を知ったとき「文字に映像を越えられた」と悔しがった。以来、カタツムリにのめり込み、カタツムリ料理の本場フランスへ数回行っている。はじめは耕衣の俳句を越えようとしたのだが、次第に肉をレンズを通して活写することにのめり込んでいった。
順平はカタツムリを透明のガラスの上に置いて下から撮るようになった。ガラスに密着するとカタツムリは肉そのもの。これが動くとぞくぞくするほど訴えてくる。これはもう裏ビデオを見るよりも性的で猥褻……いいや、むしろあらゆる猥雑を除外した肉そのものの動きは神聖の領域へ入り込んでいる。順平が女を撮らないわけを洋介は深く理解していた。
洋介は順平と会った翌日の土曜日、奥多摩の高岩山へ向った。一月前シロヤシオを見にここへ来たとき道に迷った。繁茂した薮を抜けようとしたとき肩や首に毛虫がいくつかついた。そばに松の大木が四五本あって枯れかけていた。そのときはそこをすばやく通り過ぎたが、写真を始末しようと決意したときその場所がまほろばのように甘美によみがえった。
毛虫と一緒に写真を燃やす。
その考えが雷のように全身を走った。
前回うじゃうじゃいたと思った毛虫は今日見ると松の根元に十数匹いるにすぎない。燃やすという目的を持つとその数は多くない。サチの写真は五十枚ある。それに見合う毛虫が欲しい。見上げると幹にとりついてかなりうごめいている。棒で叩き落とすと毛虫は毬栗のようにおもしろいほど落ちてきた。どれも元気で放っておくとどこかへ行ってしまうので洋介はひとまず帽子の中に入れた。
一枚目の写真に火をつける。炎はときに青くときに緑がかってサチをつつむ。炎がサチの股間へ迫ると泣きたくなる。写真は一枚一枚微妙に異なりそれぞれがサチの違う声を伝える。五枚までは写真のみ静かに焼きサチとの感傷に浸っていたが、六枚目の写真を焼くとき毛虫一匹を載せてみた。火に触れて毛虫が反転してチリチリ音をたてる。その音は次の毛虫を燃やせという。二三匹毛虫を加えるとなんともいえぬ匂いがする。サチも燃えている。
洋介はサチの体臭を感じた。特に生理時のどうしようもない生臭さが鼻の奥をついた。毛虫の燃える匂いは女の生臭さとは全然ちがい食欲をかきたてるのだが、ふたつの匂いは渾然一体となった。洋介はたびたび胸を抑えて興奮に耐えた。
自分ももうじきこのように燃えてこの世を去ってゆく。サチはとうにこの世にいないが、その残像がいま消えてゆく。そしてサチを狂おしく抱いた自分もこのように煙になってゆく。洋介はすがすがしい思いで煙を吸っていた。
|
|
|
|
|
|
|
|
mixi文芸 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
mixi文芸のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人