本居宣長と鷹伝説からみえてくる邪馬台国と謎の4世紀
田川に舞い降りた新羅の神
その田川に残る伝説が、都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)という伽耶の王子がこの田川に住み着いたと豊前風土記は語る。また香春にある現人神神社にも同じ伝承が残る。
『日本書紀』における、都怒我阿羅斯等は伽耶から船で穴門(山口県)に着き、そこから出雲そして笥飯浦(敦賀)に来着したという。その名残が今の気比(けひ)こと敦賀(つるが)である。
『日本書紀』には同じ様な人物がもう一人記述されている。その神が天の日矛(あめのひほこ)と言う新羅の王が今の兵庫県豊岡市にたどり着いたいう。その両者に共通するのが、姫を追って日本へやって来たという内容だ。
豊前風土記を信用するなら、穴門よりこの田川の方が先となる。田川には香春神社が存在しこの香春神社には、渡来系の雰囲気が漂っているのである。
豊前国風土記によれば「田河の郡、香春の郷 郡の北東のかたにあり。此の郷の中に河あり。年魚(あゆ)あり。 其の源は郡の東北の杉坂山より出でて、すぐにま西を指して流れ下りて、真漏河に湊い会えり。 此の河の瀬清浄し、因りて清河原の村と号けき。今、香春の郷と謂うは訛れるなり。
昔、新羅の国の神、自ら度り到来りて、此の河原に住みき、すなわち名づけて香春の神と曰う。又、郷の北に峰あり。 頂に沼あり、 闊さ三十歩あり 。黄楊[つげ]の樹生いたり。兼、竜の骨あり。第二の峰には銅と竜の骨とあり。第三の峰には竜の骨あり。」
という記述と現人神神社の記述と風土記の内容が一致することがわかる。
そして香春にある香春神社の秘められた姿がまた凄い。香春三山(香春神社)に正一位の神階が与えられたのは、承和10年(843年)のことだったが、これは奈良の大神神社(859年)、石上神宮(868年)、大和神社(897年)が正一位になった年よりも、はるかに早い。そして豊前の国の一の宮は宇佐でなくこの香春(『全国神社名鑑』全国神社名鑑刊行会)という記述も残されているのだから謎は深まるばかりである。
この香春神社(香春三山)には、銅が採れ、鉄と金も少しだが採れていたと香春町の学芸員は説明していた。補足だが、遠賀川の左岸と右岸では全然違う文化が存在していたのも事実であり、私見として左岸の邪馬台国に対して右岸の渡来系(ヤマトと連携した)の国が存在していたに違いないと私は考えている。
『邪馬台国は秦族に征服された』安藤輝国氏の著書があるのも都怒我阿羅斯等は秦氏という渡来系に意味するならそう理解もできよう。また大和岩雄氏は「秦氏の研究で」新羅の神=秦氏=鍛冶=鷹という説明をしている。そう考えると、初期邪馬台国は北部九州の何処かに存在し、その邪馬台国を潰したのは「都怒我阿羅斯等」か。
この状況を説明するには、卑弥呼の時代に衰退している地域がある。それが伊都や吉野ヶ里である。逆に勢いが増したのが日田の小迫辻原遺跡(おざこつじばる)で、今でも日本最古の豪族居館跡で、この遺跡の特徴は布留式土器が出土する。考古学的には、布留式土器とはヤマトの土器と言ったほうが早い。そして宇佐などには赤塚古墳という前方後円墳ができる。
邪馬台国九州説の方には、九州がヤマトに滅ぼされると言うと反感を買うが、そう考えた事で、神話や伝承や考古学的な意味がつながってくると私は思う。
私見でしかないが、この都怒我阿羅斯等(武内宿禰)の勢力は磐井の乱の530年頃まで持続していたと私は思う。その象徴が「鷹」としか思えない。
邪馬台国と本居宣長
魏志』倭人伝の邪馬台国を本居宣長は、九州の偽ヤマトを『魏志』は記述しているという。その仮説を説いたのが本居宣長である。
本居は厳密には「邪馬台国=大和朝廷」であり、「魏志倭人伝」の「邪馬台国」は「九州の豪族が勝手に名乗った偽者」だと仮説している。
卑弥呼の時代は鉄=権力であり、朝鮮半島でも同じ現象がある。台与の時代になると鉄がヤマトへと移動を始めている。卑弥呼の時代は九州の遺跡発掘からもわかるように、圧倒的に多い。卑弥呼の時代とその卑弥呼の宗女(血縁関係はわからない)の時代には劇的な社会変化があとしか思えない現象である。
本居宣長の説を延長したら、卑弥呼と台与の時代に九州とヤマトは内乱状態が(『魏志』には卑弥呼の前に倭国大乱の記述)つづき、九州の偽卑弥呼が魏に朝貢し私が倭国の王であると報告した。一般的に本居宣長が九州説といわれるのだが、本当は偽物卑弥呼なのであるが、『魏志』を読む限り卑弥呼は九州なのである。
ヤマトが神話では神功皇后や仲哀天皇や武内宿禰が九州へ動き、そしてその動きと符合してくるのが日田市の日本最古の豪族居館跡の「小迫辻原遺跡」である。この遺跡は考古学も注目し、ヤマトの出城であり、謎の4世紀を解く重要な遺跡と新聞で紹介されている。
意外と知られていないのが田油津媛の兄である、夏羽の存在なのである。夏羽は田油津媛(卑弥呼かも)に援軍として行くときに、死んだ事を知り、逃げ帰ったという。そして、この田川になんと夏羽が殺されたという伝承が残っている。現在は夏羽から夏吉に地名が変わっているのだが、夏羽(陰)のイメージからか地名も変化したのだろう。
仮に卑弥呼の時代の九州勢力図として、伊都を中心とした勢力が、この香春の銅の権力を保持し、鉄と銅をヤマトからの勢力に奪われないように対抗していたのではないか。
本居宣長の説の延長にはどうも、ヤマトと連合した都怒我阿羅斯等(天の日矛)が田川を攻め支配したという構図につながる。
そして九州邪馬台国は都怒我阿羅斯等というヤマトから攻められ、伊都より後退した卑弥呼は八女へと逃げ落ち最後は日本書紀や風土記がいう田油津媛が神功皇后から殺された歴史真実を伝えているのではないかと。ここに言う説は本居宣長と日田の小迫辻原遺跡を推理した歴史作家の関裕二氏の仮説である。
英彦山と日田と田川に残る「鷹」伝承の謎
『豊後国志』に記述されている鷹伝説を紹介する。「遙か昔、山々に囲まれた日田盆地はとても大きな湖でした。そこへ東から大鷹が飛んで来て、湖の上を飛びまわり北に向かい去ると、突然と地震で鳴り動いて、昼間であるのに夜のように暗くなり、西の崖が崩れ裂け、水が抜けて涸渇すると、平野となって、3つの丘が向かい合うように立ち、水の痕はただ1帯の川として残りました」と日田の創世神話が残されている。
また同じ内容が豊西記にも記述されているが、豊後国志には、日田から鷹が飛び去った事が書かれている。その内容は「鷹が日田から鷹羽郡に飛び去って行った」という。その鷹羽郡は今の田川の事である。
古代日田は「日鷹」と呼ばれていて太陽信仰の神が日田に舞い降りた伝承を意味しているのである。また宇佐にも、八幡大神が鷹の姿で現れた伝承そして田川も古来は「鷹羽郡」と読まれていて、要するに「鷹」で豊の国はつながっている。
伊藤塾長は、朝鮮半島の渡来系は、先に山の高いところに拠点をつくり、そこから下流域にむけて動くという。そう考えると、英彦山を中心にした渡来系の意味が、筑豊であり日田であり宇佐であろう。その勢力が筑紫に睨みをきかせた勢力だったと理解できようではないか。
そして英彦山を創建したのが藤原恒雄(藤山恒雄)である。英彦山は、継体天皇25年(531年)、北魏の僧・善正(ぜんしょう)が英彦山山中で修行中に猟師・藤原恒雄(のちの忍辱〈にんにく〉)に会い、殺生の罪を説いた。しかしそれでも恒雄は猟を続け、1頭の白鹿を射た。その時、3羽の鷹が出現して白鹿に檜の葉に浸した水を与えると、白鹿は生き返った。それを見た恒雄は、この白鹿は神の化身なのだと悟り、善正の弟子となって当社を建立したという。
そして意外や意外。九州を統治していたのが磐井であり、継体天皇が物部麁鹿火を磐井を殺すために差し向けたのが磐井の乱527年だ。
そして磐井は豊の国の奥に逃げ込んだとされるが、磐井と藤原恒雄との関連は無関係なのであろうか?
恒雄とは檀君神話に登場するものか?。檀君(だんくん)とは、13世紀末に書かれた『三国遺事』に初めて登場する、伝説上の古朝鮮の王。『三国遺事』によると、天神桓因の子桓雄と熊との間に生まれたと伝えられる。『三国遺事』の原注によると、檀君とは「檀国の君主」の意味であって個人名ではなく、個人名は王倹という。
恒雄の名も朝鮮の檀君神話の桓雄に由来するのではないかという指摘もある。(中野幡能「英彦山と九州の修験道」や大和岩雄氏は「秦氏の研究」の中に(以下参照)
記紀神話では、天忍穂耳命でなく、その子のニニギが天降っているが、ニニギにするわけにいかないから、オシホミミにしたのである。桓雄は太白山に天降っているから、桓雄をオシホミミに変えたのであり、この伝承の根は、朝鮮の始祖降臨の檀君神話にある。朝鮮の始祖降臨神話の主人公が、彦山伝承では語られていたが (但し、「藤原恒雄」と日本人化してはいたが)、それが、記・紀神話の主人公に変えられて、天忍穂耳命となり、香春神社の祭神忍骨命となったのである。『彦山流記』 は、彦山に降臨した「王子晋」 の分身を「天童」というと書くように、王子晋も御子忍穂耳(忍骨)も、同じイメージである。彦山の「彦」は「日子」 で、日の御子の意である。対馬の天童伝説では、天童を日の御子とみている。
という想像を絶する仮説を言っている。英彦山(高住神社=鷹住神社)を創建した藤原恒雄の神が香春で奉られるという謎だらけの説。
要するに英彦山とは日子山であり、天皇家の皇子的要因を含め、鷹という伝承を後世に残そうとしたのではないかと思う。そして余談でしかないがどうして「藤原」なのか。藤原とは8世紀に蘇我氏を滅亡させていた、悪党藤原氏(蘇我氏を乗っ取る)ではないか。
そして、西から飛んできた鷹が日田を創世し、飛んで行った田川の神話の裏側にあるのが、宗像三神である。彦山縁起に、宗像三神は宇佐から英彦山行き、それから宗像へ舞い降りたという記述と折り重なるのである。そして女性を追って来たのも都怒我阿羅斯等と天の日矛なのである。その神が姫島などに祭神される「ひめごそ」という神。
そこには住吉という神功皇后がひかかってくる。特に北部九州には神功皇后伝承が多く存在し、『記紀』神話では、今の宇美町で応神天皇を産んだというのは有名である。余談になるが、住吉の伝承では、応神天皇の父親は「武内宿禰」という謎が残っている。
そして宗像神社には「宗像の子が住吉で、住吉の子が宇佐」であるという言い伝えが残り、宇佐の重要性を意味している。
住吉と言えば神功皇后であり宇佐は応神天皇だから宗像の神はどの神であるか難解な問題でもある。私が筑豊の神社をまわり、気づいたのが、饒速日命という神の存在と豊姫たる神の存在の多さだ。
宗像三神を祭神する神社には、木造の梁と梁に挟まれて身動きがとれない女神がいたり、本当は男神の神社に宗像三神が祭神されていたりして謎だらけとしか言いようがないのである。
宇佐と日田と田川と宗像という同じ神でつながっているのは間違えない真実だと思う。
本当の歴史
日田は卑弥呼の時代まで、筑後川流域や熊襲(熊本)その関係(甕棺)が強かった地域であったが、ヤマトが朝鮮半島の勢力と絡み、九州を征服しようと試み、最終的出城が日田だったのではないか。
豊臣も徳川も九州を統治する場所として日田に楔を打ち込んでいる事実は歴史を繰り返したのであって、古代でも同じ現象が起きていたのである。
本来日田は筑紫の圏内なのに何故か日田が豊の国に属するのかという謎も、日田が豊前と強い結びつきがあったわけで、そう理解できるのではいか。ヒメゴソ伝承を信用するなら、瀬戸内から来た勢力(ヤマト)は宇佐から上陸し、英彦山にいったん司令塔をつくり、日田と田川へと天孫降臨していったのではないか。
ここが問題なのだが、神武東征の意味するものである。次回そのつづきを。
田川に舞い降りた新羅の神
その田川に残る伝説が、都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)という伽耶の王子がこの田川に住み着いたと豊前風土記は語る。また香春にある現人神神社にも同じ伝承が残る。
『日本書紀』における、都怒我阿羅斯等は伽耶から船で穴門(山口県)に着き、そこから出雲そして笥飯浦(敦賀)に来着したという。その名残が今の気比(けひ)こと敦賀(つるが)である。
『日本書紀』には同じ様な人物がもう一人記述されている。その神が天の日矛(あめのひほこ)と言う新羅の王が今の兵庫県豊岡市にたどり着いたいう。その両者に共通するのが、姫を追って日本へやって来たという内容だ。
豊前風土記を信用するなら、穴門よりこの田川の方が先となる。田川には香春神社が存在しこの香春神社には、渡来系の雰囲気が漂っているのである。
豊前国風土記によれば「田河の郡、香春の郷 郡の北東のかたにあり。此の郷の中に河あり。年魚(あゆ)あり。 其の源は郡の東北の杉坂山より出でて、すぐにま西を指して流れ下りて、真漏河に湊い会えり。 此の河の瀬清浄し、因りて清河原の村と号けき。今、香春の郷と謂うは訛れるなり。
昔、新羅の国の神、自ら度り到来りて、此の河原に住みき、すなわち名づけて香春の神と曰う。又、郷の北に峰あり。 頂に沼あり、 闊さ三十歩あり 。黄楊[つげ]の樹生いたり。兼、竜の骨あり。第二の峰には銅と竜の骨とあり。第三の峰には竜の骨あり。」
という記述と現人神神社の記述と風土記の内容が一致することがわかる。
そして香春にある香春神社の秘められた姿がまた凄い。香春三山(香春神社)に正一位の神階が与えられたのは、承和10年(843年)のことだったが、これは奈良の大神神社(859年)、石上神宮(868年)、大和神社(897年)が正一位になった年よりも、はるかに早い。そして豊前の国の一の宮は宇佐でなくこの香春(『全国神社名鑑』全国神社名鑑刊行会)という記述も残されているのだから謎は深まるばかりである。
この香春神社(香春三山)には、銅が採れ、鉄と金も少しだが採れていたと香春町の学芸員は説明していた。補足だが、遠賀川の左岸と右岸では全然違う文化が存在していたのも事実であり、私見として左岸の邪馬台国に対して右岸の渡来系(ヤマトと連携した)の国が存在していたに違いないと私は考えている。
『邪馬台国は秦族に征服された』安藤輝国氏の著書があるのも都怒我阿羅斯等は秦氏という渡来系に意味するならそう理解もできよう。また大和岩雄氏は「秦氏の研究で」新羅の神=秦氏=鍛冶=鷹という説明をしている。そう考えると、初期邪馬台国は北部九州の何処かに存在し、その邪馬台国を潰したのは「都怒我阿羅斯等」か。
この状況を説明するには、卑弥呼の時代に衰退している地域がある。それが伊都や吉野ヶ里である。逆に勢いが増したのが日田の小迫辻原遺跡(おざこつじばる)で、今でも日本最古の豪族居館跡で、この遺跡の特徴は布留式土器が出土する。考古学的には、布留式土器とはヤマトの土器と言ったほうが早い。そして宇佐などには赤塚古墳という前方後円墳ができる。
邪馬台国九州説の方には、九州がヤマトに滅ぼされると言うと反感を買うが、そう考えた事で、神話や伝承や考古学的な意味がつながってくると私は思う。
私見でしかないが、この都怒我阿羅斯等(武内宿禰)の勢力は磐井の乱の530年頃まで持続していたと私は思う。その象徴が「鷹」としか思えない。
邪馬台国と本居宣長
魏志』倭人伝の邪馬台国を本居宣長は、九州の偽ヤマトを『魏志』は記述しているという。その仮説を説いたのが本居宣長である。
本居は厳密には「邪馬台国=大和朝廷」であり、「魏志倭人伝」の「邪馬台国」は「九州の豪族が勝手に名乗った偽者」だと仮説している。
卑弥呼の時代は鉄=権力であり、朝鮮半島でも同じ現象がある。台与の時代になると鉄がヤマトへと移動を始めている。卑弥呼の時代は九州の遺跡発掘からもわかるように、圧倒的に多い。卑弥呼の時代とその卑弥呼の宗女(血縁関係はわからない)の時代には劇的な社会変化があとしか思えない現象である。
本居宣長の説を延長したら、卑弥呼と台与の時代に九州とヤマトは内乱状態が(『魏志』には卑弥呼の前に倭国大乱の記述)つづき、九州の偽卑弥呼が魏に朝貢し私が倭国の王であると報告した。一般的に本居宣長が九州説といわれるのだが、本当は偽物卑弥呼なのであるが、『魏志』を読む限り卑弥呼は九州なのである。
ヤマトが神話では神功皇后や仲哀天皇や武内宿禰が九州へ動き、そしてその動きと符合してくるのが日田市の日本最古の豪族居館跡の「小迫辻原遺跡」である。この遺跡は考古学も注目し、ヤマトの出城であり、謎の4世紀を解く重要な遺跡と新聞で紹介されている。
意外と知られていないのが田油津媛の兄である、夏羽の存在なのである。夏羽は田油津媛(卑弥呼かも)に援軍として行くときに、死んだ事を知り、逃げ帰ったという。そして、この田川になんと夏羽が殺されたという伝承が残っている。現在は夏羽から夏吉に地名が変わっているのだが、夏羽(陰)のイメージからか地名も変化したのだろう。
仮に卑弥呼の時代の九州勢力図として、伊都を中心とした勢力が、この香春の銅の権力を保持し、鉄と銅をヤマトからの勢力に奪われないように対抗していたのではないか。
本居宣長の説の延長にはどうも、ヤマトと連合した都怒我阿羅斯等(天の日矛)が田川を攻め支配したという構図につながる。
そして九州邪馬台国は都怒我阿羅斯等というヤマトから攻められ、伊都より後退した卑弥呼は八女へと逃げ落ち最後は日本書紀や風土記がいう田油津媛が神功皇后から殺された歴史真実を伝えているのではないかと。ここに言う説は本居宣長と日田の小迫辻原遺跡を推理した歴史作家の関裕二氏の仮説である。
英彦山と日田と田川に残る「鷹」伝承の謎
『豊後国志』に記述されている鷹伝説を紹介する。「遙か昔、山々に囲まれた日田盆地はとても大きな湖でした。そこへ東から大鷹が飛んで来て、湖の上を飛びまわり北に向かい去ると、突然と地震で鳴り動いて、昼間であるのに夜のように暗くなり、西の崖が崩れ裂け、水が抜けて涸渇すると、平野となって、3つの丘が向かい合うように立ち、水の痕はただ1帯の川として残りました」と日田の創世神話が残されている。
また同じ内容が豊西記にも記述されているが、豊後国志には、日田から鷹が飛び去った事が書かれている。その内容は「鷹が日田から鷹羽郡に飛び去って行った」という。その鷹羽郡は今の田川の事である。
古代日田は「日鷹」と呼ばれていて太陽信仰の神が日田に舞い降りた伝承を意味しているのである。また宇佐にも、八幡大神が鷹の姿で現れた伝承そして田川も古来は「鷹羽郡」と読まれていて、要するに「鷹」で豊の国はつながっている。
伊藤塾長は、朝鮮半島の渡来系は、先に山の高いところに拠点をつくり、そこから下流域にむけて動くという。そう考えると、英彦山を中心にした渡来系の意味が、筑豊であり日田であり宇佐であろう。その勢力が筑紫に睨みをきかせた勢力だったと理解できようではないか。
そして英彦山を創建したのが藤原恒雄(藤山恒雄)である。英彦山は、継体天皇25年(531年)、北魏の僧・善正(ぜんしょう)が英彦山山中で修行中に猟師・藤原恒雄(のちの忍辱〈にんにく〉)に会い、殺生の罪を説いた。しかしそれでも恒雄は猟を続け、1頭の白鹿を射た。その時、3羽の鷹が出現して白鹿に檜の葉に浸した水を与えると、白鹿は生き返った。それを見た恒雄は、この白鹿は神の化身なのだと悟り、善正の弟子となって当社を建立したという。
そして意外や意外。九州を統治していたのが磐井であり、継体天皇が物部麁鹿火を磐井を殺すために差し向けたのが磐井の乱527年だ。
そして磐井は豊の国の奥に逃げ込んだとされるが、磐井と藤原恒雄との関連は無関係なのであろうか?
恒雄とは檀君神話に登場するものか?。檀君(だんくん)とは、13世紀末に書かれた『三国遺事』に初めて登場する、伝説上の古朝鮮の王。『三国遺事』によると、天神桓因の子桓雄と熊との間に生まれたと伝えられる。『三国遺事』の原注によると、檀君とは「檀国の君主」の意味であって個人名ではなく、個人名は王倹という。
恒雄の名も朝鮮の檀君神話の桓雄に由来するのではないかという指摘もある。(中野幡能「英彦山と九州の修験道」や大和岩雄氏は「秦氏の研究」の中に(以下参照)
記紀神話では、天忍穂耳命でなく、その子のニニギが天降っているが、ニニギにするわけにいかないから、オシホミミにしたのである。桓雄は太白山に天降っているから、桓雄をオシホミミに変えたのであり、この伝承の根は、朝鮮の始祖降臨の檀君神話にある。朝鮮の始祖降臨神話の主人公が、彦山伝承では語られていたが (但し、「藤原恒雄」と日本人化してはいたが)、それが、記・紀神話の主人公に変えられて、天忍穂耳命となり、香春神社の祭神忍骨命となったのである。『彦山流記』 は、彦山に降臨した「王子晋」 の分身を「天童」というと書くように、王子晋も御子忍穂耳(忍骨)も、同じイメージである。彦山の「彦」は「日子」 で、日の御子の意である。対馬の天童伝説では、天童を日の御子とみている。
という想像を絶する仮説を言っている。英彦山(高住神社=鷹住神社)を創建した藤原恒雄の神が香春で奉られるという謎だらけの説。
要するに英彦山とは日子山であり、天皇家の皇子的要因を含め、鷹という伝承を後世に残そうとしたのではないかと思う。そして余談でしかないがどうして「藤原」なのか。藤原とは8世紀に蘇我氏を滅亡させていた、悪党藤原氏(蘇我氏を乗っ取る)ではないか。
そして、西から飛んできた鷹が日田を創世し、飛んで行った田川の神話の裏側にあるのが、宗像三神である。彦山縁起に、宗像三神は宇佐から英彦山行き、それから宗像へ舞い降りたという記述と折り重なるのである。そして女性を追って来たのも都怒我阿羅斯等と天の日矛なのである。その神が姫島などに祭神される「ひめごそ」という神。
そこには住吉という神功皇后がひかかってくる。特に北部九州には神功皇后伝承が多く存在し、『記紀』神話では、今の宇美町で応神天皇を産んだというのは有名である。余談になるが、住吉の伝承では、応神天皇の父親は「武内宿禰」という謎が残っている。
そして宗像神社には「宗像の子が住吉で、住吉の子が宇佐」であるという言い伝えが残り、宇佐の重要性を意味している。
住吉と言えば神功皇后であり宇佐は応神天皇だから宗像の神はどの神であるか難解な問題でもある。私が筑豊の神社をまわり、気づいたのが、饒速日命という神の存在と豊姫たる神の存在の多さだ。
宗像三神を祭神する神社には、木造の梁と梁に挟まれて身動きがとれない女神がいたり、本当は男神の神社に宗像三神が祭神されていたりして謎だらけとしか言いようがないのである。
宇佐と日田と田川と宗像という同じ神でつながっているのは間違えない真実だと思う。
本当の歴史
日田は卑弥呼の時代まで、筑後川流域や熊襲(熊本)その関係(甕棺)が強かった地域であったが、ヤマトが朝鮮半島の勢力と絡み、九州を征服しようと試み、最終的出城が日田だったのではないか。
豊臣も徳川も九州を統治する場所として日田に楔を打ち込んでいる事実は歴史を繰り返したのであって、古代でも同じ現象が起きていたのである。
本来日田は筑紫の圏内なのに何故か日田が豊の国に属するのかという謎も、日田が豊前と強い結びつきがあったわけで、そう理解できるのではいか。ヒメゴソ伝承を信用するなら、瀬戸内から来た勢力(ヤマト)は宇佐から上陸し、英彦山にいったん司令塔をつくり、日田と田川へと天孫降臨していったのではないか。
ここが問題なのだが、神武東征の意味するものである。次回そのつづきを。
|
|
|
|
|
|
|
|
日田の歴史って面白くて凄い! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
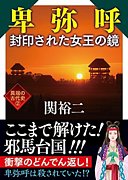





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)

















