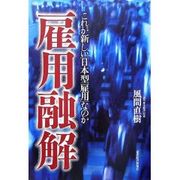NPO法人POSSEで政策提言を出しました。
↓
http://
主眼は「3年で辞めてもいい」というところにあります。
日本型雇用が破壊された今、どのような労働市場構築が望ましいのか提起しています。
ご批評よろしくお願いします。
↓
http://
主眼は「3年で辞めてもいい」というところにあります。
日本型雇用が破壊された今、どのような労働市場構築が望ましいのか提起しています。
ご批評よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(9)
読んでいい提言だと思いました。
しかし、気になる点があります。日本型雇用の良い点を無視しすぎている点です。欧米の企業は日本型雇用の特色がある企業こそ成長したといいます。例えばPG、GEなど。この提言は、安心して働ける環境をなくすということにつながるのですから、私はこの提言には反対です。
「会社の規模や、会社への忠誠心、そして正規・非正規によって人間の評価が決まる社会から、シゴトの内容を基本とした社会への転換を目指したものです。」
これ(能力主義に近い?)を実現するにはいくつかの大きな問題を超えなければならないでしょう。
たとえば、年上を敬う日本人が、年を理由に限界生産能力が落ちたからといって、「じゃあ少ない賃金でいいよね?」というのも問題かと思います。
この提言は賃金を即座に限界生産能力に一致させるという能力主義のことですか?
しかし、気になる点があります。日本型雇用の良い点を無視しすぎている点です。欧米の企業は日本型雇用の特色がある企業こそ成長したといいます。例えばPG、GEなど。この提言は、安心して働ける環境をなくすということにつながるのですから、私はこの提言には反対です。
「会社の規模や、会社への忠誠心、そして正規・非正規によって人間の評価が決まる社会から、シゴトの内容を基本とした社会への転換を目指したものです。」
これ(能力主義に近い?)を実現するにはいくつかの大きな問題を超えなければならないでしょう。
たとえば、年上を敬う日本人が、年を理由に限界生産能力が落ちたからといって、「じゃあ少ない賃金でいいよね?」というのも問題かと思います。
この提言は賃金を即座に限界生産能力に一致させるという能力主義のことですか?
さっくーさん
貴重なコメントありがとうございます。
>たとえば、年上を敬う日本人が、年を理由に限界生産能力が落ちたからといって、「じゃあ少ない賃金でいいよね?」というのも問題かと思います。
>この提言は賃金を即座に限界生産能力に一致させるという能力主義のことですか?
明日あたり、Q&Aをアップするので、ぜひそれをごらんになってください。
同一価値労働同一賃金は職種を基礎としつつ、そのプラスα部分を客観的に評価するシステムです。これを意識した政策提言です。日本型システムはこうした欧米型システムよりも圧倒的に能力主義的です。年功賃金はそこへの参入過程と、その後も「査定制度」によって極めて厳格な能力主義が貫徹された制度なのです。
しかも年功制システムでは、年齢や性別など属人的要素によって賃金表かがなされてきました。それがさまざまな弊害をうんでいるわけですね。
この点について、より公正なシステムに変えていこう、ということです。
別に安定を破壊せよといっているわけではありません。
その一部の人にとっての「安定」は、実は大きな不平等を前提になりたっていたということを指摘したいのです。
賃金が評価されるときに、何が基準になるべきでしょうか?
年齢でしょうか?
性別でしょうか?
国籍でしょうか?
私は仕事の内容だと思います。
さらに、高齢の方で仕事の能率が落ちたからと言って即座に賃金が減るわけではありません。
なぜなら、いわゆる成果主義とは違って、職務給はどのようなシゴトについているか、で基本的な給与が保証されるからです。
もちろん、その上乗せ部分にはシゴトの内容が関わってきますが。
日本型雇用のように、定年を迎えると再雇用で一気に低賃金になる。あるいは女性が「結婚退職」をさせられ、パートになったことを理由に低賃金になる。このようなシステムからの転換が必要だと考えています。
これからもいろいろご指摘おねがいします。
貴重なコメントありがとうございます。
>たとえば、年上を敬う日本人が、年を理由に限界生産能力が落ちたからといって、「じゃあ少ない賃金でいいよね?」というのも問題かと思います。
>この提言は賃金を即座に限界生産能力に一致させるという能力主義のことですか?
明日あたり、Q&Aをアップするので、ぜひそれをごらんになってください。
同一価値労働同一賃金は職種を基礎としつつ、そのプラスα部分を客観的に評価するシステムです。これを意識した政策提言です。日本型システムはこうした欧米型システムよりも圧倒的に能力主義的です。年功賃金はそこへの参入過程と、その後も「査定制度」によって極めて厳格な能力主義が貫徹された制度なのです。
しかも年功制システムでは、年齢や性別など属人的要素によって賃金表かがなされてきました。それがさまざまな弊害をうんでいるわけですね。
この点について、より公正なシステムに変えていこう、ということです。
別に安定を破壊せよといっているわけではありません。
その一部の人にとっての「安定」は、実は大きな不平等を前提になりたっていたということを指摘したいのです。
賃金が評価されるときに、何が基準になるべきでしょうか?
年齢でしょうか?
性別でしょうか?
国籍でしょうか?
私は仕事の内容だと思います。
さらに、高齢の方で仕事の能率が落ちたからと言って即座に賃金が減るわけではありません。
なぜなら、いわゆる成果主義とは違って、職務給はどのようなシゴトについているか、で基本的な給与が保証されるからです。
もちろん、その上乗せ部分にはシゴトの内容が関わってきますが。
日本型雇用のように、定年を迎えると再雇用で一気に低賃金になる。あるいは女性が「結婚退職」をさせられ、パートになったことを理由に低賃金になる。このようなシステムからの転換が必要だと考えています。
これからもいろいろご指摘おねがいします。
回答ありがとうございます。またたびたび質問しようと思います。(つまらない質問ですいません。。)
また疑問があります。仕事を基準に賃金を決定する場合、定型労働と創造的労働のパイは決まっているのですから、結局はいまの非正規雇用の人は今と同じくらい低賃金になるのではないでしょうか?
今非正規雇用の人に、レベルの高い仕事は、企業にとってはリスキーなのでやらせてくれないと思います。
今の非正規雇用者は、仕事で必要な集中力や先を読む力が備わっていない可能性が高いのが問題で、それらは短期的な職業訓練でも身に付かないとおもいます。
イメージ的には正規雇用者の賃金カーブをかなり緩やかにし、非正規雇用者の賃金カーヴをそれにちかずける、という提案だと思いますが、かえって生産能力(つまり職能)と乖離してしまう可能性はないのでしょうか。
また疑問があります。仕事を基準に賃金を決定する場合、定型労働と創造的労働のパイは決まっているのですから、結局はいまの非正規雇用の人は今と同じくらい低賃金になるのではないでしょうか?
今非正規雇用の人に、レベルの高い仕事は、企業にとってはリスキーなのでやらせてくれないと思います。
今の非正規雇用者は、仕事で必要な集中力や先を読む力が備わっていない可能性が高いのが問題で、それらは短期的な職業訓練でも身に付かないとおもいます。
イメージ的には正規雇用者の賃金カーブをかなり緩やかにし、非正規雇用者の賃金カーヴをそれにちかずける、という提案だと思いますが、かえって生産能力(つまり職能)と乖離してしまう可能性はないのでしょうか。
さっくーさん
相変わらず議論をふっていただいて、感謝の限りです。
>今非正規雇用の人に、レベルの高い仕事は、企業にとってはリスキーなのでやらせてくれないと思います。
→どうでしょうか。どの程度のことを議論されているのか教えて下さい。飲食店の店長クラスはすでに非正規雇用ですし、かなり高度なエンジニアも非正規雇用に切り替えられつつあります。
>今の非正規雇用者は、仕事で必要な集中力や先を読む力が備わっていない可能性が高いのが問題で、それらは短期的な職業訓練でも身に付かないとおもいます。
→そのようなことが問題になっている根拠を教えてください。私はそのような研究報告は知りません。研究データがあるのでしたら、知りたいところです。
>イメージ的には正規雇用者の賃金カーブをかなり緩やかにし、非正規雇用者の賃金カーヴをそれにちかずける、という提案だと思いますが、かえって生産能力(つまり職能)と乖離してしまう可能性はないのでしょうか。
→なぜ生産能力の低下がおこるのでしょうか。因果関係の根拠を示して頂けると嬉しく思います。比較の基準がはっきりすれば、それは賃金格差が生じる原因にはなるかもしれませんし、逆に格差は縮まるかもしれません。そうした細かいところは労使の力関係にかかっています。これが、労使関係論や労働市場論の原則的な理解の仕方です。
今、社会政策の次元で議論されている最先端の問題は、非正規雇用の基幹化が進む中で、やはり職員分離は存在している。では、それがどのような内容なのか、ということです。
つまり、総じて非正規が戦力化されていることはもはや疑いようがないのだが、やはり非正規であるために、中枢にはいたっていないので、その評価を厳密に行う必要があるということです。
同一価値労働同一賃金とは、正にシゴト内容の適切な評価が眼目にあります。そのためには職種やシゴト内容の厳正な比較が必要となるのです。
そのための基準は、残念ながら日本にはまだありません。
この内容を議論していくことが、ポスト日本型雇用の議論の中心的な課題になるのではないでしょうか。
相変わらず議論をふっていただいて、感謝の限りです。
>今非正規雇用の人に、レベルの高い仕事は、企業にとってはリスキーなのでやらせてくれないと思います。
→どうでしょうか。どの程度のことを議論されているのか教えて下さい。飲食店の店長クラスはすでに非正規雇用ですし、かなり高度なエンジニアも非正規雇用に切り替えられつつあります。
>今の非正規雇用者は、仕事で必要な集中力や先を読む力が備わっていない可能性が高いのが問題で、それらは短期的な職業訓練でも身に付かないとおもいます。
→そのようなことが問題になっている根拠を教えてください。私はそのような研究報告は知りません。研究データがあるのでしたら、知りたいところです。
>イメージ的には正規雇用者の賃金カーブをかなり緩やかにし、非正規雇用者の賃金カーヴをそれにちかずける、という提案だと思いますが、かえって生産能力(つまり職能)と乖離してしまう可能性はないのでしょうか。
→なぜ生産能力の低下がおこるのでしょうか。因果関係の根拠を示して頂けると嬉しく思います。比較の基準がはっきりすれば、それは賃金格差が生じる原因にはなるかもしれませんし、逆に格差は縮まるかもしれません。そうした細かいところは労使の力関係にかかっています。これが、労使関係論や労働市場論の原則的な理解の仕方です。
今、社会政策の次元で議論されている最先端の問題は、非正規雇用の基幹化が進む中で、やはり職員分離は存在している。では、それがどのような内容なのか、ということです。
つまり、総じて非正規が戦力化されていることはもはや疑いようがないのだが、やはり非正規であるために、中枢にはいたっていないので、その評価を厳密に行う必要があるということです。
同一価値労働同一賃金とは、正にシゴト内容の適切な評価が眼目にあります。そのためには職種やシゴト内容の厳正な比較が必要となるのです。
そのための基準は、残念ながら日本にはまだありません。
この内容を議論していくことが、ポスト日本型雇用の議論の中心的な課題になるのではないでしょうか。
「しかし、シゴトを基準に賃金を決めようにも、これまでの日本ではシゴトの訓練のほとんどが、個別企業ごとに行われる、いわゆる「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」でした。これは正社員のみを対象とするもので、非正社員は何年働き続けてもキャリアとして認められません。この制度を、正社員が会社を辞めても、あるいは非正社員でも企業の外で、シゴトのスキルを習得できるシステム=「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」に切り替えていくことが必要です。具体的には国や自治体による無料の職業訓練システムや、国家資格制度を整えていくことが考えられます。」
とありますが、これだと企業特殊的熟練の価格はゼロということになってしまいます。企業特殊的熟練を蓄積させない働き方が「成長促す働き方」だとはいえないのではないでしょうか?
長期育成で熟練を蓄積するという日本企業の競争力を支える人材戦略を放棄するということにつながります。(労務屋より)
□それと、シゴトを基準とすると、今のフリーターなどの待遇は上がるのでしょうか?
「技能を向上する機会がな」い仕事は昔からあったわけですが、現状では将来の産業・経済を担うべき若年の相当数がそうした仕事につき、「別の選択肢をほとんど持て」ずにいることはたしかに大問題です。それを「人材の浪費」と言っているのであれば、そのとおりかもしれません。とはいえ、職務別賃金にすればそれが解決されるかといえばそんなことはないわけで、「技能を向上する機会がな」いような低技能・低付加価値の職務にはそれに応じた低水準の賃金が市場原理で設定されるだけのことです。(労務屋より)
□あとシゴトを基準にというのはできるのでしょうか?
《繰り返し書いていますが、そもそも企業の人事管理において「均衡処遇」は非常に重要な課題なんですよ。「つりあいの取れる程度に是正」なんてお気楽に書いてくれていますが、どうすればその「つりあい」がうまくとれるのか、が人事労務管理の最大の難問のひとつなんです。およそ神ならぬ人間に「この人・仕事であれはこの賃金が正しい」なんてことがわかるわけも決められるわけもないわけで、そこは団体交渉とか労働市場の需給関係などで決めているわけです。で、その結果として、これが正しいかどうかわからないけれど、おそらくは細かくみればいろいろと矛盾や齟齬もあるだろうけれど、とにかく大方の人たちが不満を残しながらもそれなりに納得するように、バランスを取りながら決まっていくわけです。それが「均衡処遇」というものだと思います。たしかに格差はあるでしょう。大きくみえることもあるでしょう。しかしそれが「均衡」なのだと思います。
もちろん、非正社員の賃金が低いから政策的に上げたい、というのもひとつの意見としてありうるとは思います。しかし、それは「均衡処遇」を崩すという政策だということを理解して議論する必要があります。それでも非正社員の賃金を上げたいのなら、別途の理屈を考えていただく必要があります。》労務屋より抜粋
論題の資料としてもってきました。難しい問題ですね〜 すべて労務屋からです。
すべて労務屋からです。
とありますが、これだと企業特殊的熟練の価格はゼロということになってしまいます。企業特殊的熟練を蓄積させない働き方が「成長促す働き方」だとはいえないのではないでしょうか?
長期育成で熟練を蓄積するという日本企業の競争力を支える人材戦略を放棄するということにつながります。(労務屋より)
□それと、シゴトを基準とすると、今のフリーターなどの待遇は上がるのでしょうか?
「技能を向上する機会がな」い仕事は昔からあったわけですが、現状では将来の産業・経済を担うべき若年の相当数がそうした仕事につき、「別の選択肢をほとんど持て」ずにいることはたしかに大問題です。それを「人材の浪費」と言っているのであれば、そのとおりかもしれません。とはいえ、職務別賃金にすればそれが解決されるかといえばそんなことはないわけで、「技能を向上する機会がな」いような低技能・低付加価値の職務にはそれに応じた低水準の賃金が市場原理で設定されるだけのことです。(労務屋より)
□あとシゴトを基準にというのはできるのでしょうか?
《繰り返し書いていますが、そもそも企業の人事管理において「均衡処遇」は非常に重要な課題なんですよ。「つりあいの取れる程度に是正」なんてお気楽に書いてくれていますが、どうすればその「つりあい」がうまくとれるのか、が人事労務管理の最大の難問のひとつなんです。およそ神ならぬ人間に「この人・仕事であれはこの賃金が正しい」なんてことがわかるわけも決められるわけもないわけで、そこは団体交渉とか労働市場の需給関係などで決めているわけです。で、その結果として、これが正しいかどうかわからないけれど、おそらくは細かくみればいろいろと矛盾や齟齬もあるだろうけれど、とにかく大方の人たちが不満を残しながらもそれなりに納得するように、バランスを取りながら決まっていくわけです。それが「均衡処遇」というものだと思います。たしかに格差はあるでしょう。大きくみえることもあるでしょう。しかしそれが「均衡」なのだと思います。
もちろん、非正社員の賃金が低いから政策的に上げたい、というのもひとつの意見としてありうるとは思います。しかし、それは「均衡処遇」を崩すという政策だということを理解して議論する必要があります。それでも非正社員の賃金を上げたいのなら、別途の理屈を考えていただく必要があります。》労務屋より抜粋
論題の資料としてもってきました。難しい問題ですね〜
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
労働市場政策 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-