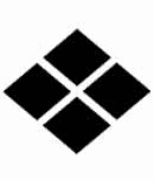武田勝頼が滅亡した織田信長の甲州征伐の直接のきっかけは、木曽義昌の離反だと言われています。勝頼は木曽氏討伐軍を派遣し鳥居峠の合戦となりました。但し、合戦の内容や回数、参加者、戦死者は諸説あって、一定していません。
一般的には、義昌離反を確信した勝頼は、天正10年1月28日、武田信豊を大手の大将として今福昌和、山県昌満ら三千騎、仁科盛信を搦め手の大将として二千騎を木曽に進撃させたと言われています。このとき、木曽義昌は必死の弁明に務めました。(『甲乱記』)
この後『甲乱記』は以下のよう趣旨で戦いの様子を記載しています。
2月2日の勝頼の出馬を受け、今福筑前守(昌和)を初めとした三千騎が、義昌の人数が少ないうちに、守りを固めていた鳥井峠へ向かった。ところが、山道に慣れた敵のため、数百名打たれ敗色が濃くなった。しかし、諏訪越中守(頼豊)、諏訪伊豆守(頼忠)、秋山紀伊守らが駆けつけ、敵を撃退した。そして奈良井、贄川に陣取った。
このようなところに木曽義昌は、全く逆意を含んでいないと弁明したが、認めてもらえず、勝頼が出陣したのを聞いたため、義昌は、信長へ助勢を求めた。これにより、信長の長男の城之介信忠を大将として、滝川一益、川尻秀隆、森長可ら三万騎が伊那口から、織田有楽、苗木久兵衛等3万が木曽口から進撃を開始した。
このため武田の諸将は動揺し、勝頼は諏訪に退いた。
『信長公記』によると、2月16日勝頼は、今福筑前を大将として木曽勢と戦いました。
戦いの概要は以下の通りです。
2月16日、敵勢の今福筑前守が武者大将となり、藪原から鳥居峠へ足軽を出してきた。これに対し織田方からは木曽勢に苗木久兵衛父子が加わり、奈良井坂より駈け上がって鳥居峠で敵勢に向かい、見事一戦を遂げた。この戦で織田勢が討ち取った首は跡部治部丞・有賀備後守・笠井某・笠原某ほか首数四十余にのぼり、敵勢は主立った侍を多く失った。
その後、この木曽口には織田勢から、織田長益・織田某・織田孫十郎・稲葉貞通・梶原平次郎・塚本小大膳・水野藤次郎・簗田彦四郎・丹羽勘介
以上の人数が加勢に加わり、木曽勢と一手となって鳥居峠を固めることとなった。これに対し敵勢からは馬場信春の子が深志城に籠り、鳥居峠と対陣した。
なお、『武田三代軍記』は武田信豊が「三千余人を以て、鳥井峠に於て木曾と合戦し、散々に戦負けて引退く」と記しています。
これらの記述から推測すると、天正10年における鳥居峠の戦いは2回あり、第一回目の戦いは2月上旬(2月2日より数日後)に行われ、武田方が辛勝し鳥居峠を確保しました。このときの、織田方の武将は、木曽勢のみであり、武田方の武将は今福昌和、山県昌満、諏訪頼豊らです。
しかし、2月16日再度、戦いとなり織田方の大勝利となり鳥居峠を奪還しました。織田方の武将は、木曽勢と苗木城主遠山久兵衛友忠であり、武田方の武将は、今福昌和、跡部治部丞・有賀備後守・笠井某・笠原某らです。この戦いにも山県昌満、諏訪頼豊が加わっていた可能性が高いと思われます。
武田信豊は、総大将として加わったものの、後方に陣取っていたのでしょうか?
この戦いの戦死者に今福昌和、山県昌満、諏訪頼豊があげられます。また一説には、戦いの後、諏訪頼豊は捕らえられて、織田軍によって処刑されたともいわれています。また、今福筑前は高遠城に撤退後戦死、山県昌満は武田滅亡の際、郡内で殺されたとの説もあります。
一般に天正10年の鳥居峠の戦いは、武田方の大敗といわれています。しかし、この解釈は、『甲乱記』の記載と合致していません。このため、鳥居峠の戦いは2度会ったと解釈したらいかがでしょうか? 皆さん、どう思われますか?
一般的には、義昌離反を確信した勝頼は、天正10年1月28日、武田信豊を大手の大将として今福昌和、山県昌満ら三千騎、仁科盛信を搦め手の大将として二千騎を木曽に進撃させたと言われています。このとき、木曽義昌は必死の弁明に務めました。(『甲乱記』)
この後『甲乱記』は以下のよう趣旨で戦いの様子を記載しています。
2月2日の勝頼の出馬を受け、今福筑前守(昌和)を初めとした三千騎が、義昌の人数が少ないうちに、守りを固めていた鳥井峠へ向かった。ところが、山道に慣れた敵のため、数百名打たれ敗色が濃くなった。しかし、諏訪越中守(頼豊)、諏訪伊豆守(頼忠)、秋山紀伊守らが駆けつけ、敵を撃退した。そして奈良井、贄川に陣取った。
このようなところに木曽義昌は、全く逆意を含んでいないと弁明したが、認めてもらえず、勝頼が出陣したのを聞いたため、義昌は、信長へ助勢を求めた。これにより、信長の長男の城之介信忠を大将として、滝川一益、川尻秀隆、森長可ら三万騎が伊那口から、織田有楽、苗木久兵衛等3万が木曽口から進撃を開始した。
このため武田の諸将は動揺し、勝頼は諏訪に退いた。
『信長公記』によると、2月16日勝頼は、今福筑前を大将として木曽勢と戦いました。
戦いの概要は以下の通りです。
2月16日、敵勢の今福筑前守が武者大将となり、藪原から鳥居峠へ足軽を出してきた。これに対し織田方からは木曽勢に苗木久兵衛父子が加わり、奈良井坂より駈け上がって鳥居峠で敵勢に向かい、見事一戦を遂げた。この戦で織田勢が討ち取った首は跡部治部丞・有賀備後守・笠井某・笠原某ほか首数四十余にのぼり、敵勢は主立った侍を多く失った。
その後、この木曽口には織田勢から、織田長益・織田某・織田孫十郎・稲葉貞通・梶原平次郎・塚本小大膳・水野藤次郎・簗田彦四郎・丹羽勘介
以上の人数が加勢に加わり、木曽勢と一手となって鳥居峠を固めることとなった。これに対し敵勢からは馬場信春の子が深志城に籠り、鳥居峠と対陣した。
なお、『武田三代軍記』は武田信豊が「三千余人を以て、鳥井峠に於て木曾と合戦し、散々に戦負けて引退く」と記しています。
これらの記述から推測すると、天正10年における鳥居峠の戦いは2回あり、第一回目の戦いは2月上旬(2月2日より数日後)に行われ、武田方が辛勝し鳥居峠を確保しました。このときの、織田方の武将は、木曽勢のみであり、武田方の武将は今福昌和、山県昌満、諏訪頼豊らです。
しかし、2月16日再度、戦いとなり織田方の大勝利となり鳥居峠を奪還しました。織田方の武将は、木曽勢と苗木城主遠山久兵衛友忠であり、武田方の武将は、今福昌和、跡部治部丞・有賀備後守・笠井某・笠原某らです。この戦いにも山県昌満、諏訪頼豊が加わっていた可能性が高いと思われます。
武田信豊は、総大将として加わったものの、後方に陣取っていたのでしょうか?
この戦いの戦死者に今福昌和、山県昌満、諏訪頼豊があげられます。また一説には、戦いの後、諏訪頼豊は捕らえられて、織田軍によって処刑されたともいわれています。また、今福筑前は高遠城に撤退後戦死、山県昌満は武田滅亡の際、郡内で殺されたとの説もあります。
一般に天正10年の鳥居峠の戦いは、武田方の大敗といわれています。しかし、この解釈は、『甲乱記』の記載と合致していません。このため、鳥居峠の戦いは2度会ったと解釈したらいかがでしょうか? 皆さん、どう思われますか?
|
|
|
|
|
|
|
|
武田勝頼 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
武田勝頼のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77430人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209454人
- 3位
- 空を見上げるのが好き
- 139113人