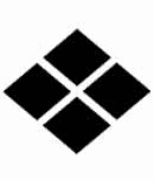はじめまして、コミュニティ初参加です。当然トピックも初めてです。
取りあえず、以下のタイトルで本日、自分ホームにアップした内容を掲載します。
======================−
武田勝頼が何故滅びたのか?それは、勝頼の内政・軍政・外交・家臣団構成など、さまざまな分野に原因がある。軍事力編成に関していえば、一般に、長篠・設楽原合戦に敗れたことによる兵力の著しい低下が挙げられる。それは、山県昌景、馬場信房、原昌胤、土屋昌次、甘利信康、内藤昌豊 をはじめとした信玄以来のそうそうたる重臣が戦死してしまったことによる。
これら長篠・設楽原合戦の戦死者は、武田家のために命を捧げた人々であり、真に忠義の者たちであった。
これに対し生き残った者の中には、穴山信君、武田信綱、武田信豊など早々に戦線離脱した人物が含まれている。
長篠・設楽原合戦によって、武田勝頼の家臣団構成は大きく変わった。
柴辻俊六・平山優編『武田勝頼のすべて』の中に「武田勝頼の駿河・遠江支配」という柴裕之氏の論考がある。それによると、(以下同書P149より引用)「敗戦後すぐに勝頼は駿河江尻城に従兄、御親類衆穴山信君を配置した。(関家文書ほか)江尻城は武田氏による駿河・遠江支配の拠点であり、これまで城代として御譜代家老衆山県昌景を据え、軍事力編成を行ってきた。山県戦死により、勝頼は信君を、江尻城代として中核に据え、そのもと支配と駿・遠先方衆への軍事統制を行うよう再編した。」
しかし、信君は長篠城で軍令違反をしたような人物である。案の定、天正十年、織田・徳川・北条勢の東西から挟撃されるや勝頼から離反した。武田信綱も同じ年、援軍として入った信州大島城を放棄し、甲斐に逃げ帰った後、誅殺される。
長篠・設楽原合戦による家臣団の変化は兵卒のレベルにまで及んだ。
前掲した『武田勝頼のすべて』「武田勝頼の軍事力編成」(平山優著)によると、(以下引用)勝頼は、天正五年閏七月五日に、三箇条に及ぶ最後の軍法を、寄親クラスの家臣たちに通達している。(略)勝頼は、当家興亡の危機を克服するため、領国各地より身分を問わず、十五歳以上六十歳以下の男子を、二十日間の期限つきで挑発し、出陣の際に帯同するよう命じたのである。武田氏の軍政において、年齢規定を設けて、領内の男子をことごとく動員する方針が明示されたのは、これが所見である。それまで武田氏は、永禄十二年十月令以来、領内の武勇人・有徳人を除く、百姓・町人・禰宜・幼弱の者を軍役衆として動員することは、謀反の原因となるとして、厳しくその帯同を家臣達に禁じてきた。それを勝頼は破棄し、二十日間の期限つきで戦場に参加させることを決断したのである。(略)勝頼がこのような、領民の大量動員に踏み切ったのは、武田氏がほんらい想定していた、兵卒となるべき有徳人、武勇人が、もはや払拭気味であったからである。こうした人々が数多く、常に村々や宿町にいたわけではない。それらの多くは、父信玄の晩年から長篠敗戦後までの間に、すでに動員しつ尽くされてしまっていた。つまり、軍団の高度な質の恒常的確保の実現という問題は、すでに信玄の晩年に始まっていたのであり、長篠敗戦がそれを一挙に顕在化させてしまったわけである。P103
この結果、武田氏の兵の質は著しく低下した。
武田信綱が大島城を放棄し、甲斐に逃げ帰ったのは、織田軍の侵攻を前にして城兵が逃亡したからだと言われている。穴山信君離反の報に接した後、勝頼の諏訪の陣からは部隊毎兵士が消滅し、その後も逃亡者が続出した。これほどまでに兵の質が低下したのは、指揮官の質の低下と共に、百姓・町人・禰宜・幼弱の者を軍役衆として強制的に動員した結果に外ならない。
取りあえず、以下のタイトルで本日、自分ホームにアップした内容を掲載します。
======================−
武田勝頼が何故滅びたのか?それは、勝頼の内政・軍政・外交・家臣団構成など、さまざまな分野に原因がある。軍事力編成に関していえば、一般に、長篠・設楽原合戦に敗れたことによる兵力の著しい低下が挙げられる。それは、山県昌景、馬場信房、原昌胤、土屋昌次、甘利信康、内藤昌豊 をはじめとした信玄以来のそうそうたる重臣が戦死してしまったことによる。
これら長篠・設楽原合戦の戦死者は、武田家のために命を捧げた人々であり、真に忠義の者たちであった。
これに対し生き残った者の中には、穴山信君、武田信綱、武田信豊など早々に戦線離脱した人物が含まれている。
長篠・設楽原合戦によって、武田勝頼の家臣団構成は大きく変わった。
柴辻俊六・平山優編『武田勝頼のすべて』の中に「武田勝頼の駿河・遠江支配」という柴裕之氏の論考がある。それによると、(以下同書P149より引用)「敗戦後すぐに勝頼は駿河江尻城に従兄、御親類衆穴山信君を配置した。(関家文書ほか)江尻城は武田氏による駿河・遠江支配の拠点であり、これまで城代として御譜代家老衆山県昌景を据え、軍事力編成を行ってきた。山県戦死により、勝頼は信君を、江尻城代として中核に据え、そのもと支配と駿・遠先方衆への軍事統制を行うよう再編した。」
しかし、信君は長篠城で軍令違反をしたような人物である。案の定、天正十年、織田・徳川・北条勢の東西から挟撃されるや勝頼から離反した。武田信綱も同じ年、援軍として入った信州大島城を放棄し、甲斐に逃げ帰った後、誅殺される。
長篠・設楽原合戦による家臣団の変化は兵卒のレベルにまで及んだ。
前掲した『武田勝頼のすべて』「武田勝頼の軍事力編成」(平山優著)によると、(以下引用)勝頼は、天正五年閏七月五日に、三箇条に及ぶ最後の軍法を、寄親クラスの家臣たちに通達している。(略)勝頼は、当家興亡の危機を克服するため、領国各地より身分を問わず、十五歳以上六十歳以下の男子を、二十日間の期限つきで挑発し、出陣の際に帯同するよう命じたのである。武田氏の軍政において、年齢規定を設けて、領内の男子をことごとく動員する方針が明示されたのは、これが所見である。それまで武田氏は、永禄十二年十月令以来、領内の武勇人・有徳人を除く、百姓・町人・禰宜・幼弱の者を軍役衆として動員することは、謀反の原因となるとして、厳しくその帯同を家臣達に禁じてきた。それを勝頼は破棄し、二十日間の期限つきで戦場に参加させることを決断したのである。(略)勝頼がこのような、領民の大量動員に踏み切ったのは、武田氏がほんらい想定していた、兵卒となるべき有徳人、武勇人が、もはや払拭気味であったからである。こうした人々が数多く、常に村々や宿町にいたわけではない。それらの多くは、父信玄の晩年から長篠敗戦後までの間に、すでに動員しつ尽くされてしまっていた。つまり、軍団の高度な質の恒常的確保の実現という問題は、すでに信玄の晩年に始まっていたのであり、長篠敗戦がそれを一挙に顕在化させてしまったわけである。P103
この結果、武田氏の兵の質は著しく低下した。
武田信綱が大島城を放棄し、甲斐に逃げ帰ったのは、織田軍の侵攻を前にして城兵が逃亡したからだと言われている。穴山信君離反の報に接した後、勝頼の諏訪の陣からは部隊毎兵士が消滅し、その後も逃亡者が続出した。これほどまでに兵の質が低下したのは、指揮官の質の低下と共に、百姓・町人・禰宜・幼弱の者を軍役衆として強制的に動員した結果に外ならない。
|
|
|
|
コメント(18)
書き込みありがとうございます。
武田家が滅んだ原因を信玄に求めることは可能です。
もしも信玄が、もっと長生きしていたら・・・、
もしも信玄が、織田信長との同盟関係を壊していなかったら・・・、
もしも信玄が、勝頼にきちんと家督相続をさせていたら・・・、
歴史は変わっていたかもしれません。
たしかに、勝頼は、負の遺産も含めて、武田家を引き継ぎました。しかし、それ以上に、120万石といわれる広大な領土と、きら星のごとき優秀な人材を引き継いだのも事実です。
勝頼も精一杯努力しました。しかし、結局は武田家を滅亡させてしまったのです。その原因はどこにあるのか、また、どうすれば武田家の滅亡を防ぐことができたのか、興味の尽きないところです。
武田家が滅んだ原因を信玄に求めることは可能です。
もしも信玄が、もっと長生きしていたら・・・、
もしも信玄が、織田信長との同盟関係を壊していなかったら・・・、
もしも信玄が、勝頼にきちんと家督相続をさせていたら・・・、
歴史は変わっていたかもしれません。
たしかに、勝頼は、負の遺産も含めて、武田家を引き継ぎました。しかし、それ以上に、120万石といわれる広大な領土と、きら星のごとき優秀な人材を引き継いだのも事実です。
勝頼も精一杯努力しました。しかし、結局は武田家を滅亡させてしまったのです。その原因はどこにあるのか、また、どうすれば武田家の滅亡を防ぐことができたのか、興味の尽きないところです。
むらちさん、
引用が多くて、自分でもわかりにくい説明なのに「おもしろい」なんて恐縮です。
むらちさんのおっしゃるように、「織田家は確か早い段階から、兵農分離して、常備軍を作っており、その局面局面で本拠地を移動することが可能」になったことが天下統一の原動力だと思います。
一方、武田家はそれが出来なかったのです。しかし、新府移転は、本拠地移転による兵農分離を目指したものという説もあるようです。
上杉家に限らず生産力の低い山国を根拠地としながら、長すぎる戦をしたことが、兵の弱体化に繋がっていったと思います。
結果として、勝頼が三河や美濃に出兵して城を落としたとしても、
戦費がかさみ、民心が離れていくことになっていくと思います。
御館の乱で上杉景勝から、黄金をもらって同盟することになったのも、財政難が一因だと思います。
勝頼は上杉から得た黄金で諏訪大社を再建し、新府城を造りました。
結果、 少なくとも諏訪の人心は掌握し、諏訪の武将は最期まで勝頼に従う人が多く出ています。
答えになっているようないないような・・・。 それでは
引用が多くて、自分でもわかりにくい説明なのに「おもしろい」なんて恐縮です。
むらちさんのおっしゃるように、「織田家は確か早い段階から、兵農分離して、常備軍を作っており、その局面局面で本拠地を移動することが可能」になったことが天下統一の原動力だと思います。
一方、武田家はそれが出来なかったのです。しかし、新府移転は、本拠地移転による兵農分離を目指したものという説もあるようです。
上杉家に限らず生産力の低い山国を根拠地としながら、長すぎる戦をしたことが、兵の弱体化に繋がっていったと思います。
結果として、勝頼が三河や美濃に出兵して城を落としたとしても、
戦費がかさみ、民心が離れていくことになっていくと思います。
御館の乱で上杉景勝から、黄金をもらって同盟することになったのも、財政難が一因だと思います。
勝頼は上杉から得た黄金で諏訪大社を再建し、新府城を造りました。
結果、 少なくとも諏訪の人心は掌握し、諏訪の武将は最期まで勝頼に従う人が多く出ています。
答えになっているようないないような・・・。 それでは
武田勝頼、最近かなり好きな武将です。研究をすればするほど彼が悪いとは思えません。
例えばまず武田信玄。この人はいま少し後継路線を確かめておくべきでしたね。
確かに勝頼に将軍の名の一文字と官位を拝領しようとしたら、信長様に邪魔されて失敗したとかあったでしょうが、
もう少し後継者に気を配っていれば、これほどの大惨敗にはならなかったはずです。親族が勝頼をこれほど軽んじることもなかったでしょう。
一方勝頼とは仲が悪かったといわれている重臣の人たちは皆長篠で死んでしまったわけで、この悪循環が勝頼を滅ぼしてしまいました。
あの時山県昌景や馬場信春が死なずに穴山梅雪が死んでいたら、勝頼はもっと長生きできていたでしょう。
政治改革、軍事改革にも意欲的だった勝頼。信長様をある意味において信玄以上に恐れさせただけの力はあっただけに惜しかったです。
例えばまず武田信玄。この人はいま少し後継路線を確かめておくべきでしたね。
確かに勝頼に将軍の名の一文字と官位を拝領しようとしたら、信長様に邪魔されて失敗したとかあったでしょうが、
もう少し後継者に気を配っていれば、これほどの大惨敗にはならなかったはずです。親族が勝頼をこれほど軽んじることもなかったでしょう。
一方勝頼とは仲が悪かったといわれている重臣の人たちは皆長篠で死んでしまったわけで、この悪循環が勝頼を滅ぼしてしまいました。
あの時山県昌景や馬場信春が死なずに穴山梅雪が死んでいたら、勝頼はもっと長生きできていたでしょう。
政治改革、軍事改革にも意欲的だった勝頼。信長様をある意味において信玄以上に恐れさせただけの力はあっただけに惜しかったです。
廃人課長show@Ganryuz様
コメントありがとうございます。基本的に廃人課長show@Ganryuzさんの意見に賛成です。
結果論ですが、私も武田信玄が、いま少し後継路線を確かめておくべきだったと思います。しかし、信玄もよもや 自分の寿命が三方原の戦いや野田城攻めの後尽きようなどとは思っても見なかったのではないかと思います。
確かに長篠で死んだ重臣の多くは、勝頼とは仲が悪かったと言われています。しかし、それでも彼らは武田家のために命を懸けていたわけで、あの時山県昌景や馬場信春が死なずに穴山梅雪が死んでいたら、おっしゃるように勝頼はもっと長生きできていたと思いますし、武田家も滅ばないで済んでいたかもしれません。
長篠で卑怯な振る舞いをした輩は、結局武田家滅亡時にも勝頼を裏切った訳で、高坂弾正が進言したように、勝頼も卑怯な輩には断固とした処置をすべきだったのかもしれません。
コメントありがとうございます。基本的に廃人課長show@Ganryuzさんの意見に賛成です。
結果論ですが、私も武田信玄が、いま少し後継路線を確かめておくべきだったと思います。しかし、信玄もよもや 自分の寿命が三方原の戦いや野田城攻めの後尽きようなどとは思っても見なかったのではないかと思います。
確かに長篠で死んだ重臣の多くは、勝頼とは仲が悪かったと言われています。しかし、それでも彼らは武田家のために命を懸けていたわけで、あの時山県昌景や馬場信春が死なずに穴山梅雪が死んでいたら、おっしゃるように勝頼はもっと長生きできていたと思いますし、武田家も滅ばないで済んでいたかもしれません。
長篠で卑怯な振る舞いをした輩は、結局武田家滅亡時にも勝頼を裏切った訳で、高坂弾正が進言したように、勝頼も卑怯な輩には断固とした処置をすべきだったのかもしれません。
>タケタケ様
結構過激な暴論を書きましたが、丁寧なご回答ありがとうございました。
信玄も信長様も毛利元就も豊臣秀吉も上杉謙信も世上英雄といわれた人物は自分がある日突然死ぬことを全く考えていません。
ある意味自信があったのかもしれませんが、この部分で彼らを反面教師にしたのは徳川家康だけでした。
後継者のことはきちんと考えておかないとお家の危機でした、特に家康以外の時代は皆戦国でしたし。
長篠で死んだ重臣は勝頼と折り合いが悪かったというのは江戸時代以降の根拠の薄い資料ばかりですし、
長篠の際の判断は軍勢を山すそに隠し、片っ端から物見を始末して言った織田信長の作戦がちという部分はありました。
実際あのときに戦うべきを選択したのは重臣そのものの判断で謀略に引っかかって負けたのだと私個人では感じています。
これだけ勝頼に忠義を尽くそうとしたならば、折り合いが悪かったというのもなかったのではないかと思います。
高坂弾正の建策も実は疑っています。これだけ重臣が死んだところで穴山梅雪や武田信豊を処刑していたら、武将クラスの城主がさらに人材枯渇しますので。
ただ、この連中が進撃を主張しながらも全く戦意がなく長篠では惨めに敗走し、土壇場で皆勝頼を裏切ったのは間違いありません。
しかし、穴山梅雪も木曽義昌も武田逍遙軒も主家を裏切ったり敗走しただけの親戚はろくな目にあっていません。
全くもってこれらの人々は許しがたい人々ですが、報いは受けています。因果応報です。
その意味では最後まで裏切らなかった真田昌幸は家は大名家になり、彼自身も本望の生き方を貫けました。
長篠までは史実どおりであったにせよ真田昌幸を馬場や山県のような重臣にすえ、穴山らを押さえ込めれば、いま少し武田家も長生きできたかもしれません。
結構過激な暴論を書きましたが、丁寧なご回答ありがとうございました。
信玄も信長様も毛利元就も豊臣秀吉も上杉謙信も世上英雄といわれた人物は自分がある日突然死ぬことを全く考えていません。
ある意味自信があったのかもしれませんが、この部分で彼らを反面教師にしたのは徳川家康だけでした。
後継者のことはきちんと考えておかないとお家の危機でした、特に家康以外の時代は皆戦国でしたし。
長篠で死んだ重臣は勝頼と折り合いが悪かったというのは江戸時代以降の根拠の薄い資料ばかりですし、
長篠の際の判断は軍勢を山すそに隠し、片っ端から物見を始末して言った織田信長の作戦がちという部分はありました。
実際あのときに戦うべきを選択したのは重臣そのものの判断で謀略に引っかかって負けたのだと私個人では感じています。
これだけ勝頼に忠義を尽くそうとしたならば、折り合いが悪かったというのもなかったのではないかと思います。
高坂弾正の建策も実は疑っています。これだけ重臣が死んだところで穴山梅雪や武田信豊を処刑していたら、武将クラスの城主がさらに人材枯渇しますので。
ただ、この連中が進撃を主張しながらも全く戦意がなく長篠では惨めに敗走し、土壇場で皆勝頼を裏切ったのは間違いありません。
しかし、穴山梅雪も木曽義昌も武田逍遙軒も主家を裏切ったり敗走しただけの親戚はろくな目にあっていません。
全くもってこれらの人々は許しがたい人々ですが、報いは受けています。因果応報です。
その意味では最後まで裏切らなかった真田昌幸は家は大名家になり、彼自身も本望の生き方を貫けました。
長篠までは史実どおりであったにせよ真田昌幸を馬場や山県のような重臣にすえ、穴山らを押さえ込めれば、いま少し武田家も長生きできたかもしれません。
長篠の戦いが、どのように行われたのか?これについては、別途明らかにしたいテーマに一つです。どのような戦いであったにせよ結果的に、織田信長の作戦勝ちであることは、否めません。
ご指摘のように、長篠後の人員配置の問題は、武田家の生き残りの明暗を分ける大問題だと思います。勝頼は、長篠後、武藤家を嗣がせた昌幸を真田家の当主に据え、少なくとも滅亡直前には勝頼の意思決定にかかわる重臣に据えていたのではないかと思いますが、それだけでは穴山信君らを押さえることができませんでした。また、長篠で戦死した馬場や山県や内藤の子息を重要なポジションにつけられなかった(或いは、つけなかった)ことが、勝頼にとってどう影響しているのか、考えてみたい課題の一つです。
山県や馬場の子孫は、甲州崩れの際に、それなりの働きをしたようなのですが、成果を出すことができませんでした。二人とも鳥居峠の戦いでは、勝頼の戦力となって働いたようです。(その後馬場の子孫は深志城を放棄したようですが・・)
天目山の戦いでの土屋惣蔵の活躍振りに象徴されるように、私は、長篠の忠臣の子孫や一族は、それなりに立派な活躍をしたのではないかと思うところもあるのですが、もう少し調べさせてください。
もしも、長篠で戦死した人の子孫が、武田家にとって有為な人材であったとしたならば、長篠後、その人達の処遇の問題が重要になってくるのではないかと考えています。そのことと、甲州崩れの問題がどうかかわってくるのか?まだまだ、考えなければならない問題です。
ご指摘のように、長篠後の人員配置の問題は、武田家の生き残りの明暗を分ける大問題だと思います。勝頼は、長篠後、武藤家を嗣がせた昌幸を真田家の当主に据え、少なくとも滅亡直前には勝頼の意思決定にかかわる重臣に据えていたのではないかと思いますが、それだけでは穴山信君らを押さえることができませんでした。また、長篠で戦死した馬場や山県や内藤の子息を重要なポジションにつけられなかった(或いは、つけなかった)ことが、勝頼にとってどう影響しているのか、考えてみたい課題の一つです。
山県や馬場の子孫は、甲州崩れの際に、それなりの働きをしたようなのですが、成果を出すことができませんでした。二人とも鳥居峠の戦いでは、勝頼の戦力となって働いたようです。(その後馬場の子孫は深志城を放棄したようですが・・)
天目山の戦いでの土屋惣蔵の活躍振りに象徴されるように、私は、長篠の忠臣の子孫や一族は、それなりに立派な活躍をしたのではないかと思うところもあるのですが、もう少し調べさせてください。
もしも、長篠で戦死した人の子孫が、武田家にとって有為な人材であったとしたならば、長篠後、その人達の処遇の問題が重要になってくるのではないかと考えています。そのことと、甲州崩れの問題がどうかかわってくるのか?まだまだ、考えなければならない問題です。
>タケタケさま
すばらしい。長篠の人員配置は良質の資料でも確認が出来ますので、間違いない事実でしょう。
長坂はこの合戦に参戦すらしていませんし、馬場、山県らの重臣の判断で戦ったのは間違いないと思います。
彼らは自分たちの判断ミスの責任を取って、勝頼への忠誠心に殉じたのでしょう。
この後が問題でおそらく種々の本でも言及されているところですが、もっとも勝頼が頼りにした側近は真田昌幸だったはずです。
しかし、昌幸は信濃衆で馬場や山県の末裔も立てなければならないうえに、親類衆はアレだけの失態を犯しながらも、
信玄時代以上に権限を欲しがり城に引きこもり、命令をあまり聞かなくなる。結局勝頼は長篠の後よい軍制改革までしながらも、
結局真田昌幸を信濃から動かせずに文弱?の跡部や長坂を重臣として動かさなくてはならない状態から依存できませんでした。
さすがに、忠誠は尽くしましたが、馬場も山県も高坂の末裔も上手な使いどころがなく猪突して死んでしまいます。
おそらくタケタケさんがもう少し調べさせてくださいとおっしゃっている部分は若返った重臣と真田昌幸で存分に戦おうとした
勝頼の行動に親族が圧力をかけたことによる軋轢で十分に動けなかったというのが真相でしょう。
すばらしい。長篠の人員配置は良質の資料でも確認が出来ますので、間違いない事実でしょう。
長坂はこの合戦に参戦すらしていませんし、馬場、山県らの重臣の判断で戦ったのは間違いないと思います。
彼らは自分たちの判断ミスの責任を取って、勝頼への忠誠心に殉じたのでしょう。
この後が問題でおそらく種々の本でも言及されているところですが、もっとも勝頼が頼りにした側近は真田昌幸だったはずです。
しかし、昌幸は信濃衆で馬場や山県の末裔も立てなければならないうえに、親類衆はアレだけの失態を犯しながらも、
信玄時代以上に権限を欲しがり城に引きこもり、命令をあまり聞かなくなる。結局勝頼は長篠の後よい軍制改革までしながらも、
結局真田昌幸を信濃から動かせずに文弱?の跡部や長坂を重臣として動かさなくてはならない状態から依存できませんでした。
さすがに、忠誠は尽くしましたが、馬場も山県も高坂の末裔も上手な使いどころがなく猪突して死んでしまいます。
おそらくタケタケさんがもう少し調べさせてくださいとおっしゃっている部分は若返った重臣と真田昌幸で存分に戦おうとした
勝頼の行動に親族が圧力をかけたことによる軋轢で十分に動けなかったというのが真相でしょう。
勝頼の発給文書は正式な当主としての形式に則っており、実際には勝頼は陣代などではない。
織田家は「兵農分離」などしていないので、条件は同じ。
金山の収益がどの程度あったのか?あったとしてどの程度が武田家に入ったのか?そもそも黒川金山の金堀衆が直接雇用でないあたり、経営の実態すら疑わしい。
長篠のような地形では、後詰の穴山が先に退かねば他は退けない。前線の将が討死するのは至極当然の結果でしかない。穴山逃亡説は後付けの濡れ衣であろう。
同じく『信長公記』では勝頼と共に田野で果てた跡部・長坂も、『甲陽軍鑑』では最後に逃亡した事にされている。ある種の意図を持って編集されたと見るべきだろう。
形勢不利となれば領地領民を守るために寝返るのは当然の行動で、穴山も小山田も責められる立場に無い。小山田は武田領国の東の端という地理的要因故に、最後の最後になっただけで、信長・信忠のその後の甲斐統治を見る限り、土壇場だからどうこうという問題では無い。
長篠があろうが無かろうが、武田家は既に織田徳川連合、上杉、北条と接しているのであって、容易に領国を広げられない。
信長は、西に相対的に小さい勢力がいくつもあり、どんどん勢力を広げる。
国力差は開く一方で、基本的に勝てるものではない。
信玄が死んだ時点で、先代は先代であると方針を翻したなら、生き残る事は出来たやもしれぬ。
が、そんな勝頼であったなら、ロマンを感じないのであって、好きになる事も無かったであろう。
織田家は「兵農分離」などしていないので、条件は同じ。
金山の収益がどの程度あったのか?あったとしてどの程度が武田家に入ったのか?そもそも黒川金山の金堀衆が直接雇用でないあたり、経営の実態すら疑わしい。
長篠のような地形では、後詰の穴山が先に退かねば他は退けない。前線の将が討死するのは至極当然の結果でしかない。穴山逃亡説は後付けの濡れ衣であろう。
同じく『信長公記』では勝頼と共に田野で果てた跡部・長坂も、『甲陽軍鑑』では最後に逃亡した事にされている。ある種の意図を持って編集されたと見るべきだろう。
形勢不利となれば領地領民を守るために寝返るのは当然の行動で、穴山も小山田も責められる立場に無い。小山田は武田領国の東の端という地理的要因故に、最後の最後になっただけで、信長・信忠のその後の甲斐統治を見る限り、土壇場だからどうこうという問題では無い。
長篠があろうが無かろうが、武田家は既に織田徳川連合、上杉、北条と接しているのであって、容易に領国を広げられない。
信長は、西に相対的に小さい勢力がいくつもあり、どんどん勢力を広げる。
国力差は開く一方で、基本的に勝てるものではない。
信玄が死んだ時点で、先代は先代であると方針を翻したなら、生き残る事は出来たやもしれぬ。
が、そんな勝頼であったなら、ロマンを感じないのであって、好きになる事も無かったであろう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
武田勝頼 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
武田勝頼のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77430人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209454人
- 3位
- 空を見上げるのが好き
- 139113人