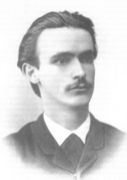32週
11/3〜11/9
私は力の充実を感じて
自分を世界のために
役立たせたいと願う。
自分の存在が力づけられて
この世の運命の中で
明晰な自己を保ちたいと感じる。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
……………………………
『治療教育講義』の先回の部分を読んでいたら
『シュタイナー自伝』を思い出した。
シュタイナーは10代の頃、
人間の思考能力の及ぶ範囲はどこまでか、
という問題を捉えていた。
思考を、世界内の諸物、
諸現象を己の中に包括する力へと
造り上げることが可能であるようにシュタイナーには思われたのだ。
「物質」は、思考作用の外部にとどまっていて
単に「考察される」だけだ、
という思想は彼には耐え難かった。
事物の中にあるものは、
人間の思考の中にも入り込んでくるはずだ、
と彼は考えていた。
15歳前後の頃、休暇中、
散歩にでる場合は時と場所を選ばず座り込み、
人間はいかにして単純で明晰な概念から
自然現象の具体的なイメージに到達し得るかという問題を、
繰り返し考えてみたようである。
当時のシュタイナーにとっては、
人間の思考中には生きた精神(霊)が活動しているということを、
どの程度まで証明できるかという問題が最大の課題であった。
そして、この「認識の問題」において彼の逢着した難問をきっかけとして、
彼の裡に一種の「認識論」が形成されはじめた。
思考活動とは、霊界における魂の経験が、
人間の肉体中に入射して反映したものである、
と彼は次第に考えるようになったのである。
さらに『シュタイナー自伝』(143p〜)によると
「美とは、感覚的形態をとった理念の現われではなく、
霊の形態をとった感覚的なものの表現である。
それゆえ、芸術とは、感覚的世界の中へ
霊界を移し入れることに他ならない。
真の芸術家は、程度の差こそあれ、
無意識のうちに霊的なものを承認している。
したがって、霊的世界の認識に到達するためには、
感覚的素材に取り組んでいる芸術家の裡に作用している魂の諸力を、
感覚に依存しない純粋に霊的な観照へと改変しさえすれば良い・・・
当時の私は常にこのように考えていた。
真の認識と芸術における霊的なものの顕現、
そして倫理的意志は、人間の裡で一つの全体へと統合されている、
と当時の私には思われた。
人間の人格にはある中心が存在し、
人格はこの中心において世界の
最も根源的な本性と直接に関係している。
この中心から意志が湧き起こる。
そして、この中心で霊の明るい光が作用するとき、
意志は自由になる。
その時人間は、世界の霊性と合致して行動するようになる。
世界の霊性は、何らかの必然性によって創造的になるのではなく
人間が自己の本性を実現する場合にのみ創造的になる。
人間の人格の中心部においては、
行為の目標は暗い衝動から生ずるのではなく、
どんな明晰な思想にも劣らぬ
それ自体明晰な直感である<倫理的直感>から生じる。
自由な意志を直感することによって、私は霊を見出そうとした。
人間は霊の力でこの世に個人として存在するのである。
真に美しいものを感受することによって、
私は霊を観照しようとした。
人間が感覚的なものに取り組み、
自己の本性を単に自由な行為として表すだけでなく、
自己の本性がその霊性を、
霊からなってはいるものの霊を直接に開示してはいない
世界に向かって流出させる時、
霊は人間を通して作用するのである。
真実を直感することによって、
私は霊の本性の現れを体験しようとした。
倫理的行為はこの霊の本性が反映したものであり、
芸術的創造は、感覚的形式を作り出すことによって
霊の本性に近づこうとするのである。
『自由の哲学』が、
霊を渇望し美を志向する感覚世界の人生観が、
溌剌たる真理の世界の霊的直感が
私の魂の中で形を取り始めていた。」(「シュタイナー自伝」より)
「物質」は、思考作用の外部にとどまっていて
単に「考察される」だけなのではない。
事物の中にあるものは、人間の思考の中にも入り込んでくる。
だから、人間の思考中には生きた精神(霊)が活動しているのである。
美しいものに数多く触れることの大切さがここでも良く理解できる。
さらに、先回考察したように
眼の中において、
自我組織とアストラル体とが物質的な諸事象の中にまで直接働きかけ、
そして物質的なものを認識する。
人がものを見るとき、
自我組織とアストラル体もその事象に入り
相互に影響を受け合っているのである。
ここで、一種の化学変化が生じて
魂に影響を及ぼすのである。
さて、先回のつづきで、
シュタイナーは「てんかん」について
以下のように語っている。
「てんかんは特に子どもの時期には、
いま述べたような在り方をしているのです。
てんかんの本来の問題はここにあるのです。
−てんかん症状の場合、
その自我組織とアストラル体が肉体とエーテル体の中に沈潜
することはできるのですが、
そこから物質界の中へは出ていけず、
内にしっかりと閉じ込められているのです。
そこで考えてみてください。
たとえば肺の中に入っていき、
そこでしっかり閉じ込められて、
ふたたび出ていけなくなったときのアストラル体は、
どういう状態になっているのでしょうか。
アストラル体は肺の表面の内側に押しつけられて、
せきとめられています。
自我組織もそこに閉じ込められ、
せきとめられています。
その状態は、外から見ると、
痙攣または発作という形をとって現われます。
痙攣が現われるたびに、
どこかの器官の内側で、
せきとめられた状態が起こっているのです。
このせきとめられた状態は特に脳の部分
に存在していますが、
すでに脳と他の諸器官との関係について述べたように、
脳のその状態は、
肝臓か肺の鬱積の単なる反映、
弱められた模像にすぎないのです。
痙攣があるときはかならず、
自我とアストラル体の鬱積がどこかの器官内部に認められます。
そしてそこにこそ、単なる外的な記述に終始してきた
てんかん性痙攣の真の原因があるのです。
肉体とエーテル体から自我とアストラル体にまで眼を移さないかぎり、
この状態を本当に知ることも、
痙攣の真の内容を語ることもできません。
そこでは器官の内側で、
アストラル体と自我組織が、
恐ろしいくらいに押し込められていて、
外に出られず、
外に向かって無理やりに押し合いへし合いしているのです。
以上に述べたことを理解すれば、
皆さんはさらに次のように問うでしょう。
『子どもの中にてんかんの徴候が現われたとき、
私は何をしたらよいのか』。
その徴候は痙攣を伴った意識の欠落や、
これから述べようとするその代償現象を伴っています。
そのような場合、
私たちは何をすることができるのでしょうか。
そのような場合、いわば本能的な仕方で、
まずその意識障害が、ある種のてんかん症状
によく起こるようなめまいの発作を伴って生じているかどうかを
確かめなければなりません。
子どもの場合、徴候は萌芽の状態で現われます。
意識の欠落がごく短い代わりに、
著しいめまいが現われる場合には、
自我組織とアストラル体が、
均衡カに直接関われないのです。
その子の自我組織とアストラル体が、
均衡を保つ力と直接関わることができない場合には、
体操かオイリュトミーをさせます。
つまり亜鈴(図例10)のような器具を与えて、
均衡感覚を養う練習をやらせるのです。
歯の生え変わりから、
思春期までの子どもにやらせるのがいいのです。
子どもには二つの同じ重さの亜鈴を与えます。
皆さんは薬剤師のように
正確にその重さが同じになるように計らなげればなりません。
そしてこれを使ってオイリュトミ−や体操を子どもにやらせますと、
重要な治療の一歩を始めたことになります。
次に左手に右手のものよりも軽い亜鈴を持たせて、
ふたたび運動させ、
次に右手に左手のものより軽い亜鈴を持たせて運動させ、
次に重いものを−特別重い必要はありません−
一方の足に結びつけて子どもを歩かせ、
足にひっぱる力を感じさせるのです。
普通、歩行しているときの子は、そのようなカを感じていません。
子どもの自我組織で、
そのカを感じ取るためには、
足に何かを結びつければいいのです。
それからもう一方の足にも同じことをして、
子どもがからだの動きに精神的に関わっていけるようにします。
また左の腕を伸ばしたり、右の腕を伸ばしたり、
両腕を同時に伸ばしたりさせます。
さらに片方の足を上げて、
もう一方の足だけで立たせることで、
重さを知覚させます。
要するに、めまいの発作が現われた子どもは
大地の力に正しく関わっていませんから、
均衡状態を維持することが学べるような運動をさせるのです。
てんかんやそれに類似した症状を示す子どもたちを扱うときには、
それ以外にもいろいろなカに子どもを
関わらせる処置が必要になります。
さてこれまでのところは、
そのようにしてやっていけます。
特に循環系に障害のあるてんかん疾患の場合、
それは良い結果をもたらすでしょう。
前述のような症状は本来、
体液循環の障害から起こってくるのです。
ですから痙攣やめまいを伴うてんかんの発作が、
特別の不快感と結びついているとき、
それは水(一般化した言い方です)の要素と正しい関係に
ないことを示しています。
そのような場合、体内に摂取する前に、
あらかじめ水の要素をできるだけ子どもに意識させ、
食べ物や飲み物をよく感じ取れるようにして
子どもに提供することが大きな助けになるでしょう。
水泳を学ばせることも良い結果を生みます。
水泳の練習はてんかん疾患にとっての、
非常に良い手段です。
ただ問題点を完全に洞察していなければなりません。
患者が特別の不快感を持たずに、
意識の昏迷を引き起こすときは、
注意深く呼吸を整える練習をさせて、
空気との結びつきを作ってあげるのも良いことです。
熱との正しい関係を持たせることも必要なので、
てんかん症の子どもには、
日頃から熱をよく感じ取れるようにしておきます。
言い換えますと、通常の子どもでさえも、
膝を剥き出しにして、
寒い中を半分裸で歩き廻るのは、非常に悪いことなのです。
それは盲腸を刺激して、
しばしば後年になって盲腸炎を引き起こす原因になります。
ですからそうすることは、
てんかん症の子に対しては、
まさに毒を与えるに等しい行為となるのです。
てんかん症の子には、常に汗をかくくらいに着物を着せて、
汗でいくぶん身体が湿った状態にあるくらいにしておきます。
これは治療の一部分なのです。
今日、鍛練の必要が説かれています。
子どもを鍛練して、
丈夫な子に育てようとするのですが、
その結果は後年陽の当たった広場を
膝をガクガクさせずには歩いて渡れないような人を作ってしまいます。
平気で陽の当たる広場を横ぎることができる人は、
鍛練をしないですんだ人なのです。
皆さんは立派な紳士が陽の当たる広場を膝をガクガクさせながら
渡っているのをご覧になる必要があります。
それは概して、鍛練でからだを硬くされた結果なのです。
これまで私たちが問題にしてきたのは、
子どもの時期に自我組織を身体の中に
正しく導き入れる教育上の作業だったのですが、
ここからは、教育に医者が直接
関わっていかなければならない分野が始まります。
なぜならてんかんの症状が見られるときには、
治療手段(薬剤)を用いて問題を解決する必要が生じるからです。
ですから薬を使って問題の解決を
図ることを恐れてはなりません。
子どもにてんかん症状が現われ、
アストラル体が問題になっているとき、
つまり上部のエーテル体が
アストラル体を外界に出ていけなくしているときには、
私たち自身が子どものエーテル体に働きかけなければなりません。
大切なのは、
私たちが正しい道を見出すことなのですが、
その前に大切なのは、
まずアストラル体が正しく働いているかどうか、
を認識することです。
それではいったい、
アストラル体が正しく働いているかどうかを、
どのようにして認識するのでしょうか。
多くのてんかん症、
あるいはてんかん質の子どもたちを観察してきた人は、
互いに非常に奥なる二つの症状を区別するでしょう。
一方の症状においては、
子どもが道徳的に何も問題を示していません。
その場合、子どもは容易に社会に適応することができます。
一方のてんかん症、あるいはてんかん質の子どもは、
容易に道徳秩序に従うことができるのです。
ところがもう一方で、
道徳習慣に従うことができずに、
たとえば発作に際して、
すぐに暴力行為に及ぶ子どもたちもいます。
実際てんかんの発作が暴力行為の
仮面をかぶって現われるとき、
子どもはしばしばそのことを何も覚えていません。
そのようなとき、
つまり社会道徳に欠陥が現われたとき、
実際に薬を使って、
その子のてんかんを克服しなければならなくなります。
一般に使用されている薬もありますし、
硫黄とかベラドンナのような、
私たちによって処方された薬もありますが、
それを正しく使用して治療するのです。
医学の問題は後で述べるつもりですが、
今日は教育的な処置から医学的な処置へ移行する必要
のある場合を、どうすれば外から知ることができるか、
という問題だけを取り上げたいの
です。
てんかんの子の場合、特に忘れてならないのは、
周囲の社会と良い関係が保たれて
いるときには、外的なトレーニングを避け、
特に内的治療法によって働きかけなければな
らないということです。」(p64〜p70)
つづく
11/3〜11/9
私は力の充実を感じて
自分を世界のために
役立たせたいと願う。
自分の存在が力づけられて
この世の運命の中で
明晰な自己を保ちたいと感じる。
(Rudolf Steiner 高橋 巌訳)
……………………………
『治療教育講義』の先回の部分を読んでいたら
『シュタイナー自伝』を思い出した。
シュタイナーは10代の頃、
人間の思考能力の及ぶ範囲はどこまでか、
という問題を捉えていた。
思考を、世界内の諸物、
諸現象を己の中に包括する力へと
造り上げることが可能であるようにシュタイナーには思われたのだ。
「物質」は、思考作用の外部にとどまっていて
単に「考察される」だけだ、
という思想は彼には耐え難かった。
事物の中にあるものは、
人間の思考の中にも入り込んでくるはずだ、
と彼は考えていた。
15歳前後の頃、休暇中、
散歩にでる場合は時と場所を選ばず座り込み、
人間はいかにして単純で明晰な概念から
自然現象の具体的なイメージに到達し得るかという問題を、
繰り返し考えてみたようである。
当時のシュタイナーにとっては、
人間の思考中には生きた精神(霊)が活動しているということを、
どの程度まで証明できるかという問題が最大の課題であった。
そして、この「認識の問題」において彼の逢着した難問をきっかけとして、
彼の裡に一種の「認識論」が形成されはじめた。
思考活動とは、霊界における魂の経験が、
人間の肉体中に入射して反映したものである、
と彼は次第に考えるようになったのである。
さらに『シュタイナー自伝』(143p〜)によると
「美とは、感覚的形態をとった理念の現われではなく、
霊の形態をとった感覚的なものの表現である。
それゆえ、芸術とは、感覚的世界の中へ
霊界を移し入れることに他ならない。
真の芸術家は、程度の差こそあれ、
無意識のうちに霊的なものを承認している。
したがって、霊的世界の認識に到達するためには、
感覚的素材に取り組んでいる芸術家の裡に作用している魂の諸力を、
感覚に依存しない純粋に霊的な観照へと改変しさえすれば良い・・・
当時の私は常にこのように考えていた。
真の認識と芸術における霊的なものの顕現、
そして倫理的意志は、人間の裡で一つの全体へと統合されている、
と当時の私には思われた。
人間の人格にはある中心が存在し、
人格はこの中心において世界の
最も根源的な本性と直接に関係している。
この中心から意志が湧き起こる。
そして、この中心で霊の明るい光が作用するとき、
意志は自由になる。
その時人間は、世界の霊性と合致して行動するようになる。
世界の霊性は、何らかの必然性によって創造的になるのではなく
人間が自己の本性を実現する場合にのみ創造的になる。
人間の人格の中心部においては、
行為の目標は暗い衝動から生ずるのではなく、
どんな明晰な思想にも劣らぬ
それ自体明晰な直感である<倫理的直感>から生じる。
自由な意志を直感することによって、私は霊を見出そうとした。
人間は霊の力でこの世に個人として存在するのである。
真に美しいものを感受することによって、
私は霊を観照しようとした。
人間が感覚的なものに取り組み、
自己の本性を単に自由な行為として表すだけでなく、
自己の本性がその霊性を、
霊からなってはいるものの霊を直接に開示してはいない
世界に向かって流出させる時、
霊は人間を通して作用するのである。
真実を直感することによって、
私は霊の本性の現れを体験しようとした。
倫理的行為はこの霊の本性が反映したものであり、
芸術的創造は、感覚的形式を作り出すことによって
霊の本性に近づこうとするのである。
『自由の哲学』が、
霊を渇望し美を志向する感覚世界の人生観が、
溌剌たる真理の世界の霊的直感が
私の魂の中で形を取り始めていた。」(「シュタイナー自伝」より)
「物質」は、思考作用の外部にとどまっていて
単に「考察される」だけなのではない。
事物の中にあるものは、人間の思考の中にも入り込んでくる。
だから、人間の思考中には生きた精神(霊)が活動しているのである。
美しいものに数多く触れることの大切さがここでも良く理解できる。
さらに、先回考察したように
眼の中において、
自我組織とアストラル体とが物質的な諸事象の中にまで直接働きかけ、
そして物質的なものを認識する。
人がものを見るとき、
自我組織とアストラル体もその事象に入り
相互に影響を受け合っているのである。
ここで、一種の化学変化が生じて
魂に影響を及ぼすのである。
さて、先回のつづきで、
シュタイナーは「てんかん」について
以下のように語っている。
「てんかんは特に子どもの時期には、
いま述べたような在り方をしているのです。
てんかんの本来の問題はここにあるのです。
−てんかん症状の場合、
その自我組織とアストラル体が肉体とエーテル体の中に沈潜
することはできるのですが、
そこから物質界の中へは出ていけず、
内にしっかりと閉じ込められているのです。
そこで考えてみてください。
たとえば肺の中に入っていき、
そこでしっかり閉じ込められて、
ふたたび出ていけなくなったときのアストラル体は、
どういう状態になっているのでしょうか。
アストラル体は肺の表面の内側に押しつけられて、
せきとめられています。
自我組織もそこに閉じ込められ、
せきとめられています。
その状態は、外から見ると、
痙攣または発作という形をとって現われます。
痙攣が現われるたびに、
どこかの器官の内側で、
せきとめられた状態が起こっているのです。
このせきとめられた状態は特に脳の部分
に存在していますが、
すでに脳と他の諸器官との関係について述べたように、
脳のその状態は、
肝臓か肺の鬱積の単なる反映、
弱められた模像にすぎないのです。
痙攣があるときはかならず、
自我とアストラル体の鬱積がどこかの器官内部に認められます。
そしてそこにこそ、単なる外的な記述に終始してきた
てんかん性痙攣の真の原因があるのです。
肉体とエーテル体から自我とアストラル体にまで眼を移さないかぎり、
この状態を本当に知ることも、
痙攣の真の内容を語ることもできません。
そこでは器官の内側で、
アストラル体と自我組織が、
恐ろしいくらいに押し込められていて、
外に出られず、
外に向かって無理やりに押し合いへし合いしているのです。
以上に述べたことを理解すれば、
皆さんはさらに次のように問うでしょう。
『子どもの中にてんかんの徴候が現われたとき、
私は何をしたらよいのか』。
その徴候は痙攣を伴った意識の欠落や、
これから述べようとするその代償現象を伴っています。
そのような場合、
私たちは何をすることができるのでしょうか。
そのような場合、いわば本能的な仕方で、
まずその意識障害が、ある種のてんかん症状
によく起こるようなめまいの発作を伴って生じているかどうかを
確かめなければなりません。
子どもの場合、徴候は萌芽の状態で現われます。
意識の欠落がごく短い代わりに、
著しいめまいが現われる場合には、
自我組織とアストラル体が、
均衡カに直接関われないのです。
その子の自我組織とアストラル体が、
均衡を保つ力と直接関わることができない場合には、
体操かオイリュトミーをさせます。
つまり亜鈴(図例10)のような器具を与えて、
均衡感覚を養う練習をやらせるのです。
歯の生え変わりから、
思春期までの子どもにやらせるのがいいのです。
子どもには二つの同じ重さの亜鈴を与えます。
皆さんは薬剤師のように
正確にその重さが同じになるように計らなげればなりません。
そしてこれを使ってオイリュトミ−や体操を子どもにやらせますと、
重要な治療の一歩を始めたことになります。
次に左手に右手のものよりも軽い亜鈴を持たせて、
ふたたび運動させ、
次に右手に左手のものより軽い亜鈴を持たせて運動させ、
次に重いものを−特別重い必要はありません−
一方の足に結びつけて子どもを歩かせ、
足にひっぱる力を感じさせるのです。
普通、歩行しているときの子は、そのようなカを感じていません。
子どもの自我組織で、
そのカを感じ取るためには、
足に何かを結びつければいいのです。
それからもう一方の足にも同じことをして、
子どもがからだの動きに精神的に関わっていけるようにします。
また左の腕を伸ばしたり、右の腕を伸ばしたり、
両腕を同時に伸ばしたりさせます。
さらに片方の足を上げて、
もう一方の足だけで立たせることで、
重さを知覚させます。
要するに、めまいの発作が現われた子どもは
大地の力に正しく関わっていませんから、
均衡状態を維持することが学べるような運動をさせるのです。
てんかんやそれに類似した症状を示す子どもたちを扱うときには、
それ以外にもいろいろなカに子どもを
関わらせる処置が必要になります。
さてこれまでのところは、
そのようにしてやっていけます。
特に循環系に障害のあるてんかん疾患の場合、
それは良い結果をもたらすでしょう。
前述のような症状は本来、
体液循環の障害から起こってくるのです。
ですから痙攣やめまいを伴うてんかんの発作が、
特別の不快感と結びついているとき、
それは水(一般化した言い方です)の要素と正しい関係に
ないことを示しています。
そのような場合、体内に摂取する前に、
あらかじめ水の要素をできるだけ子どもに意識させ、
食べ物や飲み物をよく感じ取れるようにして
子どもに提供することが大きな助けになるでしょう。
水泳を学ばせることも良い結果を生みます。
水泳の練習はてんかん疾患にとっての、
非常に良い手段です。
ただ問題点を完全に洞察していなければなりません。
患者が特別の不快感を持たずに、
意識の昏迷を引き起こすときは、
注意深く呼吸を整える練習をさせて、
空気との結びつきを作ってあげるのも良いことです。
熱との正しい関係を持たせることも必要なので、
てんかん症の子どもには、
日頃から熱をよく感じ取れるようにしておきます。
言い換えますと、通常の子どもでさえも、
膝を剥き出しにして、
寒い中を半分裸で歩き廻るのは、非常に悪いことなのです。
それは盲腸を刺激して、
しばしば後年になって盲腸炎を引き起こす原因になります。
ですからそうすることは、
てんかん症の子に対しては、
まさに毒を与えるに等しい行為となるのです。
てんかん症の子には、常に汗をかくくらいに着物を着せて、
汗でいくぶん身体が湿った状態にあるくらいにしておきます。
これは治療の一部分なのです。
今日、鍛練の必要が説かれています。
子どもを鍛練して、
丈夫な子に育てようとするのですが、
その結果は後年陽の当たった広場を
膝をガクガクさせずには歩いて渡れないような人を作ってしまいます。
平気で陽の当たる広場を横ぎることができる人は、
鍛練をしないですんだ人なのです。
皆さんは立派な紳士が陽の当たる広場を膝をガクガクさせながら
渡っているのをご覧になる必要があります。
それは概して、鍛練でからだを硬くされた結果なのです。
これまで私たちが問題にしてきたのは、
子どもの時期に自我組織を身体の中に
正しく導き入れる教育上の作業だったのですが、
ここからは、教育に医者が直接
関わっていかなければならない分野が始まります。
なぜならてんかんの症状が見られるときには、
治療手段(薬剤)を用いて問題を解決する必要が生じるからです。
ですから薬を使って問題の解決を
図ることを恐れてはなりません。
子どもにてんかん症状が現われ、
アストラル体が問題になっているとき、
つまり上部のエーテル体が
アストラル体を外界に出ていけなくしているときには、
私たち自身が子どものエーテル体に働きかけなければなりません。
大切なのは、
私たちが正しい道を見出すことなのですが、
その前に大切なのは、
まずアストラル体が正しく働いているかどうか、
を認識することです。
それではいったい、
アストラル体が正しく働いているかどうかを、
どのようにして認識するのでしょうか。
多くのてんかん症、
あるいはてんかん質の子どもたちを観察してきた人は、
互いに非常に奥なる二つの症状を区別するでしょう。
一方の症状においては、
子どもが道徳的に何も問題を示していません。
その場合、子どもは容易に社会に適応することができます。
一方のてんかん症、あるいはてんかん質の子どもは、
容易に道徳秩序に従うことができるのです。
ところがもう一方で、
道徳習慣に従うことができずに、
たとえば発作に際して、
すぐに暴力行為に及ぶ子どもたちもいます。
実際てんかんの発作が暴力行為の
仮面をかぶって現われるとき、
子どもはしばしばそのことを何も覚えていません。
そのようなとき、
つまり社会道徳に欠陥が現われたとき、
実際に薬を使って、
その子のてんかんを克服しなければならなくなります。
一般に使用されている薬もありますし、
硫黄とかベラドンナのような、
私たちによって処方された薬もありますが、
それを正しく使用して治療するのです。
医学の問題は後で述べるつもりですが、
今日は教育的な処置から医学的な処置へ移行する必要
のある場合を、どうすれば外から知ることができるか、
という問題だけを取り上げたいの
です。
てんかんの子の場合、特に忘れてならないのは、
周囲の社会と良い関係が保たれて
いるときには、外的なトレーニングを避け、
特に内的治療法によって働きかけなければな
らないということです。」(p64〜p70)
つづく
|
|
|
|
|
|
|
|
シュタイナー的生活を楽しむ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
シュタイナー的生活を楽しむのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6472人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19250人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人