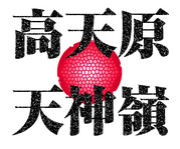.
サイドストーリーズ ■ 担当:たかひ狼 ■
『 無題 . 4 』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「…ニコ」
ふと、背中で大じいの声が聞こえた。
低いトーンのその声はかすかに重い、説教か何かを心の奥底に感じつつ、ニコは振り返った。
「今日はずいぶん早いな、何かあったのか?」
「うん、池袋行ったんだけどね、巡回してる警官に職質されそうになったから全部捨てて逃げた」
「…で、うまく逃げおおせたのか」
「ちょうど大通公園でさ、源さんがかくまってくれた、助かったよ」
「そうか…ならほとぼりが冷めた頃、なんか持って行ってやらにゃいかんぞ」
大じいが軽く鼻で笑う、機嫌は悪くなかったようだ。
「そうだね、焼酎でも買っていくよ今度」
ニコもそれにつられて、軽く微笑み返した。
「あ、いや…焼酎はダメだ」
「え?」
「あいつは酒乱の癖があるからな、確かてめぇ自身で断酒するとか抜かしてた…他のにしろ」
「あ、うん…分かった」
ニコは胸ポケットからさっきの手帳を取り出し、先ほど赤線を引いた池袋の欄に注釈を一個、書き入れた。
「池袋の源さんにお酒は厳禁…と」
「ムッ! ガァーッ!!!」
突然、沈黙を通していた伴じいがチェス盤をひっくり返し、大声で叫んだ。
「だめだだめだだめだ! ンなもん絶対に勝てるわけない! 畜生!!!」
あっけに取られるニコ。
しかし大じいはそのサプライズに驚くわけでもなく、サラリと返した。
「伴…確かにおめーは強ぇ、外へ出りゃ間違ぇ無く天下取れっぞ」
伴じいの身体は、ワナワナと怒りに小刻みに震えていた。
だがその怒りに臆することも無く、大じいは最後のとどめを刺した。
「ま、このワシに勝てれば、の話だけどな。ガハハハハ!」
高らかな笑い声がテント中に響き渡る。
「大じい…もうそのぐらいにしておこうよ」
「んにゃ、まだまだだ、このくらいの屈辱を与えん事には、本気の勝負は務まらん」
「ウガアアアアアッ! 覚えてろ! 今度はきっと! きっと!!!」
「おうよ、死なない程度に頑張れ!」
まるで尻尾を丸めた負け犬のように、伴じいはダッシュでテントから駆けて逃げていった。
「まだまだ若ぇんだ、あいつはな…」
大じいは鼻でせせら笑うと、今度はニコのほうへと向き直った。
「ニコよ…お前」
悪戯っぽい瞳で覗くかのように、今度は小声で話かける。
「な、なに、今度は?」
「聞いたぞお前、か・の・じょが出来たらしいじゃねぇか」
ニコの背中が一瞬にして冷たくなった。
「ち! ちがうちがう! 彼女じゃないってば! ただの仲間だよ!」
「そうか? この前猫っぽいねーちゃんと仲良く話してるの見・た・ぞ」
大じいのその顔は、もはやスケベな爺そのものと化していた。
、その攻撃に、ニコの顔はすっかり紅潮していた。
「いっぺんお前の部屋に誘ってみろ、大丈夫、手出しはしねぇさ」
「さ…誘って一体なにしろって言うんだよ!」
「こう…押し倒してだな、チューを…」
「しないしないしない! そんなこと絶対絶対絶対!!!」
「平気だ、ワシのテクニックを信じろニコ!」
「だからだから、彼女でもなんでもないんだから!」
「特別にお茶でも何でもサービスしてやるわな、家に入れちまえ、な?」
「だから、家に入れたくないってば!」
「なんだ、足が臭いこと気にしてるのか?」
「ちょ…それ、禁句…」
弱点を突かれ、ニコは頭を抱えた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 マスターより 】
文字規制uzeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
これから短めにポツポツと行くしかなさそうですね…
サイドストーリーズ ■ 担当:たかひ狼 ■
『 無題 . 4 』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「…ニコ」
ふと、背中で大じいの声が聞こえた。
低いトーンのその声はかすかに重い、説教か何かを心の奥底に感じつつ、ニコは振り返った。
「今日はずいぶん早いな、何かあったのか?」
「うん、池袋行ったんだけどね、巡回してる警官に職質されそうになったから全部捨てて逃げた」
「…で、うまく逃げおおせたのか」
「ちょうど大通公園でさ、源さんがかくまってくれた、助かったよ」
「そうか…ならほとぼりが冷めた頃、なんか持って行ってやらにゃいかんぞ」
大じいが軽く鼻で笑う、機嫌は悪くなかったようだ。
「そうだね、焼酎でも買っていくよ今度」
ニコもそれにつられて、軽く微笑み返した。
「あ、いや…焼酎はダメだ」
「え?」
「あいつは酒乱の癖があるからな、確かてめぇ自身で断酒するとか抜かしてた…他のにしろ」
「あ、うん…分かった」
ニコは胸ポケットからさっきの手帳を取り出し、先ほど赤線を引いた池袋の欄に注釈を一個、書き入れた。
「池袋の源さんにお酒は厳禁…と」
「ムッ! ガァーッ!!!」
突然、沈黙を通していた伴じいがチェス盤をひっくり返し、大声で叫んだ。
「だめだだめだだめだ! ンなもん絶対に勝てるわけない! 畜生!!!」
あっけに取られるニコ。
しかし大じいはそのサプライズに驚くわけでもなく、サラリと返した。
「伴…確かにおめーは強ぇ、外へ出りゃ間違ぇ無く天下取れっぞ」
伴じいの身体は、ワナワナと怒りに小刻みに震えていた。
だがその怒りに臆することも無く、大じいは最後のとどめを刺した。
「ま、このワシに勝てれば、の話だけどな。ガハハハハ!」
高らかな笑い声がテント中に響き渡る。
「大じい…もうそのぐらいにしておこうよ」
「んにゃ、まだまだだ、このくらいの屈辱を与えん事には、本気の勝負は務まらん」
「ウガアアアアアッ! 覚えてろ! 今度はきっと! きっと!!!」
「おうよ、死なない程度に頑張れ!」
まるで尻尾を丸めた負け犬のように、伴じいはダッシュでテントから駆けて逃げていった。
「まだまだ若ぇんだ、あいつはな…」
大じいは鼻でせせら笑うと、今度はニコのほうへと向き直った。
「ニコよ…お前」
悪戯っぽい瞳で覗くかのように、今度は小声で話かける。
「な、なに、今度は?」
「聞いたぞお前、か・の・じょが出来たらしいじゃねぇか」
ニコの背中が一瞬にして冷たくなった。
「ち! ちがうちがう! 彼女じゃないってば! ただの仲間だよ!」
「そうか? この前猫っぽいねーちゃんと仲良く話してるの見・た・ぞ」
大じいのその顔は、もはやスケベな爺そのものと化していた。
、その攻撃に、ニコの顔はすっかり紅潮していた。
「いっぺんお前の部屋に誘ってみろ、大丈夫、手出しはしねぇさ」
「さ…誘って一体なにしろって言うんだよ!」
「こう…押し倒してだな、チューを…」
「しないしないしない! そんなこと絶対絶対絶対!!!」
「平気だ、ワシのテクニックを信じろニコ!」
「だからだから、彼女でもなんでもないんだから!」
「特別にお茶でも何でもサービスしてやるわな、家に入れちまえ、な?」
「だから、家に入れたくないってば!」
「なんだ、足が臭いこと気にしてるのか?」
「ちょ…それ、禁句…」
弱点を突かれ、ニコは頭を抱えた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 マスターより 】
文字規制uzeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
これから短めにポツポツと行くしかなさそうですね…
|
|
|
|
コメント(6)
大じいの住むスペースのすぐ隣が、ニコの家である。
大きさはちょっとしたワンルーム程度だが、職人ホームレス仲間がニコのために快適な環境を、と真心こめて作っただけあって、そこいらのマンション部屋とそん色無い出来栄えである。
すきま風に悩まされないよう、目張りも完璧。型は古いが立派なエアコンだって入っている。
室内アンテナで写りは微妙だが、TVも置いてあるし、冷蔵庫も完備されている。
(電源はどこから引いているのか? と言うのは秘密で)
そしてなにより、パソコンも置いてある。
使用用途はもっぱら毎日のニュースと、ライジンの活動を調べるために使っている。
情報がかなり制限されているTVより、ネットで見たほうがずっと便利で早い。
…が、しかし。
「はぁ…やる事ないなぁ」
家に帰るなり、ニコは居間にゴロンと寝そべり、ずっと天井を見つめていた。
いつもならば仕事が終わるのは夕方近く、今日は警察のおかげで半分しか済んでいない。
夕食の手伝いをしようと思っても、ヌコロフはもうほとんど終えているだろうし。
ライジン退治はいつもチームワークでの仕事、今は成すべき時ではないし。
昼寝をしようにも、全然身体が疲れていない…困った。
何より、ニコは身体を動かしたかったのだ。
何かをしていたい、自分のためにでも、みんなのためにでも。
そうして身体の真までぐったり疲れ、床に着く。
これで1日が充実して、満足できるのだから。
「なんかする事無いか…な?」
寝そべっていたニコの頭の上で、冷たい何かがちょこんと触れた。
コロコロ…
それは、ニコが得物として使っている棒だった。
「あ、昨日ほっぽって寝ちゃったんだっけ…」
1,5mほどの手ごろな鉄パイプの中に硬い心材を詰め、滑り止めのバンデージを隙間無くきっちり巻きつける。
上背が低く、肉弾戦に不向きなニコがようやくめぐり会えた実戦格闘術、それが棒術だ。
「…そっか」
立ち上がったニコは爪先で棒を軽くちょんと蹴り上げ、捉えた両手でクルクルと形をとった。
「よぉし行くか! ムー先生のところへ」
水を得た魚のように、ニコの思いつきは即ダッシュへとつながって行った。
「どこへ行くんだニコ?」
「ムー先生のところ! 稽古つけてもらいに行ってくる」
大じいが問うのもつかの間、ニコは一陣のつむじ風の如く外へと姿を消して行った。
大きさはちょっとしたワンルーム程度だが、職人ホームレス仲間がニコのために快適な環境を、と真心こめて作っただけあって、そこいらのマンション部屋とそん色無い出来栄えである。
すきま風に悩まされないよう、目張りも完璧。型は古いが立派なエアコンだって入っている。
室内アンテナで写りは微妙だが、TVも置いてあるし、冷蔵庫も完備されている。
(電源はどこから引いているのか? と言うのは秘密で)
そしてなにより、パソコンも置いてある。
使用用途はもっぱら毎日のニュースと、ライジンの活動を調べるために使っている。
情報がかなり制限されているTVより、ネットで見たほうがずっと便利で早い。
…が、しかし。
「はぁ…やる事ないなぁ」
家に帰るなり、ニコは居間にゴロンと寝そべり、ずっと天井を見つめていた。
いつもならば仕事が終わるのは夕方近く、今日は警察のおかげで半分しか済んでいない。
夕食の手伝いをしようと思っても、ヌコロフはもうほとんど終えているだろうし。
ライジン退治はいつもチームワークでの仕事、今は成すべき時ではないし。
昼寝をしようにも、全然身体が疲れていない…困った。
何より、ニコは身体を動かしたかったのだ。
何かをしていたい、自分のためにでも、みんなのためにでも。
そうして身体の真までぐったり疲れ、床に着く。
これで1日が充実して、満足できるのだから。
「なんかする事無いか…な?」
寝そべっていたニコの頭の上で、冷たい何かがちょこんと触れた。
コロコロ…
それは、ニコが得物として使っている棒だった。
「あ、昨日ほっぽって寝ちゃったんだっけ…」
1,5mほどの手ごろな鉄パイプの中に硬い心材を詰め、滑り止めのバンデージを隙間無くきっちり巻きつける。
上背が低く、肉弾戦に不向きなニコがようやくめぐり会えた実戦格闘術、それが棒術だ。
「…そっか」
立ち上がったニコは爪先で棒を軽くちょんと蹴り上げ、捉えた両手でクルクルと形をとった。
「よぉし行くか! ムー先生のところへ」
水を得た魚のように、ニコの思いつきは即ダッシュへとつながって行った。
「どこへ行くんだニコ?」
「ムー先生のところ! 稽古つけてもらいに行ってくる」
大じいが問うのもつかの間、ニコは一陣のつむじ風の如く外へと姿を消して行った。
「…やっぱ若いのぉ、ニコは」
「ら? 今のニコですか?」
独り言をいう大じいの隣で、青年の声が聞こえた。
「おほ、すまんの気づかずに…でお前さん一体?」
大じいには初対面の、亀の姿をした青年ー匠ーが、小型ノートPCを抱えて側に立っていた。
「あ、ごめんなさいニコ君のおじいちゃん、匠って言います、ニコ君の友達です」
「おおぅ、ニコがよく言っていたタッ君か、亀とは聞いていたが…なるほどの!」
大じいは皺に埋もれた細い目で、匠を上から下までずいっと見回した。
長老を名乗るだけあって、彼の眼力は凄まじく良い。
目に見えないもの…人の良し悪しや敵意悪意、はたまた占い予知(?)さえも、なんでも見分ける事ができる。
そして匠も、その大じいの見えない眼力に見止められていた…ほんの2〜3秒の間だが。
「あ…と、その信じて…もらえますか?」
その眼力に気づいたのか、ちょっと匠も困っていた。
「分かるさ、お前さんもニコの匂いを持っているからな」
「え、匂い…ですか?」
「そう、鼻で感じるのではなく、目で見る匂いだがな、ガハハハハ!」
哲学的な答えを返し、大じいは大声で笑った。
「はぁ…信じてもらってありがとうございます…あれ?」
どう返事をしようか迷っていた匠の目に、チェスの用具一式が留まった。
「おじいさん、チェスやってるんですか?」
「おうこれか、いやはや将棋やら囲碁はワシの肌に合わなくての…あの獲ったコマをリサイクルできる概念がどうもな、好きになれんのじゃ」
「実は、僕もちょっとばかしチェスかじってるんですよ」
見えない険の抜けた大じいに安堵すると、匠は老人の座っている縁台に腰を下ろした。
そう、それは…
「ワシと一手やってみ「やりましょう!」」
匠のその微笑みは、まさに小悪魔的だった。
「ハンデは?」
「いえ、いりません」
大じいの口の端がにやりと上がる。
「ワシに挑んだ事、後悔するんじゃないぞ…」
「はは…お手柔らかに」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方ニコは、公園の反対側にある空き地に足を進めていた。
そこは大きな川が見渡せる、涼しい風が吹く場所。
ニコの棒術の師が住んでいる場所が、この一角であった。
少年は時間があるときにここで格闘術や棒術を学び、汗を流していたのだ。
「はっ! たっ!」
小気味いい棒の乱打の音と、なにやら聞いたことのある声がニコの耳に入った。
師匠の家の裏、芝生の生えていない土のフィールドが、ニコの修行場だ。
そのフィールドで、2人の男が棒を得物に戦っていた。
もちろんガチでの戦いではない事は、お互いの棒の交じあわせ方から察してはいた。
「あれ? キリンジのおっちゃん?」
師匠と模擬戦を繰り広げていたのは誰でもない、兄貴分であるキリンジだった。
「よう、ニコか」
「ら? 今のニコですか?」
独り言をいう大じいの隣で、青年の声が聞こえた。
「おほ、すまんの気づかずに…でお前さん一体?」
大じいには初対面の、亀の姿をした青年ー匠ーが、小型ノートPCを抱えて側に立っていた。
「あ、ごめんなさいニコ君のおじいちゃん、匠って言います、ニコ君の友達です」
「おおぅ、ニコがよく言っていたタッ君か、亀とは聞いていたが…なるほどの!」
大じいは皺に埋もれた細い目で、匠を上から下までずいっと見回した。
長老を名乗るだけあって、彼の眼力は凄まじく良い。
目に見えないもの…人の良し悪しや敵意悪意、はたまた占い予知(?)さえも、なんでも見分ける事ができる。
そして匠も、その大じいの見えない眼力に見止められていた…ほんの2〜3秒の間だが。
「あ…と、その信じて…もらえますか?」
その眼力に気づいたのか、ちょっと匠も困っていた。
「分かるさ、お前さんもニコの匂いを持っているからな」
「え、匂い…ですか?」
「そう、鼻で感じるのではなく、目で見る匂いだがな、ガハハハハ!」
哲学的な答えを返し、大じいは大声で笑った。
「はぁ…信じてもらってありがとうございます…あれ?」
どう返事をしようか迷っていた匠の目に、チェスの用具一式が留まった。
「おじいさん、チェスやってるんですか?」
「おうこれか、いやはや将棋やら囲碁はワシの肌に合わなくての…あの獲ったコマをリサイクルできる概念がどうもな、好きになれんのじゃ」
「実は、僕もちょっとばかしチェスかじってるんですよ」
見えない険の抜けた大じいに安堵すると、匠は老人の座っている縁台に腰を下ろした。
そう、それは…
「ワシと一手やってみ「やりましょう!」」
匠のその微笑みは、まさに小悪魔的だった。
「ハンデは?」
「いえ、いりません」
大じいの口の端がにやりと上がる。
「ワシに挑んだ事、後悔するんじゃないぞ…」
「はは…お手柔らかに」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方ニコは、公園の反対側にある空き地に足を進めていた。
そこは大きな川が見渡せる、涼しい風が吹く場所。
ニコの棒術の師が住んでいる場所が、この一角であった。
少年は時間があるときにここで格闘術や棒術を学び、汗を流していたのだ。
「はっ! たっ!」
小気味いい棒の乱打の音と、なにやら聞いたことのある声がニコの耳に入った。
師匠の家の裏、芝生の生えていない土のフィールドが、ニコの修行場だ。
そのフィールドで、2人の男が棒を得物に戦っていた。
もちろんガチでの戦いではない事は、お互いの棒の交じあわせ方から察してはいた。
「あれ? キリンジのおっちゃん?」
師匠と模擬戦を繰り広げていたのは誰でもない、兄貴分であるキリンジだった。
「よう、ニコか」
ちょうどその頃…
ギィン!
鈍くぶつかり合う鉄の音が、人気のない工事現場に響き渡っていた。
そこはニコの家から30分ほど離れた場所。
たくさんの土管と鋼材に囲まれたそれは、あたかも郊外にポツリと現れた格闘技のリングの様であった。
「だから…違うって言うてるじゃありませんか!」
この周辺ではあまり聞き慣れない言葉。
「黙れだヌ! こんな場所で刀持ってること自体凄く怪しいんだヌ!」
そして相対する方も、負けず劣らずの珍妙な言葉使いであった。
「これは…その、ライジン言う連中退治するための武器ですわ、信じ…てっ!」
刀を構えていた青年ー渚ーが懸命に答えようとするが、謎の人物は全く解さない様子であった。
それどころか…
「な゛ーっ!!」
謎の人物の黒い身体が大きく舞い上がり、そして渚に襲いかかった。
ズン!
大きな地響き、もうもうと霧の様に舞い立つ砂煙たち。
間一髪、渚はその必殺パンチをかわしていた。
「あっぶな…っ」
地面に突き刺さった己の右拳をゆっくりと引き抜く、その黒い巨体。
不釣り合いに大きな両腕。
そしてその先から伸びる、鋭いカギ爪。
しかしそれ以上に奇妙なのが、その顔つきであった。
長い。
口に相当する部分が見当たらず、鼻面ともいうべきその口吻からは、青く細い舌がちろちろとせわしなく出入りしていた。
そう、それはまさに…
「あ…アリクイ!?」
「悪いかだヌ!」
そして、第二戦が幕を開けた。
ギィン!
鈍くぶつかり合う鉄の音が、人気のない工事現場に響き渡っていた。
そこはニコの家から30分ほど離れた場所。
たくさんの土管と鋼材に囲まれたそれは、あたかも郊外にポツリと現れた格闘技のリングの様であった。
「だから…違うって言うてるじゃありませんか!」
この周辺ではあまり聞き慣れない言葉。
「黙れだヌ! こんな場所で刀持ってること自体凄く怪しいんだヌ!」
そして相対する方も、負けず劣らずの珍妙な言葉使いであった。
「これは…その、ライジン言う連中退治するための武器ですわ、信じ…てっ!」
刀を構えていた青年ー渚ーが懸命に答えようとするが、謎の人物は全く解さない様子であった。
それどころか…
「な゛ーっ!!」
謎の人物の黒い身体が大きく舞い上がり、そして渚に襲いかかった。
ズン!
大きな地響き、もうもうと霧の様に舞い立つ砂煙たち。
間一髪、渚はその必殺パンチをかわしていた。
「あっぶな…っ」
地面に突き刺さった己の右拳をゆっくりと引き抜く、その黒い巨体。
不釣り合いに大きな両腕。
そしてその先から伸びる、鋭いカギ爪。
しかしそれ以上に奇妙なのが、その顔つきであった。
長い。
口に相当する部分が見当たらず、鼻面ともいうべきその口吻からは、青く細い舌がちろちろとせわしなく出入りしていた。
そう、それはまさに…
「あ…アリクイ!?」
「悪いかだヌ!」
そして、第二戦が幕を開けた。
謎のアリクイは執拗に、渚を建造途中のビルの奥へ奥へと追い込んで行った。
オーバーなモーションで繰り出すそのカギヅメ攻撃。
「な゛ーっ!! な゛ーっ!!」
凄まじい掛け声とともに炸裂するその攻撃は、渚の背後にあるコンクリート製の土管ですらも一撃で真っ二つにしてしまうほどであった。
「くっ…なんつー馬鹿パワーや!」
「どうしたんだヌ! その刀を抜いてこないのはどうしてだヌ!」
後方を確認しながら逃げる一方の渚。
その腰に下げた刀を構えることなく、ひたすら軽妙なバックステップで下がり続けるばかりであった。
さながら掘削機のように、アリクイの左右にある土管や鉄骨たちが砕け散り、ひしゃげて行く。
しかしその背後の道すら、鉄骨の山によって絶たれようとしていた。
渚の背後を、ひんやりとした感覚が襲う。
「行き止まり…か」
「さぁ! もうお前には後がないんだヌ!」
掘削機は両腕を大きく上に上げ、小動物を襲う羆のごときポーズを取り始めた。
「ライジンだかなんだか知らないけど、この行き止まりでお前はゲームセットだヌ!」
「いやその…まだ僕は倒れるワケには行かないんですわ」
精一杯の笑みで取り繕いながら、渚は眼前にそびえ立つアリクイをなだめようとした。
「お前はここで死ぬんだヌ! 死んでそのブザマな死体を荒野にさらすんだヌ!」
「言ってもダメ…か」
渚の左手が、愛用の刀にそっと置かれた。
その時。
トッ!
アリクイの背後、崩れ落ちたガレキたちを足場に、軽快に飛び跳ねる何かの姿が。
それは右、左、そして上へと、さながらリズミカルに。
「静ちゃん!」
「なんだヌ!?」
その気配と声にアリクイが振り向いた直後だった。
「めーーーん!」
ゴムッ!
アリクイの細い頭頂部に、静の木刀がめり込む。
「ヌ…ぁ!」
「っしゃ!」
そのわずかな隙を狙い、渚の左手の刀から放たれた「一閃」が、アリクイのみぞおちに炸裂した。
そう、斬ったのではない。
柄に触れることなく、鞘を握った渚の強烈な「柄」の一撃。
「ガ…っ!」
静の気配に気づくまでのわずか数秒。
彼女の存在を認めるまでも無く、そのアリクイの巨躯は、2手で幕を閉じていった。
オーバーなモーションで繰り出すそのカギヅメ攻撃。
「な゛ーっ!! な゛ーっ!!」
凄まじい掛け声とともに炸裂するその攻撃は、渚の背後にあるコンクリート製の土管ですらも一撃で真っ二つにしてしまうほどであった。
「くっ…なんつー馬鹿パワーや!」
「どうしたんだヌ! その刀を抜いてこないのはどうしてだヌ!」
後方を確認しながら逃げる一方の渚。
その腰に下げた刀を構えることなく、ひたすら軽妙なバックステップで下がり続けるばかりであった。
さながら掘削機のように、アリクイの左右にある土管や鉄骨たちが砕け散り、ひしゃげて行く。
しかしその背後の道すら、鉄骨の山によって絶たれようとしていた。
渚の背後を、ひんやりとした感覚が襲う。
「行き止まり…か」
「さぁ! もうお前には後がないんだヌ!」
掘削機は両腕を大きく上に上げ、小動物を襲う羆のごときポーズを取り始めた。
「ライジンだかなんだか知らないけど、この行き止まりでお前はゲームセットだヌ!」
「いやその…まだ僕は倒れるワケには行かないんですわ」
精一杯の笑みで取り繕いながら、渚は眼前にそびえ立つアリクイをなだめようとした。
「お前はここで死ぬんだヌ! 死んでそのブザマな死体を荒野にさらすんだヌ!」
「言ってもダメ…か」
渚の左手が、愛用の刀にそっと置かれた。
その時。
トッ!
アリクイの背後、崩れ落ちたガレキたちを足場に、軽快に飛び跳ねる何かの姿が。
それは右、左、そして上へと、さながらリズミカルに。
「静ちゃん!」
「なんだヌ!?」
その気配と声にアリクイが振り向いた直後だった。
「めーーーん!」
ゴムッ!
アリクイの細い頭頂部に、静の木刀がめり込む。
「ヌ…ぁ!」
「っしゃ!」
そのわずかな隙を狙い、渚の左手の刀から放たれた「一閃」が、アリクイのみぞおちに炸裂した。
そう、斬ったのではない。
柄に触れることなく、鞘を握った渚の強烈な「柄」の一撃。
「ガ…っ!」
静の気配に気づくまでのわずか数秒。
彼女の存在を認めるまでも無く、そのアリクイの巨躯は、2手で幕を閉じていった。
ー一方、ニコはと言うと。
「キリンジのおっちゃんも、ムー先生に稽古を?」
キリンジの槍術は我流で通しているとずっと思っていただけに、ニコが驚くのも無理はなかった。
「ニコ…ムーじゃないとあれほど言ってただろうが」
半ばあきれた声で、老いた白山羊の様な風貌の男が、キリンジの隣から顔を出した。
「え、だってみんなムー先生って呼んでるじゃん」
「私の名前はウーミンだ、アイウのウ! だからウーで良いんだと言っておろうが!」
その男の名は「無名」と書いて「ウーミン」と呼ぶ。
もっとも、過去も名前も全てを捨てて生きている人だらけのこの界隈、ウーミンとは呼んでも「むめい」と言うその言葉の真意を知る人は誰もいなかった。
その名のとおり、彼は中国出身。それだけは明らかだった。
そして中国の武術に長けており、この地に来て間もない頃のニコに、身を守る術を教えたのが彼であった。
「で、ウー先生、キリンジさんにも教えてたの? 武術」
「いんや違う、キリンジ君の力を確かめてみたくてな、ちょっと手合わせしていたところだ」
「あぁ、ムーミン先生も俺と同じで中国でスタントとかいろいろやっていたって聞いたから、話聞こうと思ってたら…こんな感じにな」
「…ウーミンだ」
無名が横目でキリンジをじろりと睨み付ける。
「へぇ、で、キリンジさん強かった?」
「あぁ…キリンジ君はとても強い、私の指導なんてもっての他だ」
「いやでも、ムー先生に学ぶことだって結構ある、俺なんてまだヒヨっ子だ」
「…だから、ウーだっての」
無名が持っていた棒で、キリンジの頭をこつんと叩いた。
「それにしても、ニコ今日は早いな、何かあったのか?」
こいつは学校へ行かずに、毎日仕事や雑用で汗を流していることぐらい知っている。
毎日風来坊のように生きているキリンジには、その忙しい毎日が少しだけうらやましかった。
「…警察に見つかった、へへ」
舌をぺろんと出して、キリンジに弁解するニコ。
それははた目から見て、兄弟のような…もしくは年の近い親子に似た、そんな感じだった。
「で、ここに来たってワケか…稽古付けに」
「うん、ウーさんは僕の師匠だもん」
「うむ、ニコは上背が無いからな、若干でもリーチ稼げる棒術が一番最適だと思っとるんだ」
長く伸びた白いヒゲを整えながら、無名はキリンジに説明した。
「しかしのぉ…私の教えたいことはほぼ教えてしまったから、正直今来られても…お?」
ふと、無名の言葉が止まった。
「どしたの、先生?」
ニコが怪訝そうな顔をして、師匠を下からのぞき込む。
「ちょうどいいわ、キリンジ君、ニコと手合わせしてくれんか?」
「「ええええ!?」」
「キリンジのおっちゃんも、ムー先生に稽古を?」
キリンジの槍術は我流で通しているとずっと思っていただけに、ニコが驚くのも無理はなかった。
「ニコ…ムーじゃないとあれほど言ってただろうが」
半ばあきれた声で、老いた白山羊の様な風貌の男が、キリンジの隣から顔を出した。
「え、だってみんなムー先生って呼んでるじゃん」
「私の名前はウーミンだ、アイウのウ! だからウーで良いんだと言っておろうが!」
その男の名は「無名」と書いて「ウーミン」と呼ぶ。
もっとも、過去も名前も全てを捨てて生きている人だらけのこの界隈、ウーミンとは呼んでも「むめい」と言うその言葉の真意を知る人は誰もいなかった。
その名のとおり、彼は中国出身。それだけは明らかだった。
そして中国の武術に長けており、この地に来て間もない頃のニコに、身を守る術を教えたのが彼であった。
「で、ウー先生、キリンジさんにも教えてたの? 武術」
「いんや違う、キリンジ君の力を確かめてみたくてな、ちょっと手合わせしていたところだ」
「あぁ、ムーミン先生も俺と同じで中国でスタントとかいろいろやっていたって聞いたから、話聞こうと思ってたら…こんな感じにな」
「…ウーミンだ」
無名が横目でキリンジをじろりと睨み付ける。
「へぇ、で、キリンジさん強かった?」
「あぁ…キリンジ君はとても強い、私の指導なんてもっての他だ」
「いやでも、ムー先生に学ぶことだって結構ある、俺なんてまだヒヨっ子だ」
「…だから、ウーだっての」
無名が持っていた棒で、キリンジの頭をこつんと叩いた。
「それにしても、ニコ今日は早いな、何かあったのか?」
こいつは学校へ行かずに、毎日仕事や雑用で汗を流していることぐらい知っている。
毎日風来坊のように生きているキリンジには、その忙しい毎日が少しだけうらやましかった。
「…警察に見つかった、へへ」
舌をぺろんと出して、キリンジに弁解するニコ。
それははた目から見て、兄弟のような…もしくは年の近い親子に似た、そんな感じだった。
「で、ここに来たってワケか…稽古付けに」
「うん、ウーさんは僕の師匠だもん」
「うむ、ニコは上背が無いからな、若干でもリーチ稼げる棒術が一番最適だと思っとるんだ」
長く伸びた白いヒゲを整えながら、無名はキリンジに説明した。
「しかしのぉ…私の教えたいことはほぼ教えてしまったから、正直今来られても…お?」
ふと、無名の言葉が止まった。
「どしたの、先生?」
ニコが怪訝そうな顔をして、師匠を下からのぞき込む。
「ちょうどいいわ、キリンジ君、ニコと手合わせしてくれんか?」
「「ええええ!?」」
「キリンジ君とニコ、背丈は正反対なれど、扱う武器は共に似通っておる、お互いの欠点とかを知るのにちょうどいいチャンスじゃないのかな?」
無名がキリンジの持っていた槍をスッと手に取る。
「どうかな? まぁちょっとした練習試合だと思えばいい」
そう言いつつ、無名はキリンジの手に、自分の使っていた棒を握らせた。
「…やらせる気マンマンじゃねーか…、ま、確かに悪くはないな…ニコとはやったことないし」
キリンジはため息混じりにつぶやくと、手にした得物をクルクルとバトンのように回した。
「ニコはどうする?」
愛用の革ジャケットを脱ぎ捨て、すでにあっち側は臨戦態勢だ。
「う…ん」
「どうした? 俺とじゃ不服か?」
最初に言われて驚いてはいたが、ニコの方はやや浮かない顔だ。
「じゃ…なくてさ、ライジンならともかく、仲間同士でっていうのは…その、手加減とか…」
「バーカ、子供のクセに手加減とかいちいち考えるんじゃねぇっつーの、思いっきりブチ込んでこい!」
白いタンクトップから透ける胸板をドンと叩き、自分の強靭さをアピール。
ニコと違って確かに、キリンジは鍛え抜かれた身体だ、ちょっとやそっとじゃ倒れないだろう。
「でも…う〜ん…」
しかしそれでも、ニコはまだ浮かない顔だった。
優しさが邪魔をしているのか、それとも…
「んじゃこうしよう、ニコが俺に勝ったら、明日っから飯のときにピーマン代わりに食ってやる、それでどうだ?」
「え…と、もう一言!」
「くっ…じゃブロッコリーも食ってやる(俺も嫌いだが)」
「わかった、じゃあ…やる!」
その問答は、もはや兄弟と言うよりかはクラスメートに似た感じだった。
「んで、お前が負けたら…チハヤと静にアレでもバラしてやるかな?」
キリンジの逆襲が始まった。
その一言に、ニコの笑顔がピンと引きつる。
「あ…アレって一体なに? キキキキリンジのおっちゃん」
「まぁ手始めに、お前の足がすっげー臭いこととか…」
「ちょ! いや! だめ! それ絶対言わないでって以前男同士の約束したじゃん!!!」
痛いところを突かれたニコは、慌ててキリンジにすがり付いた。
「俺だって苦手な食いモン代わりに食ってやるんだ、勝ったらバレないんだぞ? いいじゃねぇか」
「くっ…!」
「その意気込みでやれば俺なんて一発で負かせるさ、だろ?」
「う…うん、分かった、やろう試合…!」
複雑な面持ちで、ニコは自分の愛用の棒をギュッと握り締める。
「(けど…キリンジのおっちゃんにケガさせちゃったら…)」
棒の先端に引っ掛けていた愛用のサンダルをいそいそと履き、いつも練習をしている隣の広場へと足を向ける。
「(はぁ〜、来なきゃよかった…遅いけど)」
「よし、手足か身体に有効打を当てたら一本、それの3本勝負で始めるぞ!」
準備を確認した無名が、双方に話しかける。
「オッケー」
「わかった!」
「よし…はじめ!!」
無名がキリンジの持っていた槍をスッと手に取る。
「どうかな? まぁちょっとした練習試合だと思えばいい」
そう言いつつ、無名はキリンジの手に、自分の使っていた棒を握らせた。
「…やらせる気マンマンじゃねーか…、ま、確かに悪くはないな…ニコとはやったことないし」
キリンジはため息混じりにつぶやくと、手にした得物をクルクルとバトンのように回した。
「ニコはどうする?」
愛用の革ジャケットを脱ぎ捨て、すでにあっち側は臨戦態勢だ。
「う…ん」
「どうした? 俺とじゃ不服か?」
最初に言われて驚いてはいたが、ニコの方はやや浮かない顔だ。
「じゃ…なくてさ、ライジンならともかく、仲間同士でっていうのは…その、手加減とか…」
「バーカ、子供のクセに手加減とかいちいち考えるんじゃねぇっつーの、思いっきりブチ込んでこい!」
白いタンクトップから透ける胸板をドンと叩き、自分の強靭さをアピール。
ニコと違って確かに、キリンジは鍛え抜かれた身体だ、ちょっとやそっとじゃ倒れないだろう。
「でも…う〜ん…」
しかしそれでも、ニコはまだ浮かない顔だった。
優しさが邪魔をしているのか、それとも…
「んじゃこうしよう、ニコが俺に勝ったら、明日っから飯のときにピーマン代わりに食ってやる、それでどうだ?」
「え…と、もう一言!」
「くっ…じゃブロッコリーも食ってやる(俺も嫌いだが)」
「わかった、じゃあ…やる!」
その問答は、もはや兄弟と言うよりかはクラスメートに似た感じだった。
「んで、お前が負けたら…チハヤと静にアレでもバラしてやるかな?」
キリンジの逆襲が始まった。
その一言に、ニコの笑顔がピンと引きつる。
「あ…アレって一体なに? キキキキリンジのおっちゃん」
「まぁ手始めに、お前の足がすっげー臭いこととか…」
「ちょ! いや! だめ! それ絶対言わないでって以前男同士の約束したじゃん!!!」
痛いところを突かれたニコは、慌ててキリンジにすがり付いた。
「俺だって苦手な食いモン代わりに食ってやるんだ、勝ったらバレないんだぞ? いいじゃねぇか」
「くっ…!」
「その意気込みでやれば俺なんて一発で負かせるさ、だろ?」
「う…うん、分かった、やろう試合…!」
複雑な面持ちで、ニコは自分の愛用の棒をギュッと握り締める。
「(けど…キリンジのおっちゃんにケガさせちゃったら…)」
棒の先端に引っ掛けていた愛用のサンダルをいそいそと履き、いつも練習をしている隣の広場へと足を向ける。
「(はぁ〜、来なきゃよかった…遅いけど)」
「よし、手足か身体に有効打を当てたら一本、それの3本勝負で始めるぞ!」
準備を確認した無名が、双方に話しかける。
「オッケー」
「わかった!」
「よし…はじめ!!」
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
高天原・天神嶺 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高天原・天神嶺のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90060人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208308人