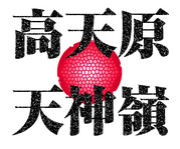第3ターンリアクション ・ 3―1 ■ 担当:たつおか ■
『 大・宴・会! 』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
―――――――――
見つめていればいつしかそこへ落ちていくかのような錯覚を思わせるほどに、空には深く遠い青が満ちていた。
そしてそんな青(そら)の彼方を見上げ続けるうち、そこに真夏の太陽をひとつ見つけ出して――
「――ふえ……へっくしゅん!」
神城 渚(かみしろ・なぎさ)は大きなくしゃみをひとつした。
そのくしゃみで我に返り、改めて渚は自分の乗る交換船の船内を見渡す。
そこには、
「♪Aカップ Bカップ Cカップ Dカップ Eカップ Fカップ Gカップ Hカップ」
「♪8組バストを選ぶとしたら、君ならどれが好き〜」
「F!」
なにやら珍妙な歌をデュエットするソーショクのカバ獣人・ヌコロフ(―)とライジンの犬人少女・クアン、そしてそれに合いの手を入れている同じくライジンの少女・シュラの姿が見えていた。二列14席からなる船内には先頭の席にかのヌコロフ達一同と、そして最後尾には渚が座っている。それ以外に客の姿は見えない。
一同を乗せた船は、東京から南南西180kmの孤島・三宅島へと向かっている。軍籍を持ち、私的にライジンを追う渚は今回、軍内のとある情報筋からライジンがそこへ集うかも知れぬという情報を得てこうして、都と島とを結ぶ交換船に乗り込んでいるというわけであった。
そんな旅の船内で相席したのが――誰でもない目の前の一同というわけである。
「まさかここで“彼ら”に出会うことになろうとはね。ライジンと君達は、つくづく縁が切れへんらしいな」
呟き、渚は交換船最後部にある自販機からアイスキャンディーをひとつ購入してそれを咥えた。
渚は目の前の人物達を良く知っている。“彼ら”は軍内でもちょっと名の通った有名人であったからだ。
ヌコロフと歌っていた少女二人(シュラとクアン)については詳しい情報が無いものの、それ以外のメンバーはある程度の調べがついていた。――彼等は先の『乃木崎重七襲撃事件』の容疑者とされる人物達である。
「静ねーちゃんは泊りとか大丈夫なの? 家族の人とか心配してない?」
「うん、大丈夫。今回はね、素直に『仲の良い友達と旅行に行く』って言ってあるから。だからいっぱい楽しもうね、二コちゃん」
隣席の少女へと声を掛けたザッシュの犬型獣人少年が香月 仁冴(かづき・にこ)だ。彼は乃木崎事件の折には、かの人物の右頬へ飛び蹴りをかましたとされている。そしてそれに語りかけられた少女は、同じくザッシュのライオン獣人である田中 静(たなか・しずか)その人。先の事件には直接の関与はないものの、過去に起きた『ライジン学園襲撃事件』を体験してきた人物であり、その事件の作戦指揮を取っていたのが乃木崎であったことからも、彼との因縁・因果関係は少なくはない。
そして中央通路を挟んで右の二席。
窓側にタツジンの亀型獣人・稲田 匠(いなだ・たくみ)と、通路側にソーショクのキリン獣人・境 麒麟児(さかい・きりんじ)の二人が並んで座っているのもまた確認できた。
「………はぁ」
「どうした、タクミ? 船に酔ったか?」
流れる外の風景に漏らしたそのため息を聞きつけ、キリンジはこの日6本目となる缶ビールの開けるながら語りかける。
「いえ、そんなわけじゃ。――ちょっと考え込んじゃって」
「話を聞こうか? とはいえ、解決の助けにはなれないだろうが」
相談を聞く気が有るのか無いのか、どこか突き放したようなキリンジの口調はどこまでも無体な印象を聞く者に思わせる。しかしながらそういったキリンジの『無関心さ』は、他者の心情(プライバシー)へ踏み込みすぎないようにする気遣いと、そして適度な距離感を保とうとする彼流の思いやりでもある。
どんな時も、そしてどんなに互いの身分が変わろうとも、きっと彼のそんな付き合い方が変わることはない。たとえ数十年と生き別れになって再開を果たしても、まるで昨日別れたのと変わらない態度で、彼は『元気か?』と軽い会釈をするだけだろう。
そんなキリンジの付かず離れずの接し方は、共に泣き笑うばかりが『友情』ではないことを教えてくれる。親友以上の信頼感と安堵を、彼と付き合う者は感じるのだ。
「上手く言えないかも知れませんけど、キリンジさんのその『キリン』っていう容姿は、けっこう珍しい種類なんですよね。そんな『他に類のない』種類に変化したことに、何か意味を考えたことはありませんか?」
タクミの問いに耳を傾けながら、キリンジは開けたばかりのビールを一気に飲み干して、小さく吐息を弾けさせた。
そして、
「私からは何も言えないな。アドバイス出来ることがあるのなら、『もっと悩め』としかいえない」
先のタクミの問いからはまったく脈絡のないそんな答えを返していた。
「私の考えを聞いたところで、所詮はそれは『他人事』だ。自分で答えを見つけ出せない限り、自分の悩みなど解決は出来ない――否、納得できまいて」
タクミの言う通り、まさにキリンジはその類まれなる己の容姿に様々な思いを巡らせたせたことがあった。――否それは、『あった』程度の話ではなく、自分の生き甲斐であったはずの俳優業を奪うまでに彼を追い込んだ深刻な悩みであった。
しかしながらキリンジはそんな悩みと、そしてこの世界と自分との間に生じたズレを見事に克服―― 一致させることが出来た。それも全ては自分の問題として受け止め、逃げることなく受け入れたがゆえの結果である。
もっともキリンジ本人は無気力無関心な体たらくではあるから、今に述べたような葛藤は本人が思うほど感じてはいないわけだが。
「そうですよねぇ――僕とキリンジさんは、『違う』んですよねぇ」
しかしながらタクミは、そんなキリンジの言わんとしている事を理解したような気がした。
この世界に、自分とまったく同じ存在など在りはしない。それと同じように、自分と『同じ悩み』などというものも存在はしないのだ。どんなに同じに見えても、その悩みの根幹にあるものは微妙ながらも違ってくる。
キリンジがそうしたからといって、それを聞いてタクミの悩みが解決するわけではない。――否、むしろ他者とのそうした比較にギャップを感じて、さらなる煩慮の深みへとはまってしまうやも知れない。
そうなってしまうことを案じたからこそ、キリンジは『もっと悩め』と答えたのだ。自分がそうであったように、『自分で考える』ことを提案したのである。
「キリンジさんは優しいですよね。誰よりも無関心そうなのに、実は一番相手のことを想ってくれてる」
「そうかね? 君は穿ち過ぎるな、私はもっと単純な男だよ。面倒くさがりなだけだ」
そう言われたことが柄にもなく照れたのか、キリンジはもう一本ビールを取り出すと、今度はゆっくりと喉に傾けるのであった。
「いやー、歌ったんだなぁ♪ 楽しかったのよ」
そんな二人の元へと、先ほど席の先頭で熱唱していたヌコロフが戻ってきた。
そして自分の席へ座ろうとしたその時、
「――ん?」
ヌコロフは、席の最後尾から自分達を観察しているだろう渚の視線に気付いた。
――あの子、誰なんだな? ただ見てるにしても気の配り方が違う。
つい見返してしまう視線の先――そこに白の毛並みを基調とした狼型のザッシュ少年・渚を確認してヌコロフは眉をひそめた。
背の丈は静と同じくらいであろうか。10月とはいえ残暑厳しいこの季節に、足元まであるコートとTシャツにジーンズと言う装いである。
――もっとも、これくらいならキリンジと変わらないんだけどね。問題は……
ヌコロフがこの少年にもっとも注意を引かれたそれは――その眼の動きそれであった。
監視にせよ、偶然に騒々しい客を眺めているにせよ、無意識に物を見つめている時の人間の視線は大抵、一点に集約しそこからあまり動かないものである。しかしながらこの渚は違う。
ヌコロフ一点を見つめながらも、その前方でクアンが何か動きをすれば視線は一瞬そこに動き、そしてそこから離れたニコと静に動きがあればまたそこへ一瞬視線が行くという、実に状況へ流動的に対応した、さながら監視カメラの如き機械的な動きであった。そこにはまるで、場の状況全てを暗記(インプット)しようとするかのような意図が見て取れる。
そんな目の動きは軍の――それも諜報活動の訓練を受けた者の目の動きに似ていた。
――人種から推理するにSIS(イギリス・軍情報部)かDGSE(フランス・対
外治安総局)? いや、大国のCIA(アメリカ・中央情報局)という説
も捨てきれないし、傭兵家業の情報屋が独自に調査しているとも言い
切れないんだなぁ。
考えれば考えるほどに疑念は深まっていく。
そんなヌコロフと、しばし視線を絡めていた渚であったが――
「お歌、上手でしたね♪ 明日にもデビューできまんねんよ、今のユニットで」
突如笑みを見せたかと思うと、今までの気配がウソのような穏やかな声で、渚はヌコロフへと声を掛けてきたのであった。そんな笑顔とそして言葉に我に返り、
「あ――あぁ、いや、そんな」
その思わぬ邂逅にすっかりヌコロフも気を抜かれ、二・三言葉を交わすと、ようやく席に腰を落ち着けた。
「どうしたんだ、ヌコロフのおッちゃん? 知り合い?」
「ん? いや、ちがうんだなぁ。あの子のアイスの食べ方がエッチぃくて、ついみとれちゃったのね♪」
訊ねてくるニコに対してヌコロフもそうに応えてみせる。そんな答えに促されて振り返るそこには確かにどこか艶かしくアイスキャンディーを頬張る渚の姿があった。――あったが、いかんせん子供のニコにはその仕草の意味が判らない。
「エッチぃ……のかなぁ?」
「んふふ、そのうちニコも判るのよ♪」
そんな小首をかしげるニコにヌコロフもコロコロと笑って相づちを打つ。
しかしながらその実――ニコの言う『知り合い』という言葉は、ヌコロフにも当たらずも遠からずであった。
ヌコロフはあの渚という少年を知っていた。一番最初に彼に視線が止まったのも実は、その面影にどこか見覚えがあったからだ。
とはいえ、
――誰だったかなぁ? ここまで出掛かってるんだけど。
どうにもその『誰か?』が思い出せない。そんないまひとつ想起の及ばない感覚にもどかしさを覚えながら、ヌコロフは喉をさすり頭を捻るのであった。
そしてそうこうしているうちに――
「あ、見えました。島が見えましたよーッ」
静の声に一同はその視線を前方に向ける。
空と海、それら青の光景しか広がっていなかった水平線の極みが、僅かに白くグラデーションを作り出していた。
「あそこが三宅島。ヤマタノオロチの封印二つが眠る場所――」
その光景を前にシュラは呟くよう漏らして眉をひそめる。
目の前の水平線にはいつしか、三宅島の島影が確認できていた。
2
―――――――――
渡船場から降りると一同は、
『ん〜〜〜〜〜、ッくはぁ……!』
揃って腰に両手を当ててその背を仰け反らせた。そうして大きく息をはく動作まで同調させると、
「じゃ、今回のお宿に行きましょうか」
タクミを先頭に、一同は今回の宿となる民宿旅館・しおさい庵へと揃って歩き出した。
そんな折、
「むむむぅ、いなくなってるんだな」
「ん? どうした、おっちゃん?」
その列の最後尾で渡船場を見渡しているヌコロフに気付いてニコが声を掛ける。
しきりに辺りを見渡すヌコロフ――彼は件の少年・渚を探していた。先の船旅を終え、気がつけば渚の姿が消えていたのだ。
船の中ではヌコロフ達よりもずっと後ろの最後尾に座っていた彼である。前の席の一同よりも先に下りたとするならば、その姿を見失うはずはないのだが――しかしながら現実に、ヌコロフは渚の姿を完全に見失ってしまっていた。
――やはり只者ではなかった。軍の関係者となると厄介なのね。今後はもっ
と気を配っておかなくちゃ……。
「おっちゃん、ヌコロフのおっちゃんッ。どうしたんだよぉ、具合悪いの?」
「――、え? あぁ、ううん大丈夫よ」
ニコに揺すられてようやく我に返るヌコロフ。今日はずっとこんな感じだ。
どうにも軍属であった前身を持つせいか、ヌコロフにはこういった気苦労が絶えない。自分自身そういったことには気を遣わないように生きているつもりでも、どうしても体に染み付いた習性は無意識のうちに彼を行動させてしまうのだった。
それ自体は悪いことではないだろうが、いかんせん自分の行動にはそれが行き過ぎる嫌いがある。ネコのくしゃみを軍の秘密細菌兵器などと勘違いして生きていては、日常生活を営むことなどは戦争に等しい。そしてそんな戦争を日常としていては、いつかはストレスで死んでしまうことだろう。
「気楽が一番よねぇ♪」
「へぇ? 変なおっちゃん」
あの少年はただの観光客だった、見失ってしまったのは気のせいだ――そう思い込むようにすると、ヌコロフもまた自分の荷物を担いで、鼻歌交じりに歩き出した。あとに残されたニコは意味も判らずに両肩をすくませるばかり。
そうして民宿へと向かう道中で、
「今回のこの地には、ふたつのヤマタノオロチの気配を感じます」
シュラはそのことを一同へと告げた。
「ふたつも。――ということはライジンの人達もやっぱり」
「そうですね。私が感じるのと同様に母もそれを察しているはず――かの者達の刺客がここを訪れていることは間違いないでしょう」
シュラのそんな重い口調に静も小さくため息をついた。『楽しい旅』ばかりとはならなさそうな気配である。
「ともあれ、今は宿に落ち着いてから今後の事は考えましょう。ほら、見えてきましたよ」
タクミの声に一同は顔を上げる。
松の木に挟まれた砂浜の小道を辿る一行の先に、白塗りの土塀に囲まれた大きな数奇屋造りの家屋が目に入った。
「ほぉ、『民宿』という割には立派な造りだな」
その様子に声を上げて頷くキリンジ。
そうこうしてそこに辿り着こうとする一同に気付き、民宿の玄関先で水撒きをしていたクチバシらしき仲居がこちらへと小走りに寄ってくる。
そして、
「いらっしゃいませ〜♪ 稲田様ご一行ですね? このたびは……――あぁ!?」
「ん? えッ、君はぁッ!?」
かの仲居と顔をあわせた瞬間、互いはそろって驚きの声を上げた。
なぜなら目の前にいたクチバシの仲居は――
「き、君は――チハヤじゃないか!?」
「そ、そういうアンタはタッ君!? っていうか姫様に静もいるじゃん!?」
そう――誰でもない彼女こそは先の池袋中央公園において死闘を繰り広げたライジンの刺客、森羅万衆・風のチハヤその人であった。
「きゃあ〜ん、ニコー久しぶりー♪ 元気だった?」
「ち、ちょっとぉ! なんでチハヤがこんなところにいるのさッ?」
そしてメンバーの中に自分を見つけて抱きしめてくるチハヤに、ニコもその胸の中から彼女に問いただす。
そんな入り口での騒動に、
「チハヤー? 『稲田』様、お見えになったのー?」
青の生地に『しおさい庵』と白抜きされたはっぴを着た、ネクタイ姿の虎の少年が民宿の中から出てくる。そして先のチハヤ同様に一同と顔をあわせ――
「ん? う、うわぁ!? し、静さん! それに皆さんも!?」
「あはは。こんな所で会っちゃうなんてね、ナユタ君」
「やれやれ、きな臭くなってきたぞ」
ナユタもこれまた同じくに驚きの声を上げるのであった。かの虎少年もまたチハヤと同じくに、このメンバー達へ戦いを挑んだライジン、森羅万衆・火のナユタその人である。
「その慌てぶりを見ると、私達を罠にはめようと待ち伏せていた――という訳ではなさそうだな」
一歩前に出るキリンジにチハヤも依然ニコを抱きしめたまま、眉をひそめてその視線を睨み返す。
「今度は何を企んでいる?」
「さぁてね。聞かれたからってあたしが素直に答えると思って?」
見下ろしてくるキリンジの眼力にまったく引けをとらず、それどころか不敵にも笑みを浮かべて見返してくる様はさすが森羅万衆といったところである。度胸が据わっている。
「なるほど。――静」
「は、はい?」
そんなチハヤの視線に鼻を鳴らして頷くと、キリンジは静を呼び寄せて何かを耳打ちする。
「ふんふん――えぇッ? そ、そんなことするんですかぁ?」
「みんなの為だ、ここは一肌脱いでくれ。ここで奴らに先を越されたとなると、今までの苦労も水の泡だからな」
「ん〜……気が乗らないなぁ。なんか騙すみたいで」
何を耳打ちされたのかどこか気乗りなさげな面持ちで静はナユタへと近づく。
「ねぇ、ナユタ君」
「な、なんでしょうッ、静さんッ?」
そしてナユタの右手を取ったかと思うと、
「ナユタ君達は何をしにここに来たの? 教えてほしいな」
「え? んおッッ――――!!?」
その取ったナユタの右掌を――そっと静は自分の胸元へと運んだ。
そんな彼女の行動に反応して、ナユタの毛並みが獅子のたてがみと見紛わんばかりに八方へ逆立つ。そうしてすっかり魂の抜けきった面相で、
「封印の保護をする為に民宿のバイトを装ってここに来ました〜……」
「あ!? ナユタ、このやろ!」
ナユタはオモチャのロボットのよう、口元を上下させていとも簡単に全てを白状していた。
「なによ! だったらアタシにも『旨み』をちょうだい! ニコーッ♪」
「え? ん、んん〜〜〜〜〜〜ッッ!!」
一方のチハヤも腕の中のニコをさらに動けないようきつくホールドすると、熱烈にその唇を奪う。
「そういえば、電話で予約した時に対応してくれた『徳田』さんって、もしかして君? なんとなく声が似てるなって思ってはいたんだけど」
「ん〜っちゅ、ん〜っちゅ、んん〜〜〜〜〜〜〜っぷは。え? あぁ、それアタシ。世を忍ぶ森羅万衆・チハヤは、ここでは『徳田 千羽矢(トクダ・チハヤ)ですから』」
ため息交じりに掛けられるタクミの言葉に、ようやくチハヤもニコを解放してそれに応える。
「まったく、僕のフルネームで予約した時に気付かなかったの?」
「だってアタシ、タッ君の苗字なんて知らないもん。『匠』って名前聞いた時にはなんか嬉しかったけどさ♪」
見知らぬ人間の土地で働く最中、知り合いと同じ名前を発見できたのが嬉しかったと言って、チハヤは屈託なく笑うのであった。
「その笑顔には誤魔化されんぞ。して、何を企む?」
「企むも何も判らないわよ、そんなの。だって今回はアタチ達の仕切りじゃないしね」
「『アタシ達じゃない』、ということは別な誰かが今回の作戦の指揮を取るということか?」
「さぁねー。ま、こっからは自分で調べてちょうだいよ。とにかく、そういうわけで今回アタシ達はノータッチだから。中立ってーことで、ひとつヨロシク。んじゃ、荷物運ぶねー♪」
チハヤの腹芸にキリンジも舌を巻くばかりである。ただ、今回もまた一騒動起こることだけは間違いなさそうではあったが。
かくしてチハヤに案内されて民宿へと入っていく一同―――そうして玄関口には、
「…………」
「………………」
すっかり放心状態となったニコとナユタが残されるばかりであった。
3
―――――――――
「うわぁー、気持ち良いお部屋―♪」
静の弾んだ声が部屋に響く。
部屋割りは男性陣と女性陣、それぞれに分かれることとなった。そしていま静たちが通された部屋は二階の六畳間二つを連結した、何とも広々とした部屋であった。
しかしながら、静が思わず声に出してしまった感動はそんな部屋の広さではない。窓辺の障子戸を開いたそこから望める、大海原の展望を見てのことであった。
「姫様―ッ、ご覧くださいませ。絶景でありますぞ」
「確かに良い風が入りますね。眺めも言うことはありません」
開いた窓からその身を乗り出して海を望むクアンの隣へシュラもまた、そこから広がる海の景観を一望して小さく感嘆のため息を漏らした。
「気に入ってくれたかしら、姫様?」
そんな二人の後ろから、茶道具の一式を運んだチハヤが声を掛ける。
「うむ、大儀であるぞチハヤ」
「アタシが聞いてるのはアンタじゃないよ、クアン。ま、アタシは『裏切り者なんて物置小屋で十分』って言ったんだけど、ナユタがうるさくてさぁ」
「まぁ、ナユタが?」
「へーへー。姫様、アンタが下々の世界に降りられて苦労なされてることが忍びないんですと」
湯飲みに人数分プラス自分の分のお茶を注ぐと、チハヤは遠慮する様子もなく茶請けの菓子蓋を開けてそこにあったせんべいを一枚かじった。
「お前、姫様に出された茶請けを――ましてや客のそれを客よりも先に食うな!」
「ま、そー言うわけですからゆっくりしてくださいよ。あとで気付いたらナユタにも一言なんか言ってやってくださいませ。何だかんだ言いながら、姫様は未だにアイツのアイドルですからね」
「えぇ、もちろんそうさせて頂きますわ。そしてチハヤ、アナタにもありがとう。感謝しております」
「うッ――アタシにはいいんだってば。そういう姫様の空気の読めないところが苦手よ」
面と向かってシュラから礼を言われたことが恥ずかしかったのか、チハヤはかじっていたせんべいをいそいそと食べ終え、ちゃぶ台に両手を突いて立ち上がった。
「でもチハヤちゃん。こんないいお部屋、私達だけで使っちゃってもいいの?」
「気にしないでちょうだいよ、アンタ達以外にはあと一人しか客いないんだからさ」
「『あと一人』? 私達以外に誰かいるの?」
そうして訊ねられる静の言葉に、チハヤもその宿泊客のことを思い出そうと頭をひねる。
「なんて名前だったかなぁ……チャコじゃなくてミーナでもなくて。ともあれその人、変わった人でさ。アンタ達の残りの男供と相部屋で良いって言うんだよね」
「変わってる人? もしかしたら、今日ここに来る船で一緒だった人かも」
「あ、知ってる? まぁ、その人も男だし、向こうが良いって言うんならうちとしては構わないからさ。直接交渉してもらってるんだけど――あ、思い出したその人の名前!」
話しているうちに渦中の人物の名を思い出して手の平を打つチハヤ。
その名前に一同が注目する中、チハヤから出された名は―――
※ ※ ※
「僕、神城 渚ってええます。みなはん、ひとつよろしゅうお願いしますわ♪」
部屋に入るなりそう先客に挨拶され、男性陣一同はどう対処したら良いものか思案にくれた。
「あぁ、すいません。こちらのお客さんなんですけど、皆さんと相部屋を望んでまして」
皆の荷物を背負ったナユタが一同の間に入ってことの説明をする。
「宿側としては判断しかねることだったんで、お客様にその交渉をしていただくよう言ってあったんです」
「一体なぜ?」
そうして改めて向き合い当然の質問をするキリンジに対し、少年・渚も何とも人懐こい笑顔を見せる。
「船の中にいた時からみなはんのことは知ってましたからね。せっかくここで会えたのも縁やし、ご一緒させてもらいたくて無理を言ったんですけど」
「僕は構わないですけど、アナタは気になりませんか? あ、僕『稲田 巧』っていいます」
「これはご丁寧に♪ 僕は渚でええですよ。話は戻りまっけど、見ての通り一人旅でしてね、他のみなはんと一緒にいた方が僕も寂しい思いしなくて済みますんや。どうですやろか? 無理にとは言いまへんけど」
突如として相部屋を申し出てくる少年――結論を言うのなら、この上なく怪しい。
しかしながらコロコロと笑う愛嬌のある仕草と、柔らかい声音で語られる大阪弁の響きは、なんとも暖か気で見る者の警戒心を解かせる様な空気に満ちていた。
「しかしなぁ……」
とはいえしかし、先のチハヤの言葉からも新たなるライジンの刺客もまたここに投入されていることも確かである。この少年がそれではないと言い切れる証拠はどこにもない。
故に『しかし』と考えあねぐ一同を後ろ押ししたのは、
「うははー、美少年は大好きなんだなぁ♪ 僕は大賛成なのよ! っていうか、一緒に泊まっちゃおうよぉ☆」
誰でもないヌコロフその人であった。
「でもさぁ、おっちゃん。やっぱり怪しいよ。もし本当にこの人がライジンだったらどうするつもりさ?」
そんなヌコロフの言葉に当然のよう、ニコは皆の総意を代弁する。しかし――
「だからぁー、“だからこそ”都合が良いじゃないのよ」
ヌコロフは一同の肩を抱きこみ輪を作るようにすると、
「確かに彼がライジンだった場合その接近を必要以上に許してしまうことにはなるけど、だけどそれって言い方を変えれば、『ライジンの行動を監視できる』ってことでもあるんだなぁ」
ひそめたその声でそんな考えを打ち明けた。
「あ、なるほどね」
そのヌコロフの考え・言葉にタクミを始め一同は頷く。
「もし彼が何らかの行動を起こした時、その被害を最小限に抑えることが出来る――と言うわけだな?」
「それだけじゃありません。彼を懐に抱くことでその意図を知ることが出来れば、ライジンよりも早くヤマタノオロチに辿り着けます。足止めはすでにもう出来ているわけですから」
「おっちゃん、冴えてるな!」
円陣のなか、すでに渚をライジンと勘違いして話を進める一同にヌコロフはどこか申し訳なく思う。
なぜならば、渦中の人物である『神城渚』がライジンではないということを、ヌコロフは誰よりも知っているからであった。
――ゴメンね、みんな。だけどあの渚君が、ボキの知ってる『神城渚』か
どうかを、どうしても知りたいのよ……。
円陣からチラリと渚へと、ヌコロフはその視線を投げかける。
そこには食えぬ笑顔で依然微笑み続ける渚の姿があった。
4
―――――――――
高く青い空と、その水平線に積み上げられるかのようくっきりと形を保ち立ち上がる入道雲――そんなどこから見ても夏の砂浜に、
「海だぁー! って、あちちち!!」
その焼けた砂浜へと飛び出し、踊るように飛び跳ねるニコの無邪気な姿があった。
「ニコー、待ってよー。準備運動しなきゃ危ないよー。――もう、あんなにはしゃいじゃって」
「いいんじゃない? あれこそ本来のニコの姿なんだなぁ」
そうしてすでに海の中へと入っていってしまっているニコに鼻を鳴らすタクミと微笑ましく笑うヌコロフ。
一方、砂浜の一角に虹柄の行楽シートを敷いてパラソルを立てるアロハと麦藁帽子のキリンジは中継基地に設置に余念がない。持ってきたクーラーボックスには他のメンバーのジュース以上に缶ビールやら各種チューハイが入れられていることから、泳ぎはせずにこの夏の青空を肴に一杯やろうという魂胆が見てとれた。
そして―――
「な、なんか……恥ずかしいな」
そんな消え入りそうな声と共に登場した静の姿に一同は息を飲んだ。
そこには白地を基調としたワンピースタイプの水着と、そしてその上にパーカーを着込んだ静の姿があった。
食い込みの角度もいたって普通な、比較的“地味”な水着ではあるがしかし――それを着た静の姿はどこまでも艶かしく見えた。出るところの出た胸や尻は元より、僅かに盛り上がった下腹の凝縮感は、より肉感的な静の魅力を見る者へ伝えるようである。
「うわわ。静さん、エッチィなぁ。顔があどけないから余計に感じるね」
「ナユタ君がいたら卒倒だったんだな。とりあえず一枚♪」
そんな静の登場に腕組みをして頷くタクミとデジカメのシャッターを切るヌコロフ。
しかし衝撃はそれだけに留まらなかった。
「うう〜ん、これが地上での『泳ぎの正装』か? まるっきり下着ではないか」
静の後に続いて登場したクアンの水着姿それにタクミはさらに目を見張る。
そこには黒のビキニに身を包んだクアンの姿――しかしながらそれを目の当たりにした一同の視線は、否が応にもその胸元に注がれた。あどけない顔つきと、そしてまだまだ発展途上の体――しかしながらその胸元には静のモノを遥かにしのぐ凶悪なまでの巨乳二つが、たわわに実っていた。
「なッ……なんっていうアンバランス!」
「しかし歪んだ果実もまた美しいものなんだなぁ!! ちなみにあの水着はボキがプロデュースしたのね♪」
そんなクアンのバディに驚愕するタクミと、残り容量全てを使わんばかりの勢いで様々な角度からデジカメのシャッターを切るヌコロフ。
しかし衝撃はそれでも――それでもまだ収まらなかった!
「お待たせしました、皆さ〜ん。地上の人の『泳ぎの正装』はなんとも解放的なのですね♪」
そんなシュラの声に、タクミはそれとなくその方向へ視線を移し――そして固まった。
目の前には白の水着――というか、『白のヒモ』に局部だけを隠したシュラの姿があったから。
Y字を模した水着(?)はその前面で乳首二つを隠すとへその上でひとつに交わり、そこから一本線を描いて股間を申し訳程度に隠している。ヒップにいたっては紐と見紛わんその水着が完全に割れ目の中に嵌ってしまい、その尻を丸出しにさらけ出させていたるかのようにすら見えた。
「んおー!! 堪らないのよ、シュラちゅわぁ〜ん!! そのままビーチバレーなんかしてみようかー!!!」
そうしてどこから取り出したかハンディカメラでその動画を収めようとするヌコロフを――
『いいかげんにしろ!』
場のメンバー一同のツッコミが同時に彼を打ち伏せていた。
ともあれ、シュラには静が自分の水着(――弟の哲(サトシ)がこっそり静の荷物に忍ばせたビキニ)を貸し与え、一同はそれぞれに夏のビーチを堪能した。
「これがレシーブか?」
「そうそう、上手いうまい♪」
静の手ほどきでビーチバレーに興じるクアンとシュラに――
「悪くない――うん、悪くない」
太陽に缶チューハイを掲げて、その青空を肴にそれをゆっくりと傾けるキリンジ――
「んあー! タイ、採ったどー!!」
「ヌコロフ、それオニカサゴ(毒)だよ!!」
さらには素潜りにて海鮮類の捕獲に興じる素手のヌコロフとタクミ―――それぞれが夏の海を堪能するのだった。
そんななか、
「…………」
一休みのつもりで浜に上がったニコは、そこを散策しながらどこか物思いに耽っていた。
眼前に広がる大海原の光景は、雄雄しくもどこか物寂しくそのさざ波の残り音をニコの心に響かせるのであった。
そんな海を見つめていたら――知らずの内に涙が一滴、瞳から溢れて頬を伝った。
「あ、あれ?」
その涙の意味をニコは判らない。
曰くそれは亡き両親を思い出したのか、それとも今日の仲間との逸楽に散り散りとなった兄弟達思い出したのか、それともただ海の美しさに心の琴線が打ち鳴らされてしまったからなのか―――ただ海を見つめるニコの涙は止まらなかった。
「泣いているのかい?」
そんな折に掛けられた声に、ニコは涙を噴くことも忘れて振り返る。そこには、例のコートのポケットに両手を入れた渚の姿があった。
「な、泣いてなんかないよ! た、太陽が、太陽が眩しかったから――」
同時に頬を伝う涙に気付いて、ニコは必死にそれを拭って苦しい言い訳をする。
そんなニコの隣になるよう渚も歩みを進めると、その肩を並べて海を見る。
「――海は、この世の天国に繋がってる」
「え?」
そして呟くようにそんなことを口にした。
「ニコ、君の前世はもしかしたら、名もなき鳥だったのかもしれないよ?」
同時に一気に話が飛躍することにニコはすっかり付いていけずにただ混乱するばかり。それを承知で渚も話を続ける。
「その名もなき鳥は、自分の人生を精一杯に生き終え、そして土に帰ったことだろう。その土は風を受け雨に流されて、やがてはこの海へと帰ってきた。そこでさらに小さな生き物に生まれ変わって、食物連鎖の中に戻る。そしてその旅を終えた前世の君は、やがては君のお母さんの中に入り、君を構成する一部となって――そして“香月 仁冴”として生まれ変わったんだ」
そんな渚の話に、まるで歌を聞くかのようニコは耳を傾け続けた。難しい話はさっぱりである。しかしそれでも彼の奏でる言葉にはその心を――魂をひきつけられるような何かがあった。
「命は――魂は繰り返す。この海がある限りね。だから君は一人ぼっちじゃない。この海がある限り、君の両親も君の中にきっと『帰って』いる。この空がある限り、どんなに離れたって大切な人達の心は途切れない。そしてこの地がある限り――」
「…………」
「僕達はいつまでも同じ場所にいる。どんなには離れても、いつまでも一緒だ」
そう言って――そう謳い終えて振り返る渚の笑顔に、ニコの中にあった『海に涙する何か』は全て拭われてしまった。
ただ心には、この海と同じ心地よい青さが広がっている。
「――オレ、難しい話は判らないよ」
そして頭の後ろで手を組むと、渚に背を向けて足下にあったかいがらのひとつを蹴る。だけど――
「だけど――なんか元気でた。ありがとな」
そういって振り返ると、ニコは今までにした事のないような無邪気な笑顔を見せた。
「じゃ、もうちょっと遊んでくる! 渚もさ、あとで来なよ。みんなと一緒なら、きっともっと楽しいからさ!」
そうしてビーチバレーに明け暮れる静達の元へ走っていくニコ。そんな彼を見送りながら、
「ふふふ。行きたいのも山々だけど、ちょっと気になる人達もいるからね」
そんことを呟き、今度は渚が海を見つめるのであった。
※ ※ ※
「――島への上陸は中止だ。こちらの動きに気付いた者がいる」
一同がいる三宅島から5キロ先の海上――国連海軍所有の武装船上にて、渉里 真夏(わたり・まな)は覗き込んでいた双眼鏡を下ろし、背後の士官へとそれを告げた。
双眼鏡の先の海岸には――かの渚が、こちらへとその目を光らせていた。
偶然大海原に見つけた船を見つめている、というわけではないその眼光は明らかにこちらの動向を監視していると同時、その動きに対応しようと威嚇しているようにすら思えた。
「お言葉ですが軍曹。自分が見ますに、この船の存在に気付いたのはあの海岸の男一人と思われます。その程度でしたら、作戦に支障はないのでは?」
「――君はもう一度士官学校からやり直せ。例え一人であろうと我らの存在が知れた以上、今現在におけるこの作戦の成功はありえない」
マナは背後の士官に振り返ることなく、抑揚の無いその声で冷たく言い放った。
「我らが乃木崎長官は、『暴漢を残らず抹殺すること』あるいは『捕縛』を望んでおられる。今の状態で海岸に近づき、あの男が他の連中へ我らの存在を知らせたらどうなる? 抵抗あるいは逃走されることは考えるに易い。そうなった時に、君はその責任を取れるというのか――そんな安っぽい命ひとつで」
淡々と掛けられるマナの言葉に士官は何も血の気が引く思いがした。今回の作戦はかの乃木崎重七より直接に言い渡されたものである。それでヘタを踏んでしまっては、まさに自分達の命の保障が無い。
「あの男の特徴を本部に伝え照合を行え。これより船はさらに5キロ沖に後退、作戦は深夜を以て実行とする」
マナの号令に大きく敬礼を返して船内にもどっていく士官。そうして船上に一人残されたマナはもう一度――渚達のいる海岸を観望するのであった
5
―――――――――
海底から水面へ顔を出し、その沖からタクミは砂浜の様子を見る。そこではすでにヌコロフを中心にバーベキューパーティが始まっているようであった。
「人数分にはもう少し足りないんだよなぁ。僕がもうちょっと潜るか」
呟くとおり、昼食にしてはまだ食材が少なかった。そしてもう少しその食材に追加をすべく、再びタクミは海中へと潜り込んだ。
澄み渡った海中の視界は良好であった。数十メートル先まで見渡せる海には、空から差した陽光がキラキラと海中を漂う砂粒に反射して、何とも幻想的な世界を目の前に広げている。
「キレイだ……海は本当に、どこまでも美しい」
改めて見渡すその光景に、ついらしくもない言葉が漏れた。
古の詩人達はこの海に関する多くの詩(うた)を残している。しかしそれは彼らが『詩人』であったからではなく、今の自分と同じようにこの海の美しさにそんな素直な気持ちが現れたからではないのか――そんなことを、海中を漂うタクミは考えていた。
そんな海中の様子に見惚れていたその時である。
「ん?」
その世界の中に、明らかに砂のそれをは違う煌きをタクミは確認した。
今までのそれらとはまったく違った光の反射――そんな煌きを反射(かえ)すそれは、10メートルほど先の海域を左右に移動をしていた。
――なんだろう、アレ? 魚? でも姿が全然見えない……
以前目で追い続けるそれは、確かに何か魚影のようにも見えた。しかしそれは、まるで保護色の動物が背景の一部になりきるかのようこの海に溶け込んで、時折その体をうねらせて推進力を得る時以外は、まったくといってその姿を確認させなかった。
しかもその大きさたるや2メートルはくだらない。そんな巨大な物体――生物がこの海に溶け込んで自分の目の前を泳いでいたのだ。そんな生物と世界を供する事実に、先の美しさとは裏腹に、改めてタクミは海の恐ろしさを知ったような気がした。
しかし次の瞬間――そんなタクミの恐怖は払拭される。
ふとその海域を泳いでいた鯛(獲物)をその影が捕らえた瞬間、今まで透明であったそれの姿が一瞬――不降り注ぐ陽光の元にその姿を現せた。
それは一人の、タツジンの女性であった。
イルカやシャチのような艶やかな黒の体躯とウェーブ掛かった金の髪――形の良い乳房とヒップラインの体躯を捻り獲物を捕らえる姿は、おとぎ話の中にある人魚を見つめているかのような幻想をタクミに覚えさせるようであった。
そんな光景の中、かのタツジンとタクミの視線とが触れ合った。
時間にしてみれば、まさに一瞬である。その一瞬――かの人魚は、タクミを見て微笑んだ。その笑顔に、まるで魔法にでも掛かったのかのようタクミは見惚れて動けなくなった。
そして我に返った次の瞬間には、彼女はまた消えていた。
「え、えぇ? あれ? どこに」
そこから慌てて周囲を見渡すも、すでに彼女の姿はどこにも無かった。
そうして一人海中世界の中に残されたタクミは、ただ今の光景を夢か正気か己に問うばかりであった。
※ ※ ※
「夢じゃないの、それ?」
一連のタクミの体験談に、聞き手であったニコは苦笑いをひとつ浮かべた。
場所は海から戻ってしおさい庵――男部屋での話である。
「そんなことないよ! いたんだ――いたはずなんだ」
一方そんなニコの言葉にタクミも反論してみせるが――その声も終りでの方では己自身に問うかのような弱々しいものへと変わっていった。言われる通りニコの言う『夢』という可能性もまた、タクミ自身も捨てきれずにいる。それほどに、あの海の中にいた彼女は美しかった。
「確かにタツジンはいるかもしれないけどさ、こんな所で都合よく会えるものかなぁ? タッ君だってずっと海の中で呼吸(いき)が出来るわけじゃないんでしょ。酸欠になって幻を見たんじゃないの?」
「うう〜ん。言い返せない……」
ニコには珍しいその理論立った言葉を聞いていると、ますます自分の中にあるあの体験は夢物語のような気がしてきた。その証拠にタクミの心の中にいる彼女の美しさは、もはや神々しいほどにまで美化されてしまっている。
そんなタクミと向き合っているニコを、
「私には君のフロ嫌いの方が信じられんよ」
突如としてキリンジが、その襟首を持ち上げた。
「風呂に行くぞ、ニコ。露天温泉があるそうだ」
「な、なんだよ急に? オレはいいよぉ」
急のキリンジの申し出に当然のよう戸惑うニコ。しかし、
「良いものか、臭うぞ君はヒック。まだ私の方がマシなくらいだ。ウイー」
「え゛!? そ、そうなの……?」
キリンジの思わぬ言葉にニコも改めて自分の体を見下ろす。
大き目のオーバーオールにシャツ、そして擦り切れたマフラーとサンダルの格好はこの南の島においても変わらない。(もっともキリンジも、つい先ほどまではコートにジーンズであった訳だが)
実際はキリンジが言うほどのニオイはニコからは発せられてはいない。しかしながらその一張羅ゆえ、自分の体臭や清潔と言うものに過敏になっているニコを見かねたキリンジが、彼なりに気を利かせたというわけであった。
「い、いいよキリンジのおっちゃんッ。オレ、自分でやるよぉ。っていうか、酔ってるだろ?」
「それこそ良いものか。こういうものは自分ではヒック、洗えてないものなのだ。そんなことじゃチハヤやクアンや静に嫌われるぞ、ヒィィック!」
「うッ――そ、それは」
「いいから、任せる! 今日は皮の裏の裏まで洗い倒してやるぞ、バーロー!」
かくしてニコを小脇に部屋を出て行く酔っ払い。その光景に、
「とんでもないのに絡まれたのね、ニコは」
「う、うん。言っちゃ何やけど、僕やなくて良かったよ」
男達一同は合掌。苦笑いしか出てこない。
「失礼しまーす」
そんなキリンジ達と入れ違いにナユタが部屋へと入ってくる。
「どうしたんだい、ナユタ君? 晩御飯はまだ先やろ?」
「いえ、うちの女将が挨拶をしたいと申しまして」
訊ねる渚にナユタも苦笑いをひとつ浮かべる。
「今しがた女性の皆さんには済ませてきたんですけど、遅れちゃってスイマセン。本当なら皆さんがお越しした時に挨拶させたかったんですが、ちょうどその時は今夜の食材の調達に出てまして」
「ふぅ〜ん、なるほどね。興味あるんだなぁ♪ ねぇ、タッ君」
「ん? あぁ、そうだね」
同意を求めてくるヌコロフの言葉にも、今日のタクミはどこか上の空だ。
今回この宿をインターネットで探した時、情報サイトの説明には『美人女将が接待する宿』として、このしおさい庵は紹介されていた。今回の宿選びは主に予算を中心に決められたものではあったが、それでも少しは皆の旅情気分を盛り上げようと、タクミはその謳い文句を一同へ伝えていたのであった。
タクミも男である以上、美人は嫌いではない。そして今日の宿の女将にも興味はあったが――いかんせん、昼のあの人魚に心を奪われて以来、もはや現実世界の美人などにタクミの食指は動かなくなっていた。
「じゃあ、よろしくお願いします。レイシアさぁーん」
かくしてナユタの呼びかけに応じ、丁寧にふすま戸を開けて一同の前に三つ指を立てる女将・レイシア。
「このたびはしおさい庵へご足労いただきましたこと、誠にありがとうございます」
そしてそこからゆっくりと顔を上げる彼女に――
「え――え、えぇ!? あぁー!!」
そのレイシアに思わずタクミは立ち上がり、そして失礼にも彼女を指差してしまった。
そこにいた、かの女将こそ―――タクミが先ほど海の中で見た『人魚』その人であったからだった。
深い藍の地肌のタツジンが彼女・レイシアであった。直立型の大型人竜をモデルとした彼女の体つきは何とも豊満で、そして母性的であった。そのプロポーションは全体に大きく脂肪を蓄えながらも、出るところが出て締まる所の締まった典型的な“ひょうたん型”を維持し、和装の着物の上からもそんな肉感的なボディのラインを見る者に想像させた。
同じ肉感的な体型ではあっても若さと張りのある静とは違い、レイシアのそれはまるで液体の入った水袋のよう柔ら気でしっとりとした、なんとも『熟れた魅力』に満ち満ちている。そして波打った黄金の髪を後ろ頭に結い上げたその髪型は、衣紋から覗くうなじを露とさせ、そんな彼女の艶やかさをさらに際立たせるかのようであった。
「あら。あなたは、たしか海の中にいましたね」
顔を上げたレイシアは自分の前で立ち尽くしているタクミに気付き、朗らかに笑みを向けた。
「や、やっぱりアナタだったんですね! あの海の中の人はッ」
どこかおっとりとした彼女の口調とは裏腹に、何ともタクミは忙しくそして緊張した声で応えた。
「えぇ。今夜お客様に出しますお食事の食材を採っていたんです。――でも、恥ずかしいわ。誰もいないと思って裸で潜っていたから」
「は、裸――」
成熟しながらもしかし、どこか少女のような笑顔を見せて微笑むレイシアの言葉に、タクミの脳裏には彼女を初めて見た時の光景がありありと蘇る。
豊満な彼女の一糸纏わぬその姿――そしてその彼女が目の前にいることにタクミの羞恥心は限界を向かえ、
「お、お風呂いってきまーす!」
跳ねるよう飛び上がると、タクミは逃げるよう部屋を後にした。
そして廊下のどこかでつまづいたのであろう、激しく転び転げる音が遠く伝わってくるのを聞き、
「青春やねぇ♪」
「タッ君にも暑い春が来たんだなぁ」
ヌコロフと渚は深くため息をついた。
「あの方が予約を入れてくださった、『稲田匠』さんなんですね?」
同時にそんなタクミの出て行ったふすま戸の向こうを見つめながら呟くように確認をするレイシア。
「そうなのよ。見ての通りの子だから、仲良くしてあげて欲しいんだなぁ。もちろんボキ達ともね♪」
「えぇ、もちろんですわ。たっぷりとご奉仕させていただきます」
そういって微笑むレイシア。
その笑顔には先のものとはまた違った、なんとも妖艶な気配が含まれていた。
6
―――――――――
一階の離れに造られた二十五畳の大広間が、一同が夕の食事を取る『宴会場―夕顔の間』そこであった。
「えー、改めまして今夜の席でみんなとの友情をさらに深めたいと思いますのね。それでは僭越ではありますが乾杯の音頭をとらせてもらいますなんだなぁ。んじゃ――かんぱい!」
そうしてヌコロフの乾杯の音頭と共に――
『かんぱーい!』
それぞれが手にしたグラスを掲げ、かくて一同の大宴会は始まった。
「う、ううん……」
「ん? どうしたんだ、ニコ?」
その席の一角で、なにやら浴衣の上からしきりに腰元を気にしているニコへとクアンが語りかける。それに対し、
「な、なんでもないッ。なんでもないよぉ……」
どこかいたずらのばれた子供のよう悪びれた様子でクアンの視線から逃れようとするニコの傍らから、
「まだ痛むか、ニコ? チ○コは?」
その隣からずけずけと、そのニコの異変の原因をキリンジは言ってのけた。
「お、おっちゃん!!」
「まぁ、そんな大切な部分がどうかしましたの?」
そんなキリンジに慌てふためくニコと、そしてニコの身を案じているのかそれとも単にそういう話が好きなのか、シュラが同時にキリンジへと声を掛ける。
「いやな。夕方一緒に風呂に入った時に、『皮っかむり』だったもんだからな、ひん剥いて直接洗ってやったんだ」
「まぁ☆」
「お、おっちゃーんッッ!!」
「姫様! そのような話を聞いては耳が穢れます!!」
「もう13なんだから遅くは無いぞ、ニコ。それに見た感じ『出口』もしっかり広がってたし、包茎じゃなくて良かったではないか」
「えぇ。いつまでも被ったままでは『モテません』わ」
『うぅ……ッ』
相次いでキリンジとシュラから浴びせられるセクハラトークに、当の本人であるニコとそしてシュラの侍従であるところのクアンは揃ってうめきを漏らした。
「でもね、ニコ。それは大事なことなんだなぁ。時期になっても被せたままだと病気の原因にもなるのよ」
「そうそう。それに敏感になりすぎて、いざちう時に堪え性もなくなるよ、ニコ君」
「赤ちゃんを作ることに関わることだからね。それは重要なことなのよ、ニコちゃん」
「ウガーッ!! どうしてオレのチン○のことに、みんなしてそうお節介なんだよぉ!! それに静姉ちゃん、酔ってるだろ!?」
いじられ過ぎてついには爆発するニコ。期せずして場に一同の笑い声が響き渡る。
そんな中に、
「はいはぁ〜い。コンパニオンの登場でぇ〜す♪」
チハヤを始めとし、女装した(させられた)ナユタとそしてレイシアが宴会の中に入り、それぞれに酌をして回る。
「なになに? 何の話をしてるわけ?」
そして当然のようにニコの騒動の中へと入ってくるチハヤ。
「あ、チハヤちゃん。今ね、ニコの○ンコの話をしてたんだな」
「え、マジで? どういうこと? どーいうことよ!?」
「それがね、お風呂でねキリンジさんが皮を剥いちゃったんだって、ニコちゃんの♪ うふふふ、あははは!」
「本当それ!? って、静……アンタかなり酔ってるわね」
ニコの話題も然ることながら、普段の清楚な静からは信じられないその乱れ様にチハヤも苦笑いをひとつ。
「だ、大丈夫ですか、静さん? 気分とか悪くなってませんか?」
そしてそんな静の身を案じ、間に入ってその様子を伺うナユタに対しても――
「わぁ、なぁにナユタ君その格好? かーわいいー♪」
静(酔っ払い)は構うことなく絡みついた。
「こ、これは――接待するのに女の子が足りないから僕も加われって、チハヤが強引に」
「すごい似合ってるよ、ナユタ君。っていうか、普通に可愛い♪ もー、このまま抱いて連れ去っちゃいたい!」
どこか乗り気ではないナユタとは天と地ほどのそのテンションで、胸に両手を置いて萌え悶えてみせる静。そして次の瞬間――
「ナユタ君。もう、私達と戦うのなんてやめてうちに来なよぉ。うちの子になっちゃいなよ♪」
「ッ!? し、静さん!?」
言うや否や、静はナユタをその胸元へ抱き込んだ。浴衣の襟元から無防備に覗くその胸元に顔を埋められその体を硬直させるナユタ。
さらには――
「ナユタ。このたびの宿は、貴方が骨を折ってくれたようですね」
シュラもまた近づく。
そして、
「仲違いしてしまった身でありながら、こんな私にここまで尽くしてくれる貴方の気持ちに感謝しますよ。ありがとう、ナユタ」
「あ、あああ! シ、シュラ様もぉ!? っていうか、二人とも酔ってますね!?」
その背後からシュラもまたナユタを抱きしめた。
そうしてナユタは前後から憧れの人に抱かれ、
「あ、あああああッ!」
そして存分におっぱいに挟まれて―――
「ああ、ああああああああ………―――きゅぅうん」
イッた。
場はさらに混沌の度合いを増していく。
「キリンジぃー! アレをやれ! アレをやってくれ!!」
ついにはクアンも酔いだしキリンジにあの技のリクエストをする。
「仕方のないやつだな。ならば注目あれ! 一番キリンジ、槍を出します!!」
言うや否や大きく広げた口の中に拳を入れ、やがてその喉の奥から得物の槍を引きずり出すキリンジ。拍手大喝采が場に飛び交う。さらに、
「今日は大サービス!」
「まさか!? 二本目も!?」
「ホントにどこに入ってるの!?」
そこからさらに二本目の槍も吐き出してみせるキリンジの芸に場の全員が―― 一同が地上人もライジンも忘れて、惜しみない声援と拍手をキリンジに送った。
そんな光景を、ただ一人タクミは微笑ましく見守っていた。
ノリが悪いわけではない。十分に楽しんでいる。ただ、タクミの反応があくまで『普通』であり、むしろ周りはそれ以上の、ありえないほどのテンションで盛り上がっていたのだ。
そんなタクミへと、
「楽しい皆さんですね」
女将であるレイシアがそっと近づいた。
「レ、レイシアさんッ」
「ふふふ。お酌いたしますわ」
そう言ってタクミに杯を持たせると優雅な手つきで銚子の日本酒をそこへ傾ける。
タクミもやや恐縮しながらもそれを受けると、一息にそれを飲み干した。
「まぁ、お強いんですね」
「そ、そんな。僕は普通ですよッ」
その一杯に心が打ち解けてか、二人は様々なことを話していった。
それは今まで旅のことであり、そして戦いのこと。さらにはシュラとクアンを始めとする様々な人達との出会いと――そしてその出会いゆえに、今まで以上にライジン達と判り合いたくなったという胸の内を、タクミはレイシアへと明かした。
そしてそんな話の終りに、
「レイシアさんは、自分がタツジンに変身した事に何か意味があると思いますか?」
タクミはそのことを彼女に尋ねていた。
それは兼ねてより、タクミが考え続けていたことであった。
高天原の出現と同時に人類が獣化したあの日――タクミは『新たな自分』の発見に胸を躍らせると同時、そうなってしまった『自分の存在』に戸惑いもした。
タクミやレイシアの『タツジン』という種族は獣化人類の中においても、その数が極めて少ないとされる種である。そのような希少種にどうして自分はなり得たのか?
『偶然』という言葉では片付けたくはなかった。運命と言うものがもしあるのだとするのなら、この獣化は『必然』であるはずだ。ならばその『意味』とは――『自分の存在』とは何かをタクミは探し続けていた。
そんな時に現れたのがレイシアである。
自分以外には初めて出会う『タツジン』――思えば彼女と初めて出会った時に感じた胸の昂揚は、そのことにも起因していたのかもしれない。だからこそタクミは己の悩みを彼女に打ち明けた。彼女がタクミの抱えるこの問題に対し、どのような受け止め方をしているのかを聞いてみたかったのだ。
そんなタクミの話を聞き終え、レイシアは小さく数度頷いた。そして伏せていた瞳を開き、やや上目遣いにタクミを見ると、
「タクミさんはきっと――まだ自分が獣化した言うことを、受け入れてないんだと思います」
そう言って小さく息をついた。
「え―――」
以外であった。
レイシアの『考え』を聞いたはずが、戻ってきたのはタクミ(自分)自身への指摘であったのだから。
「質問の答えになっていないようですいません。でも私は、あなたのお話からそんな印象を受けたんです」
そんな唖然とするタクミを前にレイシアは続ける。
「あなたがまだ人間であった頃、自分が『人』であるということを今ほど意識したことはあったでしょうか? おそらくは、無かったと思います。獣化以前よりもそのことに思い悩んでいたのなら、今になって急にそのことを思い悩むということは無かったはずですからね」
「たしかに……そうかもしれません」
言われる通り獣化前は、自分の存在を『考え』こそすれども、今のように『戸惑う』事はなかった。
「今のタクミさんは、獣化した自分を『認めて』はいても『受け入れて』はいないんだと思います。頭では受け入れたつもりでも、心ではまだどこか今の自分を否定している――そんな体(頭)と心のズレこそが今の悩みの原因となっているんじゃないでしょうか?」
「ならば――ならば、レイシアさんは受け入れているのですかッ?」
話しているうちに、タクミはいつの間にか強く鼓動が脈打つのを感じていた。静かに起き上がった興奮は、知らずの内にタクミを熱くしていた。
そして、
「あなたは――自分と心の間にズレは無いのですか?」
そしてレイシアの次の答えに――
「えぇ。どんな姿でどんな場所に居ようとも、私は私ですから」
タクミの中にあったそんな熱は一気に醒めた。
なんだか納得してしまった。しかし『納得』はすれども、自分のなかにあるあの戸惑いは未だに解決している様子は無かった。レイシアの言った体と心のズレのよう、タクミは今の答えを『納得』は出来ても『理解』は出来なかったのだ。
そして同時に、またもや生じたそんなズレは益々以てタクミの妄念をより深くさせてしまうのだった。
かくして数時間後、宴会は一同の悲喜交々を含んでお開きとなった。
そしてこれより、長き夜が始まろうとしていた。
7
―――――――――
時はすでに深夜の2時を回ろうとしていた。
すっかり人の気配が消えた冷えた廊下を人影がひとつ、足音静かに進んでいた。
やがて人影は露天温泉の更衣室まで辿り着くと、その身に纏っていた衣類を脱ぎ捨て一糸纏わぬ姿となりその胸元をタオルで包み込む。
そうして更衣室を出て、露天温泉の月明かりの下に現れたのは――
「はぁ、素敵なお風呂」
誰でもない静その人であった。
先の宴会より数時間、僅かに酔いの醒めた静はその体を清めようと一人ここの温泉を訪れていた。
このしおさい庵に着いてからまだ温泉には入っていなかった。どうにもここのメンバーに、例え同性ではあれ自分の肌を見られるのが恥ずかしいような気がしたのだ。
別段シュラやクアンを、そしてもちろんのことながら他のメンバーを厭っているわけではない。ただ、先月の事件(おっぱいポロリ)もあったせいか、どうにも自分の肌を見せるのが恥ずかしくなってしまったのだった。
故に水着もワンピースにパーカー姿なら、入浴もこんな時間帯にコソコソと済ませに来たという訳である。
数度のかけ湯で身を清めると、その髪をタオルに巻いて、静は肩まで温泉に浸かる。
入り始めは少々高めの湯の熱が身の内を強く硬く凝縮させるようであったが、それも湯の温度に慣れてくると、今度はそうして凝り固まっていた力や疲れが湯の中に広がるよう脱力して、その心地好さに静は大きくため息をつくのだった。
こうして身も心もほぐれると、ちっぽけな羞恥心で一人の入浴を選んでしまったことに僅かな後悔を感じないでもなかった。
「シュラさんやクアンちゃんと一緒に入ったら、もっと楽しかっただろうなぁ」
そんなことを呟いて、露天岩風呂の一角に上体をうつ伏せたその時であった。
「あら、今からでも遅くありませんわ」
まるで静の呟きに応えるかのよう、突如として響(かえ)ってきたその声に静は顔を上げる。
そうして露天風呂の入り口――その湯煙の中から進んできたのは、
「ご一緒しても宜しいかしら、静さん」
誰でもないシュラであった。
「シュ、シュラさんッ?」
そんな突然のシュラの登場と、そしてあまりのタイミングの良さについ静の声も高くなる。
「起きてらしたんですか?」
「いえ、私もいま起きたばかりです。少しばかり酔いが過ぎたようで、逆に目が覚めてしまったのです。それでその酔いを醒まそうとここへ」
そして静と同じようにかけ湯を浴びると、岩風呂の縁へ腰掛けるようにしてシュラも入浴をした。
そうして二人、肩を並べて湯船に浸かる。そんな今の状況に、思えば二人きりになること自体が初めてであることに静は気付く。
「そういえば初めてですね、私とシュラさんが二人きりになるのって。クアンちゃんはどうしたんですか?」
そう。いつもこのシュラの回りには、必ずといって良いほどクアンが居たのだ。考えてもみれば、そのクアンのせいで今までシュラと落ち着いて会話ができなかったということもあった訳だが。
「ふふふ。クアンは、夕の宴がよほど楽しかったのでしょうね。すっかり眠ってしまって、起こしてしまうのも可哀想でしたから、そのままにして私だけが参りました」
その問い答えることに思わず笑ってしまったのは、静と同じくに常日頃のクアンの様子を思い出してのことからであった。
「あれにも苦労をかけます。天神嶺においては、私の唯一の理解者でありましたからね。だからこそ感謝もしております」
「シュラさん」
そんなシュラの言葉に静は、改めて彼女が己の一族であるライジン族を裏切り地上に降りた身であることを思い出した。
まだ16の身の少女がである。ましてや箱の中に入れられ、世の苦しみとは隔絶されていた少女が、単身住みなれた地を捨ててこんな双方の戦いが激化する地上に降りてきているのかと思うと、静は何とも不憫に思えて仕方がなかった。
「今の生き方は悲しくは……つらくはないですか?」
つい余計なこととは思いつつもそんなことを訊ねる。否、訊ねずにはいられない。シュラは静にとって大切な仲間であるのだ。だからこそ少しでもその苦しみを理解し、そして共有してやりたかった。
「日々の暮らしにそれを感じたことはありません。クアンを始め、ヌコロフさんやキリンジさん、そしてたくさんの皆さんが良くしてくださいます。――ただ」
シュラは応える。
「――ただ?」
「……そう、愛する人に自分の想いが受け入れてもらえなかったことは、どんなことよりも苦痛で、そして悲しく思います」
そう続けるとシュラは天を仰いだ。
見上げるそこは、今宵の月の眩さに星すら確認できぬほど月光に満たされていた。
そして遥か北北東の彼方に見える高天原の姿もハッキリと確認することが出来た。
「私は――ただ、その人に認められたかったのです。でもその人は私を受け入れてはくれなかった。もしかしたら私がこうして地上に降りたのは、正義や義務感などではなく、こんなちっぽけな私の『わがまま』であったのかも知れません」
空の天神嶺を見つめたまま語るシュラの口調はもはや独白に近かった。まるで自分自身にそのことを問いただしているかのよう静には聞こえた。
そして同時に彼女の身の上もまた思いだす。かのヤマタノロチの復活を目論んだ京帝スオウは、一族の長にしてそして彼女の母でもあるという。そんな近しい存在の人が人の道を踏み外そうとする様を見守ることはどれだけに心苦しいことか。そして、肉親と道を別つことでしかそれを止める術をもたない運命とはどれだけ残酷なことか――そんな彼女の身の上を思うと、まるで静は己のことのようその胸が熱く苦しくなるのだった。
「シュラさん、絶対に止めてみせましょうね。ヤマタノオロチの復活を」
そう言うと静はシュラの手を取った。
「私にはシュラさんの苦悩を理解してあげることも、そしてその苦しみを解決してあげることも出来ません。でも、ヤマタノオロチの復活を止めることは出来るかもしれない」
「静さん」
握り締める両手は、己の意思とは反応してその力が強くなっていった。まるでこのシュラを助けてやろうとする決意に比例するかのよう強くなるのであった。
「あのヤマタノオロチの復活を止めることが出来たなら、きっとそれは全ての解決の糸口になると思います。――だから頑張りましょう、みんなで。私や他のみんなは、皆シュラさんの味方ですからね」
「静さん――私は幸せ者です。クアンだけじゃなくあなたや、そして多くの人々にこうして勇気をいただけるのですから」
微笑を返すシュラの瞳にも涙が一滴浮かんだ。
「これからもどうかよろしくお願いします、静さん。こんな私ではありますが、どうか力を貸してあげてください」
「水臭いですよ、そんな」
「そうなんだな! ボキも頑張っちゃうのよ!」
そうしてシュラとヌコロフも静の手を取り、三人はそれぞれにその誓いを新たにした。………新たにしたがしかし、
「ん?」
何か『異変』があることに静は気付く。
「シュラちゃん、困ったことがあったら何でもボキにいって欲しいんだな。ご飯の準備から、下(シモ)のお世話までなんだってしてあげちゃうんだから。だから、シュラちゃんも頑張って!」
目の前には、立ち上がり熱を込めて修羅を励ますヌコロフの姿。
ここは女湯のはずである。
「あ、あの〜、ヌコロフさん?」
当初は静とシュラの二人しか居なかったはずであった。
それなのに、
「な、なんでヌコロフさんがここに居るんですか?」
「へ? ……あれ? あぁ! 男湯と間違えたんだなぁ☆」
静の問いにヌコロフは辺りを見渡すと、わざとらしく頷いて立てた親指を静達へと向けるのであった。―――もちろんのことながら、確信犯的『勘違い』である。
次の瞬間、
「そんなワケないでしょー! この人はぁー!!」
静は叫ぶや否やヌコロフを持ち上げると、昼のビーチバレーよろしくに彼をトスで打ち上げる。
そしてその宙で体を丸まらせるヌコロフのお尻へと、
「殿方は男湯ですわぁー!」
「んあー! 東洋の魔女ここに復活なのねぇー!!」
シュラの痛烈なアタックがそこを打ち弾き、ヌコロフを浴場の仕切りとなる衝立の向こうへと叩き込んだ。
そうして男湯で大きく上がる水しぶき。
「んあ〜、ひどい目にあったんだなぁ」
その湯の中から頭を上げるとヌコロフはピルピルと耳を震わせてお湯を振り払った。
そんな彼へと、
「災難やったね。でも、アレはあんはんが悪いや。さすがに」
どこが笑いを含んだ声が掛けられる。その声の先に居たのは――
「き、君は……」
「おこんばんは♪」
誰でもない神城渚であった。
「ど、どうしたんだな? こんな夜中にこんな場所で?」
「『こないな場所で』って、お風呂に入りに来よったに決まってるやないか。静はん達と一緒や」
そういって微笑みながらすくった湯を肩口にかける渚。そんな渚の体を改めて間近で見て、ヌコロフは息を飲んだ。
その渚の体には――実に大小様々な、無数の傷跡が見て取れた。裂傷を縫い合わせた跡や銃創などの戦争で負ったであろうものを始め、中にはそれらとはまた違った気配の傷達も見られた。
その小さく果敢なげな体に刻まれたそれらは、この少年がどのような生き方をしてきたのかを、見る者に無言で語りかけるかのようであった。
そしてその体を確認し、
――間違いない。この子は……
ヌコロフは完全にこの少年――神城渚の正体を知るに到った。
「神城渚……」
「………気付いたかい? ヌコロフ・アナルビッチ・チョメチョメスキー」
「君は―――」
そしてその正体を、言葉にして確認しようとした瞬間―――
「ぬ、ヌコロフさん! 海を見てください!」
突如として響き渡ったシュラの声にヌコロフは続く言葉を飲み込んだ。
そしてその声に導かれ露天温泉から望む大海原には、
「な、なんなのね? あれはッ?」
その沖から天に向かい、蒼く立ち上がる光の筋が見えていた。
「あれこそはヤマタノオロチの分身のひとつです。とうとう、その姿を現しました」
「あれが? こんな時に現れるなんて」
「ともあれ、私はすぐにそこへ向かいます。ヌコロフさんもどうかッ」
仕切りの向こうの女湯でバシャバシャと湯を掻き分けて進むシュラと、そしてその後を追ったであろう静の気配が感じられた。
しかし今夜の騒動はそれだけに留まらなかった。
そんなシュラ達が湯船を後にするのとほぼ同時――今度は地震かと思うばかりの爆音が低い地響きとなってヌコロフ達の足元を揺らした。
「こ、今度は何なんだな!?」
辺りには湯煙に混じり、明らかに何かが焼ける饐えた匂いが漂い始める。おそらくは先の爆発において、宿の一部が炎上を起こしたのであろう。
「どうやら、『昼の連中』も行動を解したようやね。こうなりよったらもう、あまりゆっくりしてはいられへんな。行くよ、ヌコロフ」
「え、えぇ? 『昼の連中』って誰なのよ? あ! ちょっと、渚くーん!」
そうして自分ひとり状況を理解して温泉を後にする渚と、何も判らずに慌ててその後を追うヌコロフ。
長き夜は今――始まろうとしていた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 マスターより 】
物語は、
『 3-2・機械仕掛けのオレンジ 』(地上偏・対国連軍シナリオ)
http://
『 3-3・新しい君 』(海偏・対ライジンシナリオ)
http://
――に続きます。
.
|
|
|
|
|
|
|
|
高天原・天神嶺 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高天原・天神嶺のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 写真を撮るのが好き
- 208428人
- 2位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42967人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82636人