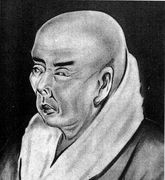正しい信心の特徴を
【蓮華の五徳】を通して
明らかにしたいと思います。
◎蓮華の五徳
今回は、蓮の花についてのお話です。
仏教と蓮の花は、大いに関係があります。仏様は、蓮の花の中に立っておられたり、また、座っておられます。仏様が立ったり、座ったりされているところは、蓮台です。また、極楽の絵を見ても、蓮の花が描かれています。タンポポやパンジーやダリヤなどの他の花は、ありません。蓮の花しかありません。このように、仏教では、蓮の花が描かれますが、蓮の花と仏教は、どういう関係があるのでしょうか。
蓮の花は、「正しい信心」を表しています。
浄土真宗の皆さんなら、朝晩勤行(おつとめ)されると思いますが、そのおつとめで読まれる『正信偈』は、親鸞聖人が書かれたものです。親鸞聖人は、今から約八百年前の方で、親鸞聖人の教えられたことは、唯一、全人類が救われる教えなので、親鸞聖人のことを、世界の光と言われます。親鸞聖人は、90才でお亡くなりになっていますが、その間、教えられたことは、「正しい信心」一つです。
◎正しい信心
私たちは、いろいろなものを信じています。言葉を換えれば、いろいろな信心をもっています。しかし、正しい信心でないと、幸せになれません。正しい信心でないと、人間に生まれてきてよかった、という幸せになれないぞ、と親鸞聖人は教えられています。
テレビのニュースなどで、「これを信じたら、お金が儲かる」と言われ信じたが、それが間違っていて、苦しんでいる人を見ますが、信じてはならないものを信じると、苦しまねばならない、泣かねばならない、幸せになれない、ということです。正しい信心でなければ、幸せになれません。
幸せになれないということは、救われない、ということです。正しい信心をえれば、救われますが、正しい信心をえなければ、助かりません。正しい信心をえた人は、この世も救われ、未来、後生も救われます。
蓮の花のような正しい信心を頂いた人は、死ねば仏になります。ですから、仏様は、蓮の花の上におられます。奈良の大仏は、蓮の花の上に座っていますし、阿弥陀仏は、立っておられます。
親鸞聖人は、『正信偈』に、「帰命無量寿如来、南無不可思議光、法蔵菩薩因位時・・・」と、正しい信心とはどういうものか、正しい信心をえなさいよ、と教えられているのです。
ここでは、正しい信心を表した蓮の花についての話をします。
もう一つ話しなければならないのは、正しい信心は、二つも三つもないということです。「正」という字は、見ておわかりのように、「一」に「止」と書きます。「一つに止まる」ということで、一つしかない、二つも三つもない、ということです。漢字というのはよくできていますね。
◎五つの特徴
大宇宙に一つしかない正しい信心を表したのが、蓮の花です。蓮の花には、五つの特徴があります。これを「蓮華の五徳(れんげのごとく)」といいます。百花繚乱と言われるように、いろいろな花がありますが、蓮の花には、五つの特徴があります。蓮華の五徳の「徳」は、特徴の「特」と同じです。蓮の花にしかない特徴が五つあります。それぞれ、蓮の花のどんな特徴か、また、それがどのように正しい信心の特徴を表しているのか、以下、解説をします。
◎淤泥不染(おでいふぜん)の徳
淤泥不染という特徴があります。これは、蓮の花の咲く場所の特徴を表したものです。蓮の花は、どんなところに咲いているでしょうか。みんなが嫌がるところ、近づきたくないところ、ドロドロしたところに咲いています。深い田んぼで、足を入れるとズブズブーと沈んで、片足を上げると、もう一方の足が沈み、その足を上げると、もう一方の足が沈み、にっちもさっちもいかなくなってしまうようなところ、そういうドロドロのドロ田に蓮の花は咲いています。
いわゆる高原陸地には咲きません。高原陸地とは、海抜何百メートルというところで、綺麗で、固くて、飛んだり跳ねたりできるところで、皆さんが好きなところです。蓮の花は、みんなが好きな高原陸地には咲かず、みんながおそれる、嫌がる、ドロドロのドロ田に咲きます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。淤泥とは、悪人のことを例えられています。高原陸地とは、淤泥の反対ですから、善人のことです。皆、悪人は、恐れますし、嫌いです。善人は、皆、好きです。蓮の花は、高原陸地には咲かない、淤泥に咲くとは、蓮の花のような正しい信心の花は、悪人の心に開くということです。善人様は後回しということです。
これを親鸞聖人は、「悪人正機(あくにんしょうき)」と教えられています。
◎悪人正機の教え
「正機」とは、正客ということです。悪人が正客であるということですが、これは、よく間違われているところです。それで、早く正しい信心をえるには、悪いことをやった方がよい。善人は、救われないと思っている人がありますが、そんなことを、親鸞聖人が言われているのではありません。
親鸞聖人は、悪人こそが正しい機(き)ざまである、本当の姿は、悪人であるということを言われています。善人様の心には、咲きません。蓮の花のような正しい信心は、悪人の淤泥の心に咲くことを教えられています。
悪人と知らされた人の心に真実の信心が徹底します。「正しい信心」を「真実の信心」といってもいいです。
悪人といっても、見方によっていろいろな悪人があります。
ちょうど手を見るにしても、肉眼で見るのと、虫眼鏡で見るのと、顕微鏡で見るのでは、違います。トイレから出て、「石鹸で手を洗いました」といっても、肉眼なら綺麗に見えますが、虫メガネで見ますと、少しは汚れが見えるでしょう。まして電子顕微鏡で見ると、バイ菌だらけです。
肉眼というのは、法律です。虫眼鏡というのは、倫理道徳です。そして顕微鏡というのは、仏教という法鏡です。「私は、法律を侵すようなことやっていない、警察の厄介になったことはないから、悪人ではない、善人だ」と思っています。また、倫理でも、「あの人よりはましだ」と思っています。しかし、微塵の悪も見逃さない仏教という顕微鏡で見ると、皆、悪人です。
◎機の深信
法鏡という顕微鏡で知らされた姿を、善導大師という方は、このように言われています。
「自身は、現に是、罪悪生死の凡夫、昿劫より已来、常に没し、常に流転して、出離の縁有ることなし」と深信す
これを「機の深信(きのじんしん)」といいます。「機」とは、私の姿、「深信」とは、ハッキリ知らされたということです。
そのような善導大師が、仏法というレントゲンにうつされた姿を知らされて、こうに言われています。「自身は、現に是、罪悪生死の凡夫、昿劫より已来、常に没し、常に流転して、出離の縁有ることなしと深信す」。「深信す」とは、このような姿であったと、ハッキリ知らされた、ということです。
ですから、私たちが「自分は善人だ」と思っているのは、完全な自惚れです。法律、倫理で見ているのです。手には、バイ菌がうようよしているのに、肉眼や虫メガネで見て、キレイだと思っているのです。顕微鏡で見えるバイ菌だらけの姿、すなわち、人間の姿を、このように言われているのです。
善導大師という方は、法律や倫理から見れば、百点満点、いや、三百満点というお方です。そのような善導大師が、仏教という法鏡、すなわち、真実の姿を映し出す鏡にうつれた姿を、そのように言われています。
善導大師は、仏教を求められ、法の鏡によって自分の姿が知らされました。私たちも、仏教を聞くということは、法の鏡に近づくということで、善導大師が御自身の姿を知らされたように、そこまで求めなければなりません。仏教を聞いていきますと、法の鏡によって、本当の自分の姿が知らされます。善導大師は、微塵の悪も見逃さない法鏡で、本当の自分の姿が知らされ、びっくりして言われた驚きの言葉が、上のお言葉です。
「自身は」とは、私は、ということです。他の人のことはわかりませんが、「この善導は、罪悪生死の凡夫である」ということです。
「罪悪生死の凡夫」ということですが、「罪悪」とは、罪ばかり造っている、悪ばかり造っている、ということ、「生死」とは、生まれては死に、生まれては死にと、迷いを重ねている、ということ、「凡夫」とは、人間ということです。
お釈迦様は、私たちの姿を、「心は常に悪を思い、口は常に悪を言い、身は常に悪を行って、いまだかって一つの善もない」と言われています(これについては真実の自己の講義参照)が、善導大師は、「お釈迦様の言われる通りであった、善導は、罪悪生死の凡夫であった、そういう情けない人間であった」と言われているということです。
「罪悪生死の凡夫」は、いつから始まったことかというと、「昿劫より已来」と言われています。「昿劫」とは、果てしない過去ということです。果てしない過去から罪悪生死の凡夫であったと知らされます。
次に「常に没し、常に流転して」ということですが、「常に没し」とは、常に沈没している、ということ、「常に流転して」とは、常に迷い続けている、ということです。
◎出離の縁有ること無し
ですから、「出離の縁有ることなし、と深信す」となります。「深信す」とは、ハッキリ知らされたということです。
「出離の縁有ることなし」と「出離の縁なし」の違いを、例えを使って、説明します。
ある人がお金を知り合いに借りに行きます。「どうか百万円、貸して下さい」と頼むと、友人に「わしの家には、百万円はないわ」と言われました。これは、今は百万円ないが、未来、百万円ある可能性があるという含みがあります。
しかし、先の例えで友人に「わしの家には、百万円は、あること無しだ」と言われたら、これは、今も無いし、これからも無いということになります。“有ること”が無いんですから。こんな友人にはいくら頼んでも仕方ありません。
これで「有ることなし」と「無し」の違いがわかりられたでしょうか。
ですから「出離の縁有ることなし」とは、永久に助かる縁手掛かりなし、金輪際、助かる縁手掛かりなし、ということになります。“ひょっとしたら、助かる”というものではありません。罪悪生死の凡夫ですから、地獄に堕ちて、当然なのです。金輪際、助かる縁手掛かりのない罪悪生死の凡夫であったとハッキリ知らされました、と善導大師は仰有っているのです。
善導大師がこのように知らされた時に、信心決定(しんじんけつじょう)なされました。ということは、正しい信心の花が開いた、正しい信心を頂かれた、ということです。その時の親鸞聖人のお言葉が『教行信証』に次のように仰有っています。
噫、弘誓の強縁は、多生にも値いがたく、真実の浄信は、億劫にも獲がたし。偶(たまたま)行信を獲ば遠く宿縁を慶べ。若しまたこの廻(たび)疑網(ぎもう)に覆蔽(ふくへい)せられなば更(かえ)りてまた昿劫を逕歴(きょうりゃく)せん。誠なるかなや、摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮することなかれ。
◎機法二種一具の深信
「機の深信」、すなわち、本当の私の姿が知らされた時に、「法の深信(ほうのじんしん)」が明らかに知らされます。
機の深信と、法の深信は、同時に知らされますので、これを「機法二種一具の深信(きほうにしゅいちぐのじんしん)」と言われます。
法の深信とは、阿弥陀仏の真実の御慈悲がハッキリ知らされたということで、衆生を摂受したまうこと、助けたまうことに疑いがないということです。
機の深信とは、堕ちるに疑いが晴れたこと、法の深信は、助かることに疑いが晴れたことです。これが、同時に知らされるので、機法二種一具の深信と言われます。“堕ちるに間違いなし”、そんな者を“助けるに間違いなし”と同時に知らされます。「一具」とは、同時ということです。
「私は、絶対に助かる縁手掛かりのない罪悪生死の凡夫でした」と知らされた人の心に、蓮の花のような正しい信心が開きます。
それまでは皆、自惚れています。何とかすれば、何とかなれると思っています。それが、助かる望みが断ち切られて、出離の縁有ることのない罪悪生死の凡夫であったと知らされた人の心に、正しい信心の花が開きます。それで、蓮の花が開くのは淤泥と教えています。高原陸地には、咲きません。
罪悪生死は、皆、恐れています。罪や悪を造れば、それで苦しみますから。そのような極悪人と知らされた人の心に、正しい信心の花が開きます。
自分は善人だ、あの人よりはましだ、何とかすれば何とかなれると思っている人は、善人様です。そういう人の心には、蓮の花のような正しいの信心の花は、開きません。蓮の花が高原陸地に咲かないように、そういう人の心に、正しい信心は咲きません。
善導大師のような方でも、「出離の縁有ることなし」と言われていますから、すべての人は、皆そうです。それなのに、「自分は善人だ」などと思っているのは、自惚れているからです。そんな人の心には、正しい信心の花は開きません。
次にいきます。淤泥不染の「不染」とは、染まらず、ということですが、これはどういうことでしょうか。蓮の花は、淤泥、すなわち、ドロドロのドロ田に咲きますが、そこに咲く蓮の花は、綺麗で、清らかで、ドロドロに汚れていません。
蓮の花のような正しい信心は、罪悪生死の凡夫であったと知らされた人の心に開きます。ところが罪悪生死は、正しい信心が起きてからも、変わりません。ちょうど、蓮の花が咲く前は、ドロドロだったのに、蓮の花が咲いたら、固い、セメントで固められたような陸地になったとか、そういうことはありません。正しい信心の花が咲いてからも、淤泥は淤泥のまま、変わりません。
もっといえば、罪悪生死とは、煩悩、煩悩具足ということです。煩悩とは、欲、怒り、愚痴の心などに代表される108の煩悩のことです。正しい信心の花が開けば、これの煩悩は、開く前よりは少なくなるだろうとか、罪や悪は余り造らなくなるだろう、と思いがちですが、そうではありません。欲や怒りの愚痴の心が少なくなって、108あった煩悩が、50ぐらいに減るのではないか、と思っていますが、そうではないのです。。
◎三毒の煩悩と真実の信心の関係
正しい信心の花が咲いても、煩悩は、なくなりません。それを善導大師は、どのように言われていますか。
衆生貪瞋煩悩中 能生清浄願往生心
「煩悩中」とは、煩悩の中に、罪悪生死の中に、欲や怒り、愚痴の中に、ということです。「衆生貪瞋煩悩中、能生清浄願往生心(しゅじょうとんじんぼんのうちゅう、のうしょうしょうじょうがんおうじょうしん)」とありますが、「能生清浄願往生心」とは、正しい信心の花が開く、ということです。
淤泥に蓮の花は開きますが、蓮の花が開く前も、開いた後も、淤泥は変わりません。そのように、蓮の花のような正しい信心が、煩悩、欲や怒りや愚痴の心に、開いても、煩悩や罪悪は、変わりません。正しい信心と、煩悩、これらの関係を、蓮の中は、淤泥不染と教えています。
世間の人の間違っている迷信を、蓮の花は、打ち破っています。「正しい信心はこうですよ。正しい信心の花が開いても、ドロドロのドロ田は、変わりませんよ。罪悪生死は変わりませんよ。煩悩は変わりませんよ」と教えているのです。
それをまた、覚如上人(かくにょしょうにん)は、このように教えられています。
三毒の煩悩は、しばしば起きれども、真実(まこと)の信心は、かれらにもさえられず、顛倒(てんどう)の妄念は、常に絶えざれども、更に未来の悪報をば、まねかず
蓮の花のような正しい信心の花が開いても、三毒の煩悩は、変わりません。「三毒の煩悩は、しばしば起きれども、真実の信心は、かれらにもさえられず」とは、三毒の煩悩がしばしば起きるけれども、真実の信心は、少しも汚されないんだ、ということです。「顛倒の妄念は、常に絶えざれども、更に未来の悪報をば、まねかず」とは、無常の命とは言われるけれどとてもそうは思えないという引っ繰り返った思い(顛倒の妄念)は、なくならないが、それによって、未来、地獄に堕ちるということは、ないんだと言うことです。
蓮の花が咲く前も咲いた後も、ドロドロのドロ田は変わりません。そのように、蓮の花のような正しい信心が開いても、罪悪、煩悩、かれらは、少しも変わりません。正しい信心が開く前も、開いてからも、罪悪生死の凡夫は、変わりません。
淤泥不染とは、正しい信心と、これらの関係を表しています。
(続く)
【蓮華の五徳】を通して
明らかにしたいと思います。
◎蓮華の五徳
今回は、蓮の花についてのお話です。
仏教と蓮の花は、大いに関係があります。仏様は、蓮の花の中に立っておられたり、また、座っておられます。仏様が立ったり、座ったりされているところは、蓮台です。また、極楽の絵を見ても、蓮の花が描かれています。タンポポやパンジーやダリヤなどの他の花は、ありません。蓮の花しかありません。このように、仏教では、蓮の花が描かれますが、蓮の花と仏教は、どういう関係があるのでしょうか。
蓮の花は、「正しい信心」を表しています。
浄土真宗の皆さんなら、朝晩勤行(おつとめ)されると思いますが、そのおつとめで読まれる『正信偈』は、親鸞聖人が書かれたものです。親鸞聖人は、今から約八百年前の方で、親鸞聖人の教えられたことは、唯一、全人類が救われる教えなので、親鸞聖人のことを、世界の光と言われます。親鸞聖人は、90才でお亡くなりになっていますが、その間、教えられたことは、「正しい信心」一つです。
◎正しい信心
私たちは、いろいろなものを信じています。言葉を換えれば、いろいろな信心をもっています。しかし、正しい信心でないと、幸せになれません。正しい信心でないと、人間に生まれてきてよかった、という幸せになれないぞ、と親鸞聖人は教えられています。
テレビのニュースなどで、「これを信じたら、お金が儲かる」と言われ信じたが、それが間違っていて、苦しんでいる人を見ますが、信じてはならないものを信じると、苦しまねばならない、泣かねばならない、幸せになれない、ということです。正しい信心でなければ、幸せになれません。
幸せになれないということは、救われない、ということです。正しい信心をえれば、救われますが、正しい信心をえなければ、助かりません。正しい信心をえた人は、この世も救われ、未来、後生も救われます。
蓮の花のような正しい信心を頂いた人は、死ねば仏になります。ですから、仏様は、蓮の花の上におられます。奈良の大仏は、蓮の花の上に座っていますし、阿弥陀仏は、立っておられます。
親鸞聖人は、『正信偈』に、「帰命無量寿如来、南無不可思議光、法蔵菩薩因位時・・・」と、正しい信心とはどういうものか、正しい信心をえなさいよ、と教えられているのです。
ここでは、正しい信心を表した蓮の花についての話をします。
もう一つ話しなければならないのは、正しい信心は、二つも三つもないということです。「正」という字は、見ておわかりのように、「一」に「止」と書きます。「一つに止まる」ということで、一つしかない、二つも三つもない、ということです。漢字というのはよくできていますね。
◎五つの特徴
大宇宙に一つしかない正しい信心を表したのが、蓮の花です。蓮の花には、五つの特徴があります。これを「蓮華の五徳(れんげのごとく)」といいます。百花繚乱と言われるように、いろいろな花がありますが、蓮の花には、五つの特徴があります。蓮華の五徳の「徳」は、特徴の「特」と同じです。蓮の花にしかない特徴が五つあります。それぞれ、蓮の花のどんな特徴か、また、それがどのように正しい信心の特徴を表しているのか、以下、解説をします。
◎淤泥不染(おでいふぜん)の徳
淤泥不染という特徴があります。これは、蓮の花の咲く場所の特徴を表したものです。蓮の花は、どんなところに咲いているでしょうか。みんなが嫌がるところ、近づきたくないところ、ドロドロしたところに咲いています。深い田んぼで、足を入れるとズブズブーと沈んで、片足を上げると、もう一方の足が沈み、その足を上げると、もう一方の足が沈み、にっちもさっちもいかなくなってしまうようなところ、そういうドロドロのドロ田に蓮の花は咲いています。
いわゆる高原陸地には咲きません。高原陸地とは、海抜何百メートルというところで、綺麗で、固くて、飛んだり跳ねたりできるところで、皆さんが好きなところです。蓮の花は、みんなが好きな高原陸地には咲かず、みんながおそれる、嫌がる、ドロドロのドロ田に咲きます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。淤泥とは、悪人のことを例えられています。高原陸地とは、淤泥の反対ですから、善人のことです。皆、悪人は、恐れますし、嫌いです。善人は、皆、好きです。蓮の花は、高原陸地には咲かない、淤泥に咲くとは、蓮の花のような正しい信心の花は、悪人の心に開くということです。善人様は後回しということです。
これを親鸞聖人は、「悪人正機(あくにんしょうき)」と教えられています。
◎悪人正機の教え
「正機」とは、正客ということです。悪人が正客であるということですが、これは、よく間違われているところです。それで、早く正しい信心をえるには、悪いことをやった方がよい。善人は、救われないと思っている人がありますが、そんなことを、親鸞聖人が言われているのではありません。
親鸞聖人は、悪人こそが正しい機(き)ざまである、本当の姿は、悪人であるということを言われています。善人様の心には、咲きません。蓮の花のような正しい信心は、悪人の淤泥の心に咲くことを教えられています。
悪人と知らされた人の心に真実の信心が徹底します。「正しい信心」を「真実の信心」といってもいいです。
悪人といっても、見方によっていろいろな悪人があります。
ちょうど手を見るにしても、肉眼で見るのと、虫眼鏡で見るのと、顕微鏡で見るのでは、違います。トイレから出て、「石鹸で手を洗いました」といっても、肉眼なら綺麗に見えますが、虫メガネで見ますと、少しは汚れが見えるでしょう。まして電子顕微鏡で見ると、バイ菌だらけです。
肉眼というのは、法律です。虫眼鏡というのは、倫理道徳です。そして顕微鏡というのは、仏教という法鏡です。「私は、法律を侵すようなことやっていない、警察の厄介になったことはないから、悪人ではない、善人だ」と思っています。また、倫理でも、「あの人よりはましだ」と思っています。しかし、微塵の悪も見逃さない仏教という顕微鏡で見ると、皆、悪人です。
◎機の深信
法鏡という顕微鏡で知らされた姿を、善導大師という方は、このように言われています。
「自身は、現に是、罪悪生死の凡夫、昿劫より已来、常に没し、常に流転して、出離の縁有ることなし」と深信す
これを「機の深信(きのじんしん)」といいます。「機」とは、私の姿、「深信」とは、ハッキリ知らされたということです。
そのような善導大師が、仏法というレントゲンにうつされた姿を知らされて、こうに言われています。「自身は、現に是、罪悪生死の凡夫、昿劫より已来、常に没し、常に流転して、出離の縁有ることなしと深信す」。「深信す」とは、このような姿であったと、ハッキリ知らされた、ということです。
ですから、私たちが「自分は善人だ」と思っているのは、完全な自惚れです。法律、倫理で見ているのです。手には、バイ菌がうようよしているのに、肉眼や虫メガネで見て、キレイだと思っているのです。顕微鏡で見えるバイ菌だらけの姿、すなわち、人間の姿を、このように言われているのです。
善導大師という方は、法律や倫理から見れば、百点満点、いや、三百満点というお方です。そのような善導大師が、仏教という法鏡、すなわち、真実の姿を映し出す鏡にうつれた姿を、そのように言われています。
善導大師は、仏教を求められ、法の鏡によって自分の姿が知らされました。私たちも、仏教を聞くということは、法の鏡に近づくということで、善導大師が御自身の姿を知らされたように、そこまで求めなければなりません。仏教を聞いていきますと、法の鏡によって、本当の自分の姿が知らされます。善導大師は、微塵の悪も見逃さない法鏡で、本当の自分の姿が知らされ、びっくりして言われた驚きの言葉が、上のお言葉です。
「自身は」とは、私は、ということです。他の人のことはわかりませんが、「この善導は、罪悪生死の凡夫である」ということです。
「罪悪生死の凡夫」ということですが、「罪悪」とは、罪ばかり造っている、悪ばかり造っている、ということ、「生死」とは、生まれては死に、生まれては死にと、迷いを重ねている、ということ、「凡夫」とは、人間ということです。
お釈迦様は、私たちの姿を、「心は常に悪を思い、口は常に悪を言い、身は常に悪を行って、いまだかって一つの善もない」と言われています(これについては真実の自己の講義参照)が、善導大師は、「お釈迦様の言われる通りであった、善導は、罪悪生死の凡夫であった、そういう情けない人間であった」と言われているということです。
「罪悪生死の凡夫」は、いつから始まったことかというと、「昿劫より已来」と言われています。「昿劫」とは、果てしない過去ということです。果てしない過去から罪悪生死の凡夫であったと知らされます。
次に「常に没し、常に流転して」ということですが、「常に没し」とは、常に沈没している、ということ、「常に流転して」とは、常に迷い続けている、ということです。
◎出離の縁有ること無し
ですから、「出離の縁有ることなし、と深信す」となります。「深信す」とは、ハッキリ知らされたということです。
「出離の縁有ることなし」と「出離の縁なし」の違いを、例えを使って、説明します。
ある人がお金を知り合いに借りに行きます。「どうか百万円、貸して下さい」と頼むと、友人に「わしの家には、百万円はないわ」と言われました。これは、今は百万円ないが、未来、百万円ある可能性があるという含みがあります。
しかし、先の例えで友人に「わしの家には、百万円は、あること無しだ」と言われたら、これは、今も無いし、これからも無いということになります。“有ること”が無いんですから。こんな友人にはいくら頼んでも仕方ありません。
これで「有ることなし」と「無し」の違いがわかりられたでしょうか。
ですから「出離の縁有ることなし」とは、永久に助かる縁手掛かりなし、金輪際、助かる縁手掛かりなし、ということになります。“ひょっとしたら、助かる”というものではありません。罪悪生死の凡夫ですから、地獄に堕ちて、当然なのです。金輪際、助かる縁手掛かりのない罪悪生死の凡夫であったとハッキリ知らされました、と善導大師は仰有っているのです。
善導大師がこのように知らされた時に、信心決定(しんじんけつじょう)なされました。ということは、正しい信心の花が開いた、正しい信心を頂かれた、ということです。その時の親鸞聖人のお言葉が『教行信証』に次のように仰有っています。
噫、弘誓の強縁は、多生にも値いがたく、真実の浄信は、億劫にも獲がたし。偶(たまたま)行信を獲ば遠く宿縁を慶べ。若しまたこの廻(たび)疑網(ぎもう)に覆蔽(ふくへい)せられなば更(かえ)りてまた昿劫を逕歴(きょうりゃく)せん。誠なるかなや、摂取不捨の真言、超世希有の正法、聞思して遅慮することなかれ。
◎機法二種一具の深信
「機の深信」、すなわち、本当の私の姿が知らされた時に、「法の深信(ほうのじんしん)」が明らかに知らされます。
機の深信と、法の深信は、同時に知らされますので、これを「機法二種一具の深信(きほうにしゅいちぐのじんしん)」と言われます。
法の深信とは、阿弥陀仏の真実の御慈悲がハッキリ知らされたということで、衆生を摂受したまうこと、助けたまうことに疑いがないということです。
機の深信とは、堕ちるに疑いが晴れたこと、法の深信は、助かることに疑いが晴れたことです。これが、同時に知らされるので、機法二種一具の深信と言われます。“堕ちるに間違いなし”、そんな者を“助けるに間違いなし”と同時に知らされます。「一具」とは、同時ということです。
「私は、絶対に助かる縁手掛かりのない罪悪生死の凡夫でした」と知らされた人の心に、蓮の花のような正しい信心が開きます。
それまでは皆、自惚れています。何とかすれば、何とかなれると思っています。それが、助かる望みが断ち切られて、出離の縁有ることのない罪悪生死の凡夫であったと知らされた人の心に、正しい信心の花が開きます。それで、蓮の花が開くのは淤泥と教えています。高原陸地には、咲きません。
罪悪生死は、皆、恐れています。罪や悪を造れば、それで苦しみますから。そのような極悪人と知らされた人の心に、正しい信心の花が開きます。
自分は善人だ、あの人よりはましだ、何とかすれば何とかなれると思っている人は、善人様です。そういう人の心には、蓮の花のような正しいの信心の花は、開きません。蓮の花が高原陸地に咲かないように、そういう人の心に、正しい信心は咲きません。
善導大師のような方でも、「出離の縁有ることなし」と言われていますから、すべての人は、皆そうです。それなのに、「自分は善人だ」などと思っているのは、自惚れているからです。そんな人の心には、正しい信心の花は開きません。
次にいきます。淤泥不染の「不染」とは、染まらず、ということですが、これはどういうことでしょうか。蓮の花は、淤泥、すなわち、ドロドロのドロ田に咲きますが、そこに咲く蓮の花は、綺麗で、清らかで、ドロドロに汚れていません。
蓮の花のような正しい信心は、罪悪生死の凡夫であったと知らされた人の心に開きます。ところが罪悪生死は、正しい信心が起きてからも、変わりません。ちょうど、蓮の花が咲く前は、ドロドロだったのに、蓮の花が咲いたら、固い、セメントで固められたような陸地になったとか、そういうことはありません。正しい信心の花が咲いてからも、淤泥は淤泥のまま、変わりません。
もっといえば、罪悪生死とは、煩悩、煩悩具足ということです。煩悩とは、欲、怒り、愚痴の心などに代表される108の煩悩のことです。正しい信心の花が開けば、これの煩悩は、開く前よりは少なくなるだろうとか、罪や悪は余り造らなくなるだろう、と思いがちですが、そうではありません。欲や怒りの愚痴の心が少なくなって、108あった煩悩が、50ぐらいに減るのではないか、と思っていますが、そうではないのです。。
◎三毒の煩悩と真実の信心の関係
正しい信心の花が咲いても、煩悩は、なくなりません。それを善導大師は、どのように言われていますか。
衆生貪瞋煩悩中 能生清浄願往生心
「煩悩中」とは、煩悩の中に、罪悪生死の中に、欲や怒り、愚痴の中に、ということです。「衆生貪瞋煩悩中、能生清浄願往生心(しゅじょうとんじんぼんのうちゅう、のうしょうしょうじょうがんおうじょうしん)」とありますが、「能生清浄願往生心」とは、正しい信心の花が開く、ということです。
淤泥に蓮の花は開きますが、蓮の花が開く前も、開いた後も、淤泥は変わりません。そのように、蓮の花のような正しい信心が、煩悩、欲や怒りや愚痴の心に、開いても、煩悩や罪悪は、変わりません。正しい信心と、煩悩、これらの関係を、蓮の中は、淤泥不染と教えています。
世間の人の間違っている迷信を、蓮の花は、打ち破っています。「正しい信心はこうですよ。正しい信心の花が開いても、ドロドロのドロ田は、変わりませんよ。罪悪生死は変わりませんよ。煩悩は変わりませんよ」と教えているのです。
それをまた、覚如上人(かくにょしょうにん)は、このように教えられています。
三毒の煩悩は、しばしば起きれども、真実(まこと)の信心は、かれらにもさえられず、顛倒(てんどう)の妄念は、常に絶えざれども、更に未来の悪報をば、まねかず
蓮の花のような正しい信心の花が開いても、三毒の煩悩は、変わりません。「三毒の煩悩は、しばしば起きれども、真実の信心は、かれらにもさえられず」とは、三毒の煩悩がしばしば起きるけれども、真実の信心は、少しも汚されないんだ、ということです。「顛倒の妄念は、常に絶えざれども、更に未来の悪報をば、まねかず」とは、無常の命とは言われるけれどとてもそうは思えないという引っ繰り返った思い(顛倒の妄念)は、なくならないが、それによって、未来、地獄に堕ちるということは、ないんだと言うことです。
蓮の花が咲く前も咲いた後も、ドロドロのドロ田は変わりません。そのように、蓮の花のような正しい信心が開いても、罪悪、煩悩、かれらは、少しも変わりません。正しい信心が開く前も、開いてからも、罪悪生死の凡夫は、変わりません。
淤泥不染とは、正しい信心と、これらの関係を表しています。
(続く)
|
|
|
|
コメント(8)
◎一茎一花(いっけいいっか)の徳
次に一茎一花の徳です。一茎一花の徳とは、“一つの茎に一つの花をつける”ということです。これは、蓮の花だけの特徴ではなくて、チューリップもそうです。世の中には、一つに茎に、いくつかの花をつけるものもありますが、蓮の花は、一つの茎に、一つの花をつけます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
蓮如上人は、「往生は一人一人のしのぎなり」と言われています。これは、“身代わりはきかない”ということです。例えば、夫婦のように、どんな密接な関係のある人でも、トイレに行きたいとき、「俺の代わりに行ってくれ」とは言えません。また、腹が減ったとき、「自分の代わりに、食事をしてくれ」とも言えません。代わりに食べてもらっても、自分のお腹は満腹になりません。トイレや食事でさえ、身代わりはきかないのですから、ましていわんや、正しい信心は、身代わりはきかないということです。「俺の代わりに、仏教を聞きに行ってくれ」といっても、身代わりはききません。代わりに聞きに行った人は、その人が法鏡に近づいて、その人の仏縁になり、やがて、信心決定して、極楽に往きます。代わりに行ってくれと言った人は、何にもなっていません。ですから、「一人一人のしのぎなり」と言われたのです。
これは、当然すぎることですが、これを誤解している人が、少なくありません。「親鸞聖人がご苦労して下されたから、私たちは、苦労して聞かなくてもよい」と言う人があります。親鸞聖人がご苦労して下されたから、私たちは、ただ聞いて、念仏さえ称えていたら、死ねば極楽へいけると思っています。それはとんでもない誤りです。
では、一茎一花ということと親鸞聖人のご苦労とは、どういう関係があるのでしょうか。
11月28日に、親鸞聖人がお亡くなりになられましたが、その頃に行われるのが、浄土真宗の「報恩講(ほうおんこう)」です。報恩講とは、“親鸞聖人の御恩に報いる集まり”ということです。親鸞聖人の御恩に報いる報恩講と、一茎一花ということは、どういう関係があるのでしょうか。
次に一茎一花の徳です。一茎一花の徳とは、“一つの茎に一つの花をつける”ということです。これは、蓮の花だけの特徴ではなくて、チューリップもそうです。世の中には、一つに茎に、いくつかの花をつけるものもありますが、蓮の花は、一つの茎に、一つの花をつけます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
蓮如上人は、「往生は一人一人のしのぎなり」と言われています。これは、“身代わりはきかない”ということです。例えば、夫婦のように、どんな密接な関係のある人でも、トイレに行きたいとき、「俺の代わりに行ってくれ」とは言えません。また、腹が減ったとき、「自分の代わりに、食事をしてくれ」とも言えません。代わりに食べてもらっても、自分のお腹は満腹になりません。トイレや食事でさえ、身代わりはきかないのですから、ましていわんや、正しい信心は、身代わりはきかないということです。「俺の代わりに、仏教を聞きに行ってくれ」といっても、身代わりはききません。代わりに聞きに行った人は、その人が法鏡に近づいて、その人の仏縁になり、やがて、信心決定して、極楽に往きます。代わりに行ってくれと言った人は、何にもなっていません。ですから、「一人一人のしのぎなり」と言われたのです。
これは、当然すぎることですが、これを誤解している人が、少なくありません。「親鸞聖人がご苦労して下されたから、私たちは、苦労して聞かなくてもよい」と言う人があります。親鸞聖人がご苦労して下されたから、私たちは、ただ聞いて、念仏さえ称えていたら、死ねば極楽へいけると思っています。それはとんでもない誤りです。
では、一茎一花ということと親鸞聖人のご苦労とは、どういう関係があるのでしょうか。
11月28日に、親鸞聖人がお亡くなりになられましたが、その頃に行われるのが、浄土真宗の「報恩講(ほうおんこう)」です。報恩講とは、“親鸞聖人の御恩に報いる集まり”ということです。親鸞聖人の御恩に報いる報恩講と、一茎一花ということは、どういう関係があるのでしょうか。
◎「一人一人のしのぎ」と「親鸞聖人のご苦労」の関係
親鸞聖人は、ご承知のように、4才の時に、お父さんを亡くされ、8才の時に、お母さんを亡くされ、「今度は自分の番だ、死んだ後は真っ暗だ」と、後生の一大事に驚かれました。それで、9才の時に、比叡山に入られ、天台宗の僧侶となられました。その時に、詠んだといわれる有名がお歌が、「明日ありと、思う心の仇(あだ)桜、夜半に嵐の吹かぬものかわ」という歌です。
親鸞聖人は、9才の時に比叡山に入り、大曼(だいまん)の修行までなされ、大変ご苦労されました。親鸞聖人が我が身の後生の一大事の解決の為、自分の魂の解決の為になされたのです。そののち、親鸞聖人は、建仁元年(聖人29才のとき)に、「誠なるかなや、摂取不捨の真言」と仰有り、阿弥陀仏の本願まことだった、と叫ばれました。信心決定なされたのです。そして29才から90才までの61年間、私たちを導かんが為にご苦労されました。
ある時は日野左衛門という男の門前で、石を枕に、雪を褥(しとね)に、ご苦労されました。また、ある時は山伏弁円を済度なさるなど、親鸞聖人は、いろいろとご苦労されていますが、これらは、ひとえに私たちの為です。
これは、どういうことなのか、山登りを例に考えてみましょう。「笠あげて、道連れ招く、清水かな」という歌があります。
親鸞聖人が山を登って行かれました。頂上が、後生の一大事の解決です。一緒にたくさんの人が登って行きましたが、喉が渇いて、「もう登れない」と言ってバタバタ倒れる人が出てきました。親鸞聖人は、そういう人たちに、“もう少しだから、頑張ろう”と呼びかけられましたが、やがて、また一人、また一人と、倒れていき、とうとう親鸞聖人お一人しか登って行く人がいなくなってしまいました。そしてその親鸞聖人も、喉が渇き、もう登ることができないと、バッタリ倒れてしまいました。その時が「いづれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされた時です。と同時に倒れたところに滾々と湧き出るつめたーい清水があって、それをガブガブっと飲まれ、親鸞一人が為の清水であった、と阿弥陀仏の本願の清水によって無碍の一道へ出ておられるのです。
親鸞聖人の9才から29才までのご苦労は、自分の後生の一大事の解決の為です。そこまで登らないと、清水は飲めません。そして、「いづれの行も及び難き親鸞、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされたと同時に、「親鸞一人が為の清水であった」と、阿弥陀仏の本願の水を飲まれておられます。
それから90才までの61年間のご苦労は、「早く親鸞と同じような身になってくれ、早く親鸞と同じように救われてくれ」と叫んでおられるご苦労です。山登りで言えば、下で倒れている仲間たちに「おーい、ここに、おいしい清水があるぞ、そこまで頑張れ、そこまで進め」と呼びかけておられるのです。
その御恩に報いるのが報恩講であります。
だから、「親鸞聖人がご苦労されたんだから」とか言って、居眠りしながら聞いていても、救われません。「往生は一人一人のしのぎ」です。身代わりはきかないということを、蓮の花は、一茎一花の徳で教えています。
(続く)
親鸞聖人は、ご承知のように、4才の時に、お父さんを亡くされ、8才の時に、お母さんを亡くされ、「今度は自分の番だ、死んだ後は真っ暗だ」と、後生の一大事に驚かれました。それで、9才の時に、比叡山に入られ、天台宗の僧侶となられました。その時に、詠んだといわれる有名がお歌が、「明日ありと、思う心の仇(あだ)桜、夜半に嵐の吹かぬものかわ」という歌です。
親鸞聖人は、9才の時に比叡山に入り、大曼(だいまん)の修行までなされ、大変ご苦労されました。親鸞聖人が我が身の後生の一大事の解決の為、自分の魂の解決の為になされたのです。そののち、親鸞聖人は、建仁元年(聖人29才のとき)に、「誠なるかなや、摂取不捨の真言」と仰有り、阿弥陀仏の本願まことだった、と叫ばれました。信心決定なされたのです。そして29才から90才までの61年間、私たちを導かんが為にご苦労されました。
ある時は日野左衛門という男の門前で、石を枕に、雪を褥(しとね)に、ご苦労されました。また、ある時は山伏弁円を済度なさるなど、親鸞聖人は、いろいろとご苦労されていますが、これらは、ひとえに私たちの為です。
これは、どういうことなのか、山登りを例に考えてみましょう。「笠あげて、道連れ招く、清水かな」という歌があります。
親鸞聖人が山を登って行かれました。頂上が、後生の一大事の解決です。一緒にたくさんの人が登って行きましたが、喉が渇いて、「もう登れない」と言ってバタバタ倒れる人が出てきました。親鸞聖人は、そういう人たちに、“もう少しだから、頑張ろう”と呼びかけられましたが、やがて、また一人、また一人と、倒れていき、とうとう親鸞聖人お一人しか登って行く人がいなくなってしまいました。そしてその親鸞聖人も、喉が渇き、もう登ることができないと、バッタリ倒れてしまいました。その時が「いづれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされた時です。と同時に倒れたところに滾々と湧き出るつめたーい清水があって、それをガブガブっと飲まれ、親鸞一人が為の清水であった、と阿弥陀仏の本願の清水によって無碍の一道へ出ておられるのです。
親鸞聖人の9才から29才までのご苦労は、自分の後生の一大事の解決の為です。そこまで登らないと、清水は飲めません。そして、「いづれの行も及び難き親鸞、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされたと同時に、「親鸞一人が為の清水であった」と、阿弥陀仏の本願の水を飲まれておられます。
それから90才までの61年間のご苦労は、「早く親鸞と同じような身になってくれ、早く親鸞と同じように救われてくれ」と叫んでおられるご苦労です。山登りで言えば、下で倒れている仲間たちに「おーい、ここに、おいしい清水があるぞ、そこまで頑張れ、そこまで進め」と呼びかけておられるのです。
その御恩に報いるのが報恩講であります。
だから、「親鸞聖人がご苦労されたんだから」とか言って、居眠りしながら聞いていても、救われません。「往生は一人一人のしのぎ」です。身代わりはきかないということを、蓮の花は、一茎一花の徳で教えています。
(続く)
◎「一人一人のしのぎ」と「親鸞聖人のご苦労」の関係
親鸞聖人は、ご承知のように、4才の時に、お父さんを亡くされ、8才の時に、お母さんを亡くされ、「今度は自分の番だ、死んだ後は真っ暗だ」と、後生の一大事に驚かれました。それで、9才の時に、比叡山に入られ、天台宗の僧侶となられました。その時に、詠んだといわれる有名がお歌が、「明日ありと、思う心の仇(あだ)桜、夜半に嵐の吹かぬものかわ」という歌です。
親鸞聖人は、9才の時に比叡山に入り、大曼(だいまん)の修行までなされ、大変ご苦労されました。親鸞聖人が我が身の後生の一大事の解決の為、自分の魂の解決の為になされたのです。そののち、親鸞聖人は、建仁元年(聖人29才のとき)に、「誠なるかなや、摂取不捨の真言」と仰有り、阿弥陀仏の本願まことだった、と叫ばれました。信心決定なされたのです。そして29才から90才までの61年間、私たちを導かんが為にご苦労されました。
ある時は日野左衛門という男の門前で、石を枕に、雪を褥(しとね)に、ご苦労されました。また、ある時は山伏弁円を済度なさるなど、親鸞聖人は、いろいろとご苦労されていますが、これらは、ひとえに私たちの為です。
これは、どういうことなのか、山登りを例に考えてみましょう。「笠あげて、道連れ招く、清水かな」という歌があります。
親鸞聖人が山を登って行かれました。頂上が、後生の一大事の解決です。一緒にたくさんの人が登って行きましたが、喉が渇いて、「もう登れない」と言ってバタバタ倒れる人が出てきました。親鸞聖人は、そういう人たちに、“もう少しだから、頑張ろう”と呼びかけられましたが、やがて、また一人、また一人と、倒れていき、とうとう親鸞聖人お一人しか登って行く人がいなくなってしまいました。そしてその親鸞聖人も、喉が渇き、もう登ることができないと、バッタリ倒れてしまいました。その時が「いづれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされた時です。と同時に倒れたところに滾々と湧き出るつめたーい清水があって、それをガブガブっと飲まれ、親鸞一人が為の清水であった、と阿弥陀仏の本願の清水によって無碍の一道へ出ておられるのです。
親鸞聖人の9才から29才までのご苦労は、自分の後生の一大事の解決の為です。そこまで登らないと、清水は飲めません。そして、「いづれの行も及び難き親鸞、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされたと同時に、「親鸞一人が為の清水であった」と、阿弥陀仏の本願の水を飲まれておられます。
それから90才までの61年間のご苦労は、「早く親鸞と同じような身になってくれ、早く親鸞と同じように救われてくれ」と叫んでおられるご苦労です。山登りで言えば、下で倒れている仲間たちに「おーい、ここに、おいしい清水があるぞ、そこまで頑張れ、そこまで進め」と呼びかけておられるのです。
その御恩に報いるのが報恩講であります。
だから、「親鸞聖人がご苦労されたんだから」とか言って、居眠りしながら聞いていても、救われません。「往生は一人一人のしのぎ」です。身代わりはきかないということを、蓮の花は、一茎一花の徳で教えています。
(続く)
親鸞聖人は、ご承知のように、4才の時に、お父さんを亡くされ、8才の時に、お母さんを亡くされ、「今度は自分の番だ、死んだ後は真っ暗だ」と、後生の一大事に驚かれました。それで、9才の時に、比叡山に入られ、天台宗の僧侶となられました。その時に、詠んだといわれる有名がお歌が、「明日ありと、思う心の仇(あだ)桜、夜半に嵐の吹かぬものかわ」という歌です。
親鸞聖人は、9才の時に比叡山に入り、大曼(だいまん)の修行までなされ、大変ご苦労されました。親鸞聖人が我が身の後生の一大事の解決の為、自分の魂の解決の為になされたのです。そののち、親鸞聖人は、建仁元年(聖人29才のとき)に、「誠なるかなや、摂取不捨の真言」と仰有り、阿弥陀仏の本願まことだった、と叫ばれました。信心決定なされたのです。そして29才から90才までの61年間、私たちを導かんが為にご苦労されました。
ある時は日野左衛門という男の門前で、石を枕に、雪を褥(しとね)に、ご苦労されました。また、ある時は山伏弁円を済度なさるなど、親鸞聖人は、いろいろとご苦労されていますが、これらは、ひとえに私たちの為です。
これは、どういうことなのか、山登りを例に考えてみましょう。「笠あげて、道連れ招く、清水かな」という歌があります。
親鸞聖人が山を登って行かれました。頂上が、後生の一大事の解決です。一緒にたくさんの人が登って行きましたが、喉が渇いて、「もう登れない」と言ってバタバタ倒れる人が出てきました。親鸞聖人は、そういう人たちに、“もう少しだから、頑張ろう”と呼びかけられましたが、やがて、また一人、また一人と、倒れていき、とうとう親鸞聖人お一人しか登って行く人がいなくなってしまいました。そしてその親鸞聖人も、喉が渇き、もう登ることができないと、バッタリ倒れてしまいました。その時が「いづれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされた時です。と同時に倒れたところに滾々と湧き出るつめたーい清水があって、それをガブガブっと飲まれ、親鸞一人が為の清水であった、と阿弥陀仏の本願の清水によって無碍の一道へ出ておられるのです。
親鸞聖人の9才から29才までのご苦労は、自分の後生の一大事の解決の為です。そこまで登らないと、清水は飲めません。そして、「いづれの行も及び難き親鸞、とても地獄は一定すみかぞかし」と知らされたと同時に、「親鸞一人が為の清水であった」と、阿弥陀仏の本願の水を飲まれておられます。
それから90才までの61年間のご苦労は、「早く親鸞と同じような身になってくれ、早く親鸞と同じように救われてくれ」と叫んでおられるご苦労です。山登りで言えば、下で倒れている仲間たちに「おーい、ここに、おいしい清水があるぞ、そこまで頑張れ、そこまで進め」と呼びかけておられるのです。
その御恩に報いるのが報恩講であります。
だから、「親鸞聖人がご苦労されたんだから」とか言って、居眠りしながら聞いていても、救われません。「往生は一人一人のしのぎ」です。身代わりはきかないということを、蓮の花は、一茎一花の徳で教えています。
(続く)
◎花果同時(かかどうじ)の徳
次に、花果同時の徳です。これは、蓮の花には、五つの特徴がありますが、特に花果同時の徳は、蓮の花ならではの特徴です。
花果同時の徳とは、花と実が同時にできるということで、蓮の花は、バサッといって、開きます。蓮の花がバサッと開く音を、ラジオなどで聞いたことがある人もあると思います。蓮花の近くにマイクを置いて、音を拾うと、バサッと聞こえるのでしょう。そのように、蓮の花は、バサッと一時に開きます。
他の花は違います。一番わかりやすいのは、桜です。今日の桜は二部咲きだなぁ、とか、今日は五部咲きだ、とか、今日は七部咲き、八部咲きなどと言います。そして、今日は満開だ、と言います。これは、桜の花は少しずつ開く、ということです。ところが蓮の花は、バサッと一度に、開きます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
蓮の花のような正しい信心は、“一念で開く”ということです。一念で正しい信心の花は開きます。
「一念」とはどういうことでしょうか。親鸞聖人は、このように言われています。
一念とは、是れ、信楽開発(しんぎょうかいほつ)の時尅の極促を顕す
これは、親鸞聖人が書かれた『教行信証』の信巻に書かれています。「信楽開発」とは、心が晴れて大満足、ということで、人間に生まれてこなければよかったという不足の心が、人間に生まれてきてよかったという大満足の心になることです。「開発」とは、「起きる」ということです。これを、「信心決定(しんじんけつじょう)」ともいいます。「時尅の極促」とは、「極促」は、これ以上短い時間はないということですから、時間のきわまりということです。「一念」とは、何億分の一秒よりも短い時間、正しい信心の花は、何億分の一秒よりも短い時間で開くのです。
他の宗教では、「私は、○○教を3年信じています」とか、「私は、××教を4年信じています」とか言いますが、正しい信心は、そんな信心とは違います。それらの宗教は、幸せが来なければ、「それはまだ信心が足りんからだ。もっと信心しなさい」と言ったりしますが、そういう足したり、引いたりできるような信心は、正しい信心ではありません。それは、迷信、邪教の信心です。
信楽開発の時尅の極促を顕す一念でおきる信心、それが正しい信心です。それを教えているのが蓮の花なのです。
他の宗教などは、いつとはなしの信心ですから、正しい信心ではありません。
(続く)
次に、花果同時の徳です。これは、蓮の花には、五つの特徴がありますが、特に花果同時の徳は、蓮の花ならではの特徴です。
花果同時の徳とは、花と実が同時にできるということで、蓮の花は、バサッといって、開きます。蓮の花がバサッと開く音を、ラジオなどで聞いたことがある人もあると思います。蓮花の近くにマイクを置いて、音を拾うと、バサッと聞こえるのでしょう。そのように、蓮の花は、バサッと一時に開きます。
他の花は違います。一番わかりやすいのは、桜です。今日の桜は二部咲きだなぁ、とか、今日は五部咲きだ、とか、今日は七部咲き、八部咲きなどと言います。そして、今日は満開だ、と言います。これは、桜の花は少しずつ開く、ということです。ところが蓮の花は、バサッと一度に、開きます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
蓮の花のような正しい信心は、“一念で開く”ということです。一念で正しい信心の花は開きます。
「一念」とはどういうことでしょうか。親鸞聖人は、このように言われています。
一念とは、是れ、信楽開発(しんぎょうかいほつ)の時尅の極促を顕す
これは、親鸞聖人が書かれた『教行信証』の信巻に書かれています。「信楽開発」とは、心が晴れて大満足、ということで、人間に生まれてこなければよかったという不足の心が、人間に生まれてきてよかったという大満足の心になることです。「開発」とは、「起きる」ということです。これを、「信心決定(しんじんけつじょう)」ともいいます。「時尅の極促」とは、「極促」は、これ以上短い時間はないということですから、時間のきわまりということです。「一念」とは、何億分の一秒よりも短い時間、正しい信心の花は、何億分の一秒よりも短い時間で開くのです。
他の宗教では、「私は、○○教を3年信じています」とか、「私は、××教を4年信じています」とか言いますが、正しい信心は、そんな信心とは違います。それらの宗教は、幸せが来なければ、「それはまだ信心が足りんからだ。もっと信心しなさい」と言ったりしますが、そういう足したり、引いたりできるような信心は、正しい信心ではありません。それは、迷信、邪教の信心です。
信楽開発の時尅の極促を顕す一念でおきる信心、それが正しい信心です。それを教えているのが蓮の花なのです。
他の宗教などは、いつとはなしの信心ですから、正しい信心ではありません。
(続く)
◎花と実が同時にできる
花果同時の徳とは、花と実が一念で同時にできるということですが、これは、蓮の花だけにある特徴です。蓮の花には、五つの特徴がありますが、一番の特徴が、花果同時です。花と実が同時にできるのは、蓮の花だけです。他の花は、花が咲いて、おしべとめしべが結合して、花が散ってから、実ができます。ですから、花ができるのと、実ができるのに、時間のズレがあります。しかし、蓮の花は、花と実が同時にできます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
正しい信心を頂いた一念で、無上の幸福を頂くということです。実とは、利益のことで、利益とは、幸福のことです。正しい信心を頂いた一念で、利益、幸福、人間に生まれてきてよかったという幸せの身になります。他の宗教は、これを信仰すれば、やがて幸せになれる。信心が足りないぞとか、もっと信心しなさいとか、そういうことを言います。ですが、正しい信心は一念で無上の幸福を頂きますので、足すものも引くものもありません。
◎一念往生の教え
また、花果同時ですから、生きている今、無上の幸福を頂きます。これを親鸞聖人は、「一念往生」と言われています。一念で、往生、生きている今、絶対の幸福に生かされて、往きます。浄土真宗の人は「死んだらお助け、死んだらお助け」と思っている人ばかりですが、蓮の花は、死んだらお助けではないぞ、と教えています。花と果が同時にできるように、正しい信心を頂くと同時に、無上の幸福になると教えています。幸福になるとは、救われるということですから、死んだら救われるのではなく、生きている今、無上の幸福、救われるのだ、ということです。
そして、今救われた者は、死ぬと同時に往生します。この「往生」は、一念往生の「往生」とは、違います。“往って生まれる”ということで、阿弥陀仏の極楽へ往って、生まれるということです。一念往生の「往生」は、一念で、無碍の一道へ生かされて往くということです。
正しい信心をえた時に、利益をえます。利益とは、今日の言葉でいうと、喜び、幸福、満足です。無上の幸福、無碍の一道へ出ます。「念仏者は無碍の一道なり」と『歎異鈔』にありますが、「念仏者」とは、「正しい信心をえた人」のことです。正しい信心をえた人は、「無碍の一道」へ出るんだ、と教えられています。
花果同時の徳とは、花と実が一念で同時にできるということですが、これは、蓮の花だけにある特徴です。蓮の花には、五つの特徴がありますが、一番の特徴が、花果同時です。花と実が同時にできるのは、蓮の花だけです。他の花は、花が咲いて、おしべとめしべが結合して、花が散ってから、実ができます。ですから、花ができるのと、実ができるのに、時間のズレがあります。しかし、蓮の花は、花と実が同時にできます。
これは、正しい信心の何を表しているのでしょうか。
正しい信心を頂いた一念で、無上の幸福を頂くということです。実とは、利益のことで、利益とは、幸福のことです。正しい信心を頂いた一念で、利益、幸福、人間に生まれてきてよかったという幸せの身になります。他の宗教は、これを信仰すれば、やがて幸せになれる。信心が足りないぞとか、もっと信心しなさいとか、そういうことを言います。ですが、正しい信心は一念で無上の幸福を頂きますので、足すものも引くものもありません。
◎一念往生の教え
また、花果同時ですから、生きている今、無上の幸福を頂きます。これを親鸞聖人は、「一念往生」と言われています。一念で、往生、生きている今、絶対の幸福に生かされて、往きます。浄土真宗の人は「死んだらお助け、死んだらお助け」と思っている人ばかりですが、蓮の花は、死んだらお助けではないぞ、と教えています。花と果が同時にできるように、正しい信心を頂くと同時に、無上の幸福になると教えています。幸福になるとは、救われるということですから、死んだら救われるのではなく、生きている今、無上の幸福、救われるのだ、ということです。
そして、今救われた者は、死ぬと同時に往生します。この「往生」は、一念往生の「往生」とは、違います。“往って生まれる”ということで、阿弥陀仏の極楽へ往って、生まれるということです。一念往生の「往生」は、一念で、無碍の一道へ生かされて往くということです。
正しい信心をえた時に、利益をえます。利益とは、今日の言葉でいうと、喜び、幸福、満足です。無上の幸福、無碍の一道へ出ます。「念仏者は無碍の一道なり」と『歎異鈔』にありますが、「念仏者」とは、「正しい信心をえた人」のことです。正しい信心をえた人は、「無碍の一道」へ出るんだ、と教えられています。
◎一花多果(いっかたか)の徳
次に、一花多果の徳です。「一花多果」とは、一つの花に多くの実をつけるということです。これは、蓮の花だけにある特徴とは言えないかもしれませんが、蓮の花は、たくさんの実をつけます。一花とは、今まで述べてきたように、正しい信心です。多果とは、限りなき幸福ということです。正しい信心を頂けば、限りなき幸福を頂く身になれるということを、表しています。
これを、親鸞聖人は、どのように教えられていますか。
五濁悪世の有情の
選択本願信ずれば
不可称不可説不可思議の
功徳は行者の身にみてり
(正像末和讃)
「五濁悪世(ごじょくあくせ)の有情(うじょう)」とは、「五濁悪世」、濁った悪い世、とありますが、今日のような世の中のことです。孫がお爺さん、お婆さんを殺したり、子供が親を殺したり、妻が夫を殺したり、埋めたり、反対に夫が妻を殺したり、埋めたりするこんにちの世の中です。自殺者は、日本で三万人を超え、交通事故で死ぬ人の何倍という数にのぼります。また、核兵器を造って、いつ全人類が滅亡するかわかりません。“終末時計が早められた”とかなんとか言われますが、五十年前、百年前には、考えられなかったような恐ろしいことが起きています。こういう現在を、五濁悪世と言われます。「有情」とは、「なさけあるもの」ということで人間のことです。
五濁悪世の有情が、「選択本願(せんじゃくほんがん)信ずれば」とありますが、「選択本願」とは、阿弥陀仏の本願のことで、阿弥陀仏の本願を信ずれば、ということです。親鸞聖人は、“正しい信心とは、阿弥陀仏の本願を信ずることである”と教えられています。選択本願信ずれば、すなわち、正しい信心をもてば、「不可称不可説不可思議の功徳」が行者の身にみちる、と言われています。「不可称」とは、「言うことができない」、「不可説」とは、「説くことができない」、「不可思議」とは、「思議することもできない」ということです。思議するべからず、説くべからず、言うべからず、これが「不可称不可説不可思議」ということです。「功徳」とは、利益、幸福のことです。「行者ぎょうじゃ」」とは、選択本願を信じた人です。
ですから「不可称不可説不可思議の功徳は行者の身のみてり」で、正しい信心をえた人は不可称不可説不可思議の功徳が身に満ちるんだ、ということです。そして、そのお礼で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と称えるのです。
(続く)
次に、一花多果の徳です。「一花多果」とは、一つの花に多くの実をつけるということです。これは、蓮の花だけにある特徴とは言えないかもしれませんが、蓮の花は、たくさんの実をつけます。一花とは、今まで述べてきたように、正しい信心です。多果とは、限りなき幸福ということです。正しい信心を頂けば、限りなき幸福を頂く身になれるということを、表しています。
これを、親鸞聖人は、どのように教えられていますか。
五濁悪世の有情の
選択本願信ずれば
不可称不可説不可思議の
功徳は行者の身にみてり
(正像末和讃)
「五濁悪世(ごじょくあくせ)の有情(うじょう)」とは、「五濁悪世」、濁った悪い世、とありますが、今日のような世の中のことです。孫がお爺さん、お婆さんを殺したり、子供が親を殺したり、妻が夫を殺したり、埋めたり、反対に夫が妻を殺したり、埋めたりするこんにちの世の中です。自殺者は、日本で三万人を超え、交通事故で死ぬ人の何倍という数にのぼります。また、核兵器を造って、いつ全人類が滅亡するかわかりません。“終末時計が早められた”とかなんとか言われますが、五十年前、百年前には、考えられなかったような恐ろしいことが起きています。こういう現在を、五濁悪世と言われます。「有情」とは、「なさけあるもの」ということで人間のことです。
五濁悪世の有情が、「選択本願(せんじゃくほんがん)信ずれば」とありますが、「選択本願」とは、阿弥陀仏の本願のことで、阿弥陀仏の本願を信ずれば、ということです。親鸞聖人は、“正しい信心とは、阿弥陀仏の本願を信ずることである”と教えられています。選択本願信ずれば、すなわち、正しい信心をもてば、「不可称不可説不可思議の功徳」が行者の身にみちる、と言われています。「不可称」とは、「言うことができない」、「不可説」とは、「説くことができない」、「不可思議」とは、「思議することもできない」ということです。思議するべからず、説くべからず、言うべからず、これが「不可称不可説不可思議」ということです。「功徳」とは、利益、幸福のことです。「行者ぎょうじゃ」」とは、選択本願を信じた人です。
ですから「不可称不可説不可思議の功徳は行者の身のみてり」で、正しい信心をえた人は不可称不可説不可思議の功徳が身に満ちるんだ、ということです。そして、そのお礼で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と称えるのです。
(続く)
◎中虚外直(ちゅうこげちょく)の徳
5番目は、中虚外直の徳です。今までの4つは、花の特徴でしたが、これは、茎の特徴です。蓮の花の茎は、蓮根のように、小さな穴がたくさんあります。それが「中虚」ということです。竹のようではなくて、小さな穴がたくさんあります。
全部、埋まっていた方が強いように思えますが、穴がある方が強いです。正しい信心、真実の信心、他力の信心を頂いている人は、いざという時は、大変強い、ということです。
それに対して、自力の信心、正しい信心でない信心は、強そうで弱いです。
これも例えで言いますと、強そうで弱いのは、「歯」です。歯は強そうですが、欠けたり、抜けたりします。ですから、歯抜け爺さんや、歯抜け婆さんがいます。
反対に、弱そうで強いのが「舌」です。舌は、やわらかく、弱そうですが、いつになっても、元気に動いています。ですから、舌抜け婆さんや、舌抜け爺さんはいません。年齢が増えれば増えるほど舌が元気になる、とさえ感じます。
正しい信心をえた人は、弱そうですが、大変強い、それが中虚ということです。
「外直」とは、真っ直ぐということです。蓮の花は曲がっていません。これは、正しい信心をえた人は、真っ直ぐに生きよ、曲がってはならないということです。
このように、蓮の花は、正しい信心を教えられています。
5番目は、中虚外直の徳です。今までの4つは、花の特徴でしたが、これは、茎の特徴です。蓮の花の茎は、蓮根のように、小さな穴がたくさんあります。それが「中虚」ということです。竹のようではなくて、小さな穴がたくさんあります。
全部、埋まっていた方が強いように思えますが、穴がある方が強いです。正しい信心、真実の信心、他力の信心を頂いている人は、いざという時は、大変強い、ということです。
それに対して、自力の信心、正しい信心でない信心は、強そうで弱いです。
これも例えで言いますと、強そうで弱いのは、「歯」です。歯は強そうですが、欠けたり、抜けたりします。ですから、歯抜け爺さんや、歯抜け婆さんがいます。
反対に、弱そうで強いのが「舌」です。舌は、やわらかく、弱そうですが、いつになっても、元気に動いています。ですから、舌抜け婆さんや、舌抜け爺さんはいません。年齢が増えれば増えるほど舌が元気になる、とさえ感じます。
正しい信心をえた人は、弱そうですが、大変強い、それが中虚ということです。
「外直」とは、真っ直ぐということです。蓮の花は曲がっていません。これは、正しい信心をえた人は、真っ直ぐに生きよ、曲がってはならないということです。
このように、蓮の花は、正しい信心を教えられています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
★親鸞聖人★ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
★親鸞聖人★のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人