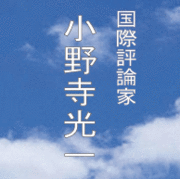また大阪市議選で振替不正選挙が行われたらしい。不自然な選挙結果である。
山形市長選挙の不正選挙の異議申し立ては山形市の方は特に今日提出していただきたい。
山形市の方は、本日山形市役所に届ければいい。異議申し立ては無料である。住所電話も書き加えておいていただきたい。
(とりあえず提出であとからでもいいが)提出できた人は私に連絡をください。
間に合わないとか県外の人に限りFAXでもいいと思われる。
なぜなら全国の人に関係するからである。
落選者にも説得していただきたい。不正選挙があるかぎり明日はない。
以下は参考にしていただきたい。
<訴状>
東京地方裁判所御中
被告 安倍晋三内閣総理大臣
(又は安全保障法案に賛成した国会議員氏名)
原告
住所
電話番号
氏名
<安全保障法案の違憲無効および委員会採決無効の確認訴訟>
請求の趣旨
平成27年9月17日安全保障関連法案の参議院委員会採決は違憲無効である。
この違憲法案の強引な虚偽成立により市民の平和的生存権が侵害されて多大な精神的苦痛をこうむった。原告一人あたり10万円の損害賠償に該当する。
予備的主張として安全保障法案自体および制定手続きは違憲であるという宣言を
求める。
請求の理由
混乱の中で行われた安全保障関連法の参院平和安全法制特別委員会での採決は、
速記録に「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」と書かれており、採決自体が存在してい
なかった。このことは、憲法第31条の「適正手続きの保障」が行政に及ぶこと
に違反する。また参議院規則第49条 第136条 第137条に違反する
ものである。
したがって平成27年9月17日の安全保障法案の参議院委員会採決は、
違憲無効である。したがってそのあとの本会議採決も無効である。
法案の内容自体も違憲無効であり、その採決の手続き自体も違憲違法により
無効である。
安保関連法案の採決不存在の確認
参議院に設置された「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(以下「特
別委」)は、2015年9月17日、同特別委に審議を付託された安保関連法案等計5件の採決を
行い、いずれも賛成多数で可決されたと虚偽の主張を行っている。
採決が行われたとされる、同日16時30分頃の委員会室の模様を参議院のインターネット中
継やテレビの中継・録画で視ると、鴻池委員長席の周囲は与野党議員によって何重にも取
り囲まれ、委員長の議事進行の声を委員が聴き取れる状況になかったことは明らかである。
また、各議員に取り囲まれて、委員長も動議提出の声を聴き取り、各委員の起立を確認でき
る状況になかったことは明らかである。
参議院規則「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する」(第
136条)、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立
者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する」(第137条)との定めは、
委員会審議については「議長」を「委員長」と読み替えて理解すべきであるが、一連の事実
と状況に照らせば、上記5件の「採決」なるものは、表決の要件を充たしていないことが明
らかである。
なお、同規則49条は、委員会審議に関して136条と同様の定めをし、参議院委員会先例録第
2章第9節・155には、「採決は、挙手又は起立の方法によるのを例とする」との表題で、
「委員会における採決は、挙手又は起立の方法によるのを例とするが、異議の有無を諮(は
か)ってこれを行った例も多い。挙手又は起立により採決するときは、委員長は、
問題を可とする者を挙手又は起立させ、挙手又は起立者の多少を認定して可否の結果を宣告
する。なお、記名投票によった…例もある」とされている。
いずれにせよ、今回の「採決」なるものが表決の要件を充たしていないことは明らかであ
る。
十八日に出された未定稿の速記録では、「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」としか記
載されていない。
しかも録画では、鴻池委員長が全く見えない中、山本一太氏が、委員長でもないのに
勝手に「採決をしようとして何かを読み上げようとしている」場面が写っている。
それも含めて、「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」であったわけだが
勝手に委員長でもないものが、委員長の代読をしようと試みていると思われる。
国会での審議が進めば進むほど違憲であるとして国民の多数が反対している
安保関連法案を参議院規則まで踏みにじり、締め括りの質疑も省いて、
虚偽の「採決」なるものを強行しそのあと本会議にかけたことは、違憲違法により
採決は無効である。
したがって
5件の「採決」と称されるものは、すべて採決の要件を充たさず、採決は不存在である。
「採決」が存在しない以上、安保関連法案の審議は未了である。
また市民の平和的生存権が侵害された。
平和的生存権は、日本国憲法前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から
免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」に根拠がある。
憲法は、本来人権の体系である。第9条の戦争の放棄・戦力の不保持も、平和的生存権とい
う基本権を保障するための制度である。
9条をないがしろにする安倍内閣の行為によって平和的生存権が侵害された。
この違憲法案の強引な虚偽成立により市民の平和的生存権が侵害されて多大な精
神的苦痛をこうむった。原告一人あたり10万円の損害賠償に該当する。
また、伊藤正己著「憲法入門」229P に司法権 統治行為について
「すでにみたように議員の定数の選挙区に対する配分の不均衡が争われた事件で、極端な不平等であれば違憲と判定できるとしているから、このようなかなりの政治性をもつ問題も統治行為であるとは認めていないことになる。統治行為の理論は、主として法令の違憲審査に際して問題となるのであり、この審査権が国民の権利保障にとって重要なものであることからみて、裁判所がこの理論を
安易に利用して判断を避けることの許されないことはいうまでもない」
と書かれている。
したがって裁判所は、この違憲法案に関するこの訴訟について
統治行為論を安易に利用して判断を避けることは許されないものである。
まして、門前払いにすることは憲法第32条に定める「裁判をうける権利」
に対する憲法違反を裁判所が行うことになる。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又
はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあら
かじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」
と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多
様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことであ
る。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。
この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利へ
の侵害・制約についても適用されると理解される。
たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題について
も適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶ
と解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守るこ
とであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障
が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会運営(採決など)自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある国会運営が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、国会運営(採決など)において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://
4回連続まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破!
記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン。
まぐまぐ大賞2008政治第1位
http://
まぐまぐ大賞2007政治第1位
http://
まぐまぐ大賞2006政治第1位
http://
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://
山形市長選挙の不正選挙の異議申し立ては山形市の方は特に今日提出していただきたい。
山形市の方は、本日山形市役所に届ければいい。異議申し立ては無料である。住所電話も書き加えておいていただきたい。
(とりあえず提出であとからでもいいが)提出できた人は私に連絡をください。
間に合わないとか県外の人に限りFAXでもいいと思われる。
なぜなら全国の人に関係するからである。
落選者にも説得していただきたい。不正選挙があるかぎり明日はない。
以下は参考にしていただきたい。
<訴状>
東京地方裁判所御中
被告 安倍晋三内閣総理大臣
(又は安全保障法案に賛成した国会議員氏名)
原告
住所
電話番号
氏名
<安全保障法案の違憲無効および委員会採決無効の確認訴訟>
請求の趣旨
平成27年9月17日安全保障関連法案の参議院委員会採決は違憲無効である。
この違憲法案の強引な虚偽成立により市民の平和的生存権が侵害されて多大な精神的苦痛をこうむった。原告一人あたり10万円の損害賠償に該当する。
予備的主張として安全保障法案自体および制定手続きは違憲であるという宣言を
求める。
請求の理由
混乱の中で行われた安全保障関連法の参院平和安全法制特別委員会での採決は、
速記録に「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」と書かれており、採決自体が存在してい
なかった。このことは、憲法第31条の「適正手続きの保障」が行政に及ぶこと
に違反する。また参議院規則第49条 第136条 第137条に違反する
ものである。
したがって平成27年9月17日の安全保障法案の参議院委員会採決は、
違憲無効である。したがってそのあとの本会議採決も無効である。
法案の内容自体も違憲無効であり、その採決の手続き自体も違憲違法により
無効である。
安保関連法案の採決不存在の確認
参議院に設置された「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(以下「特
別委」)は、2015年9月17日、同特別委に審議を付託された安保関連法案等計5件の採決を
行い、いずれも賛成多数で可決されたと虚偽の主張を行っている。
採決が行われたとされる、同日16時30分頃の委員会室の模様を参議院のインターネット中
継やテレビの中継・録画で視ると、鴻池委員長席の周囲は与野党議員によって何重にも取
り囲まれ、委員長の議事進行の声を委員が聴き取れる状況になかったことは明らかである。
また、各議員に取り囲まれて、委員長も動議提出の声を聴き取り、各委員の起立を確認でき
る状況になかったことは明らかである。
参議院規則「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する」(第
136条)、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立
者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する」(第137条)との定めは、
委員会審議については「議長」を「委員長」と読み替えて理解すべきであるが、一連の事実
と状況に照らせば、上記5件の「採決」なるものは、表決の要件を充たしていないことが明
らかである。
なお、同規則49条は、委員会審議に関して136条と同様の定めをし、参議院委員会先例録第
2章第9節・155には、「採決は、挙手又は起立の方法によるのを例とする」との表題で、
「委員会における採決は、挙手又は起立の方法によるのを例とするが、異議の有無を諮(は
か)ってこれを行った例も多い。挙手又は起立により採決するときは、委員長は、
問題を可とする者を挙手又は起立させ、挙手又は起立者の多少を認定して可否の結果を宣告
する。なお、記名投票によった…例もある」とされている。
いずれにせよ、今回の「採決」なるものが表決の要件を充たしていないことは明らかであ
る。
十八日に出された未定稿の速記録では、「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」としか記
載されていない。
しかも録画では、鴻池委員長が全く見えない中、山本一太氏が、委員長でもないのに
勝手に「採決をしようとして何かを読み上げようとしている」場面が写っている。
それも含めて、「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」であったわけだが
勝手に委員長でもないものが、委員長の代読をしようと試みていると思われる。
国会での審議が進めば進むほど違憲であるとして国民の多数が反対している
安保関連法案を参議院規則まで踏みにじり、締め括りの質疑も省いて、
虚偽の「採決」なるものを強行しそのあと本会議にかけたことは、違憲違法により
採決は無効である。
したがって
5件の「採決」と称されるものは、すべて採決の要件を充たさず、採決は不存在である。
「採決」が存在しない以上、安保関連法案の審議は未了である。
また市民の平和的生存権が侵害された。
平和的生存権は、日本国憲法前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から
免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」に根拠がある。
憲法は、本来人権の体系である。第9条の戦争の放棄・戦力の不保持も、平和的生存権とい
う基本権を保障するための制度である。
9条をないがしろにする安倍内閣の行為によって平和的生存権が侵害された。
この違憲法案の強引な虚偽成立により市民の平和的生存権が侵害されて多大な精
神的苦痛をこうむった。原告一人あたり10万円の損害賠償に該当する。
また、伊藤正己著「憲法入門」229P に司法権 統治行為について
「すでにみたように議員の定数の選挙区に対する配分の不均衡が争われた事件で、極端な不平等であれば違憲と判定できるとしているから、このようなかなりの政治性をもつ問題も統治行為であるとは認めていないことになる。統治行為の理論は、主として法令の違憲審査に際して問題となるのであり、この審査権が国民の権利保障にとって重要なものであることからみて、裁判所がこの理論を
安易に利用して判断を避けることの許されないことはいうまでもない」
と書かれている。
したがって裁判所は、この違憲法案に関するこの訴訟について
統治行為論を安易に利用して判断を避けることは許されないものである。
まして、門前払いにすることは憲法第32条に定める「裁判をうける権利」
に対する憲法違反を裁判所が行うことになる。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又
はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあら
かじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」
と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多
様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことであ
る。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。
この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利へ
の侵害・制約についても適用されると理解される。
たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題について
も適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶ
と解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守るこ
とであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障
が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会運営(採決など)自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある国会運営が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、国会運営(採決など)において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://
4回連続まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破!
記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン。
まぐまぐ大賞2008政治第1位
http://
まぐまぐ大賞2007政治第1位
http://
まぐまぐ大賞2006政治第1位
http://
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国際評論家 小野寺光一 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-