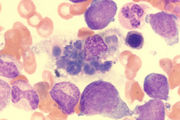|
|
|
|
コメント(40)
凝固に詳しい先生に聞いてみました!
以下 引用。
とある研究会でも話題に出てました。
「H先生」の見解では、あまり意味は無いとのこと。
高いことで何か臨床的な意義を求めるというわけにはいかないようでした。
仮に 外因系因子が過剰な状況であるとしても それで何かあるのか?ということは、寡聞にしてそういう認識はないです。
また、全血で測定する場合、ヘマトクリットが異常低値(例えば25%とか)であれば、比率が異なり→高値ということもありますが、近頃、全血ということもないでしょうねえ。
質問者の方は 凝固亢進や血栓傾向を期待しているのかもしれませんが、それを検索するならば やはりDdimer、SF、TATで見るべきでしょう。
とまあ、あまり回答にはなってませんが 臨床的意義はあまりないと考えてよさそうです。
以下 引用。
とある研究会でも話題に出てました。
「H先生」の見解では、あまり意味は無いとのこと。
高いことで何か臨床的な意義を求めるというわけにはいかないようでした。
仮に 外因系因子が過剰な状況であるとしても それで何かあるのか?ということは、寡聞にしてそういう認識はないです。
また、全血で測定する場合、ヘマトクリットが異常低値(例えば25%とか)であれば、比率が異なり→高値ということもありますが、近頃、全血ということもないでしょうねえ。
質問者の方は 凝固亢進や血栓傾向を期待しているのかもしれませんが、それを検索するならば やはりDdimer、SF、TATで見るべきでしょう。
とまあ、あまり回答にはなってませんが 臨床的意義はあまりないと考えてよさそうです。
☆hakoさんへ
もう一人の凝固に詳しい先生からのご意見を頂戴いたしました。
内容的には一緒でしたが、観点が違うように思えたので連絡させていただきます。
ご参考になれば!
以下、Yさんのご意見引用。
基本的にトロンボテストやPT、APTTなどの検査は出血傾向を見る検査で過凝固をとらえる検査ではありません。
したがってトロンボテストの検量線は、ワーファリンのコントロール域で最も感度良くとらえる事のできるものとなっているはずです。
PTもトロンボテストも100から0%までは実際の試料から作製したものですが100%以上については検量線を延長して理論上150%とか200%と言う値を出しているだけであり、100%以上のものについての解釈は少なくともPTに関しては意味のないものと思います。
もう一人の凝固に詳しい先生からのご意見を頂戴いたしました。
内容的には一緒でしたが、観点が違うように思えたので連絡させていただきます。
ご参考になれば!
以下、Yさんのご意見引用。
基本的にトロンボテストやPT、APTTなどの検査は出血傾向を見る検査で過凝固をとらえる検査ではありません。
したがってトロンボテストの検量線は、ワーファリンのコントロール域で最も感度良くとらえる事のできるものとなっているはずです。
PTもトロンボテストも100から0%までは実際の試料から作製したものですが100%以上については検量線を延長して理論上150%とか200%と言う値を出しているだけであり、100%以上のものについての解釈は少なくともPTに関しては意味のないものと思います。
☆コスさんへ
スチールボールの機械ですね。
凝固時間法/粘度変化感知方式(ビスコシティー・ディテクション方式)で物理力学的に凝固終末点を検出するので、採血手技の影響を除外する事を前提に考えますと、溶血、乳び、黄疸に関してはこの測定原理では影響を受けないと考えています。
ちなみに、散乱光検出による凝固時間法でも測光前のODをブランクとして散乱光の増加を検出するので、ある程度影響を受けずに測定可能です。ただ、自験例では乳びの高いのは濁度が邪魔をして凝固終末点を捉えられないときがあります。
凝固検査のいい本については、
?全般的にカバー:スタンダード検査血液学!
?基礎的なこと:最近sysmexさんが持ってこられた凝固に関するテキスト(ど〜やら営業さん向けの勉強本らしい)
&三菱化学ヤトロンさんは、この領域の研修会で何度も御世話になっており、毎回良いテキストを持ってきてくれます。
?DICに関しては:
http://mbc.meteo-intergate.com/bookcenter/public/item/mbc/item16637.html
?臨床検査全般ですが:
http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.asp?bookcode=290410
などがあります。
また、いい本があれば連絡しますね。
スチールボールの機械ですね。
凝固時間法/粘度変化感知方式(ビスコシティー・ディテクション方式)で物理力学的に凝固終末点を検出するので、採血手技の影響を除外する事を前提に考えますと、溶血、乳び、黄疸に関してはこの測定原理では影響を受けないと考えています。
ちなみに、散乱光検出による凝固時間法でも測光前のODをブランクとして散乱光の増加を検出するので、ある程度影響を受けずに測定可能です。ただ、自験例では乳びの高いのは濁度が邪魔をして凝固終末点を捉えられないときがあります。
凝固検査のいい本については、
?全般的にカバー:スタンダード検査血液学!
?基礎的なこと:最近sysmexさんが持ってこられた凝固に関するテキスト(ど〜やら営業さん向けの勉強本らしい)
&三菱化学ヤトロンさんは、この領域の研修会で何度も御世話になっており、毎回良いテキストを持ってきてくれます。
?DICに関しては:
http://mbc.meteo-intergate.com/bookcenter/public/item/mbc/item16637.html
?臨床検査全般ですが:
http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.asp?bookcode=290410
などがあります。
また、いい本があれば連絡しますね。
☆やまぴーさんへ
この内容の質問には幾通りもの考え方ややり方があると思いますので、今回は、当院での方法をご紹介します。
>PT時間の秒数の基準値はどのように決めていますか?
検診業務があればいいのですが、当院にはありませんので、外来患者で抗凝固療法を行なう可能性の低い診療科&肝機能正常患者のデータを300件ほど測定。縦軸に件数、横軸に秒・%・INRをそれぞれ取った図(3種類)を作成。一応、反復切断法も行いました。(反復切断法については、こちら→http://www.chiringi.or.jp/soft/kaisetu/StssBunpu.htm)
後は、活性%70〜80%、INR0.85〜1.15の間に入る秒を逆演算で算出しました。(この数字は強引に決めました)
>活性値100%の標準物質について
以前は、活性%は試薬純正の標準物質を、Local SI測定は、キャリブレーターを用いていました。
しかし、最近はLocal SI測定時に算出されるMNPT値が良好な活性値100%の秒数を反映していることに気づき、活性%の検量線は標準物質を用いて作成していますが、100%の秒数はMNPT値を採用しています。ただし、この方法は試薬と機器および標準物質の相性が良好なときのみ適応されると考えていますのでご注意ください。(測定パラメータの関係上です)
以上、私の意見は終了!
不十分な回答になり、残念に思っています。
どなたか、別の意見をお願いします。
この内容の質問には幾通りもの考え方ややり方があると思いますので、今回は、当院での方法をご紹介します。
>PT時間の秒数の基準値はどのように決めていますか?
検診業務があればいいのですが、当院にはありませんので、外来患者で抗凝固療法を行なう可能性の低い診療科&肝機能正常患者のデータを300件ほど測定。縦軸に件数、横軸に秒・%・INRをそれぞれ取った図(3種類)を作成。一応、反復切断法も行いました。(反復切断法については、こちら→http://www.chiringi.or.jp/soft/kaisetu/StssBunpu.htm)
後は、活性%70〜80%、INR0.85〜1.15の間に入る秒を逆演算で算出しました。(この数字は強引に決めました)
>活性値100%の標準物質について
以前は、活性%は試薬純正の標準物質を、Local SI測定は、キャリブレーターを用いていました。
しかし、最近はLocal SI測定時に算出されるMNPT値が良好な活性値100%の秒数を反映していることに気づき、活性%の検量線は標準物質を用いて作成していますが、100%の秒数はMNPT値を採用しています。ただし、この方法は試薬と機器および標準物質の相性が良好なときのみ適応されると考えていますのでご注意ください。(測定パラメータの関係上です)
以上、私の意見は終了!
不十分な回答になり、残念に思っています。
どなたか、別の意見をお願いします。
やまぴー様
私達の施設では、秒数の基準値は100人以上(男性50人以上女性50人以上の血漿を使用した統計的に算出したところ、検査法提要(だったかな?)の数値とほぼ変わらなかったため、検査法提要の数値を採用していたと思います。(随分前のことで記憶不鮮明です)活性値%のの基準値も同じ感じです。
毎回の活性値%の基準となる秒数は、100人以上の健常人のプール血漿(男性・女性各50人以上からなる)を使用していました。私どもは「トロンボプラスチンC+」(シスメックスでしたっけ?)を使用していましたが、たしかいつも10.8秒(だったと思いましたが結構前のことなので・・・記憶が不確)が出ていたと思います。けっこう安定した秒数が得られました。少し外れる秒数の出る試薬LOTは事前に検定をしてお断りしていました。
同一LOT内ではほとんど秒数は動かなかったので、同一LOT使用中は毎日基準秒数は測定せず、機器内に登録した秒数を使用していました。
そんなところですが。
正常血漿の既製品はLOT間のブレが大きく、なおかつ能書には、「標準物質として使用しないこと」と書いてあることが多かったと思いますね。逆に皆さんはどんな感じでやっているのか知りたいですね。
私達の施設では、秒数の基準値は100人以上(男性50人以上女性50人以上の血漿を使用した統計的に算出したところ、検査法提要(だったかな?)の数値とほぼ変わらなかったため、検査法提要の数値を採用していたと思います。(随分前のことで記憶不鮮明です)活性値%のの基準値も同じ感じです。
毎回の活性値%の基準となる秒数は、100人以上の健常人のプール血漿(男性・女性各50人以上からなる)を使用していました。私どもは「トロンボプラスチンC+」(シスメックスでしたっけ?)を使用していましたが、たしかいつも10.8秒(だったと思いましたが結構前のことなので・・・記憶が不確)が出ていたと思います。けっこう安定した秒数が得られました。少し外れる秒数の出る試薬LOTは事前に検定をしてお断りしていました。
同一LOT内ではほとんど秒数は動かなかったので、同一LOT使用中は毎日基準秒数は測定せず、機器内に登録した秒数を使用していました。
そんなところですが。
正常血漿の既製品はLOT間のブレが大きく、なおかつ能書には、「標準物質として使用しないこと」と書いてあることが多かったと思いますね。逆に皆さんはどんな感じでやっているのか知りたいですね。
コス様、耳ちっちゃいで様
>スチールボールの機械ですね。
>凝固時間法/粘度変化感知方式(ビスコシティー・ディテクション方式)で物理力学的に凝固終末点を検出するので、採血手技の影響を除外する事を前提に考えますと、溶血、乳び、黄疸に関してはこの測定原理では影響を受けないと考えています。
私もそう思います。
>ちなみに、散乱光検出による凝固時間法でも測光前のODをブランクとして散乱光の増加を検出するので、ある程度影響を受けずに測定可能です。ただ、自験例では乳びの高いのは濁度が邪魔をして凝固終末点を捉えられないときがあります。
私の経験ですと、特にフィブリノーゲンについては乳ビの影響が出やすかったと思います。
>スチールボールの機械ですね。
>凝固時間法/粘度変化感知方式(ビスコシティー・ディテクション方式)で物理力学的に凝固終末点を検出するので、採血手技の影響を除外する事を前提に考えますと、溶血、乳び、黄疸に関してはこの測定原理では影響を受けないと考えています。
私もそう思います。
>ちなみに、散乱光検出による凝固時間法でも測光前のODをブランクとして散乱光の増加を検出するので、ある程度影響を受けずに測定可能です。ただ、自験例では乳びの高いのは濁度が邪魔をして凝固終末点を捉えられないときがあります。
私の経験ですと、特にフィブリノーゲンについては乳ビの影響が出やすかったと思います。
>よろさんへ
検査結果だけ見ると、
AT? 29%
FBG 50mg/dl以下
HPT 10%
極度の凝固亢進のDICデータです。
重篤な肝障害も併発しているかも。(可能であればラクテートの値が判れば!高ければ肝臓は動いていない事になります。血液ガスで結構測られている項目なので)
>抗凝固剤を大量に使うとこういうデータがでるのですか?
僕の知る限りではこの様な経験はないのですが、皆さん如何でしょうか?
一つだけ確認してください。
検体採取の際にヘパリンフラッシュを十分にされておられるかを!
輸液による検体の希釈が頭をぐるぐる回りました。
FDP,Dダイマーは患者様の状態を把握しないとコメントしづらい所ですが、FBG 50mg/dl以下は、よっぽどでないと起こりえない検査結果ですね〜。
検査結果だけ見ると、
AT? 29%
FBG 50mg/dl以下
HPT 10%
極度の凝固亢進のDICデータです。
重篤な肝障害も併発しているかも。(可能であればラクテートの値が判れば!高ければ肝臓は動いていない事になります。血液ガスで結構測られている項目なので)
>抗凝固剤を大量に使うとこういうデータがでるのですか?
僕の知る限りではこの様な経験はないのですが、皆さん如何でしょうか?
一つだけ確認してください。
検体採取の際にヘパリンフラッシュを十分にされておられるかを!
輸液による検体の希釈が頭をぐるぐる回りました。
FDP,Dダイマーは患者様の状態を把握しないとコメントしづらい所ですが、FBG 50mg/dl以下は、よっぽどでないと起こりえない検査結果ですね〜。
>やなぎさん えと、私も初めまして
関節内の出血か、皮下、筋肉内の出血かちょっと気になります
内出血というとやはり紫斑が見えているのでしょうから後者でしょうかね
複数の部位で出血しているというとやはり全身的に何かあるのでしょうかね
熱感が強いとすると血管炎みたいな病気か出血しているから若干の熱感は
当たり前なのかな、凝固だと抗生剤でビタミンK不足、、後天性血友病の仲間
あとアスピリン多用で血小板の機能低下・・・。
血管強度のスクリーニング検査って今は何が普通なのでしょうね?
なかなか相談先の病院泣かせのような気もします。
いずれにしてもたいしたことがないことをお祈り申し上げます。
関節内の出血か、皮下、筋肉内の出血かちょっと気になります
内出血というとやはり紫斑が見えているのでしょうから後者でしょうかね
複数の部位で出血しているというとやはり全身的に何かあるのでしょうかね
熱感が強いとすると血管炎みたいな病気か出血しているから若干の熱感は
当たり前なのかな、凝固だと抗生剤でビタミンK不足、、後天性血友病の仲間
あとアスピリン多用で血小板の機能低下・・・。
血管強度のスクリーニング検査って今は何が普通なのでしょうね?
なかなか相談先の病院泣かせのような気もします。
いずれにしてもたいしたことがないことをお祈り申し上げます。
>かなり素朴な疑問系の質問なのですが…
かなり難しい質問です。疑問も無く過ごしてきましたが、根拠が乏しいかと思います。
想像するには、
内径10mm、長さが100mmの小試験管は、手に入りやすかったのでないでしょうか?ご存知だと思いますが、全血凝固時間やCa再加時間は内径10mmを用いています。重要なのは接触因子の活性化が凝固時間に影響すると事だと思うのです。接触面積を規定するために、10mmと決めたかと思いますし、プロトロンビン時間も同様に内径8mmに規定し、PTT、APTT、トロンボテストなどが追従したと思います。接触面積を一定にするという標準化が図られていたと解釈しています。一方、ゆっくり動かすのと、連続的に動かすので凝固時間が変わりますので、技師によってデータに差があったかと思います。そのために対照血漿を同時測定していたと思います。また、確認はしていませんが、凝固終末点ととらえるフィブリン析出がみやすいのかも。
自動分析になると、サンプルを静置したまま測定する(一部の機械を除いて)のが多いと思います。凝固終末点をとらえるため様々な工夫がされていますが、内径に対しては議論されていなかったかと思います。
>試しに8mmと10mmの両方で何回かやってみたところ、……
以前、私どもでもCa再加時間は、PTと同様な試験管を用いて検査していました。
かなり難しい質問です。疑問も無く過ごしてきましたが、根拠が乏しいかと思います。
想像するには、
内径10mm、長さが100mmの小試験管は、手に入りやすかったのでないでしょうか?ご存知だと思いますが、全血凝固時間やCa再加時間は内径10mmを用いています。重要なのは接触因子の活性化が凝固時間に影響すると事だと思うのです。接触面積を規定するために、10mmと決めたかと思いますし、プロトロンビン時間も同様に内径8mmに規定し、PTT、APTT、トロンボテストなどが追従したと思います。接触面積を一定にするという標準化が図られていたと解釈しています。一方、ゆっくり動かすのと、連続的に動かすので凝固時間が変わりますので、技師によってデータに差があったかと思います。そのために対照血漿を同時測定していたと思います。また、確認はしていませんが、凝固終末点ととらえるフィブリン析出がみやすいのかも。
自動分析になると、サンプルを静置したまま測定する(一部の機械を除いて)のが多いと思います。凝固終末点をとらえるため様々な工夫がされていますが、内径に対しては議論されていなかったかと思います。
>試しに8mmと10mmの両方で何回かやってみたところ、……
以前、私どもでもCa再加時間は、PTと同様な試験管を用いて検査していました。
>オーシャンさん
レスありがとうございました。
>接触面積を規定するために、10mmと決めたかと思いますし、プロトロンビン時間も同様に内径8mmに規定し、PTT、APTT、トロンボテストなどが追従したと思います。接触面積を一定にするという標準化が図られていたと解釈しています。
やはり、そんなところではないかな…と私も考えていました。
私のところでは、Ca再加は生の秒数ですが、PT、TTOについては検量線を引いて活性%、APTTについては標準血漿の結果と並記で秒数を報告しています。
秒数での報告では、標準化という意味できちんと条件を定めた方がいいと思いますが、活性%で報告する際に、検量線を引くための標準血漿の検査も同じ条件で行えば、8mmであろうと、10mmであろうと、結局出る結果は同じだと思っていましたので、あまり気にしていませんでした。
(^_^;
実際に機械(CA-6000)で出した活性%の値と、用手法(8mm,10mm両方)で出した値はほとんど違いませんでした。
ただ、今はもう機械が出す値を報告するだけで、用手法はパニック値や過去歴乖離のある検体の検証を行うくらいでしか行っていませんが…
オーシャンさん、貴重なご意見ありがとうございました。
レスありがとうございました。
>接触面積を規定するために、10mmと決めたかと思いますし、プロトロンビン時間も同様に内径8mmに規定し、PTT、APTT、トロンボテストなどが追従したと思います。接触面積を一定にするという標準化が図られていたと解釈しています。
やはり、そんなところではないかな…と私も考えていました。
私のところでは、Ca再加は生の秒数ですが、PT、TTOについては検量線を引いて活性%、APTTについては標準血漿の結果と並記で秒数を報告しています。
秒数での報告では、標準化という意味できちんと条件を定めた方がいいと思いますが、活性%で報告する際に、検量線を引くための標準血漿の検査も同じ条件で行えば、8mmであろうと、10mmであろうと、結局出る結果は同じだと思っていましたので、あまり気にしていませんでした。
(^_^;
実際に機械(CA-6000)で出した活性%の値と、用手法(8mm,10mm両方)で出した値はほとんど違いませんでした。
ただ、今はもう機械が出す値を報告するだけで、用手法はパニック値や過去歴乖離のある検体の検証を行うくらいでしか行っていませんが…
オーシャンさん、貴重なご意見ありがとうございました。
こんにちは。
PT−INRについてとのことですが、私もINRだけでは30分はしゃべれません(笑)
凝固検査としてのPTとは何か?TTとの違いも取り入れるべきですよね。
(他部署の方も見えるなら)
ワーファリンコントロールをINRで行っているのはどういうことか?
海外ではINRが主流ですが、日本とヨーロッパの一部ではTTが使われているのは何故か?等調べると面白いですよ(笑)
あと、INRは国際標準化と言われてますが、PT中のTFの由来がウサギ、人、リコンビナントではISIで補正しているとはいえ、かなり差が出てきます。
その点も文献等で確認してみてください。
メディエンスの凝固・線溶検査ポケットブックはDr用の検査項目説明書みたいなものなので、あまり参考にはならないかもしれません。(^^;アセ
PT−INRについてとのことですが、私もINRだけでは30分はしゃべれません(笑)
凝固検査としてのPTとは何か?TTとの違いも取り入れるべきですよね。
(他部署の方も見えるなら)
ワーファリンコントロールをINRで行っているのはどういうことか?
海外ではINRが主流ですが、日本とヨーロッパの一部ではTTが使われているのは何故か?等調べると面白いですよ(笑)
あと、INRは国際標準化と言われてますが、PT中のTFの由来がウサギ、人、リコンビナントではISIで補正しているとはいえ、かなり差が出てきます。
その点も文献等で確認してみてください。
メディエンスの凝固・線溶検査ポケットブックはDr用の検査項目説明書みたいなものなので、あまり参考にはならないかもしれません。(^^;アセ
あ さんへ
PT検査では、試薬と測定機器の多様性が問題となっていました。
ご存知とは思いますが、INRは、PT検査をワーファリン治療のモニタリングとして、どこの施設でも同様の結果が得られるように考えられた指標です。
INRを決定づける要素として、ISI値と正常人秒数があります。
正常人秒数については、今回はふれません。
ISI値は、試薬と測定機器で決定され、メーカーSIとローカルSIがあります。
試薬は試薬種別間差と同じ試薬でもロット間差があります。
測定機器は、使用年数や機器特性があります。
メーカーSIは、試薬ロット毎に各測定機器に対してメーカー側が設定した値です。
恐らくですが、メーカー基準機を用いて算出されていると思います。
ローカルSIは、使用PT試薬と測定機器でISIキャリブレータを測定することにより算出されるISI値です。
メーカーSIに対しローカルSIでは、測定機器の使用状況の影響を反映したISI値が算出できます。
まとめますと、ローカルSIはその施設の試薬と機器に応じたISI値が設定されます。メーカーSI値では、試薬ロットはさほど気にしなくてもいいのですが、使用機器の条件が反映できない設定値となります。
長文&回りくどい文章になったかと思いますが、理解しにくいところがあれば、引き続きフォローください。
PT検査では、試薬と測定機器の多様性が問題となっていました。
ご存知とは思いますが、INRは、PT検査をワーファリン治療のモニタリングとして、どこの施設でも同様の結果が得られるように考えられた指標です。
INRを決定づける要素として、ISI値と正常人秒数があります。
正常人秒数については、今回はふれません。
ISI値は、試薬と測定機器で決定され、メーカーSIとローカルSIがあります。
試薬は試薬種別間差と同じ試薬でもロット間差があります。
測定機器は、使用年数や機器特性があります。
メーカーSIは、試薬ロット毎に各測定機器に対してメーカー側が設定した値です。
恐らくですが、メーカー基準機を用いて算出されていると思います。
ローカルSIは、使用PT試薬と測定機器でISIキャリブレータを測定することにより算出されるISI値です。
メーカーSIに対しローカルSIでは、測定機器の使用状況の影響を反映したISI値が算出できます。
まとめますと、ローカルSIはその施設の試薬と機器に応じたISI値が設定されます。メーカーSI値では、試薬ロットはさほど気にしなくてもいいのですが、使用機器の条件が反映できない設定値となります。
長文&回りくどい文章になったかと思いますが、理解しにくいところがあれば、引き続きフォローください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
検査血液学 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
検査血液学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人