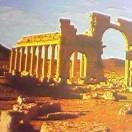6月のユングセミナーは「遠藤周作と『深い河』の登場人物たち」 〜
<その宗教思想的背景と深層心理を探る> のタイトルで、
前田史子さんにお話をしていただきました。
前田さんから頂いたレジュメを転載させていただきます。
1、『深い河』について
1993年(遠藤周作氏70歳のとき)に発表された作品。
1995年に映画化された。
遠藤周作氏の生涯のテーマ「キリスト教と日本人」の最終章となった作品といわれる。
2、キリスト教のシンボルーー十字架にかかったイエス像ーー
・十字架は“葛藤”のシンボル
縦軸と横軸の交差する点(葛藤の中心)にイエス・キリストは磔にされている。
*イエスの場合は、中心より少し上で磔になっている。
・キリスト教は、見つめる対象を分割する機能がある。
神のまねび(善であること)を求められる生活は、“そうできないときの自分”を浮き彫りにする。
『深い河』の中にも、そのような“対”となる登場人物の組み合わせがある。
大津と美津子、ガストンと塚田、沼田(内向)と三條(外向)、マリア様とヒンズー教の女神チャームンダー
*未だ分化していない登場人物もある=東洋人の典型(混沌・未分化)
磯部;「合理・現実主義」と「非合理・神秘主義」など。
3、イニシエーション(特に洗礼)について
イニシエーションとは、“死と再生の儀式”。
内的な“死と再生の体験”を目に見える形で儀式化したもの。
(例)成人式、結婚式など。
(未開の地でのイニシエーション、結婚式での白無垢)
「イニシエーション前の自分」と「イニシエーション後の自分」は違う
(自分の中の何かが死に、新しい何かが自分の中に生まれる)。
宗教の中には、そうした儀式がたくさん見られる。「洗礼」もそのひとつ。
*洗礼とは、水を使ったキリスト教入信の際の儀式。水盤の中で水を浴びたりする。
(遠藤周作氏の場合)
1回目の洗礼;12歳の時に叔母の影響を受けてキリスト教の洗礼を受ける。
2回目の洗礼;『深い河』の作品の中におけるガンジス川での沐浴
4、遠藤周作氏の宗教的背景
東洋の日本にて、叔母の影響を受け、12歳の時に洗礼を受けた。
その時から、異教的な環境(キリスト教的な観点)の中で、内的にはキリスト教を生きる人生が始まった、といえる。
・日本;汎神論的・アニミズム的宗教観が強い。
他宗教にわりと寛容な神道・仏教が主な宗教の土地(ex.宗教多元主義、神仏習合など)。
“心の中に神や仏がいる”という考えに抵抗がない(神の内在)。内と外があいまい。
・西洋(キリスト教世界);一神論。排他的。
キリスト教以外は異教であり、地獄に堕ちる(ex.十字軍、異端を切り捨ててきた歴史)。
神は、自分の外側に存在するもの(神の外在)。神と人間は別物。その神との契約による宗教。内と外を区切る思考形態。
*ユング心理学の立場は・・・?
5、登場人物について
『深い河』を遠藤氏のアクティブ・イマジネーションととらえ、
登場人物を“遠藤氏の心の中のいくつかの特徴が人格化されたもの”と考えてみる。
○大津;母の影響でクリスチャンとなり、キリスト教系の大学に入り神父を志す。純朴だが、不器用な生き方しかできない男性。在学中に美津子に誘惑されキリストを裏切ろうとするが、美津子に捨てられた後に、返って惨めな自分をキリストが救ってくれることを知る。その後、フランスに留学するが、自分の考えがキリスト教神学と相容れず、インドに渡る。そこで、行き倒れたヒンズー教徒を火葬しガンジス川へ流す仕事をしているときに、美津子と再会する。
○美津子;女性の魅力に富んでいるが、他人を愛した経験がなく、学生時代には複数の男性の心を弄んだ。大津を棄教させることができたかと思ったが、結婚後、フランスにキリスト教の留学をした大津の噂を聞き、新婚旅行の際に一人で彼に会いに行く。その後離婚し、愛情のなさを自覚した彼女は、愛情の真似事をするために末期がん患者の世話をするボランティアを始める。ある日、同窓会で、大津がインドに行ったことを聞き、インドツアーに参加する。
・木口;戦時中にインパール作戦に参加した経験のある老人。長く苦しい撤退の後、マラリアで死にそうなところを戦友塚田に救ってもらう。終戦後、再会した塚田の病死を弔うため、インドツアーに参加する。
□塚田;木口の戦友。インパール作戦の際、木口と自分の命を救うため、人肉を食べたことを気に病み、アル中となった。死の間際、看護ボランティアのガストンに人肉を食べた秘密とその辛さと悔恨を告白して死んでゆく。
*キリスト教の儀式「聖餐」;パンをキリストの肉、ワインをキリストの血として食し、キリストと同化する儀式(神秘的融即)。
*キリスト教の悔悛の秘蹟「懺悔」「告解」
□ガストン;病院で介護ボランティアをしているクリスチャンの白人。小説『おバカさん』の登場人物。『おバカさん』の中では、どんな悪人にでも寄り添い付き添っていく“信じること”を戒として生きることを決意した不器用な人物として描かれている。(キリストの象徴?)
・磯部;日本の男性を象徴するような老年期にさしかかった男。妻の死に際の「生まれ変わった私を探し出して」といううわ言にとらわれ、理性では信じられないにもかかわらず、日本人の生まれ変わりがいるというインドへ向かう。
△沼田;中年の童話作家。少年期は中国の大連に住んでいた。その時の飼い犬が最大の友達であった体験をもとに動物と対話する童話を書いていた。結核が再燃し、手術を受けている最中(彼は心停止を起こしていた)に飼っていた九官鳥が死んだことを知り、身代わりになってくれたと思う。インドに野生保護区がたくさんあることを知り、九官鳥を買い求め、保護区に開放してやることを思い立って、インドツアーに参加する。
*“鳥”は“霊spirit”の比喩(『「深い河」をさぐる』から)
*“インド”は“無意識”の比喩(『「深い河」をさぐる』から)
*“動物”は“キリスト”の象徴(『「深い河」創作日記』から)
△三條;新婚のカメラマン。タブーを犯してでもスクープをとり、ひと旗あげたいと思っている。
・江波;インドツアーのガイド。表面的なインドしか見ようとしないツアー客を軽蔑しながらも、インドの深さをツアー客に理解してもらいたいと思っている。インドへの深い理解と愛情を持つ。
6、自己(セルフ)の象徴
自己(セルフ)の象徴としてよく人々のイメージにのぼってくるものとして、「川」「水」「動物(=問題となっている内容と機能がまだ意識の彼方にあるときのイメージ)」「神」「キリスト」「仏」・・・などがある。
*ガンジス川とは;どんな宗教に属していようが、あるいは宗教に属していまいが、あらゆる人間の持つ複雑な人生および善悪を包み込んで(彼岸へと)流してくれる存在=遠藤氏の考えるキリスト像、あるいはキリストの愛(←しかし、これは“異端”的な考え)。
*そのような“キリスト”が遠藤氏の「セルフ」の象徴であると仮定すると、キリスト像の変容は、遠藤氏の個性化の過程とも考えられる。
7、「東洋への回帰」とみるか「統合」と見るか
『深い河』のストーリーから暗示される遠藤氏の人生を“東洋への回帰”と見るか“統合”とみるか。
*「神秘的融即」(ex.美津子の沐浴の後の大津の死)とみるか「神秘的統合」(確かに統合のための努力はあった)とみるか。
<その宗教思想的背景と深層心理を探る> のタイトルで、
前田史子さんにお話をしていただきました。
前田さんから頂いたレジュメを転載させていただきます。
1、『深い河』について
1993年(遠藤周作氏70歳のとき)に発表された作品。
1995年に映画化された。
遠藤周作氏の生涯のテーマ「キリスト教と日本人」の最終章となった作品といわれる。
2、キリスト教のシンボルーー十字架にかかったイエス像ーー
・十字架は“葛藤”のシンボル
縦軸と横軸の交差する点(葛藤の中心)にイエス・キリストは磔にされている。
*イエスの場合は、中心より少し上で磔になっている。
・キリスト教は、見つめる対象を分割する機能がある。
神のまねび(善であること)を求められる生活は、“そうできないときの自分”を浮き彫りにする。
『深い河』の中にも、そのような“対”となる登場人物の組み合わせがある。
大津と美津子、ガストンと塚田、沼田(内向)と三條(外向)、マリア様とヒンズー教の女神チャームンダー
*未だ分化していない登場人物もある=東洋人の典型(混沌・未分化)
磯部;「合理・現実主義」と「非合理・神秘主義」など。
3、イニシエーション(特に洗礼)について
イニシエーションとは、“死と再生の儀式”。
内的な“死と再生の体験”を目に見える形で儀式化したもの。
(例)成人式、結婚式など。
(未開の地でのイニシエーション、結婚式での白無垢)
「イニシエーション前の自分」と「イニシエーション後の自分」は違う
(自分の中の何かが死に、新しい何かが自分の中に生まれる)。
宗教の中には、そうした儀式がたくさん見られる。「洗礼」もそのひとつ。
*洗礼とは、水を使ったキリスト教入信の際の儀式。水盤の中で水を浴びたりする。
(遠藤周作氏の場合)
1回目の洗礼;12歳の時に叔母の影響を受けてキリスト教の洗礼を受ける。
2回目の洗礼;『深い河』の作品の中におけるガンジス川での沐浴
4、遠藤周作氏の宗教的背景
東洋の日本にて、叔母の影響を受け、12歳の時に洗礼を受けた。
その時から、異教的な環境(キリスト教的な観点)の中で、内的にはキリスト教を生きる人生が始まった、といえる。
・日本;汎神論的・アニミズム的宗教観が強い。
他宗教にわりと寛容な神道・仏教が主な宗教の土地(ex.宗教多元主義、神仏習合など)。
“心の中に神や仏がいる”という考えに抵抗がない(神の内在)。内と外があいまい。
・西洋(キリスト教世界);一神論。排他的。
キリスト教以外は異教であり、地獄に堕ちる(ex.十字軍、異端を切り捨ててきた歴史)。
神は、自分の外側に存在するもの(神の外在)。神と人間は別物。その神との契約による宗教。内と外を区切る思考形態。
*ユング心理学の立場は・・・?
5、登場人物について
『深い河』を遠藤氏のアクティブ・イマジネーションととらえ、
登場人物を“遠藤氏の心の中のいくつかの特徴が人格化されたもの”と考えてみる。
○大津;母の影響でクリスチャンとなり、キリスト教系の大学に入り神父を志す。純朴だが、不器用な生き方しかできない男性。在学中に美津子に誘惑されキリストを裏切ろうとするが、美津子に捨てられた後に、返って惨めな自分をキリストが救ってくれることを知る。その後、フランスに留学するが、自分の考えがキリスト教神学と相容れず、インドに渡る。そこで、行き倒れたヒンズー教徒を火葬しガンジス川へ流す仕事をしているときに、美津子と再会する。
○美津子;女性の魅力に富んでいるが、他人を愛した経験がなく、学生時代には複数の男性の心を弄んだ。大津を棄教させることができたかと思ったが、結婚後、フランスにキリスト教の留学をした大津の噂を聞き、新婚旅行の際に一人で彼に会いに行く。その後離婚し、愛情のなさを自覚した彼女は、愛情の真似事をするために末期がん患者の世話をするボランティアを始める。ある日、同窓会で、大津がインドに行ったことを聞き、インドツアーに参加する。
・木口;戦時中にインパール作戦に参加した経験のある老人。長く苦しい撤退の後、マラリアで死にそうなところを戦友塚田に救ってもらう。終戦後、再会した塚田の病死を弔うため、インドツアーに参加する。
□塚田;木口の戦友。インパール作戦の際、木口と自分の命を救うため、人肉を食べたことを気に病み、アル中となった。死の間際、看護ボランティアのガストンに人肉を食べた秘密とその辛さと悔恨を告白して死んでゆく。
*キリスト教の儀式「聖餐」;パンをキリストの肉、ワインをキリストの血として食し、キリストと同化する儀式(神秘的融即)。
*キリスト教の悔悛の秘蹟「懺悔」「告解」
□ガストン;病院で介護ボランティアをしているクリスチャンの白人。小説『おバカさん』の登場人物。『おバカさん』の中では、どんな悪人にでも寄り添い付き添っていく“信じること”を戒として生きることを決意した不器用な人物として描かれている。(キリストの象徴?)
・磯部;日本の男性を象徴するような老年期にさしかかった男。妻の死に際の「生まれ変わった私を探し出して」といううわ言にとらわれ、理性では信じられないにもかかわらず、日本人の生まれ変わりがいるというインドへ向かう。
△沼田;中年の童話作家。少年期は中国の大連に住んでいた。その時の飼い犬が最大の友達であった体験をもとに動物と対話する童話を書いていた。結核が再燃し、手術を受けている最中(彼は心停止を起こしていた)に飼っていた九官鳥が死んだことを知り、身代わりになってくれたと思う。インドに野生保護区がたくさんあることを知り、九官鳥を買い求め、保護区に開放してやることを思い立って、インドツアーに参加する。
*“鳥”は“霊spirit”の比喩(『「深い河」をさぐる』から)
*“インド”は“無意識”の比喩(『「深い河」をさぐる』から)
*“動物”は“キリスト”の象徴(『「深い河」創作日記』から)
△三條;新婚のカメラマン。タブーを犯してでもスクープをとり、ひと旗あげたいと思っている。
・江波;インドツアーのガイド。表面的なインドしか見ようとしないツアー客を軽蔑しながらも、インドの深さをツアー客に理解してもらいたいと思っている。インドへの深い理解と愛情を持つ。
6、自己(セルフ)の象徴
自己(セルフ)の象徴としてよく人々のイメージにのぼってくるものとして、「川」「水」「動物(=問題となっている内容と機能がまだ意識の彼方にあるときのイメージ)」「神」「キリスト」「仏」・・・などがある。
*ガンジス川とは;どんな宗教に属していようが、あるいは宗教に属していまいが、あらゆる人間の持つ複雑な人生および善悪を包み込んで(彼岸へと)流してくれる存在=遠藤氏の考えるキリスト像、あるいはキリストの愛(←しかし、これは“異端”的な考え)。
*そのような“キリスト”が遠藤氏の「セルフ」の象徴であると仮定すると、キリスト像の変容は、遠藤氏の個性化の過程とも考えられる。
7、「東洋への回帰」とみるか「統合」と見るか
『深い河』のストーリーから暗示される遠藤氏の人生を“東洋への回帰”と見るか“統合”とみるか。
*「神秘的融即」(ex.美津子の沐浴の後の大津の死)とみるか「神秘的統合」(確かに統合のための努力はあった)とみるか。
|
|
|
|
コメント(52)
本当に私も参加させていただきたかったです。
ミネルヴァさん・・・お疲れ様でした。
遠藤さんの「深い河」は、これまでの遠藤文学のまとめ・・なんでしょうね。
私も読んでいて、「あ、これはあの小説の○○だ」とか、思い浮かんだので、ここでまとめたいんだな、という思いは伝わってきました。ただ逆にいうと、それらを読んでない・・とあの小説のおもしろさはわかりにくかったかな、という難点はあったかな、という気がしています。
遠藤さんがフランス留学中に感じたことは、「日本にあったキリスト教があってもいいんじゃないか」っていうことだったみたいですね。
その強い思いが、「沈黙」を書かせたのだと思います。
「沈黙」の中に、奉行が司祭にむかって、日本には日本の女がいる。キリスト教という異国の女を押しつけなくても・・という台詞がありました。ダイレクトに、ローマ勢のキリスト教を押しつける・・ということには遠藤さんも批判的だったようですね。
その思いが、東洋と西洋の宗教の対話という路線だったのかな、と思います。
大津は救われたか、どうか・・という話。
私も参加したかったです。
私は救われた・・とまではいかなくても、ある種の「救い」はあったのかな、と思います。というか思いたい。
彼は、美津子へのつらい思いを断ち切るためにインドへ渡り、そこで皮肉なことに美津子に再会してしまい、結局はたしかに「認められる」のだけれど、大変なことをやってるのだけれど、決して賞賛される生き方ではない。だけど、ひたすらやっていた。その中である種の「悟り」というか「心の安らぎ」は得ていたと思うし・・。
その時に、美津子と再会・・っていうのは、神様のいたずら・・だったのか、おためし・・だったのか。
ただ、小説自体が、なぜか私は消化不良だった。終わりがぱーんと断ち切られる終わり方だったというのもありますが・・。
もっとも、これは「自分は説明しない。あとは読み手にゆだねる」っていう遠藤さんのお考えもあったのでしょうね。しかし、これも今までの小説のパターンで考えると、大津の善の部分は高められた、そして美津子(”悪人”ではないですが、あまり好ましくない心の持ち主)の気持ちもある程度動かすことができた・・っていうことで、ひとつの力を発揮したのかな、という気がします。
遠藤さんの小説には、女性の形を借りた「悪魔」がよく出てきますね。悪魔の午後・・っていう作品だったと思うのですが、人の心を鋭く見抜き、その人の隠れた願望を言い当てて、悪いことでもそれを実行させてしまう・・という恐ろしいような力を持った女性が出てきた作品がありました。「深い河」を読んだとき、美津子とこの女性がかぶりました。(もっとも、この“悪魔の午後”はTVドラマ化され、ヒロインを秋吉久美子が演じていて、”深い河”の映画(私は未見ですが)では、やはり美津子を秋吉さんが演じてた・・っていうことがあったのかもしれませんが。この神vs悪魔、善vs悪・・というのは、いかにもキリスト教的視点ですね。
しかし、最後にそれらをのみこむガンジス河・・っていう形にもっていったのは面白いです。やはり・・・偉大な河なのでしょうね。
みちさん、私もインドには惹かれるけれど、インドには怖くて行けない・・っていう・・。たぶん、好きになってはまる・・ほうにはいるのかな、と思います。
東南アジアで行ったのはタイまで・・で、その先はなぜか行けない・・・。
ミネルヴァさん、いつか一緒に行きますか?(笑)
みちさんにご先達、お願いしましょう。
清志朗さん、日記のほうも読ませていただきましゃが、ダライ・ラマの講演に行かれたのですね。その分類はうなずけます。
「人、もの皆、仏性あり」っていう仏教・・って、たしかに「神」はいないですね。
私のイギリス人の友人に、自分はそういう考えを昔からしてたから、カトリックの学校に行ってても違和感があった・・と言ってました。そういう気持ち、なんとなく理解できる気がします。
なんかまとまりのないことばかり書いてすみません。
「深い河」の話なので、何か書きたくて・・。(^^)
ミネルヴァさん・・・お疲れ様でした。
遠藤さんの「深い河」は、これまでの遠藤文学のまとめ・・なんでしょうね。
私も読んでいて、「あ、これはあの小説の○○だ」とか、思い浮かんだので、ここでまとめたいんだな、という思いは伝わってきました。ただ逆にいうと、それらを読んでない・・とあの小説のおもしろさはわかりにくかったかな、という難点はあったかな、という気がしています。
遠藤さんがフランス留学中に感じたことは、「日本にあったキリスト教があってもいいんじゃないか」っていうことだったみたいですね。
その強い思いが、「沈黙」を書かせたのだと思います。
「沈黙」の中に、奉行が司祭にむかって、日本には日本の女がいる。キリスト教という異国の女を押しつけなくても・・という台詞がありました。ダイレクトに、ローマ勢のキリスト教を押しつける・・ということには遠藤さんも批判的だったようですね。
その思いが、東洋と西洋の宗教の対話という路線だったのかな、と思います。
大津は救われたか、どうか・・という話。
私も参加したかったです。
私は救われた・・とまではいかなくても、ある種の「救い」はあったのかな、と思います。というか思いたい。
彼は、美津子へのつらい思いを断ち切るためにインドへ渡り、そこで皮肉なことに美津子に再会してしまい、結局はたしかに「認められる」のだけれど、大変なことをやってるのだけれど、決して賞賛される生き方ではない。だけど、ひたすらやっていた。その中である種の「悟り」というか「心の安らぎ」は得ていたと思うし・・。
その時に、美津子と再会・・っていうのは、神様のいたずら・・だったのか、おためし・・だったのか。
ただ、小説自体が、なぜか私は消化不良だった。終わりがぱーんと断ち切られる終わり方だったというのもありますが・・。
もっとも、これは「自分は説明しない。あとは読み手にゆだねる」っていう遠藤さんのお考えもあったのでしょうね。しかし、これも今までの小説のパターンで考えると、大津の善の部分は高められた、そして美津子(”悪人”ではないですが、あまり好ましくない心の持ち主)の気持ちもある程度動かすことができた・・っていうことで、ひとつの力を発揮したのかな、という気がします。
遠藤さんの小説には、女性の形を借りた「悪魔」がよく出てきますね。悪魔の午後・・っていう作品だったと思うのですが、人の心を鋭く見抜き、その人の隠れた願望を言い当てて、悪いことでもそれを実行させてしまう・・という恐ろしいような力を持った女性が出てきた作品がありました。「深い河」を読んだとき、美津子とこの女性がかぶりました。(もっとも、この“悪魔の午後”はTVドラマ化され、ヒロインを秋吉久美子が演じていて、”深い河”の映画(私は未見ですが)では、やはり美津子を秋吉さんが演じてた・・っていうことがあったのかもしれませんが。この神vs悪魔、善vs悪・・というのは、いかにもキリスト教的視点ですね。
しかし、最後にそれらをのみこむガンジス河・・っていう形にもっていったのは面白いです。やはり・・・偉大な河なのでしょうね。
みちさん、私もインドには惹かれるけれど、インドには怖くて行けない・・っていう・・。たぶん、好きになってはまる・・ほうにはいるのかな、と思います。
東南アジアで行ったのはタイまで・・で、その先はなぜか行けない・・・。
ミネルヴァさん、いつか一緒に行きますか?(笑)
みちさんにご先達、お願いしましょう。
清志朗さん、日記のほうも読ませていただきましゃが、ダライ・ラマの講演に行かれたのですね。その分類はうなずけます。
「人、もの皆、仏性あり」っていう仏教・・って、たしかに「神」はいないですね。
私のイギリス人の友人に、自分はそういう考えを昔からしてたから、カトリックの学校に行ってても違和感があった・・と言ってました。そういう気持ち、なんとなく理解できる気がします。
なんかまとまりのないことばかり書いてすみません。
「深い河」の話なので、何か書きたくて・・。(^^)
人は「神」に向かって生きている・・と私は思っています。
どんなに時間がかかっても。いくつもの人生を通過しても。
「神」になることが最終的な目的ではなく
あるものは「神」そのものに、あるものはそれに近い何か別のもの、
それぞれの最終形に生まれ変わっていくようになっている。
そのために「神」はいろいろな体験や機会となって、ひとりひとりを訪れる。
生まれ変わるには、沢山の犠牲となる苦しみ、痛みが必要なのでしょう。
その苦しみや激しさに耐えられるかどうかで
神様の現れ方はその人によって違う。そんな気がします。
そして「神」はあまたのものに内在している。
たとえば、ここしばらく、ほとんど活字を読むことができなくなっていた私が
この小説を読もうと思ったこと自体にも、「神」は存在すると思います。
こうやって、文章にまとめようとしていること自体にも。
その「神」とは・・・
これから、自分自身でも体感して見つけていきたいと思っていますが
そこには触れずに、感想を書いてみたいと思います。
どんなに時間がかかっても。いくつもの人生を通過しても。
「神」になることが最終的な目的ではなく
あるものは「神」そのものに、あるものはそれに近い何か別のもの、
それぞれの最終形に生まれ変わっていくようになっている。
そのために「神」はいろいろな体験や機会となって、ひとりひとりを訪れる。
生まれ変わるには、沢山の犠牲となる苦しみ、痛みが必要なのでしょう。
その苦しみや激しさに耐えられるかどうかで
神様の現れ方はその人によって違う。そんな気がします。
そして「神」はあまたのものに内在している。
たとえば、ここしばらく、ほとんど活字を読むことができなくなっていた私が
この小説を読もうと思ったこと自体にも、「神」は存在すると思います。
こうやって、文章にまとめようとしていること自体にも。
その「神」とは・・・
これから、自分自身でも体感して見つけていきたいと思っていますが
そこには触れずに、感想を書いてみたいと思います。
大津は、私には、人間ではなく、神が人の姿を取って人生を生きたもののように思えます。
あらゆる痛みや苦しみを味わい、愛をさらに確信していく生き方は
本人の生き方としてはナイフの上を歩くかのような痛みを伴うけれども
大勢の人を救うことになるのでしょう。
彼の生き方は、たとえ、世俗的には何も役に立っていないように見えても
そうではなく
あちらの世界に、沢山の人たちを安らかに送る、ということだけでも
たぶん、次の人生に生きるさまざまな魂を救い、ステージをあげたりあるいは
滑らかなものにする、大きな働きをしているはずです。
また、美津子のような人をも救っています。
美津子は、人を愛するということを知らない女性として書かれています。
その苦しみを自分のみで背負うのではなく、意識した上で、さらに人をも苦しめる。
私が最も苦手とするタイプです。悪魔のよう、とも感じます。
悪魔になった経緯については詳しくは書かれていませんが
悪魔なりの痛みが彼女にもあるということなのかもしれません。
でも、彼女には自身の内面を、ごまかさずに見つめて認める潔さがありました。
だからこそ、神の意思を引き寄せ
「神」の化身となっていく大津を、その対象に選ぶことができた。
美津子はこの後、どんな人生を辿るのでしょうか。
ふと、奴隷商人から、嵐の海で神に出会い神父になった、ジョン・ニュートン・・
アメイジング・グレイスの作曲者が浮かびました。
「悪魔」と「神」を大津の死によって両方自分自身の中に持つことになりそうな美津子・・・
そのふたつを統合させている人物はとても魅力的であり、人にも大きく影響します。
美津子を救い、美津子の人生に一緒に転生することでまた、別の何かを救おうとしている
それが大津の生き方なのかな・・・と
そんなことも感じました。
あらゆる痛みや苦しみを味わい、愛をさらに確信していく生き方は
本人の生き方としてはナイフの上を歩くかのような痛みを伴うけれども
大勢の人を救うことになるのでしょう。
彼の生き方は、たとえ、世俗的には何も役に立っていないように見えても
そうではなく
あちらの世界に、沢山の人たちを安らかに送る、ということだけでも
たぶん、次の人生に生きるさまざまな魂を救い、ステージをあげたりあるいは
滑らかなものにする、大きな働きをしているはずです。
また、美津子のような人をも救っています。
美津子は、人を愛するということを知らない女性として書かれています。
その苦しみを自分のみで背負うのではなく、意識した上で、さらに人をも苦しめる。
私が最も苦手とするタイプです。悪魔のよう、とも感じます。
悪魔になった経緯については詳しくは書かれていませんが
悪魔なりの痛みが彼女にもあるということなのかもしれません。
でも、彼女には自身の内面を、ごまかさずに見つめて認める潔さがありました。
だからこそ、神の意思を引き寄せ
「神」の化身となっていく大津を、その対象に選ぶことができた。
美津子はこの後、どんな人生を辿るのでしょうか。
ふと、奴隷商人から、嵐の海で神に出会い神父になった、ジョン・ニュートン・・
アメイジング・グレイスの作曲者が浮かびました。
「悪魔」と「神」を大津の死によって両方自分自身の中に持つことになりそうな美津子・・・
そのふたつを統合させている人物はとても魅力的であり、人にも大きく影響します。
美津子を救い、美津子の人生に一緒に転生することでまた、別の何かを救おうとしている
それが大津の生き方なのかな・・・と
そんなことも感じました。
沼田は、生きることの寂しさ、切なさを、心の肉に針のように入れたまま生きているけれど
それに立ち向かう強さを、まだ手に入れていないともいえます。
でもその痛みを少しづつでも癒していかなければ、
神に向かう強さは生まれてこないことでしょう。
それでも、ゆるやかに神に向かっているからこそ、
そうなるべき人生を辿った後インドに向かったと思えますし
また、彼の繊細さから生まれた童話は、同じような立場の人々を救っているかもしれません。
このこと自体も神のお計らいなのかもしれません。
時間がかかっても、あるいは次の人生までかかっても
沼田は神に出会う道を歩み続けるのではないでしょうか。
塚田の心が、私は一番理解が難しかった。
それは、彼が体験した悲惨さを実際に想像することが難しいからでしょう。
地獄絵巻のような世界から生きて帰ってきたとき、
人はこころの大きな部分を傷つけて、その後の生を生きることになるのでしょう。
それでも生き抜く術を身につけて生きた塚田、
それに押しつぶされていのちを落としていく木口
どちらも私にはよくわかりませんが、
どちらかというと木口のほうに感情移入できるのはどうしてなのでしょう。
ガストンという神の化身に彼が救われたのは死の直前ですが、
自身が救われるとともに、塚田にその救いのバトンを渡したともいえます。
三條は私自身が一番興味を持てない人物、ナルシストであり自分自身を一番と思い
それを疑うことをしない人物ですが、こういった人間は、実は一番幸せなのかもしれません。
最も、神とも悪魔とも遠い存在であると感じます。
そう思うと、悩み、苦しみ、痛み、疑い、自己嫌悪などの感情は
人を洗い清めるための神からの恵みとはいえないでしょうか。
磯部は私が一番感情移入でき、また愛しさも感じた存在でした。
彼は彼を心から愛して人生を捧げた妻の死によって、
気がつくことのなかった自分自身の愛情や
また「生活」ではない「人生」への扉を開かれたのですね。
それは、「救い」への扉。神への道の扉ともいえるものです。
ここの文章に涙ぐんだ私でした。
この世は集団ができると、対立が生じ、争いが作られ、相手を貶めるための策略が生まれる。
戦争と戦後の日本の中で生きてきた磯辺はそういう人間や集団を嫌というほど見てきた。正義という
言葉も聞きあきるほど耳にした。そしていつか心の底で、何も信じられぬという漠然とした気分がいつも残った。
だから会社の中で彼は愛想良く誰とも付き合ったが、その一人をも心の底から信じていなかった。それぞれの底には
それぞれのエゴイズムがあり、そのエゴイズムを糊装するために、善意だの正しい方向だのと主張していることを
実生活を通して承知していた。彼もそれを認めたうえで波風のたたぬ人生を送ってきたのだ。
だが、一人ぼっちになった今、磯辺は生活と人生が根本的に違うことがやっとわかってきた。
そして自分には生活のために交わった他人は多かったが、人生の中で本当に触れあった人間はたった二人
母親と妻しかいなかったことを認めざるを得なかった。
私は自分自身のCDに「ひとはふたつの人生を同時に生きると思います」
という文章を書きました。
たぶん、私は人生は沢山生きていると思いますが、生活の重さのほうは
私ではなく、主人が背負っている部分が多いのだと思います。
また、音楽の仕事で出会った数人の顔が浮かびました。
私は些細なことで、彼らを信じられない、許せないと思ったこともあるけれど
ふたつの人生の重さを必死で生きている人間としての、その人たちの心を思い浮かべたときに、
その想いが消えました。
理解でき、共感できれば、許すことはできるのですね。
そして、それぞれの人生を進むのだという、こころの中での別れを選択できます。
彼は彼を心から愛して人生を捧げた妻の死によって、
気がつくことのなかった自分自身の愛情や
また「生活」ではない「人生」への扉を開かれたのですね。
それは、「救い」への扉。神への道の扉ともいえるものです。
ここの文章に涙ぐんだ私でした。
この世は集団ができると、対立が生じ、争いが作られ、相手を貶めるための策略が生まれる。
戦争と戦後の日本の中で生きてきた磯辺はそういう人間や集団を嫌というほど見てきた。正義という
言葉も聞きあきるほど耳にした。そしていつか心の底で、何も信じられぬという漠然とした気分がいつも残った。
だから会社の中で彼は愛想良く誰とも付き合ったが、その一人をも心の底から信じていなかった。それぞれの底には
それぞれのエゴイズムがあり、そのエゴイズムを糊装するために、善意だの正しい方向だのと主張していることを
実生活を通して承知していた。彼もそれを認めたうえで波風のたたぬ人生を送ってきたのだ。
だが、一人ぼっちになった今、磯辺は生活と人生が根本的に違うことがやっとわかってきた。
そして自分には生活のために交わった他人は多かったが、人生の中で本当に触れあった人間はたった二人
母親と妻しかいなかったことを認めざるを得なかった。
私は自分自身のCDに「ひとはふたつの人生を同時に生きると思います」
という文章を書きました。
たぶん、私は人生は沢山生きていると思いますが、生活の重さのほうは
私ではなく、主人が背負っている部分が多いのだと思います。
また、音楽の仕事で出会った数人の顔が浮かびました。
私は些細なことで、彼らを信じられない、許せないと思ったこともあるけれど
ふたつの人生の重さを必死で生きている人間としての、その人たちの心を思い浮かべたときに、
その想いが消えました。
理解でき、共感できれば、許すことはできるのですね。
そして、それぞれの人生を進むのだという、こころの中での別れを選択できます。
人間は生きているうちに
いろいろな蠍に体を噛まれて、毒が回ることも
治りはしても傷を抱えて生きることになることも
あるでしょう。
また、ひとりの人間はこうである、と類型することも
難しいものです。いろいろな面があって当然ですし
それら全てでひとりの人はできている。
たとえば、全く魅力を感じなかった三條のような面も
私にはあるのだと思いますし。
美津子のような面も、あるのだと思います。
その自分のこころの中にある、ひとつひとつのものに
光をあてて読むことができ、いろいろな気づきを得ることが
できたことに、この本を読んだ意味を感じました。
人は神に向かって生きている。
こんなことを、はっきりと感じたことはありませんでしたが
私自身の内側の芯のひとつのようです。
拙い感想の文章に
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
いろいろな蠍に体を噛まれて、毒が回ることも
治りはしても傷を抱えて生きることになることも
あるでしょう。
また、ひとりの人間はこうである、と類型することも
難しいものです。いろいろな面があって当然ですし
それら全てでひとりの人はできている。
たとえば、全く魅力を感じなかった三條のような面も
私にはあるのだと思いますし。
美津子のような面も、あるのだと思います。
その自分のこころの中にある、ひとつひとつのものに
光をあてて読むことができ、いろいろな気づきを得ることが
できたことに、この本を読んだ意味を感じました。
人は神に向かって生きている。
こんなことを、はっきりと感じたことはありませんでしたが
私自身の内側の芯のひとつのようです。
拙い感想の文章に
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
清志朗さん
キリスト教の神は、間主観の神なのですよね。
西洋では、その間主観的な考え方に偏りすぎて、儀式やボランティア行為が形骸化してしまっている・・・というお話をセミナーでもしていただきました。キリスト教徒は当然のようにボランティア活動をするけれど、誰もそれを“愛の行為”だなどと思ってはいない・・・と。
その点、私は、遠藤周作氏はこの小説の中でその形骸化したキリスト教の儀式をリアルに生きようとしたのではないか・・・と思ったりもするのですよ。そして、それは、彼が東洋人であったが故の試みでもあったのかな・・・なんて思っています。
ところで、ユングのキリスト観は、案外、遠藤氏とよく似ていたのではないか・・・と私は思っています。
キリストをセルフの象徴にするあたり、神の内在の概念を思わせますし、そのセルフはキリストと反キリストを含むものだと言ったりもしていますから・・
遠藤氏も同じキリスト教徒として、ユングに慰めを得ていたのではないか・・・と推測してます。
でも、ユングは神の外在も肯定していたように私には思えます。
「シンクロシニティ」の考え方は、神の内在と外在を統合させる理論と捉えることはできないでしょうか。ウィルバー風に言うなら、神を4象限すべてに存在させようとした試みのように、私には思えるのですよ
キリスト教の神は、間主観の神なのですよね。
西洋では、その間主観的な考え方に偏りすぎて、儀式やボランティア行為が形骸化してしまっている・・・というお話をセミナーでもしていただきました。キリスト教徒は当然のようにボランティア活動をするけれど、誰もそれを“愛の行為”だなどと思ってはいない・・・と。
その点、私は、遠藤周作氏はこの小説の中でその形骸化したキリスト教の儀式をリアルに生きようとしたのではないか・・・と思ったりもするのですよ。そして、それは、彼が東洋人であったが故の試みでもあったのかな・・・なんて思っています。
ところで、ユングのキリスト観は、案外、遠藤氏とよく似ていたのではないか・・・と私は思っています。
キリストをセルフの象徴にするあたり、神の内在の概念を思わせますし、そのセルフはキリストと反キリストを含むものだと言ったりもしていますから・・
遠藤氏も同じキリスト教徒として、ユングに慰めを得ていたのではないか・・・と推測してます。
でも、ユングは神の外在も肯定していたように私には思えます。
「シンクロシニティ」の考え方は、神の内在と外在を統合させる理論と捉えることはできないでしょうか。ウィルバー風に言うなら、神を4象限すべてに存在させようとした試みのように、私には思えるのですよ
まり庵さん
遠藤周作氏は『深い河』を自分の最期の作品になるかもしれない・・・と考えていたと、私も思います。
日記だったかに“よくここまで身体がもってくれた”みたいなことも書いていましたし、久しぶりの純文学作品でしたからね・・・。そんなことを日大の先生(ゴーダマさん)もおっしゃっていました。
また、ゴーダマさんは、ガンジス川は本当に聖なる河として、インドの人々に受けとめられている、ともお話されていましたよ。
でも、死体を焼いて川に流す仕事はアウトカーストの仕事で、外国人がそこに手を出すと、歯まで折られてしまうほどボコボコにされるのだそうです。
ゴーダマ先生は、大津のそうした姿がイエスと重なる・・・ともおっしゃっていましたよ・・・。
それから、私たち日本人がガンジス川で沐浴するのはけっこう危険、ともおっしゃっていました。チフスや伝染病になることも多いのですって
沐浴するなら予防注射をいっぱい打っとかないといけないそうですよ。
さて、みち☆さんを先導役にインドに行ったあかつきには、シタールの演奏を聴きながら、自己の内面を旅してみるのも面白いかもしれませんね
遠藤周作氏は『深い河』を自分の最期の作品になるかもしれない・・・と考えていたと、私も思います。
日記だったかに“よくここまで身体がもってくれた”みたいなことも書いていましたし、久しぶりの純文学作品でしたからね・・・。そんなことを日大の先生(ゴーダマさん)もおっしゃっていました。
また、ゴーダマさんは、ガンジス川は本当に聖なる河として、インドの人々に受けとめられている、ともお話されていましたよ。
でも、死体を焼いて川に流す仕事はアウトカーストの仕事で、外国人がそこに手を出すと、歯まで折られてしまうほどボコボコにされるのだそうです。
ゴーダマ先生は、大津のそうした姿がイエスと重なる・・・ともおっしゃっていましたよ・・・。
それから、私たち日本人がガンジス川で沐浴するのはけっこう危険、ともおっしゃっていました。チフスや伝染病になることも多いのですって
沐浴するなら予防注射をいっぱい打っとかないといけないそうですよ。
さて、みち☆さんを先導役にインドに行ったあかつきには、シタールの演奏を聴きながら、自己の内面を旅してみるのも面白いかもしれませんね
ミネルバさん
>西洋では、その間主観的な考え方に偏りすぎて、儀式やボランティア行為が形骸化してしまっている・・・
>というお話をセミナーでもしていただきました。キリスト教徒は当然のようにボランティア活動をするけれど、
>誰もそれを“愛の行為”だなどと思ってはいない・・・と。
少し訂正です。
中世までは、間主観領域の神を信仰していたが、科学主義の台頭により、近代は客観領域が全てとなった。
その結果、間主観領域における大いなる他者に対する信仰や信愛が、客観世界における正義や倫理にすり替わっていったため、本来の意味が分からなくなっている。
ダライラマ法王は、こういったものを「世俗の倫理」と言ってました。
神という大いなる他者のいない世界観において、愛や慈悲は、世俗の倫理観によってなりたっていると言ってました。
しかしながら、こういった世俗の倫理観は、執着の罠から抜けられないので、非常に難しいと。
>西洋では、その間主観的な考え方に偏りすぎて、儀式やボランティア行為が形骸化してしまっている・・・
>というお話をセミナーでもしていただきました。キリスト教徒は当然のようにボランティア活動をするけれど、
>誰もそれを“愛の行為”だなどと思ってはいない・・・と。
少し訂正です。
中世までは、間主観領域の神を信仰していたが、科学主義の台頭により、近代は客観領域が全てとなった。
その結果、間主観領域における大いなる他者に対する信仰や信愛が、客観世界における正義や倫理にすり替わっていったため、本来の意味が分からなくなっている。
ダライラマ法王は、こういったものを「世俗の倫理」と言ってました。
神という大いなる他者のいない世界観において、愛や慈悲は、世俗の倫理観によってなりたっていると言ってました。
しかしながら、こういった世俗の倫理観は、執着の罠から抜けられないので、非常に難しいと。
ミネルバさん
神という言葉は、難しいですね。
間主観領域、つまり大いなる他者として現れた現象を、「神」といった方が、混乱がなくて良いと思います。
なので、
大いなる自己、セルフを超えた先にある大いなるものを、仏、仏性
大いなる他者を、神
大いなるそれを、宇宙、自然と読んでみました。
またセルフについて、遠藤氏が、
セルフ=意識+無意識
か?と河合氏に聞いたという話があったように思います。
凄く、おおざっぱには、これでもいいかと思いますが、正確には、これらは次元の異なる話が、混ざっていると思います。
つまり、意識、無意識は、心的領域に現れたものであり、
セルフは、それらを支える背後にある中心点、求心力のようなものだと思います。
遠藤氏と、河合氏の対談では、こういった説明は、きっとないのでしょうね。
残念だけれど。
神という言葉は、難しいですね。
間主観領域、つまり大いなる他者として現れた現象を、「神」といった方が、混乱がなくて良いと思います。
なので、
大いなる自己、セルフを超えた先にある大いなるものを、仏、仏性
大いなる他者を、神
大いなるそれを、宇宙、自然と読んでみました。
またセルフについて、遠藤氏が、
セルフ=意識+無意識
か?と河合氏に聞いたという話があったように思います。
凄く、おおざっぱには、これでもいいかと思いますが、正確には、これらは次元の異なる話が、混ざっていると思います。
つまり、意識、無意識は、心的領域に現れたものであり、
セルフは、それらを支える背後にある中心点、求心力のようなものだと思います。
遠藤氏と、河合氏の対談では、こういった説明は、きっとないのでしょうね。
残念だけれど。
清志朗さん
全体が神の現われである。。。その部分ではそのとおりなのですが、
大津を美津子が救ったのか。
私はそうは思いません。
美津子は彼にとって超える存在でしかなかった。
大津を救ったのは、美津子でなくて
彼のこころの中の神だったと思うのです。
きっかけは、美津子でしたけれども
美津子のことを最後まで想っていたとも思えません。
そして、美津子でなくても
誰であっても、何かの出来事で
彼は神に救われて解脱に向かったのではと
私は思っています。
ただ、美津子を救うことができたのは、大津だけでした。
彼女は自分の中に大津を住まわせることで、個性化への
可能性を得た。
大津はそうではないと思います。
男女の愛は執着でもあると思いますが、そういったものはもう超えた状態にいたと思われます。
最後に会ったとき、美津子に「後悔はしていません」
「あなたにもう生きて会うことはないと思います」と爽やかに答えています。
大津は、最後は三條の力で
生きるということをも、超えてしまった。
そう、きっかけは誰でも良かった。
ここで私が書いている「神」は、「大いなるすべての神」というものとは
すこし違って、人を救い解脱に向かわせる力、といったようなものですが
そこに到達して神と一体になったものが大津、
その前に位置して、少し進んだのが美津子・・
これが私の感じたことです。
東洋的ですね^^
全体が神の現われである。。。その部分ではそのとおりなのですが、
大津を美津子が救ったのか。
私はそうは思いません。
美津子は彼にとって超える存在でしかなかった。
大津を救ったのは、美津子でなくて
彼のこころの中の神だったと思うのです。
きっかけは、美津子でしたけれども
美津子のことを最後まで想っていたとも思えません。
そして、美津子でなくても
誰であっても、何かの出来事で
彼は神に救われて解脱に向かったのではと
私は思っています。
ただ、美津子を救うことができたのは、大津だけでした。
彼女は自分の中に大津を住まわせることで、個性化への
可能性を得た。
大津はそうではないと思います。
男女の愛は執着でもあると思いますが、そういったものはもう超えた状態にいたと思われます。
最後に会ったとき、美津子に「後悔はしていません」
「あなたにもう生きて会うことはないと思います」と爽やかに答えています。
大津は、最後は三條の力で
生きるということをも、超えてしまった。
そう、きっかけは誰でも良かった。
ここで私が書いている「神」は、「大いなるすべての神」というものとは
すこし違って、人を救い解脱に向かわせる力、といったようなものですが
そこに到達して神と一体になったものが大津、
その前に位置して、少し進んだのが美津子・・
これが私の感じたことです。
東洋的ですね^^
みっくんさま
ありがとうございます。みっくんさまの
>近ければ是非ミィ〜さんやみちさんにも出席していただきたかったです。
私のコメンテーターメモですが、ご参考までにそのままアップしておきます。
優しいお言葉とこのコメントが私のこころに深く浸み込み感涙しています。。ともすれば「深い河」の感動がこのみっくんさまの解説によってまた違ったこころの思いが波うち〜もっともっと深く極めたい気持ちが押し寄せてまいります。宗教においてはその国の民族性や
>その時代・地域・民族・文化・社会を背景に意識化された集合意識と考えられます。それは、人類に普遍的な無意識(見えない元型)である宗教性が、いろいろなイメージとなって意識化された姿と考えられます
その通りだと私も解釈しています。だから宗教の違いによって色んなご意見もありましょう・・・・・
でも私はこの阿弥陀仏を信じ手をあわし自分へのこころの安らぎを得たことにより毎日の拠り所を得たと思っています。
色んな方々のコメントを読ませて頂き、こんな解釈もあるのだ〜と!いろいろ思っています。
ただ私が信じる宗教には「因果報応」「転生輪廻」など確実にあるように思います。それゆえに現世において無鉄砲な行いをしてはいけないという自分へ戒めと、解釈しています。
すごくみっくんさまのこのコメントに、もっと知りたい!もっと深く探ってみたい
欲望に駆られています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。みっくんさまの
>近ければ是非ミィ〜さんやみちさんにも出席していただきたかったです。
私のコメンテーターメモですが、ご参考までにそのままアップしておきます。
優しいお言葉とこのコメントが私のこころに深く浸み込み感涙しています。。ともすれば「深い河」の感動がこのみっくんさまの解説によってまた違ったこころの思いが波うち〜もっともっと深く極めたい気持ちが押し寄せてまいります。宗教においてはその国の民族性や
>その時代・地域・民族・文化・社会を背景に意識化された集合意識と考えられます。それは、人類に普遍的な無意識(見えない元型)である宗教性が、いろいろなイメージとなって意識化された姿と考えられます
その通りだと私も解釈しています。だから宗教の違いによって色んなご意見もありましょう・・・・・
でも私はこの阿弥陀仏を信じ手をあわし自分へのこころの安らぎを得たことにより毎日の拠り所を得たと思っています。
色んな方々のコメントを読ませて頂き、こんな解釈もあるのだ〜と!いろいろ思っています。
ただ私が信じる宗教には「因果報応」「転生輪廻」など確実にあるように思います。それゆえに現世において無鉄砲な行いをしてはいけないという自分へ戒めと、解釈しています。
すごくみっくんさまのこのコメントに、もっと知りたい!もっと深く探ってみたい
欲望に駆られています。
ありがとうございます。
アンナさん
>キリスト教的か、仏教的かというのは、法王も言われるように、思想体系の違いであり、AQALでいうと視点の違いなわけですから、この視点の違いをしらないが故の対立であり、苦しみだと思うわけです。
>神なき愛の世俗倫理
激しく同意ありがとうございます。
ダライラマ法王の法話は、とてもシンプルで、明快で、奥が深いことをわかり易く伝えていました。
特に世俗の倫理についての話は、眼からウロコで、言われて見ればそうだなと深く関心しました。
でもほとんどの人は、この法話は、難しかったらしいです。
日本人特有だな〜と思いましたが。
法王がさらに言っていたことは、知恵をつけよ、勉強せよということでした。
知恵をつけずして、浸っているだけではなんにもならないと。
つまりどんなに素晴らしい体験を仮にしたとしても、それを理解できる知識がとても重要だということをなんどもなんども言ってました。
とっても腑に落ちる言葉だったです。
でも質問者の話を聞いていると、あ〜〜あ、という感じでしたけどね。
>キリスト教的か、仏教的かというのは、法王も言われるように、思想体系の違いであり、AQALでいうと視点の違いなわけですから、この視点の違いをしらないが故の対立であり、苦しみだと思うわけです。
>神なき愛の世俗倫理
激しく同意ありがとうございます。
ダライラマ法王の法話は、とてもシンプルで、明快で、奥が深いことをわかり易く伝えていました。
特に世俗の倫理についての話は、眼からウロコで、言われて見ればそうだなと深く関心しました。
でもほとんどの人は、この法話は、難しかったらしいです。
日本人特有だな〜と思いましたが。
法王がさらに言っていたことは、知恵をつけよ、勉強せよということでした。
知恵をつけずして、浸っているだけではなんにもならないと。
つまりどんなに素晴らしい体験を仮にしたとしても、それを理解できる知識がとても重要だということをなんどもなんども言ってました。
とっても腑に落ちる言葉だったです。
でも質問者の話を聞いていると、あ〜〜あ、という感じでしたけどね。
はじめまして。最近、このコミュに入って、ご挨拶もせずにROMってました。これは場をわきまえない発言だと思いますので、管理人様の判断で削除していただいてもかまいません。
私は神学やさんなので、その立場からいくつか。あ、神学やのユンギアンなら樋口先生がいますけど。
遠藤周作はユングをかなり読んでいました。これについて、井上洋治神父と対談というより論争していたのを読んだことがありますが、読み込みは足りないんじゃないの?という印象。また遠藤周作はウィルバーも読んでます、同じ本で、訳者と対談していましたが、これも読み込みが足らない感じ。
諸宗教間対話というのはもう、ここ50年くらい神学などの分野で非常に重要なセクションでした。現実に神父さんとお坊さんが何度も交流会や学術会議をひらいています。ここから出てきたのがジョン・ヒックというイギリスの宗教学者でして、この人は諸宗教間対話の中ではちょっと異端視されているんですけど、遠藤周作は『深い河』執筆にあたって、この学説を強く取り入れています。
あと日本らしいキリスト教は、昔から言われていることでして、遠藤の独創ではないのです。遠藤は文学者としてその一つの形を提示したにすぎません。
日本人クリスチャンが、仏教のお坊さんに「いいなぁ」と言うと、勉強した真面目なお坊さんなら「いやいや、仏教は所詮外来宗教でして、長い間間借りしているだけですよ」とおっしゃいます。
それから遠藤はカトリック、ユング家は長老派(カルヴァン)ですので、宗教思想の背景はかなり違います。ちなみにユング『ヨブへの答え』を批判したスイスの神学者カール・バルトも長老派です。
では、失礼いたしました
私は神学やさんなので、その立場からいくつか。あ、神学やのユンギアンなら樋口先生がいますけど。
遠藤周作はユングをかなり読んでいました。これについて、井上洋治神父と対談というより論争していたのを読んだことがありますが、読み込みは足りないんじゃないの?という印象。また遠藤周作はウィルバーも読んでます、同じ本で、訳者と対談していましたが、これも読み込みが足らない感じ。
諸宗教間対話というのはもう、ここ50年くらい神学などの分野で非常に重要なセクションでした。現実に神父さんとお坊さんが何度も交流会や学術会議をひらいています。ここから出てきたのがジョン・ヒックというイギリスの宗教学者でして、この人は諸宗教間対話の中ではちょっと異端視されているんですけど、遠藤周作は『深い河』執筆にあたって、この学説を強く取り入れています。
あと日本らしいキリスト教は、昔から言われていることでして、遠藤の独創ではないのです。遠藤は文学者としてその一つの形を提示したにすぎません。
日本人クリスチャンが、仏教のお坊さんに「いいなぁ」と言うと、勉強した真面目なお坊さんなら「いやいや、仏教は所詮外来宗教でして、長い間間借りしているだけですよ」とおっしゃいます。
それから遠藤はカトリック、ユング家は長老派(カルヴァン)ですので、宗教思想の背景はかなり違います。ちなみにユング『ヨブへの答え』を批判したスイスの神学者カール・バルトも長老派です。
では、失礼いたしました
>けろりんさん
情報ありがとう。私は漫画に疎いので、知らなかったのですが、興味ありますね。でも探すのむずかしそうですね。
>清志朗さん
エロスとロゴス、双方使いこなしたいもんです。まだ間に合うかしら(汗)
たしかに永遠のおっかけっこ・・って感じはしますが、きっと両立させている人もいるんでしょう。
>みっしぇるさん
はじめまして。
私はプロテスタントの学校で教育を受けたのですが、遠藤周作の、たとえば「沈黙」に関しては、聖書の先生(牧師さん)たちは否定的でした。
プロテスタントとカトリックでは違いがあるのかもしれませんね。しかし、カトリックでも一時期、「遠藤周作の本は読むな」と言われてた時期があったと聞いてます。
長崎の隠れキリシタンの末えい・・という友人に話を聞いたら、生き残るために、土着のものと混じり合ったのかな、という印象を受けました。そういう意味では、たしかに遠藤さんが最初に言いだしたのではないですね。
しかし、キリスト教になじみがないほとんどの日本人に、文学という形でも、少しキリスト教を近づけた(と言っていいかわからないけれど)遠藤さんの功績は大きかったかな、という気はします。
情報ありがとう。私は漫画に疎いので、知らなかったのですが、興味ありますね。でも探すのむずかしそうですね。
>清志朗さん
エロスとロゴス、双方使いこなしたいもんです。まだ間に合うかしら(汗)
たしかに永遠のおっかけっこ・・って感じはしますが、きっと両立させている人もいるんでしょう。
>みっしぇるさん
はじめまして。
私はプロテスタントの学校で教育を受けたのですが、遠藤周作の、たとえば「沈黙」に関しては、聖書の先生(牧師さん)たちは否定的でした。
プロテスタントとカトリックでは違いがあるのかもしれませんね。しかし、カトリックでも一時期、「遠藤周作の本は読むな」と言われてた時期があったと聞いてます。
長崎の隠れキリシタンの末えい・・という友人に話を聞いたら、生き残るために、土着のものと混じり合ったのかな、という印象を受けました。そういう意味では、たしかに遠藤さんが最初に言いだしたのではないですね。
しかし、キリスト教になじみがないほとんどの日本人に、文学という形でも、少しキリスト教を近づけた(と言っていいかわからないけれど)遠藤さんの功績は大きかったかな、という気はします。
>まり庵さん
はじめまして。そうですね、今でも遠藤文学に否定的なクリスチャンはカトリックにもプロテスタントにもいます。むしろ、海外での評価の方が高いんじゃないかな。カトリックは元々、土着的だと思います。キリスト教に対する遠藤の功績は確かに大きいですね。ただ、どうだろう?たとえば『沈黙』と、『深い河』はやっぱり違いはあるなんじゃないかなぁ。それを先鋭化したととるか、退化したととるかは分かれるけど。
カトリックとプロテスタントという分類もそうですけど、プロテスタントでもルターとカルヴァンじゃだいぶ違いますからねぇ・・・。他にも正教会系とか英国国教会系とかまた違うし・・・。
ユングといえば、ユングによるカトリックのミサの象徴を解説したやつがありますけど、ユングの頃と現在のカトリックのミサは色々変化している部分もあるからなぁ・・・どうなんだろう。
はじめまして。そうですね、今でも遠藤文学に否定的なクリスチャンはカトリックにもプロテスタントにもいます。むしろ、海外での評価の方が高いんじゃないかな。カトリックは元々、土着的だと思います。キリスト教に対する遠藤の功績は確かに大きいですね。ただ、どうだろう?たとえば『沈黙』と、『深い河』はやっぱり違いはあるなんじゃないかなぁ。それを先鋭化したととるか、退化したととるかは分かれるけど。
カトリックとプロテスタントという分類もそうですけど、プロテスタントでもルターとカルヴァンじゃだいぶ違いますからねぇ・・・。他にも正教会系とか英国国教会系とかまた違うし・・・。
ユングといえば、ユングによるカトリックのミサの象徴を解説したやつがありますけど、ユングの頃と現在のカトリックのミサは色々変化している部分もあるからなぁ・・・どうなんだろう。
>みっしぇるさん
おはようございます。そうですね、おっしゃるとおり、たしかに「深い河」と「沈黙」は違いますね。「深い河」が集大成のような気がしたので、「沈黙」で描きたかったことも含まれるのかな、とは思ったのですが・・。世界観はたしかに違いますね。
たしかに、プロテスタントもいろいろありますね。日本人は、たとえばバプティスト、エピスコパル・・だの、そういう違い言っても、あまりピンとこないでしょうね。カトリックとプロテスタントの違いさえわかってない人が多いし、無理はないかな、と思います。キリスト教系の学校を出ても、神父と牧師で、どっちがどっちかわかってない知人もいましたしね・・。それにオーソドックスがはいったらお手上げでしょうね。
>アンナさん
「沈黙」は時代背景もあるし、現代とはかなり違ってるけれど、でも、現代に通じるところもあるでしょうから、たしかにキリスト教圏の人にとっては、「文化を学ぶ」テキストになるんでしょうね。
>けろりんさん
聖娼・・ですか。いいな・・なんかこの響き、何かびびっときちゃいました。
めざそう・・と言っても、なれるもんではなさそう(^^;)
色々と調べてみます。ありがとう。
取り急ぎ、だだっとレス、書き散らかしで、失礼します。
おはようございます。そうですね、おっしゃるとおり、たしかに「深い河」と「沈黙」は違いますね。「深い河」が集大成のような気がしたので、「沈黙」で描きたかったことも含まれるのかな、とは思ったのですが・・。世界観はたしかに違いますね。
たしかに、プロテスタントもいろいろありますね。日本人は、たとえばバプティスト、エピスコパル・・だの、そういう違い言っても、あまりピンとこないでしょうね。カトリックとプロテスタントの違いさえわかってない人が多いし、無理はないかな、と思います。キリスト教系の学校を出ても、神父と牧師で、どっちがどっちかわかってない知人もいましたしね・・。それにオーソドックスがはいったらお手上げでしょうね。
>アンナさん
「沈黙」は時代背景もあるし、現代とはかなり違ってるけれど、でも、現代に通じるところもあるでしょうから、たしかにキリスト教圏の人にとっては、「文化を学ぶ」テキストになるんでしょうね。
>けろりんさん
聖娼・・ですか。いいな・・なんかこの響き、何かびびっときちゃいました。
めざそう・・と言っても、なれるもんではなさそう(^^;)
色々と調べてみます。ありがとう。
取り急ぎ、だだっとレス、書き散らかしで、失礼します。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-