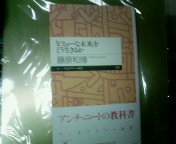今年度もまたフリージアのよのなか科が始まりました。
また新しい学校でのチャレンジです。
「よのなか科通信」第1号をお届けします。
今回は、職員室の先生方にも配布するということで、
まずは、よのなか科とはという特集から入りました。
「よのなか科」通信は、○○中学校選択社会の授業報告です。
【よのなか科とは?】
よのなか科は、東京都で初めて義務教育民間人校長となった藤原和博先生(前杉並区立和田中学校校長、現在は大阪府知事教育政策特別顧問)が始めた授業です。大阪では「こころざし科」。
よのなか科で扱う題材は世の中すべてです。20世紀成長社会といわれた時代には、みんなが一緒でいることを求められました。そこでは、正解主義といわれる、情報処理力(TIMSS型学力)が重視されました。しかし、21世紀になり、社会が成熟社会となり、経済成長も頭打ちの時代が到来し、今までのような正解を求めていく教育だけではなく、さらに、修正主義といわれる、情報編集力(PISA型学力)が求められるようになりました。これは、問題解決に正解はなく、それぞれが納得する解答、すなわち「納得解」を導き出すことが求められるようになりました。この「納得解」を導き出すのが、よのなか科のめざすところでもあります。今までの「読み・書き・そろばん」のような、知識を覚えて使うといった情報処理力だけではなく、さまざまな知識や情報を自分の視点で編集し、自分の頭で考えて結論を導き出す情報編集力を身につけることを目標としています。
このよのなか科の授業では、正解が一つではありません。いろいろな問題を提起して、生徒たちが地域の方や、学生などの身近な大人と一緒に議論しながら学んでいきます。その手法として、ディベートで、論理的思考力や他者とのコミュニケーション力を育成したり、ロールプレイと呼ばれるゲーム的な手法を用い、自分とは違う人の視点に立って考えさせたりします。それらは、Critical Thinking(複眼的思考)といわれ、物事を多面的に見ることを目的としています。そして、そのテーマに沿った。ゲストをお招きし、本物とふれる機会を与えることも大事な要素です。
現在、このよのなか科はネットワーク型授業とも呼ばれ、文部科学省の地域本部の立ち上げとともに、予算がついている事業です。そして、このようなネットワーク型授業の実施の推進がコミュニティスクールの拡大と共に、閣議決定されました。
知識を獲得する授業は絶対に必要です。そして、これからの成熟社会を生き抜く人材育成にとって、
正解のない、複眼的思考を育成する授業が求められています。
「コンテンツの紹介その1」 ハンバーガー店の店長になろう。
自分が、ハンバーガー店の店長だったら、与えられた地図上のどこに出店をするのかを考えるという授業。出店するにあたって、どのような場所を選ぶのか、その選んだ理由も含めて自分の考えをまとめていく。出店に際して、どのような要件をみなければいけないのかということを、考える授業。
「コンテンツの紹介その2」 中学生はもう大人?まだ子ども?6回シリーズの授業
(1)あなたに関わる経済と法律 (2)イギリス・バルがー事件から少年法を考える (3)少年の社会に対する責任について (4)模擬少年審判廷 (5)同じ事件が成人だったら模擬刑事裁判 (6)犯罪被害者の家族 など、コミュニケーション力やプレゼンテーション力の育成や、他者あるいは社会に目を向ける姿勢を育むことも目的としている。
【よのなか科ガイダンス】 5月27日(水)第2校時
今年度のよのなか科を選択した生徒は、男子14人、女子12人の計26人です。人数、男女比も非常にバランスの取れたクラスとなりました。教室は、グループ活動がしやすいように、図書室を使用させていただくことにしました。今年度、初めて、座席をこちらで指定しました。今までは、みんなで話し合ったり、じゃんけんだったり、生徒たちの自主性で決まっていたのですが、自分が望んだ席では(グループ)ではない状態で、どの程度コミュニケーションをとることができるのかと、あえて、席をこちらから指定しました。
図書室に入ってきた生徒たちは、座席が決められていることに、少々戸惑いや、不満をもらしました。しかし、初対面ということもあり、私に対してのブーイングはほとんどでませんでした。
まず、授業の開始にあたって、よのなか科とはいう説明をし、よのなか科とはどんなものかを体感するアイスブレイクを行いました。生徒たちに一枚の用紙を渡しました。そして、ただ、二つに折ってくださいと3回言い続けました。それだけ折って、その用紙の2箇所をちぎってくださいと指示を出しました。そして、ちぎった後に、折りたたんだ用紙を広げてもらいました。生徒たちの用紙は、誰一人として同じにちぎっているものはなく、それぞれカタチも大きさもばらばらの穴が開いています。これこそがよのなか科なのです。その後、よのなか科にとって大事な自己紹介をやってもらいました。一人1分。どれだけ、人に自分の印象を残せるのか、先日のよのなか科の集まりの時の、元教え子の自己紹介を披露しました。元教え子は、自分の名前と顔の特徴をひっかけて、見事に初対面の人にインパクトを与えました。しかし、現実には、なかなか難しい自己紹介で、生徒たちは、悪戦苦闘でした。多分、これが1年間の授業をうけたあとでは、自己紹介もかわってくるものと思われます。一人ひとりの自己紹介のあとの拍手の練習もしました。なかなか温かい拍手の音がでません。何度かの練習でずいぶんと拍手もいい音がでるようになりました。
最後に、用意したワークシートの記入をしてもらいました。生徒たちが記入したものです。。
【この授業を選んだ理由】
○興味があったから ○社会が一番ましだと思ったから ○ハンバーガー屋さんの授業がおもしろそうだったから ○社会といっても勉強じゃなかったから ○とくになし ○友達が選んでいたから
【この授業でどのようなことを期待していますか】
○あまりなし ○楽しく授業を受けたい ○自分が出せるようになりたい ○みんなで楽しく笑えること ○未来にむけて ○話す力をつける ○いっぱい発言をしてみんなにわかってほしい。
【この授業でどのようなことを身につけたいと思いますか】
○伝える力 ○自分の意見を言えるようにしたい ○本当の自分を出したい ○自己紹介で緊張しないようになりたい ○話す力をつけたい ○考えたことを文章にしたり、発表するということが得意じゃないのでそれができるようになりたい ○コミュニケーション力をつけたい ○世の中の仕組みを理解したい
次回授業のご案内 第1回 「今の自分」を知ろう PISAの学力調査から
6月3日(水)2校時 9時50分から10時35分(45分授業) ○○中学校3階図書室
また新しい学校でのチャレンジです。
「よのなか科通信」第1号をお届けします。
今回は、職員室の先生方にも配布するということで、
まずは、よのなか科とはという特集から入りました。
「よのなか科」通信は、○○中学校選択社会の授業報告です。
【よのなか科とは?】
よのなか科は、東京都で初めて義務教育民間人校長となった藤原和博先生(前杉並区立和田中学校校長、現在は大阪府知事教育政策特別顧問)が始めた授業です。大阪では「こころざし科」。
よのなか科で扱う題材は世の中すべてです。20世紀成長社会といわれた時代には、みんなが一緒でいることを求められました。そこでは、正解主義といわれる、情報処理力(TIMSS型学力)が重視されました。しかし、21世紀になり、社会が成熟社会となり、経済成長も頭打ちの時代が到来し、今までのような正解を求めていく教育だけではなく、さらに、修正主義といわれる、情報編集力(PISA型学力)が求められるようになりました。これは、問題解決に正解はなく、それぞれが納得する解答、すなわち「納得解」を導き出すことが求められるようになりました。この「納得解」を導き出すのが、よのなか科のめざすところでもあります。今までの「読み・書き・そろばん」のような、知識を覚えて使うといった情報処理力だけではなく、さまざまな知識や情報を自分の視点で編集し、自分の頭で考えて結論を導き出す情報編集力を身につけることを目標としています。
このよのなか科の授業では、正解が一つではありません。いろいろな問題を提起して、生徒たちが地域の方や、学生などの身近な大人と一緒に議論しながら学んでいきます。その手法として、ディベートで、論理的思考力や他者とのコミュニケーション力を育成したり、ロールプレイと呼ばれるゲーム的な手法を用い、自分とは違う人の視点に立って考えさせたりします。それらは、Critical Thinking(複眼的思考)といわれ、物事を多面的に見ることを目的としています。そして、そのテーマに沿った。ゲストをお招きし、本物とふれる機会を与えることも大事な要素です。
現在、このよのなか科はネットワーク型授業とも呼ばれ、文部科学省の地域本部の立ち上げとともに、予算がついている事業です。そして、このようなネットワーク型授業の実施の推進がコミュニティスクールの拡大と共に、閣議決定されました。
知識を獲得する授業は絶対に必要です。そして、これからの成熟社会を生き抜く人材育成にとって、
正解のない、複眼的思考を育成する授業が求められています。
「コンテンツの紹介その1」 ハンバーガー店の店長になろう。
自分が、ハンバーガー店の店長だったら、与えられた地図上のどこに出店をするのかを考えるという授業。出店するにあたって、どのような場所を選ぶのか、その選んだ理由も含めて自分の考えをまとめていく。出店に際して、どのような要件をみなければいけないのかということを、考える授業。
「コンテンツの紹介その2」 中学生はもう大人?まだ子ども?6回シリーズの授業
(1)あなたに関わる経済と法律 (2)イギリス・バルがー事件から少年法を考える (3)少年の社会に対する責任について (4)模擬少年審判廷 (5)同じ事件が成人だったら模擬刑事裁判 (6)犯罪被害者の家族 など、コミュニケーション力やプレゼンテーション力の育成や、他者あるいは社会に目を向ける姿勢を育むことも目的としている。
【よのなか科ガイダンス】 5月27日(水)第2校時
今年度のよのなか科を選択した生徒は、男子14人、女子12人の計26人です。人数、男女比も非常にバランスの取れたクラスとなりました。教室は、グループ活動がしやすいように、図書室を使用させていただくことにしました。今年度、初めて、座席をこちらで指定しました。今までは、みんなで話し合ったり、じゃんけんだったり、生徒たちの自主性で決まっていたのですが、自分が望んだ席では(グループ)ではない状態で、どの程度コミュニケーションをとることができるのかと、あえて、席をこちらから指定しました。
図書室に入ってきた生徒たちは、座席が決められていることに、少々戸惑いや、不満をもらしました。しかし、初対面ということもあり、私に対してのブーイングはほとんどでませんでした。
まず、授業の開始にあたって、よのなか科とはいう説明をし、よのなか科とはどんなものかを体感するアイスブレイクを行いました。生徒たちに一枚の用紙を渡しました。そして、ただ、二つに折ってくださいと3回言い続けました。それだけ折って、その用紙の2箇所をちぎってくださいと指示を出しました。そして、ちぎった後に、折りたたんだ用紙を広げてもらいました。生徒たちの用紙は、誰一人として同じにちぎっているものはなく、それぞれカタチも大きさもばらばらの穴が開いています。これこそがよのなか科なのです。その後、よのなか科にとって大事な自己紹介をやってもらいました。一人1分。どれだけ、人に自分の印象を残せるのか、先日のよのなか科の集まりの時の、元教え子の自己紹介を披露しました。元教え子は、自分の名前と顔の特徴をひっかけて、見事に初対面の人にインパクトを与えました。しかし、現実には、なかなか難しい自己紹介で、生徒たちは、悪戦苦闘でした。多分、これが1年間の授業をうけたあとでは、自己紹介もかわってくるものと思われます。一人ひとりの自己紹介のあとの拍手の練習もしました。なかなか温かい拍手の音がでません。何度かの練習でずいぶんと拍手もいい音がでるようになりました。
最後に、用意したワークシートの記入をしてもらいました。生徒たちが記入したものです。。
【この授業を選んだ理由】
○興味があったから ○社会が一番ましだと思ったから ○ハンバーガー屋さんの授業がおもしろそうだったから ○社会といっても勉強じゃなかったから ○とくになし ○友達が選んでいたから
【この授業でどのようなことを期待していますか】
○あまりなし ○楽しく授業を受けたい ○自分が出せるようになりたい ○みんなで楽しく笑えること ○未来にむけて ○話す力をつける ○いっぱい発言をしてみんなにわかってほしい。
【この授業でどのようなことを身につけたいと思いますか】
○伝える力 ○自分の意見を言えるようにしたい ○本当の自分を出したい ○自己紹介で緊張しないようになりたい ○話す力をつけたい ○考えたことを文章にしたり、発表するということが得意じゃないのでそれができるようになりたい ○コミュニケーション力をつけたい ○世の中の仕組みを理解したい
次回授業のご案内 第1回 「今の自分」を知ろう PISAの学力調査から
6月3日(水)2校時 9時50分から10時35分(45分授業) ○○中学校3階図書室
|
|
|
|
|
|
|
|
よのなか科 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-