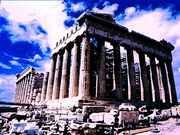平間のミニ講義 − ソクラテス以前の哲学
前書きとなりますが、プラトンの饗宴のミニ講義が好評だったので、暇を持て余しているということもあり、ちょっとだけソクラテス以前の哲学について語りたいと思います。 ちなみに私は講師をした時に単に暗記させてテストで覚えているかってことは全くしませんでした。 たとえばこんな文があるとします。
“Ich weiß nicht, was sol les bedeuten, Daß ich so traurig bin.”
ドイツのローレライという詩の冒頭に出てくる有名な一節ですが、ドイツ語をまったく知らない人でも暗記したり朗読はできるんです。 哲学はそんなもんではないと私は確信しているので、もっと内容理解と、私自身が大切にしている「あっ、しらなかった」という驚きをミニ講義で感じていただければ幸いです。
「食後にすぐ寝ると牛になる」ってみなさんいわれたとします。 私ならぐさっときますが。 それは別にしてあれは比ゆっていいます。 例えのことです。 ちょっと詳しくやると直喩と暗喩の二つがあるんですが、哲学での例えの定義は簡単に言うとこうなります。 「文字どおりに捉えると変な意味になったり、ばからしくなるんです。」 初めの文に戻ってみましょう。 「食後にすぐ寝ると牛になる。」 そのまま捉えたら人が本当にモーっていう牛になったら恐ろしいです。 あの文の意味は、食後に寝ると太るって意味です。 例えはそのまま受け取ると変な意味ですが、ちゃんと本当の意味があるんですよって覚えておいてください。 もうちょっとだけ皆さんを押します。 変な意味があるものを聞いたら、変な意味は何かの例えだから、ちゃんとした意味があるんですよって気もに銘じていてくださいね。
ターレスがすべてのものは水であるっていいました。 哲学1年生の方は「なんじゃこりぁ?」なんて思うのも当然です。 教科書の説明をちょっと書きます。 ターレスは人類で初めて、迷信や神話などに頼らずに自分の論理を使って物事を説明したので哲学者ですって書いてあるとおもいますが、ここまでできたら50点。 だからといって水っていう答えは変じゃないかと思う方がいます。 そういう方は、水って本気に鵜呑みにしちゃったからなんです。 だからここから先は例えだったと思ってその本当の意味を探すんですね。 (たぶんターレスは本気で水って思っていたと思いますが)
哲学に還元主義ってあります。 英語で言うとReductionismです。 簡単に言うと「身の回りにはいろんなものがあるますが、それを簡単に単純で便利な説明してみましょう」って考えです。 還元主義を使った代表的なものは化学で出てくる原子の周期表です。 水素、ヘリウムって具合のやつです。 身の回りの物はそれら原子の集まりでできているんですが、それら一つ一つまったく別な名前で呼ぶことできますか。 たとえばつまようじ1000本にひとつひとつ別の名前を付けていくようなこと。 普通の人は出来ませんよね。 つまようじ1000本、いっぱいあるけど、あれは木でできてますとか、木は酸素、炭素などの原子でできてますって具合に身の回りの物すべてが簡単なものでできているんだよって説明ができるんです。 それが還元主義。
還元主義にも3種類あって、すべてのものは一つのものからできているって極端にしたものを一元論 monism, 二つあると唱える二元四 dualism, そして化学の周期表のように3つ以上あるものをすべて多元論 pluralism っていうんです。 ターレスは一番還元主義を突き進めて一元論をとったので、世界中にあるもの建物、動物、砂、人間などはすべて水からくるっていったんです。 だからといって水じゃ変だって思い人のために答えを用意しております。
経験主義 Empiricism と合理主義 Rationalismについてです。 すごーく簡単にいえば経験主義は見たのも体験したものが本物で、合理主義は見たものや体験したものに頭を使って考えたものが本物っていうんです。 たとえばこたつの上にミカンがあるとします。 ミカンが見えたので、ミカンがこたつの上にあるっていえます。 典型的な経験主義の発想です。 さて、さばくでみえる蜃気楼はどうでしょうか。 遠くに湖が見えますが、あると思って追いかけたらあなたの最後です。 見えているけど、頭を使って考えたものが本物です。 ちなみに懐疑主義といってSkepticism (米)・Scepticism (英)がありますが、これば別の機会に。
ターレスは合理主義だったから別にオリーブが100個あろうがうまが5000頭いようが目で見たものを鵜呑みにしないで、そこに一元主義を足して水がすべての元となるっておもったんです。
ここまできて水ではちがうんじゃないかと思う方がいます。 素晴らしい。 ただ2600年以上も前にいたターレス。 そこはちょっとだけ簡便してあげてねといっても納得しない方のためにスペシャルで次の物を用意しました。
みなさんアインシュタインの相対性理論って聞いたことありますよね。 有名なやつがE=MC2です。 ご心配なく。 計算機は使いません。 あれはたとえばこたつの上のミカンを光の速度で飛ばしたら、純粋なエネルギーに代わってしまいますよって意味なんです。 身の回りの物、人、車、ネコ、こたつ、みかんなどなどすべてのものは光の速度まで加速するとエネルギーになっちゃうんです。 つまりすべてのものはエネルギーからできているって言ったら、これも一元十義ですよね。 2600年前のターレスはエネルギーとは言えなかったけど、水とはいった。 これはすごいことじゃないでしょうか。
前書きとなりますが、プラトンの饗宴のミニ講義が好評だったので、暇を持て余しているということもあり、ちょっとだけソクラテス以前の哲学について語りたいと思います。 ちなみに私は講師をした時に単に暗記させてテストで覚えているかってことは全くしませんでした。 たとえばこんな文があるとします。
“Ich weiß nicht, was sol les bedeuten, Daß ich so traurig bin.”
ドイツのローレライという詩の冒頭に出てくる有名な一節ですが、ドイツ語をまったく知らない人でも暗記したり朗読はできるんです。 哲学はそんなもんではないと私は確信しているので、もっと内容理解と、私自身が大切にしている「あっ、しらなかった」という驚きをミニ講義で感じていただければ幸いです。
「食後にすぐ寝ると牛になる」ってみなさんいわれたとします。 私ならぐさっときますが。 それは別にしてあれは比ゆっていいます。 例えのことです。 ちょっと詳しくやると直喩と暗喩の二つがあるんですが、哲学での例えの定義は簡単に言うとこうなります。 「文字どおりに捉えると変な意味になったり、ばからしくなるんです。」 初めの文に戻ってみましょう。 「食後にすぐ寝ると牛になる。」 そのまま捉えたら人が本当にモーっていう牛になったら恐ろしいです。 あの文の意味は、食後に寝ると太るって意味です。 例えはそのまま受け取ると変な意味ですが、ちゃんと本当の意味があるんですよって覚えておいてください。 もうちょっとだけ皆さんを押します。 変な意味があるものを聞いたら、変な意味は何かの例えだから、ちゃんとした意味があるんですよって気もに銘じていてくださいね。
ターレスがすべてのものは水であるっていいました。 哲学1年生の方は「なんじゃこりぁ?」なんて思うのも当然です。 教科書の説明をちょっと書きます。 ターレスは人類で初めて、迷信や神話などに頼らずに自分の論理を使って物事を説明したので哲学者ですって書いてあるとおもいますが、ここまでできたら50点。 だからといって水っていう答えは変じゃないかと思う方がいます。 そういう方は、水って本気に鵜呑みにしちゃったからなんです。 だからここから先は例えだったと思ってその本当の意味を探すんですね。 (たぶんターレスは本気で水って思っていたと思いますが)
哲学に還元主義ってあります。 英語で言うとReductionismです。 簡単に言うと「身の回りにはいろんなものがあるますが、それを簡単に単純で便利な説明してみましょう」って考えです。 還元主義を使った代表的なものは化学で出てくる原子の周期表です。 水素、ヘリウムって具合のやつです。 身の回りの物はそれら原子の集まりでできているんですが、それら一つ一つまったく別な名前で呼ぶことできますか。 たとえばつまようじ1000本にひとつひとつ別の名前を付けていくようなこと。 普通の人は出来ませんよね。 つまようじ1000本、いっぱいあるけど、あれは木でできてますとか、木は酸素、炭素などの原子でできてますって具合に身の回りの物すべてが簡単なものでできているんだよって説明ができるんです。 それが還元主義。
還元主義にも3種類あって、すべてのものは一つのものからできているって極端にしたものを一元論 monism, 二つあると唱える二元四 dualism, そして化学の周期表のように3つ以上あるものをすべて多元論 pluralism っていうんです。 ターレスは一番還元主義を突き進めて一元論をとったので、世界中にあるもの建物、動物、砂、人間などはすべて水からくるっていったんです。 だからといって水じゃ変だって思い人のために答えを用意しております。
経験主義 Empiricism と合理主義 Rationalismについてです。 すごーく簡単にいえば経験主義は見たのも体験したものが本物で、合理主義は見たものや体験したものに頭を使って考えたものが本物っていうんです。 たとえばこたつの上にミカンがあるとします。 ミカンが見えたので、ミカンがこたつの上にあるっていえます。 典型的な経験主義の発想です。 さて、さばくでみえる蜃気楼はどうでしょうか。 遠くに湖が見えますが、あると思って追いかけたらあなたの最後です。 見えているけど、頭を使って考えたものが本物です。 ちなみに懐疑主義といってSkepticism (米)・Scepticism (英)がありますが、これば別の機会に。
ターレスは合理主義だったから別にオリーブが100個あろうがうまが5000頭いようが目で見たものを鵜呑みにしないで、そこに一元主義を足して水がすべての元となるっておもったんです。
ここまできて水ではちがうんじゃないかと思う方がいます。 素晴らしい。 ただ2600年以上も前にいたターレス。 そこはちょっとだけ簡便してあげてねといっても納得しない方のためにスペシャルで次の物を用意しました。
みなさんアインシュタインの相対性理論って聞いたことありますよね。 有名なやつがE=MC2です。 ご心配なく。 計算機は使いません。 あれはたとえばこたつの上のミカンを光の速度で飛ばしたら、純粋なエネルギーに代わってしまいますよって意味なんです。 身の回りの物、人、車、ネコ、こたつ、みかんなどなどすべてのものは光の速度まで加速するとエネルギーになっちゃうんです。 つまりすべてのものはエネルギーからできているって言ったら、これも一元十義ですよね。 2600年前のターレスはエネルギーとは言えなかったけど、水とはいった。 これはすごいことじゃないでしょうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
ギリシア哲学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-