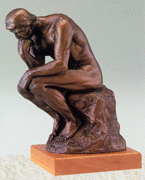中学3年生は,最後のテスト,学年末テストです。それに向けての対策をやっていました。
K子さんが質問にやってきました。理科,秒速を求める問題です。「1秒間に50打点する記録タイマー」などが出てくる問題です。
途中までは何とか説明を加えてやってきましたが,なかなか進みません。前に何度もやった問題ですが,頭に残っていません。それで,ぼくはこういいました。
「もう,これは捨てなさい」
そして,「これはこれ以上やっても,明日のテストでは点数はもらえないよ。それよりも2分野のあなたがある程度分かる問題に集中した方がいいよ」と。
そして,
「テストは明日だよ。まったく分からない問題を一から理解するのは難しい。それよりも,もう少しで完全に理解できそうだと思う問題に集中したほうがいい」と付け加えました。
テストに対する意欲はあるのですが,理解力がついて来ないのです。
かわいそうだとは思います。ほかの生徒は一所懸命に解いている問題を,「あなたはもう捨てなさい」と言われるのですから。
ぼくもすっきりしているわけではありません。何とか理解させたいとは思うのですが,時間との問題です。そして,これに時間をかけていては別の問題に時間をかけることができません。
ある程度くると,優先順位をつけながらさせなければいけません。100点をねらって50点しかとれないというより,70点をねらって70点を取った方がいいと思うのです。
これから入試に向かいます。「もうこれは捨てなさい」ということがたびたび起こるかと思います。
「もうこれは捨てなさい」
みなさんはどう思いますか。
K子さんが質問にやってきました。理科,秒速を求める問題です。「1秒間に50打点する記録タイマー」などが出てくる問題です。
途中までは何とか説明を加えてやってきましたが,なかなか進みません。前に何度もやった問題ですが,頭に残っていません。それで,ぼくはこういいました。
「もう,これは捨てなさい」
そして,「これはこれ以上やっても,明日のテストでは点数はもらえないよ。それよりも2分野のあなたがある程度分かる問題に集中した方がいいよ」と。
そして,
「テストは明日だよ。まったく分からない問題を一から理解するのは難しい。それよりも,もう少しで完全に理解できそうだと思う問題に集中したほうがいい」と付け加えました。
テストに対する意欲はあるのですが,理解力がついて来ないのです。
かわいそうだとは思います。ほかの生徒は一所懸命に解いている問題を,「あなたはもう捨てなさい」と言われるのですから。
ぼくもすっきりしているわけではありません。何とか理解させたいとは思うのですが,時間との問題です。そして,これに時間をかけていては別の問題に時間をかけることができません。
ある程度くると,優先順位をつけながらさせなければいけません。100点をねらって50点しかとれないというより,70点をねらって70点を取った方がいいと思うのです。
これから入試に向かいます。「もうこれは捨てなさい」ということがたびたび起こるかと思います。
「もうこれは捨てなさい」
みなさんはどう思いますか。
|
|
|
|
コメント(8)
中学生ぐらいになると能力差がどんどん開いてくるのを確かに感じますね。中学生の学習はその年代の生徒にふさわしく構成されているのでしょうから、問題は学習内容ではなく、個々の学習に対する力によるのでしょうね。
何が足りないのか…? 何が足りすぎているのか。私はどうも自立に問題があるように思います。聞きに来るタイミングが早すぎる?生徒は伸びにくい。
自分でしっかり思考錯誤してから来るのではなく、早く捌いて効率よく学習した方がいいと思っているところに結局は分かるようになれない理由があるように思うのです。
受験を意識した学習を指導しなければならない場合は、当然その子の理解の範疇にないと思える問題をゴリ押しすることは、時間の無駄であるばかりでなく、反って精神的なダメージになる場合があるだろうから「できる問題の精度を高める方がいい。」と思います。
気持ち的にも出来る問題が自分にはあると思う方が、出来ない部分ばかりがその子の中でクローズアップされているより余程いい結果が出ると思います。
何年も教えていて、はるかに能力の異なる生徒がほとんど同じような点数をとってくるのに驚くことがあります。「実力って何なのだろう?」と思います。
人の思い、純粋にがんばろうという気持ちを整えることが、支援者としては一番するべき仕事なのかなと思うこの頃です。
何が足りないのか…? 何が足りすぎているのか。私はどうも自立に問題があるように思います。聞きに来るタイミングが早すぎる?生徒は伸びにくい。
自分でしっかり思考錯誤してから来るのではなく、早く捌いて効率よく学習した方がいいと思っているところに結局は分かるようになれない理由があるように思うのです。
受験を意識した学習を指導しなければならない場合は、当然その子の理解の範疇にないと思える問題をゴリ押しすることは、時間の無駄であるばかりでなく、反って精神的なダメージになる場合があるだろうから「できる問題の精度を高める方がいい。」と思います。
気持ち的にも出来る問題が自分にはあると思う方が、出来ない部分ばかりがその子の中でクローズアップされているより余程いい結果が出ると思います。
何年も教えていて、はるかに能力の異なる生徒がほとんど同じような点数をとってくるのに驚くことがあります。「実力って何なのだろう?」と思います。
人の思い、純粋にがんばろうという気持ちを整えることが、支援者としては一番するべき仕事なのかなと思うこの頃です。
クリスさん,コメントありがとうございます。
>>>聞きに来るタイミングが早すぎる?生徒は伸びにくい。
ぼくもそう思います。
「自分なりの答えを持っておいで」「説明をきちんと読んで」「自分の頭を使って」
などと言って,追い返すこともあります。
ぼくの塾では決められた課題を終えれば帰ることができます。基本的には,やる気を持っていい感じで進んでいますが,とにかく早く終わればいい,と考える子もいて,困っています。
「思考錯誤」・・・ クリスさんは意識的にこのような漢字にしたのでしょうか。それとも単なるワープロ的な間違いでしょうか。単なるワープロ的な間違いはぼくはよくやりますが,・・・。
本来は,「試行錯誤」です。
でも「思考錯誤」っていいですね。「思って,考えて,そして間違えて」それから得るところはたくさんあるのですね。
その「思考錯誤」をどんどんやって欲しい。
>>> 受験を意識した学習を指導しなければならない場合は、当然その子の理解の範疇にないと思える問題をゴリ押しすることは、時間の無駄であるばかりでなく、反って精神的なダメージになる場合があるだろうから「できる問題の精度を高める方がいい。」と思います。
できない問題をさせるのは,その子の精神的にもよくないのですね。
安易に使ってはいけないでしょうが,
「もう,これは捨てなさい」と言うのは必要ですね。
>>>聞きに来るタイミングが早すぎる?生徒は伸びにくい。
ぼくもそう思います。
「自分なりの答えを持っておいで」「説明をきちんと読んで」「自分の頭を使って」
などと言って,追い返すこともあります。
ぼくの塾では決められた課題を終えれば帰ることができます。基本的には,やる気を持っていい感じで進んでいますが,とにかく早く終わればいい,と考える子もいて,困っています。
「思考錯誤」・・・ クリスさんは意識的にこのような漢字にしたのでしょうか。それとも単なるワープロ的な間違いでしょうか。単なるワープロ的な間違いはぼくはよくやりますが,・・・。
本来は,「試行錯誤」です。
でも「思考錯誤」っていいですね。「思って,考えて,そして間違えて」それから得るところはたくさんあるのですね。
その「思考錯誤」をどんどんやって欲しい。
>>> 受験を意識した学習を指導しなければならない場合は、当然その子の理解の範疇にないと思える問題をゴリ押しすることは、時間の無駄であるばかりでなく、反って精神的なダメージになる場合があるだろうから「できる問題の精度を高める方がいい。」と思います。
できない問題をさせるのは,その子の精神的にもよくないのですね。
安易に使ってはいけないでしょうが,
「もう,これは捨てなさい」と言うのは必要ですね。
Yojiさん
お恥ずかしい限りです。…が本気で思考錯誤だと思っていました。試行と出たら打ちなおしていたかも知れません。正確さに欠けるので、学校の先生にはなれませんね。塾の先生としても問題かもしれません。ごめんなさいと言って訂正するしかありません。以降多分間違えないでしょう。
辞書に間違えやすい例として「気をつけましょう」と載っていました。
難しさとは、複雑さの度合いだと思うのです。複雑さに耐える練習が必要だとよく思います。内容は何でもいいと言ったら語弊があるでしょうか? 私がよく使うのは、4年生なら四捨五入です。3年生なら単位の換算です。それが出来るようになるまであきらめないでやりきらせる。
ひとつしっかりやりきることができたら、そのレベルの複雑さには耐えられるようになる。
またよく理解できない子は算数なら算数の専門用語をしっかりと理解する力が弱いように思います。半径と直径があいまいであるとか平行と垂直がどっち?というぐあいです。言葉全体に対してそうなのかもしれません。
言葉に対するイメージ力が弱い。はっきりわからない言葉をはっきりさせる力が弱い。わからないことの積み重ねでどうせ私なんか…となるのが困る。
中学生で開き直ってしまったらもう動かしようがありません。
お恥ずかしい限りです。…が本気で思考錯誤だと思っていました。試行と出たら打ちなおしていたかも知れません。正確さに欠けるので、学校の先生にはなれませんね。塾の先生としても問題かもしれません。ごめんなさいと言って訂正するしかありません。以降多分間違えないでしょう。
辞書に間違えやすい例として「気をつけましょう」と載っていました。
難しさとは、複雑さの度合いだと思うのです。複雑さに耐える練習が必要だとよく思います。内容は何でもいいと言ったら語弊があるでしょうか? 私がよく使うのは、4年生なら四捨五入です。3年生なら単位の換算です。それが出来るようになるまであきらめないでやりきらせる。
ひとつしっかりやりきることができたら、そのレベルの複雑さには耐えられるようになる。
またよく理解できない子は算数なら算数の専門用語をしっかりと理解する力が弱いように思います。半径と直径があいまいであるとか平行と垂直がどっち?というぐあいです。言葉全体に対してそうなのかもしれません。
言葉に対するイメージ力が弱い。はっきりわからない言葉をはっきりさせる力が弱い。わからないことの積み重ねでどうせ私なんか…となるのが困る。
中学生で開き直ってしまったらもう動かしようがありません。
クリスさん,ぼくは漢字が弱いので,よく間違えます。
試行錯誤は,trial and error の訳として日本語になったのだと思います。心理学ではよく用いられる用語です。だから知っていたのです。
でも,「思考錯誤」というので本当におもしろいと思います。
思って,考えて,そして間違えたことは,身に付くんだよ,とよく生徒にはいいますからね。
>>>難しさとは、複雑さの度合いだと思うのです。複雑さに耐える練習が必要
その通りだと思います。
その「耐える力」というのは間違いなく,低下していると思います。
その耐える力がないので,つい甘くなってしまう。甘くなると,さらに耐える力がなくなる。
逆に,きびしくすると,折れてしまいます。ぼくの塾はきびしくて毎日だから,と敬遠されているところもあるようです。
その子の,きびしさに打ち克つ力を見極め,その少し上のきびしさを与えて,それに慣れさせ,次の段階に進む,ということが頭には浮かびます。しかし,それを実践するのは容易なことではありません。
容易ではありませんが,耐える力を育てるという観点はとても大切なことだと思います。
>>> 中学生で開き直ってしまったらもう動かしようがありません。
その通りです。言われた通りにはしないですね。
その子が変わるように,声をかけたりして,種を蒔く。その種が子どもの中で育ってくれるように願って待つ,という感じです。
何もしないわけではなく,できるだけの働きかけはする。しかし,それが期待したように育つかどうかは,神のみぞ知る,でしょうか。
でも,確率は低いかもしれませんが,育っていることがあるのです。あるときを境に変わってくれることがあります。
「もう,これは捨てなさい」とぼくが言ったK子さんは,とても素直な子です。そのようなことを言っても,すねなたり,開き直ったりしないで,ついてきてくれます。だから,教えていて大変ではあるのですが,できるだけのことはやってあげたいと思っています。
Youjさん みなさん こんにちは
私は、いつのころからか「それをやるよりこちらから先理解したほうがいいよ」と適正でないと思われる問題を質問している子には別の学習をすすめます。
なぜ、その質問をしているかが大切ですよね。どうしてもそれを克服したいと思っているのか、単にテスト範囲だからやろうとしているのか。その状況によってもどこまで私が介入するかも違ってきます。
学習者を一律に見ないことが大切で、結果も一人一人違うのが当たり前と思っています。
クリスさんの
>人の思い、純粋にがんばろうという気持ちを整えることが、支援者としては一番するべき仕事なのかなと思うこの頃です。
これ大切ですよね。
先日のTVでオランダの教育者がオートノミーといっていましたが、私も最近、自律ということを意識して生徒と関わるようにしています。
私は、いつのころからか「それをやるよりこちらから先理解したほうがいいよ」と適正でないと思われる問題を質問している子には別の学習をすすめます。
なぜ、その質問をしているかが大切ですよね。どうしてもそれを克服したいと思っているのか、単にテスト範囲だからやろうとしているのか。その状況によってもどこまで私が介入するかも違ってきます。
学習者を一律に見ないことが大切で、結果も一人一人違うのが当たり前と思っています。
クリスさんの
>人の思い、純粋にがんばろうという気持ちを整えることが、支援者としては一番するべき仕事なのかなと思うこの頃です。
これ大切ですよね。
先日のTVでオランダの教育者がオートノミーといっていましたが、私も最近、自律ということを意識して生徒と関わるようにしています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
セルフラーニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
セルフラーニングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人