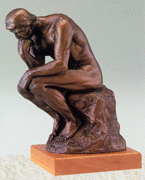私の塾では,4年前から読書指導をしています。
齋藤孝氏の3色ボールペン方式です。3色ボールペン方式とは,大切なところは青色,とても大切なところは赤色,おもしろいところは緑色で線を引く方式ですね。
生徒に,本をそれぞれ与えます。保護者にはその旨伝え,読書を始める年度から月謝を500円上げました。
青い鳥文庫,岩波少年少女文庫,ポプラ社の文庫,フォアー文庫など,少年少女文庫から選びます。
これまで,星新一「おーいでてこーい」,Oヘンリー短編集「最後の一葉」,アガサクリスティ短編集,小泉八雲「耳なしほういち(怪談)」 (思い出しながらかいているので正確ではありません)
ノルマは1日15ページ。週2〜3回。
生徒は,読書のある日は15ページ読み,赤,青,緑の線を入れ,しおりをはさんで提出します。私は,次回の読書の暇でにそれをチェック。赤線をみます。それが適切なかしょに引かれていれば,○,だいたいよければ△,見当違いの場合は×をつけます。
○の生徒は,次回はその次を読み進みます。×,△の生徒は間違い直しにきます。私との問答の中で,その文章のポイントをつかんでいきます。
齋藤孝氏も述べていますが,本にはその作者が述べたいところがある。それをつかむことができなければいけません。それを赤線で引くのですが,ちゃんと引けているかどうかで,その生徒の理解度がよく分かります。
上に列挙した本は,赤線がはっきりしています。どこでもいいわけではありません。
私との問答の中で,その生徒がそのポイントを理解したときは,本当に目を輝かせるのですよ。
この方法はとてもいい方法です。目の前の成績をあげることはできないかもしれませんが,学力を考えると一番大切なことだと思います。
先日,卒業生からメールが届きました。
学校で漢文をしているが,杜子春が出てきた。セルフで芥川龍之介の杜子春を読んでいたので,楽しく授業を受けることができた,とのことです。うれしかったですね。
セルフで星新一を知って,学校の図書館にある星新一の本はすべて読んだよ,という子もいます。
また,不良っぽい生徒がいましたが,その子がお母さんに,「この本おもしろいぜ,読んでみたら」と勧めた,とお母さんがとてもうれしそうに語っていました。星新一は人気です。
何とか読書をさせることができないか,と以前から考えていました。しかし問題はチェックです。S
SJさんも書いてあるように,読書感想文では読書をきらいにするだけです。でもこの方法なら簡単です。もちろん,チェックをするのは大変ですが。宮沢賢治は私もどこに線を引いたらいいのか分からなかったですね。「ぼっちゃん」も難しい。でも,読んでくれればいいと思い,読ませました。
長くなったので,いちおうここまでにします。何か質問があったらどうぞ。
齋藤孝氏の3色ボールペン方式です。3色ボールペン方式とは,大切なところは青色,とても大切なところは赤色,おもしろいところは緑色で線を引く方式ですね。
生徒に,本をそれぞれ与えます。保護者にはその旨伝え,読書を始める年度から月謝を500円上げました。
青い鳥文庫,岩波少年少女文庫,ポプラ社の文庫,フォアー文庫など,少年少女文庫から選びます。
これまで,星新一「おーいでてこーい」,Oヘンリー短編集「最後の一葉」,アガサクリスティ短編集,小泉八雲「耳なしほういち(怪談)」 (思い出しながらかいているので正確ではありません)
ノルマは1日15ページ。週2〜3回。
生徒は,読書のある日は15ページ読み,赤,青,緑の線を入れ,しおりをはさんで提出します。私は,次回の読書の暇でにそれをチェック。赤線をみます。それが適切なかしょに引かれていれば,○,だいたいよければ△,見当違いの場合は×をつけます。
○の生徒は,次回はその次を読み進みます。×,△の生徒は間違い直しにきます。私との問答の中で,その文章のポイントをつかんでいきます。
齋藤孝氏も述べていますが,本にはその作者が述べたいところがある。それをつかむことができなければいけません。それを赤線で引くのですが,ちゃんと引けているかどうかで,その生徒の理解度がよく分かります。
上に列挙した本は,赤線がはっきりしています。どこでもいいわけではありません。
私との問答の中で,その生徒がそのポイントを理解したときは,本当に目を輝かせるのですよ。
この方法はとてもいい方法です。目の前の成績をあげることはできないかもしれませんが,学力を考えると一番大切なことだと思います。
先日,卒業生からメールが届きました。
学校で漢文をしているが,杜子春が出てきた。セルフで芥川龍之介の杜子春を読んでいたので,楽しく授業を受けることができた,とのことです。うれしかったですね。
セルフで星新一を知って,学校の図書館にある星新一の本はすべて読んだよ,という子もいます。
また,不良っぽい生徒がいましたが,その子がお母さんに,「この本おもしろいぜ,読んでみたら」と勧めた,とお母さんがとてもうれしそうに語っていました。星新一は人気です。
何とか読書をさせることができないか,と以前から考えていました。しかし問題はチェックです。S
SJさんも書いてあるように,読書感想文では読書をきらいにするだけです。でもこの方法なら簡単です。もちろん,チェックをするのは大変ですが。宮沢賢治は私もどこに線を引いたらいいのか分からなかったですね。「ぼっちゃん」も難しい。でも,読んでくれればいいと思い,読ませました。
長くなったので,いちおうここまでにします。何か質問があったらどうぞ。
|
|
|
|
コメント(48)
私の塾の卒業生からメールが届きました。このトピを読んでの意見です。それに返事を書いていたのですが,このトピでみんなにも読んでもらいたいと思い,ここに書くことにしました。
> 読書のことですが、私は、全く読まないわけじゃないけど、よく読む人よりは読みません。小さいときから、そんなに読書をした覚えはないです。新聞も同じです。でも、周りに本はたくさんあって、家族は3人ともよく本を読む人たちだったと思います。
>
> でも、読解の問題は苦手じゃなかったと思っています。多分、3色ボールペンで色を入れていけば、赤いラインを引くべきところをほとんどもらさないはずです。
>
> だから、読解力が読書量と関係があるのかどうか、いつも不思議です。
(Yojiからの返事)
あなたのお父さんもお母さんも知的な人です。だから環境的によかったと思いますよ。国語は日常会話の中でも育っています。だから,生まれたときから国語に関しては教育が始まっているんですよね。
あなたは読書をしない方と書いていますが,少なくともいまぼくが指導している生徒たちよりしていますよ。
まず,読みとれない人は読書をしません。読みとれなければおもしろくないのですから。だから,読む練習をさせ,読みとれるようにならないと読書をするようにならないことは確かです。
確かに,読書だけによって読解力がつくかどうかは,疑問です。もともとの能力もあるでしょうし,家庭環境(良心との会話など)も影響するでしょう。しかし,読書と読解力に相関はあると思います。
> 読書のことですが、私は、全く読まないわけじゃないけど、よく読む人よりは読みません。小さいときから、そんなに読書をした覚えはないです。新聞も同じです。でも、周りに本はたくさんあって、家族は3人ともよく本を読む人たちだったと思います。
>
> でも、読解の問題は苦手じゃなかったと思っています。多分、3色ボールペンで色を入れていけば、赤いラインを引くべきところをほとんどもらさないはずです。
>
> だから、読解力が読書量と関係があるのかどうか、いつも不思議です。
(Yojiからの返事)
あなたのお父さんもお母さんも知的な人です。だから環境的によかったと思いますよ。国語は日常会話の中でも育っています。だから,生まれたときから国語に関しては教育が始まっているんですよね。
あなたは読書をしない方と書いていますが,少なくともいまぼくが指導している生徒たちよりしていますよ。
まず,読みとれない人は読書をしません。読みとれなければおもしろくないのですから。だから,読む練習をさせ,読みとれるようにならないと読書をするようにならないことは確かです。
確かに,読書だけによって読解力がつくかどうかは,疑問です。もともとの能力もあるでしょうし,家庭環境(良心との会話など)も影響するでしょう。しかし,読書と読解力に相関はあると思います。
上で紹介した卒業生のHigaeri*さんからメールが届きました。
もし、「読解力と『ある一定の』読書量」に関係があるというなら、確かに、そんなに読書をしない私でもその「ある一定」を越えているんでしょうね。それなら納得できます。
読書は嫌いじゃないし楽しめますから、読み出すと、ざっと読んだり、その時期は読書ラッシュになったりもします。嫌いと言うわけではないのにあまり読書をしていないのは、ただ、全体的に飽きっぽいからだと思います。
その読解の話と関連して一つ。
国語が必要な理由を説明するのに、よく「国語がわからない子は、数学の問題で何を問われているのかもわからない。だから国語は重要なんだ」というような説明をしますよね。わたしは、それに関しても、とても疑問です。
数学の問題が分からなくても試験以外の社会生活で困ることはありません。問題を他の言葉で言い換えることで回答できるのなら、数学の試験に関しては、それでいいと思います。(その、数学の問題の意味が分からないという理由はは、母語教育である国語のことではなくて、日本語母語話者以外の人に対する日本語教育のときには当てはまるかもしれません。)
国語が大切なことは、本当によく感じています。
人は、頭の中の言葉を使って物を考えます。
もし、その言葉がなければ、そんな気持ちになりません。
それは、その言葉の表す、その気持ちを知らないからです。
人の心は、言葉と一緒に動いているはずです。
だから、母語教育が必要で、とても重要なのだと私は思っています。
数学の例も、「考える基」という意味ではそうだと思いますが、なんか私の中ではしっくり来ません。だからといって、とてもいいわかりやすい説明ができるわけではないのですが。
ようじさんはどう思いますか。どう説明していますか。
もし、「読解力と『ある一定の』読書量」に関係があるというなら、確かに、そんなに読書をしない私でもその「ある一定」を越えているんでしょうね。それなら納得できます。
読書は嫌いじゃないし楽しめますから、読み出すと、ざっと読んだり、その時期は読書ラッシュになったりもします。嫌いと言うわけではないのにあまり読書をしていないのは、ただ、全体的に飽きっぽいからだと思います。
その読解の話と関連して一つ。
国語が必要な理由を説明するのに、よく「国語がわからない子は、数学の問題で何を問われているのかもわからない。だから国語は重要なんだ」というような説明をしますよね。わたしは、それに関しても、とても疑問です。
数学の問題が分からなくても試験以外の社会生活で困ることはありません。問題を他の言葉で言い換えることで回答できるのなら、数学の試験に関しては、それでいいと思います。(その、数学の問題の意味が分からないという理由はは、母語教育である国語のことではなくて、日本語母語話者以外の人に対する日本語教育のときには当てはまるかもしれません。)
国語が大切なことは、本当によく感じています。
人は、頭の中の言葉を使って物を考えます。
もし、その言葉がなければ、そんな気持ちになりません。
それは、その言葉の表す、その気持ちを知らないからです。
人の心は、言葉と一緒に動いているはずです。
だから、母語教育が必要で、とても重要なのだと私は思っています。
数学の例も、「考える基」という意味ではそうだと思いますが、なんか私の中ではしっくり来ません。だからといって、とてもいいわかりやすい説明ができるわけではないのですが。
ようじさんはどう思いますか。どう説明していますか。
赤備えさんのいう「最低限のレベル」に達するまでは、「相関関係が大いにあり」
そこを越えたら、「読み方の差により読解力が左右される」というのは,とてもよく分かります。
おりじんさんと私の違いは,最低限のレベルの上を見ているのか,下の見ているのか,という気もします。
おりじんさんは,自分でも読書をよくするので,上を見ている。だから,読書をすれば内容は把握できるだろう,と考える。
私は実際に読書指導をして,その最低限に達していない生徒を見て,「読んでも読んでいない」というのが見える。
そのレベルに達した生徒にはほとんどなにもいいません。もともとこの方法は指導というより,読書をさせるために,ただ座っているだけではなく,読むという行為をチェックするために始めたのですね。
だから,ある程度読むことができれば,それを続けさせるればいいと思っていたのです。
Higaerikoさんの国語力と数学についても同じようなことが言えます。私も塾をやるまでは数学ができないのは国語ができないから,というのはうそだ,と思っていました。しかし,その最低限のレベルに達していない生徒は国語力のなさで,数学ができないことがあるのです。まず,漢字が読めないと数学の文章問題は解けない。語彙力もそうです。Higaerikoさんは優秀でしたから,その最低限をクリアしていない生徒のことが理解できないのでしょうね。私もそいうでした。あきれてしまうくらいの国語力の子がいるのですよ。本当に指導ではなっく治療ですね。
赤備えさんは中学入試を指導しているのですから,そこに集まる子は優秀でしょうね。
さて,ひとつの提案です。「ぼっこちゃん」をどうにか手に入れて,コピーして生徒に読ませて,最後に問いを一つ。「その店の人たちはどうなったでしょう」
させてみませんか。実は,沖縄は学力が低いので,分からないのかなあ,という不安もあります。みなさんのところではどうでしょうか。
そこを越えたら、「読み方の差により読解力が左右される」というのは,とてもよく分かります。
おりじんさんと私の違いは,最低限のレベルの上を見ているのか,下の見ているのか,という気もします。
おりじんさんは,自分でも読書をよくするので,上を見ている。だから,読書をすれば内容は把握できるだろう,と考える。
私は実際に読書指導をして,その最低限に達していない生徒を見て,「読んでも読んでいない」というのが見える。
そのレベルに達した生徒にはほとんどなにもいいません。もともとこの方法は指導というより,読書をさせるために,ただ座っているだけではなく,読むという行為をチェックするために始めたのですね。
だから,ある程度読むことができれば,それを続けさせるればいいと思っていたのです。
Higaerikoさんの国語力と数学についても同じようなことが言えます。私も塾をやるまでは数学ができないのは国語ができないから,というのはうそだ,と思っていました。しかし,その最低限のレベルに達していない生徒は国語力のなさで,数学ができないことがあるのです。まず,漢字が読めないと数学の文章問題は解けない。語彙力もそうです。Higaerikoさんは優秀でしたから,その最低限をクリアしていない生徒のことが理解できないのでしょうね。私もそいうでした。あきれてしまうくらいの国語力の子がいるのですよ。本当に指導ではなっく治療ですね。
赤備えさんは中学入試を指導しているのですから,そこに集まる子は優秀でしょうね。
さて,ひとつの提案です。「ぼっこちゃん」をどうにか手に入れて,コピーして生徒に読ませて,最後に問いを一つ。「その店の人たちはどうなったでしょう」
させてみませんか。実は,沖縄は学力が低いので,分からないのかなあ,という不安もあります。みなさんのところではどうでしょうか。
>16: Yoji さん
> おりじんさんと私の違いは,最低限のレベルの
-----(中略)-----
>ただ座っているだけではなく,読むという行為をチェックするために始めたのですね。
これは別トピのコーチングのことも言えるかもしれませんね。私は実際には読書指導というものをしたことがありませんので、生徒がどの程度「読めている」のかに関しての経験値が無いに等しいです。なので、読んで情報を受け取ることに関しては、基準が自分になってしまっているのはたしかです。
読んでも、そこにあるべき情報を汲み取れていない生徒に関しては、治療という観点での指導をすべきでしょうね。
おそらく関連はあると思うのですが、最近、生徒と話(特に雑談)をしていると説明が下手な生徒が多いと感じます。そういう生徒は大体国語が苦手です。
そのようなことをかんがみても、3色ボールペン指導による最低限の文章読解は必要なのだろうと思いました。
Yojiさんの提案ですが、是非やってみたいとは思います。しかし、私が今働いている塾では私はアルバイト講師なので、主要教科から外れるような指導を提案してもできないと思います。ですが、家庭教師を一人持っているので(中3生)その生徒にやってみようかとは思っています。
> おりじんさんと私の違いは,最低限のレベルの
-----(中略)-----
>ただ座っているだけではなく,読むという行為をチェックするために始めたのですね。
これは別トピのコーチングのことも言えるかもしれませんね。私は実際には読書指導というものをしたことがありませんので、生徒がどの程度「読めている」のかに関しての経験値が無いに等しいです。なので、読んで情報を受け取ることに関しては、基準が自分になってしまっているのはたしかです。
読んでも、そこにあるべき情報を汲み取れていない生徒に関しては、治療という観点での指導をすべきでしょうね。
おそらく関連はあると思うのですが、最近、生徒と話(特に雑談)をしていると説明が下手な生徒が多いと感じます。そういう生徒は大体国語が苦手です。
そのようなことをかんがみても、3色ボールペン指導による最低限の文章読解は必要なのだろうと思いました。
Yojiさんの提案ですが、是非やってみたいとは思います。しかし、私が今働いている塾では私はアルバイト講師なので、主要教科から外れるような指導を提案してもできないと思います。ですが、家庭教師を一人持っているので(中3生)その生徒にやってみようかとは思っています。
Higaeri* さんの書き込みに,国語力と数学は無関係ではないのか,というのがありました。
もう少し,考えてみましょう。
私は,国語力が極端に低い生徒,例えば漢字が読めない,語彙力が極端に低い,読解力がとても低いときには,数学の文章の意味を理解できないので,数学が解けないと書きました。
思考は言語で考えるので,言語が貧弱だと思考はできない,という心理学者もいます。齋藤孝氏もそれに近いことを書いていたように思います(間違えていたらすみません)。
しかし,やはり数学と国語の頭の使い方は少し違うような気がするのです。うまくいえないのですが。
女の子は国語が得意です。読書をさせると女の子がいい。しかし,逆に男の子は数学が得意です。特に図形は。
文章問題を読むときと,小説を読むときの読み方はかなり違うように感じるのです。もちろん,きちんと線を引くことはできないでしょうけど。
文章問題の質問があるとき,その生徒に「では読んでごらん」というと,立て板に水のごとく,すらすら読むことが多い。数学の問題をこんなふうにすらすら読んで理解できるはずがない。
この問題,前から考えてはいるのですが,うまくまとまらないです。
私は「授業の工夫」というコミュにも入っているので,そこでも話題にしてみます。分かったことはお知らせします。
もう少し,考えてみましょう。
私は,国語力が極端に低い生徒,例えば漢字が読めない,語彙力が極端に低い,読解力がとても低いときには,数学の文章の意味を理解できないので,数学が解けないと書きました。
思考は言語で考えるので,言語が貧弱だと思考はできない,という心理学者もいます。齋藤孝氏もそれに近いことを書いていたように思います(間違えていたらすみません)。
しかし,やはり数学と国語の頭の使い方は少し違うような気がするのです。うまくいえないのですが。
女の子は国語が得意です。読書をさせると女の子がいい。しかし,逆に男の子は数学が得意です。特に図形は。
文章問題を読むときと,小説を読むときの読み方はかなり違うように感じるのです。もちろん,きちんと線を引くことはできないでしょうけど。
文章問題の質問があるとき,その生徒に「では読んでごらん」というと,立て板に水のごとく,すらすら読むことが多い。数学の問題をこんなふうにすらすら読んで理解できるはずがない。
この問題,前から考えてはいるのですが,うまくまとまらないです。
私は「授業の工夫」というコミュにも入っているので,そこでも話題にしてみます。分かったことはお知らせします。
赤備えさんのコメント,読んではいたのですが,自分の考えがまとまらず,書き込みきれませんでした。
●算数 :演繹重視の科目
●国語 :帰納重視 → 演繹軽視(現状)の科目
算数と国語が「実は根が同じ」
文系・理系と科目を分けるよりも、
?論理重視系
?知識重視系
ある面で,正しいように感じます。ただ,まだすっと落ちないところがあります。もうしばらく考えてみます。
赤備えさんが書いているように,
国語は、かなり(公的には)未発達=指導が確立していない分野
だと思います。私自身が国語がまだとらえきれていません。
もっと考えてみたいと思います。
でも,このような場は,自分がまったく思ってもいなかった面からのアプローチがあるので,考えさせられます。楽しみです。
これからもよろしく
●算数 :演繹重視の科目
●国語 :帰納重視 → 演繹軽視(現状)の科目
算数と国語が「実は根が同じ」
文系・理系と科目を分けるよりも、
?論理重視系
?知識重視系
ある面で,正しいように感じます。ただ,まだすっと落ちないところがあります。もうしばらく考えてみます。
赤備えさんが書いているように,
国語は、かなり(公的には)未発達=指導が確立していない分野
だと思います。私自身が国語がまだとらえきれていません。
もっと考えてみたいと思います。
でも,このような場は,自分がまったく思ってもいなかった面からのアプローチがあるので,考えさせられます。楽しみです。
これからもよろしく
40: 生グレ姉さん
3色ボールペン式を,私は読解の指導には用いていません。読書の指導です。
読解と読書は,確かに切っても切れない関係にありますね。
ただ,読解の指導という場合は,精読であり,細かいところまで読みとる必要が出てきます。
私は,読書の喜びを知ってもらうために,3色を用いています。
生徒たちは,1冊の本を通読します。
問題は,読書をしたか,本当に読んだかです。それのチェックがこれまではできなかった。
朝の読書運動や本の貸し出し数などでは,本当に読んだかどうか分からない。生徒が「読みました」と言えば,もうそれを信じるしかない。
それで,3色ボールペン方式を使うことにしたのです。
>>3色はどうしても主観がはいってしまうため
とありますが,本には主題があります。それを赤線で引ききれない生徒は,その本を読んでいないのです。字面は追っているかもしれないが,読んでいない。
星新一のショートショートでは,「おち」があります。それが分かっているかどうかは,赤線の場所で分かります。
クリスティーの推理小説では,犯人がだれなのかはっきりしているところに赤線を引いてない場合は読みとっていないのです。
そこは主観ではありません。それをちゃんと引いていない生徒は不合格にするのです。
もちろんそれも読解の指導ではあるでしょうが,何に力を入れるかで違いがあります。
読解の指導はそれで大切です。私の塾でもやっています。
ただ,読解の指導では読書好きにすることは難しいです。それに比べると,私が行っている3色ボールペン方式の読書指導で,読書が好きになった生徒は少なくありません。
3色ボールペン式を,私は読解の指導には用いていません。読書の指導です。
読解と読書は,確かに切っても切れない関係にありますね。
ただ,読解の指導という場合は,精読であり,細かいところまで読みとる必要が出てきます。
私は,読書の喜びを知ってもらうために,3色を用いています。
生徒たちは,1冊の本を通読します。
問題は,読書をしたか,本当に読んだかです。それのチェックがこれまではできなかった。
朝の読書運動や本の貸し出し数などでは,本当に読んだかどうか分からない。生徒が「読みました」と言えば,もうそれを信じるしかない。
それで,3色ボールペン方式を使うことにしたのです。
>>3色はどうしても主観がはいってしまうため
とありますが,本には主題があります。それを赤線で引ききれない生徒は,その本を読んでいないのです。字面は追っているかもしれないが,読んでいない。
星新一のショートショートでは,「おち」があります。それが分かっているかどうかは,赤線の場所で分かります。
クリスティーの推理小説では,犯人がだれなのかはっきりしているところに赤線を引いてない場合は読みとっていないのです。
そこは主観ではありません。それをちゃんと引いていない生徒は不合格にするのです。
もちろんそれも読解の指導ではあるでしょうが,何に力を入れるかで違いがあります。
読解の指導はそれで大切です。私の塾でもやっています。
ただ,読解の指導では読書好きにすることは難しいです。それに比べると,私が行っている3色ボールペン方式の読書指導で,読書が好きになった生徒は少なくありません。
42: 生グレ姉さん
こちらこそ,説明不足のために誤解を招いてしまいました。申し訳ございません。
他の方にも誤解を与えてしまっただろうと,反省しています。
いまはそこまで管理しないと読まない生徒が多いと思います。私が小さいころから,読書をしないと言われてきましたが,私の小さいころより,読書ができない環境になってきていると思います。ゲームを筆頭に,読書よりおもしろいものが多すぎますね。
だから,強制をしてでも読書に目を向けさせたいと思っています。
いますぐの点数には結びつかないだろうけど,長い目でみれば読書というのが,他のどの科目よりも大切だと思います。
時間をなんとか工面してやっています。こういうのは塾長というものの強みですね。
うちの塾の読書によって読書の喜びを知った子は少なくありません。
こちらこそ,説明不足のために誤解を招いてしまいました。申し訳ございません。
他の方にも誤解を与えてしまっただろうと,反省しています。
いまはそこまで管理しないと読まない生徒が多いと思います。私が小さいころから,読書をしないと言われてきましたが,私の小さいころより,読書ができない環境になってきていると思います。ゲームを筆頭に,読書よりおもしろいものが多すぎますね。
だから,強制をしてでも読書に目を向けさせたいと思っています。
いますぐの点数には結びつかないだろうけど,長い目でみれば読書というのが,他のどの科目よりも大切だと思います。
時間をなんとか工面してやっています。こういうのは塾長というものの強みですね。
うちの塾の読書によって読書の喜びを知った子は少なくありません。
生グレ姉さん との意見交換の中で,読書も,内発的動機付け(知的好奇心)と外発的動機付けの問題をはらんでいることに気づきました。
42: 生グレ姉さん のコメントに
「個人的にはそこまで管理されないと読めないのかという点に
落胆しますが」
とあるように,できれば読書の楽しさという内発的な動機で読んでもらいたい。その点については私もまったく同意見です。
読み聞かせは,本を読むおもしろさをおしえるものですから,基本的に内発的動機づけによる読書教育でしょうね。
そういう意味で,読み聞かせというのはとても大切なものです。
しかし,読み聞かせだけでは,読書が好きにならない生徒がいます。
読み聞かせと自分で読書するということの間には,大きなギャップがあるからです。
読み聞かせは受け身で聴いていればいいのですが,読書は自分で文字を読むという行動が必要になります。それがおもしろくない,めんどうだ,ということで読書に向かわない子がいると思うのです。
だから,私は小学低学年の子には音読をさせます。そして,3色ボールペンに入ります。
そこでは,強制的に課題として与えますから,他からの力が働いているので,外発的動機になります。
内発的動機で読書をやってくれればいいのですが,そうでない場合は外発的動機ででもさせる必要があると思うのです。
実際,これまでの読書指導によって読書が好きになって,ほかの本も図書館から借りて読んでいるよ,という報告もあります。
42: 生グレ姉さん のコメントに
「個人的にはそこまで管理されないと読めないのかという点に
落胆しますが」
とあるように,できれば読書の楽しさという内発的な動機で読んでもらいたい。その点については私もまったく同意見です。
読み聞かせは,本を読むおもしろさをおしえるものですから,基本的に内発的動機づけによる読書教育でしょうね。
そういう意味で,読み聞かせというのはとても大切なものです。
しかし,読み聞かせだけでは,読書が好きにならない生徒がいます。
読み聞かせと自分で読書するということの間には,大きなギャップがあるからです。
読み聞かせは受け身で聴いていればいいのですが,読書は自分で文字を読むという行動が必要になります。それがおもしろくない,めんどうだ,ということで読書に向かわない子がいると思うのです。
だから,私は小学低学年の子には音読をさせます。そして,3色ボールペンに入ります。
そこでは,強制的に課題として与えますから,他からの力が働いているので,外発的動機になります。
内発的動機で読書をやってくれればいいのですが,そうでない場合は外発的動機ででもさせる必要があると思うのです。
実際,これまでの読書指導によって読書が好きになって,ほかの本も図書館から借りて読んでいるよ,という報告もあります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
セルフラーニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
セルフラーニングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8450人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208285人