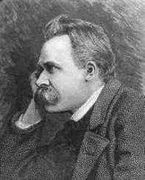特にこうした抽象的な概念が入る議論では、構造構成主義の観点を踏まえないと不毛な結果に終わることが多いと思います。そこで、このトピでは、以下の項目に同意して頂ける方だけに参加をお願いします。(或いは、高度に自分の意見をコントロールできる人が、仮に同意した立場をとって議論に加わることも歓迎です)
本トピに参加する同意条件(多分、まじめに考えれば、多くの人が同意できるはずの内容だと思います)
(1)心は、実感・体験という現象を生起させる
(2)心は、まとまりをもった働きにより、認識や判断という現象を生起させている
本トピのその他のローカル・ルール(1)
(1)自説を通すことではなくて、より真理に近づくことを目的としている
(当たり前のようでいて、多分、MIXI内で例外的に勇気を必要とする項目でしょう)
(2)可能な限り参考文献や著名人の意見としてではなくて、この場で自分のことばで発言する(自分の発言は、自分で責任を負う)
(3)相手を尊重する言葉使いをする
本トピのその他のローカル・ルール(2)
誰かに質問をされたら、以下のいずれかの答えを返す
(1)できるだけ丁寧に分かりやすく説明する
(2)質問の意味が分からない場合には、聞き返す
(3)やむを得ない場合にのみ著名な学者の意見に従っていることを具体的に説明する
(4)説明できないという
(5)説明が膨大になるか、余りにも多数の質問があって、答えられないという
どうしてこのようなローカル・ルールを作るかというと、自分に都合の悪い質問は、意識的、無意識的に無視してしまう傾向があるからです。それでは、議論をしている意味がありません。
また、自分のことばで発言するということの趣旨は、例え話や著名人の引用は、議論を分かりにくくするし、話題をいたずらに広げてしまう傾向があるからです。
常識かもしれませんが、論理的な議論をする場合、以下の仮説(私たちの認識は、全て仮説だといえますが)を選択するようにします。
(1)周辺の領域とより整合性があるもの
(2)より論理的に説明できるもの
(3)より簡潔明瞭であるもの
すごく当たり前のことかもしれませんが、多くのトピでは散々無視されていると思います。
上記のルールから外れた方は、自主的に退場して下さい。(指摘はするかもしれませんが)
本トピに参加する同意条件(多分、まじめに考えれば、多くの人が同意できるはずの内容だと思います)
(1)心は、実感・体験という現象を生起させる
(2)心は、まとまりをもった働きにより、認識や判断という現象を生起させている
本トピのその他のローカル・ルール(1)
(1)自説を通すことではなくて、より真理に近づくことを目的としている
(当たり前のようでいて、多分、MIXI内で例外的に勇気を必要とする項目でしょう)
(2)可能な限り参考文献や著名人の意見としてではなくて、この場で自分のことばで発言する(自分の発言は、自分で責任を負う)
(3)相手を尊重する言葉使いをする
本トピのその他のローカル・ルール(2)
誰かに質問をされたら、以下のいずれかの答えを返す
(1)できるだけ丁寧に分かりやすく説明する
(2)質問の意味が分からない場合には、聞き返す
(3)やむを得ない場合にのみ著名な学者の意見に従っていることを具体的に説明する
(4)説明できないという
(5)説明が膨大になるか、余りにも多数の質問があって、答えられないという
どうしてこのようなローカル・ルールを作るかというと、自分に都合の悪い質問は、意識的、無意識的に無視してしまう傾向があるからです。それでは、議論をしている意味がありません。
また、自分のことばで発言するということの趣旨は、例え話や著名人の引用は、議論を分かりにくくするし、話題をいたずらに広げてしまう傾向があるからです。
常識かもしれませんが、論理的な議論をする場合、以下の仮説(私たちの認識は、全て仮説だといえますが)を選択するようにします。
(1)周辺の領域とより整合性があるもの
(2)より論理的に説明できるもの
(3)より簡潔明瞭であるもの
すごく当たり前のことかもしれませんが、多くのトピでは散々無視されていると思います。
上記のルールから外れた方は、自主的に退場して下さい。(指摘はするかもしれませんが)
|
|
|
|
コメント(238)
>抱石さん
禅寺、NLPの例示とプロセスについては、同意です。
そして、この構造においては、A)厚みのないいわゆる外界とB)抱石さんのおっしゃるプロセスで厚みのできた外界、および、C)発言No3で分類した(5)でいうところの「心」との関係が浮き彫りになると思います。B)C)間の関係は曖昧であろうと直感することは既に申し述べた通りですが、A)B)の関係はB)C)側(つまり人間知性)からは、解くことのできない方程式のように見えますね。不完全性定理を持ち出すのは適切ではないと思いますが、この関係にはその臭いが漂います。
とはいえ、B)のプロセスこそが驚異的な能力と言える訳ですけれども、それは、脳科学的にいずれ明らかになることであって、このトピックで哲学的に問うているのは、解くことができないように見えるA)とは何かなのではないかと思うようになりました。あるいは、A)からB)入力そのものでしょうか。
なぜかというと、A)のいわゆる外界が存在するなどと確定(確信であるが実は誤解)させているのは、何人をもってしてもB)にならざるを得ず、確定しているときの真のA)は既に過ぎ去った後だからです。思うに、A)を前提条件にしたり、ブラックボックスとして扱うとB)プロセスの核心を取り逃がすのではないでしょうか。
禅寺、NLPの例示とプロセスについては、同意です。
そして、この構造においては、A)厚みのないいわゆる外界とB)抱石さんのおっしゃるプロセスで厚みのできた外界、および、C)発言No3で分類した(5)でいうところの「心」との関係が浮き彫りになると思います。B)C)間の関係は曖昧であろうと直感することは既に申し述べた通りですが、A)B)の関係はB)C)側(つまり人間知性)からは、解くことのできない方程式のように見えますね。不完全性定理を持ち出すのは適切ではないと思いますが、この関係にはその臭いが漂います。
とはいえ、B)のプロセスこそが驚異的な能力と言える訳ですけれども、それは、脳科学的にいずれ明らかになることであって、このトピックで哲学的に問うているのは、解くことができないように見えるA)とは何かなのではないかと思うようになりました。あるいは、A)からB)入力そのものでしょうか。
なぜかというと、A)のいわゆる外界が存在するなどと確定(確信であるが実は誤解)させているのは、何人をもってしてもB)にならざるを得ず、確定しているときの真のA)は既に過ぎ去った後だからです。思うに、A)を前提条件にしたり、ブラックボックスとして扱うとB)プロセスの核心を取り逃がすのではないでしょうか。
>抱石さん
抱石さんのおっしゃる非科学的な常識とは、No199のB)プロセスの内部にあって、私が(確信であるが実は誤解)と言っている部分ですよね。そして、科学は、特に空間と時間の理解をその誤解(間違いではないが実体ではない)の上に乗せているという構造ですよね。
私は素人なので自由に書いてしまいますが、No199を書いた頃からイメージするのは、ドーナツ構造と逆ドーナツ構造の量子場です。つまり、ドーナツの身が「外界」を象徴し、真ん中が「心」を象徴するとして、ドーナツ構造は、心が空洞、逆ドーナツ構造は外界が空洞です。そしてこの両方の構造が同時に両方とも正しいという結論なのではないかと。
一般には、「心も外界も存在する」ですね。
しかし、外界はあるでもない、ないでもない(Bから観ると馬鹿のようですが
・・・)、心もあるでもないないでもない。つまり脳だけでなくA)を含め、全体としても量子場であるということなんです。
そして我々はその内部にいるので、そのことに気づきにくいということなのではないでしょうか。
以上を考えているのも脳量子場だということからは逃れられませんが・・
その先の結論を考え中です。
抱石さんのおっしゃる非科学的な常識とは、No199のB)プロセスの内部にあって、私が(確信であるが実は誤解)と言っている部分ですよね。そして、科学は、特に空間と時間の理解をその誤解(間違いではないが実体ではない)の上に乗せているという構造ですよね。
私は素人なので自由に書いてしまいますが、No199を書いた頃からイメージするのは、ドーナツ構造と逆ドーナツ構造の量子場です。つまり、ドーナツの身が「外界」を象徴し、真ん中が「心」を象徴するとして、ドーナツ構造は、心が空洞、逆ドーナツ構造は外界が空洞です。そしてこの両方の構造が同時に両方とも正しいという結論なのではないかと。
一般には、「心も外界も存在する」ですね。
しかし、外界はあるでもない、ないでもない(Bから観ると馬鹿のようですが
・・・)、心もあるでもないないでもない。つまり脳だけでなくA)を含め、全体としても量子場であるということなんです。
そして我々はその内部にいるので、そのことに気づきにくいということなのではないでしょうか。
以上を考えているのも脳量子場だということからは逃れられませんが・・
その先の結論を考え中です。
例えば、「存在」という概念があります。これについては、既に考えがまとまっているのですが、少し横道にそれて意味を探ってみます。
3次元空間の中で、3次元のサイコロは、存在すると思われます。しかし、厚さゼロの(つまり2次元の)四角形は、存在しないと考えられますね。厚さゼロというのは、物が存在しないのと同じだからです。厳密な扱いは横に置くことにして、つまり私たちの周囲を科学するとき、その前提条件となる存在という概念は、「人間から見て存在することを理解できるかどうか」を基礎に置いているということになります。
そもそも、あらゆる言語による概念は、「人間から見て」或いは「人間にとって」ということを前提としています。
3次元空間の中で、3次元のサイコロは、存在すると思われます。しかし、厚さゼロの(つまり2次元の)四角形は、存在しないと考えられますね。厚さゼロというのは、物が存在しないのと同じだからです。厳密な扱いは横に置くことにして、つまり私たちの周囲を科学するとき、その前提条件となる存在という概念は、「人間から見て存在することを理解できるかどうか」を基礎に置いているということになります。
そもそも、あらゆる言語による概念は、「人間から見て」或いは「人間にとって」ということを前提としています。
>抱石さん
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」
二つあります。
まず、一つは、
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」の如何に理解するかです。
例えば、サイコロを甲さんと孫の乙さんが見ていたとします。
甲さんは長年賭場で壺を振っていてサイコロ振りの達人で
一方、乙さんはサイコロを初めて見ます。1の赤い●を日本の国旗だと感じています。
同じサイコロを見ているのに甲さんと乙さんはそれぞれのサイコロを別々に存在させています。
同様にそのサイコロを見て何人も各々のサイコロを存在させるわけで
真のサイコロなどどこにもないことになります。
それでも一応、みんなが、そこにサイコロが存在すると感じ取っているから、
間違いなく存在していることになってしまっているということですね。
もちろん私もそれを見れば、サイコロが存在しますが、それはやはり私の内部に存在します。
もう一つは
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」とは、
サイコロを存在させているのはそれを理解する人間側であるということですね。
そして、サイコロの実相は、厚みがなく、何もないという見方もできます。
事実サイコロには時間幅が全くありません。
その場合、何も無いにもかかわらず、なぜ、みんながそこにサイコロを存在させているかです。
時間幅を持たせる人間側がサイコロを把握するのは、変化を捉えているわけで、その変化を固まり(時間幅)として存在とせしめていると言えるのではないでしょうか。
人間は変化しないものを把握することができませんし、サイコロの実体は何もない変化だけがあるのではないかと思うんですね。電磁場、重力場、量子場等の場の変化だけということかもしれませんこの辺は熟考してません。
いずれにしてもここで一番言いたかったことは、いわゆる外界には、私の内部にサイコロが存在しているようサイコロが存在しているわけではないということですね。
それにしても、考えれば考えるほど、脳は、驚異的な能力をもって自分の内部に時間幅を作り上げていますよね。
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」
二つあります。
まず、一つは、
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」の如何に理解するかです。
例えば、サイコロを甲さんと孫の乙さんが見ていたとします。
甲さんは長年賭場で壺を振っていてサイコロ振りの達人で
一方、乙さんはサイコロを初めて見ます。1の赤い●を日本の国旗だと感じています。
同じサイコロを見ているのに甲さんと乙さんはそれぞれのサイコロを別々に存在させています。
同様にそのサイコロを見て何人も各々のサイコロを存在させるわけで
真のサイコロなどどこにもないことになります。
それでも一応、みんなが、そこにサイコロが存在すると感じ取っているから、
間違いなく存在していることになってしまっているということですね。
もちろん私もそれを見れば、サイコロが存在しますが、それはやはり私の内部に存在します。
もう一つは
>「人間から見て存在することを理解できるかどうか」とは、
サイコロを存在させているのはそれを理解する人間側であるということですね。
そして、サイコロの実相は、厚みがなく、何もないという見方もできます。
事実サイコロには時間幅が全くありません。
その場合、何も無いにもかかわらず、なぜ、みんながそこにサイコロを存在させているかです。
時間幅を持たせる人間側がサイコロを把握するのは、変化を捉えているわけで、その変化を固まり(時間幅)として存在とせしめていると言えるのではないでしょうか。
人間は変化しないものを把握することができませんし、サイコロの実体は何もない変化だけがあるのではないかと思うんですね。電磁場、重力場、量子場等の場の変化だけということかもしれませんこの辺は熟考してません。
いずれにしてもここで一番言いたかったことは、いわゆる外界には、私の内部にサイコロが存在しているようサイコロが存在しているわけではないということですね。
それにしても、考えれば考えるほど、脳は、驚異的な能力をもって自分の内部に時間幅を作り上げていますよね。
サイコロの例は、分かりやすいので使ったのですが、本当は3次元のサイコロは、あなたの言われる通り存在しません。もし4次元、つまり時間的な持続性がなければ、一瞬の出来事で誰も存在に気づかないからです。
そして、存在ということの性質は、更に高次元でも同様のことが類推されます。つまり、もし時間軸の全体を見渡せる人がいたら、5次元目の軸に沿って移動しない限りサイコロは存在できないのです。
何が言いたいのかというと、これもbazumix003さんの言われる通り、経時変化がなければ、私たちは存在と認めることができないようになっています。
もう少し厳密に考えてみると、私たちは、3次元の世界にありながら、心の中では4次元的な広がりを持っています。そのことによって、経時変化を感じることができるのです。
このようにn次元の住人は、(n+1)次元の幅をもっているとき、そしてn次元が(n+1)次元に沿って移動している場合にだけ、存在を認めることができるのです。
このn次元と(n+1)次元の接触こそが、私たちに主体という現象や、実感・体験という現象(この二つは表裏一体で、同じことを意味しますが)を生起させていると言えるでしょう。
この辺を深く探求してゆくことができれば、心のあり方の実相が見えてくるかもしれませんね。
そして、存在ということの性質は、更に高次元でも同様のことが類推されます。つまり、もし時間軸の全体を見渡せる人がいたら、5次元目の軸に沿って移動しない限りサイコロは存在できないのです。
何が言いたいのかというと、これもbazumix003さんの言われる通り、経時変化がなければ、私たちは存在と認めることができないようになっています。
もう少し厳密に考えてみると、私たちは、3次元の世界にありながら、心の中では4次元的な広がりを持っています。そのことによって、経時変化を感じることができるのです。
このようにn次元の住人は、(n+1)次元の幅をもっているとき、そしてn次元が(n+1)次元に沿って移動している場合にだけ、存在を認めることができるのです。
このn次元と(n+1)次元の接触こそが、私たちに主体という現象や、実感・体験という現象(この二つは表裏一体で、同じことを意味しますが)を生起させていると言えるでしょう。
この辺を深く探求してゆくことができれば、心のあり方の実相が見えてくるかもしれませんね。
古代の仏教教団がいくつもの部派へと分裂した部派仏教時代にも、説一切有部と経量部の間で心と外界の関係について鋭い意見の対立があった。
前者は、「心というものは外界・対象を照らしているに過ぎない。心の中に決して対象の形象があるわけではない。すなわち、心の中に外界の対象の表象が存在しているわけではない」と考えた。
これに対して後者は、「人は外界の対象そのものを決して見ることはできない。それは不可知であって、ただそれから人の心に投げ込まれる形象だけを人は見ているのだ。心に外界の対象の表象があるのは確かに外界の対象が存在したからだが、それはあくまでも一瞬前の対象であって、表象を見てる時にはすでに消滅している」と考えた。
前者は、「心というものは外界・対象を照らしているに過ぎない。心の中に決して対象の形象があるわけではない。すなわち、心の中に外界の対象の表象が存在しているわけではない」と考えた。
これに対して後者は、「人は外界の対象そのものを決して見ることはできない。それは不可知であって、ただそれから人の心に投げ込まれる形象だけを人は見ているのだ。心に外界の対象の表象があるのは確かに外界の対象が存在したからだが、それはあくまでも一瞬前の対象であって、表象を見てる時にはすでに消滅している」と考えた。
五感によって直接知られるもの(色声香味触など)をセンスデータと呼ぶなら、テーブルはセンスデータであるとは言えないし、センスデータがそのままテーブルの性質なのだとも言えないと分析した上でラッセルは、もしも実在のテーブルがあるとしたら、それとセンスデータの関係はいかなるものかと問い掛ける。
実在のテーブルが存在すると仮定し、それを物的対象と呼んだ場合、物的対象とセンスデータの関係はいかなるものなのか。
ラッセルはあらゆる物的対象をひっくるめて物質と呼ぶとしたら、先の二つの問題はこう言い直せるという。
1 そもそも物質のようなものは存在するのか。
2 もし存在するとしたら、その本性はいかなるものか。
実在のテーブルが存在すると仮定し、それを物的対象と呼んだ場合、物的対象とセンスデータの関係はいかなるものなのか。
ラッセルはあらゆる物的対象をひっくるめて物質と呼ぶとしたら、先の二つの問題はこう言い直せるという。
1 そもそも物質のようなものは存在するのか。
2 もし存在するとしたら、その本性はいかなるものか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|