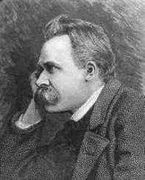勝手なイメージなんですけど、哲学を好きそうな人ってクラシックとか好んで聴いていそうな気がするんのですがどうなんですかね?
(名作ドラマ 結婚できない男 の阿部寛みたいな…)
そして哲学を愛好される方々がクラシックを聴いて何を感じ何を考えるのか、とても興味があるし、それについて語り合えるとしたら、とても意義深い事のように感じるのです。
(とは言え私自身は音楽自体、全般的に好きなのですが、別にクラシックについて詳しい訳では無かったりします。)
特に興味深く特徴的なのが、クラシックの評価基準として〈精神性の高さ〉なるものが有るようなのですが、これってなんか哲学的なテーマっぽく感じませんか?
例えば、現代を生きる我々のような凡人(リアリスト兼ニヒリスト)が、美や神聖さや宗教や神の本質には至るには、なにか導入として扱いやすい題材が必要で、たぶんクラシック音楽を深く語ることは、その題材として最適なような気がするのですが…
どうですかね?
(名作ドラマ 結婚できない男 の阿部寛みたいな…)
そして哲学を愛好される方々がクラシックを聴いて何を感じ何を考えるのか、とても興味があるし、それについて語り合えるとしたら、とても意義深い事のように感じるのです。
(とは言え私自身は音楽自体、全般的に好きなのですが、別にクラシックについて詳しい訳では無かったりします。)
特に興味深く特徴的なのが、クラシックの評価基準として〈精神性の高さ〉なるものが有るようなのですが、これってなんか哲学的なテーマっぽく感じませんか?
例えば、現代を生きる我々のような凡人(リアリスト兼ニヒリスト)が、美や神聖さや宗教や神の本質には至るには、なにか導入として扱いやすい題材が必要で、たぶんクラシック音楽を深く語ることは、その題材として最適なような気がするのですが…
どうですかね?
|
|
|
|
コメント(23)
よくフルトヴェングラーのような大昔の巨匠が指揮するベートーヴェンの交響曲は精神性が高いなどといわれるが、果たして本当にそう言えるのか?
フルヴェンにしろワルターにしろクナッパーツブッシュにしろ、主に戦前に活躍した指揮者であり、生の演奏を聴いたことのある日本人はほとんどいないだろう。
大半の人間は彼らの録音しか聴いていないだろうが、当時の貧弱な録音技術から精神性の高さを聴きとることが可能なのだろうか。
ひょっとして昔の巨匠を精神性が高いといって賞賛している日本人の多くは実際には存在しない音を聴いたつもりになっているだけかもしれない。
そうなるとフルトヴェングラーの指揮するベートーヴェンは精神性が高いというのは一種の宗教、あるいはオカルトといっても過言ではないかもしれない。
フルヴェンにしろワルターにしろクナッパーツブッシュにしろ、主に戦前に活躍した指揮者であり、生の演奏を聴いたことのある日本人はほとんどいないだろう。
大半の人間は彼らの録音しか聴いていないだろうが、当時の貧弱な録音技術から精神性の高さを聴きとることが可能なのだろうか。
ひょっとして昔の巨匠を精神性が高いといって賞賛している日本人の多くは実際には存在しない音を聴いたつもりになっているだけかもしれない。
そうなるとフルトヴェングラーの指揮するベートーヴェンは精神性が高いというのは一種の宗教、あるいはオカルトといっても過言ではないかもしれない。
>>[3]
難しいですねー。
音楽全般と哲学みたいなトピックにしてみたかったような気もするのですが、そうすると多種多様で収集がつかなくなるような気もして、クラシックの評価基準をテーマにしようかな…
なんて迷いながらも、結局問いかけとして中途半端になってしまったような気もしてます。
でもまぁ、哲学を語るような饒舌な人達が得意の話術を駆使して、なにかしら芸術(今回はクラシック)ついて言語化すること自体、たいへん興味深いし、聴くに値する学びを提供してくれそうなので、それはそれでよいのでは無いかと想っています。
それにあまりにもトピックの意図を限定してしまうと書き込みしにくいだろうし、一定の自由度は許容したほうがざっくばらんに盛り上がるのかなとも考えているので、些細なことは気にしないようにするつもりです。
それに私は、頭の固そうな哲学者達が、芸術なんていう不確定で曖昧なテーマについて語る様子を見れたなら、それはそれで嬉しい!
難しいですねー。
音楽全般と哲学みたいなトピックにしてみたかったような気もするのですが、そうすると多種多様で収集がつかなくなるような気もして、クラシックの評価基準をテーマにしようかな…
なんて迷いながらも、結局問いかけとして中途半端になってしまったような気もしてます。
でもまぁ、哲学を語るような饒舌な人達が得意の話術を駆使して、なにかしら芸術(今回はクラシック)ついて言語化すること自体、たいへん興味深いし、聴くに値する学びを提供してくれそうなので、それはそれでよいのでは無いかと想っています。
それにあまりにもトピックの意図を限定してしまうと書き込みしにくいだろうし、一定の自由度は許容したほうがざっくばらんに盛り上がるのかなとも考えているので、些細なことは気にしないようにするつもりです。
それに私は、頭の固そうな哲学者達が、芸術なんていう不確定で曖昧なテーマについて語る様子を見れたなら、それはそれで嬉しい!
>>[10]
至極単純に言うならば「人を感動させる曲や演奏」ということになるのでしょうが、そもそも音楽それだけで精神性の高さを表現することができるものなのでしょうか。
純粋な音楽以外の、例えばベートーヴェンは耳が聞こえ中田などの作曲家のエピソードや、音楽が演奏された場所や、演者や聴衆の置かれた状況などにも左右される場合が多いのではないでしょうか。
例えばフルトヴェングラーが指揮したいわゆる「バイロイトの第九」は精神性の高い名盤とよく言われますが、これがもしナチスの党大会でヒトラーの総統就任を祝うための演奏だったら全く同じ曲、同じ演奏だったとしても精神性が高いという評価を受けていたでしょうか。
私は疑問に思います。
至極単純に言うならば「人を感動させる曲や演奏」ということになるのでしょうが、そもそも音楽それだけで精神性の高さを表現することができるものなのでしょうか。
純粋な音楽以外の、例えばベートーヴェンは耳が聞こえ中田などの作曲家のエピソードや、音楽が演奏された場所や、演者や聴衆の置かれた状況などにも左右される場合が多いのではないでしょうか。
例えばフルトヴェングラーが指揮したいわゆる「バイロイトの第九」は精神性の高い名盤とよく言われますが、これがもしナチスの党大会でヒトラーの総統就任を祝うための演奏だったら全く同じ曲、同じ演奏だったとしても精神性が高いという評価を受けていたでしょうか。
私は疑問に思います。
>>[14]
>長調曲より短調曲の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
そういう傾向はあるが、長調の曲が多いベートーヴェンやモーツァルトは精神性が高いとされるのに、チャイコフスキーの『悲愴』とかはあまり精神性が高いといわれない。
>テンポの速い曲より、遅い曲の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これも確かにそういう傾向はあるが、その一方でトスカニーニやムラヴィンスキーのようなテンポの速い即物的な演奏をする指揮者も精神性が高いとされたりする。
>協和音より、その中に不協和音があった方が、相対的に精神性の高さを感じる?
それは不明。ただ坂本龍一と武満徹、どちらが精神性が高いかと問われれば武満徹の方を挙げる人が多いと思う。
>クレッシェンドより、デクレッシェンドの方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これはあまり聞いたことがない。
>上昇音形より、下降音形の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これもあまり聞いたことがない。
>長調曲より短調曲の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
そういう傾向はあるが、長調の曲が多いベートーヴェンやモーツァルトは精神性が高いとされるのに、チャイコフスキーの『悲愴』とかはあまり精神性が高いといわれない。
>テンポの速い曲より、遅い曲の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これも確かにそういう傾向はあるが、その一方でトスカニーニやムラヴィンスキーのようなテンポの速い即物的な演奏をする指揮者も精神性が高いとされたりする。
>協和音より、その中に不協和音があった方が、相対的に精神性の高さを感じる?
それは不明。ただ坂本龍一と武満徹、どちらが精神性が高いかと問われれば武満徹の方を挙げる人が多いと思う。
>クレッシェンドより、デクレッシェンドの方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これはあまり聞いたことがない。
>上昇音形より、下降音形の方が、相対的に精神性の高さを感じる?
これもあまり聞いたことがない。
>>[2]
フルトヴェングラーの指揮するヴァイロイトの第九聴いてみました。
途中まで。
YouTubeで。
その他、マーラーやブラームスやモーツァルト等の作品の演奏なども。
>当時の貧弱な録音技術〜
って仰ってましたが、クラシックって録音の古さが気にならないですね。
会場や客やシチュエーションにも言及されていましたが、確かに演奏の中に〈空間〉を感じるのはオーケストラの特徴のような印象を受け、それがその場その時の会場や環境に影響を及ぼし、聖域を造り出すかのような神聖さを感じました。
〈精神性の高さ〉についてはまだ良くはわかりませんが、オーケストラという組織の中に漲る極度の集中力と緊張感と一体感は、純度の高い高度な精神力の現れであり、精神性というものが決して作品単体や個人的なパーソナルなものではなく、集団的で集合的なもののようにも感じられました。
(読書感想文みたい )
)
やっぱり初心者には最初に誰かの解説が有った方がわかりやすいんですよね。
真面目にクラシックを聴く事ができた良い機会に感謝。
フルトヴェングラーの指揮するヴァイロイトの第九聴いてみました。
途中まで。
YouTubeで。
その他、マーラーやブラームスやモーツァルト等の作品の演奏なども。
>当時の貧弱な録音技術〜
って仰ってましたが、クラシックって録音の古さが気にならないですね。
会場や客やシチュエーションにも言及されていましたが、確かに演奏の中に〈空間〉を感じるのはオーケストラの特徴のような印象を受け、それがその場その時の会場や環境に影響を及ぼし、聖域を造り出すかのような神聖さを感じました。
〈精神性の高さ〉についてはまだ良くはわかりませんが、オーケストラという組織の中に漲る極度の集中力と緊張感と一体感は、純度の高い高度な精神力の現れであり、精神性というものが決して作品単体や個人的なパーソナルなものではなく、集団的で集合的なもののようにも感じられました。
(読書感想文みたい
やっぱり初心者には最初に誰かの解説が有った方がわかりやすいんですよね。
真面目にクラシックを聴く事ができた良い機会に感謝。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
哲学が好き 更新情報
哲学が好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196469人
- 2位
- 暮らしを楽しむ
- 76863人
- 3位
- 酒好き
- 171485人