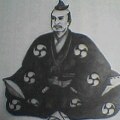- 詳細 2022年11月26日 21:24更新
-
筑後十五城や筑後戦国史に興味のある方、その他のコミュニティ。
【筑後十五城】
筑後十五城とは、戦国時代の筑後国において共存共栄していた大身(※)十五家の国人ことであり、筑後守護以来、筑後を支配した豊後の大友氏の幕下の外様大名として存在した。十五家は以下であり、その筆頭(十五城旗頭)は、蒲池氏の嫡流である柳川城主の蒲池氏(下蒲池)だった。
※大身(たいしん)とは、身分が高く、禄高の多い人、位が高く富んだ家の人のこと。室町時代から戦国時代にかけては、国人領主の中でも数郡以上を領有し大名並の勢力を持った領主で、鎌倉時代以来の氏族を、一般に大身と呼んだ。
●蒲池氏(下蒲池) 山門・三潴・下妻郡 12000町(12万石)。
●蒲池氏(上蒲池) 上妻郡 8600町(8万6千石)。
●問註所氏 生葉郡 1000町(1万石)。
●星野氏 生葉郡・竹野郡 1000町(1万石)。
●黒木氏 上妻郡 2000町(2万石)。
●河崎氏 上妻郡 1000町(1万石)。
●草野氏 山本郡 900町(9千石)。
●丹波氏 高良山 2000町(2万石)。
●三原氏 御原郡 700町(7千石)。
●西牟田氏 三潴郡 1000町(1万石)。
●田尻氏 山門郡 1600町(1万6千石)。
●五条氏 上妻郡 1400町(1万4千石)。
●溝口氏 下妻郡 1000町(1万石)。
●三池氏 三池郡 800町(8千石)。
蒲池氏が二氏あるのは、筑後における蒲池氏の勢力伸長を恐れた大友氏が、蒲池氏を分けたためである。
【蒲池氏】
平安時代の嵯峨天皇の子で大納言従一位左大臣の源融にはじまる嵯峨源氏の源満末の子で鎌倉時代に筑後国三潴郡の地頭職となった源久直(蒲池久直)にはじまる。
南北朝時代に藤原氏北家の藤原道長の兄の藤原道兼の流れを汲む宇都宮氏の宇都宮久憲(蒲池久憲)が名跡を継ぐ。
【蒲池鑑盛(蒲池宗雪)】
十五城の筆頭として筑後を統括したのが、蒲池氏嫡流である柳川城主の蒲池氏(下蒲池)であり、最盛期の当主は、鎌倉時代の初代の蒲池久直から数えて16代目の蒲池鑑盛だった。
鑑盛は、少弐氏重臣の馬場頼周の龍造寺討伐のため筑後に落ち延びてきた肥前の龍造寺家兼を保護した。龍造寺氏は大友氏に敵対的だから鑑盛にとっては敵方となり、また簡単に討つことも出来たが、戦の場以外では落ち延びてきた者を討つという、人の弱みにつけこむようなことを清廉な鑑盛は嫌った。風前の灯だった龍造寺氏は蒲池鑑盛により滅亡から救われたといえよう。
それだけではなく、家兼の遺言で家を継いだ龍造寺隆信もまた佐賀を追われて筑後に逃げてきた時、鑑盛は隆信を討つことをせず、領内の三潴郡一木村に住まわせ、3百石を扶持し、約2年間にわたって保護した。そした隆信が佐賀を奪回する時、鑑盛は精兵3百を隆信につけ護衛させたのだった。鑑盛は龍造寺氏にとっては地獄に仏のような大恩ある存在といえよう。
蒲池鑑盛は、柳川城を水郷を張り巡らせることにより九州随一の難攻不落の城とする優れた築城技術を持つばかりではなく、兵法家として苛烈に戦う武人でもあったが、「義心は鉄のごとし」といわれるほど義侠心の強い武人でもあった。
鑑盛により滅亡から救われ、佐賀を奪回した龍造寺隆信は、大恩ある鑑盛の嫡男の鎮漣(鎮並)の妻に娘をめあわせた。
【蒲池鎮漣(蒲池鎮並)】
しかし、入道して蒲池宗雪と号した鑑盛が耳川の戦いで壮烈な討ち死にをした後、大友氏の勢力後退の混乱に乗じた龍造寺隆信は筑後侵攻を開始した。鑑盛の跡を継いだ蒲池鎮漣(鎮並)は当初は、舅である隆信の先鋒を勤めるが、そのうち隆信とは対立的となる。龍造寺軍は2万の兵で柳川を攻めるが、柳川城の堅塁を落とすことが出来なかった。蒲池と龍造寺の両家は、鎮漣の伯父で龍造寺方にあった田尻鑑種の仲介で和解した。しかし柳川を領有せんとした隆信は、柳川城攻めには手を焼いたため、和解の宴席という謀略で鎮漣を肥前におびき出し謀殺した。さらに隆信は、鎮漣の一族を冷酷に殺戮し尽くすという所業に出、その結果、一時的に筑後を支配するが、筑後の大身は言うに及ばず、龍造寺の家中からも疑問視する声が上がり、龍造寺氏没落の遠因となるのだった。
蒲池鑑盛は、安土桃山時代から江戸時代にかけての柳川藩主の立花宗茂と共に筑後や柳川を代表する武士とされている。
江戸時代の柳川藩家老格の蒲池氏は、蒲池鑑盛の三男の蒲池統安の子孫であり、柳川藩蒲池氏のもっとも有名な子孫に歌手の松田聖子(蒲池法子)がいる。
■蒲池氏についてのコミュニティ
柳川・蒲池物語
http://mixi.jp /view_c ommunit y.pl?id =150053 6
難攻不落・筑後国柳川城
http://mixi.jp /view_c ommunit y.pl?id =186161 8
■ウィキペディア
蒲池氏
http://ja.wiki pedia.o rg/wiki /%E8%92 %B2%E6% B1%A0%E 6%B0%8F
蒲池鑑盛
http://ja.wiki pedia.o rg/wiki /%E8%92 %B2%E6% B1%A0%E 9%91%91 %E7%9B% 9B
筑後国
http://ja.wiki pedia.o rg/wiki /%E7%AD %91%E5% BE%8C%E 5%9B%BD
筑後十五城
http://ja.wiki pedia.o rg/wiki /%E7%AD %91%E5% BE%8C%E 5%8D%81 %E4%BA% 94%E5%9 F%8E