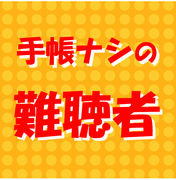東京での私用のついでに埼玉大会に寄って来ました。
1日の夜に早々と帰りましたが、ちょっとしたミニ報告です。
今回の埼玉大会では、第二分科会「障害者制度改革と障害者総合支援法」で軽中度難聴者の支援(デシベルダウン)をとりあげてもらいましたが、今回の分科会の主旨は現在の障害者制度改革の中でデシベルダウンがどのような位置にあるのかという問題です。
障害者総合福祉法への骨格提言は多数あるのですが、そのうちデシベルダウンに関係あるものは、「谷間や空白の解消」「障害程度区分を廃止した本人のニーズに合った支援サービス」などです。
しかし今回成立した「障害者総合支援法」は、これらの骨格提言のうち採用されたものはわずか1%だけだそうです。
茨城難協の会長さんの話によると骨格提言60のうち採用されたものは3つ、残りの48項目は触れてもらうこともできなかったそうです。
すなわち今回成立した「障害者総合支援法」は以前の「障害者自立支援法」の一部改正という形で終わっています。
今回の「障害者総合支援法」は来年4月から施行されますが、その後3年をめどにまた検討されることになります。
しかし依然として谷間の障害が残る医学モデルを維持していますので、デシベルダウンなどとても望めたものではありません。
ここで少し話の方向を変えますが、今回の分科会は座長が全難聴理事の新谷さん、助言者が茨城県難協会長の斎藤さん、東京都難協理事の寺田翔さん、情報文化センターの森さんでした。
この中で興味をもった方は元・当事者であった寺田さんのお話です。
彼は元・当事者の立場として、デシベルダウンに必要なものとして下記の3つをあげています。
? 障害の受容
? 自らの障害を自覚した上での援助を受ける(受援力)
? 当事者がまとまること
?の受援力とは、当事者が自ら具体的に自分にとって必要な援助を他者に説明することです。
たいへん的を得たお話で感心いたしましたが、私の方からも参加者として難協役員に釘をさしておきました。
→決して呪いのわら人形ではありません。
「全難聴は以前からデシベルダウンについては当事者に声をあげてもらうことだと主張していますが、障害の受容が難しい人達に声をあげてもらうことを望むのは大変酷なことです。デシベルダウンについては手帳のある重度の難聴の人達が彼らの手を引っ張って支えていく姿勢を見せて下さい。また実際には(このmixiのように)当事者からの声が多数出ているのにもかかわらず、全難聴も地域協会も彼らの声を聞く姿勢、態度を見せませんでした。当事者の意見を集約する場をぜひ作って下さい。」
これに対し、新谷さんや難協役員の方から大変貴重な意見として受け入れてもらいました。
寺田翔さんは「確かに今までの難聴者協会は軽中度難聴者のことは考えてきませんでしたねぇ〜。」
新谷さんからは「ネット配信・・・という方法もあるねぇ〜。」
まぁ、どこまで本腰を入れて考えていくかはわかりませんけどね。
1度ならず2度、3度、10度位まで訴えていく肝っ玉は必要ですよ。
10度訴えてダメだったら本物の呪いのわら人形に釘打っといて下さい。
まぁ、9年前に見たあの全難聴役員のおしらけムードはなかったので、今回は少しほっとした部分があります。
1日の夜に早々と帰りましたが、ちょっとしたミニ報告です。
今回の埼玉大会では、第二分科会「障害者制度改革と障害者総合支援法」で軽中度難聴者の支援(デシベルダウン)をとりあげてもらいましたが、今回の分科会の主旨は現在の障害者制度改革の中でデシベルダウンがどのような位置にあるのかという問題です。
障害者総合福祉法への骨格提言は多数あるのですが、そのうちデシベルダウンに関係あるものは、「谷間や空白の解消」「障害程度区分を廃止した本人のニーズに合った支援サービス」などです。
しかし今回成立した「障害者総合支援法」は、これらの骨格提言のうち採用されたものはわずか1%だけだそうです。
茨城難協の会長さんの話によると骨格提言60のうち採用されたものは3つ、残りの48項目は触れてもらうこともできなかったそうです。
すなわち今回成立した「障害者総合支援法」は以前の「障害者自立支援法」の一部改正という形で終わっています。
今回の「障害者総合支援法」は来年4月から施行されますが、その後3年をめどにまた検討されることになります。
しかし依然として谷間の障害が残る医学モデルを維持していますので、デシベルダウンなどとても望めたものではありません。
ここで少し話の方向を変えますが、今回の分科会は座長が全難聴理事の新谷さん、助言者が茨城県難協会長の斎藤さん、東京都難協理事の寺田翔さん、情報文化センターの森さんでした。
この中で興味をもった方は元・当事者であった寺田さんのお話です。
彼は元・当事者の立場として、デシベルダウンに必要なものとして下記の3つをあげています。
? 障害の受容
? 自らの障害を自覚した上での援助を受ける(受援力)
? 当事者がまとまること
?の受援力とは、当事者が自ら具体的に自分にとって必要な援助を他者に説明することです。
たいへん的を得たお話で感心いたしましたが、私の方からも参加者として難協役員に釘をさしておきました。
→決して呪いのわら人形ではありません。
「全難聴は以前からデシベルダウンについては当事者に声をあげてもらうことだと主張していますが、障害の受容が難しい人達に声をあげてもらうことを望むのは大変酷なことです。デシベルダウンについては手帳のある重度の難聴の人達が彼らの手を引っ張って支えていく姿勢を見せて下さい。また実際には(このmixiのように)当事者からの声が多数出ているのにもかかわらず、全難聴も地域協会も彼らの声を聞く姿勢、態度を見せませんでした。当事者の意見を集約する場をぜひ作って下さい。」
これに対し、新谷さんや難協役員の方から大変貴重な意見として受け入れてもらいました。
寺田翔さんは「確かに今までの難聴者協会は軽中度難聴者のことは考えてきませんでしたねぇ〜。」
新谷さんからは「ネット配信・・・という方法もあるねぇ〜。」
まぁ、どこまで本腰を入れて考えていくかはわかりませんけどね。
1度ならず2度、3度、10度位まで訴えていく肝っ玉は必要ですよ。
10度訴えてダメだったら本物の呪いのわら人形に釘打っといて下さい。
まぁ、9年前に見たあの全難聴役員のおしらけムードはなかったので、今回は少しほっとした部分があります。
|
|
|
|
コメント(5)
上記の補足です。
今回の分科会でも出ていた話ですが、難聴者は他の障害者と比べるとかなりの数なので是非考えていただかなくてはいけないという内容の話がよく出てきます。
しかし本当に他の障害分野と比べて多数なのでしょうか?
難聴者は600万人以上いると言われています。
しかし難病患者は750万人以上もいます。
発達障害者も難聴とほぼ同じ出現率です。
療育手帳が取得できない軽度の知的障害者もかなりの数です。
これらのことを考えると、国や行政が難聴者だけを優遇するような制度や事業を作ると思いますか?
京都の難聴児親の会が京都府・市に対して、補聴器助成の要望書を提出した時、担当者から次のような回答が返ってきているようです。
「難聴の子供だけではなく、発達障害や難病の子供達もいます。限られた予算の中で
どこから手をつけていったらいいのか考えていかなくてはいけません。」
制度の谷間にある者は難聴者だけではありません。
750万人もいる難病患者の中で難病指定を受けているものは75万人です。
わずか10%です。
今回の障害者総合支援法の成立で難病患者の一部が支援の対象の中に加えれました。
(支援対象=手帳所持者+α)
しかし本当にごく一部です。
このことを考えるとデシベルダウンなんて本当に夢のような話ですね。
京都市の難聴児に対する補聴器支援事業にしても、そのうち予算オーバーして対応できなくなり、事業廃止になることだってあるかもしれません。
ただこの辺りのことを何度説明してもわからない人はわからないのです。
今回の分科会でも参加者から「他の障害者のことなんてわからない。難聴の範囲内で考えてもらいたい。」という意見が出ていました。
しかし今回の講演者である佐藤久夫先生(日本社会事業大学教授)から「単独の団体で運動を起こしても国は耳を傾けませんよ。」という答えが返ってきました。
障害者運動や当事者は同じ次元の中を何十年もグルグル、ぐるぐる回り続けているだけだと言われています。
そして最後には死を迎えるのです。
今回の分科会でも出ていた話ですが、難聴者は他の障害者と比べるとかなりの数なので是非考えていただかなくてはいけないという内容の話がよく出てきます。
しかし本当に他の障害分野と比べて多数なのでしょうか?
難聴者は600万人以上いると言われています。
しかし難病患者は750万人以上もいます。
発達障害者も難聴とほぼ同じ出現率です。
療育手帳が取得できない軽度の知的障害者もかなりの数です。
これらのことを考えると、国や行政が難聴者だけを優遇するような制度や事業を作ると思いますか?
京都の難聴児親の会が京都府・市に対して、補聴器助成の要望書を提出した時、担当者から次のような回答が返ってきているようです。
「難聴の子供だけではなく、発達障害や難病の子供達もいます。限られた予算の中で
どこから手をつけていったらいいのか考えていかなくてはいけません。」
制度の谷間にある者は難聴者だけではありません。
750万人もいる難病患者の中で難病指定を受けているものは75万人です。
わずか10%です。
今回の障害者総合支援法の成立で難病患者の一部が支援の対象の中に加えれました。
(支援対象=手帳所持者+α)
しかし本当にごく一部です。
このことを考えるとデシベルダウンなんて本当に夢のような話ですね。
京都市の難聴児に対する補聴器支援事業にしても、そのうち予算オーバーして対応できなくなり、事業廃止になることだってあるかもしれません。
ただこの辺りのことを何度説明してもわからない人はわからないのです。
今回の分科会でも参加者から「他の障害者のことなんてわからない。難聴の範囲内で考えてもらいたい。」という意見が出ていました。
しかし今回の講演者である佐藤久夫先生(日本社会事業大学教授)から「単独の団体で運動を起こしても国は耳を傾けませんよ。」という答えが返ってきました。
障害者運動や当事者は同じ次元の中を何十年もグルグル、ぐるぐる回り続けているだけだと言われています。
そして最後には死を迎えるのです。
さらに補足です。
障害者運動は地方から広がり、最後には国につながっていくこともあると言われています。
難聴児親の会の補聴器助成運動も結構、地方から広がっていますよね。
軽中度難聴者の場合も、当事者の意見集約をどこに持っていくのかが大きな課題ですよね。地方なのか中央なのか?
ちなみに新谷さんの話によると、東京都の難聴者協会は会員数700人のうち、手帳所持者が3分の1、手帳なしが3分の1、健聴者が3分の1だそうです。
まぁ、どこまで本当かはわかりませんが、地域協会によっては手帳なしが入会できなかったり、賛助会員だったりする制度はぜひ改めていかなくてはいけませんね。
一体、どこの協会が手帳なしを賛助にしたり、入会不可にしたりしているのでしょうか?教えて下さい。
今回の件は新谷さんのみならず、高岡さんにも訴えます。
特に意見集約についてはぜひ考えていかなくてはならない大切な問題ですから。
障害者運動は地方から広がり、最後には国につながっていくこともあると言われています。
難聴児親の会の補聴器助成運動も結構、地方から広がっていますよね。
軽中度難聴者の場合も、当事者の意見集約をどこに持っていくのかが大きな課題ですよね。地方なのか中央なのか?
ちなみに新谷さんの話によると、東京都の難聴者協会は会員数700人のうち、手帳所持者が3分の1、手帳なしが3分の1、健聴者が3分の1だそうです。
まぁ、どこまで本当かはわかりませんが、地域協会によっては手帳なしが入会できなかったり、賛助会員だったりする制度はぜひ改めていかなくてはいけませんね。
一体、どこの協会が手帳なしを賛助にしたり、入会不可にしたりしているのでしょうか?教えて下さい。
今回の件は新谷さんのみならず、高岡さんにも訴えます。
特に意見集約についてはぜひ考えていかなくてはならない大切な問題ですから。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
手帳ナシの難聴者 更新情報
-
最新のアンケート