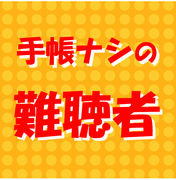「秋の教育講座」からの続きですがトピックを変えますね。
この15年の間に国の障害者施策は「措置制度」から「支援費制度」、そして現在の「障害者自立支援法」へと大きく変遷しています。
「支援費制度」が施行されたのは2003年4月、「自立支援法」が施行されたのは2006年4月ですから、「支援費制度」はわずか3年しかもたない法律でした。
そして5年前に制定された「障害者自立支援法」も見直しを要求され、来年1月には「障害者総合福祉法(案)」が提出されようとしています。
「案」ですよ。念のため・・・。
しかし実質的に「障害者総合福祉法」(仮称)が制定されるのは平成25年の予定なので、
あと1年余りで国の障害者施策は新たに生まれ変わることになります。
この新法「障害者総合福祉法」を作るために、当事者や関係者が出席し、2010年1月から「障がい者制度改革推進会議」が開催されているのですが、その中の論議の一つとして「障害の定義」(制度の谷間)が論議されているのです。
全難聴からは新谷理事が出席し、「聴覚障害の認定基準をWHO基準並みに40dB以上からにしてもらいたい」という要望書を出しています。
しかし障害に対する見方が従来の医学モデルから社会モデルへと変遷していく中でこのような要望がどこまで取り上げられるのかは大きな疑問です。
何しろ40dB以上からを聴覚障害とみなすと、身体障害者330万人に対し、聴覚障害者は600万人以上になりますからね。
制度の谷間については難聴のみならず、難病、発達障害、高次脳機能障害、知的障害などかなりの数で問題になっています。
医学モデルのみならず、あらゆる角度から考えていかなければならない問題です。
尚、国の法律が次から次へと変遷するのは当事者やその関係者から苦情の声があがり、法律改正を迫られているからです。
一旦、新法が制定してもそれが問題になれば、また変えられることになります。
しかしいずれにせよ、国の法律は当事者が作っていくものです。
当事者が国や行政を「なるほど!」と言わせる要望を出さなければ、公的機関は見向きもしません。
「なるほど!」と言わせる要望を皆様方で作って下さい。
この15年の間に国の障害者施策は「措置制度」から「支援費制度」、そして現在の「障害者自立支援法」へと大きく変遷しています。
「支援費制度」が施行されたのは2003年4月、「自立支援法」が施行されたのは2006年4月ですから、「支援費制度」はわずか3年しかもたない法律でした。
そして5年前に制定された「障害者自立支援法」も見直しを要求され、来年1月には「障害者総合福祉法(案)」が提出されようとしています。
「案」ですよ。念のため・・・。
しかし実質的に「障害者総合福祉法」(仮称)が制定されるのは平成25年の予定なので、
あと1年余りで国の障害者施策は新たに生まれ変わることになります。
この新法「障害者総合福祉法」を作るために、当事者や関係者が出席し、2010年1月から「障がい者制度改革推進会議」が開催されているのですが、その中の論議の一つとして「障害の定義」(制度の谷間)が論議されているのです。
全難聴からは新谷理事が出席し、「聴覚障害の認定基準をWHO基準並みに40dB以上からにしてもらいたい」という要望書を出しています。
しかし障害に対する見方が従来の医学モデルから社会モデルへと変遷していく中でこのような要望がどこまで取り上げられるのかは大きな疑問です。
何しろ40dB以上からを聴覚障害とみなすと、身体障害者330万人に対し、聴覚障害者は600万人以上になりますからね。
制度の谷間については難聴のみならず、難病、発達障害、高次脳機能障害、知的障害などかなりの数で問題になっています。
医学モデルのみならず、あらゆる角度から考えていかなければならない問題です。
尚、国の法律が次から次へと変遷するのは当事者やその関係者から苦情の声があがり、法律改正を迫られているからです。
一旦、新法が制定してもそれが問題になれば、また変えられることになります。
しかしいずれにせよ、国の法律は当事者が作っていくものです。
当事者が国や行政を「なるほど!」と言わせる要望を出さなければ、公的機関は見向きもしません。
「なるほど!」と言わせる要望を皆様方で作って下さい。
|
|
|
|
コメント(14)
どの自治体もおそらく18歳未満という制限をつけるでしょうね。
難聴児の補聴器助成制度が全国的に展開されてきているのは、子供の場合は数が限られ、予算が組みやすいからでしょう。
京都市の場合は、年間25人の難聴児に200万円という予算枠を作りました。
しかし半期で25人のご家庭が申請をしましたので、年間にするとおそらく40人〜50人以上になるかもしれません。
それだけたくさんの軽・中度難聴児がいるということです。
しかし成人の場合は、その数が何十倍、何百倍にも膨れ上がってしまいます。
とても対応しきれるものではありません。
超高齢社会で難聴者が大勢いるにもかかわらず、補聴器を購入する人が意外と少ないので、補聴器の値段も高額のままのようです。
補聴器代に関しては、補聴器業界を通して、いろいろと考えていかなければならない問題が多いですね。
ところで軽・中度難聴児の問題は補聴器だけなのでしょうか?
教育面、心理面などで様々な悩みを抱えている子供達が多いと思います。
子供の時から難聴だったという人に、ある専門家が「あなたは親から自分の障害を理解されてきましたか?」というアンケート調査をしたところ、90%以上の人が「理解されてこなかった」と答えているようです。
特に軽・中度難聴児の場合は、親から「おまえは障害者ではない」と言われて育てられた人達が多いため、「自分は障害者なのか、健常者なのか、わからない」という心理的苦痛を抱え、どちらの世界にも入れないで孤立したまま、大人になってしまった人達が多いのではないでしょうか?
⇒私どもの世代(30〜40代以上)
しかし今の若い親御さんは、私どもの親の世代(戦前、戦中生まれ)とは違いますから、障害に対する見方、考え方、育て方も新鮮だと思います。
親御さんが自分の子供の障害を素直に認識したり、問題意識を持つことで、子供達もまた自分の障害を認めることができるのではないか・・・と思っています。
難聴児の補聴器助成制度が全国的に展開されてきているのは、子供の場合は数が限られ、予算が組みやすいからでしょう。
京都市の場合は、年間25人の難聴児に200万円という予算枠を作りました。
しかし半期で25人のご家庭が申請をしましたので、年間にするとおそらく40人〜50人以上になるかもしれません。
それだけたくさんの軽・中度難聴児がいるということです。
しかし成人の場合は、その数が何十倍、何百倍にも膨れ上がってしまいます。
とても対応しきれるものではありません。
超高齢社会で難聴者が大勢いるにもかかわらず、補聴器を購入する人が意外と少ないので、補聴器の値段も高額のままのようです。
補聴器代に関しては、補聴器業界を通して、いろいろと考えていかなければならない問題が多いですね。
ところで軽・中度難聴児の問題は補聴器だけなのでしょうか?
教育面、心理面などで様々な悩みを抱えている子供達が多いと思います。
子供の時から難聴だったという人に、ある専門家が「あなたは親から自分の障害を理解されてきましたか?」というアンケート調査をしたところ、90%以上の人が「理解されてこなかった」と答えているようです。
特に軽・中度難聴児の場合は、親から「おまえは障害者ではない」と言われて育てられた人達が多いため、「自分は障害者なのか、健常者なのか、わからない」という心理的苦痛を抱え、どちらの世界にも入れないで孤立したまま、大人になってしまった人達が多いのではないでしょうか?
⇒私どもの世代(30〜40代以上)
しかし今の若い親御さんは、私どもの親の世代(戦前、戦中生まれ)とは違いますから、障害に対する見方、考え方、育て方も新鮮だと思います。
親御さんが自分の子供の障害を素直に認識したり、問題意識を持つことで、子供達もまた自分の障害を認めることができるのではないか・・・と思っています。
その通りです。
諸外国には手帳制度がありません。
手帳制度があるのは日本と韓国ぐらいだと聞いております。
私もデシベルや語韻明瞭度に沿った線引きにはあまり賛成できません。
そこからこぼれ落ちる人が必ず出てくるからです。
デシベルや語韻明瞭度がよくても、生活には不自由しているという難聴者がたくさんいます。
しかし難聴者のニーズや社会モデルを沿った考え方では、あまりにも曖昧なので、医学モデルを基準にした40dBからにしてもらいたいという意見もあります。
福祉制度の谷間については、難病や発達障害、高次脳機能障害、知的障害など、他の障害分野も含めた徹底的な論議が必要ですね。
この問題は障害者総合福祉法制定後も延々と論議されていくと思います。
諸外国には手帳制度がありません。
手帳制度があるのは日本と韓国ぐらいだと聞いております。
私もデシベルや語韻明瞭度に沿った線引きにはあまり賛成できません。
そこからこぼれ落ちる人が必ず出てくるからです。
デシベルや語韻明瞭度がよくても、生活には不自由しているという難聴者がたくさんいます。
しかし難聴者のニーズや社会モデルを沿った考え方では、あまりにも曖昧なので、医学モデルを基準にした40dBからにしてもらいたいという意見もあります。
福祉制度の谷間については、難病や発達障害、高次脳機能障害、知的障害など、他の障害分野も含めた徹底的な論議が必要ですね。
この問題は障害者総合福祉法制定後も延々と論議されていくと思います。
難聴の息子を持ってからまだまだ日が浅く、勉強中の身ですが、色々と思うことは出てきますね♪
例えば手帳。
持っていれば電車やバスが半額、公共の場などでも優遇がありますね。
難聴ならではの用事(通院やろう学校通学など)では有意義な制度だと思います。
そして3級からは月々の補助金がいただけるそうですが、これは同じ手帳持ちでも6級にはないモノ。
私の素人考えですが、そう言う補助金のように現金での支給ではなく制度として予算に組み込んでもらいたいなぁと思うのです。
3級以上の方が受け取っていらっしゃる給付金は例えば難聴(障害)ならではの使い道があるなら、この浅はかな思い付きはゴメンナサイ!ですが。。。
その現金で支給している分の予算で、手帳の恩恵からこぼれてしまっていて、それでも補聴器を必要としている人達への助成、組めませんかねぇ?
わからないことばかりですので、これからも色々と教えて下さい♪
例えば手帳。
持っていれば電車やバスが半額、公共の場などでも優遇がありますね。
難聴ならではの用事(通院やろう学校通学など)では有意義な制度だと思います。
そして3級からは月々の補助金がいただけるそうですが、これは同じ手帳持ちでも6級にはないモノ。
私の素人考えですが、そう言う補助金のように現金での支給ではなく制度として予算に組み込んでもらいたいなぁと思うのです。
3級以上の方が受け取っていらっしゃる給付金は例えば難聴(障害)ならではの使い道があるなら、この浅はかな思い付きはゴメンナサイ!ですが。。。
その現金で支給している分の予算で、手帳の恩恵からこぼれてしまっていて、それでも補聴器を必要としている人達への助成、組めませんかねぇ?
わからないことばかりですので、これからも色々と教えて下さい♪
「現金での支給ではなく制度として・・・」というご意見ですが、ユニバーサルデザインの考え方がこれに当たるかもしれません。
みなさんお使いのデジタルテレビは字幕ボタンをON、OFFするだけで字幕が出たり消えたりしますね。
このようなデジタルテレビはユニバーサルデザインの商品になります。
それに対して昔のアナログテレビは文字放送デコーダを使わなければ、字幕が出ませんでした。
このように特別に何か別のものを作ることによって障壁をなくす商品はバリアフリー商品と呼ばれていました。
しかしバリアフリー商品にはお金がかかります。
それに対してユニバーサルデザインのものは最初から組み込んでいるものなので経費はかかりません。
欧米では制度(法律)を作り、最初から経費のかからない方法で障壁をなくす社会を作っている国が多いようです。
みなさんお使いのデジタルテレビは字幕ボタンをON、OFFするだけで字幕が出たり消えたりしますね。
このようなデジタルテレビはユニバーサルデザインの商品になります。
それに対して昔のアナログテレビは文字放送デコーダを使わなければ、字幕が出ませんでした。
このように特別に何か別のものを作ることによって障壁をなくす商品はバリアフリー商品と呼ばれていました。
しかしバリアフリー商品にはお金がかかります。
それに対してユニバーサルデザインのものは最初から組み込んでいるものなので経費はかかりません。
欧米では制度(法律)を作り、最初から経費のかからない方法で障壁をなくす社会を作っている国が多いようです。
上記の説明を補足します。
デジタルテレビが普及する以前のアメリカでは全てのテレビに字幕のチップが導入されており、文字デコーダーなしでも字幕が見れる状態でした。
それに対して日本ではテレビの他に文字デコーダーを購入しなければ字幕番組が見れませんでした。
そのコストはアメリカの字幕チップが2千円、日本の文字デコーダーが東芝製で3万円、松下製で8万円でした。
この違いは一体、何なのでしょうか?
日本では障害者手帳の所持者のみにデコーダーの購入資金を全額補助していたのに対し、アメリカでは法律を作り、製造する全てのテレビに対して字幕チップを組み込んでいたのです。
要するにアメリカでは、国民全体で字幕チップのコストを負担していたということです。
国民全体で負担すれば、これだけコストが安くなるのです。
ここまで説明して、おわかりいただけますでしょうか?
手帳制度はあめ玉福祉です。
障害の程度に応じた福祉サービスを作り、補助金(あめ玉)を支給しているのです。
しかし手帳制度のない欧米ではそうではありません。
テレビの字幕でもおわかりのように、社会全体をバリアフリー化し、国民全体でそのコストを負担しようとしています。
アメリカで、わずか2千円のコストで字幕番組を見ていた時代に、日本では手帳所持者(30万人以上の聴覚障害者)に3万円、8万円のデコーダを支給していたのです。
これから考えてもいかに日本の福祉が遅れているかがわかるでしょう。
私たちは日本の古い福祉制度の枠組みの中から、難聴者という狭い視野の中から、難聴者の福祉を考えようとしています。
これがいかに愚かなことか、どんなに日本の福祉を遅らせるのか、考えていただきたいと思います。
軽・中度難聴児の福祉や問題を考える時も、諸外国の事情や他の障害分野(発達障害など)のこともよく勉強した上で考えていけば、子供達の未来は開けると思います。
日本では2011年7月にアナログ放送が終了し、全ての家庭で字幕番組が見れる時代になりました。⇒デジタル難民もまだまだいることとは思いますが・・・。
しかしアメリカではその10年前、20年前から既に字幕番組が見れるテレビが普及しています。
しかもそのアメリカのテレビは日本製だったという皮肉な話です。
日本では法律がなかったために、字幕チップ入りテレビを製造しなかったのです。
デジタルテレビが普及する以前のアメリカでは全てのテレビに字幕のチップが導入されており、文字デコーダーなしでも字幕が見れる状態でした。
それに対して日本ではテレビの他に文字デコーダーを購入しなければ字幕番組が見れませんでした。
そのコストはアメリカの字幕チップが2千円、日本の文字デコーダーが東芝製で3万円、松下製で8万円でした。
この違いは一体、何なのでしょうか?
日本では障害者手帳の所持者のみにデコーダーの購入資金を全額補助していたのに対し、アメリカでは法律を作り、製造する全てのテレビに対して字幕チップを組み込んでいたのです。
要するにアメリカでは、国民全体で字幕チップのコストを負担していたということです。
国民全体で負担すれば、これだけコストが安くなるのです。
ここまで説明して、おわかりいただけますでしょうか?
手帳制度はあめ玉福祉です。
障害の程度に応じた福祉サービスを作り、補助金(あめ玉)を支給しているのです。
しかし手帳制度のない欧米ではそうではありません。
テレビの字幕でもおわかりのように、社会全体をバリアフリー化し、国民全体でそのコストを負担しようとしています。
アメリカで、わずか2千円のコストで字幕番組を見ていた時代に、日本では手帳所持者(30万人以上の聴覚障害者)に3万円、8万円のデコーダを支給していたのです。
これから考えてもいかに日本の福祉が遅れているかがわかるでしょう。
私たちは日本の古い福祉制度の枠組みの中から、難聴者という狭い視野の中から、難聴者の福祉を考えようとしています。
これがいかに愚かなことか、どんなに日本の福祉を遅らせるのか、考えていただきたいと思います。
軽・中度難聴児の福祉や問題を考える時も、諸外国の事情や他の障害分野(発達障害など)のこともよく勉強した上で考えていけば、子供達の未来は開けると思います。
日本では2011年7月にアナログ放送が終了し、全ての家庭で字幕番組が見れる時代になりました。⇒デジタル難民もまだまだいることとは思いますが・・・。
しかしアメリカではその10年前、20年前から既に字幕番組が見れるテレビが普及しています。
しかもそのアメリカのテレビは日本製だったという皮肉な話です。
日本では法律がなかったために、字幕チップ入りテレビを製造しなかったのです。
4ヶ月も遅れた返信となりますが、マーヤさんの疑問にわかる範囲でお答えします。
⇒この4ヶ月、見ていませんでした。
欧米ではおそらく医学モデルを基準にしたシステムはないと思います。
ドイツなどでは医師が「この患者には補聴器を必要だ」と認めてサインすれば、国から自動的に補聴器が下りてくるシステムがあるようです。
以前、アメリカから来たアスペルガー症候群(発達障害)の女性が「アメリカでは障害が重いとか軽いとかいう概念はありません。障害者福祉に関して最も大切なことはニーズです。」と語っていました。
ニーズとは今、日本で語られている「必要な人には必要な支援(サービス)を」という考え方に等しいものです。
以前もお話したと思いますが、日本でデジタルテレビが普及する20年以上も前からアメリカでは字幕内蔵入りテレビが普及しているのです。
国民全体でバリアフリーにかかるコストを負担するというのが欧米の考え方です。
⇒ユニバーサルデザイン
日本の福祉が遅れていることを国のせいにしてはいけませんよ。
社会を変えるのは当事者自身の発言力にかかっていますから、当事者自身がたくさんのことを学ばなければいけません。
国や行政を納得させる要望を作るのは当事者自身です。
日本の国から手帳制度がなくならないのは手帳の非該当者からの要望があまり出てこなかったことも一つの理由です。
今回の新法「障害者総合支援法」も制度の谷間の問題は先送りされましたが、難病患者に対しては光が当てられました。
福祉サービスの対象に加えられることになったのです。
これは難病指定を受けられなかった難病患者やその家族が長い間、国や行政に対して運動を起こしてきたことの結果です。
今、日本全国で軽中度難聴児の補聴器助成事業が始まっているのも親御さんが頑張って運動を起こしてきたこと結果です。
親御さんだけではなく、当事者自身も今、何が問題になっているのかということを強くアピールしていく必要を感じます。
⇒この4ヶ月、見ていませんでした。
欧米ではおそらく医学モデルを基準にしたシステムはないと思います。
ドイツなどでは医師が「この患者には補聴器を必要だ」と認めてサインすれば、国から自動的に補聴器が下りてくるシステムがあるようです。
以前、アメリカから来たアスペルガー症候群(発達障害)の女性が「アメリカでは障害が重いとか軽いとかいう概念はありません。障害者福祉に関して最も大切なことはニーズです。」と語っていました。
ニーズとは今、日本で語られている「必要な人には必要な支援(サービス)を」という考え方に等しいものです。
以前もお話したと思いますが、日本でデジタルテレビが普及する20年以上も前からアメリカでは字幕内蔵入りテレビが普及しているのです。
国民全体でバリアフリーにかかるコストを負担するというのが欧米の考え方です。
⇒ユニバーサルデザイン
日本の福祉が遅れていることを国のせいにしてはいけませんよ。
社会を変えるのは当事者自身の発言力にかかっていますから、当事者自身がたくさんのことを学ばなければいけません。
国や行政を納得させる要望を作るのは当事者自身です。
日本の国から手帳制度がなくならないのは手帳の非該当者からの要望があまり出てこなかったことも一つの理由です。
今回の新法「障害者総合支援法」も制度の谷間の問題は先送りされましたが、難病患者に対しては光が当てられました。
福祉サービスの対象に加えられることになったのです。
これは難病指定を受けられなかった難病患者やその家族が長い間、国や行政に対して運動を起こしてきたことの結果です。
今、日本全国で軽中度難聴児の補聴器助成事業が始まっているのも親御さんが頑張って運動を起こしてきたこと結果です。
親御さんだけではなく、当事者自身も今、何が問題になっているのかということを強くアピールしていく必要を感じます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
手帳ナシの難聴者 更新情報
-
最新のアンケート