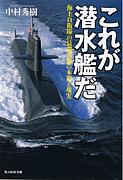他所のサイトで、原潜保有について投稿したので、転記します。
皆さんは、どう思いますか?
原潜は、非核三原則には抵触しないので、建造保有は可能です。
また、某造船所の技術者に聞いたところ、技術的にも原潜の建造は可能なようです。
核アレルギーのことを云々されるのですが、原発に反対しているのは、いわゆるプロ活動家です。
今の日本から原発をなくしたら、電力供給ができなくなるのは、子供にもわかるでしょう。
原潜の核動力も、本質は原発と同じです。
政治家も自衛隊も、反発がある、と決めてかかっていますが、私はそうは思いません。プロ活動家やその筋のマスコミは内容にかかわらず、自衛隊のやることには無条件に反対するので置いておいて。
質問者さんがこのような質問をされるのは、日本にも原潜があってもおかしくない、という意識があるからではないでしょうか。
外国の軍人も、原発が許容されて原潜が許容されないはずはない、と申しておりました。
原潜と電池潜水艦の行動能力の差は、原チャリ(第2種原動機付自転車ですよ)と徒歩くらいの差があります。その原チャリも燃料無制限です。
原チャリがゆっくり走って、人間ががんばれば短時間は勝負できますが、じきに引き離されます。そんなもんです。
ただ、原潜は建造費が高くつきます。造ってみねばわかりませんが、安く見積もっても2000億はかかるでしょうから、5〜600億の電池潜水艦を何隻か犠牲にする覚悟は要ります。
日本では、潜水艦は16隻(練習艦を除く)ですが、建造費を元に計算すれば、原潜を仮に3隻持てば、通常型は4、5隻に減らすことになり、潜水艦の保有数は半減します。
行動周期(修理、訓練、作戦)を考慮すれば、常時1隻の作戦用潜水艦を維持するには、3隻保有する必要がありますから、実質、原潜1隻、通常潜1〜2隻の兵力で有事に備えることになります。この判断は、評価の分かれるところでしょう。
私は、これでもいいと思います。原潜一隻の価値は通常潜10隻以上はあるでしょう。数の確保も無視できないので、原潜3隻、通常型6隻がいいところではないか、と思います。役に立たない大型護衛艦を節約すればすむことです。
皆さんは、どう思いますか?
原潜は、非核三原則には抵触しないので、建造保有は可能です。
また、某造船所の技術者に聞いたところ、技術的にも原潜の建造は可能なようです。
核アレルギーのことを云々されるのですが、原発に反対しているのは、いわゆるプロ活動家です。
今の日本から原発をなくしたら、電力供給ができなくなるのは、子供にもわかるでしょう。
原潜の核動力も、本質は原発と同じです。
政治家も自衛隊も、反発がある、と決めてかかっていますが、私はそうは思いません。プロ活動家やその筋のマスコミは内容にかかわらず、自衛隊のやることには無条件に反対するので置いておいて。
質問者さんがこのような質問をされるのは、日本にも原潜があってもおかしくない、という意識があるからではないでしょうか。
外国の軍人も、原発が許容されて原潜が許容されないはずはない、と申しておりました。
原潜と電池潜水艦の行動能力の差は、原チャリ(第2種原動機付自転車ですよ)と徒歩くらいの差があります。その原チャリも燃料無制限です。
原チャリがゆっくり走って、人間ががんばれば短時間は勝負できますが、じきに引き離されます。そんなもんです。
ただ、原潜は建造費が高くつきます。造ってみねばわかりませんが、安く見積もっても2000億はかかるでしょうから、5〜600億の電池潜水艦を何隻か犠牲にする覚悟は要ります。
日本では、潜水艦は16隻(練習艦を除く)ですが、建造費を元に計算すれば、原潜を仮に3隻持てば、通常型は4、5隻に減らすことになり、潜水艦の保有数は半減します。
行動周期(修理、訓練、作戦)を考慮すれば、常時1隻の作戦用潜水艦を維持するには、3隻保有する必要がありますから、実質、原潜1隻、通常潜1〜2隻の兵力で有事に備えることになります。この判断は、評価の分かれるところでしょう。
私は、これでもいいと思います。原潜一隻の価値は通常潜10隻以上はあるでしょう。数の確保も無視できないので、原潜3隻、通常型6隻がいいところではないか、と思います。役に立たない大型護衛艦を節約すればすむことです。
|
|
|
|
コメント(26)
通常潜水艦を削減しても、機動力に富む原潜があれば、問題提起をしたように、何倍(10倍としましたが)もの効果があります。
離れた場所に同時に配備するには数が必要です。しかし、重要目標(高速移動する空母など)を攻撃するケースを考えましょう。
通常潜なら、予想針路上に複数を配備しておく必要があり、速力の関係から取り付けない可能性もあります。
原潜なら、追い越して待ち伏せも出来るので、一隻で何度でも攻撃をかけられます。
電池では静かな通常潜ですが、時にはスノーケルをしなければなりません。この際騒音を出すのと、自分のソーナーが極度に能力低下するので、この間に原潜にやられる可能性もあります。
敵が通常型とわかっていれば、原潜なら、アクティブソーナーを使うことも可能です。
その差は計り知れないので、少数でも原潜を持つ価値はあります。
護衛艦は、現状でも対潜戦にはまったく寄与していません。
護衛艦がいかにも対潜能力がある、ように宣伝している海上自衛隊は、護衛艦乗りの仕切っている世界なので、彼らの誤解と自信過剰がその根底にあります。
艦隊戦=対水上戦 でしょうが、潜水艦があれば敵の水上艦船は自在に攻撃できます。
護衛艦の対水上戦能力は、敵味方識別問題や敵の近接防空能力、発射できるミサイルの数などの問題があります。
ミサイルの射程は遠すぎて、探知したのが確実に敵軍艦かどうか識別する手段はありません。国際法上、敵軍艦以外は攻撃できないので、法的にミサイル戦は成立しません。
次に、仮にミサイルを発射しても、敵の防空システムにかなり撃墜されますから、命中弾は少ないはずです。
護衛艦を実際にごらんになればわかりますが、ハープーンキャニスターを定数(8発)搭載している艦はありません。
だから、定数に満たない護衛艦部隊(護衛隊群の定数は8隻だが、8隻で行動することはまずない)が、更に定数を満たさないミサイルを発射しても、その数が知れていて、更に効果は少ない。
結論
護衛艦を削減しても、対潜戦や対水上戦に影響はございません。
離れた場所に同時に配備するには数が必要です。しかし、重要目標(高速移動する空母など)を攻撃するケースを考えましょう。
通常潜なら、予想針路上に複数を配備しておく必要があり、速力の関係から取り付けない可能性もあります。
原潜なら、追い越して待ち伏せも出来るので、一隻で何度でも攻撃をかけられます。
電池では静かな通常潜ですが、時にはスノーケルをしなければなりません。この際騒音を出すのと、自分のソーナーが極度に能力低下するので、この間に原潜にやられる可能性もあります。
敵が通常型とわかっていれば、原潜なら、アクティブソーナーを使うことも可能です。
その差は計り知れないので、少数でも原潜を持つ価値はあります。
護衛艦は、現状でも対潜戦にはまったく寄与していません。
護衛艦がいかにも対潜能力がある、ように宣伝している海上自衛隊は、護衛艦乗りの仕切っている世界なので、彼らの誤解と自信過剰がその根底にあります。
艦隊戦=対水上戦 でしょうが、潜水艦があれば敵の水上艦船は自在に攻撃できます。
護衛艦の対水上戦能力は、敵味方識別問題や敵の近接防空能力、発射できるミサイルの数などの問題があります。
ミサイルの射程は遠すぎて、探知したのが確実に敵軍艦かどうか識別する手段はありません。国際法上、敵軍艦以外は攻撃できないので、法的にミサイル戦は成立しません。
次に、仮にミサイルを発射しても、敵の防空システムにかなり撃墜されますから、命中弾は少ないはずです。
護衛艦を実際にごらんになればわかりますが、ハープーンキャニスターを定数(8発)搭載している艦はありません。
だから、定数に満たない護衛艦部隊(護衛隊群の定数は8隻だが、8隻で行動することはまずない)が、更に定数を満たさないミサイルを発射しても、その数が知れていて、更に効果は少ない。
結論
護衛艦を削減しても、対潜戦や対水上戦に影響はございません。
初めてコメントさせて頂きます。
私は原潜建造は何ら違法ではないと思います。
逆に専守防衛を主張するならば、優れた兵器を有しているのが当然であると考えます。その点から原潜保有は問題であるとは考えられません。最も国際問題にはなるかもしれませんが。
ふくろうさんが仰るように原潜ほど海洋戦略及び四方を海に囲まれた日本にとって原潜は重要な役割を果たすこととなるでしょう。
日本近海で活動する他国の潜水艦に対し、大きな抑止力を発揮すると考えます。
ところで非核三原則に関してですが、これは「国是」であって、法的拘束力は全く無いものです。そのため、これを理由としての原潜建造反対論には違和感を覚えます。また冷戦中に世界中の海で繰り広げられた原潜による水面下の抑止力をどのように国会議員等は考えているのか疑問です。
今後、どのように潜水艦に関する技術が発展していくか、またどのように法整備がなされていくかもあわせて注目したいと思います。
私は原潜建造は何ら違法ではないと思います。
逆に専守防衛を主張するならば、優れた兵器を有しているのが当然であると考えます。その点から原潜保有は問題であるとは考えられません。最も国際問題にはなるかもしれませんが。
ふくろうさんが仰るように原潜ほど海洋戦略及び四方を海に囲まれた日本にとって原潜は重要な役割を果たすこととなるでしょう。
日本近海で活動する他国の潜水艦に対し、大きな抑止力を発揮すると考えます。
ところで非核三原則に関してですが、これは「国是」であって、法的拘束力は全く無いものです。そのため、これを理由としての原潜建造反対論には違和感を覚えます。また冷戦中に世界中の海で繰り広げられた原潜による水面下の抑止力をどのように国会議員等は考えているのか疑問です。
今後、どのように潜水艦に関する技術が発展していくか、またどのように法整備がなされていくかもあわせて注目したいと思います。
初コメント失礼します。
日立のWH買収は原潜建造にプラスになりませんか。
ブラジルでさえ原潜建造すると発表していますが、我が国にとってそんなに難しいものなのでしょうか…?
無論、原子力船「むつ」などに対するマスコミ・プロ市民の極端な拒否反応という異常な事実も過去にはありましたが、現在ではジョージ・ワシントンが横須賀を母港にし、オハイオが横須賀に寄港しています。
状況は変化しているのですから、いつまでも縮こまり志向は止めて我が国にとって有効な装備であれば真剣に検討すべであると考えます。
核についても開発・維持費用だとか狭い国土でどうだとか言いますが、パキスタンや北朝鮮が保有できて、日本が保有できない訳がないと思います。
要は意志の問題なのではないでしょうか。
何か…我が国では「専門家」と称する方々は「可能性を否定」する事が存在意義のように振舞っているようにも感じています。
私は難しい問題を解決するために専門家が存在するものと思っています。
あくまでも「ど素人」の考えですが…。
日立のWH買収は原潜建造にプラスになりませんか。
ブラジルでさえ原潜建造すると発表していますが、我が国にとってそんなに難しいものなのでしょうか…?
無論、原子力船「むつ」などに対するマスコミ・プロ市民の極端な拒否反応という異常な事実も過去にはありましたが、現在ではジョージ・ワシントンが横須賀を母港にし、オハイオが横須賀に寄港しています。
状況は変化しているのですから、いつまでも縮こまり志向は止めて我が国にとって有効な装備であれば真剣に検討すべであると考えます。
核についても開発・維持費用だとか狭い国土でどうだとか言いますが、パキスタンや北朝鮮が保有できて、日本が保有できない訳がないと思います。
要は意志の問題なのではないでしょうか。
何か…我が国では「専門家」と称する方々は「可能性を否定」する事が存在意義のように振舞っているようにも感じています。
私は難しい問題を解決するために専門家が存在するものと思っています。
あくまでも「ど素人」の考えですが…。
難しい問題だと思います。
用兵側の要求として「強い兵器」を求めるのは自然なことですし、やがて日本も原潜を持つ時代が来るのかもしれません。しかし、それが今、もしくは近い将来、とはとても思えません。
日本はNPTに縛られています。それと抱き合わせでIAEAの査察も受け入れていますしお金も出しています。これが「原発とは別なので原潜持ちます」と言ったところで、とても受け入れてもらえないでしょう。今でさえ「なんで日本は良くてイランはダメ?」「なんでイスラエルは良くて?」「なんでインドは?」と不協和音のNPTですし、覇権主義!と言われているアメリカが「日本はいいの!」と、技術供与をしてくれるとも思えない。では国産…となると、それがスムーズに運用できるまでには相当長い時間が要るでしょう。その間「日本がいいならウチも」と、周辺の「原潜拡散」が一気に進むような気がします。ロシアやフランス、中国だって「日本が持つならうちで造って売ってあげますよ」となりそうな気がします。そうして増えた多数の艦を相手に、実績のない日本の原潜がどれだけ相手になれるか??それが日本の相対的な防衛力の強化になるのか?というのも勘案すべきでしょう。あまつさえ、日本の原潜保持がNPT崩壊の引き金になるかもしれない、そういった時の日本の立ち位置は?そんなことさえ考えてしまいます。
原潜は極めて政治的なものだと思います。恐らく、通常型の空母を持つよりハードルは高いでしょう(核弾頭の次、くらいでしょう)。
じゃんけんで絶対勝つには「後出し」することです。「まわりがみんな持ってるんだからしかたないじゃないですか」という時になって初めて、アメリカから買えばいい(売ってくれるなら)。それまで待たないと、藪をつついて蛇をだすことになりゃしないか、と思います。
私は用兵にも技術にも国際関係にも素人です。ですから思いつきだけで書きました。詳しい方に突っ込んでいただければ、と思います。
用兵側の要求として「強い兵器」を求めるのは自然なことですし、やがて日本も原潜を持つ時代が来るのかもしれません。しかし、それが今、もしくは近い将来、とはとても思えません。
日本はNPTに縛られています。それと抱き合わせでIAEAの査察も受け入れていますしお金も出しています。これが「原発とは別なので原潜持ちます」と言ったところで、とても受け入れてもらえないでしょう。今でさえ「なんで日本は良くてイランはダメ?」「なんでイスラエルは良くて?」「なんでインドは?」と不協和音のNPTですし、覇権主義!と言われているアメリカが「日本はいいの!」と、技術供与をしてくれるとも思えない。では国産…となると、それがスムーズに運用できるまでには相当長い時間が要るでしょう。その間「日本がいいならウチも」と、周辺の「原潜拡散」が一気に進むような気がします。ロシアやフランス、中国だって「日本が持つならうちで造って売ってあげますよ」となりそうな気がします。そうして増えた多数の艦を相手に、実績のない日本の原潜がどれだけ相手になれるか??それが日本の相対的な防衛力の強化になるのか?というのも勘案すべきでしょう。あまつさえ、日本の原潜保持がNPT崩壊の引き金になるかもしれない、そういった時の日本の立ち位置は?そんなことさえ考えてしまいます。
原潜は極めて政治的なものだと思います。恐らく、通常型の空母を持つよりハードルは高いでしょう(核弾頭の次、くらいでしょう)。
じゃんけんで絶対勝つには「後出し」することです。「まわりがみんな持ってるんだからしかたないじゃないですか」という時になって初めて、アメリカから買えばいい(売ってくれるなら)。それまで待たないと、藪をつついて蛇をだすことになりゃしないか、と思います。
私は用兵にも技術にも国際関係にも素人です。ですから思いつきだけで書きました。詳しい方に突っ込んでいただければ、と思います。
へぼ担当さん
法律の盲点のご指摘、ありがとうございました。
そういう、堅実な議論が、本コミュ設立の目的なので、感謝します。
ところで、法律論ですが。
今回ご指摘いただいた内外の法的問題を考慮しても、まだ私が楽観視している理由は次のようなものです。
20年ほど前までは、私も原潜をもつことは、政治情勢社会情勢から絶対無理、と考えておりました。
その視点を変えたのは、米海軍の潜水艦出身の提督でした。
彼は私が潜水艦乗りだったので、あえて日本の原潜保有を課題に研究したらどうか、と提案しました。
私が、とってもむりですよ、と答えたところ、原発が許容され、米原潜の寄港が日常化している情勢から、日本自体が原潜を持つことに、政治的社会的障害はないはずだ、といいました。なるほど、そういう見方もあるかと、私も発想を持てない側から、持つ方にシフトしたわけです。
ちょうど、同じ時期、イージス艦の保有も急に実現しました。
冷戦当時、米海軍の保全意識からして、イージスシステムを日本に渡すなど、想像を絶する転換です。
同様に、米国が日本に原潜を保有させたい、と考えればあっという間に実現する気がします。
国内法も、外圧次第で一気に改正に進むでしょう。
あとは、技術的な問題と予算です。
些細なことも進まないときは進みませんが、大きな変化も来るときは来ます。
大きな流れ、情勢として、原潜保有を楽観視しているのは、そんな理由で、最初の問題提起に書いたとおりです。
条約の改正が難航するのは、国益の対立(国内情勢も含め)があるからで、それが一致すると進捗します。
今日明日、どうこうはないと思いますが、ある時期、ある事件をきっかけに進捗するのではないかと。
たとえば、原子力空母の配備に、プロ活動家や動員された左翼運動員の他には、反対運動がまったく盛り上がらない社会情勢。
原潜の寄港がまったく日常化して、ニュースにもならない。
潜水艦の核動と核弾頭の違いが、一般国民にも浸透してきた事実。
原発の普及。
これらは、日本の原潜保有に有利な情勢だと思います。私のように数十年前、原潜や原子力空母の一時寄港での大騒ぎを知っているものには、隔世の感があります。
法律の盲点のご指摘、ありがとうございました。
そういう、堅実な議論が、本コミュ設立の目的なので、感謝します。
ところで、法律論ですが。
今回ご指摘いただいた内外の法的問題を考慮しても、まだ私が楽観視している理由は次のようなものです。
20年ほど前までは、私も原潜をもつことは、政治情勢社会情勢から絶対無理、と考えておりました。
その視点を変えたのは、米海軍の潜水艦出身の提督でした。
彼は私が潜水艦乗りだったので、あえて日本の原潜保有を課題に研究したらどうか、と提案しました。
私が、とってもむりですよ、と答えたところ、原発が許容され、米原潜の寄港が日常化している情勢から、日本自体が原潜を持つことに、政治的社会的障害はないはずだ、といいました。なるほど、そういう見方もあるかと、私も発想を持てない側から、持つ方にシフトしたわけです。
ちょうど、同じ時期、イージス艦の保有も急に実現しました。
冷戦当時、米海軍の保全意識からして、イージスシステムを日本に渡すなど、想像を絶する転換です。
同様に、米国が日本に原潜を保有させたい、と考えればあっという間に実現する気がします。
国内法も、外圧次第で一気に改正に進むでしょう。
あとは、技術的な問題と予算です。
些細なことも進まないときは進みませんが、大きな変化も来るときは来ます。
大きな流れ、情勢として、原潜保有を楽観視しているのは、そんな理由で、最初の問題提起に書いたとおりです。
条約の改正が難航するのは、国益の対立(国内情勢も含め)があるからで、それが一致すると進捗します。
今日明日、どうこうはないと思いますが、ある時期、ある事件をきっかけに進捗するのではないかと。
たとえば、原子力空母の配備に、プロ活動家や動員された左翼運動員の他には、反対運動がまったく盛り上がらない社会情勢。
原潜の寄港がまったく日常化して、ニュースにもならない。
潜水艦の核動と核弾頭の違いが、一般国民にも浸透してきた事実。
原発の普及。
これらは、日本の原潜保有に有利な情勢だと思います。私のように数十年前、原潜や原子力空母の一時寄港での大騒ぎを知っているものには、隔世の感があります。
昨夜、ノーチラスについてDVDで観たところですが、1950年代に就役した初の原潜の建造には、当時のアメリカでも反対意見が強かったといいます。それは、当然、数年前の原爆の印象が強烈だったからです。
今の日本の状況は、それよりはまし、ではないでしょうか?
民間船舶の核動力は一般化しないで終わりそうですが、軍艦には普及して、今更、という感じです。
プロ活動家と、マスゴミはカビの生えた放射能漏れ云々をことさら騒ぎますが、そんな時代でもないでしょう。
法律改正は、社会情勢次第でころっと実現することもあれば、絶対必要な改正も、まったく進まないこともあるのは、既述の通りです。
興味のあるのは、技術的可能性です。
初の原潜ノーチラスは、あの当時の技術で3000トン程度の排水量に収まっています。
また、原潜実現の前提は、米国の同意あるいは積極的な希望(イージス同様裏があるでしょうが)ですから、古い技術の提供も期待できるのではないでしょうか?
技術的可能性だけから、5,6千トンの規模で建造することは可能ではないでしょうか?
今の日本の状況は、それよりはまし、ではないでしょうか?
民間船舶の核動力は一般化しないで終わりそうですが、軍艦には普及して、今更、という感じです。
プロ活動家と、マスゴミはカビの生えた放射能漏れ云々をことさら騒ぎますが、そんな時代でもないでしょう。
法律改正は、社会情勢次第でころっと実現することもあれば、絶対必要な改正も、まったく進まないこともあるのは、既述の通りです。
興味のあるのは、技術的可能性です。
初の原潜ノーチラスは、あの当時の技術で3000トン程度の排水量に収まっています。
また、原潜実現の前提は、米国の同意あるいは積極的な希望(イージス同様裏があるでしょうが)ですから、古い技術の提供も期待できるのではないでしょうか?
技術的可能性だけから、5,6千トンの規模で建造することは可能ではないでしょうか?
その静粛性、ですが。
初期の原潜は、減速装置からの騒音が最大でしたから、現在は発電機と電動機の組み合わせでそれを解消しています。
発電機と電動機は、日本にも実績があるわけですからよしとして。
蒸気タービンと、1次2次の冷却水に関する装置と言うことになるのでしょうか。
ポンプは気になりますが、回転型にするなど、が考えられますね。
へぼ担当さんは、静粛化に最も障害になる機械は、なんだとお考えですか?
ところで、海自潜水艦の大型化は私も気に入りません。用法が明確でないため、あれもこれも、と要求だけが増えた結果で、まったく用兵側の不明が原因です。
潜水艦作戦を真剣に考えている者が居ないからです。
魚雷発射管は4門でよいし、定員も40〜50名に抑えるべきでしょう。魚雷と機関科は減らせると思っています。
まず、第一世代の原潜は現有潜水艦と同様に、対潜戦、対水上戦が主任務でしょう。騒音次第では、対潜任務に使えない事態も考えられますが、その場合は、対水上戦に充てればよいでしょう。
潜航深度も現有潜水艦程度ですでに十分です。
初期の原潜は、減速装置からの騒音が最大でしたから、現在は発電機と電動機の組み合わせでそれを解消しています。
発電機と電動機は、日本にも実績があるわけですからよしとして。
蒸気タービンと、1次2次の冷却水に関する装置と言うことになるのでしょうか。
ポンプは気になりますが、回転型にするなど、が考えられますね。
へぼ担当さんは、静粛化に最も障害になる機械は、なんだとお考えですか?
ところで、海自潜水艦の大型化は私も気に入りません。用法が明確でないため、あれもこれも、と要求だけが増えた結果で、まったく用兵側の不明が原因です。
潜水艦作戦を真剣に考えている者が居ないからです。
魚雷発射管は4門でよいし、定員も40〜50名に抑えるべきでしょう。魚雷と機関科は減らせると思っています。
まず、第一世代の原潜は現有潜水艦と同様に、対潜戦、対水上戦が主任務でしょう。騒音次第では、対潜任務に使えない事態も考えられますが、その場合は、対水上戦に充てればよいでしょう。
潜航深度も現有潜水艦程度ですでに十分です。
>大多数は蒸気タービンから減速装置を介して推進軸を回すものと、私個人は理解しています
私は、現用潜水艦で、減速装置を使用して推進軸を回すものはない、という認識です。
>某海自潜水艦見学の際に説明された乗組員の方にそう伺ったことがあります。民生用機器と比較できないこともありませんが、機密に触れることになりかねませんので、これ以上は言及できません。
民間人の見学者相手に、潜水艦乗員(誰かも問題ですが)が説明したのなら、機密に触れる話ではありません。ご遠慮は要りません。
守秘義務のない民間人見学者に、機密に触れる話をする潜水艦乗りがいるとは思えません。
へぼ担当者さんが、特別な立場(保全上の審査を受けて)で、特別な内容(あえて秘密事項だと断られた内容)をお聞きになったのなら、それは、また別ですが。
往復ポンプより回転ポンプが騒音が少ないことは、潜水艦用のポンプ(他の圧力発生装置も同様)が回転型に置き換わっていることが証明しているし、理屈からいってもそうだと思います。
主機、補機など騒音発生機器や配管は、船体への振動を遮断するために、ゴム製緩衝材を介在させて取り付けるのが世界的な傾向だと認識しています。
(オハイオ級紹介テレビ番組でも、例えば、パイプの太さと同じくらいの厚さの緩衝ゴムを使用していました。この雑音対策でも排水量のかなりの部分を占めています。)
この場合、発生雑音が高周波の方が低周波より遮断効果がある、とイメージしていますが、間違いでしょうか?
また、高周波は仮に船外に洩れても減衰が大きいので、周波数の高い回転音の方が往復で発生する低周波音よりはましかと。
コストは、費用対効果、ですから絶対額では論じられない問題です。
米海軍が潜水艦をすべて原潜にしたのは、メンテや破棄に要する費用を考慮しても、原潜の軍事的価値を認めたからでしょうし、空母の原子力化も同じでしょう。
原潜には電池潜水艦には絶対できないことができる、これが私が原潜にこだわる理由です。それが、原潜の軍事的価値です。米海軍も同様でしょう。
その価値が認められれば、他の欠点は許容されるのでしょう。
後から付け足されたMDで今頃価値が出てきましたが、建造費も維持費も高額なイージス艦は、冷戦構造崩壊後、費用対効果がまったくないにもかかわらず、続々建造されていました。
原潜は、あれよりはずっとましなプロジェクトだと思います。
私は、現用潜水艦で、減速装置を使用して推進軸を回すものはない、という認識です。
>某海自潜水艦見学の際に説明された乗組員の方にそう伺ったことがあります。民生用機器と比較できないこともありませんが、機密に触れることになりかねませんので、これ以上は言及できません。
民間人の見学者相手に、潜水艦乗員(誰かも問題ですが)が説明したのなら、機密に触れる話ではありません。ご遠慮は要りません。
守秘義務のない民間人見学者に、機密に触れる話をする潜水艦乗りがいるとは思えません。
へぼ担当者さんが、特別な立場(保全上の審査を受けて)で、特別な内容(あえて秘密事項だと断られた内容)をお聞きになったのなら、それは、また別ですが。
往復ポンプより回転ポンプが騒音が少ないことは、潜水艦用のポンプ(他の圧力発生装置も同様)が回転型に置き換わっていることが証明しているし、理屈からいってもそうだと思います。
主機、補機など騒音発生機器や配管は、船体への振動を遮断するために、ゴム製緩衝材を介在させて取り付けるのが世界的な傾向だと認識しています。
(オハイオ級紹介テレビ番組でも、例えば、パイプの太さと同じくらいの厚さの緩衝ゴムを使用していました。この雑音対策でも排水量のかなりの部分を占めています。)
この場合、発生雑音が高周波の方が低周波より遮断効果がある、とイメージしていますが、間違いでしょうか?
また、高周波は仮に船外に洩れても減衰が大きいので、周波数の高い回転音の方が往復で発生する低周波音よりはましかと。
コストは、費用対効果、ですから絶対額では論じられない問題です。
米海軍が潜水艦をすべて原潜にしたのは、メンテや破棄に要する費用を考慮しても、原潜の軍事的価値を認めたからでしょうし、空母の原子力化も同じでしょう。
原潜には電池潜水艦には絶対できないことができる、これが私が原潜にこだわる理由です。それが、原潜の軍事的価値です。米海軍も同様でしょう。
その価値が認められれば、他の欠点は許容されるのでしょう。
後から付け足されたMDで今頃価値が出てきましたが、建造費も維持費も高額なイージス艦は、冷戦構造崩壊後、費用対効果がまったくないにもかかわらず、続々建造されていました。
原潜は、あれよりはずっとましなプロジェクトだと思います。
>どんどん歯切れが悪くなったことを良く覚えており、見学条件他から注意することとなっています。
(笑)
たぶん、保全上の配慮ではなく、質問のレベルに案内者がついていけなかったのだと、推察します。(^^;
乗組員は、自ら雑音対策を採ることはなく(設計や建造の問題と思っている)、雑音を測定したり、目標の雑音を捕らえることのほうに関心が強いので、へぼ担当さんの質問のレベルだけでなく、発想や視点が違いすぎたんでしょう。
振動の遮断策は、ゴムのほか、スプリングや、機器をまとめて甲板に装備して、甲板ごと浮かせて装備する方法もあるかもしれません。高温部には、有効かと思います。
20年ほど前、制振材を見たことがあります。一見普通の鉄板(鋼板)ながら、叩いても振動せず、べたっとした音が一度するだけ。
こういう材料を、あまり強度を要しない艦内の浮甲板や、接続部品に使ったらと想像したことがありますが、その後どうなったか。
素人考えかもしれませんが、一見いいアイデァは採用されず、効果のない方法ばかりが採用されるように感じます。
マスカーなどその典型でしたね。
(笑)
たぶん、保全上の配慮ではなく、質問のレベルに案内者がついていけなかったのだと、推察します。(^^;
乗組員は、自ら雑音対策を採ることはなく(設計や建造の問題と思っている)、雑音を測定したり、目標の雑音を捕らえることのほうに関心が強いので、へぼ担当さんの質問のレベルだけでなく、発想や視点が違いすぎたんでしょう。
振動の遮断策は、ゴムのほか、スプリングや、機器をまとめて甲板に装備して、甲板ごと浮かせて装備する方法もあるかもしれません。高温部には、有効かと思います。
20年ほど前、制振材を見たことがあります。一見普通の鉄板(鋼板)ながら、叩いても振動せず、べたっとした音が一度するだけ。
こういう材料を、あまり強度を要しない艦内の浮甲板や、接続部品に使ったらと想像したことがありますが、その後どうなったか。
素人考えかもしれませんが、一見いいアイデァは採用されず、効果のない方法ばかりが採用されるように感じます。
マスカーなどその典型でしたね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
本当の潜水艦のコミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
本当の潜水艦のコミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90047人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6428人
- 3位
- 独り言
- 9045人