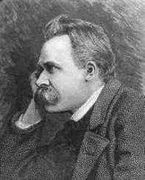|
|
|
|
コメント(107)
>>[69]
僕もどちらでもいいと思います。クオリアは確かめることはできない。
たとえば、身近に多重人格者がいて、
彼に対して、
「たくさんの人間のふりをしている一人の人間として接する」ことと、
「一つの肉体を共有したたくさんの人間として接する」ことと、
この二つの態度のどちらが正しいかを決定することはできません。
同一性の問題は、「自分がどう感じるか、行動するか」の問題で、
この問題のように、容易に意図的に切り替えることもできる場合もあります。
トピの問題も、こういう意思決定の問題、ある種のプラグマティズムの問題として、
「僕がこの世界を夢だと思って生きることでどう世界が変化するのか」
「夢か現実かどちらかを決定することで、僕の経験や人生は変化するのか」
そのように問うことでしか、その問いに意味を見いだせないと思っています。
ぼくは、「この世界は夢幻だ」と思ってだいたい生きています。
僕もどちらでもいいと思います。クオリアは確かめることはできない。
たとえば、身近に多重人格者がいて、
彼に対して、
「たくさんの人間のふりをしている一人の人間として接する」ことと、
「一つの肉体を共有したたくさんの人間として接する」ことと、
この二つの態度のどちらが正しいかを決定することはできません。
同一性の問題は、「自分がどう感じるか、行動するか」の問題で、
この問題のように、容易に意図的に切り替えることもできる場合もあります。
トピの問題も、こういう意思決定の問題、ある種のプラグマティズムの問題として、
「僕がこの世界を夢だと思って生きることでどう世界が変化するのか」
「夢か現実かどちらかを決定することで、僕の経験や人生は変化するのか」
そのように問うことでしか、その問いに意味を見いだせないと思っています。
ぼくは、「この世界は夢幻だ」と思ってだいたい生きています。
「実生活においては、たとえ疑わしい考えであっても、あたかもそれが疑いえないものであるかのようにそれに寄りかかって生活することが時には必要なのだ、
といつからか私は気づいていた。
しかし、今や私は真理の探究にこそ取り掛かろうと志しているのだから、こういう態度とは反対のことをすべきだ。
わずかでも疑問を持ちうるものは真理とは言えないと考えてこれを投げ捨て、その果てに一体投げ捨てえないものが残されるかどうか、
私は試してみたい。
まず第一に、感覚は私を欺くものだから、感覚が私の心に産み付けるものはこれを投げ捨てる。
第二に、幾何学の最も簡単な問題さえ推理を誤る人がいるのだから、私もまたすべての人と同じように推理を誤ることがあるに違いないと考えて、すべて推理はかつて信じたものといえども投げ捨てる。
最後に、私が目覚めている時に見るようなものは私が眠っている時でさえ同じように見るのだから、
夢を真実でないと投げ捨てるのと同じように、目覚めている時に見たすべてもまた真実とは言えないと投げ捨てることを決意した。」
(ルネ・デカルト『方法序説』第四部より)
といつからか私は気づいていた。
しかし、今や私は真理の探究にこそ取り掛かろうと志しているのだから、こういう態度とは反対のことをすべきだ。
わずかでも疑問を持ちうるものは真理とは言えないと考えてこれを投げ捨て、その果てに一体投げ捨てえないものが残されるかどうか、
私は試してみたい。
まず第一に、感覚は私を欺くものだから、感覚が私の心に産み付けるものはこれを投げ捨てる。
第二に、幾何学の最も簡単な問題さえ推理を誤る人がいるのだから、私もまたすべての人と同じように推理を誤ることがあるに違いないと考えて、すべて推理はかつて信じたものといえども投げ捨てる。
最後に、私が目覚めている時に見るようなものは私が眠っている時でさえ同じように見るのだから、
夢を真実でないと投げ捨てるのと同じように、目覚めている時に見たすべてもまた真実とは言えないと投げ捨てることを決意した。」
(ルネ・デカルト『方法序説』第四部より)
>>[78]
78のデカルトの意見を踏まえて発言しますが、
デカルトが、78のように、「疑うことができるが、信じないと生きていけない」
と言っているのは、「現実」の世界での出来事だと思います。
一応、僕はデカルトの方法序説、哲学省察を読んだのですが、やっぱりそういう考えです。
(まあ、数年前の記憶ですが)
つまり、デカルトは、「夢と現実の区別をつけることはできる」と思っている。
だが、「それを、説明することはできない」と言っているのだと思います。
ここで問題にしたいのは、デカルトも説明できなかったと思われる、
現実が現実であると思われるその感覚です。
それをなんとか、説明できないものでしょうか。
78のデカルトの意見を踏まえて発言しますが、
デカルトが、78のように、「疑うことができるが、信じないと生きていけない」
と言っているのは、「現実」の世界での出来事だと思います。
一応、僕はデカルトの方法序説、哲学省察を読んだのですが、やっぱりそういう考えです。
(まあ、数年前の記憶ですが)
つまり、デカルトは、「夢と現実の区別をつけることはできる」と思っている。
だが、「それを、説明することはできない」と言っているのだと思います。
ここで問題にしたいのは、デカルトも説明できなかったと思われる、
現実が現実であると思われるその感覚です。
それをなんとか、説明できないものでしょうか。
>>[087]、どうもありがとうございます。
このぼくが抜き出した箇所だけを読むと、ここでデカルトは
「夢と現実については普段、私たちは特別精査したりしたわけでもないのに、その区別を疑わず、『夢は信じられない、現実は信じられる』と思い込んで過ごしているし、確かにそれで問題なくやっていけてるわけだ。
しかし、本当の本当に信じられる所から出発しようと考える真理探究の立場からしたら、このような普段の私たちの態度は不十分だ。
『曖昧だがそう信じて、問題ないからOKとしよう』なんてゆう普段の態度はいったん捨ててみるべきだ。
むしろ、
『夢で見ているようなことは現実と呼んでいる世界でも似たように見ているだけじゃないか。長く長く醒めないだけじゃないか』
と疑いが成り立つことをいったん認めようじゃないか」
と言っているようにぼくは読みました。
と言っても、ぼくはデカルト全体を詳しく読んでいないので、
あくまでもその箇所だけの印象です。
このぼくが抜き出した箇所だけを読むと、ここでデカルトは
「夢と現実については普段、私たちは特別精査したりしたわけでもないのに、その区別を疑わず、『夢は信じられない、現実は信じられる』と思い込んで過ごしているし、確かにそれで問題なくやっていけてるわけだ。
しかし、本当の本当に信じられる所から出発しようと考える真理探究の立場からしたら、このような普段の私たちの態度は不十分だ。
『曖昧だがそう信じて、問題ないからOKとしよう』なんてゆう普段の態度はいったん捨ててみるべきだ。
むしろ、
『夢で見ているようなことは現実と呼んでいる世界でも似たように見ているだけじゃないか。長く長く醒めないだけじゃないか』
と疑いが成り立つことをいったん認めようじゃないか」
と言っているようにぼくは読みました。
と言っても、ぼくはデカルト全体を詳しく読んでいないので、
あくまでもその箇所だけの印象です。
>>[86]
今が現実であれ、夢であれ、むしろ
「〜でない(と言える)」の確かさ は全て別の「ある」に還元することによって棄却し得る
(「〜ではない」→”では(〜ではないのであれば)それは何ですか?”→「〜である」 と言う事により)
・・・・ということがこの世の全ての拠り所なのだと私は思います。
「私は今夢を見ていないと言えない」のは確かではありますけれど
逆にというか同様に「私は今現実を見ていないと言えない」のも確かなのです(・×・)
これはもちろん私一人だけでない、誰にでも言えることです。
ある は私達を離れた世界の中では「ない」と同格なのかもしれませんが
人間の世界認識の内では「ない」よりもほんの少〜しだけ優勢な概念なんですよねw
今が現実であれ、夢であれ、むしろ
「〜でない(と言える)」の確かさ は全て別の「ある」に還元することによって棄却し得る
(「〜ではない」→”では(〜ではないのであれば)それは何ですか?”→「〜である」 と言う事により)
・・・・ということがこの世の全ての拠り所なのだと私は思います。
「私は今夢を見ていないと言えない」のは確かではありますけれど
逆にというか同様に「私は今現実を見ていないと言えない」のも確かなのです(・×・)
これはもちろん私一人だけでない、誰にでも言えることです。
ある は私達を離れた世界の中では「ない」と同格なのかもしれませんが
人間の世界認識の内では「ない」よりもほんの少〜しだけ優勢な概念なんですよねw
>>[91]
演奏や映画なんかは予め”はじめこうなって最後こうなって”っていう細かいシナリオを基に再現するんで
詳細なシナリオが用意されている前提ではない私たちの人生(生まれる成長する老いる死ぬを除きますけどw) と
同じ土俵に上げられるかはちょっと私にはわかんないです(^^;
ただ、夢も現実もいつも後から「どうだったかな」と判断するものであって
「今この瞬間」毎に私達は夢なのか現実なのか【真の意味で同時に】体験しながらの判断・実感はしてないんですよね、現実問題←w
でも、哲学は疑問を明らかにした結果で成立してゆくものなのかもですが
人生は明らかにするという以上に「判断」「選択」の結果で成立する
人間の生というか体験というもんがそういった性質のものなので
後から「夢だ」「現実だ」と判断した通り生きるしかない(>>[86]) っていうのはホントその通りで。
他人から物理的な意味で判断が覆されるような何かがあったら、そのときにまた考えればいいというかw
私の場合は物理的にも第三者と本人で判断が分かれる例を何度も目の当たりにするせいで
ちょっと考え込むことが多い・・・・・のですけどねww
演奏や映画なんかは予め”はじめこうなって最後こうなって”っていう細かいシナリオを基に再現するんで
詳細なシナリオが用意されている前提ではない私たちの人生(生まれる成長する老いる死ぬを除きますけどw) と
同じ土俵に上げられるかはちょっと私にはわかんないです(^^;
ただ、夢も現実もいつも後から「どうだったかな」と判断するものであって
「今この瞬間」毎に私達は夢なのか現実なのか【真の意味で同時に】体験しながらの判断・実感はしてないんですよね、現実問題←w
でも、哲学は疑問を明らかにした結果で成立してゆくものなのかもですが
人生は明らかにするという以上に「判断」「選択」の結果で成立する
人間の生というか体験というもんがそういった性質のものなので
後から「夢だ」「現実だ」と判断した通り生きるしかない(>>[86]) っていうのはホントその通りで。
他人から物理的な意味で判断が覆されるような何かがあったら、そのときにまた考えればいいというかw
私の場合は物理的にも第三者と本人で判断が分かれる例を何度も目の当たりにするせいで
ちょっと考え込むことが多い・・・・・のですけどねww
>>[90]
横からごめんなさい、
夢と現実という基準を据えることってのが
生活上完全なる自己完結的な問題じゃなくなっているので
つい「なんとかならんものか」と考えてしまうんだと思うんですよね。
私とかもどっちかというと、そうなんですけどね。
例えば・・・・・・
これはあくまでもライトな例側ですけど(w)
うちのマンション、数年前からどうやら統合失調症のヒトが住み始めてたらしくて
不定期的にもんのすっごい怒声が聞こえるんです、誰かをなじるというか罵るような?声が。
酷いときには一時間くらい、いやもっと?wかな。
最初はだれかと喧嘩してるんだと思ってたんで、声のするとこ突き止めて
うるさい静かにしろって文句言ってやろうと思ってたんですけど
ある日、たまたま外で同じ声を聞いてその場面を直接見たら・・・・・・・
ことば聞いてたら確かに誰かにめっちゃわめいてる風なのに
周りには、だ〜〜〜れもいなかったんですよね(^^;
これは文句言ったところで通用しない って悟りましたw
でも、「始まる」とまじめにうるさいんですよね、しかも
いつ終わるか始まるかもわかんないから、その間気分悪くて
おうちでろくにくつろげないし・・・・(・×・)
(今日は仕事休みで幸いにもそのヒトはどっかいっていないか静かなのでくつろげてますw)
横からごめんなさい、
夢と現実という基準を据えることってのが
生活上完全なる自己完結的な問題じゃなくなっているので
つい「なんとかならんものか」と考えてしまうんだと思うんですよね。
私とかもどっちかというと、そうなんですけどね。
例えば・・・・・・
これはあくまでもライトな例側ですけど(w)
うちのマンション、数年前からどうやら統合失調症のヒトが住み始めてたらしくて
不定期的にもんのすっごい怒声が聞こえるんです、誰かをなじるというか罵るような?声が。
酷いときには一時間くらい、いやもっと?wかな。
最初はだれかと喧嘩してるんだと思ってたんで、声のするとこ突き止めて
うるさい静かにしろって文句言ってやろうと思ってたんですけど
ある日、たまたま外で同じ声を聞いてその場面を直接見たら・・・・・・・
ことば聞いてたら確かに誰かにめっちゃわめいてる風なのに
周りには、だ〜〜〜れもいなかったんですよね(^^;
これは文句言ったところで通用しない って悟りましたw
でも、「始まる」とまじめにうるさいんですよね、しかも
いつ終わるか始まるかもわかんないから、その間気分悪くて
おうちでろくにくつろげないし・・・・(・×・)
(今日は仕事休みで幸いにもそのヒトはどっかいっていないか静かなのでくつろげてますw)
>>[88] 僕もほとんどあいまいな記憶と理解しかないと思いますが、
78910の解釈に同意します。
たしか、デカルトは、
じぶんの普段の日常的な意識では、
自分のこの感じている感覚世界が夢であるなんてことは考えもせず、
自分の身体が本当は自分の身体でなかったり、あるいは存在しないとか、
魂と身体は分離された二つの実体であるとか、
そういうことについて、疑うことは全然ない。
しかし、方法的懐疑をし、哲学をするという条件で考えるなら、
そういう懐疑が導き出すもろもろのものを真理だと考える、とか、
そういうことを言っていた記憶があります。
つまり、78910さんがいう言葉で言えば、
『曖昧だがそう信じて、問題ないからOKとしよう』というレベルの日常的生活意識と、
『疑えるものはすべて疑う』という方法的懐疑の哲学的意識を、
分けて、その二重の意識のもとでものをとらえていた、と考えることもできるわけです。
次からは解釈だけになりますが、
この二つの意識状態は、相互不可分なものだと言え、
1、 「日常的な意識」から方法的懐疑を経ると「哲学的意識」のレベルに至る。
2、 「哲学的意識」では日常生活は送れないので、それは、「日常的な意識」レベルへと、回帰する。
僕が問題にしているのは、この2の部分の、流れです。
デカルトが、方法的懐疑で、感覚的世界、論理の世界、自分の身体と魂、そして、
世界の現実性など、どのように疑っても、
否定しても否定しても迫りくるものとして、われ思うゆえにわれあり、というのがあった。
ここから不思議なんですが、「欺く神」などを想定していたり着いた結論である、この第一命題から、
神の存在や、論理の正しさや、世界の現実性などが自然に回復してくる。
この問題は、デカルト循環というパラドクスに関係があり、
たとえば、「デカルトの推論も一つの論理的推論である」と考えると、
「それも欺く神が見せているものにすぎない」となって、打ち捨てられてしまう。
なぜそうならないのかと言えば、神が正しくこの世界を作っているから、という結論になります。
すくなくとも、後世で、スピノザは、そのように解釈している。
この「現実回復」の過程です。
78910の解釈に同意します。
たしか、デカルトは、
じぶんの普段の日常的な意識では、
自分のこの感じている感覚世界が夢であるなんてことは考えもせず、
自分の身体が本当は自分の身体でなかったり、あるいは存在しないとか、
魂と身体は分離された二つの実体であるとか、
そういうことについて、疑うことは全然ない。
しかし、方法的懐疑をし、哲学をするという条件で考えるなら、
そういう懐疑が導き出すもろもろのものを真理だと考える、とか、
そういうことを言っていた記憶があります。
つまり、78910さんがいう言葉で言えば、
『曖昧だがそう信じて、問題ないからOKとしよう』というレベルの日常的生活意識と、
『疑えるものはすべて疑う』という方法的懐疑の哲学的意識を、
分けて、その二重の意識のもとでものをとらえていた、と考えることもできるわけです。
次からは解釈だけになりますが、
この二つの意識状態は、相互不可分なものだと言え、
1、 「日常的な意識」から方法的懐疑を経ると「哲学的意識」のレベルに至る。
2、 「哲学的意識」では日常生活は送れないので、それは、「日常的な意識」レベルへと、回帰する。
僕が問題にしているのは、この2の部分の、流れです。
デカルトが、方法的懐疑で、感覚的世界、論理の世界、自分の身体と魂、そして、
世界の現実性など、どのように疑っても、
否定しても否定しても迫りくるものとして、われ思うゆえにわれあり、というのがあった。
ここから不思議なんですが、「欺く神」などを想定していたり着いた結論である、この第一命題から、
神の存在や、論理の正しさや、世界の現実性などが自然に回復してくる。
この問題は、デカルト循環というパラドクスに関係があり、
たとえば、「デカルトの推論も一つの論理的推論である」と考えると、
「それも欺く神が見せているものにすぎない」となって、打ち捨てられてしまう。
なぜそうならないのかと言えば、神が正しくこの世界を作っているから、という結論になります。
すくなくとも、後世で、スピノザは、そのように解釈している。
この「現実回復」の過程です。
>「夢と現実を区別しうる確かなしるしが全くないことに気付き、私はすっかり驚いてしまい、今、私は夢を見ているのだと信じかねないほどなのである。」
By デカルト
普段私たちが何気なく信じている夢と現実の区別・境界線について、
いったんその信念の握りしめをゆるめた所から、
私たちが現実と思っているものについて
「これも夢だとどうして言えないのか? これ自体、巨大な巨大な夢の中かもしれない、と疑いうるではないか!」
とデカルトは考え、また私たちも彼とまったく同じように考えることが可能である。
現実とは何か?
こうして一所懸命、問いを立て、頭を悩まし、ああでもないこうでもないとやっている私たちのこの知覚そのものはとりあえず私たちに確かなものとして感じられる(こういうものをフッサールは〈内在〉と呼んだ)。
このフッサールが言うところの、確かに知覚として疑いえないととりあえず私たちが落ち着き、それ以上あえて疑う動機が日常的には尽きてしまう内在こそ、
私たちが夢と区別して現実という名称を〈超越〉的に与えてしまう世界の根拠に他ならない。
「これは現実である」という同定は内在を越えた超越であり、超越は常に疑いうるのは間違いないが、
私たちがこの超越に対して、とりあえずこれ以上疑うことを馬鹿らしいと考えて、疑う気持ちがなえてしまうような知覚(すなわち内在)を対応させているなら、
私たちは将来に(たとえば2050年に)巨大な夢が醒めてしまわない限り、
これが現実だと思っていていいのである。
By デカルト
普段私たちが何気なく信じている夢と現実の区別・境界線について、
いったんその信念の握りしめをゆるめた所から、
私たちが現実と思っているものについて
「これも夢だとどうして言えないのか? これ自体、巨大な巨大な夢の中かもしれない、と疑いうるではないか!」
とデカルトは考え、また私たちも彼とまったく同じように考えることが可能である。
現実とは何か?
こうして一所懸命、問いを立て、頭を悩まし、ああでもないこうでもないとやっている私たちのこの知覚そのものはとりあえず私たちに確かなものとして感じられる(こういうものをフッサールは〈内在〉と呼んだ)。
このフッサールが言うところの、確かに知覚として疑いえないととりあえず私たちが落ち着き、それ以上あえて疑う動機が日常的には尽きてしまう内在こそ、
私たちが夢と区別して現実という名称を〈超越〉的に与えてしまう世界の根拠に他ならない。
「これは現実である」という同定は内在を越えた超越であり、超越は常に疑いうるのは間違いないが、
私たちがこの超越に対して、とりあえずこれ以上疑うことを馬鹿らしいと考えて、疑う気持ちがなえてしまうような知覚(すなわち内在)を対応させているなら、
私たちは将来に(たとえば2050年に)巨大な夢が醒めてしまわない限り、
これが現実だと思っていていいのである。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
哲学が好き 更新情報
哲学が好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75494人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9044人