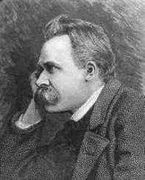今日、自然科学的主張は全て仮説と表現されています。
これは、古くは定説とされていたものが後に否定され、別の事実が認められてきた経緯あってのことです。
ニュートン力学はその有効性は今尚であるものの、宇宙や微粒子といったミクロ・マクロの世界を扱う科学分野から見れば条件つきの法則であり、少なくともその万能性は崩れ去ってしまいました。
しかし、この「全て仮説」とはどういうことでしょうか?
科学の厳正さと慎重さを重視する考えは容易に理解出来ますが、これを適用すれば「地球は丸い」「太陽は東から昇る」「人は水中で呼吸出来ない」といった当たり前のことまで仮説となってしまいます。
個人的にこの「自然科学的主張は全て仮説」とする概念は、科学が「自然の斉一性」への依存性が強く関わっていることを考えました。
自然の斉一性
http://
太陽の動きは多くの科学的観測とデータ分析により予測され、また我々が太陽の運動が今日も明日も変わらないことを観測することは容易です。これらの事実の蓄積から、(日食というイレギュラーは別として。そもそも日食は太陽を遮断するだけ)明日も太陽は東から昇ることは明言出来ます。反面これは、自然現象が今日も明日も変わらない法則で働き続けるという原則に立っての予測であり、(とても考えられないことですが)もし仮に一度でも太陽が西から昇る現象が観測されれば、定説である筈の太陽の運動についての科学的根拠が根底から崩れてしまうことになります。
そしてこの自然の斉一性、科学の根底の1つでありながら実際には帰納法的手段でのみ認められる原則であり、科学で証明することが出来ません。
五感とは我々が考える以上に偏りが強く、錯覚に捉われるものです。
その人の知覚能力の落とし穴に陥らないが為の科学的手法ではありますが、同時に科学的手法を認めるには、こうした矛盾を飲み込む必要があるのも事実です。
科学的主張を全て仮説と考えるには、何もこのような意図だけではありません。そしてまた、今回のような主張は詭弁でもありますが、科学という概念を考えるきっかけとしては有用ではないかと考えました。
全てを『仮説』とするこの考え、いかに解釈すれば良いでしょうか?
御意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
これは、古くは定説とされていたものが後に否定され、別の事実が認められてきた経緯あってのことです。
ニュートン力学はその有効性は今尚であるものの、宇宙や微粒子といったミクロ・マクロの世界を扱う科学分野から見れば条件つきの法則であり、少なくともその万能性は崩れ去ってしまいました。
しかし、この「全て仮説」とはどういうことでしょうか?
科学の厳正さと慎重さを重視する考えは容易に理解出来ますが、これを適用すれば「地球は丸い」「太陽は東から昇る」「人は水中で呼吸出来ない」といった当たり前のことまで仮説となってしまいます。
個人的にこの「自然科学的主張は全て仮説」とする概念は、科学が「自然の斉一性」への依存性が強く関わっていることを考えました。
自然の斉一性
http://
太陽の動きは多くの科学的観測とデータ分析により予測され、また我々が太陽の運動が今日も明日も変わらないことを観測することは容易です。これらの事実の蓄積から、(日食というイレギュラーは別として。そもそも日食は太陽を遮断するだけ)明日も太陽は東から昇ることは明言出来ます。反面これは、自然現象が今日も明日も変わらない法則で働き続けるという原則に立っての予測であり、(とても考えられないことですが)もし仮に一度でも太陽が西から昇る現象が観測されれば、定説である筈の太陽の運動についての科学的根拠が根底から崩れてしまうことになります。
そしてこの自然の斉一性、科学の根底の1つでありながら実際には帰納法的手段でのみ認められる原則であり、科学で証明することが出来ません。
五感とは我々が考える以上に偏りが強く、錯覚に捉われるものです。
その人の知覚能力の落とし穴に陥らないが為の科学的手法ではありますが、同時に科学的手法を認めるには、こうした矛盾を飲み込む必要があるのも事実です。
科学的主張を全て仮説と考えるには、何もこのような意図だけではありません。そしてまた、今回のような主張は詭弁でもありますが、科学という概念を考えるきっかけとしては有用ではないかと考えました。
全てを『仮説』とするこの考え、いかに解釈すれば良いでしょうか?
御意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
|
|
|
|
コメント(52)
> タカヤ氏
横から失礼。
補足しておきます。
簡潔に述べれば、科学は“これが真理だ”と言えても“真理とは何か?”について言及を重ねるような学問ではないと言うことです。
古代ギリシャ時代には学問の明確な区分がなく、哲学が哲学として認知されるようになったのはソフィスト(知者)が現れてからのものです。
元々は、『宇宙(コスモロジー)・自然(ピュシス)の究極原理(ロゴス)の探求』するもの、それがソフィストの出現により人間中心の問い掛けにシフトチェンジしていったとされています。
哲学は“万学の王”と言われた時代もあり、西洋では全ての学問の上位に位置付けられていました。
史実に興味があれば「自由七科」を調べてみると良いでしょう。
まあ、学問そのものは神話の世界から生まれたものだと思いますけれど・・・
横から失礼。
補足しておきます。
簡潔に述べれば、科学は“これが真理だ”と言えても“真理とは何か?”について言及を重ねるような学問ではないと言うことです。
古代ギリシャ時代には学問の明確な区分がなく、哲学が哲学として認知されるようになったのはソフィスト(知者)が現れてからのものです。
元々は、『宇宙(コスモロジー)・自然(ピュシス)の究極原理(ロゴス)の探求』するもの、それがソフィストの出現により人間中心の問い掛けにシフトチェンジしていったとされています。
哲学は“万学の王”と言われた時代もあり、西洋では全ての学問の上位に位置付けられていました。
史実に興味があれば「自由七科」を調べてみると良いでしょう。
まあ、学問そのものは神話の世界から生まれたものだと思いますけれど・・・
「科学は仮説」というのは問題があると考えます。
それを肯定すると現在使用中の知識を仮説とせねばならず、無責任なことになります。
たとえば、
「この検査結果からするとあなた癌ですね。仮説ですけど。」
「この治療法は有効で安全だと思います。仮説ですけど。」
とかほざく医者は殴るしかないですよね。
そうでなくても、何らかの知識を行為において使用することは、信じるのと同じことですから、真理として扱うのと実質的に同じことです。仮説もへったくれもありません。
こういう困った事態を防ぐには、仮説という言葉・概念を使わなければいいわけです。
「仮説」は、「真理」と対になっています。真理は疑うべからざるものという意味を持っています。
また、仮説は「検証」によって真理に格上げされると考えられています。
仮説→検証→真理は正当化主義です。これはマズイのです。
上で誰かが言っておられましたが、「カラスは黒い(全てのXについてXがカラスであるならばXは黒い)」は、「一羽の黒くないカラスの存在」によって否定されます。そうである以上、「カラスは黒い」を検証するためには、全てのカラスを実際に調べなければなりません。
しかも、検証を重ねることによってより確からしいと言うことはできない。
100羽調べるより一億羽調べた方が確からしいとは言えないわけです。全部でなければダメです。
そこで、仮説・検証・真理に替えて、
「理論」「反証」「実在」
を使うことにする。
理論は何でもいいわけです。ただし、実験によって反証できるものでなければなりません。反証可能性です。実験とは広義のもので言わば反証例探しでよいです。
反証は理論をデリートすることです。
実験が理論の価値を高めることはできないのは先に説明したとおりですが、否定することはできます。
そうやって言わば「ドS」的に理論を批判し、間違った理論を排除してゆこうというわけです。
そうして厳しいテストに耐えた理論が「生き残る」わけです。
知ってる人が多いと思いますが、これはポパーの「批判的合理主義」の考えです。
以上は知ってる人が多いのですが、問題は以下です。
科学理論の使用はどうやって正当化されるのかです。
ポパーは、「最もよくテストされた理論を選択すべきである」と言っています。
「よく」とは「カラス一億羽」というような検証の積み重ねを思わせますが、違うのだそうです。「よく」とは、「多様な」という意味なのだそうです。
多様な反証の試みに耐えた理論は、「実在」によく適合しているわけです。
ポパーは実は、実在論に立ち自然法則の厳存を認めているわけです。
それを肯定すると現在使用中の知識を仮説とせねばならず、無責任なことになります。
たとえば、
「この検査結果からするとあなた癌ですね。仮説ですけど。」
「この治療法は有効で安全だと思います。仮説ですけど。」
とかほざく医者は殴るしかないですよね。
そうでなくても、何らかの知識を行為において使用することは、信じるのと同じことですから、真理として扱うのと実質的に同じことです。仮説もへったくれもありません。
こういう困った事態を防ぐには、仮説という言葉・概念を使わなければいいわけです。
「仮説」は、「真理」と対になっています。真理は疑うべからざるものという意味を持っています。
また、仮説は「検証」によって真理に格上げされると考えられています。
仮説→検証→真理は正当化主義です。これはマズイのです。
上で誰かが言っておられましたが、「カラスは黒い(全てのXについてXがカラスであるならばXは黒い)」は、「一羽の黒くないカラスの存在」によって否定されます。そうである以上、「カラスは黒い」を検証するためには、全てのカラスを実際に調べなければなりません。
しかも、検証を重ねることによってより確からしいと言うことはできない。
100羽調べるより一億羽調べた方が確からしいとは言えないわけです。全部でなければダメです。
そこで、仮説・検証・真理に替えて、
「理論」「反証」「実在」
を使うことにする。
理論は何でもいいわけです。ただし、実験によって反証できるものでなければなりません。反証可能性です。実験とは広義のもので言わば反証例探しでよいです。
反証は理論をデリートすることです。
実験が理論の価値を高めることはできないのは先に説明したとおりですが、否定することはできます。
そうやって言わば「ドS」的に理論を批判し、間違った理論を排除してゆこうというわけです。
そうして厳しいテストに耐えた理論が「生き残る」わけです。
知ってる人が多いと思いますが、これはポパーの「批判的合理主義」の考えです。
以上は知ってる人が多いのですが、問題は以下です。
科学理論の使用はどうやって正当化されるのかです。
ポパーは、「最もよくテストされた理論を選択すべきである」と言っています。
「よく」とは「カラス一億羽」というような検証の積み重ねを思わせますが、違うのだそうです。「よく」とは、「多様な」という意味なのだそうです。
多様な反証の試みに耐えた理論は、「実在」によく適合しているわけです。
ポパーは実は、実在論に立ち自然法則の厳存を認めているわけです。
> せり氏
その見識は、現実世界に規定される事実であって直感的に知覚される常識的判断に基づく見解が合理的妥当性のあるものとして認識されることによるもの。
それが無条件に“ 現実を受け入れて信じざるを得ない”という理性的判断を生む。
何度でも言うが事実を用いて「〜べきである」という断定的要素を導くことは出来ない。あくまでもそういう倫理観は自己規定概念に適用されてくるもの。
信じる信じないの話。
話が逸れてしまったが、客観的実在性としての存在と認識論的存在とが混在して語られてくると頭が混乱してくる。
実在論を用いるのであれば、反実在論も見ておかなければならない。
現実対応させる意味で言っているのであれば、その通りであるとは思う。
その見識は、現実世界に規定される事実であって直感的に知覚される常識的判断に基づく見解が合理的妥当性のあるものとして認識されることによるもの。
それが無条件に“ 現実を受け入れて信じざるを得ない”という理性的判断を生む。
何度でも言うが事実を用いて「〜べきである」という断定的要素を導くことは出来ない。あくまでもそういう倫理観は自己規定概念に適用されてくるもの。
信じる信じないの話。
話が逸れてしまったが、客観的実在性としての存在と認識論的存在とが混在して語られてくると頭が混乱してくる。
実在論を用いるのであれば、反実在論も見ておかなければならない。
現実対応させる意味で言っているのであれば、その通りであるとは思う。
>32 myinyaさん
「カラスは黒い」は、帰納による正当化が無効であることを示すための極度に単純な実例です。
このレベルで重要なのは、調べられているかどうかです。
「『カラスは黒い』は聖なる教えの書に記されておるから真理である」とか言って、白いカラスについての報告を握りつぶしたり、カラスの色にかんする研究を弾圧したりしてないことが重要なわけです。
反証テストが継続的に行われているかぎりにおいて、黒くないカラスが未だ発見されていない状況では、「黒い」は理論として有効なんだと思います。
28>の最後に述べた理論の選択の問題は、あるテーマにおいて複数の理論が競合する場合に、ある一つの理論を支持する根拠について述べたものだと思います。
たとえば、太陽系に関する天動説と地動説、生物における創造説と進化論などです。宇宙物理学なんかでも複数の理論が競合してます。
そこで多様な反証テストが問題になるわけです。
比較優位のことなんではないか、と私は解釈してます。これについては完全にはっきりしてないところがあるので、また勉強してみます。
>33 春助さん
これは自然科学における事実認識についての話です。自然科学は実在の探求がすべてですので、約束として素朴実在論です。頭ごなしにド唯物論です。
哲学・宗教・形而上学における真理を扱うには、また別の方法が必要なわけです。
「カラスは黒い」は、帰納による正当化が無効であることを示すための極度に単純な実例です。
このレベルで重要なのは、調べられているかどうかです。
「『カラスは黒い』は聖なる教えの書に記されておるから真理である」とか言って、白いカラスについての報告を握りつぶしたり、カラスの色にかんする研究を弾圧したりしてないことが重要なわけです。
反証テストが継続的に行われているかぎりにおいて、黒くないカラスが未だ発見されていない状況では、「黒い」は理論として有効なんだと思います。
28>の最後に述べた理論の選択の問題は、あるテーマにおいて複数の理論が競合する場合に、ある一つの理論を支持する根拠について述べたものだと思います。
たとえば、太陽系に関する天動説と地動説、生物における創造説と進化論などです。宇宙物理学なんかでも複数の理論が競合してます。
そこで多様な反証テストが問題になるわけです。
比較優位のことなんではないか、と私は解釈してます。これについては完全にはっきりしてないところがあるので、また勉強してみます。
>33 春助さん
これは自然科学における事実認識についての話です。自然科学は実在の探求がすべてですので、約束として素朴実在論です。頭ごなしにド唯物論です。
哲学・宗教・形而上学における真理を扱うには、また別の方法が必要なわけです。
>36 のむらさん
受け売りなので、文献を紹介しときます。
■「批判的合理主義の思想」蔭山 泰之著 ポイエーシス叢書44 未来社
http://www.amazon.co.jp/%E6%89%B9%E5%88%A4%E7%9A%84%E5%90%88%E7%90%86%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E6%80%9D%E6%83%B3-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E5%8F%A2%E6%9B%B8-44-%E8%94%AD%E5%B1%B1-%E6%B3%B0%E4%B9%8B/dp/4624932447
哲学者じゃない、システムエンジニアが書いた本ですけど、私の知る限り最良の入門書です。
それで、のむらさんには大体わかっていただいていると思います。
「科学は仮説」は盲信しやすい一般大衆を啓蒙する意義があると思います。
しかし仮説という漢語はやはり真理への格上げを想起させる点で、違和感があります。英語ではどうなんだろうね。
行為において使用の状態にある理論は、当該個人にとっては真理と同じ扱いなのではないか。決断や選択がありますし、やり直しが効かないこともあるからね。
とすると仮説だと言い張ると行為の正当化が出来なくなると思わない?
(逆に言うと、もうやっちまったことは正当化するしかない。これが宗教の始まりなんではないかと思う)
理論の選択という考えを導入すると真理のキュークツさから解放されるのではないでしょうか。
進化論には独特の問題があって、歴史に属するこの理論には「反証可能性」があるのか、という話があります。この話は創造論の人のお気に入りなんだけど(笑
化石掘るのも「実験」か?
その辺はいまいちよくわからない。
もちまささんがどこかで言ったように、白亜紀の地層から人間でも出てくれば崩壊するでしょうねえ、進化論は。
受け売りなので、文献を紹介しときます。
■「批判的合理主義の思想」蔭山 泰之著 ポイエーシス叢書44 未来社
http://www.amazon.co.jp/%E6%89%B9%E5%88%A4%E7%9A%84%E5%90%88%E7%90%86%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E6%80%9D%E6%83%B3-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E5%8F%A2%E6%9B%B8-44-%E8%94%AD%E5%B1%B1-%E6%B3%B0%E4%B9%8B/dp/4624932447
哲学者じゃない、システムエンジニアが書いた本ですけど、私の知る限り最良の入門書です。
それで、のむらさんには大体わかっていただいていると思います。
「科学は仮説」は盲信しやすい一般大衆を啓蒙する意義があると思います。
しかし仮説という漢語はやはり真理への格上げを想起させる点で、違和感があります。英語ではどうなんだろうね。
行為において使用の状態にある理論は、当該個人にとっては真理と同じ扱いなのではないか。決断や選択がありますし、やり直しが効かないこともあるからね。
とすると仮説だと言い張ると行為の正当化が出来なくなると思わない?
(逆に言うと、もうやっちまったことは正当化するしかない。これが宗教の始まりなんではないかと思う)
理論の選択という考えを導入すると真理のキュークツさから解放されるのではないでしょうか。
進化論には独特の問題があって、歴史に属するこの理論には「反証可能性」があるのか、という話があります。この話は創造論の人のお気に入りなんだけど(笑
化石掘るのも「実験」か?
その辺はいまいちよくわからない。
もちまささんがどこかで言ったように、白亜紀の地層から人間でも出てくれば崩壊するでしょうねえ、進化論は。
「仮説」についてナーバスな部分の議論が行われ、この場での結論も出されたようですが
科学的「仮説」の捉え方について私にはちょっと引っ掛かったので、補足のような形で少し書かせて下さい。
>0 自然の斉一性
との絡みで全ての仮定を疑ってみることが私もあります。・・しかし、そこから自分は「仮説」をどう考えるか決めないと、根底がグラグラしてしまうような気がして、この問題には何度も立ち返ってよく考えるのです。
>0 ニュートン力学はその有効性は今尚であるものの、宇宙や微粒子といったミクロ・マクロの世界を扱う科学分野から見れば条件つきの法則であり、少なくともその万能性は崩れ去ってしまいました。
考え方なんですが、物理学で言えばこのニュートン力学から量子論への移行には大きな概念の変換が必要でした。ここでいう条件付き仮説を含む、をどう解釈するかはとても大切だと思います。
実験精度が上がってプランク・スケールまで降りるとそこには不確定性定理の世界があるのですが、これを不確定だからすでに説(仮説)は成り立たないのじゃないか?と考えるのではなく、量子(電子や中性子・陽子など)の振る舞いを塊(場の理論)ごと受け入れようとする考え方です。
不確定であっても「場」という概念を導入することで、乗り越えられる問題もあったわけです。ここでは、人間の物理的限界に立ち入らずとも概念自体の変換が科学を前進させた例だと思います。←視点の拡大
それから、
>0その人の知覚能力の落とし穴に陥らないが為の科学的手法ではありますが、同時に科学的手法を認めるには、こうした矛盾を飲み込む必要があるのも事実です
矛盾を飲み込むとはちょっと違うような気がします。
むしろ矛盾を見つめて追及していく。人間の物理的な限界や理性の限界を見つめつつも、その範疇を押し広げていこうとするのが科学ではないかと思うのです。
近年の物理学では、「一般相対性理論」との統合ができていない高エネルギーな領域で、「超ひも理論」や「超対称性粒子の存在」といった仮説が取りざたされています。これらは式にすでに虚数部分を含んでおり(どんどん数学的イメージの世界になっていきますが)充分理性の限界を越えているものだと思います。
最近では「ループ量子重力理論」などという新しい考え方もありますが、これも量子論が古典物理学を超えたように、なんらかのパラダイム・シフトを齎すものかもしれません。つまり、物理学においては理性の限界を押し広げる変換が起こる可能性を、含んでいるんじゃないかと思うのです。
(ループ量子重力理論)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%87%8D%E5%8A%9B%E7%90%86%E8%AB%96
これらはまだ「仮説」ですが、それをどのような視点で捉えるかが大切だと思います。
その辺りに分野によって違いがあるのかどうか私にはよくわかりませんが、新しい発見が思想さえを塗り替える可能性が常にあるように思うのです。
そして、このことはプラトンのイデア界に代表されるような、「世界は虚構である」という考えに傾きがちな科学思想の捉え方とは、一線を画すものであるとも思います。
何故なら、相対性理論や量子論は実験技術と実験精度の向上において、充分検証可能な部分を含むからです。
科学的「仮説」の捉え方について私にはちょっと引っ掛かったので、補足のような形で少し書かせて下さい。
>0 自然の斉一性
との絡みで全ての仮定を疑ってみることが私もあります。・・しかし、そこから自分は「仮説」をどう考えるか決めないと、根底がグラグラしてしまうような気がして、この問題には何度も立ち返ってよく考えるのです。
>0 ニュートン力学はその有効性は今尚であるものの、宇宙や微粒子といったミクロ・マクロの世界を扱う科学分野から見れば条件つきの法則であり、少なくともその万能性は崩れ去ってしまいました。
考え方なんですが、物理学で言えばこのニュートン力学から量子論への移行には大きな概念の変換が必要でした。ここでいう条件付き仮説を含む、をどう解釈するかはとても大切だと思います。
実験精度が上がってプランク・スケールまで降りるとそこには不確定性定理の世界があるのですが、これを不確定だからすでに説(仮説)は成り立たないのじゃないか?と考えるのではなく、量子(電子や中性子・陽子など)の振る舞いを塊(場の理論)ごと受け入れようとする考え方です。
不確定であっても「場」という概念を導入することで、乗り越えられる問題もあったわけです。ここでは、人間の物理的限界に立ち入らずとも概念自体の変換が科学を前進させた例だと思います。←視点の拡大
それから、
>0その人の知覚能力の落とし穴に陥らないが為の科学的手法ではありますが、同時に科学的手法を認めるには、こうした矛盾を飲み込む必要があるのも事実です
矛盾を飲み込むとはちょっと違うような気がします。
むしろ矛盾を見つめて追及していく。人間の物理的な限界や理性の限界を見つめつつも、その範疇を押し広げていこうとするのが科学ではないかと思うのです。
近年の物理学では、「一般相対性理論」との統合ができていない高エネルギーな領域で、「超ひも理論」や「超対称性粒子の存在」といった仮説が取りざたされています。これらは式にすでに虚数部分を含んでおり(どんどん数学的イメージの世界になっていきますが)充分理性の限界を越えているものだと思います。
最近では「ループ量子重力理論」などという新しい考え方もありますが、これも量子論が古典物理学を超えたように、なんらかのパラダイム・シフトを齎すものかもしれません。つまり、物理学においては理性の限界を押し広げる変換が起こる可能性を、含んでいるんじゃないかと思うのです。
(ループ量子重力理論)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%87%8D%E5%8A%9B%E7%90%86%E8%AB%96
これらはまだ「仮説」ですが、それをどのような視点で捉えるかが大切だと思います。
その辺りに分野によって違いがあるのかどうか私にはよくわかりませんが、新しい発見が思想さえを塗り替える可能性が常にあるように思うのです。
そして、このことはプラトンのイデア界に代表されるような、「世界は虚構である」という考えに傾きがちな科学思想の捉え方とは、一線を画すものであるとも思います。
何故なら、相対性理論や量子論は実験技術と実験精度の向上において、充分検証可能な部分を含むからです。
仮説とゆーても
何をもとに言説を立ち上げるかにより「仮」の重みは変動しますね。
あるいは、「公理」をどのようなものとして捕らえるのかにも。
仮説とは個人的には、言説を説くものの独善的に陥るつもりはありませんという意味を含む社交辞令によく用いられているような気もして
蓋然性をある程度承認された公理をもとに言説を説くとき、かなりのヒトは
「仮説ととりあえず公言するが、これを真理と私は信じる」といった姿勢があるようにも感じられます。
、と言説への個人的スタンスはともかくとして
私は、これは仮説ではないと言いきれる言説を知りません。
仮説が仮説でなくなる瞬間とは、いかなるものなんでしょうか?
……と、とりあえずあげてみよう………|×・)
何をもとに言説を立ち上げるかにより「仮」の重みは変動しますね。
あるいは、「公理」をどのようなものとして捕らえるのかにも。
仮説とは個人的には、言説を説くものの独善的に陥るつもりはありませんという意味を含む社交辞令によく用いられているような気もして
蓋然性をある程度承認された公理をもとに言説を説くとき、かなりのヒトは
「仮説ととりあえず公言するが、これを真理と私は信じる」といった姿勢があるようにも感じられます。
、と言説への個人的スタンスはともかくとして
私は、これは仮説ではないと言いきれる言説を知りません。
仮説が仮説でなくなる瞬間とは、いかなるものなんでしょうか?
……と、とりあえずあげてみよう………|×・)
>>[43]
してみる事ができるものに関してはそれで大丈夫そうですね。
ただ、仮説というのは「して」説くものと「みて」説くものと二通りあるんではないでしょうか。
例えば地動説などは明らかに「その通りにしてみる」ことでうまくいって
仮説じゃないかのように説かれているわけではないところがありますよね。
しかし、一応昔は一時期天動説が説かれてそれが信じ続けられてきた歴史もあって
そこが地動説を仮説という概念から脱することを許さぬ要素になってるのでは
とすら思えてしまいます。
「一度変わった事があるものは変わらないと言い切れない」というような。
それを云ってしまうと、
人間の一生涯を超え宇宙の歴史を超え、それでもなお普遍の事実
ということ以外は、全て仮説扱いから脱しきれない
ということになってしまう(トピ主さんと同じような帰結)のでは、と。
してみる事ができるものに関してはそれで大丈夫そうですね。
ただ、仮説というのは「して」説くものと「みて」説くものと二通りあるんではないでしょうか。
例えば地動説などは明らかに「その通りにしてみる」ことでうまくいって
仮説じゃないかのように説かれているわけではないところがありますよね。
しかし、一応昔は一時期天動説が説かれてそれが信じ続けられてきた歴史もあって
そこが地動説を仮説という概念から脱することを許さぬ要素になってるのでは
とすら思えてしまいます。
「一度変わった事があるものは変わらないと言い切れない」というような。
それを云ってしまうと、
人間の一生涯を超え宇宙の歴史を超え、それでもなお普遍の事実
ということ以外は、全て仮説扱いから脱しきれない
ということになってしまう(トピ主さんと同じような帰結)のでは、と。
>>[46]
>天動説について言えば日常的には依然として現役です。
ああ、「お日さまが昇った沈んだ」とかそういうののことですね。
地動説的にいえば本来ならば
「お日さまが見える位置に地上が動いた見えない位置に動いた」となるところが
そうではないことがさも天動説的であると。
ただ、それは天動説が真実で地動説が仮説だからそのように日常で表現しているということではなく
地動説の立場で全ての人間生活の営みを表現すると長い説明になってめんどくさいからとか
そういった次元なのではないでしょうか(^^;
>「あらゆることを説明してやろう」という立場からはどんな説明も仮説です。
例えば、「1+1=2」という公式など、いまのところこれを仮説とは言いませんが
1とは何を以ってして1というのか?という部分で研究が進み
仮にそこでの1という表現が棄却されそうになったときに”「1+1=2」は仮説に過ぎないのでは”となる
・・・・・・・という観点での「あらゆること」でしょうか?
>天動説について言えば日常的には依然として現役です。
ああ、「お日さまが昇った沈んだ」とかそういうののことですね。
地動説的にいえば本来ならば
「お日さまが見える位置に地上が動いた見えない位置に動いた」となるところが
そうではないことがさも天動説的であると。
ただ、それは天動説が真実で地動説が仮説だからそのように日常で表現しているということではなく
地動説の立場で全ての人間生活の営みを表現すると長い説明になってめんどくさいからとか
そういった次元なのではないでしょうか(^^;
>「あらゆることを説明してやろう」という立場からはどんな説明も仮説です。
例えば、「1+1=2」という公式など、いまのところこれを仮説とは言いませんが
1とは何を以ってして1というのか?という部分で研究が進み
仮にそこでの1という表現が棄却されそうになったときに”「1+1=2」は仮説に過ぎないのでは”となる
・・・・・・・という観点での「あらゆること」でしょうか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
哲学が好き 更新情報
哲学が好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人