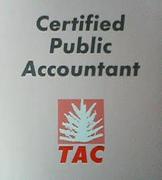22年度論文式の合格者数約2000人から逆算すると・・・
(先日、会計士試験についての懇談会で当面合格者数を2000名にと意見された↓下記記事参照)
http://
論文受験者数 偏差値52基準→約6000人
?20年度 短答合格免除者 1500人
?21年度 短答合格免除者 1500人
?大学院卒等短答免除 800人
?22年度短答合格者数(12月・5月合算) 6000人−(?+?+?)=2200人
12月と来年5月短答の受験者レベルを勘案すると
今年5月合格ラインの読みが外れて惜しくも涙を飲んだ受験生や
短答に集中できる環境(論文はほぼ考えなくていい環境)のある12月の方が
合格者数は若干多い。
よって12月の合格ラインの読みは・・・↓
短答式?受験者数 17,583人
合格者数 1200人
合格率 約7%
O原データリサーチから推測(本年度と昨年度のデータリサーチを踏まえて)
得点比率 75%で合格ライン。
と考えています。
皆さんはどう思いますか?
(先日、会計士試験についての懇談会で当面合格者数を2000名にと意見された↓下記記事参照)
http://
論文受験者数 偏差値52基準→約6000人
?20年度 短答合格免除者 1500人
?21年度 短答合格免除者 1500人
?大学院卒等短答免除 800人
?22年度短答合格者数(12月・5月合算) 6000人−(?+?+?)=2200人
12月と来年5月短答の受験者レベルを勘案すると
今年5月合格ラインの読みが外れて惜しくも涙を飲んだ受験生や
短答に集中できる環境(論文はほぼ考えなくていい環境)のある12月の方が
合格者数は若干多い。
よって12月の合格ラインの読みは・・・↓
短答式?受験者数 17,583人
合格者数 1200人
合格率 約7%
O原データリサーチから推測(本年度と昨年度のデータリサーチを踏まえて)
得点比率 75%で合格ライン。
と考えています。
皆さんはどう思いますか?
|
|
|
|
コメント(10)
Umaさん>
75%でもありえないってほど今回は簡単だったというのが友達の感想なのでしょうか?
試験前に過去問を解いたのですが、そんなにレベルが違うようには感じなかったです
もちろん予備校の短答用の問題集が過去問を参考に作られていることで過去問と似たような問題に解きなれていましたけど、逆に過去問のレベルで69%が合格ラインだった1年前の方が受かりやすかったように思います。
模試でもそうですけど、解説聞いたらすごく簡単な問題だったってことがよくあるじゃないですか
しかもノンプレッシャーの状態で問題を見るんで簡単に思えたのではないでしょうか
自分も各予備校で解答がわれているトコロで75%切っちゃうかもなんでかなり心配です
75%でもありえないってほど今回は簡単だったというのが友達の感想なのでしょうか?
試験前に過去問を解いたのですが、そんなにレベルが違うようには感じなかったです
もちろん予備校の短答用の問題集が過去問を参考に作られていることで過去問と似たような問題に解きなれていましたけど、逆に過去問のレベルで69%が合格ラインだった1年前の方が受かりやすかったように思います。
模試でもそうですけど、解説聞いたらすごく簡単な問題だったってことがよくあるじゃないですか
しかもノンプレッシャーの状態で問題を見るんで簡単に思えたのではないでしょうか
自分も各予備校で解答がわれているトコロで75%切っちゃうかもなんでかなり心配です
面白そうな話なので書き込みさせていただきます。
私はボーダー70%だと思います。
なぜならば・・75%だと財務局側(というか金融庁か)にあまり
メリットがないからです。
いやらしい話ですが
たぶん一つの目的として年2回の試験で国は受験料20000円×10000人が2回
と仮に考えても2回分合計4億の収入が国に増えるわけです。
これは財政が厳しい今の国にとってかなりおいしいはずです。
あまり厳しいラインにすると今後受験しなくなる人の可能性が増えるからです。
メリットがない。
たとえ二回の短答式で合格人数が増えても・・・論文式で合格しなければ
会計士にはなれないわけなので・・・合格人数を調整するのは
論文式だと思いますし。
逆に言えば論文式試験で合格するハードルはかなり高くなると
考えられます。
多分ね(^^♪(笑)
私はボーダー70%だと思います。
なぜならば・・75%だと財務局側(というか金融庁か)にあまり
メリットがないからです。
いやらしい話ですが
たぶん一つの目的として年2回の試験で国は受験料20000円×10000人が2回
と仮に考えても2回分合計4億の収入が国に増えるわけです。
これは財政が厳しい今の国にとってかなりおいしいはずです。
あまり厳しいラインにすると今後受験しなくなる人の可能性が増えるからです。
メリットがない。
たとえ二回の短答式で合格人数が増えても・・・論文式で合格しなければ
会計士にはなれないわけなので・・・合格人数を調整するのは
論文式だと思いますし。
逆に言えば論文式試験で合格するハードルはかなり高くなると
考えられます。
多分ね(^^♪(笑)
70基準を超えて、仮に75をボーダーにした場合、もはや金融庁側は提示した基準を守ることを考えてないと判断することが出来るので、論文の得点比率も、53、54%があり得ると考えられます。
しかし、今回及び5月短答でボーダーを基準値70に留めた場合、論文52基準も守る意思があると推測できると思います。
金融庁の今回の合格者減についてのコメントは「原則(基準値70と52)に戻した」というものでしたから、この原則を今後も守る意思があるならば、今回のボーダーは70、五月のボーダーも70で、論文のボーダーは52%となるのではないでしょうか。
そう仮定した場合、5月短答の難易度を調節して、人数を最終合格者2,000人程度にしてくると思います。
しかし、今回及び5月短答でボーダーを基準値70に留めた場合、論文52基準も守る意思があると推測できると思います。
金融庁の今回の合格者減についてのコメントは「原則(基準値70と52)に戻した」というものでしたから、この原則を今後も守る意思があるならば、今回のボーダーは70、五月のボーダーも70で、論文のボーダーは52%となるのではないでしょうか。
そう仮定した場合、5月短答の難易度を調節して、人数を最終合格者2,000人程度にしてくると思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
公認会計士をめざす会! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
公認会計士をめざす会!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6478人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19254人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人