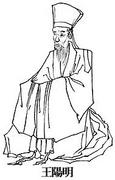http://
以下の文章は「やすいゆたかの部屋」の「日本思想史入門講座」の「近世の思想」からの引用です。ご批評、ご感想いただけましたら幸甚です。
少し触れていますが、本居宣長の「もののあはれ」論は実は陽明学の影響ではないかと感じています。宣長が陽明学に接したという文献的な史料があればいいのですが、内容的には非常に近いと思われませんか。
陽明学の思想
庭前の竹
朱子学に傾倒していた王陽明(1472〜1528) は,『伝習録』によりますと,一木一草に理があるという朱子学の教えを実際に確証しようと, 庭前の竹を切って, その切り口をじっと見つめていました。七日間睨み続けていたのですが, 結局,事物内の理には格(いた)る事ができなかったのです。この逸話は彼が観察と認識の区別が分かっていなかっただけだとも言えるでしょうが,ともかく事物の中に理を求める朱子学の限界を陽明は実感したのです。
事物が心の外にあって,外の事物に理があり,心にも理があるとしますと,心はどのようにして外の物の理に格ることができ,その理と心の理を一つにするにはどうすればよいのでしょうか。陽明にはそれができません。 それで自分は聖賢の器ではないと諦めようともしました。でも朱子によりますと,心とは「主となりて客とならざるもの」なのですから,天地万物の理を窮めつくしそれに倣って心の理を見出さなくても,心の理は心自身の中に見出される筈なのです。
心即理
陽明が37歳の時ですから, 1509年中国は明の時代でした。陽明は宦官劉瑾(りゅうきん) の弾劾運動に加わって,南方の僻地竜場駅に流されました。猛獣毒蛇の住む土地で塗炭の苦しみを体験したのです。彼はその中にあって,自己一身の利害得失や生死のことなど全く捨て去って,ただひたすら道を求めて瞑想したのです。そしてついに理は自分の心にある,元来聖人の道は自分の性の中に具わっているのだと自覚したのです。
実はこの「心即理」は朱子のライバルであった陸象山(1139〜1192) のとなえた説です。象山は性と情を分けられないとし,「心」を渾然たる一者と捉えました。そして心と宇宙を一つだと捉えたのです。「宇宙は即ちこれ吾が心, 吾が心は即ちこれ宇宙。東海に聖人出づるあるも, この心同じきなり, この理同じきなり。」つまり天地の道理も孔孟の教えも,みんな心の理であって,その理に従えば,天と合一し自分自身が理であるから「己の欲するところに従いて矩(のり)をこえず」の境地に達すると考えたのです。
致知格物と知行合一
陽明は「心即理」の立場から「格物致知」の新解釈を行いました。「わたしのいう致知格物は,わが心の良知を事事物物に致すことである。わが心の良知は、天理である。わが心の良知を事事物物に致せば,事事物物みなその理を得るのである。わが心の良知を致すのが『致知』であり,事事物物みなその理を得るのが『格物』である。つまりわたしの立場は,心と理を合一するものにほかならない。」(『伝習録』)
「格物」の「格」は朱子の「いたる」という意味から「正す」という意味に変えられています。「致知」も知識を磨くという意味ではなく,知(良知)を実現するという意味で使われています。良知を実現するのを「致良知」と呼んで強調しました。それに「格物致知」が「致知格物」になっていて,「良知を実現するのが物を正すということだ」という実践的な意味になっています。つまり知ることと行うことは合一しているのです。これを「知行合一」と呼びます。そして実践によって知を磨いていく事を「事上磨錬」と言います。
万物一体の仁
もし心と物とを二元的に捉え,その上で物の理と心の理を一致させようとしても,心と物の究極的な合一が前提でなければ,とても無理だと考えたのです。でも心と物を二元的に捉えていればそれは難しいですね。そこで事事物物も心のありようだと考えれば良いということです。仏教では唯識論にあたりますね。
でもそれぞれの個人が自分の心こそ天理だと主張すれば,天理が一つだという前提が成り立ちません。それでは各人の心がばらばらだというのはどうして生じるのでしょう。それは万物が一体だということを悟らず,自己一身の身体的欲望に囚われて,自分の本来の天理を宿している心を失っているからなのです。心即理ならば天下に心外の事,心外の理などある筈がないのです。ですから全ての事物や全ての人々の姿に心動かされ,それらの心と一つになって情が起こるのが「万物一体の仁」なのです。これは本居宣長の「物の哀れを知る心」と通じていますね。
子供が井戸に落ちそうになった時に起こる惻隠の心,鳥獣の哀しそうな鳴き声を聞いて起こる忍びざる心,草木の枯れ折れるのを見て起こる憐憫の心,瓦石の壊れるのを見て起こる惜む心,これらの心はみな万物一体の仁なのです。
「人は天地の心であり,天地万物はもと吾と一体なるものである。生民の困苦荼毒(とどく),一つとして吾が身に切実な疾痛でないものがあろうか。吾が身の疾痛を知らざる者は『是非の心なき者』というべきである。是非の心は『慮らずして知り,学ばずして能くする』もの,すなわち良知であり,良知は聖と愚、古と今を問わず同一なるものである。」ここでは生民の痛みを自分の痛みと感じないものは,「是非の心」がなく良知に欠けるということになります。
陽明学における主客の統一
このように朱子学の理気二元論や性情分離論を克服した陽明学は,心即理の立場に立って,主観・客観の対立図式を超克します。そのことによって世界を自らの良知を表現するキャンパスにしたのです。このように朱子学における主観・客観認識図式と,陽明学におけるその超克の実例は,前近代においても認識図式をめぐる対立の問題が哲学の根本問題を成していたことを窺わせます。古代では儒墨対老荘ではやはりこの対立は鮮明でした。
1994年に亡くなった廣松渉は, 主・客認識図式がすぐれて近代的な認識図式であり,その超克が近代的な認識図式の超克だという議論を展開していました。そして主・客認識図式は世界が物によって構成されていると考える物的世界観に対応し,その超克の立場は第一義的な存在は事態あるいは事から成り, 物はその物象化的倒錯に陥った解釈にすぎないという事的世界観に対応すると強調していました。しかし古代からそういう対立軸が見られるとしたら, 主・客認識図式の超克や事的世界観の立場は必ずしも近代を超克する立場とは言えないことになるかもしれませんね。
日本の陽明学派
中江藤樹(1608〜1648) は,近江の小川村の生まれでしたが,9歳の時に米子藩の祖父の養子となり,藩主の転封で伊予の大洲(おおず)へ移り,15歳で祖父を失い郡奉行を継ぎました。ところが18歳で故郷の父をなくしてからは, 母への思いが募り27歳で郡奉行をやめて脱藩して故郷に帰ったのです。つまり彼は君主への忠より, 母への孝をとったのです。
33歳の著書『翁問答』では, 「孝」の徳を道徳の根源として説きました。そして生みの親に対する孝に止まらず, 人間の生みの親である天(皇上帝) に対する孝にまで拡げられました。そして社会制度としての身分秩序は認めながらも,「万民は皆ことごとく天地の子なれば、われも人も人間の形ある程のものは、みな兄弟なり。」と万人平等を主張したのです。
そして「孝」の実践の要領を次のように説明します。「孝徳の感通をてぢかくなづけいへば,愛敬の二字にきはまれり。愛はねんごろに親しむ意なり,敬は上をうやまひ,下をかろしめあなどらざる義なり。」この孝の実践こそ陽明の説く「致良知」に他ならないと考え,陽明学に傾倒して,「日本陽明学の祖」と呼ばれたのです。
徳の主体的なはたらきについて藤樹の「権」の思想が注目されます。「権」は「時と所と位」に応じて,その都度適切な道徳判断を行う主体的な心のはたらきです。道徳的判断の主体として責任有る決定が問われたところに,彼の君主をとるか親をとるかの決断の体験が投影していると思われます。
藤樹の弟子熊沢蕃山(1619〜1691) は, 岡山藩の番頭となり, 王道政治を実現しようと努力しました。彼は同士を集めて相互に錬磨しあう花畠教場を主宰します。「花園盟約」で武士の職分は人民の守護育成にありと人民本位の政治を掲げ,致良知に基づく慈愛と勇強の文武の徳性の涵養が学問の目的だとしました。この動きをキリシタンに関係ありと幕府に疑われて, 岡山藩を離れざるを得なくなったのです。
蕃山も時・処・位に応じて変通する態度を強調しました。キリスト教では, 「神への愛と隣人への愛」のように何時でも, 何処でも, 誰に対しても妥当する普遍妥当的原理を重視しますが, 儒教では, たとえ惻隠の心に基づく同じ行為でも時・処・位を弁えていなければ道徳的に評価されないのです。
大塩中斎(平八郎)(1792〜1837) は大坂町奉行所の与力でしたが, 38歳で辞職して家塾洗心洞を開いて子弟の教育にあたりました。当時打ち続く飢饉で農民・都市貧民が飢えているのに, 奉行所や豪商たちは腐敗堕落していました。彼は陽明学で知行合一を教えているのに, これを傍観することができません。ついに「大塩平八郎の乱」を起こしたのです。
彼は「心を太虚に帰す」ことを力説しました。これは人欲を去って精神の純粋性を実現するという意味です。原点に帰ってゼロから出直すという意味に取れば,そのラジカルな意義が分かります。現実の社会体制はたとえ正しい大義名分から出発したとしても,様々な私利私欲や権益によって歪められており,簡単に改革することはできません。かといって現実に民が飢え苦しんでいるのですから,これを救えないなら,いったんゼロに戻して民を救える体制に作り直すしかないのです。
これにヒントを得たわけではありませんが,最近「リエンジニアリング」という方法が抜本的業務改革法として打ち出されています。創業の原点に帰り,業務の目的に最も有効な組織にゼロから組織し直そうという方法です。これを本格的にやられますと,企業の収益は飛躍的に改善される場合もありますが,長年忠勤に励んできた中堅社員まで無用の長物としてばっさり切り捨てられる事がありますから御用心。
以下の文章は「やすいゆたかの部屋」の「日本思想史入門講座」の「近世の思想」からの引用です。ご批評、ご感想いただけましたら幸甚です。
少し触れていますが、本居宣長の「もののあはれ」論は実は陽明学の影響ではないかと感じています。宣長が陽明学に接したという文献的な史料があればいいのですが、内容的には非常に近いと思われませんか。
陽明学の思想
庭前の竹
朱子学に傾倒していた王陽明(1472〜1528) は,『伝習録』によりますと,一木一草に理があるという朱子学の教えを実際に確証しようと, 庭前の竹を切って, その切り口をじっと見つめていました。七日間睨み続けていたのですが, 結局,事物内の理には格(いた)る事ができなかったのです。この逸話は彼が観察と認識の区別が分かっていなかっただけだとも言えるでしょうが,ともかく事物の中に理を求める朱子学の限界を陽明は実感したのです。
事物が心の外にあって,外の事物に理があり,心にも理があるとしますと,心はどのようにして外の物の理に格ることができ,その理と心の理を一つにするにはどうすればよいのでしょうか。陽明にはそれができません。 それで自分は聖賢の器ではないと諦めようともしました。でも朱子によりますと,心とは「主となりて客とならざるもの」なのですから,天地万物の理を窮めつくしそれに倣って心の理を見出さなくても,心の理は心自身の中に見出される筈なのです。
心即理
陽明が37歳の時ですから, 1509年中国は明の時代でした。陽明は宦官劉瑾(りゅうきん) の弾劾運動に加わって,南方の僻地竜場駅に流されました。猛獣毒蛇の住む土地で塗炭の苦しみを体験したのです。彼はその中にあって,自己一身の利害得失や生死のことなど全く捨て去って,ただひたすら道を求めて瞑想したのです。そしてついに理は自分の心にある,元来聖人の道は自分の性の中に具わっているのだと自覚したのです。
実はこの「心即理」は朱子のライバルであった陸象山(1139〜1192) のとなえた説です。象山は性と情を分けられないとし,「心」を渾然たる一者と捉えました。そして心と宇宙を一つだと捉えたのです。「宇宙は即ちこれ吾が心, 吾が心は即ちこれ宇宙。東海に聖人出づるあるも, この心同じきなり, この理同じきなり。」つまり天地の道理も孔孟の教えも,みんな心の理であって,その理に従えば,天と合一し自分自身が理であるから「己の欲するところに従いて矩(のり)をこえず」の境地に達すると考えたのです。
致知格物と知行合一
陽明は「心即理」の立場から「格物致知」の新解釈を行いました。「わたしのいう致知格物は,わが心の良知を事事物物に致すことである。わが心の良知は、天理である。わが心の良知を事事物物に致せば,事事物物みなその理を得るのである。わが心の良知を致すのが『致知』であり,事事物物みなその理を得るのが『格物』である。つまりわたしの立場は,心と理を合一するものにほかならない。」(『伝習録』)
「格物」の「格」は朱子の「いたる」という意味から「正す」という意味に変えられています。「致知」も知識を磨くという意味ではなく,知(良知)を実現するという意味で使われています。良知を実現するのを「致良知」と呼んで強調しました。それに「格物致知」が「致知格物」になっていて,「良知を実現するのが物を正すということだ」という実践的な意味になっています。つまり知ることと行うことは合一しているのです。これを「知行合一」と呼びます。そして実践によって知を磨いていく事を「事上磨錬」と言います。
万物一体の仁
もし心と物とを二元的に捉え,その上で物の理と心の理を一致させようとしても,心と物の究極的な合一が前提でなければ,とても無理だと考えたのです。でも心と物を二元的に捉えていればそれは難しいですね。そこで事事物物も心のありようだと考えれば良いということです。仏教では唯識論にあたりますね。
でもそれぞれの個人が自分の心こそ天理だと主張すれば,天理が一つだという前提が成り立ちません。それでは各人の心がばらばらだというのはどうして生じるのでしょう。それは万物が一体だということを悟らず,自己一身の身体的欲望に囚われて,自分の本来の天理を宿している心を失っているからなのです。心即理ならば天下に心外の事,心外の理などある筈がないのです。ですから全ての事物や全ての人々の姿に心動かされ,それらの心と一つになって情が起こるのが「万物一体の仁」なのです。これは本居宣長の「物の哀れを知る心」と通じていますね。
子供が井戸に落ちそうになった時に起こる惻隠の心,鳥獣の哀しそうな鳴き声を聞いて起こる忍びざる心,草木の枯れ折れるのを見て起こる憐憫の心,瓦石の壊れるのを見て起こる惜む心,これらの心はみな万物一体の仁なのです。
「人は天地の心であり,天地万物はもと吾と一体なるものである。生民の困苦荼毒(とどく),一つとして吾が身に切実な疾痛でないものがあろうか。吾が身の疾痛を知らざる者は『是非の心なき者』というべきである。是非の心は『慮らずして知り,学ばずして能くする』もの,すなわち良知であり,良知は聖と愚、古と今を問わず同一なるものである。」ここでは生民の痛みを自分の痛みと感じないものは,「是非の心」がなく良知に欠けるということになります。
陽明学における主客の統一
このように朱子学の理気二元論や性情分離論を克服した陽明学は,心即理の立場に立って,主観・客観の対立図式を超克します。そのことによって世界を自らの良知を表現するキャンパスにしたのです。このように朱子学における主観・客観認識図式と,陽明学におけるその超克の実例は,前近代においても認識図式をめぐる対立の問題が哲学の根本問題を成していたことを窺わせます。古代では儒墨対老荘ではやはりこの対立は鮮明でした。
1994年に亡くなった廣松渉は, 主・客認識図式がすぐれて近代的な認識図式であり,その超克が近代的な認識図式の超克だという議論を展開していました。そして主・客認識図式は世界が物によって構成されていると考える物的世界観に対応し,その超克の立場は第一義的な存在は事態あるいは事から成り, 物はその物象化的倒錯に陥った解釈にすぎないという事的世界観に対応すると強調していました。しかし古代からそういう対立軸が見られるとしたら, 主・客認識図式の超克や事的世界観の立場は必ずしも近代を超克する立場とは言えないことになるかもしれませんね。
日本の陽明学派
中江藤樹(1608〜1648) は,近江の小川村の生まれでしたが,9歳の時に米子藩の祖父の養子となり,藩主の転封で伊予の大洲(おおず)へ移り,15歳で祖父を失い郡奉行を継ぎました。ところが18歳で故郷の父をなくしてからは, 母への思いが募り27歳で郡奉行をやめて脱藩して故郷に帰ったのです。つまり彼は君主への忠より, 母への孝をとったのです。
33歳の著書『翁問答』では, 「孝」の徳を道徳の根源として説きました。そして生みの親に対する孝に止まらず, 人間の生みの親である天(皇上帝) に対する孝にまで拡げられました。そして社会制度としての身分秩序は認めながらも,「万民は皆ことごとく天地の子なれば、われも人も人間の形ある程のものは、みな兄弟なり。」と万人平等を主張したのです。
そして「孝」の実践の要領を次のように説明します。「孝徳の感通をてぢかくなづけいへば,愛敬の二字にきはまれり。愛はねんごろに親しむ意なり,敬は上をうやまひ,下をかろしめあなどらざる義なり。」この孝の実践こそ陽明の説く「致良知」に他ならないと考え,陽明学に傾倒して,「日本陽明学の祖」と呼ばれたのです。
徳の主体的なはたらきについて藤樹の「権」の思想が注目されます。「権」は「時と所と位」に応じて,その都度適切な道徳判断を行う主体的な心のはたらきです。道徳的判断の主体として責任有る決定が問われたところに,彼の君主をとるか親をとるかの決断の体験が投影していると思われます。
藤樹の弟子熊沢蕃山(1619〜1691) は, 岡山藩の番頭となり, 王道政治を実現しようと努力しました。彼は同士を集めて相互に錬磨しあう花畠教場を主宰します。「花園盟約」で武士の職分は人民の守護育成にありと人民本位の政治を掲げ,致良知に基づく慈愛と勇強の文武の徳性の涵養が学問の目的だとしました。この動きをキリシタンに関係ありと幕府に疑われて, 岡山藩を離れざるを得なくなったのです。
蕃山も時・処・位に応じて変通する態度を強調しました。キリスト教では, 「神への愛と隣人への愛」のように何時でも, 何処でも, 誰に対しても妥当する普遍妥当的原理を重視しますが, 儒教では, たとえ惻隠の心に基づく同じ行為でも時・処・位を弁えていなければ道徳的に評価されないのです。
大塩中斎(平八郎)(1792〜1837) は大坂町奉行所の与力でしたが, 38歳で辞職して家塾洗心洞を開いて子弟の教育にあたりました。当時打ち続く飢饉で農民・都市貧民が飢えているのに, 奉行所や豪商たちは腐敗堕落していました。彼は陽明学で知行合一を教えているのに, これを傍観することができません。ついに「大塩平八郎の乱」を起こしたのです。
彼は「心を太虚に帰す」ことを力説しました。これは人欲を去って精神の純粋性を実現するという意味です。原点に帰ってゼロから出直すという意味に取れば,そのラジカルな意義が分かります。現実の社会体制はたとえ正しい大義名分から出発したとしても,様々な私利私欲や権益によって歪められており,簡単に改革することはできません。かといって現実に民が飢え苦しんでいるのですから,これを救えないなら,いったんゼロに戻して民を救える体制に作り直すしかないのです。
これにヒントを得たわけではありませんが,最近「リエンジニアリング」という方法が抜本的業務改革法として打ち出されています。創業の原点に帰り,業務の目的に最も有効な組織にゼロから組織し直そうという方法です。これを本格的にやられますと,企業の収益は飛躍的に改善される場合もありますが,長年忠勤に励んできた中堅社員まで無用の長物としてばっさり切り捨てられる事がありますから御用心。
|
|
|
|
コメント(6)
失礼しました 五溺です(汗
はじめは任侠の習に溺れ、二たびは騎射の習に溺れ、三たびめは辞章の習に溺れ、四たび目は神仙の習に溺れ、五たび目は仏氏の習に溺れ、正徳丙寅、初めて正しく聖賢の学に帰す(伝習録)
試験学問に堕落していた朱子学に満足できなかった陽明先生が、
若い時に、任侠道、武芸、兵法、詩文、仏教、道教に遊び学んだことを、溺れたと表現したことです。
たとえば、円萼頂経などの禅宗教典などを読むと、致良知などの解釈も当然密度を増してくる。そんな感じです^^
陽明先生が、どうしてこういう思想に至ったか。
それを学ぶことで、更なる工夫が行われると信じます。
また、話は変わりますが『抜本塞源論』などは、取り入れるべき根本的な思考の一つだと思います。
はじめは任侠の習に溺れ、二たびは騎射の習に溺れ、三たびめは辞章の習に溺れ、四たび目は神仙の習に溺れ、五たび目は仏氏の習に溺れ、正徳丙寅、初めて正しく聖賢の学に帰す(伝習録)
試験学問に堕落していた朱子学に満足できなかった陽明先生が、
若い時に、任侠道、武芸、兵法、詩文、仏教、道教に遊び学んだことを、溺れたと表現したことです。
たとえば、円萼頂経などの禅宗教典などを読むと、致良知などの解釈も当然密度を増してくる。そんな感じです^^
陽明先生が、どうしてこういう思想に至ったか。
それを学ぶことで、更なる工夫が行われると信じます。
また、話は変わりますが『抜本塞源論』などは、取り入れるべき根本的な思考の一つだと思います。
つけ加うるに、王陽明は中華の歴史上に於いて、政治家であり、軍略家であり、書家として名を残しますが、思想家としての名は、日本・台湾以外では殆ど残されてはおりません。
さて、ここで大きなポイントと感じるのは、『大日本史』の編纂を決めた、義公水戸光圀であります。
その思想的バックボーンである『朱舜水』が、朱子学と並び、本格的『陽明学』を日本に渡来させたと言うことです。
多くは水戸学と一括りにして『大日本史』の価値観を平行して見ておりますが、かの書物が与えた影響は多大の一言では済まないと思われます。
武士道の形成にすら大きな影響を与えた『大日本史』及び、『水戸学』。その背景となる『陽明学』。
そして、神君家康公の意向(自らが神となって皇室と張り合う)を無視して作り上げた国学の基本。
さて、如何お考えになりますか?
さて、ここで大きなポイントと感じるのは、『大日本史』の編纂を決めた、義公水戸光圀であります。
その思想的バックボーンである『朱舜水』が、朱子学と並び、本格的『陽明学』を日本に渡来させたと言うことです。
多くは水戸学と一括りにして『大日本史』の価値観を平行して見ておりますが、かの書物が与えた影響は多大の一言では済まないと思われます。
武士道の形成にすら大きな影響を与えた『大日本史』及び、『水戸学』。その背景となる『陽明学』。
そして、神君家康公の意向(自らが神となって皇室と張り合う)を無視して作り上げた国学の基本。
さて、如何お考えになりますか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
陽明学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-