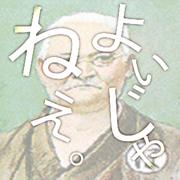方言では無いのですが、「おさきぎつね」の伝説ってご存知ですか?
玉村町でも南玉地区にいたといわれています。
「おさき」というきつねが住むと、夜にこっそり他の家の小麦粉を尻尾につけてきてもって帰るので、自分の家の粉がなくならないという言い伝えです。
冷静に考えれば泥棒ですが、恩返しするというか、その家を守るというか・・・
盗んでくるものも小麦粉というのが、二毛作、おっきりこみ好きの群馬県南部というか、ローカルです。
古い家では、必ず屋敷林に囲まれた家の西の奥にお稲荷様がまつってあり、白いキツネが対で飾られていました。お祭りや、年末、年始の夕方薄暗い時に、そこにお供えを置いてくるのが長男というか跡取の仕事とされ、小さい時から行かされました。
薄暗い中で、キツネだけがぼうっと浮き出るのが不気味で、急いでお供えをすると玄関まで走ってくるのが常でした。
稲荷信仰と結びついた素朴な伝説です。
玉村町でも南玉地区にいたといわれています。
「おさき」というきつねが住むと、夜にこっそり他の家の小麦粉を尻尾につけてきてもって帰るので、自分の家の粉がなくならないという言い伝えです。
冷静に考えれば泥棒ですが、恩返しするというか、その家を守るというか・・・
盗んでくるものも小麦粉というのが、二毛作、おっきりこみ好きの群馬県南部というか、ローカルです。
古い家では、必ず屋敷林に囲まれた家の西の奥にお稲荷様がまつってあり、白いキツネが対で飾られていました。お祭りや、年末、年始の夕方薄暗い時に、そこにお供えを置いてくるのが長男というか跡取の仕事とされ、小さい時から行かされました。
薄暗い中で、キツネだけがぼうっと浮き出るのが不気味で、急いでお供えをすると玄関まで走ってくるのが常でした。
稲荷信仰と結びついた素朴な伝説です。
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬弁辞典 更新情報
-
最新のトピック
群馬弁辞典のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6480人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19255人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人