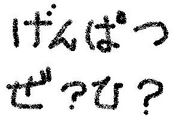|
|
|
|
コメント(175)
いろいろと考えをまとめてみたのですが、
まず私として放射線の測定について、いろいろと細かい基礎的なことを知りたい理由ですが、
世の中で放射線がどれぐらい危ないか、という場合に登場する単位にシーベルト(Sv)というものがありますが、これがなんだか今ひとつ分からん、という方は私も含めて結構多いと思うのです。
実際、
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
の場合も、GM管で数だけ数えているはずなのに測定結果はなぜかSvで出てきますから、それなんなの???となってしまうのではないかと。
なので、それぞれの測定方法の原理から始まりそれが測っている値がなんなのを把握していくことで、放射線って何なのから始まりSvって何なの、までたどり着けるのではないかと考えていました。
もちろん、その辺については
http://www.remnet.jp/
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/pdf_series_index.html
あたりを読めば分かる、みたいな話にしてしまえば終わりではあるのですが、
それだとハード過ぎると思いましたので、私なりに何かできないかなと思っているところではあります。
とりあえず、何とかする方法についてはもうちょっと考えてみます。
まず私として放射線の測定について、いろいろと細かい基礎的なことを知りたい理由ですが、
世の中で放射線がどれぐらい危ないか、という場合に登場する単位にシーベルト(Sv)というものがありますが、これがなんだか今ひとつ分からん、という方は私も含めて結構多いと思うのです。
実際、
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
の場合も、GM管で数だけ数えているはずなのに測定結果はなぜかSvで出てきますから、それなんなの???となってしまうのではないかと。
なので、それぞれの測定方法の原理から始まりそれが測っている値がなんなのを把握していくことで、放射線って何なのから始まりSvって何なの、までたどり着けるのではないかと考えていました。
もちろん、その辺については
http://www.remnet.jp/
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/pdf_series_index.html
あたりを読めば分かる、みたいな話にしてしまえば終わりではあるのですが、
それだとハード過ぎると思いましたので、私なりに何かできないかなと思っているところではあります。
とりあえず、何とかする方法についてはもうちょっと考えてみます。
>単に放射線の数と線量当量(線量ではない)に相関関係があるというだけです。この場合はガンマ線ですね・・・
だとするなら、GM管の測定値をSvまで持って行くことを考えた場合、それを途中の考証過程を飛ばして
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
のように「測った放射線の量は○○Svです」と示してしまうことは、かなり危険な感じがします。そもそも、Sv自体に医学的な見知その他が含まれているものだと思いますので。
で、私としてはその辺のところがきちんと整理できれば、安直な放射能害悪論みたいなものが少なくなるのかな、なんて考えていたりします。
だとするなら、GM管の測定値をSvまで持って行くことを考えた場合、それを途中の考証過程を飛ばして
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
のように「測った放射線の量は○○Svです」と示してしまうことは、かなり危険な感じがします。そもそも、Sv自体に医学的な見知その他が含まれているものだと思いますので。
で、私としてはその辺のところがきちんと整理できれば、安直な放射能害悪論みたいなものが少なくなるのかな、なんて考えていたりします。
で、しきり直しなんですけど、
>数字は、GM計数管を使用してのガンマ線による空間の線量等量率です。
ということは、GM計数管にも、とりあえず測定器自体の読み値としてμSv/hを出してくれるってことなんでしょうか。
とするなら、GM管の本来測定できる値であるCPSをμSV/hに換算するような機能がGM管測定器についてないとダメで、その換算方法を測定する側がよく調べておき(GM管自体の特性にあわせて揃えるとか、事前に線量等量がはっきりしている放射線源で値を測っておき、それを元に校正をかけるとか)、それにあわせた測定方法を採らないと、表示された空間線量率自体がなんだかよくわからないものになってしまいそうな気がします。
>数字は、GM計数管を使用してのガンマ線による空間の線量等量率です。
ということは、GM計数管にも、とりあえず測定器自体の読み値としてμSv/hを出してくれるってことなんでしょうか。
とするなら、GM管の本来測定できる値であるCPSをμSV/hに換算するような機能がGM管測定器についてないとダメで、その換算方法を測定する側がよく調べておき(GM管自体の特性にあわせて揃えるとか、事前に線量等量がはっきりしている放射線源で値を測っておき、それを元に校正をかけるとか)、それにあわせた測定方法を採らないと、表示された空間線量率自体がなんだかよくわからないものになってしまいそうな気がします。
>別におおよその値でいいんじゃないんですか?倍半分違うわけじゃなし・・・というか、普通、空間線量率の方ですから・・・
普通に市役所なんかで測るときはまさにおっしゃる通りだと思いますし、そうしたケースでは倍半分でも全然OKで、オーダー違いがでるぐらいで「ヤバイぞ、家の中に隠れろ!」とかそういう感じでいいのかと思います・・・
ただ、
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
の方のケースの場合、そもそもヤバイ放射線源があるという前提のもとに調査にでかけているわけですから、せいぜいで誤差が倍半分にならなくてはまずいわけで、その意味では私が指摘した点が問題だ!思うところに変わりはないのですが、
>測定方法がでたらめな方が気になります。
は決定的にダメなのかなと。
普通に市役所なんかで測るときはまさにおっしゃる通りだと思いますし、そうしたケースでは倍半分でも全然OKで、オーダー違いがでるぐらいで「ヤバイぞ、家の中に隠れろ!」とかそういう感じでいいのかと思います・・・
ただ、
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/050405fer.htm
の方のケースの場合、そもそもヤバイ放射線源があるという前提のもとに調査にでかけているわけですから、せいぜいで誤差が倍半分にならなくてはまずいわけで、その意味では私が指摘した点が問題だ!思うところに変わりはないのですが、
>測定方法がでたらめな方が気になります。
は決定的にダメなのかなと。
さきほど書いた155について、ちょっと書き直してアップします。
>なすさん
参考になるかはわからないのですが、以前は自動車、自分で持って乗ってました。乗るのをやめたのは、引っ越した場所が都心で駐車場がべらぼうに高い(月40000円以上)うえ公共交通が充実していたため、毎日のように車がないと困る状況ではなくなったからです。車が必要なときは、都心ですので近くの移動であればタクシーを利用すればそれでOKですし、長距離or長時間であっても近所でレンタカーを借りればそれで何とかやりくりできますので。
ちなみに、以前乗っていたのがこのスレで触れたシビック(EG6)でして、そのころはCO2排出など全然気にせず日光や筑波の峠をガンガンぶっ飛ばしてました・・・
>なすさん
参考になるかはわからないのですが、以前は自動車、自分で持って乗ってました。乗るのをやめたのは、引っ越した場所が都心で駐車場がべらぼうに高い(月40000円以上)うえ公共交通が充実していたため、毎日のように車がないと困る状況ではなくなったからです。車が必要なときは、都心ですので近くの移動であればタクシーを利用すればそれでOKですし、長距離or長時間であっても近所でレンタカーを借りればそれで何とかやりくりできますので。
ちなみに、以前乗っていたのがこのスレで触れたシビック(EG6)でして、そのころはCO2排出など全然気にせず日光や筑波の峠をガンガンぶっ飛ばしてました・・・
>ですから、測定自体にこの測定器を用いることに問題はありません。
>物からの距離が書いてないから、再現できる数字ではないということです。
なるほど、私の書いたダメは言い過ぎでしたね。
で、いろいろ書いてからで申し訳ないのですが、私が目指していたところは以前書いた通りなのですが、そこまでの疑問として私が持っているものを整理してみると
・放射線といってもいろいろな種類がある(アルファ線、ベータ線、ガンマ線etc.)
・同じ放射線の種類でも、それぞれの崩壊エネルギーは全然違う(ベータ線にしてもガンマ線にしても、放射性物質の崩壊方法によっては100倍とか違うし、ガンマ線の場合崩壊するときに違うエネルギーのものが同時に出てくる)
・それを「数」で測るのか「仕事やエネルギー」として測るのかで、放射線の量としての意味は変わるのではないか? 変わるとして、それぞれの量を「線量」という指標に落とし込むにあたって、どう関連づけているのか?
・さらに、線量まで落とし込んだとしても、測った値で出る「線量」と人体への影響度を測る「被ばく線量」との間にはまだ違いがあるらしい。その辺については、どのように決められているのか?
といった感じで、これを全部質問しながら皆さんに答えていただくというのは、皆さんにはかなり無理をかけること確実です。
また、ネットだけで知識を得ようとするとどうにも食い散らかしみたいになってしまいそうなので、とりあえず2〜3冊ぐらいは放射線に関する書籍をきちんと読んでみようと思います。
そこで、一応
・大学2年生レベルの物理・化学は分かる(実際私自身そこまでわからないのですが、そのレベルまでは別で努力しますので)
・数式はある程度出てきても大丈夫
・実務レベルで使えるかどうかについてはそれほど気にしない
・ただ、ネット上で発表されている「被ばく線量」等々の基準について、読みこなせるだけの知識はつけたい
・値段は3000円以下ぐらいがいいかなぁ・・・(それより高くてもいい本ならいいのですが)
といった前提として、おすすめな本ってありますでしょうか?
>物からの距離が書いてないから、再現できる数字ではないということです。
なるほど、私の書いたダメは言い過ぎでしたね。
で、いろいろ書いてからで申し訳ないのですが、私が目指していたところは以前書いた通りなのですが、そこまでの疑問として私が持っているものを整理してみると
・放射線といってもいろいろな種類がある(アルファ線、ベータ線、ガンマ線etc.)
・同じ放射線の種類でも、それぞれの崩壊エネルギーは全然違う(ベータ線にしてもガンマ線にしても、放射性物質の崩壊方法によっては100倍とか違うし、ガンマ線の場合崩壊するときに違うエネルギーのものが同時に出てくる)
・それを「数」で測るのか「仕事やエネルギー」として測るのかで、放射線の量としての意味は変わるのではないか? 変わるとして、それぞれの量を「線量」という指標に落とし込むにあたって、どう関連づけているのか?
・さらに、線量まで落とし込んだとしても、測った値で出る「線量」と人体への影響度を測る「被ばく線量」との間にはまだ違いがあるらしい。その辺については、どのように決められているのか?
といった感じで、これを全部質問しながら皆さんに答えていただくというのは、皆さんにはかなり無理をかけること確実です。
また、ネットだけで知識を得ようとするとどうにも食い散らかしみたいになってしまいそうなので、とりあえず2〜3冊ぐらいは放射線に関する書籍をきちんと読んでみようと思います。
そこで、一応
・大学2年生レベルの物理・化学は分かる(実際私自身そこまでわからないのですが、そのレベルまでは別で努力しますので)
・数式はある程度出てきても大丈夫
・実務レベルで使えるかどうかについてはそれほど気にしない
・ただ、ネット上で発表されている「被ばく線量」等々の基準について、読みこなせるだけの知識はつけたい
・値段は3000円以下ぐらいがいいかなぁ・・・(それより高くてもいい本ならいいのですが)
といった前提として、おすすめな本ってありますでしょうか?
>スピードメーターの表示は正しいんですか?
車検でスピードメーターは測定項目になっていて、メーター数値が実際より低く出るようだと車検通らないはずなので、車検を頼んだディーラーや測定した陸運支局の人を信じて、あってるものとして走ってます。
ただ、スピードメーターってドライブシャフトの回転数をはかり、それとタイヤの直径の関係で計っていたと思いますので、車検後にタイヤをインチアップしたりするとメーターの出が低くなる可能性はあると思います。
私の場合、自分で持って乗っていたときは純正とほぼ等しいサイズのタイヤを付けてましたので、数値が低めに出る可能性は低いかなと。レンタカーの場合も、やたらと変な改造して貸すことはないでしょうから、こちらも同様ではないかと。
車検でスピードメーターは測定項目になっていて、メーター数値が実際より低く出るようだと車検通らないはずなので、車検を頼んだディーラーや測定した陸運支局の人を信じて、あってるものとして走ってます。
ただ、スピードメーターってドライブシャフトの回転数をはかり、それとタイヤの直径の関係で計っていたと思いますので、車検後にタイヤをインチアップしたりするとメーターの出が低くなる可能性はあると思います。
私の場合、自分で持って乗っていたときは純正とほぼ等しいサイズのタイヤを付けてましたので、数値が低めに出る可能性は低いかなと。レンタカーの場合も、やたらと変な改造して貸すことはないでしょうから、こちらも同様ではないかと。
>なすさん
車検時のスピードメーター検査については、テレビで車検を取り上げた番組でみたのと、ユーザー車検に関する本を読んで知っている程度ですが、
車検場のスピードメーター検査のところでは、スピード測定用ローラーに自動車の駆動輪を載せ、駆動輪を回します。駆動輪が回ると自動車のスピードメーターは走っているときと同じように動き、ローラーは駆動輪の回転によってこちらも回転しますので、ローラー側でもスピードを測定すると。この2つを比較して
、スピードメーターの動作をチェックします。
実際には、自動車を操作する人は測定器につながれたボタンを持っていて、スピードメーターを見ながら40km/hまでスピードを出してボタンを押します(測定器によってはボタンではなくパッシングを利用する)。そのとき、ローラー側で測ったスピードが40km/h以下の一定範囲に収まっていれば合格、という仕組みになっていたと思います。
とここまで書いてネットを検索してみたところ、
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns06.htm#
を見る限り私の書いたものでOKそうですが、
なかには
http://www.ad-vantage.co.jp/924/car/car57.html
http://www.janis.or.jp/users/izawa/w202/2005/syaken.htm
みたいな一部車種では車検場側で対応できない、という理由でスピードメーターチェックをやっていなかったりもするみたいです・・・
車検時のスピードメーター検査については、テレビで車検を取り上げた番組でみたのと、ユーザー車検に関する本を読んで知っている程度ですが、
車検場のスピードメーター検査のところでは、スピード測定用ローラーに自動車の駆動輪を載せ、駆動輪を回します。駆動輪が回ると自動車のスピードメーターは走っているときと同じように動き、ローラーは駆動輪の回転によってこちらも回転しますので、ローラー側でもスピードを測定すると。この2つを比較して
、スピードメーターの動作をチェックします。
実際には、自動車を操作する人は測定器につながれたボタンを持っていて、スピードメーターを見ながら40km/hまでスピードを出してボタンを押します(測定器によってはボタンではなくパッシングを利用する)。そのとき、ローラー側で測ったスピードが40km/h以下の一定範囲に収まっていれば合格、という仕組みになっていたと思います。
とここまで書いてネットを検索してみたところ、
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns06.htm#
を見る限り私の書いたものでOKそうですが、
なかには
http://www.ad-vantage.co.jp/924/car/car57.html
http://www.janis.or.jp/users/izawa/w202/2005/syaken.htm
みたいな一部車種では車検場側で対応できない、という理由でスピードメーターチェックをやっていなかったりもするみたいです・・・
>車のスピードメーターが正しいことを検査する装置は正しく機能するんですか?
これについては、私も全然よく分からなかった(そこまで余り疑っていなかった)ので、とりあえず調べてみたのですが。
まず、私が先に書いたものは陸運支局で車検を受けるときのもので、よくよく考えたら「民間車検場」でも車検を受けられます。で、民間車検場の検査については国が出している民間車検場に関する規則として「指定自動車整備事業規則」というのがあり、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03901000049.html
そのなかで、
第十二条 指定自動車整備事業者は、第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。
2 指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
となってますから、1年に一度はきちんと検査を受けた測定器でスピードメーター
についても検査をしていることになりますので、インチキさえしてなければ問題ないのかなと。
で、陸運支局で行っている検査についても調べてみたのですが、こちらについては現在は国が認定した独立法人が検査を代行しているのですが、なぜかその測定に関する資料らしきものが見あたらず、よくわかりませんでした。
たぶん、どこかで資料を見ればわかるのだとは思うのですが。
これについては、私も全然よく分からなかった(そこまで余り疑っていなかった)ので、とりあえず調べてみたのですが。
まず、私が先に書いたものは陸運支局で車検を受けるときのもので、よくよく考えたら「民間車検場」でも車検を受けられます。で、民間車検場の検査については国が出している民間車検場に関する規則として「指定自動車整備事業規則」というのがあり、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03901000049.html
そのなかで、
第十二条 指定自動車整備事業者は、第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。
2 指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
となってますから、1年に一度はきちんと検査を受けた測定器でスピードメーター
についても検査をしていることになりますので、インチキさえしてなければ問題ないのかなと。
で、陸運支局で行っている検査についても調べてみたのですが、こちらについては現在は国が認定した独立法人が検査を代行しているのですが、なぜかその測定に関する資料らしきものが見あたらず、よくわかりませんでした。
たぶん、どこかで資料を見ればわかるのだとは思うのですが。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
是か?否か?原子力発電 更新情報
-
最新のアンケート
是か?否か?原子力発電のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人