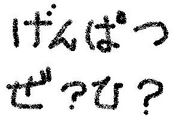|
|
|
|
コメント(36)
熱出力140MWの高速実験炉常陽は今年で臨界30周年です。日本にはこれだけの運転実績があるNa炉があるのだから「もんじゅ」のナトリウム系も大丈夫でしょう。
それより、一部が屋外に配設されているために11年間も雨風に晒されてきたタービン水蒸気系統の方が心配です。また、胴側のNaと管側の水との間で127気圧も圧力差のある蒸気発生器において、チューブリークによるNa−水反応は今後避けて通れないような気がします。
JAEAには、2次系のNaが少々配管から漏れたくらいでコソコソ隠すことなく堂々と発表し、Na−水の熱交換技術を早く確立して欲しいと思います。
もんじゅのタービン水蒸気系統は制御も難しいですし、11年という長期停止期間中に思わぬ劣化が進行していることも考えられますから、関電の美浜3号機の教訓を踏まえて現場の作業者の安全は十分に確保してほしいと思います。
高速炉開発が安全に且つ順調に進むことを願うばかりです。
それより、一部が屋外に配設されているために11年間も雨風に晒されてきたタービン水蒸気系統の方が心配です。また、胴側のNaと管側の水との間で127気圧も圧力差のある蒸気発生器において、チューブリークによるNa−水反応は今後避けて通れないような気がします。
JAEAには、2次系のNaが少々配管から漏れたくらいでコソコソ隠すことなく堂々と発表し、Na−水の熱交換技術を早く確立して欲しいと思います。
もんじゅのタービン水蒸気系統は制御も難しいですし、11年という長期停止期間中に思わぬ劣化が進行していることも考えられますから、関電の美浜3号機の教訓を踏まえて現場の作業者の安全は十分に確保してほしいと思います。
高速炉開発が安全に且つ順調に進むことを願うばかりです。
もんじゅは原子炉停止中でもNaを配管等に取り付けた電気ヒータで200℃に暖めて循環させています。
理由の一つとして、炉心に燃料が入っている間は冷却系等を最低1ループ循環させることで崩壊熱除去運転をしなければならないと保安規定に定められているためです(もんじゅは11年前から炉心に燃料を装荷したままの状態です。崩壊熱は家庭用のドライヤーの熱程度しか出ていないと思われますが・・・)。
その他の理由として、炉心の釜に入っているNaはドレンできない構造になっています。炉心のNaをそのまま冷やして固めてしまう方法も考えられますが、再びNaを溶かしたくても炉容器が巨大なので周囲に取り付けたヒータではNaを溶解しきれませんし、燃料が入ったままNaを固化させると燃料集合体が破損します。ですから、1次系のうち最低でも1ループは回し続けて局部的に固化しないようにする必要があるというわけです。
炉心の燃料集合体を水の燃料プールに運んで保管するには付着しているNaを洗浄する必要がありますので、数百体の燃料集合体を再起動までの間一旦プールに移すのは得策でないというわけです。
もんじゅの長期停止により、Na炉は炉心が冷え切っているとヒータの電気代が高くついたり、送電回線の故障等による外部電源喪失に怯えたり、といろいろ厄介な問題が浮き彫りになった感がありますので、実証炉ではその辺も考慮したプラントを設計する必要があるように思えます。
理由の一つとして、炉心に燃料が入っている間は冷却系等を最低1ループ循環させることで崩壊熱除去運転をしなければならないと保安規定に定められているためです(もんじゅは11年前から炉心に燃料を装荷したままの状態です。崩壊熱は家庭用のドライヤーの熱程度しか出ていないと思われますが・・・)。
その他の理由として、炉心の釜に入っているNaはドレンできない構造になっています。炉心のNaをそのまま冷やして固めてしまう方法も考えられますが、再びNaを溶かしたくても炉容器が巨大なので周囲に取り付けたヒータではNaを溶解しきれませんし、燃料が入ったままNaを固化させると燃料集合体が破損します。ですから、1次系のうち最低でも1ループは回し続けて局部的に固化しないようにする必要があるというわけです。
炉心の燃料集合体を水の燃料プールに運んで保管するには付着しているNaを洗浄する必要がありますので、数百体の燃料集合体を再起動までの間一旦プールに移すのは得策でないというわけです。
もんじゅの長期停止により、Na炉は炉心が冷え切っているとヒータの電気代が高くついたり、送電回線の故障等による外部電源喪失に怯えたり、といろいろ厄介な問題が浮き彫りになった感がありますので、実証炉ではその辺も考慮したプラントを設計する必要があるように思えます。
勉強不足なので、あまり詳しくは言えませんが
・燃料がプルトニウム。(ウランより危険物なイメージ)
・冷却材がナトリウム。(水と接触すると爆発する?・コンクリートと接触するとコンクリート内の水分が蒸発して脆くなる。)
・ナトリウムが通るパイプの壁が薄い。
・ナトリウムと水が薄いパイプを隔てて、隣接している。
こんなイメージです。
通常に運転できてるときは何も危険なことは無いのでしょうけど、もし不測の事態が起こったときの事を考えると不安です。
高速増殖炉を動かした時のメリットには素晴らしいものがあると思います。
それだけに、この不安な気持ちが完全に拭い去れればと思っております。
・燃料がプルトニウム。(ウランより危険物なイメージ)
・冷却材がナトリウム。(水と接触すると爆発する?・コンクリートと接触するとコンクリート内の水分が蒸発して脆くなる。)
・ナトリウムが通るパイプの壁が薄い。
・ナトリウムと水が薄いパイプを隔てて、隣接している。
こんなイメージです。
通常に運転できてるときは何も危険なことは無いのでしょうけど、もし不測の事態が起こったときの事を考えると不安です。
高速増殖炉を動かした時のメリットには素晴らしいものがあると思います。
それだけに、この不安な気持ちが完全に拭い去れればと思っております。
>9: 魔法使いセンちゃん
もんじゅは元々全ループドレンを想定していなかったため、ダンプタンクもそれだけの容量が確保されておりません。燃料全引抜ができない炉心なので、全ループドレンして崩壊熱除去運転を停止するということが有り得ないからです。1・2次系のダンプタンクは2ループ分しかドレンできない容量になっています。
今回の2次系改造工事にあたり、2次主冷却系の3ループドレンが行われましたが、これは各ループごとに工事すると費用が高くつくため特別に仮設のドレンタンクを設置して行った工事です。長期停止により炉心の崩壊熱がほぼゼロであるため、特別に許可が下りたものと推定されます。
1次系は格納容器の中ですので、ドレンタンクを新たに設置するスペースも搬入通路もありません。
JAEAのもんじゅHPにアクセスすると、現在のプラント状態を示す配管系統図を見ることができます。これを見ると判りますが、炉容器の上側から釜の中に入っていく1次系の配管が、燃料の下部にNaを送り込んでいます。これは、1次系の配管が破断しても炉内のNaの液位が低下しないようにするためです。
もんじゅの炉容器は、誤って開いたり破断すると炉心のNa液位を低下させかねないようなドレン弁やドレン配管等の類を炉容器に一切設けないことにより、冷却材喪失事故を防いでいます。また、炉容器の周りにはガードベッセルが設けられており、万一炉容器が割れてもNaの液位が燃料よりも下まで低下しないように構成されています。なお、ご存知の通りNaは沸点880(?)℃ですからNaの気化は想定していません。
もんじゅは元々全ループドレンを想定していなかったため、ダンプタンクもそれだけの容量が確保されておりません。燃料全引抜ができない炉心なので、全ループドレンして崩壊熱除去運転を停止するということが有り得ないからです。1・2次系のダンプタンクは2ループ分しかドレンできない容量になっています。
今回の2次系改造工事にあたり、2次主冷却系の3ループドレンが行われましたが、これは各ループごとに工事すると費用が高くつくため特別に仮設のドレンタンクを設置して行った工事です。長期停止により炉心の崩壊熱がほぼゼロであるため、特別に許可が下りたものと推定されます。
1次系は格納容器の中ですので、ドレンタンクを新たに設置するスペースも搬入通路もありません。
JAEAのもんじゅHPにアクセスすると、現在のプラント状態を示す配管系統図を見ることができます。これを見ると判りますが、炉容器の上側から釜の中に入っていく1次系の配管が、燃料の下部にNaを送り込んでいます。これは、1次系の配管が破断しても炉内のNaの液位が低下しないようにするためです。
もんじゅの炉容器は、誤って開いたり破断すると炉心のNa液位を低下させかねないようなドレン弁やドレン配管等の類を炉容器に一切設けないことにより、冷却材喪失事故を防いでいます。また、炉容器の周りにはガードベッセルが設けられており、万一炉容器が割れてもNaの液位が燃料よりも下まで低下しないように構成されています。なお、ご存知の通りNaは沸点880(?)℃ですからNaの気化は想定していません。
>1と2は、ウランでも一緒ですよね?程度の差はありますが・・・
一緒とはいえないと思います。現在、燃料として使われているウランを体内摂取しても内部被曝による発ガンの危険性はないでしょう。また、ウランを用いて核兵器を製造するためには、濃縮という大変難しい技術が必要ですが、プルトニウムはそのままで使えてしまいます。
>これの出典を教えて頂けますか?自分の目で確かめてきます
平成13年版原子力安全白書「第1編プルトニウムに関する安全確保について・第2章原子炉におけるプルトニウムに関する安全確保・第2節高速増殖炉」です。
http://www.nsc.go.jp/hakusyo/hakusyo13/122.htm
一緒とはいえないと思います。現在、燃料として使われているウランを体内摂取しても内部被曝による発ガンの危険性はないでしょう。また、ウランを用いて核兵器を製造するためには、濃縮という大変難しい技術が必要ですが、プルトニウムはそのままで使えてしまいます。
>これの出典を教えて頂けますか?自分の目で確かめてきます
平成13年版原子力安全白書「第1編プルトニウムに関する安全確保について・第2章原子炉におけるプルトニウムに関する安全確保・第2節高速増殖炉」です。
http://www.nsc.go.jp/hakusyo/hakusyo13/122.htm
>20: CASK23 さん
ありがとうございます
「ナトリウムボイド係数」を含めた全体の反応度係数はいかがでしょうか?
>ウランを用いて核兵器を製造するためには、濃縮という大変難しい技術が必要ですが、プルトニウムはそのままで使えてしまいます。
これについては・・・
濃縮なんてそう難しいものじゃないし、大がかりな施設がいりますけど、敵が国家レベルだったらアウトです
プルトニウムも国内では1:1MOXですから、原爆には使えません
それと、やっぱり大がかりな施設でないと作業者が死んでしまいますから・・・命知らずな集団か国家レベル出ないと無理でしょう
前回のレスで「程度の差はありますが・・・」と、書いたんですが・・・
ご理解頂けなかったようで・・・
ありがとうございます
「ナトリウムボイド係数」を含めた全体の反応度係数はいかがでしょうか?
>ウランを用いて核兵器を製造するためには、濃縮という大変難しい技術が必要ですが、プルトニウムはそのままで使えてしまいます。
これについては・・・
濃縮なんてそう難しいものじゃないし、大がかりな施設がいりますけど、敵が国家レベルだったらアウトです
プルトニウムも国内では1:1MOXですから、原爆には使えません
それと、やっぱり大がかりな施設でないと作業者が死んでしまいますから・・・命知らずな集団か国家レベル出ないと無理でしょう
前回のレスで「程度の差はありますが・・・」と、書いたんですが・・・
ご理解頂けなかったようで・・・
>「ナトリウムボイド係数」を含めた全体の反応度係数はいかがでしょうか?
出力係数のことをおっしゃっているのですね。定量的には確認していませんが、安全審査でも仮想的な炉心崩壊事故(いわゆる5項事象)を想定した評価を行っているので、ドップラー効果を加味しても正となっていると考えられます。
プルトニウムの核兵器転用については、ウランに比して危険性が高いことは国際社会の共通認識であり、そのためにアメリカでもGNEPといった枠組みが考えられています。
>前回のレスで「程度の差はありますが・・・」と、書いたんですが・・・
>ご理解頂けなかったようで・・・
そうお書きになっていたのは分かっていましたが、「ウランでも一緒ですよね?程度の差はありますが・・・」と書かれたご意見からは「たいした差ではない」という認識が汲み取れたので、そのことに違和感を持ちました。差異をきちんと理解したうえで「正しく恐れる」、そして適切な対策を立てることこそが専門家に求められています。
出力係数のことをおっしゃっているのですね。定量的には確認していませんが、安全審査でも仮想的な炉心崩壊事故(いわゆる5項事象)を想定した評価を行っているので、ドップラー効果を加味しても正となっていると考えられます。
プルトニウムの核兵器転用については、ウランに比して危険性が高いことは国際社会の共通認識であり、そのためにアメリカでもGNEPといった枠組みが考えられています。
>前回のレスで「程度の差はありますが・・・」と、書いたんですが・・・
>ご理解頂けなかったようで・・・
そうお書きになっていたのは分かっていましたが、「ウランでも一緒ですよね?程度の差はありますが・・・」と書かれたご意見からは「たいした差ではない」という認識が汲み取れたので、そのことに違和感を持ちました。差異をきちんと理解したうえで「正しく恐れる」、そして適切な対策を立てることこそが専門家に求められています。
国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)構想について、資源エネルギー庁の『エネルギー基本計画』には、以下のように書かれています。
1:1MOXで取り出す日本の再処理は、この構想に当てはまってると言うことですよね?
査察もちゃんと受けているのですから、日本のプルトニウムが「核兵器の材料となる」ことは、それほど心配しなくてもよろしいのでは?
「原子力の平和利用について「核燃料サイクル国」と「核燃料サイクルを持たない原子力発電国」という新たなフレームワークを提示。米国は、本構想の下で、放射性廃棄物を減量し、プルトニウムを単体で分離しない核拡散抵抗性に優れた先進的再処理技術開発を促進するとともに、こうして取り出されたプルトニウム等を燃やすための高速炉開発を進める方針。」
1:1MOXで取り出す日本の再処理は、この構想に当てはまってると言うことですよね?
査察もちゃんと受けているのですから、日本のプルトニウムが「核兵器の材料となる」ことは、それほど心配しなくてもよろしいのでは?
「原子力の平和利用について「核燃料サイクル国」と「核燃料サイクルを持たない原子力発電国」という新たなフレームワークを提示。米国は、本構想の下で、放射性廃棄物を減量し、プルトニウムを単体で分離しない核拡散抵抗性に優れた先進的再処理技術開発を促進するとともに、こうして取り出されたプルトニウム等を燃やすための高速炉開発を進める方針。」
一般に、国際社会で語られるプルトニウムの核兵器転用の容易さは、プルトニウムと言う物質そのものの性質、あるいは、ウランの中からプルトニウムを取り出すことの容易さを表していると考えます。
上記の視点でプルトニウムを見れば、CASK23さんの主張は正しいと思います。
一方で、もんじゅ燃料としてのプルトニウムは、核不拡散抵抗性が優れた状態となるような工夫がなされています。特に、抽出に際して、かなりの放射線遮蔽が必要であることなどを考えれば、兵器用ウランを抽出するのに匹敵するとまでは言いませんが、兵器用プルトニウムの抽出はかなりの困難があります。
その点では、魔法使いセンちゃんさんの主張も間違ってはいません。
要は、「プルトニウム」と言う用語に対して、プルトニウムという原子の性質を考えているのか、トピックの趣旨も含めてもんじゅ燃料としてとらえているのかの違いだけに思います。
自分の用語の定義に拘って、相手の見解を否定しても、有益な議論は生まれないと思うのですが、いかがでしょうか?
上記の視点でプルトニウムを見れば、CASK23さんの主張は正しいと思います。
一方で、もんじゅ燃料としてのプルトニウムは、核不拡散抵抗性が優れた状態となるような工夫がなされています。特に、抽出に際して、かなりの放射線遮蔽が必要であることなどを考えれば、兵器用ウランを抽出するのに匹敵するとまでは言いませんが、兵器用プルトニウムの抽出はかなりの困難があります。
その点では、魔法使いセンちゃんさんの主張も間違ってはいません。
要は、「プルトニウム」と言う用語に対して、プルトニウムという原子の性質を考えているのか、トピックの趣旨も含めてもんじゅ燃料としてとらえているのかの違いだけに思います。
自分の用語の定義に拘って、相手の見解を否定しても、有益な議論は生まれないと思うのですが、いかがでしょうか?
>魔法使いセンちゃんさん
>査察もちゃんと受けているのですから、日本のプルトニウムが「核兵器の材料となる」ことは、それほど心配しなくてもよろしいのでは?
おっしゃるとおりですね。私もそう思います。ただ、くどいようで恐縮ですが、プルトニウムの核拡散上の脅威を重大なことと受け止め、そのことに正しく対処した結果であると理解しています。
>なすさん
>自分の用語の定義に拘って、相手の見解を否定しても、有益な議論は生まれないと思うのですが、いかがでしょうか?
ご忠告痛み入ります。ただ、私はプルトニウムがウランに比して危険物であるという認識を専門家自身が持っているという視点は重要と考えます。そこを飛ばして「もんじゅ燃料は十分対策がされているから問題なし」といった主張は、専門家の傲慢とも言われかねません。一般の方々に分かっていただけるよう、結論を急ぐことなく丁寧に説明することはとても大事なことだと思っています。
>査察もちゃんと受けているのですから、日本のプルトニウムが「核兵器の材料となる」ことは、それほど心配しなくてもよろしいのでは?
おっしゃるとおりですね。私もそう思います。ただ、くどいようで恐縮ですが、プルトニウムの核拡散上の脅威を重大なことと受け止め、そのことに正しく対処した結果であると理解しています。
>なすさん
>自分の用語の定義に拘って、相手の見解を否定しても、有益な議論は生まれないと思うのですが、いかがでしょうか?
ご忠告痛み入ります。ただ、私はプルトニウムがウランに比して危険物であるという認識を専門家自身が持っているという視点は重要と考えます。そこを飛ばして「もんじゅ燃料は十分対策がされているから問題なし」といった主張は、専門家の傲慢とも言われかねません。一般の方々に分かっていただけるよう、結論を急ぐことなく丁寧に説明することはとても大事なことだと思っています。
>ご忠告痛み入ります。ただ、私はプルトニウムがウランに
>比して危険物であるという認識を専門家自身が
>持っているという視点は重要と考えます。
>そこを飛ばして「もんじゅ燃料は十分対策がされているから
>問題なし」といった主張は、専門家の傲慢とも言われかねません。
>一般の方々に分かっていただけるよう、結論を急ぐことなく
>丁寧に説明することはとても大事なことだと思っています。
ですから、「丁寧」と言うのは「俺が重視している視点が
抜けている。けしからん。」では、ないでしょう?
相手の主張の意図を読み解く際にも「丁寧」さは必要ですよ。
たとえば、「もんじゅの燃料中のプルトニウムは、
十分な対策が取られており、その点ではウラン相当と言う指摘は妥当です。
その一方で、プルトニウムという物質の材料のリスクも、
それはそれとして指摘することが重要でしょう。」と言う、
相手の意図をくみ取った指摘の仕方もあるわけです。
あなたは、材料のリスクについての指摘がないことにダメ出しをしていますが、
一方で、もんじゅのトピックにおいて、もんじゅ燃料としての
プルトニウムの性質について全く触れず、材料の危険性だけを指摘するのは、
それはそれで、非常に偏っていることも事実です。
丁寧な説明が必要とおっしゃるのであれば、
まず、ご自身が、トピック、議論の流れ、相手の主張を
丁寧に理解した上で、相手を否定するのではなく、
自分の主張との差異を述べるべきでしょう。
「傲慢」とか相手の専門性を否定するような発言をする必要がありますか?
私には、あなたの主張こそ、相手を見下し、
自分が全てを正しく知っているかのように感じ、
専門家固有の傲慢さを感じてしまいます。
私は、魔法使いセンちゃんさんとの面識はありませんが、
mixiにおけるこれまでの議論を通じて、
プルトニウムの危険性を軽んじているとは思えません。
また、「正しい危険さ」と言うのも議論があるところでしょう。
「程度の差はあるが」と言う表現が正しい場合もあるし、
「決定的に差がある」という表現が正しい場合もあります。
リスクコミュニケーションにおいては、相手の尊重が大切です。
もう少し、自分の視点ばかりを強調しないでほしいものです。
専門家が全員、同じ視点を持つ必要はありません。
>比して危険物であるという認識を専門家自身が
>持っているという視点は重要と考えます。
>そこを飛ばして「もんじゅ燃料は十分対策がされているから
>問題なし」といった主張は、専門家の傲慢とも言われかねません。
>一般の方々に分かっていただけるよう、結論を急ぐことなく
>丁寧に説明することはとても大事なことだと思っています。
ですから、「丁寧」と言うのは「俺が重視している視点が
抜けている。けしからん。」では、ないでしょう?
相手の主張の意図を読み解く際にも「丁寧」さは必要ですよ。
たとえば、「もんじゅの燃料中のプルトニウムは、
十分な対策が取られており、その点ではウラン相当と言う指摘は妥当です。
その一方で、プルトニウムという物質の材料のリスクも、
それはそれとして指摘することが重要でしょう。」と言う、
相手の意図をくみ取った指摘の仕方もあるわけです。
あなたは、材料のリスクについての指摘がないことにダメ出しをしていますが、
一方で、もんじゅのトピックにおいて、もんじゅ燃料としての
プルトニウムの性質について全く触れず、材料の危険性だけを指摘するのは、
それはそれで、非常に偏っていることも事実です。
丁寧な説明が必要とおっしゃるのであれば、
まず、ご自身が、トピック、議論の流れ、相手の主張を
丁寧に理解した上で、相手を否定するのではなく、
自分の主張との差異を述べるべきでしょう。
「傲慢」とか相手の専門性を否定するような発言をする必要がありますか?
私には、あなたの主張こそ、相手を見下し、
自分が全てを正しく知っているかのように感じ、
専門家固有の傲慢さを感じてしまいます。
私は、魔法使いセンちゃんさんとの面識はありませんが、
mixiにおけるこれまでの議論を通じて、
プルトニウムの危険性を軽んじているとは思えません。
また、「正しい危険さ」と言うのも議論があるところでしょう。
「程度の差はあるが」と言う表現が正しい場合もあるし、
「決定的に差がある」という表現が正しい場合もあります。
リスクコミュニケーションにおいては、相手の尊重が大切です。
もう少し、自分の視点ばかりを強調しないでほしいものです。
専門家が全員、同じ視点を持つ必要はありません。
ウランとプルトニウムが大差ないと言った点について・・・
線量告示の別表に年間の摂取限度が載っているんですけど、
吸入を例に挙げますね
そこには、不溶性の酸化物で・・・
ウラン238で、5.7E-3ベクレル
プルトニウム239で、8.3E-2ベクレル
となっています
これが、50ミリシーベルトを内部被ばくする量なんですね
同じ放射能量を吸入した場合、大差ないと言うことです
一般に、放射性物質は、ベクレル単位で考えますので・・・
で・・・プルトニウム239とウラン238とでは比放射能が100万桁(反対派の主張する100倍による)ぐらい違うので、同じ質量を吸入した場合は、ご指摘のとおりです
ウランも危険だと言うことをお忘れなく・・・
質量に対して、規制が100万倍甘いと言うことですから・・・
線量告示の別表に年間の摂取限度が載っているんですけど、
吸入を例に挙げますね
そこには、不溶性の酸化物で・・・
ウラン238で、5.7E-3ベクレル
プルトニウム239で、8.3E-2ベクレル
となっています
これが、50ミリシーベルトを内部被ばくする量なんですね
同じ放射能量を吸入した場合、大差ないと言うことです
一般に、放射性物質は、ベクレル単位で考えますので・・・
で・・・プルトニウム239とウラン238とでは比放射能が100万桁(反対派の主張する100倍による)ぐらい違うので、同じ質量を吸入した場合は、ご指摘のとおりです
ウランも危険だと言うことをお忘れなく・・・
質量に対して、規制が100万倍甘いと言うことですから・・・
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=551349&media_id=20
> 日本原子力研究開発機構の高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に18日早朝、交換用の核燃料が運び込まれた。
>
> 5月16日に続き2回目で、10月に予定される運転再開に必要な燃料はこれですべて運び終えた。
>
> もんじゅは1995年のナトリウム漏れ事故以来、運転停止中で、その間に燃料の一部が劣化。交換しなければ原子炉の再起動ができなくなっており、燃料集合体198体のうち78体を取り換える。
いよいよ、10月にも再開ですね。
日本の将来のために実用化を前倒しにする勢いでがんばってほしいです。
> 日本原子力研究開発機構の高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に18日早朝、交換用の核燃料が運び込まれた。
>
> 5月16日に続き2回目で、10月に予定される運転再開に必要な燃料はこれですべて運び終えた。
>
> もんじゅは1995年のナトリウム漏れ事故以来、運転停止中で、その間に燃料の一部が劣化。交換しなければ原子炉の再起動ができなくなっており、燃料集合体198体のうち78体を取り換える。
いよいよ、10月にも再開ですね。
日本の将来のために実用化を前倒しにする勢いでがんばってほしいです。
問題は核燃料サイクルが破綻して、プルトリウムが残存していることですね。
プルトリウムができる軽水炉ばかりなのは、欧(+ロ)米の核兵器利用の関係です。
原発を全部廃炉にすればこれ以上でないわけですが、そうは簡単にいかない。それにプルトリウムは半端でない。
ようは、安全にプルトリウムを処理、できれば燃料に使いながらできれば良いわけです。
軽水炉でなく、トリウム炉という道もあります。
正式にはトリウム溶融塩炉といいます。
核兵器転用には誠に不都合ですが、安全やプルトリウム処理には便利かも知れません。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E8%9E%8D%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
別途スレ作りたいが?
プルトリウムができる軽水炉ばかりなのは、欧(+ロ)米の核兵器利用の関係です。
原発を全部廃炉にすればこれ以上でないわけですが、そうは簡単にいかない。それにプルトリウムは半端でない。
ようは、安全にプルトリウムを処理、できれば燃料に使いながらできれば良いわけです。
軽水炉でなく、トリウム炉という道もあります。
正式にはトリウム溶融塩炉といいます。
核兵器転用には誠に不都合ですが、安全やプルトリウム処理には便利かも知れません。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E8%9E%8D%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
別途スレ作りたいが?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
是か?否か?原子力発電 更新情報
-
最新のアンケート
是か?否か?原子力発電のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人