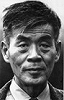先日、僕がmixi内で最もよく読んでいる橋川文三コミュで、管理人の方が、吉本隆明と糸井重里氏との3年ほど前の対談をリンクしていました。
その対談によれば、吉本は晩年まで、東京裁判のA級戦犯を悪く思っていなかったし、林房雄のように「大東亜戦争肯定論」こそ書かなかったけれど、同じようなことを考えていたことが、改めてわかりました。
こうしたことは、吉本自身、比較的初期の高村光太郎論などに書いていましたが、本当に死ぬまで変わらなかったのですね。この点では、自民党保守派とほとんど違いがないのですね。
戦後民主主義、リベラル派を代表する知識人である丸山真男や加藤周一について、吉本が糞みそに批判ているのもこの辺に原因があると思います。つまり、日本が文字通り総力戦を戦っているさなかに、「日本はどうせ負ける」「こんな日本は負けても仕方がない」と考えていたような奴らは許せない、という軍国少年的感受性、世界観が、三つ子の魂百まで、残っていたのだと思います。
こうした点を、松本健一は「吉本隆明の『暗黒』」と呼びましたが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
その対談によれば、吉本は晩年まで、東京裁判のA級戦犯を悪く思っていなかったし、林房雄のように「大東亜戦争肯定論」こそ書かなかったけれど、同じようなことを考えていたことが、改めてわかりました。
こうしたことは、吉本自身、比較的初期の高村光太郎論などに書いていましたが、本当に死ぬまで変わらなかったのですね。この点では、自民党保守派とほとんど違いがないのですね。
戦後民主主義、リベラル派を代表する知識人である丸山真男や加藤周一について、吉本が糞みそに批判ているのもこの辺に原因があると思います。つまり、日本が文字通り総力戦を戦っているさなかに、「日本はどうせ負ける」「こんな日本は負けても仕方がない」と考えていたような奴らは許せない、という軍国少年的感受性、世界観が、三つ子の魂百まで、残っていたのだと思います。
こうした点を、松本健一は「吉本隆明の『暗黒』」と呼びましたが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
|
|
|
|
コメント(17)
>>[1]
右翼テロリストの思想そのものだった、というような言葉は、吉本さん自身が高村光太郎論の中で言っていたのですね。それは、戦後民主主義社会・思想を経た時点での吉本さんなりの言い方でした。
戦時中はそれこそ軍国少年であることが当然だったわけですが、吉本さんより少し年上の橋川文三は、心酔した保田與重郎に対し20歳の誕生日、1942年の正月を機に距離をとり、さらに保田以上に過激で無内容な軍国主義イデオロギーに対してむしろ白けた感情を抱いていたという。
また、吉本や橋川と違って、従軍し特攻隊に入ったが、九死に一生を得て生き延びた上山春平は、「大東亜戦争の思想史的意義」などにおいて、戦時中の大東亜戦争史観だけでなく、ベトナムなどにかかわるアメリカの太平洋戦争史観、ソ連を中心とする共産主義運動のコミンテルン史観、中国による抗日戦争史観などの歴史観、戦争観がすべてだめであり、国家の揚棄以外に現在の矛盾は解決できないと言っていました。
この点では、吉本や橋川さんも同様だったかも知れません。
右翼テロリストの思想そのものだった、というような言葉は、吉本さん自身が高村光太郎論の中で言っていたのですね。それは、戦後民主主義社会・思想を経た時点での吉本さんなりの言い方でした。
戦時中はそれこそ軍国少年であることが当然だったわけですが、吉本さんより少し年上の橋川文三は、心酔した保田與重郎に対し20歳の誕生日、1942年の正月を機に距離をとり、さらに保田以上に過激で無内容な軍国主義イデオロギーに対してむしろ白けた感情を抱いていたという。
また、吉本や橋川と違って、従軍し特攻隊に入ったが、九死に一生を得て生き延びた上山春平は、「大東亜戦争の思想史的意義」などにおいて、戦時中の大東亜戦争史観だけでなく、ベトナムなどにかかわるアメリカの太平洋戦争史観、ソ連を中心とする共産主義運動のコミンテルン史観、中国による抗日戦争史観などの歴史観、戦争観がすべてだめであり、国家の揚棄以外に現在の矛盾は解決できないと言っていました。
この点では、吉本や橋川さんも同様だったかも知れません。
>>[002]、詳しいご案内をどうもありがとうございます。
多感な時期が皇国思想による太平洋戦争と敗北に重なった世代は、お一人お一人がほんと、自己の実存をかけてその体験を咀嚼(そしゃく)し評価なされたのだろうと思います。
だからそれこそその咀嚼と評価にはさまざまなタイプ、パターンがあったのだろうと思います。
それを見渡した時、今日のぼくたちが誰のどのような咀嚼とそこから紡がれた思想心情に共鳴できるかできないかも、
ぼくたち一人一人によるように思います。
実はぼく自身は、ごくごく教科書的な民主主義的価値観に立って来た者ですが、
吉本さんを読ませていただく中で、もう少し時代と心の相関性というものをくみ取れるように努めさせていただいている所です。
多感な時期が皇国思想による太平洋戦争と敗北に重なった世代は、お一人お一人がほんと、自己の実存をかけてその体験を咀嚼(そしゃく)し評価なされたのだろうと思います。
だからそれこそその咀嚼と評価にはさまざまなタイプ、パターンがあったのだろうと思います。
それを見渡した時、今日のぼくたちが誰のどのような咀嚼とそこから紡がれた思想心情に共鳴できるかできないかも、
ぼくたち一人一人によるように思います。
実はぼく自身は、ごくごく教科書的な民主主義的価値観に立って来た者ですが、
吉本さんを読ませていただく中で、もう少し時代と心の相関性というものをくみ取れるように努めさせていただいている所です。
松本健一が大川周明論の中で、戦時中に軍国=戦争イデオロギーである大東亜共栄圏思想のイデオローグに擬された大川の大アジア主義に吉本が共鳴、心酔していたことを、「吉本隆明のなかの暗黒」という一節の題にしているのを見て、僕は「『暗黒』とは、何を大げさな!」と思ったものでした。(松本氏は、「橋川文三は、保田與重郎の『言葉』によって殺された」というような、やはり大仰な言葉遣いをすることがあります)
しかし、吉本が晩年の80代も半ばになって、気の措けない糸井重里との対談(「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載)で、A級戦犯を擁護するような発言をしているのを見れば、林房雄のように表立って「大東亜戦争肯定論」的なものは書かなかったとはいえ、心の中では戦中派として少年時代から変わらない部分が続いていたのを垣間見る思いがしました。
松本氏の『大川周明』から該当個所を引いてみると、
<吉本隆明が戦後の思想家としてもっている特異性は、その思想の始源に戦前の暗黒が鎮められていることにある。もっと正確にいうと、戦前の思想的暗黒を自己のうちで否定しきることが吉本隆明の戦後の精神の初発のエネルギーとなっている。>
松本氏が言う通り、吉本の戦後の初発の精神はそうだったかもしれない。しかし、吉本は、少なくとも晩年には、「戦前の暗黒」をむしろ肯定していたと見える――糸井氏との対談を読むかぎりでは。
吉本や三島由紀夫などどんな多産な物書きにも、書かなかった「暗黒」があるのだろうと思う。
しかし、吉本が晩年の80代も半ばになって、気の措けない糸井重里との対談(「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載)で、A級戦犯を擁護するような発言をしているのを見れば、林房雄のように表立って「大東亜戦争肯定論」的なものは書かなかったとはいえ、心の中では戦中派として少年時代から変わらない部分が続いていたのを垣間見る思いがしました。
松本氏の『大川周明』から該当個所を引いてみると、
<吉本隆明が戦後の思想家としてもっている特異性は、その思想の始源に戦前の暗黒が鎮められていることにある。もっと正確にいうと、戦前の思想的暗黒を自己のうちで否定しきることが吉本隆明の戦後の精神の初発のエネルギーとなっている。>
松本氏が言う通り、吉本の戦後の初発の精神はそうだったかもしれない。しかし、吉本は、少なくとも晩年には、「戦前の暗黒」をむしろ肯定していたと見える――糸井氏との対談を読むかぎりでは。
吉本や三島由紀夫などどんな多産な物書きにも、書かなかった「暗黒」があるのだろうと思う。
>>[004]、大変詳しいご説明、どうもありがとうございます。
おっしゃるようにぼくたちは発表されたテキストに著者の思いは尽きていると考えがちですが、
確かにそこにいまだ書かれずにいた著者の、テキストからはみ出す思いというのも間違いなく存在するのでしょうね。
問題となっている吉本さんの件で言えば、GandhiGanjeeさんによる詳しい説明を読んだ今も、ぼくには吉本さんを嫌うことはできません。
非難することはできません。
青春時代に熱く思った内容について、公式には否定すべきだと回心しながらも、
やっぱり何だか心の底でずっとくすぶり続ける、ということは僕自身についてもよーくわかることだからです。
GandhiGanjeeさんは何だか裏切られたようで許せない、騙された、という感じなのでしょうか?
おっしゃるようにぼくたちは発表されたテキストに著者の思いは尽きていると考えがちですが、
確かにそこにいまだ書かれずにいた著者の、テキストからはみ出す思いというのも間違いなく存在するのでしょうね。
問題となっている吉本さんの件で言えば、GandhiGanjeeさんによる詳しい説明を読んだ今も、ぼくには吉本さんを嫌うことはできません。
非難することはできません。
青春時代に熱く思った内容について、公式には否定すべきだと回心しながらも、
やっぱり何だか心の底でずっとくすぶり続ける、ということは僕自身についてもよーくわかることだからです。
GandhiGanjeeさんは何だか裏切られたようで許せない、騙された、という感じなのでしょうか?
>>[5]
「裏切られたようで許せない、騙された、という感じ」とは違う何か、だとは思います。
吉本が思想家として世に出たのは、「転向論」など、獄中十何年かの後、戦後になって出獄した非転向の戦前の共産党幹部を神格化した、旧左翼への仮借ない批判によってだったと思います。彼らは同時代の大衆から遊離していたがゆえに、ちっとも偉くない、と。大衆の現実からかけ離れた政治思想は無意味であると考えたのだと思います。
そして、ここから先は吉本は書きませんでしたが、周知の事実として、大衆は、ほぼ100%が軍部の主導した大東亜戦争の必勝を願っていた。
吉本と同じようなこと(A級戦犯を批判しなかったこと)は、橋川文三も(まだ一部しか読んでいない上での推測ですが)、同様ではないかとも思います。
数年前に、NHKの番組で、終戦当時7歳だったという、戦中派より10歳余り年下のおじいさんが、「人生で最も悔しかったのは?」と聞かれて、「日本が戦争に負けたこと」と答えていました。そんな熟年世代の人はほかにもたくさんいるかもしれません。
ところで、都知事・猪瀬直樹が2009年に出した『ジミーの誕生日』によれば、A級戦犯7人が絞首刑に処された1948年12月23日は、当時の皇太子(現天皇)の誕生日に合わせて、彼と日本国民がこの日を忘れないように、意図的にこの日を選んで行われた。
当時、占領下にあった日本では最高権力者だったマッカーサーは、占領政策を最も少ない犠牲で進めるための最良の方策として、天皇制の温存を選び、それと引き換えに東条英機をはじめとするA級戦犯の処刑を急ごうとした、というのが猪瀬の終戦直後の日本観でした。日本国民は拝啓マッカーサー様と崇拝していても、法的な指揮命令系統上では、彼の上が米国国防長官であり、その上には合衆国大統領がいましたし、アメリカ以外の連合国も干渉する。そんな中で、一介の現場指揮官に過ぎないマッカーサーは、自分の信念である「天皇を救う代わりに、戦犯に犠牲になってもらう」方策を急いだのだと。
マッカーサーと意見の異なる連合国では、「天皇を処刑すべし」や「天皇は退位すべし」という意見が大きかった中で、そんなことになれば、日本全土にゲリラ戦が蔓延して、地上戦で20万人以上も亡くなった沖縄戦をはるかに上回る地獄絵になり、米兵が日本だけで100万人も戦死することも予想された。この最悪の事態を避ける方法が、天皇制の温存だと、事前に日本を研究させたマッカーサーは考えた。
話が脱線しましたが、本土決戦になっていれば、吉本はゲリラ戦士として戦っていたでしょう。
吉本より年下のマルクス主義哲学者・広松渉の本音も、実は「鬼畜米英」だったと、未亡人が話したそうです。
「裏切られたようで許せない、騙された、という感じ」とは違う何か、だとは思います。
吉本が思想家として世に出たのは、「転向論」など、獄中十何年かの後、戦後になって出獄した非転向の戦前の共産党幹部を神格化した、旧左翼への仮借ない批判によってだったと思います。彼らは同時代の大衆から遊離していたがゆえに、ちっとも偉くない、と。大衆の現実からかけ離れた政治思想は無意味であると考えたのだと思います。
そして、ここから先は吉本は書きませんでしたが、周知の事実として、大衆は、ほぼ100%が軍部の主導した大東亜戦争の必勝を願っていた。
吉本と同じようなこと(A級戦犯を批判しなかったこと)は、橋川文三も(まだ一部しか読んでいない上での推測ですが)、同様ではないかとも思います。
数年前に、NHKの番組で、終戦当時7歳だったという、戦中派より10歳余り年下のおじいさんが、「人生で最も悔しかったのは?」と聞かれて、「日本が戦争に負けたこと」と答えていました。そんな熟年世代の人はほかにもたくさんいるかもしれません。
ところで、都知事・猪瀬直樹が2009年に出した『ジミーの誕生日』によれば、A級戦犯7人が絞首刑に処された1948年12月23日は、当時の皇太子(現天皇)の誕生日に合わせて、彼と日本国民がこの日を忘れないように、意図的にこの日を選んで行われた。
当時、占領下にあった日本では最高権力者だったマッカーサーは、占領政策を最も少ない犠牲で進めるための最良の方策として、天皇制の温存を選び、それと引き換えに東条英機をはじめとするA級戦犯の処刑を急ごうとした、というのが猪瀬の終戦直後の日本観でした。日本国民は拝啓マッカーサー様と崇拝していても、法的な指揮命令系統上では、彼の上が米国国防長官であり、その上には合衆国大統領がいましたし、アメリカ以外の連合国も干渉する。そんな中で、一介の現場指揮官に過ぎないマッカーサーは、自分の信念である「天皇を救う代わりに、戦犯に犠牲になってもらう」方策を急いだのだと。
マッカーサーと意見の異なる連合国では、「天皇を処刑すべし」や「天皇は退位すべし」という意見が大きかった中で、そんなことになれば、日本全土にゲリラ戦が蔓延して、地上戦で20万人以上も亡くなった沖縄戦をはるかに上回る地獄絵になり、米兵が日本だけで100万人も戦死することも予想された。この最悪の事態を避ける方法が、天皇制の温存だと、事前に日本を研究させたマッカーサーは考えた。
話が脱線しましたが、本土決戦になっていれば、吉本はゲリラ戦士として戦っていたでしょう。
吉本より年下のマルクス主義哲学者・広松渉の本音も、実は「鬼畜米英」だったと、未亡人が話したそうです。
吉本隆明『第二の敗戦期 これからの日本をどう読むか』(春秋社、2012) を読んで、mixi日記に書いた内容から:
この本は、2008年に行われたインタビューを基に、吉本の死後に刊行された。この本で語られる吉本の考えについては、必ずしもすべて的を射ているとは思わないが、80歳を超えても現役思想家だった、と言えようか。
「第二の敗戦」でググッてみたら、古くは江藤淳が、東日本大震災後には田原総一朗が、つい最近は安倍首相の靖国参拝後に元外交官が、それぞれ別の文脈と意味で言っている。
吉本自身はどういう意味を込めているかと言えば、「知識人たちが中産階級の中以下の人たちとは関係ないことしか言わない」という現代の状況のことだという。これについて「平和な戦争において日本国が依然まだ独立していないな」と吉本は感じ、「敗戦直後と似ているな」という。
――この吉本の直感と理屈について、前半の「中の中以下云々」は当たっている気がするが、後半の敗戦直後云々はぴんと来ないのが正直なところだったが、他の個所と考え合わせるとわかる気がしてきた。
敗戦直後、獄中から釈放された共産党幹部やリベラル派の知識人は、この世の春とばかり戦後民主主義の論陣を張っていたが、国民の大多数は、政府や軍部と同様に、大東亜戦争の大義を信じ、敗戦によって深く傷ついていた。そのことに気づいていないか、気づいていても知らぬ顔をして議論していた知識人たちと、現代の知識人たちの現実に深くコミットしない姿勢とが、吉本にはオーバーラップして見えたのだろう。
この本は、2008年に行われたインタビューを基に、吉本の死後に刊行された。この本で語られる吉本の考えについては、必ずしもすべて的を射ているとは思わないが、80歳を超えても現役思想家だった、と言えようか。
「第二の敗戦」でググッてみたら、古くは江藤淳が、東日本大震災後には田原総一朗が、つい最近は安倍首相の靖国参拝後に元外交官が、それぞれ別の文脈と意味で言っている。
吉本自身はどういう意味を込めているかと言えば、「知識人たちが中産階級の中以下の人たちとは関係ないことしか言わない」という現代の状況のことだという。これについて「平和な戦争において日本国が依然まだ独立していないな」と吉本は感じ、「敗戦直後と似ているな」という。
――この吉本の直感と理屈について、前半の「中の中以下云々」は当たっている気がするが、後半の敗戦直後云々はぴんと来ないのが正直なところだったが、他の個所と考え合わせるとわかる気がしてきた。
敗戦直後、獄中から釈放された共産党幹部やリベラル派の知識人は、この世の春とばかり戦後民主主義の論陣を張っていたが、国民の大多数は、政府や軍部と同様に、大東亜戦争の大義を信じ、敗戦によって深く傷ついていた。そのことに気づいていないか、気づいていても知らぬ顔をして議論していた知識人たちと、現代の知識人たちの現実に深くコミットしない姿勢とが、吉本にはオーバーラップして見えたのだろう。
戦前でも、かなりの人たちが戦争には勝てないと知っていましたが、勝てると信じた右翼少年の心情を肯定し続けるのはなぜでしょう。ソクラテスではないですが、なぜ自分の心情を重んじ、無知に気が付くほうへはいかなかったのでしょうか。現代でも無知に気が付かないままでいたいという人が大勢います。その大勢の心情を汲むことと与することとは違うと思うのですが。なにかその区別が曖昧のようです。はっきり区別している文章があったら教えてください。上野の講演を中止させるのもこんな発言があったからではなかったでしょうか。中止させることには反対ですが、私は彼女の上からの語り方が嫌いです。
http://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201109010000/
http://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201109010000/
>>[15]
引かれたソクラテスの例では、吉本は、ソクラテスの死刑を支持した愚かな(?)民衆の一人だったのでしょう。日本のソクラテスが誰なのかは、ご教示ください。
吉本思想の源泉には、有名な「大衆の原像」をはじめとする大衆概念があり、それは最晩年まで続いた。思想は、同時代の深部としての大衆=中流以下の人々に届かねばならない、と。だから、80代になってのインタビュー『第二の敗戦期…』でも、柄谷行人などを名指しで、「知識人が中流の中以下の人たちのことを思想の課題にしていない」と批判していた。
柄谷はかつて、吉本の大衆の原像なんて「知識人の自意識(の裏返し)」に過ぎない、とクールに批判したこともあったが、吉本自身には、自分は名もない大衆の側に立っているという、理屈を超えた自信があったように見える。
吉本は、東京裁判史観、より一般的に言って戦勝国史観には組みしなかったが、「戦争そのものが絶対悪なのであって、どちらか一方が悪であるということはありえない」と考えていた。これは、戦争中の大東亜戦争史観からの、大きな戦争観・歴史観の転換だと思います。
吉本の理不尽な自信は、60年安保前後の共産党やリベラル派知識人批判において、彼らが戦争中の一般国民の戦争観を踏まえたり、汲み取ったりしないで、大衆から遊離した思想を構築していることに対し、自分自身が大東亜戦争の意義を信じた多数の国民の一人だった、そのことを決してなかったことにはしない、という点にあったかと思います。
引かれたソクラテスの例では、吉本は、ソクラテスの死刑を支持した愚かな(?)民衆の一人だったのでしょう。日本のソクラテスが誰なのかは、ご教示ください。
吉本思想の源泉には、有名な「大衆の原像」をはじめとする大衆概念があり、それは最晩年まで続いた。思想は、同時代の深部としての大衆=中流以下の人々に届かねばならない、と。だから、80代になってのインタビュー『第二の敗戦期…』でも、柄谷行人などを名指しで、「知識人が中流の中以下の人たちのことを思想の課題にしていない」と批判していた。
柄谷はかつて、吉本の大衆の原像なんて「知識人の自意識(の裏返し)」に過ぎない、とクールに批判したこともあったが、吉本自身には、自分は名もない大衆の側に立っているという、理屈を超えた自信があったように見える。
吉本は、東京裁判史観、より一般的に言って戦勝国史観には組みしなかったが、「戦争そのものが絶対悪なのであって、どちらか一方が悪であるということはありえない」と考えていた。これは、戦争中の大東亜戦争史観からの、大きな戦争観・歴史観の転換だと思います。
吉本の理不尽な自信は、60年安保前後の共産党やリベラル派知識人批判において、彼らが戦争中の一般国民の戦争観を踏まえたり、汲み取ったりしないで、大衆から遊離した思想を構築していることに対し、自分自身が大東亜戦争の意義を信じた多数の国民の一人だった、そのことを決してなかったことにはしない、という点にあったかと思います。
>>[16]
日本のソクラテス?しいて言うなら最近のギリシア哲学を謙虚に研究している人たちは、ソクラテスに近いかもしれません。しかし、あんな存在自体がアイロニィーのようなえたいのしれない人にはなれませんよ。それから死刑を支持しなかった人たちもかなりいたことは事実です。『ソクラテスの弁明』を読めばすぐにわかると思うのですが。日本の知識人の皆さんは何かを知っているという大衆の上に立ってお話をなされるからです。ソクラテスの基本は知らないことを知らないと認めるところです。知っていることもあるのは当然です。しかし、無知の知などを持っているなどとも言いません。納富氏がそのことはずいぶん前に解明していますが、いまだに、日本ではソクラテスは無知の知を持ったと言っていますからね。知識人を自認する限りソクラテスのように自分が無知な状態にいるなどとは思っていないでしょうね。
日本のソクラテス?しいて言うなら最近のギリシア哲学を謙虚に研究している人たちは、ソクラテスに近いかもしれません。しかし、あんな存在自体がアイロニィーのようなえたいのしれない人にはなれませんよ。それから死刑を支持しなかった人たちもかなりいたことは事実です。『ソクラテスの弁明』を読めばすぐにわかると思うのですが。日本の知識人の皆さんは何かを知っているという大衆の上に立ってお話をなされるからです。ソクラテスの基本は知らないことを知らないと認めるところです。知っていることもあるのは当然です。しかし、無知の知などを持っているなどとも言いません。納富氏がそのことはずいぶん前に解明していますが、いまだに、日本ではソクラテスは無知の知を持ったと言っていますからね。知識人を自認する限りソクラテスのように自分が無知な状態にいるなどとは思っていないでしょうね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
<吉本隆明・戦後最大の思想家> 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
<吉本隆明・戦後最大の思想家>のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6464人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19245人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208301人