先日新聞を読んでいると、魚の話が載ってあって、その文中魚名「カド」はアイヌ語で現在のニシンのことである、とありました。
聞いたことがあるので、記憶を辿ると、実家の岩手県南でも使っていた言葉です。
蝦夷とアイヌは同じ源流とも、金田一京助が言っていますが、
この「カド」という言葉を使っている地域はアイヌだ、とは言い切れませんが、
趣味的には言い切りたいデスw。
北海道から本州へのカド輸入で、言葉が一緒に広がったことも考えられると思います。
「カド」という言葉ご存知の方お願いいたします。
参考に
http://
聞いたことがあるので、記憶を辿ると、実家の岩手県南でも使っていた言葉です。
蝦夷とアイヌは同じ源流とも、金田一京助が言っていますが、
この「カド」という言葉を使っている地域はアイヌだ、とは言い切れませんが、
趣味的には言い切りたいデスw。
北海道から本州へのカド輸入で、言葉が一緒に広がったことも考えられると思います。
「カド」という言葉ご存知の方お願いいたします。
参考に
http://
|
|
|
|
コメント(13)
初めまして。
私、少しだけアイヌ文化の勉強をしていた者です。
ニシンをアイヌ語で「カド」ということに、違和感を感じたので、
我が家にあるアイヌ語辞典を引っ張り出して調べてみました。
北海道の道南・道央地域の方言を参考にしていると思われる辞書四点を照合してみましたところ、
heroki(ヘロキ)と称しているようです。
ちなみに、カズノコはhoma(ホマ)と言うそうです。
しかし、他の地域の方言まで、調べる術がなかったので、正直わかりません。
アイヌ語に関して言いますと、川上と川下だけでも方言が変わってしまいますので、私の書き込みは参考までにしておいて下さい。
参考文献:沙流方言アイヌ語辞典(日高沙流川流域)
萱野茂のアイヌ語辞典(沙流川流域ですが、魚名のみ長万部とのこと)
日本語・アイヌ語辞典(上川地域?)
私、少しだけアイヌ文化の勉強をしていた者です。
ニシンをアイヌ語で「カド」ということに、違和感を感じたので、
我が家にあるアイヌ語辞典を引っ張り出して調べてみました。
北海道の道南・道央地域の方言を参考にしていると思われる辞書四点を照合してみましたところ、
heroki(ヘロキ)と称しているようです。
ちなみに、カズノコはhoma(ホマ)と言うそうです。
しかし、他の地域の方言まで、調べる術がなかったので、正直わかりません。
アイヌ語に関して言いますと、川上と川下だけでも方言が変わってしまいますので、私の書き込みは参考までにしておいて下さい。
参考文献:沙流方言アイヌ語辞典(日高沙流川流域)
萱野茂のアイヌ語辞典(沙流川流域ですが、魚名のみ長万部とのこと)
日本語・アイヌ語辞典(上川地域?)
ブログやウェブサイトなどで、 「カド」または「ニシン」がアイヌ語語源だったりと述べられています。
上記のアイヌ語源の真偽は私もわかりませんが・・・・
日本語として定着している名前(地名も含む)の中で、アイヌ語源として紹介されているものの中に
安易な憶測や引用が多く、間違った語法・解説が跋扈しているのが現状です。
間違いが実に多いのです。
ですので、アイヌ語源を述べる場合には、少なくともそれが本当に正しいかどうか検証しつつ、
出典を明らかにするべきだと思います。
(※出典元自体が間違っている場合もあるので注意が必要)
多くのウェブサイトやブログで解説している人たちも 「カド」がアイヌ語語源、または「ニシン」が
アイヌ語語源というのが、何を根拠にそう述べているのかきちんと言及するなり、出典を示すなりして
いただきたいものです。
ほとんど皆無ですね。
ちなみにアイヌ語で「ニシン」とは、私は個人的に「ヘロキ(heroki)」ぐらいしか知りませんが・・・
また、「カド」がアイヌ語源というのは、ひょっとして「カト」が訛ったものという説 なんでしょうか。
アイヌ語って、通常子音は有声音(日本語で言う濁音)と無声音(日本語で言う清音)を区別しないの
ですが、大概は無声音で発音します。
参考) 萱野 茂 『 萱野茂のアイヌ語辞典』 三省堂 1996年
上記のアイヌ語源の真偽は私もわかりませんが・・・・
日本語として定着している名前(地名も含む)の中で、アイヌ語源として紹介されているものの中に
安易な憶測や引用が多く、間違った語法・解説が跋扈しているのが現状です。
間違いが実に多いのです。
ですので、アイヌ語源を述べる場合には、少なくともそれが本当に正しいかどうか検証しつつ、
出典を明らかにするべきだと思います。
(※出典元自体が間違っている場合もあるので注意が必要)
多くのウェブサイトやブログで解説している人たちも 「カド」がアイヌ語語源、または「ニシン」が
アイヌ語語源というのが、何を根拠にそう述べているのかきちんと言及するなり、出典を示すなりして
いただきたいものです。
ほとんど皆無ですね。
ちなみにアイヌ語で「ニシン」とは、私は個人的に「ヘロキ(heroki)」ぐらいしか知りませんが・・・
また、「カド」がアイヌ語源というのは、ひょっとして「カト」が訛ったものという説 なんでしょうか。
アイヌ語って、通常子音は有声音(日本語で言う濁音)と無声音(日本語で言う清音)を区別しないの
ですが、大概は無声音で発音します。
参考) 萱野 茂 『 萱野茂のアイヌ語辞典』 三省堂 1996年
再度、ニシン=カド、アイヌ語説につきまして、調べてみました。
「カド」は主に漁業・海産物販売のホームページに多く見受けられました。
そして、参考文献として、末弘恭雄著「魚の履歴書」(上下2巻:講談社)が挙げられていました。
その下巻97ページに「ニシンを北海道で『カド』(アイヌ語)と呼ぶ」と指摘されているようです。
どこまでの専門的な書なのか、不明ですが、今のところこの書しか見つかっていません。
先の3に挙げたアイヌ語辞典の他に専門書においては
「ヘロキ(heroki)」もしくは「ヘロホキ(heroxki)」しか見つかりませんでした。
参考文献を列挙します。
ヘロキ(heroki)・エロキ
満岡伸一『アイヌの足跡』第8版 1988 アイヌ民族博物館
→白老地方の大正〜昭和にかけて調べられたもの。
早川 昇『アイヌの民俗』 1977 岩崎美術社
→日本海側の道北にあたる中名寄の聴き取り調査によるもの。
難波琢雄・青木延広「沖の神(シャチ)とカムイギリ」『北海道の文化』72 2000 北海道文化財保護協会
→日本海側の余市に伝わるカムイギリという民具に付属しているニシンの木型がある。
更科源蔵『アイヌの民俗 上』更科源蔵アイヌ関係著作集? 1982 みやま書房
→(日本海沿岸)鰊はヘロキまたはエロキという。
八雲や洞爺湖近くに「鰊雪(ヘロキパウシ)」という地名がある。
山田秀三『北海道の地名』 1984 北海道新聞
→herok karushi ヘロクカルウシ 鰊を・捕る・いつもする処
同じ名前は日本海岸諸地にある(P120、484)
ヘロホキ(heroxki)
知里真志保「樺太アイヌの生活」『知里真志保著作集』3 1973 平凡社
→樺太の西海岸、白浜というところでこのように呼ばれている。
取りあえず手元にある文献からはニシンはアイヌ語でこのようにしか出てきませんでした。
「カド」は主に漁業・海産物販売のホームページに多く見受けられました。
そして、参考文献として、末弘恭雄著「魚の履歴書」(上下2巻:講談社)が挙げられていました。
その下巻97ページに「ニシンを北海道で『カド』(アイヌ語)と呼ぶ」と指摘されているようです。
どこまでの専門的な書なのか、不明ですが、今のところこの書しか見つかっていません。
先の3に挙げたアイヌ語辞典の他に専門書においては
「ヘロキ(heroki)」もしくは「ヘロホキ(heroxki)」しか見つかりませんでした。
参考文献を列挙します。
ヘロキ(heroki)・エロキ
満岡伸一『アイヌの足跡』第8版 1988 アイヌ民族博物館
→白老地方の大正〜昭和にかけて調べられたもの。
早川 昇『アイヌの民俗』 1977 岩崎美術社
→日本海側の道北にあたる中名寄の聴き取り調査によるもの。
難波琢雄・青木延広「沖の神(シャチ)とカムイギリ」『北海道の文化』72 2000 北海道文化財保護協会
→日本海側の余市に伝わるカムイギリという民具に付属しているニシンの木型がある。
更科源蔵『アイヌの民俗 上』更科源蔵アイヌ関係著作集? 1982 みやま書房
→(日本海沿岸)鰊はヘロキまたはエロキという。
八雲や洞爺湖近くに「鰊雪(ヘロキパウシ)」という地名がある。
山田秀三『北海道の地名』 1984 北海道新聞
→herok karushi ヘロクカルウシ 鰊を・捕る・いつもする処
同じ名前は日本海岸諸地にある(P120、484)
ヘロホキ(heroxki)
知里真志保「樺太アイヌの生活」『知里真志保著作集』3 1973 平凡社
→樺太の西海岸、白浜というところでこのように呼ばれている。
取りあえず手元にある文献からはニシンはアイヌ語でこのようにしか出てきませんでした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
蝦夷(えみし) 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
蝦夷(えみし)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人
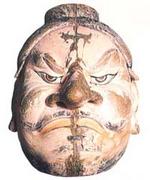





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)


![饒速日 [ニギハヤヒ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/68/50/3876850_10s.gif)













