さとっくです。
アテルイ(大墓公阿弖流為)の手作り小説を書いてみましたが、ここに投稿しても差し支えないでしょうか。途中までですが、皆さんに読んでいただければうれしいのですが・・・
このお話をつくるために主に参考にした文献は、宇治谷 孟著:講談社学術文庫、続日本記(上・中・下)です。
なお私は、高橋克彦氏の本(小説)は読んでおりません。個人的な視点で、アテルイを調べてみたかったからです。その視点は、次のようなものです。
1)当時のエミシ国には、活発な外交関係や交易ルートが既に存在していた。
2)上のことをなし得る次の2つの条件が整っていた。
・交易するに足る資源とその加工技術が存在していた(蕨手刀が代表)。
・外交や交易、また大和朝廷と張り合う戦略家やグループが存在していた。
推理ですが当時の情勢を考えると、エミシ国でこれをなし得た能力をもっていたのは百済系の移民と思われます。具体的には百済王敬福、道嶋嶋足、また海道エミシ(釜石付近から海岸線沿いで水戸付近まで居住していたと思われる民)のグループです。彼らの知恵や戦術が、結果的にアザマロやアテルイの登場を促し、774年から38年間続いた蝦夷征伐戦争で朝廷軍を翻弄したのでしょう。
もう一方の当事者桓武天皇も、百済系の人(母方)ですが、奈良時代には新羅国が優勢になりました。いろいろないきさつがあって東北に散在した百済系と、朝廷権力に入り込んだ新羅系が衝突したと思われます。平安京に遷都した直後も奈良地方には数多くの百済系住民がいたはずです。この中に坂上家の家系もつながり、百済系の田村麻呂が、ヒタカミへ調停工作に行ったと想像しています。
以上のことにより38年戦争は、当時の敵国同士であった新羅、渤海(旧百済)の代理戦争的な様相もあり、この視点もまじえて、途中まで空想話を書いてみました。なおこの中で参考にした文献一覧は次の通りです。
・間宮林蔵述・村上貞助編、東韃地方紀行他、平凡社東洋文庫484
・井上辰雄著、常陸国風土記にみる古代、学生社
・新野直吉、新古代東北史、歴史春秋社
・新野直吉、田村麻呂と阿弖流為、吉川弘文館
・梅原 猛、日本の深層(縄文・蝦夷文化を探る)、佼正出版社
・柴田弘武、鉄と俘囚の古代史、彩流社
・岩手県立博物館編、北の鉄文化
・石井昌国、佐々木稔 古代刀と鉄の科学、雄山閣版、考古学選書39
・武光 誠、古代東北まつろわぬ者の系譜、毎日新聞社
・吉田 努、岩手県の歴史と風土、創土社
・菊池敬一、北天の鬼神、岩手日報社
・井上秀雄、実証・古代朝鮮、日本放送出版協会
・井上秀雄、古代朝鮮、NHKブックス
・日本考古学協会編 北日本の考古学 吉川弘文館
・奥野正男、鉄の古代史、白水社
・近江雅和著、隠された古代、アラハバキ神の謎、彩流社
・飯田賢一、日本人の技術「金属」、研究社
・朝日百科、日本の歴史2古代、朝日新聞社
・律令国家、日本歴史2、有精堂
・祖霊信仰・民族宗教史叢書26巻、赤田光男編 雄山閣出版
・池田雅美著、みちのくの風土・その地誌学的研究、古今書院
・平川 南著、よみがえる古代文書 岩波新書
・橋本義彦編、古文書の語る日本史、筑摩書房
・小嶋芳孝著、日本海と北国文化、海と列島文化1、小学館
・大林太良編、戦・日本古代文化の探求、社会思想社
・金達寿・久野健・斉藤忠・李進煕、
古代の高句麗と日本 韓国文化院監修 学生社
・須藤良吉、古代史の謎・日本民族列島漂着考、宝文堂
・佐藤邦武著、アテルイと宗任、岩手出版
・新沼鐵夫著、蝦夷によって継承された鉄器文化東北の歴史と文化
岩手史学会編(論文集 63ページー97)
アテルイ(大墓公阿弖流為)の手作り小説を書いてみましたが、ここに投稿しても差し支えないでしょうか。途中までですが、皆さんに読んでいただければうれしいのですが・・・
このお話をつくるために主に参考にした文献は、宇治谷 孟著:講談社学術文庫、続日本記(上・中・下)です。
なお私は、高橋克彦氏の本(小説)は読んでおりません。個人的な視点で、アテルイを調べてみたかったからです。その視点は、次のようなものです。
1)当時のエミシ国には、活発な外交関係や交易ルートが既に存在していた。
2)上のことをなし得る次の2つの条件が整っていた。
・交易するに足る資源とその加工技術が存在していた(蕨手刀が代表)。
・外交や交易、また大和朝廷と張り合う戦略家やグループが存在していた。
推理ですが当時の情勢を考えると、エミシ国でこれをなし得た能力をもっていたのは百済系の移民と思われます。具体的には百済王敬福、道嶋嶋足、また海道エミシ(釜石付近から海岸線沿いで水戸付近まで居住していたと思われる民)のグループです。彼らの知恵や戦術が、結果的にアザマロやアテルイの登場を促し、774年から38年間続いた蝦夷征伐戦争で朝廷軍を翻弄したのでしょう。
もう一方の当事者桓武天皇も、百済系の人(母方)ですが、奈良時代には新羅国が優勢になりました。いろいろないきさつがあって東北に散在した百済系と、朝廷権力に入り込んだ新羅系が衝突したと思われます。平安京に遷都した直後も奈良地方には数多くの百済系住民がいたはずです。この中に坂上家の家系もつながり、百済系の田村麻呂が、ヒタカミへ調停工作に行ったと想像しています。
以上のことにより38年戦争は、当時の敵国同士であった新羅、渤海(旧百済)の代理戦争的な様相もあり、この視点もまじえて、途中まで空想話を書いてみました。なおこの中で参考にした文献一覧は次の通りです。
・間宮林蔵述・村上貞助編、東韃地方紀行他、平凡社東洋文庫484
・井上辰雄著、常陸国風土記にみる古代、学生社
・新野直吉、新古代東北史、歴史春秋社
・新野直吉、田村麻呂と阿弖流為、吉川弘文館
・梅原 猛、日本の深層(縄文・蝦夷文化を探る)、佼正出版社
・柴田弘武、鉄と俘囚の古代史、彩流社
・岩手県立博物館編、北の鉄文化
・石井昌国、佐々木稔 古代刀と鉄の科学、雄山閣版、考古学選書39
・武光 誠、古代東北まつろわぬ者の系譜、毎日新聞社
・吉田 努、岩手県の歴史と風土、創土社
・菊池敬一、北天の鬼神、岩手日報社
・井上秀雄、実証・古代朝鮮、日本放送出版協会
・井上秀雄、古代朝鮮、NHKブックス
・日本考古学協会編 北日本の考古学 吉川弘文館
・奥野正男、鉄の古代史、白水社
・近江雅和著、隠された古代、アラハバキ神の謎、彩流社
・飯田賢一、日本人の技術「金属」、研究社
・朝日百科、日本の歴史2古代、朝日新聞社
・律令国家、日本歴史2、有精堂
・祖霊信仰・民族宗教史叢書26巻、赤田光男編 雄山閣出版
・池田雅美著、みちのくの風土・その地誌学的研究、古今書院
・平川 南著、よみがえる古代文書 岩波新書
・橋本義彦編、古文書の語る日本史、筑摩書房
・小嶋芳孝著、日本海と北国文化、海と列島文化1、小学館
・大林太良編、戦・日本古代文化の探求、社会思想社
・金達寿・久野健・斉藤忠・李進煕、
古代の高句麗と日本 韓国文化院監修 学生社
・須藤良吉、古代史の謎・日本民族列島漂着考、宝文堂
・佐藤邦武著、アテルイと宗任、岩手出版
・新沼鐵夫著、蝦夷によって継承された鉄器文化東北の歴史と文化
岩手史学会編(論文集 63ページー97)
|
|
|
|
コメント(16)
アテルイ物語1 胆沢の春
今から1200年前、日高見(ヒタカミ)と呼ばれた地に生きた大墓公阿弖流為(オオタモキミノアテルイ)の小説をつくりました。7年ほど前に書いたものを修正しながら紹介してみます。
東北の奥地、雪が解けきらぬ3月の日高見(ヒタカミ)の胆沢(現岩手県水沢市)は、婚礼儀式のシーズンであった。
黄色と赤で型染めした長い衣と白袴を着け、まげを後ろに丸く結い上げた少年と、左右に結い上げた髪にめのうの玉飾りが光り、赤との縫い込みの唐衣をまとった少女が、身じろぎもせず厳寒の板間に座っていた。
二人とも痛みをこらえていた。吐く息が寒気の中に長くゆっくりとゆらいでいた。左右に立つ二人の老人の刺青の針を、顔面に受けていたのである。針はリズミカルに、休みなしに動いた。
社(やしろ)の外の風は肌を刺すように寒く、高床の板壁がときどき強い風に震えていた。しかし、傷をうけた二人の顔はほてり、社の室内は熱気が漂っていた。
二人の正面には白髪の老人が白木(木幣)と縄を振りかざしていた。幸運を祈とうするエミシに伝わる詩を口ずさみ続けていた。
「豊穣なる大地。恵みの日輪。そして一族繁栄の月よ、若き夫婦
に幸運をもたらしたまえ。光陰が幸とともに訪れよ」
老人の声は、装飾を凝らした板壁に響きわたり、外で見守る家族にも聞こえていた。この進行と一致して口から頬、さらに耳にかけて刺青の針が動く。年若い二人であったが、うめき声すら上げない。次は手首へと針が進む。
今年18になったという少年アテルイ。16歳になった少女タツノ。腕に走る激痛に耐える痙攣にあわせて血がにじみ出る。あどけない目のタツノも、刺青の痛みが全身を震わしていた。笑顔はなく、一点を凝視し、昨晩のことやこれからの自分の人生を思い描いていた。
アテルイとタツノは、昨晩、長老の館で共に夜をすごした。身の丈がやっと4尺を少し越えたばかり二人は、夫婦として長老の館で交わった。長老は臆することなくアテルイの一物から繁栄のしるしがあることを確認し、タツノも出産に支障がないかどうか検査される。
この段階で子孫繁栄があきらかに不可能とみなされた男女は、いかなる理由があろうとも、部族のリーダーの仲間にはなれず、追放された。子孫繁栄は部族としての重大な使命であったが、それ以上に男女としての一族の戒律を保つおきてがあった。これが当時のヒタカミの人権であった。
長老の検分は、新郎、新婦側の親族いずれにとっても切実なものであった。この後に、ひっそりと姿をくらまし、いわゆる山人になったり、山女として生きなければならない者も多かった。判定に容赦はない。
繁栄の判定が確認されると、部族への歓迎をしるす刺青の儀式が行われた。刺青は、えい児出産時にも行われるが、婚姻時には一人前の印として、部族特有の家系を示すマークを彫る。これは何か災いが生じたときの保険の証、部族間移動のパスポートとなった。マークを持つものはすべて「長老たちの子ども」として、権利が平等になる。
西暦760年、陸奥の国では、多賀城府ではすでに戸籍の記録を開始していた。アテルイのようなリーダー級の子弟の婚姻も、多賀城国府の斥候役を通じて中央政庁に報告されていた。穀物や金属資源等の税金徴収のためである。しかし当時は、多賀城柵が完成してまだ15年しかたっておらず、胆沢の地の戸籍調査はそれほど徹底されていなかった。このため、刺青はヒタカミ地域にとって事実上の戸籍登録であった。
痛みを克服し自己抑制力を確認する刺青は、部族にひろく認められた通過儀礼であり、部族の守り手として積極的に社会参加ができた。この儀礼はヒタカミの地の幼い子どもらのあこがれであった。長老は歌い続けた。
「林の精霊とともに朝を迎えよ。草の精霊には兵の血を捧げよ。
水の精霊に家族の無事を祈願せよ。火の精霊に黄泉を思いはせよ」
田夷長として奈良平城京の仕事をしはじめていたアテルイの父サイヒは、刺青などの時代ではないと感じつつも、長男の晴れの儀式を迎え、やはり誇らしい気持ちであった。
「サイヒさんも、めでたいことじゃな」
「はあ。村の皆さんにお世話になりまして」
サイヒがすすめる真っ白な陶磁器から、少し茶褐色の酒が、客人のめのうの杯に注がれた。冬越しの鮭の干物や塩漬けが漆塗りの膳に並んでいた。漆をふんだんに使った食器も、この日だけは特別に使える。
男子の婚姻は親にとって一人前の男を教育したしるしである。今日でいえば無事に大学卒業したような気分である。やしろの外では宴の酒を酌み交わしていた。やしろの儀式が終われば、音楽も奏でられる。麻の実に少し酔ったのか、風の寒さはそれほど感じなかった。若い頃、この地に技術者として派遣され居住したサイヒは、胆沢の習慣に馴染んだことを感じていた。
アテルイの妻タツノは、胆沢のさらに東にある東和(現花巻)という地から連れてきたエミシの娘だった。当時の貴族たちは招婿婚が流行だったが、ヒタカミの地でも、夫となる男は娘の生家でひと月は暮らす。しかし当時の女性は、今日のような人権はない。馬1頭、穀物半年分、布5人分と交換された。そして娘の嫁入りは、今生の別れであった。アテルイがタツノを連れて胆沢に戻るときは、生家や部族のものが村境まで泣いて見送りにきた。実際この当時、約2割の女が出産時に死んだ。
胆沢の部族では春を迎える季節は、ヒトにとって恋と婚姻の季節と決まっていた。初産が厳寒時期になり、恐ろしい伝染性の病原菌が少ないからである。真冬の出産は、えい児にとっては過酷である。しかし産褥熱による母体への危険が減り、母体が無事である確率が高い。生存優先権は、母体のほうにあった。
若い夫婦にはそうした婚姻の背景はわからない。昔から皆そうしていた、という習慣にしたがっているだけである。
「うう、痛かったな。大丈夫か?」
「ええ、頬のほうはともかく、腕が・・・」
タツノの丸い目がしばたき、耳に飾るヒスイの輪が揺れていた。すっかり覚悟を決め、落ち着き払った目は、この数か月で一人前の女に成長したことを示していた。タツノは常に「死」と隣り合わせであることを決意しなければならない。この刺青がこれから我が身を守るのだ。
長老は、女を意味する月の神にうやうやしく敬礼をし、玉串をかざし、儀式最後の呪文を唱えていた。婚姻儀礼は主に女の無事を祈るために行うものであった。長老は、幼顔の少し赤みが頬に残った、がっしりした体型のタツノの無事な運命を祈った。
「兄貴い、よかったな」
まだ14歳の、少し太り気味の大柄の弟ムネトが、いつのまのか高床によじのぼってきて、彫ったばかりのアテルイの腕を、パンとたたいた。痛みがはしる。そして淫らな目をタツノにむけ、にやにやしている。乱暴者のムネトが・・・と思いながらも、アテルイはじっとこらえていた。
幼い頃からの、この蝦夷の民の強靭な習慣、気質、また体力は、平城京の貴族どもが恐れるところであった。
今から1200年前、日高見(ヒタカミ)と呼ばれた地に生きた大墓公阿弖流為(オオタモキミノアテルイ)の小説をつくりました。7年ほど前に書いたものを修正しながら紹介してみます。
東北の奥地、雪が解けきらぬ3月の日高見(ヒタカミ)の胆沢(現岩手県水沢市)は、婚礼儀式のシーズンであった。
黄色と赤で型染めした長い衣と白袴を着け、まげを後ろに丸く結い上げた少年と、左右に結い上げた髪にめのうの玉飾りが光り、赤との縫い込みの唐衣をまとった少女が、身じろぎもせず厳寒の板間に座っていた。
二人とも痛みをこらえていた。吐く息が寒気の中に長くゆっくりとゆらいでいた。左右に立つ二人の老人の刺青の針を、顔面に受けていたのである。針はリズミカルに、休みなしに動いた。
社(やしろ)の外の風は肌を刺すように寒く、高床の板壁がときどき強い風に震えていた。しかし、傷をうけた二人の顔はほてり、社の室内は熱気が漂っていた。
二人の正面には白髪の老人が白木(木幣)と縄を振りかざしていた。幸運を祈とうするエミシに伝わる詩を口ずさみ続けていた。
「豊穣なる大地。恵みの日輪。そして一族繁栄の月よ、若き夫婦
に幸運をもたらしたまえ。光陰が幸とともに訪れよ」
老人の声は、装飾を凝らした板壁に響きわたり、外で見守る家族にも聞こえていた。この進行と一致して口から頬、さらに耳にかけて刺青の針が動く。年若い二人であったが、うめき声すら上げない。次は手首へと針が進む。
今年18になったという少年アテルイ。16歳になった少女タツノ。腕に走る激痛に耐える痙攣にあわせて血がにじみ出る。あどけない目のタツノも、刺青の痛みが全身を震わしていた。笑顔はなく、一点を凝視し、昨晩のことやこれからの自分の人生を思い描いていた。
アテルイとタツノは、昨晩、長老の館で共に夜をすごした。身の丈がやっと4尺を少し越えたばかり二人は、夫婦として長老の館で交わった。長老は臆することなくアテルイの一物から繁栄のしるしがあることを確認し、タツノも出産に支障がないかどうか検査される。
この段階で子孫繁栄があきらかに不可能とみなされた男女は、いかなる理由があろうとも、部族のリーダーの仲間にはなれず、追放された。子孫繁栄は部族としての重大な使命であったが、それ以上に男女としての一族の戒律を保つおきてがあった。これが当時のヒタカミの人権であった。
長老の検分は、新郎、新婦側の親族いずれにとっても切実なものであった。この後に、ひっそりと姿をくらまし、いわゆる山人になったり、山女として生きなければならない者も多かった。判定に容赦はない。
繁栄の判定が確認されると、部族への歓迎をしるす刺青の儀式が行われた。刺青は、えい児出産時にも行われるが、婚姻時には一人前の印として、部族特有の家系を示すマークを彫る。これは何か災いが生じたときの保険の証、部族間移動のパスポートとなった。マークを持つものはすべて「長老たちの子ども」として、権利が平等になる。
西暦760年、陸奥の国では、多賀城府ではすでに戸籍の記録を開始していた。アテルイのようなリーダー級の子弟の婚姻も、多賀城国府の斥候役を通じて中央政庁に報告されていた。穀物や金属資源等の税金徴収のためである。しかし当時は、多賀城柵が完成してまだ15年しかたっておらず、胆沢の地の戸籍調査はそれほど徹底されていなかった。このため、刺青はヒタカミ地域にとって事実上の戸籍登録であった。
痛みを克服し自己抑制力を確認する刺青は、部族にひろく認められた通過儀礼であり、部族の守り手として積極的に社会参加ができた。この儀礼はヒタカミの地の幼い子どもらのあこがれであった。長老は歌い続けた。
「林の精霊とともに朝を迎えよ。草の精霊には兵の血を捧げよ。
水の精霊に家族の無事を祈願せよ。火の精霊に黄泉を思いはせよ」
田夷長として奈良平城京の仕事をしはじめていたアテルイの父サイヒは、刺青などの時代ではないと感じつつも、長男の晴れの儀式を迎え、やはり誇らしい気持ちであった。
「サイヒさんも、めでたいことじゃな」
「はあ。村の皆さんにお世話になりまして」
サイヒがすすめる真っ白な陶磁器から、少し茶褐色の酒が、客人のめのうの杯に注がれた。冬越しの鮭の干物や塩漬けが漆塗りの膳に並んでいた。漆をふんだんに使った食器も、この日だけは特別に使える。
男子の婚姻は親にとって一人前の男を教育したしるしである。今日でいえば無事に大学卒業したような気分である。やしろの外では宴の酒を酌み交わしていた。やしろの儀式が終われば、音楽も奏でられる。麻の実に少し酔ったのか、風の寒さはそれほど感じなかった。若い頃、この地に技術者として派遣され居住したサイヒは、胆沢の習慣に馴染んだことを感じていた。
アテルイの妻タツノは、胆沢のさらに東にある東和(現花巻)という地から連れてきたエミシの娘だった。当時の貴族たちは招婿婚が流行だったが、ヒタカミの地でも、夫となる男は娘の生家でひと月は暮らす。しかし当時の女性は、今日のような人権はない。馬1頭、穀物半年分、布5人分と交換された。そして娘の嫁入りは、今生の別れであった。アテルイがタツノを連れて胆沢に戻るときは、生家や部族のものが村境まで泣いて見送りにきた。実際この当時、約2割の女が出産時に死んだ。
胆沢の部族では春を迎える季節は、ヒトにとって恋と婚姻の季節と決まっていた。初産が厳寒時期になり、恐ろしい伝染性の病原菌が少ないからである。真冬の出産は、えい児にとっては過酷である。しかし産褥熱による母体への危険が減り、母体が無事である確率が高い。生存優先権は、母体のほうにあった。
若い夫婦にはそうした婚姻の背景はわからない。昔から皆そうしていた、という習慣にしたがっているだけである。
「うう、痛かったな。大丈夫か?」
「ええ、頬のほうはともかく、腕が・・・」
タツノの丸い目がしばたき、耳に飾るヒスイの輪が揺れていた。すっかり覚悟を決め、落ち着き払った目は、この数か月で一人前の女に成長したことを示していた。タツノは常に「死」と隣り合わせであることを決意しなければならない。この刺青がこれから我が身を守るのだ。
長老は、女を意味する月の神にうやうやしく敬礼をし、玉串をかざし、儀式最後の呪文を唱えていた。婚姻儀礼は主に女の無事を祈るために行うものであった。長老は、幼顔の少し赤みが頬に残った、がっしりした体型のタツノの無事な運命を祈った。
「兄貴い、よかったな」
まだ14歳の、少し太り気味の大柄の弟ムネトが、いつのまのか高床によじのぼってきて、彫ったばかりのアテルイの腕を、パンとたたいた。痛みがはしる。そして淫らな目をタツノにむけ、にやにやしている。乱暴者のムネトが・・・と思いながらも、アテルイはじっとこらえていた。
幼い頃からの、この蝦夷の民の強靭な習慣、気質、また体力は、平城京の貴族どもが恐れるところであった。
アテルイ物語2 渤海国の使者
アテルイの婚礼が行われていた初春の季節は、当時、異国の使者が日本海を渡って、奈良の都へ訪れる季節でもあった。冬期間から初春の季節は日本海がなぎ、当時の日本海沿岸諸国、渤海や新羅から交易品を積んだ商人や、献上品を携えた国使がやってきた。
平城京が栄えたこの当時の日本、奈良の都は、日本海沿岸諸国との微妙なバランスの上に成り立っていた。このバランスがゆらいだとき、遷都や蝦夷地への軍事行動が起こり、アテルイらの名が歴史に登場したのである。この当時の朝鮮半島や中国との関係を少し解説しておこう。
日本が邪馬台国だった頃に朝鮮半島には三韓王朝が成立した。その三韓王朝のひとつ百済国の強力な支援により、日本の飛鳥朝廷が成立した。飛鳥朝廷には、朝鮮半島の文化様式が輸入され、この文化とともに渡来人が多数移住した。都の周囲には、中国系の漢氏、新羅系の秦氏、また高句麗、百済の滅亡に伴う貴族が住み着いた。それはあたかも、発見されたばかりの米大陸に移住したアングロ−サクソン、ヨーロッパ系を思わせるような勢いであった。
高い教養と技術をもった渡来人は、奈良の都を支える一大勢力になっていた。古代の日本は、現在の日本では想像できないほどの国際都市国家となっており、「日本海交易時代」とも呼べるような状況であった。
アテルイが生まれるわずか80年前の壬申の乱では、日本の王朝内部の戦争に、これら渡来系豪族が深く関わり、勝敗を決する要因になっていた。高句麗系や百済系の有力者を多く味方につけ、大友皇子を破った天武天皇は、吉野から不破関を通って近江王朝を焼き払い、飛鳥の古都に帰ることになった。大友皇子を支えていた百済系の大友氏はじめ、かつての渡来系王朝貴族らは、近江朝大津の地を去った。その一部は畿内に潜み、一部は関東や蝦夷地へと流れ住んだ。その百済系の末裔が、石巻市近辺に居住していたと推測される百済王敬福や道嶋(丸子氏)一族である。後で登場する道嶋嶋足の正式な姓は、牡鹿連(おじかのむらじ)と呼ぶ。この「連」名が、百済渡来人を示すものである。百済王敬福や道嶋一族は、海道エミシと呼ばれるやはり渡来系と混血した現地人と連携を取り合い、高度な文化や技術を伝えていた。この因縁がヒタカミ38年戦争に再燃するのである。
さて760年の奈良平城京の都に話を戻そう。当時の都は、藤原仲麻呂(恵美押勝)という権力者が朝廷をしきっていた。仲麻呂は、天武朝時代の知恵袋であった藤原不比等(ふひと)の孫である。仲麻呂は当時の首相であったと考えるとよい。
律令システムを利用して利権や享楽をほしいままにしていた藤原仲麻呂ら藤原家は、政局が安定した今は、橘や大友ら対抗勢力をどうにかしたいという内政しか関心がなかった。この頃は遷都が続き、インフレ財政になっていた。このため国交はあるとはいえ、当時は敵国であった新羅に対する防衛政策など海外経営には手を出せなかった。結局、仲麻呂は、渤海はじめ、新羅や唐と仲良くし、八方外交によりご機嫌取り行うことにした。しかしその一方では、国防策として長距離航海用船舶の建造も怠りはなかった。
当時の船舶は、たとえば渤海国の場合は、現中国東北部の豆満江港の羅津から、若狭湾の海路を航海していた。なぎの海であると約2週間で日本にたどり着く。その後、陸路で近江を横切った。記録では荷積み作業等をあわせて、若狭から奈良平城京まで4日で到着した。
「大炊の君(淳仁天皇)に、渤海から使者がかけつけてまいりま
した」
太師押勝(藤原仲麻呂)が帝の御前に進み、通訳(訳語職)を従え献上物を部屋に運び込ませた。淳仁天皇は、帝とはいえ押勝の義理の息子、娘婿である。押勝は帝に気配りすることもなく、通訳に語らせた。
「閣下におかれましては帝即位のめでたきをえ、我が渤海国の文
王より献上を申し上げる役をおおせつかり、参上いたしました」
押勝は、帝の御前で機嫌をそこねないように気を遣う使者の口上をじっと聞いていた。使者は、安禄山や史思明などの唐王朝をめぐる動静も伝えた。渤海は、高句麗滅亡後にできた国で、新羅と唐にはさまれた位置にある。日本にとっては朝鮮半島と中国大陸の情報を知るためにたいへん重要な使節団である。今回の来朝は、新羅や唐に対する防衛のための武具の無心であろう、と、押勝は推測しながら、次々に運び込まれた献上品に目をやった。
いつもながらの経典に加え、貨幣や墨、また弥勒、観音像があった。これらは正倉院に奉納することになる。献上品の中に、おや?と、気をひく品があった。白金のさやに納まった刀剣であった。帝との謁見後に、押勝は使者を呼び、これはなんだ、と尋ねた。
「やはり大臣様のお目にとまりましたか。これは安禄山に仕えた
わざ師が鍛えた作であります。どうぞお手にとりご覧ください」
うーむと言いつつ、押勝は抜き身を眺めた。見事に反った刀身を、さらに柄反りにより大きな彎曲をつくりだしている。両刃の鉄直刀に見慣れていた都の者にとっては、斬新なデザインだ。
唐の青竜刀よりずっと軽く、鯨刀のようなものものしさはなく、手に合致し、操作しやすい。白く光るしのぎの部分は、装飾用としても見事な槌目(つちめ)になっている。入念な素延べ作業や、土取り作業を行った跡を思わせる。
「なかなかのわざ物だ。お国では、いい鉄が取れるようですね」
「は、それはドウバとか申すもので、私の聞くところでは、帝の
お国から調達したものと伺っております」
「なに?我が国の?・・・聞いていないな」
太政大臣恵美押勝は謀略家である。この刀剣は、正倉院に奉納せず、機密物資であることにした。刀剣に関し一切の記帳をしてはいけない、と、側近の者に緘口令を出した。
反った刀身や柄反りにより大きく湾曲した刀身は、その後の日本刀の原型となった。蕨手刀(わらびてとう)である。蕨手刀はいまだデザインの起源が不明である。しかし台湾故宮博物館には、その原型となるめのう製の装飾用の刀があることを考えると、紀元前から中国大陸では広く知られていた形式の刀であったのだろう。
使者が言うには、鉄素材の出所はわが国である。
当時の鉄素材は全部国家の管理のもとで生産されていた。仲麻呂の知らない素材の出所は、管理ができなかった賊地、蝦夷地しかない。早速、押勝は兵部省(国防省)、治部省の最高担当官を呼び付け調査させることにした。伝令の者が木簡を携え、多賀城に遣わした押勝の息子である鎮守府将軍の藤原朝狩はじめ、造成中であった桃生柵の長、また出羽柵(秋田)の長らに招集がかかった。
押勝は憶測した。エミシの地になにか動きがある。蝦夷地は、当時の平城京にとっては、遠い新羅や渤海、唐よりも、さらに遠い、未知の国であった。
アテルイの婚礼が行われていた初春の季節は、当時、異国の使者が日本海を渡って、奈良の都へ訪れる季節でもあった。冬期間から初春の季節は日本海がなぎ、当時の日本海沿岸諸国、渤海や新羅から交易品を積んだ商人や、献上品を携えた国使がやってきた。
平城京が栄えたこの当時の日本、奈良の都は、日本海沿岸諸国との微妙なバランスの上に成り立っていた。このバランスがゆらいだとき、遷都や蝦夷地への軍事行動が起こり、アテルイらの名が歴史に登場したのである。この当時の朝鮮半島や中国との関係を少し解説しておこう。
日本が邪馬台国だった頃に朝鮮半島には三韓王朝が成立した。その三韓王朝のひとつ百済国の強力な支援により、日本の飛鳥朝廷が成立した。飛鳥朝廷には、朝鮮半島の文化様式が輸入され、この文化とともに渡来人が多数移住した。都の周囲には、中国系の漢氏、新羅系の秦氏、また高句麗、百済の滅亡に伴う貴族が住み着いた。それはあたかも、発見されたばかりの米大陸に移住したアングロ−サクソン、ヨーロッパ系を思わせるような勢いであった。
高い教養と技術をもった渡来人は、奈良の都を支える一大勢力になっていた。古代の日本は、現在の日本では想像できないほどの国際都市国家となっており、「日本海交易時代」とも呼べるような状況であった。
アテルイが生まれるわずか80年前の壬申の乱では、日本の王朝内部の戦争に、これら渡来系豪族が深く関わり、勝敗を決する要因になっていた。高句麗系や百済系の有力者を多く味方につけ、大友皇子を破った天武天皇は、吉野から不破関を通って近江王朝を焼き払い、飛鳥の古都に帰ることになった。大友皇子を支えていた百済系の大友氏はじめ、かつての渡来系王朝貴族らは、近江朝大津の地を去った。その一部は畿内に潜み、一部は関東や蝦夷地へと流れ住んだ。その百済系の末裔が、石巻市近辺に居住していたと推測される百済王敬福や道嶋(丸子氏)一族である。後で登場する道嶋嶋足の正式な姓は、牡鹿連(おじかのむらじ)と呼ぶ。この「連」名が、百済渡来人を示すものである。百済王敬福や道嶋一族は、海道エミシと呼ばれるやはり渡来系と混血した現地人と連携を取り合い、高度な文化や技術を伝えていた。この因縁がヒタカミ38年戦争に再燃するのである。
さて760年の奈良平城京の都に話を戻そう。当時の都は、藤原仲麻呂(恵美押勝)という権力者が朝廷をしきっていた。仲麻呂は、天武朝時代の知恵袋であった藤原不比等(ふひと)の孫である。仲麻呂は当時の首相であったと考えるとよい。
律令システムを利用して利権や享楽をほしいままにしていた藤原仲麻呂ら藤原家は、政局が安定した今は、橘や大友ら対抗勢力をどうにかしたいという内政しか関心がなかった。この頃は遷都が続き、インフレ財政になっていた。このため国交はあるとはいえ、当時は敵国であった新羅に対する防衛政策など海外経営には手を出せなかった。結局、仲麻呂は、渤海はじめ、新羅や唐と仲良くし、八方外交によりご機嫌取り行うことにした。しかしその一方では、国防策として長距離航海用船舶の建造も怠りはなかった。
当時の船舶は、たとえば渤海国の場合は、現中国東北部の豆満江港の羅津から、若狭湾の海路を航海していた。なぎの海であると約2週間で日本にたどり着く。その後、陸路で近江を横切った。記録では荷積み作業等をあわせて、若狭から奈良平城京まで4日で到着した。
「大炊の君(淳仁天皇)に、渤海から使者がかけつけてまいりま
した」
太師押勝(藤原仲麻呂)が帝の御前に進み、通訳(訳語職)を従え献上物を部屋に運び込ませた。淳仁天皇は、帝とはいえ押勝の義理の息子、娘婿である。押勝は帝に気配りすることもなく、通訳に語らせた。
「閣下におかれましては帝即位のめでたきをえ、我が渤海国の文
王より献上を申し上げる役をおおせつかり、参上いたしました」
押勝は、帝の御前で機嫌をそこねないように気を遣う使者の口上をじっと聞いていた。使者は、安禄山や史思明などの唐王朝をめぐる動静も伝えた。渤海は、高句麗滅亡後にできた国で、新羅と唐にはさまれた位置にある。日本にとっては朝鮮半島と中国大陸の情報を知るためにたいへん重要な使節団である。今回の来朝は、新羅や唐に対する防衛のための武具の無心であろう、と、押勝は推測しながら、次々に運び込まれた献上品に目をやった。
いつもながらの経典に加え、貨幣や墨、また弥勒、観音像があった。これらは正倉院に奉納することになる。献上品の中に、おや?と、気をひく品があった。白金のさやに納まった刀剣であった。帝との謁見後に、押勝は使者を呼び、これはなんだ、と尋ねた。
「やはり大臣様のお目にとまりましたか。これは安禄山に仕えた
わざ師が鍛えた作であります。どうぞお手にとりご覧ください」
うーむと言いつつ、押勝は抜き身を眺めた。見事に反った刀身を、さらに柄反りにより大きな彎曲をつくりだしている。両刃の鉄直刀に見慣れていた都の者にとっては、斬新なデザインだ。
唐の青竜刀よりずっと軽く、鯨刀のようなものものしさはなく、手に合致し、操作しやすい。白く光るしのぎの部分は、装飾用としても見事な槌目(つちめ)になっている。入念な素延べ作業や、土取り作業を行った跡を思わせる。
「なかなかのわざ物だ。お国では、いい鉄が取れるようですね」
「は、それはドウバとか申すもので、私の聞くところでは、帝の
お国から調達したものと伺っております」
「なに?我が国の?・・・聞いていないな」
太政大臣恵美押勝は謀略家である。この刀剣は、正倉院に奉納せず、機密物資であることにした。刀剣に関し一切の記帳をしてはいけない、と、側近の者に緘口令を出した。
反った刀身や柄反りにより大きく湾曲した刀身は、その後の日本刀の原型となった。蕨手刀(わらびてとう)である。蕨手刀はいまだデザインの起源が不明である。しかし台湾故宮博物館には、その原型となるめのう製の装飾用の刀があることを考えると、紀元前から中国大陸では広く知られていた形式の刀であったのだろう。
使者が言うには、鉄素材の出所はわが国である。
当時の鉄素材は全部国家の管理のもとで生産されていた。仲麻呂の知らない素材の出所は、管理ができなかった賊地、蝦夷地しかない。早速、押勝は兵部省(国防省)、治部省の最高担当官を呼び付け調査させることにした。伝令の者が木簡を携え、多賀城に遣わした押勝の息子である鎮守府将軍の藤原朝狩はじめ、造成中であった桃生柵の長、また出羽柵(秋田)の長らに招集がかかった。
押勝は憶測した。エミシの地になにか動きがある。蝦夷地は、当時の平城京にとっては、遠い新羅や渤海、唐よりも、さらに遠い、未知の国であった。
アテルイ物語3 伊治公呰麻呂
渤海国から献上された刀剣の素材、ドバは、岩鉄鉱系の鉄素材である。これは北上山地の東側で広く産出される独特な鉱石である。その一帯は当時、アラエビスの地と呼ばれていた。
この地に影響をもつ丸子(道嶋)氏の使いの者が、海路で南下し、桃生柵を通り、はるばる伊治(いじ、これはる。現宮城県築館町付近)までやってきた。使いの者は、背負っていた岩石をアザマロに手渡した。アザマロは、おお、これがドバか。マサー(砂鉄。真砂砂鉄、玉鋼(たまはがね)の原材料)とは違うな、と答えた。
手にとって見たアザマロは、伊治たたらの技術者であった。伊治では、多賀城の管理の下でこしらえた多くのたたら(古代の製鉄所)があった。そのひとつにたたらの長であった呰麻呂(あざまろ)は、このとき20代前半の若さであった。奈良時代の製鉄は全部官営であり、滋賀県琵琶湖周辺でしか許可されていなかった。蝦夷地である築館で認可されることは珍しいことである。
アザマロのアザという名は、もともと「製鉄」を意味するものであった。多賀城府ができたとき、都で流行の麻呂の名を与え、律令システムに組み込んだのであった。多賀城のものたちは現地のエンジニアや有力者を、このような形で重用した。アザマロ、のちの伊治公砦麻呂(これはるのきみあざまろ)は、歴史に名を残す事件を起こすことになる。
製鉄技術は中国や朝鮮半島から導入したものであり、製鉄を行っていたということは、渡来人が多少関与していたと考えるとよい。近江地域は百済系貴族の末裔が多く居住し、また蝦夷地である伊治の背後にも、多賀城付近に居住していた渡来系豪族、百済王や道嶋一族がいた。若いアザマロがこの仕事に就いているのは、その係累であるからである。文字も読めるし、特別の教育を受けていた。
アザマロの仕事は、火炎色で温度を見抜くことである。アザマロは村下(むらげ)と呼ぶ立場であり、アザマロの見たてで仲間に合図を送り、約10mもの広さの粘土炉(古代平炉)に、脇に控えた作業員(地下、じげ)が鹿袋で造った送風器を一斉に踏むのである。一方では多量の燃料供給を行っており、1代(1回の製鉄作業)で約10トンの木炭等の燃料が使われた。
たたら製鉄作業を開始すると5日間作業を止めることができない。もし大雨が降って粘土炉に触れると、炉が爆発する恐れがあるので、簡単な覆いをかけていた。炉を屋根で覆う本格的な高殿式の製鉄工場は、記録では江戸時代に入ってから開始されたとなっている。しかし当時は、簡単な構造の建物があったと思われる。いずれ天候との兼ね合いで作業を進める必要があり、雨季等の気象に対する知識も必要とされた。
歩留まりを高めるために、各部門では一瞬足りとも集中力を失ってはいけない。作業は、経験や体力が必要で、交代制の24時間勤務、女人禁制を徹底した緊迫した作業場であった。5日間の間に砂鉄や鉄鉱石あわせて約10トン投入され、その結果、約1トンの延べ素材(けら)が生産された。この量を、すべて人力で行っていた職業集団の団結力を想像してもらいたい。
さて、アザマロの手に渡ったドバのサンプルは、岩手県北の海岸地域で産出する非常に豊富な鉄を含む鉄鉱石である。エミシの民はその一帯をカネイシ(鉄が多量の意味)と呼んでいた。現在の釜石から久慈市の海岸線付近である。
カネイシでは、河川沿いで鉄鉱石が簡単に採取でき、伊治の鉱山のようにいちいち洞を掘ってマサ砂鉄を採取する必要がない。その昔、カネイシではゴールドラッシュのようなにぎわいもあったといわれる。当時の鉄鉱石坑道は、黄泉の国と形容され、環境の劣悪さ、作業の厳しさは、地獄に例えられたのであった。
しかしカネイシは、製鉄燃料であった松林も一時、不足になり、資源に恵まれていたとはいえ結局は限られた部族だけが定住せざるをえなかった。それは、1年もたたら作業をすると、山がひとつはげるからであった。できるだけ良質の燃料を求めて、カネイシの地から去っていった者も多い。彼らの中にはその後、金や銀の採取を行う技術者に転身する者もおり、後に百済王が東大寺造営のために献上することになった。
アザマロは、チャンスがあったら噂に聞いた鉱石の理想郷カネイシへ行ってみたい、と、この素材が埋蔵されている山河を想像していた。
渤海国から献上された刀剣の素材、ドバは、岩鉄鉱系の鉄素材である。これは北上山地の東側で広く産出される独特な鉱石である。その一帯は当時、アラエビスの地と呼ばれていた。
この地に影響をもつ丸子(道嶋)氏の使いの者が、海路で南下し、桃生柵を通り、はるばる伊治(いじ、これはる。現宮城県築館町付近)までやってきた。使いの者は、背負っていた岩石をアザマロに手渡した。アザマロは、おお、これがドバか。マサー(砂鉄。真砂砂鉄、玉鋼(たまはがね)の原材料)とは違うな、と答えた。
手にとって見たアザマロは、伊治たたらの技術者であった。伊治では、多賀城の管理の下でこしらえた多くのたたら(古代の製鉄所)があった。そのひとつにたたらの長であった呰麻呂(あざまろ)は、このとき20代前半の若さであった。奈良時代の製鉄は全部官営であり、滋賀県琵琶湖周辺でしか許可されていなかった。蝦夷地である築館で認可されることは珍しいことである。
アザマロのアザという名は、もともと「製鉄」を意味するものであった。多賀城府ができたとき、都で流行の麻呂の名を与え、律令システムに組み込んだのであった。多賀城のものたちは現地のエンジニアや有力者を、このような形で重用した。アザマロ、のちの伊治公砦麻呂(これはるのきみあざまろ)は、歴史に名を残す事件を起こすことになる。
製鉄技術は中国や朝鮮半島から導入したものであり、製鉄を行っていたということは、渡来人が多少関与していたと考えるとよい。近江地域は百済系貴族の末裔が多く居住し、また蝦夷地である伊治の背後にも、多賀城付近に居住していた渡来系豪族、百済王や道嶋一族がいた。若いアザマロがこの仕事に就いているのは、その係累であるからである。文字も読めるし、特別の教育を受けていた。
アザマロの仕事は、火炎色で温度を見抜くことである。アザマロは村下(むらげ)と呼ぶ立場であり、アザマロの見たてで仲間に合図を送り、約10mもの広さの粘土炉(古代平炉)に、脇に控えた作業員(地下、じげ)が鹿袋で造った送風器を一斉に踏むのである。一方では多量の燃料供給を行っており、1代(1回の製鉄作業)で約10トンの木炭等の燃料が使われた。
たたら製鉄作業を開始すると5日間作業を止めることができない。もし大雨が降って粘土炉に触れると、炉が爆発する恐れがあるので、簡単な覆いをかけていた。炉を屋根で覆う本格的な高殿式の製鉄工場は、記録では江戸時代に入ってから開始されたとなっている。しかし当時は、簡単な構造の建物があったと思われる。いずれ天候との兼ね合いで作業を進める必要があり、雨季等の気象に対する知識も必要とされた。
歩留まりを高めるために、各部門では一瞬足りとも集中力を失ってはいけない。作業は、経験や体力が必要で、交代制の24時間勤務、女人禁制を徹底した緊迫した作業場であった。5日間の間に砂鉄や鉄鉱石あわせて約10トン投入され、その結果、約1トンの延べ素材(けら)が生産された。この量を、すべて人力で行っていた職業集団の団結力を想像してもらいたい。
さて、アザマロの手に渡ったドバのサンプルは、岩手県北の海岸地域で産出する非常に豊富な鉄を含む鉄鉱石である。エミシの民はその一帯をカネイシ(鉄が多量の意味)と呼んでいた。現在の釜石から久慈市の海岸線付近である。
カネイシでは、河川沿いで鉄鉱石が簡単に採取でき、伊治の鉱山のようにいちいち洞を掘ってマサ砂鉄を採取する必要がない。その昔、カネイシではゴールドラッシュのようなにぎわいもあったといわれる。当時の鉄鉱石坑道は、黄泉の国と形容され、環境の劣悪さ、作業の厳しさは、地獄に例えられたのであった。
しかしカネイシは、製鉄燃料であった松林も一時、不足になり、資源に恵まれていたとはいえ結局は限られた部族だけが定住せざるをえなかった。それは、1年もたたら作業をすると、山がひとつはげるからであった。できるだけ良質の燃料を求めて、カネイシの地から去っていった者も多い。彼らの中にはその後、金や銀の採取を行う技術者に転身する者もおり、後に百済王が東大寺造営のために献上することになった。
アザマロは、チャンスがあったら噂に聞いた鉱石の理想郷カネイシへ行ってみたい、と、この素材が埋蔵されている山河を想像していた。
アテルイ物語4 カネイシへの道
アテルイの祖父は、鉄の里といわれたカネイシ(現釜石付近)に住んでいた。アテルイの母はカネイシに向かう途中の出身であり、幼い頃からカネイシへの道を往来していた。
アテルイの家族の紹介をしながら、当時の森に囲まれたカネイシへの道、現在の水沢から釜石の海岸方面に至る道を案内することにしよう。
アテルイは、田夷の郷の長である父サイヒと、母イレイの間に、イサワの地で生まれた。現在の岩手県水沢である。父のサイヒという名は、百済という国で使われていた名前であると教えられたことがあった。
父は、結婚した頃に、長老と共に朝廷に服する民、すなわち俘囚の身になった。その結果、律令システムに従い居住地名が付いて、オオタ(広い田)のサイヒと呼ぶことになった。わずかであったが納税管理を行うことになったので、公の字がつき、オオタノキミのサイヒと呼ぶのが正式の名である。これらは30年ほど前、多賀城ができたときに決まった話である。
祖父は異国の血の混じった人で、農耕や土木技術に長けていた。気仙沼から石巻方面に居住する嶋足氏と関係が深く、鉄のゴールドラッシュのときにカネイシに定住した。しかし胆沢には土着民族(いわゆるニギエビス)が多く、なじみが薄かった。そこへ土木技術者としてアテルイの父、サイヒを派遣してきたのである。こうすれば、釜石、気仙沼、水沢という三角形の交易圏ができあがる。サイヒのような技術者の派遣は珍しいものではない。アテルイが生まれた頃に亡くなった行基という大僧正も、若い頃は各地に土木技術を伝え歩いていた。土木建築などの特殊技術をもった人は、当時はどこでも大歓迎だったのである。
アテルイの父サイヒは、胆沢の農業土木技術を手がけることになった。当時、胆沢平野では北堰開発をした形跡があるが、この大規模プロジェクトに深く関わっていたと推測される。これは墾田永年私財法発布の一環として行われたと思われる。
サイヒは、すでに当時普及していた計算板(現在の九九表)や算術表をいつももち歩いていたであろう。こういう仕事は、渡来系の教育や支援があってできる仕事である。父サイヒがこのような形で、俘囚という立場における労務管理者になったとき、都から弓、弓矢、小刀、砥石、きゃはんなどの一式の道具をもらい、屋根の裏に保管していた。これらは、アラバキとかいう悪さをする奥地の集団を懲らしめるものだと聞いたが、実際には使ったことはない。しかしアテルイは幼いながら、わくわくして、弟ムネトといつも戦の話をしていた。
アテルイの母イレイは、その国にいく途中の木炭を産出する国(現遠野)の出身である。やはり百済渡来系で字の読み書きができた。おかげでアテルイら子供の教育に熱心で、早くからリーダー育成が行われていた。イレイは薬草を集めており、家族のための薬だけでなく、ムラの人にも調合をしていた。器を焼き上げるのもうまく、貯蔵壷はすべてイレイの手によるものであった。ただ、3番目の子どもを出産したときから口をあまりきかなくなり、妹のツタもそのせいか、ぼんやりした子どもになっていた。今日でいえば、イレイはうつ病であるが、当時はめずらしいことではなかった。健康に生きているだけでもありがたかった。
アテルイは、8人兄弟であったが4人死んでいた。弟ムネトの下にはツタという妹がいる。途中2人の死産があって、つい1年前、生まれる現場に立ち会った末妹ユラがいる。
母親の出産のとき、そばにいたアテルイも立ち会い、だらだら流れる血を止めたり、父と共にへその尾をきった。産婆もわきにいた。彼女の役目は、逆子を矯正するのみで、あとは祈祷するだけであった。母親は、糞尿を垂れ流し狂ったようにうめき、わらの上で青い顔をして、もはや死を覚悟していた。幼い妹ツタは泣き喚いていた。一瞬の介護のミスが家族を決める。家族の目前で愛す者が逝くことは常にあった。幼い子供たちは、こういう修羅場に立ち会い、女の痛みや使命を理解するのであった。
さてアテルイとムネトの兄弟は、いちど母の里、祖父の故郷へ行ってみたいと考えていた。年端もいかない子供のとき、準備なしで旅を試みたことがある。そこはカネイシの道、と呼んでいた。
この時代は乾飯と塩さえあれば、山の幸、川の幸が、道中の食料を与える。しかし、当時は既に獣を乱獲したせいか、子供でも安全な旅だった。蛇や蛙も貴重な食料であった。犬は人家の近くにしかいなく、野生化した山犬などは、人に食われるのを恐れ、めったに姿を見せない。子供とはいえ、狩猟の腕は確かなのである。
やはり恐いのは人間である。山の中に住む人間。途中、山人が現れた。彼らはたたら職人であることも多い。山人は、烏帽子冠のない刺青のある男子であると確認すると、何もせずに消えた。刺青をもつ男子どもを手にかけると、部族の復讐が恐いのだ。徹底して捜索され、殺されることになる。しかし、そういう印のない烏帽子姿の都の人間や、刺青のない子供たち(いわゆる浮浪者)が、山中で山人と出会うと、死を覚悟しなければならない。
山婆、山女は殺すことはないが、子供にとっては迷惑である。アテルイが3年前に出くわしたのはまだ20歳ぐらいの若い女だったが、ぎらぎらした目で迫り、子どもでも身体に抱きついてくる。不具女の烙印を押された女の悲しい性である。変にからかうと動転して殺されることもあるので、じっとするのがよい、と大人から教わっている。彼女らは普段から麻やけしの実を食し、寒さと孤独をしのいでいるらしいが、それで彼女らは気が変になった、といわれている。部族の男にとっては、遊び相手になり、衣料などの物を与え、里に降りて悪さをしないようにしている。今日でいえば売春であるが、当時の女にはほとんど人権はなく、明日の家族の運命でもあった。
カネイシの道は、時々馬が通り、荷物を運んでいた。主に塩やカネとを運んでいた。カネ(銅や鉄)を溶かして、工具や、やじり、また刀剣に変える。しかし青銅のカネなどはこけおどしで、たいして威力はない。やはり鉄だ、それもカネイシのドバ鉄なら、うまく鍛えると石を切ることができることを、子どもたちは知っていた。そんなことを語りながらも、アテルイとムネト兄弟は、道に迷ってしまい、カネイシではなく別の部族地へ入りこんでしまった。刺青のマークにより、胆沢へ送り返されたが、無事に帰ってきた息子達の顔をみて、普段は口をきかない母は、わっと声をだして泣いた。旅とは命を賭す冒険だったのである。しかしアテルイ兄弟の旅にでる気性は、生涯変わらなかった。
アテルイは婚姻を行う2年前に、今度は一人で母の国へ行ったのである。
一度歩いているからわかっているが、木げたの足取りは今度は軽い。迷わずに5日間歩き続け、サロベ(猿が石)という地に出た。そこで、川で湯浴みする裸体の山女とでくわし、はじめての経験をした。山女は自分のすみか、そまつな竪穴洞が並ぶ所へアテルイを連れて行った。話に聞いた山奥の宿泊所だ。女は、気に入った男に盗品や贈り物をあげ、また来るようにしむける。アテルイの顔の刺青で、立派な階級の出身であることがわかるのだ。一方では女は、旅の荷物の少しをわけてくれ、とせがむ。
アテルイはその山女のすみかで、驚くべきものを見せられた。
すばらしく彎曲した刃であった。近づくだけで殺気が感じられた。はやくこの場を立ち去りたいと思った。しかし女は、刃を持ってみろと言う。
取っ手に穴があいていた。毛抜き刀の原型であるが、小指をそこにひっかけるとたいへん持ちやすい。そのために、本当は重たい刀がまるで軽く感じる。これはすごい、と、アテルイは思った。なぎはらう、振り下ろす、すべての動作に刀が自在についてくる。
山女はまたじゃれついてきた。この刀をやるから、また来てほしいとせがんだ。細い体の小柄な女であった。刺青のない女なので、都の出身か浮浪者かわからないが、麻の薬のせいか、眼が異様に光っていた。アテルイはしかし、刀に心を奪われ続けていた。
アテルイの祖父は、鉄の里といわれたカネイシ(現釜石付近)に住んでいた。アテルイの母はカネイシに向かう途中の出身であり、幼い頃からカネイシへの道を往来していた。
アテルイの家族の紹介をしながら、当時の森に囲まれたカネイシへの道、現在の水沢から釜石の海岸方面に至る道を案内することにしよう。
アテルイは、田夷の郷の長である父サイヒと、母イレイの間に、イサワの地で生まれた。現在の岩手県水沢である。父のサイヒという名は、百済という国で使われていた名前であると教えられたことがあった。
父は、結婚した頃に、長老と共に朝廷に服する民、すなわち俘囚の身になった。その結果、律令システムに従い居住地名が付いて、オオタ(広い田)のサイヒと呼ぶことになった。わずかであったが納税管理を行うことになったので、公の字がつき、オオタノキミのサイヒと呼ぶのが正式の名である。これらは30年ほど前、多賀城ができたときに決まった話である。
祖父は異国の血の混じった人で、農耕や土木技術に長けていた。気仙沼から石巻方面に居住する嶋足氏と関係が深く、鉄のゴールドラッシュのときにカネイシに定住した。しかし胆沢には土着民族(いわゆるニギエビス)が多く、なじみが薄かった。そこへ土木技術者としてアテルイの父、サイヒを派遣してきたのである。こうすれば、釜石、気仙沼、水沢という三角形の交易圏ができあがる。サイヒのような技術者の派遣は珍しいものではない。アテルイが生まれた頃に亡くなった行基という大僧正も、若い頃は各地に土木技術を伝え歩いていた。土木建築などの特殊技術をもった人は、当時はどこでも大歓迎だったのである。
アテルイの父サイヒは、胆沢の農業土木技術を手がけることになった。当時、胆沢平野では北堰開発をした形跡があるが、この大規模プロジェクトに深く関わっていたと推測される。これは墾田永年私財法発布の一環として行われたと思われる。
サイヒは、すでに当時普及していた計算板(現在の九九表)や算術表をいつももち歩いていたであろう。こういう仕事は、渡来系の教育や支援があってできる仕事である。父サイヒがこのような形で、俘囚という立場における労務管理者になったとき、都から弓、弓矢、小刀、砥石、きゃはんなどの一式の道具をもらい、屋根の裏に保管していた。これらは、アラバキとかいう悪さをする奥地の集団を懲らしめるものだと聞いたが、実際には使ったことはない。しかしアテルイは幼いながら、わくわくして、弟ムネトといつも戦の話をしていた。
アテルイの母イレイは、その国にいく途中の木炭を産出する国(現遠野)の出身である。やはり百済渡来系で字の読み書きができた。おかげでアテルイら子供の教育に熱心で、早くからリーダー育成が行われていた。イレイは薬草を集めており、家族のための薬だけでなく、ムラの人にも調合をしていた。器を焼き上げるのもうまく、貯蔵壷はすべてイレイの手によるものであった。ただ、3番目の子どもを出産したときから口をあまりきかなくなり、妹のツタもそのせいか、ぼんやりした子どもになっていた。今日でいえば、イレイはうつ病であるが、当時はめずらしいことではなかった。健康に生きているだけでもありがたかった。
アテルイは、8人兄弟であったが4人死んでいた。弟ムネトの下にはツタという妹がいる。途中2人の死産があって、つい1年前、生まれる現場に立ち会った末妹ユラがいる。
母親の出産のとき、そばにいたアテルイも立ち会い、だらだら流れる血を止めたり、父と共にへその尾をきった。産婆もわきにいた。彼女の役目は、逆子を矯正するのみで、あとは祈祷するだけであった。母親は、糞尿を垂れ流し狂ったようにうめき、わらの上で青い顔をして、もはや死を覚悟していた。幼い妹ツタは泣き喚いていた。一瞬の介護のミスが家族を決める。家族の目前で愛す者が逝くことは常にあった。幼い子供たちは、こういう修羅場に立ち会い、女の痛みや使命を理解するのであった。
さてアテルイとムネトの兄弟は、いちど母の里、祖父の故郷へ行ってみたいと考えていた。年端もいかない子供のとき、準備なしで旅を試みたことがある。そこはカネイシの道、と呼んでいた。
この時代は乾飯と塩さえあれば、山の幸、川の幸が、道中の食料を与える。しかし、当時は既に獣を乱獲したせいか、子供でも安全な旅だった。蛇や蛙も貴重な食料であった。犬は人家の近くにしかいなく、野生化した山犬などは、人に食われるのを恐れ、めったに姿を見せない。子供とはいえ、狩猟の腕は確かなのである。
やはり恐いのは人間である。山の中に住む人間。途中、山人が現れた。彼らはたたら職人であることも多い。山人は、烏帽子冠のない刺青のある男子であると確認すると、何もせずに消えた。刺青をもつ男子どもを手にかけると、部族の復讐が恐いのだ。徹底して捜索され、殺されることになる。しかし、そういう印のない烏帽子姿の都の人間や、刺青のない子供たち(いわゆる浮浪者)が、山中で山人と出会うと、死を覚悟しなければならない。
山婆、山女は殺すことはないが、子供にとっては迷惑である。アテルイが3年前に出くわしたのはまだ20歳ぐらいの若い女だったが、ぎらぎらした目で迫り、子どもでも身体に抱きついてくる。不具女の烙印を押された女の悲しい性である。変にからかうと動転して殺されることもあるので、じっとするのがよい、と大人から教わっている。彼女らは普段から麻やけしの実を食し、寒さと孤独をしのいでいるらしいが、それで彼女らは気が変になった、といわれている。部族の男にとっては、遊び相手になり、衣料などの物を与え、里に降りて悪さをしないようにしている。今日でいえば売春であるが、当時の女にはほとんど人権はなく、明日の家族の運命でもあった。
カネイシの道は、時々馬が通り、荷物を運んでいた。主に塩やカネとを運んでいた。カネ(銅や鉄)を溶かして、工具や、やじり、また刀剣に変える。しかし青銅のカネなどはこけおどしで、たいして威力はない。やはり鉄だ、それもカネイシのドバ鉄なら、うまく鍛えると石を切ることができることを、子どもたちは知っていた。そんなことを語りながらも、アテルイとムネト兄弟は、道に迷ってしまい、カネイシではなく別の部族地へ入りこんでしまった。刺青のマークにより、胆沢へ送り返されたが、無事に帰ってきた息子達の顔をみて、普段は口をきかない母は、わっと声をだして泣いた。旅とは命を賭す冒険だったのである。しかしアテルイ兄弟の旅にでる気性は、生涯変わらなかった。
アテルイは婚姻を行う2年前に、今度は一人で母の国へ行ったのである。
一度歩いているからわかっているが、木げたの足取りは今度は軽い。迷わずに5日間歩き続け、サロベ(猿が石)という地に出た。そこで、川で湯浴みする裸体の山女とでくわし、はじめての経験をした。山女は自分のすみか、そまつな竪穴洞が並ぶ所へアテルイを連れて行った。話に聞いた山奥の宿泊所だ。女は、気に入った男に盗品や贈り物をあげ、また来るようにしむける。アテルイの顔の刺青で、立派な階級の出身であることがわかるのだ。一方では女は、旅の荷物の少しをわけてくれ、とせがむ。
アテルイはその山女のすみかで、驚くべきものを見せられた。
すばらしく彎曲した刃であった。近づくだけで殺気が感じられた。はやくこの場を立ち去りたいと思った。しかし女は、刃を持ってみろと言う。
取っ手に穴があいていた。毛抜き刀の原型であるが、小指をそこにひっかけるとたいへん持ちやすい。そのために、本当は重たい刀がまるで軽く感じる。これはすごい、と、アテルイは思った。なぎはらう、振り下ろす、すべての動作に刀が自在についてくる。
山女はまたじゃれついてきた。この刀をやるから、また来てほしいとせがんだ。細い体の小柄な女であった。刺青のない女なので、都の出身か浮浪者かわからないが、麻の薬のせいか、眼が異様に光っていた。アテルイはしかし、刀に心を奪われ続けていた。
アテルイ物語5 仲麻呂の野望
恵美押勝、すなわち藤原仲麻呂は、娘婿の淳仁天皇を皇位につけ、すべての権力を手中にしていた。当時は持国天と擬され諸国の長を招集することも簡単であった。
「朝猟(あさかり)、多賀城修繕工事の落ち着く間もなく呼び寄せ
たが、エミシの働きはどうなっているのか」
藤原朝猟は仲麻呂の息子である。自分の息子を多賀城の陸奥鎮守将軍にしアザマロらが製造した鉄や、漆など新開拓地陸奥エミシ国の物産は、すべて、息子を中継して仲麻呂のもとに集めていた。多賀城は軍事要塞としての機能を強めるために、当時は城壁を高くする修復工事を行っていた。その朝猟は答えた。
「はは。大臣、先日お話がありました金、鉄の産出がはかばかし
くなく、やはり多賀城だけでは監視が行き届かない問題があり
ます」
「ふむ?」
「多賀城の付近にさらに柵を作り、さらに俘囚の監視を強めるべき
かと存じます。覚べつ(一関付近)から北のエミシどもが、自由
に伊治付近へ下り、交易を交わしているようで、北へ財が流れて
いるとの話も聞きます。この動きを抑える必要があります。 柵
を造成することはいかがでしょうか」
気仙沼・釜石・胆沢の大三角形ネットワークの、気仙沼と胆沢間に、さらに関所を造れ、という提案である。ここをきっちりと抑えることにより、資源収奪がより徹底できるのである。
気仙から胆沢方面は、百済王敬福の技術支援により、黄金が産出された地域である。大仏建立のときは、多賀城付近で数キロの量しか献上していなかったが、まだ北の未開発地域、蝦夷地(現在の東北地方)がある。近い将来、柵(鎮守府)を作り、徹底的に収奪しなければならないだろう。仲麻呂は、そう考えた。
蝦夷地の開拓は、国家の財を貯え、権勢を強めるのによい事業である。仲麻呂は、貨幣を乱発したり、貨幣単位を変えてインフレをおこし、諸貴族のうらみをかっていた。しかし、自分だけの素材資源が獲得できれば、逆転勝利である。
唐風のハイカラを好んだ仲麻呂は、事実、かなりの経営手腕があり、ぬけめなく鉄資源掘削の権利を得ていた。蝦夷地はこの金属資源のみならず、長距離航海のための船舶素材、針葉樹も豊富に自生している。
このような国家プロジェクトは、天皇の詔(みことのり)により決定し、開始される。詔を発していた先の女帝(孝謙天皇)は押勝の姪であるが、今は亡き光明皇太后の世話のために一線を退いていた。その後に即位したひ弱な淳仁天皇は、仲麻呂が手を回して即位させたもので、提案に刃向かうことはまずありえない。つまり、淳仁天皇の詔は、実質上、仲麻呂の意志そのものであった。仲麻呂は答えた。
「うむ、よかろう。して場所は?」
この朝猟の提案で決まったのが、伊治柵(いじのさく)、後の伊治(当時の発音ではエゾ城と呼ぶ)城である。桃生柵からかなり離れているが、場所は出羽山道の途中であり、アザマロらのたたら製鉄がすでに展開しており、水利の面も心配はない。
仲麻呂らはエミシの地の情勢を議論しあった。
隣接する胆沢のエミシは長老一族が帰順しているとはいえ、背景にいる渡来人の勢力を借り、いつ官軍側へ反乱を起こすかわからない。この防御も考えるべきである。伊治城の造営にあたっては、胆沢の動向に注意しつつ、近くの蝦夷の俘囚や、坂東八国の浮浪人を仕丁(労役提供者)にし、多賀城や地元の首長などしかるべき者に、準備を行わせることを申し渡した。しかし仲麻呂はこの事業の完成を見ることなく世を去るのである。
「ときに、この献上品だが・・・」
と言って、仲麻呂は、白金(銀)細工のさやに収まった渤海からの献物を披露した。
「おお」
驚きの声をあげたのは、参議、藤原真先であった。この参議らもみな仲麻呂の息子である。家族内の会議といってもよい。仲麻呂は言った。
「この業物(わざもの)は、我が国のものを素材にして作ったとの
ことだ。一度試し切りをしたが、見事な切り口で、しかも軽い。
柄のこの毛抜きも巧妙に工夫され、自在に振り回すことができる
のだ」
大極悪人の安禄山に仕えた鍛冶師によるものだそうだが、おそらくこの大刀の原型自体、蝦夷地から持ち出されたのであろう、と、仲麻呂が考えを述べた。
「いちはやく、その出所を探り、それがどのように渤海に渡った
かを調べるのだ。出羽から阿支多(秋田)の防人から匠丁、雇
民に至るまでこまかく調べよ。ただし・・・秘密の内に行うよ
うに」
朝狩陸奥鎮守府将軍は父仲麻呂の野望を推し量っていた。これだけのテクノロジーを我が物にできれば、近江かいわいで気勢をあげている百済系貴族末裔の大伴氏も恐くはない。
さらにここ数年、正倉院の倉を賑やかにしている新羅や唐からの献上品に対する取り引き材料としても、この太刀は極上のものである。武器はいつの時代も先端技術であり、献上品としてもふさわしい。しかも、いま秘密裏に進めている新羅侵攻の手段にもなる。
「急がねばならない」
仲麻呂は子息らを急き立てた。仲麻呂の強力な後ろ盾であった光明天皇はすでに先立った。いかに親族とはいえ、仲麻呂にとって孝謙天皇や淳仁天皇は安心できない。
仲麻呂は自らの権力奪取を、人間関係、つまりコネの利用によって達成した人物なので、人心にことのほか気を遣った。この性格は、儒教政策の徹底でもよく示されていたが、最近の頭痛のタネは、それが通じない孝謙や淳仁が出現したことだった。この二人は、平城京の修復工事のために近江保良宮に赴いていた。
恵美押勝、すなわち藤原仲麻呂は、娘婿の淳仁天皇を皇位につけ、すべての権力を手中にしていた。当時は持国天と擬され諸国の長を招集することも簡単であった。
「朝猟(あさかり)、多賀城修繕工事の落ち着く間もなく呼び寄せ
たが、エミシの働きはどうなっているのか」
藤原朝猟は仲麻呂の息子である。自分の息子を多賀城の陸奥鎮守将軍にしアザマロらが製造した鉄や、漆など新開拓地陸奥エミシ国の物産は、すべて、息子を中継して仲麻呂のもとに集めていた。多賀城は軍事要塞としての機能を強めるために、当時は城壁を高くする修復工事を行っていた。その朝猟は答えた。
「はは。大臣、先日お話がありました金、鉄の産出がはかばかし
くなく、やはり多賀城だけでは監視が行き届かない問題があり
ます」
「ふむ?」
「多賀城の付近にさらに柵を作り、さらに俘囚の監視を強めるべき
かと存じます。覚べつ(一関付近)から北のエミシどもが、自由
に伊治付近へ下り、交易を交わしているようで、北へ財が流れて
いるとの話も聞きます。この動きを抑える必要があります。 柵
を造成することはいかがでしょうか」
気仙沼・釜石・胆沢の大三角形ネットワークの、気仙沼と胆沢間に、さらに関所を造れ、という提案である。ここをきっちりと抑えることにより、資源収奪がより徹底できるのである。
気仙から胆沢方面は、百済王敬福の技術支援により、黄金が産出された地域である。大仏建立のときは、多賀城付近で数キロの量しか献上していなかったが、まだ北の未開発地域、蝦夷地(現在の東北地方)がある。近い将来、柵(鎮守府)を作り、徹底的に収奪しなければならないだろう。仲麻呂は、そう考えた。
蝦夷地の開拓は、国家の財を貯え、権勢を強めるのによい事業である。仲麻呂は、貨幣を乱発したり、貨幣単位を変えてインフレをおこし、諸貴族のうらみをかっていた。しかし、自分だけの素材資源が獲得できれば、逆転勝利である。
唐風のハイカラを好んだ仲麻呂は、事実、かなりの経営手腕があり、ぬけめなく鉄資源掘削の権利を得ていた。蝦夷地はこの金属資源のみならず、長距離航海のための船舶素材、針葉樹も豊富に自生している。
このような国家プロジェクトは、天皇の詔(みことのり)により決定し、開始される。詔を発していた先の女帝(孝謙天皇)は押勝の姪であるが、今は亡き光明皇太后の世話のために一線を退いていた。その後に即位したひ弱な淳仁天皇は、仲麻呂が手を回して即位させたもので、提案に刃向かうことはまずありえない。つまり、淳仁天皇の詔は、実質上、仲麻呂の意志そのものであった。仲麻呂は答えた。
「うむ、よかろう。して場所は?」
この朝猟の提案で決まったのが、伊治柵(いじのさく)、後の伊治(当時の発音ではエゾ城と呼ぶ)城である。桃生柵からかなり離れているが、場所は出羽山道の途中であり、アザマロらのたたら製鉄がすでに展開しており、水利の面も心配はない。
仲麻呂らはエミシの地の情勢を議論しあった。
隣接する胆沢のエミシは長老一族が帰順しているとはいえ、背景にいる渡来人の勢力を借り、いつ官軍側へ反乱を起こすかわからない。この防御も考えるべきである。伊治城の造営にあたっては、胆沢の動向に注意しつつ、近くの蝦夷の俘囚や、坂東八国の浮浪人を仕丁(労役提供者)にし、多賀城や地元の首長などしかるべき者に、準備を行わせることを申し渡した。しかし仲麻呂はこの事業の完成を見ることなく世を去るのである。
「ときに、この献上品だが・・・」
と言って、仲麻呂は、白金(銀)細工のさやに収まった渤海からの献物を披露した。
「おお」
驚きの声をあげたのは、参議、藤原真先であった。この参議らもみな仲麻呂の息子である。家族内の会議といってもよい。仲麻呂は言った。
「この業物(わざもの)は、我が国のものを素材にして作ったとの
ことだ。一度試し切りをしたが、見事な切り口で、しかも軽い。
柄のこの毛抜きも巧妙に工夫され、自在に振り回すことができる
のだ」
大極悪人の安禄山に仕えた鍛冶師によるものだそうだが、おそらくこの大刀の原型自体、蝦夷地から持ち出されたのであろう、と、仲麻呂が考えを述べた。
「いちはやく、その出所を探り、それがどのように渤海に渡った
かを調べるのだ。出羽から阿支多(秋田)の防人から匠丁、雇
民に至るまでこまかく調べよ。ただし・・・秘密の内に行うよ
うに」
朝狩陸奥鎮守府将軍は父仲麻呂の野望を推し量っていた。これだけのテクノロジーを我が物にできれば、近江かいわいで気勢をあげている百済系貴族末裔の大伴氏も恐くはない。
さらにここ数年、正倉院の倉を賑やかにしている新羅や唐からの献上品に対する取り引き材料としても、この太刀は極上のものである。武器はいつの時代も先端技術であり、献上品としてもふさわしい。しかも、いま秘密裏に進めている新羅侵攻の手段にもなる。
「急がねばならない」
仲麻呂は子息らを急き立てた。仲麻呂の強力な後ろ盾であった光明天皇はすでに先立った。いかに親族とはいえ、仲麻呂にとって孝謙天皇や淳仁天皇は安心できない。
仲麻呂は自らの権力奪取を、人間関係、つまりコネの利用によって達成した人物なので、人心にことのほか気を遣った。この性格は、儒教政策の徹底でもよく示されていたが、最近の頭痛のタネは、それが通じない孝謙や淳仁が出現したことだった。この二人は、平城京の修復工事のために近江保良宮に赴いていた。
アテルイ物語6 孝謙女帝
「みかど(淳仁天皇)は何を卑屈になっておるのか」
煙のたなびく琵琶湖に向かい、聞こえよがしに声を張り上げる40を半ば過ぎの女性がいた。
「太政官(藤原仲麻呂)にはこの近江のかんな(鉱山)を与え、先
帝(光明)の宝物や武具も十分に賜った。この配慮だけでも口や
かましい親王達は黙っていまい。情けなや・・・これも私の信心
が薄いせいだろうか」
女性は煙で曇る空を見上げた。
「いつも曇るこの海(琵琶湖)の空のような心に、祥瑞は来ぬもの
か。それにしても、ここは好かぬ」
女性は、専制の範であった聖武を父とし、喪中である光明女帝を母とし、平城京修復のために、近江保良宮(ほらのみや、現大津市)に逗留している天武の末裔、先の孝謙女帝、高野天皇(たかののすめらみこと。後の称徳天皇)である。
何の文句を言っているかというと、淳仁帝が、保良宮への博士等を数名派遣することを依頼したのであるが、博士らはすべて京修復作業にかかりきりで、仲麻呂に説得され断られ、ぶつぶつ言っていることをたしなめているのである。
これまで孝謙女帝は、先の光明女帝を通じて、仲麻呂を思うがままに利用できた。しかし光明女帝が崩じて後は、ワンマンの秀才官僚の藤原仲麻呂に指図できる者はいなくなった。淳仁帝もその器ではなく、孝謙女帝は沽券に関わると言って手厳しくたしなめていた。
孝謙先帝と淳仁天皇が、琵琶湖湖畔に完成したばかりの、まだ漆の匂いが漂う新宮殿に来たのは、藤原仲麻呂のさしがねであった。
平城京修復は、流行り病への対策の一環として、易博士の意見により進めていた。修復のメインはもちろん天皇が居住する大極殿である。しかし他方では、その南向かいに建つ豪奢な高楼である藤原仲麻呂邸(当時は田村邸と呼んでいた)の修復も意味していた。
淳仁天皇にとっては義父、孝謙にとって叔父になる仲麻呂は、宴などで帝がときおり宿泊する自宅を、国家財政を使って改築していたのである。単なる住宅と思うなかれ。一辺が約1kmもあり、祖父の藤原不比等から伝わる当時の首相用私邸と考えるとよい。
この修復工事に対するクレームは、親王から孝謙先帝へと伝えられた。つまり、皇位継承権がないとはいえ天皇の近親である親王達は、藤原氏の我が物顔の事業に不満を強めていた。しかし時は淳仁帝の代であり、実質上、権力は義父である藤原仲麻呂の手中にあった。親王とはいえ、いつ何どき、仲麻呂の機微にふれて、長屋王のような災難にあうかわからないので、注意深く意見を差し控えて忍んだ。この鬱積が孝謙女帝へ伝えられていたのである。
日本の歴史史上、最初の「正当な女性皇太子」から帝に即位した孝謙女帝は、仲麻呂に対する遠慮などはいらなかった。それまでの女帝である、推古や天明は、大后による即位、つまり幼帝を抱えている等の事情でやむなく即位したのであるが、孝謙だけは次期天皇である皇太子から帝になったのである。したがって淳仁帝の即位に関しては、仲麻呂の推薦意見があったとはいえ、あくまでも孝謙女帝の責任で、継承させたものと信じていた。このため、仲麻呂のように淳仁帝を傷つけるような振る舞いは、自分のプライドが傷つけられるように感じたのである。
「それにしても、今日もけむいことよ。話に聞いたアラエビスの地
もこのような空なのかしら」
背後から衛兵である女、由利が近づき、うちわであおいだ。
保良宮の周りには、京や愛発関、不破関等からの情報ネットとなる「のろし台」がそびえ、一定時間ごとに煙があがる。それに加えて、背後の山々は、すでに煙の帯で覆われていた。
近江の国は、当時の日本の製鉄の中心地であった。というより、畿内以外の製鉄は、天皇の特別な許可がなければ、できないことになっていた。唯一、エミシのような圏外地を例外として。
近江では、ちょっと山道に入ると、稚児までが縦型たたら炉へ炭運搬する姿が多い。近江はまたガラスの生産地でもあり、これに青銅製造まで加えて、名だたる森林は、次々と伐採され燃料として使われていた。製鉄作業が始まり煙が立ち込めると、快晴でも空は曇り、琵琶湖上空は、雨が降らない限り、かすみに覆われ続けていた。
女衛兵の由利は、後ろから近づいてくる足音に気がついた。そちらに身構え、孝謙女帝の背後を守る。
由利は、造東大寺使吉備真備の姪である。その記憶力や判断力を買われて、孝謙女帝の秘書をしていた。同時に、彼女の口から、孝謙の動静がこまかく親王や反仲麻呂グループへ伝えられていた。足音は、齢50になる僧、道鏡であった。
この男は、孝謙の気持ちの動きがわかるのか、女帝がセンチメンタルになるタイミングに、いつも出現する。河内弓削出身の目の鋭い顔立ちは、しかし丸顔で気品があり、僧職にしては珍しく立烏帽子の貴族趣味の装いをしていた。事実、弓削一族は、渡来系の貴族の末裔である。
「おお道鏡、そなたも海(琵琶湖)の見物か」
「はは。帝のお邪魔でなければ」
門地主義の奈良朝時代では、一豪族あがりが帝に近づくことなどはあってはならない事態である。しかしサンスクリット仏教原典を読み、医者であり呪術を使うセラピストであった道鏡は、特別な存在であった。
孝謙にとっても、なんでも知っているこの男は、ひまつぶしの相手としても楽しかった。
女帝のめくばせで、由利は一歩退き、変わって道鏡が間に入る。
由利は、男のくせにいやに白く長い指をもつ道鏡が、昨晩も帝の全身マッサージを行いながら祈祷していたことを思い起こしていた。道鏡はもはや女衛兵の目も気にならなかった。むしろ衛兵は自分だといわんばかりの振る舞いであり、女帝がそれを許しているのであった。
これらのうわさは尾ひれがついて、淳仁天皇から仲麻呂へ、すでに伝わっていた。こちこちの律令主義者であった仲麻呂にとっては、道鏡の振る舞いは、やくざ者が帝に直接アプローチするようなもので、看過できないことであった。しかし逆の立場、つまり藤原系でない下級官人には、実力主義の台頭を意味していた。そういう面で道鏡は、地方出身者の希望の星であった。
「みかど(淳仁天皇)は何を卑屈になっておるのか」
煙のたなびく琵琶湖に向かい、聞こえよがしに声を張り上げる40を半ば過ぎの女性がいた。
「太政官(藤原仲麻呂)にはこの近江のかんな(鉱山)を与え、先
帝(光明)の宝物や武具も十分に賜った。この配慮だけでも口や
かましい親王達は黙っていまい。情けなや・・・これも私の信心
が薄いせいだろうか」
女性は煙で曇る空を見上げた。
「いつも曇るこの海(琵琶湖)の空のような心に、祥瑞は来ぬもの
か。それにしても、ここは好かぬ」
女性は、専制の範であった聖武を父とし、喪中である光明女帝を母とし、平城京修復のために、近江保良宮(ほらのみや、現大津市)に逗留している天武の末裔、先の孝謙女帝、高野天皇(たかののすめらみこと。後の称徳天皇)である。
何の文句を言っているかというと、淳仁帝が、保良宮への博士等を数名派遣することを依頼したのであるが、博士らはすべて京修復作業にかかりきりで、仲麻呂に説得され断られ、ぶつぶつ言っていることをたしなめているのである。
これまで孝謙女帝は、先の光明女帝を通じて、仲麻呂を思うがままに利用できた。しかし光明女帝が崩じて後は、ワンマンの秀才官僚の藤原仲麻呂に指図できる者はいなくなった。淳仁帝もその器ではなく、孝謙女帝は沽券に関わると言って手厳しくたしなめていた。
孝謙先帝と淳仁天皇が、琵琶湖湖畔に完成したばかりの、まだ漆の匂いが漂う新宮殿に来たのは、藤原仲麻呂のさしがねであった。
平城京修復は、流行り病への対策の一環として、易博士の意見により進めていた。修復のメインはもちろん天皇が居住する大極殿である。しかし他方では、その南向かいに建つ豪奢な高楼である藤原仲麻呂邸(当時は田村邸と呼んでいた)の修復も意味していた。
淳仁天皇にとっては義父、孝謙にとって叔父になる仲麻呂は、宴などで帝がときおり宿泊する自宅を、国家財政を使って改築していたのである。単なる住宅と思うなかれ。一辺が約1kmもあり、祖父の藤原不比等から伝わる当時の首相用私邸と考えるとよい。
この修復工事に対するクレームは、親王から孝謙先帝へと伝えられた。つまり、皇位継承権がないとはいえ天皇の近親である親王達は、藤原氏の我が物顔の事業に不満を強めていた。しかし時は淳仁帝の代であり、実質上、権力は義父である藤原仲麻呂の手中にあった。親王とはいえ、いつ何どき、仲麻呂の機微にふれて、長屋王のような災難にあうかわからないので、注意深く意見を差し控えて忍んだ。この鬱積が孝謙女帝へ伝えられていたのである。
日本の歴史史上、最初の「正当な女性皇太子」から帝に即位した孝謙女帝は、仲麻呂に対する遠慮などはいらなかった。それまでの女帝である、推古や天明は、大后による即位、つまり幼帝を抱えている等の事情でやむなく即位したのであるが、孝謙だけは次期天皇である皇太子から帝になったのである。したがって淳仁帝の即位に関しては、仲麻呂の推薦意見があったとはいえ、あくまでも孝謙女帝の責任で、継承させたものと信じていた。このため、仲麻呂のように淳仁帝を傷つけるような振る舞いは、自分のプライドが傷つけられるように感じたのである。
「それにしても、今日もけむいことよ。話に聞いたアラエビスの地
もこのような空なのかしら」
背後から衛兵である女、由利が近づき、うちわであおいだ。
保良宮の周りには、京や愛発関、不破関等からの情報ネットとなる「のろし台」がそびえ、一定時間ごとに煙があがる。それに加えて、背後の山々は、すでに煙の帯で覆われていた。
近江の国は、当時の日本の製鉄の中心地であった。というより、畿内以外の製鉄は、天皇の特別な許可がなければ、できないことになっていた。唯一、エミシのような圏外地を例外として。
近江では、ちょっと山道に入ると、稚児までが縦型たたら炉へ炭運搬する姿が多い。近江はまたガラスの生産地でもあり、これに青銅製造まで加えて、名だたる森林は、次々と伐採され燃料として使われていた。製鉄作業が始まり煙が立ち込めると、快晴でも空は曇り、琵琶湖上空は、雨が降らない限り、かすみに覆われ続けていた。
女衛兵の由利は、後ろから近づいてくる足音に気がついた。そちらに身構え、孝謙女帝の背後を守る。
由利は、造東大寺使吉備真備の姪である。その記憶力や判断力を買われて、孝謙女帝の秘書をしていた。同時に、彼女の口から、孝謙の動静がこまかく親王や反仲麻呂グループへ伝えられていた。足音は、齢50になる僧、道鏡であった。
この男は、孝謙の気持ちの動きがわかるのか、女帝がセンチメンタルになるタイミングに、いつも出現する。河内弓削出身の目の鋭い顔立ちは、しかし丸顔で気品があり、僧職にしては珍しく立烏帽子の貴族趣味の装いをしていた。事実、弓削一族は、渡来系の貴族の末裔である。
「おお道鏡、そなたも海(琵琶湖)の見物か」
「はは。帝のお邪魔でなければ」
門地主義の奈良朝時代では、一豪族あがりが帝に近づくことなどはあってはならない事態である。しかしサンスクリット仏教原典を読み、医者であり呪術を使うセラピストであった道鏡は、特別な存在であった。
孝謙にとっても、なんでも知っているこの男は、ひまつぶしの相手としても楽しかった。
女帝のめくばせで、由利は一歩退き、変わって道鏡が間に入る。
由利は、男のくせにいやに白く長い指をもつ道鏡が、昨晩も帝の全身マッサージを行いながら祈祷していたことを思い起こしていた。道鏡はもはや女衛兵の目も気にならなかった。むしろ衛兵は自分だといわんばかりの振る舞いであり、女帝がそれを許しているのであった。
これらのうわさは尾ひれがついて、淳仁天皇から仲麻呂へ、すでに伝わっていた。こちこちの律令主義者であった仲麻呂にとっては、道鏡の振る舞いは、やくざ者が帝に直接アプローチするようなもので、看過できないことであった。しかし逆の立場、つまり藤原系でない下級官人には、実力主義の台頭を意味していた。そういう面で道鏡は、地方出身者の希望の星であった。
アテルイ物語7 アラハバキ(荒吐)
「トゥー、ホーットゥ、トゥトゥ・・・」
声を出しながらブナ林を駆け抜けていく若者たちがいた。
5人が円形のまま谷底に向かっていく。すばやく左右に身体を振ると、頭に巻いた赤布が風になびき、背中の藁袋が跳ね上がった。アテルイら、エミシに恐れられた山岳狩猟民族、アラハバキである。尾根に向かおうと走っていた鹿の親子は、すっかり逃げ場を失い、初夏の笹薮の中を追われるまま谷川に向かって駆け降りて行った。
750年頃の恵留間(えるま)、すなわち現在の岩手県浄法寺の地は、アラハバキと呼ばれる民が住み着き、阿倍という王がいた。
アラハバキとは、彼らの信ずる神の名、アラハバキカムイのことである。奈良朝廷の言い方では、盛岡以南のニギエミシに対するアラエビス(アラエミシとも言う)で、もっとも原始的と蔑まれた民である。
彼らは、以前はアラバとも呼ばれていたが、いつの頃からか荒吐、アンバ、阿倍(あんば)の名で呼ばれるようになった。先住民族であった阿蘇部(アソベ)族の名をとった、ともいわれる。
恵留間の阿倍族は、浄法寺から八戸、久慈海岸までの勢力圏があり、海岸からはさらに、海道エミシ(現在の石巻、仙台方面の原住民)と呼ばれた民との交流があった。なお海道蝦夷は渡来系の氏族との交流があり、当時すでに水稲栽培もしていた。山岳狩猟民族と呼ぶのは正確ではない。
阿倍族は、農産品はじめ、琥珀や鉄鉱石、海草塩、材木、さらに馬を海路で輸送していた。当時、伊寺水門と呼ばれていた北上川河口付近までの太平洋岸は、これらの民や渡来系のリーダーが支配しており、奈良朝廷の勢力の及ぶところではなかった。
この安倍族王室から、南に嫁いだ姫がいた。この名にちなみ、阿倍、阿部姓がすでに平城京に伝わっていた。この姓は、ずっと後世の、前九年の役で安倍一族として歴史に再登場することになる。
保良宮に一時滞在し、仲麻呂とのいさかいで高野へ戻った孝謙女帝は、その皇太子の時の名を阿倍(あへの)皇女と言った。父の聖武天皇は、北方文エミシの雰囲気が漂うこの名に大いに躊躇したと聞くが、妻の阿閉皇女(後の元明天皇)の名もやはりアベであり、天然資源の宝庫を連想させるという理由で採用された。言葉が実態を支配すると信じられた言霊主義がはびこっていた時代なので、この命名は驚くべき出来事である。しかし本人である孝謙女帝は、皇太子時代のこの名がお気に入りであった。
そういう経緯もあり、朝廷にはすでに、新羅や渤海の渡来人だけでなく、エミシ地域からも女官が入っていた。そうではあったが、藤原家が厳重に帝の血統管理をしており、孝謙女帝が直接、蝦夷と血縁関係があったわけではない。
孝謙女帝の皇太子命名は、アラバキ、アラハバキ族の安倍王室にとって嬉しい出来事であった。奈良朝廷は、思ってもいなかった効果、つまり、蝦夷の民の帰順が増えたことに喜んだ。単純な理由であるが、実はこれで太平洋側に居住する海道エミシとの協力体制ができあがり、桃生柵が建設されたのである。覇権をもって成立する律令システムを広めたい朝廷にとっては、喜ばしいトレンドであった。この効果をさらに高めようと、人事政策では、道嶋嶋足など、蝦夷の地の渡来系の有力者を中央官庁に招聘し、重用したのであった。
孝謙女帝は幼い頃から蝦夷とのめぐりあわせがあった。すぐ後に起こった大事件でも、道嶋嶋足はじめ、数多くの蝦夷軍団が支援を行い、仲麻呂政権を排斥し、孝謙女帝を守護し、称徳天皇(孝謙の次の天皇名)の誕生に多大な貢献をすることになった。
「タゥタゥ、ヌォン(よし、弓をもて。ふせ!ふせ!)」
荒吐族の独特な言葉をかけあい、二人の誘導者が頭を低くすると、その直後に矢の風を切る音が頭上に聞こえた。
谷底の至近距離まで追いつめて射た矢は、鹿の首などは簡単に貫く。2頭の親鹿がその場でもんどりうった。小鹿があとずさりしておびえているが、若者たちは手を振って追い払った。
先頭の二人の若者は、腰の小刀をぬき、あざやかに獲物をさばいた。山の神への祈りと感謝の文句を口ずさみ、鹿の血を飲みまわした。山の中では貴重な塩分とビタミンの補給である。
「アラハバキカムイ、ツンカムイツボケの二柱をもって、水なる神、
カッパ、ヒボド、イツコ、イベガモ、モグリ、そして山神タダラに、
この恵みを捧げます」
若者たちはひととおり儀式をすませると、獲物をこまかく切断し、背中の藁袋にそれぞれ詰めた。
一度使用した矢も分解して、腰袋で持ち帰る。矢じりは貴重品で、特に自分用のものは、普段から訓練して使い慣れており、どのくらいの力で、どういう方向に飛び、どの程度殺傷力があるか熟知している。こういうものは他人にはわたさないものと教育されている。
「平賀(碇ヶ関付近)のほうでは・・・」
仕留めた若者が腰をおろして語った。
「この矢じりを使っているようだ。中身はよくわからないが」
流線形に鍛造した矢じりの血を拭き取り、皆の前に示した。矢軸を入れる口をどう加工したものか、茅の茎を適当にねじるだけで簡単に装着できる。再利用するには、いったん小刀でこまめに削り取り掃除する必要があるが、作業はきわめて簡単である。
「うーむ、ドバ鉄を鍛えたような色だが、軸穴をどのように作ったも
のか」
「これは平賀のパク山女にもらったが、うまい細工をしているようだ」
「あの女か。ヨクソのパク、国樔(こくしょう)の?」
ヨクソのパクは、まっかつ国の民で、チパンル(津軽)に漂着した後、どこをどうやって来たのか、恵留間の山中に住み着いていた。色白で眼が少し青い女であり、若者の間では評判であった。
「この矢じりは、狩部か、兵部のタダラ軍具に献上するのがいいので
は?」
律令が及ばない蝦夷の奥地、アラエビスの民は独特な政治体制があり、神部の長老が人心を統制していた。住まいが不定期に移動し、ベースキャンプのような王室部落を形成していた。新たな情報はすべて、このベースキャンプに集中するのが掟である。
ベースキャンプによる国家は、別の見方をすれば、種族のテリトリーを、勝手に作れる状況を意味する。ヨクソのパク、つまりクメール系の中国人のような者も、このルールに従い、自由に定住、生活できたのである。奥蝦夷のアラエビスの地は、日本人のみならず漂着民にとって自由な開拓地であり、多民族国家になっていた。こういう競争状態にある地では矢じりや鉄素材のような、軍事技術の情報が、まっさきに伝わる。
若者たちが鹿の肉を、阿倍王ベースキャンプに持ち帰ったのは夕方近くであった。付近一帯は琵琶湖のように煙が立ちこめていた。女や子どもも、小型のタタラへの燃料運搬を手伝っており、その付近は冶金工場と化していた。この工場から生活必需品や農耕具、そして武器が生産されるのである。
「トゥー、ホーットゥ、トゥトゥ・・・」
声を出しながらブナ林を駆け抜けていく若者たちがいた。
5人が円形のまま谷底に向かっていく。すばやく左右に身体を振ると、頭に巻いた赤布が風になびき、背中の藁袋が跳ね上がった。アテルイら、エミシに恐れられた山岳狩猟民族、アラハバキである。尾根に向かおうと走っていた鹿の親子は、すっかり逃げ場を失い、初夏の笹薮の中を追われるまま谷川に向かって駆け降りて行った。
750年頃の恵留間(えるま)、すなわち現在の岩手県浄法寺の地は、アラハバキと呼ばれる民が住み着き、阿倍という王がいた。
アラハバキとは、彼らの信ずる神の名、アラハバキカムイのことである。奈良朝廷の言い方では、盛岡以南のニギエミシに対するアラエビス(アラエミシとも言う)で、もっとも原始的と蔑まれた民である。
彼らは、以前はアラバとも呼ばれていたが、いつの頃からか荒吐、アンバ、阿倍(あんば)の名で呼ばれるようになった。先住民族であった阿蘇部(アソベ)族の名をとった、ともいわれる。
恵留間の阿倍族は、浄法寺から八戸、久慈海岸までの勢力圏があり、海岸からはさらに、海道エミシ(現在の石巻、仙台方面の原住民)と呼ばれた民との交流があった。なお海道蝦夷は渡来系の氏族との交流があり、当時すでに水稲栽培もしていた。山岳狩猟民族と呼ぶのは正確ではない。
阿倍族は、農産品はじめ、琥珀や鉄鉱石、海草塩、材木、さらに馬を海路で輸送していた。当時、伊寺水門と呼ばれていた北上川河口付近までの太平洋岸は、これらの民や渡来系のリーダーが支配しており、奈良朝廷の勢力の及ぶところではなかった。
この安倍族王室から、南に嫁いだ姫がいた。この名にちなみ、阿倍、阿部姓がすでに平城京に伝わっていた。この姓は、ずっと後世の、前九年の役で安倍一族として歴史に再登場することになる。
保良宮に一時滞在し、仲麻呂とのいさかいで高野へ戻った孝謙女帝は、その皇太子の時の名を阿倍(あへの)皇女と言った。父の聖武天皇は、北方文エミシの雰囲気が漂うこの名に大いに躊躇したと聞くが、妻の阿閉皇女(後の元明天皇)の名もやはりアベであり、天然資源の宝庫を連想させるという理由で採用された。言葉が実態を支配すると信じられた言霊主義がはびこっていた時代なので、この命名は驚くべき出来事である。しかし本人である孝謙女帝は、皇太子時代のこの名がお気に入りであった。
そういう経緯もあり、朝廷にはすでに、新羅や渤海の渡来人だけでなく、エミシ地域からも女官が入っていた。そうではあったが、藤原家が厳重に帝の血統管理をしており、孝謙女帝が直接、蝦夷と血縁関係があったわけではない。
孝謙女帝の皇太子命名は、アラバキ、アラハバキ族の安倍王室にとって嬉しい出来事であった。奈良朝廷は、思ってもいなかった効果、つまり、蝦夷の民の帰順が増えたことに喜んだ。単純な理由であるが、実はこれで太平洋側に居住する海道エミシとの協力体制ができあがり、桃生柵が建設されたのである。覇権をもって成立する律令システムを広めたい朝廷にとっては、喜ばしいトレンドであった。この効果をさらに高めようと、人事政策では、道嶋嶋足など、蝦夷の地の渡来系の有力者を中央官庁に招聘し、重用したのであった。
孝謙女帝は幼い頃から蝦夷とのめぐりあわせがあった。すぐ後に起こった大事件でも、道嶋嶋足はじめ、数多くの蝦夷軍団が支援を行い、仲麻呂政権を排斥し、孝謙女帝を守護し、称徳天皇(孝謙の次の天皇名)の誕生に多大な貢献をすることになった。
「タゥタゥ、ヌォン(よし、弓をもて。ふせ!ふせ!)」
荒吐族の独特な言葉をかけあい、二人の誘導者が頭を低くすると、その直後に矢の風を切る音が頭上に聞こえた。
谷底の至近距離まで追いつめて射た矢は、鹿の首などは簡単に貫く。2頭の親鹿がその場でもんどりうった。小鹿があとずさりしておびえているが、若者たちは手を振って追い払った。
先頭の二人の若者は、腰の小刀をぬき、あざやかに獲物をさばいた。山の神への祈りと感謝の文句を口ずさみ、鹿の血を飲みまわした。山の中では貴重な塩分とビタミンの補給である。
「アラハバキカムイ、ツンカムイツボケの二柱をもって、水なる神、
カッパ、ヒボド、イツコ、イベガモ、モグリ、そして山神タダラに、
この恵みを捧げます」
若者たちはひととおり儀式をすませると、獲物をこまかく切断し、背中の藁袋にそれぞれ詰めた。
一度使用した矢も分解して、腰袋で持ち帰る。矢じりは貴重品で、特に自分用のものは、普段から訓練して使い慣れており、どのくらいの力で、どういう方向に飛び、どの程度殺傷力があるか熟知している。こういうものは他人にはわたさないものと教育されている。
「平賀(碇ヶ関付近)のほうでは・・・」
仕留めた若者が腰をおろして語った。
「この矢じりを使っているようだ。中身はよくわからないが」
流線形に鍛造した矢じりの血を拭き取り、皆の前に示した。矢軸を入れる口をどう加工したものか、茅の茎を適当にねじるだけで簡単に装着できる。再利用するには、いったん小刀でこまめに削り取り掃除する必要があるが、作業はきわめて簡単である。
「うーむ、ドバ鉄を鍛えたような色だが、軸穴をどのように作ったも
のか」
「これは平賀のパク山女にもらったが、うまい細工をしているようだ」
「あの女か。ヨクソのパク、国樔(こくしょう)の?」
ヨクソのパクは、まっかつ国の民で、チパンル(津軽)に漂着した後、どこをどうやって来たのか、恵留間の山中に住み着いていた。色白で眼が少し青い女であり、若者の間では評判であった。
「この矢じりは、狩部か、兵部のタダラ軍具に献上するのがいいので
は?」
律令が及ばない蝦夷の奥地、アラエビスの民は独特な政治体制があり、神部の長老が人心を統制していた。住まいが不定期に移動し、ベースキャンプのような王室部落を形成していた。新たな情報はすべて、このベースキャンプに集中するのが掟である。
ベースキャンプによる国家は、別の見方をすれば、種族のテリトリーを、勝手に作れる状況を意味する。ヨクソのパク、つまりクメール系の中国人のような者も、このルールに従い、自由に定住、生活できたのである。奥蝦夷のアラエビスの地は、日本人のみならず漂着民にとって自由な開拓地であり、多民族国家になっていた。こういう競争状態にある地では矢じりや鉄素材のような、軍事技術の情報が、まっさきに伝わる。
若者たちが鹿の肉を、阿倍王ベースキャンプに持ち帰ったのは夕方近くであった。付近一帯は琵琶湖のように煙が立ちこめていた。女や子どもも、小型のタタラへの燃料運搬を手伝っており、その付近は冶金工場と化していた。この工場から生活必需品や農耕具、そして武器が生産されるのである。
アテルイ物語8 都の者たち
胆沢の地に奈良平城京の者が訪れたのは、1年ぶりであろうか。アテルイがその黒烏帽子と白装束の20人ほどの者を見かけたのは、枯葉の舞う夕暮れであった。
先頭には伊治のエミシと、舞草のエミシが数名立ち、多賀城からのおよそ30日の旅路を案内してきたのである。舞草(一関)からは水路で北上してきた。胆沢の川の桟橋はに、都の旗をつけた船が停泊した。
長老から呼び出しをうけたアテルイは、部族の若者らと共に館の警護に立った。
すでに1児を出産した妻タツノは、義母イレイらとともに、食料の調達やもてなしを行った。館の中には、この地のリーダー達が待機していた。その中に、アテルイの父、サイヒもいる。
歓迎のたいまつの列に都の者が到着した時は、もはや夜半になっていた。11月の胆沢の夜は、雪はまだ積もっていないが寒さが厳しい。警護隊長とともに立った長老側近のひとりが、冷気の中に白いと息を長く伸ばしながら歓迎の口上をのべ、一行は、アテルイらが立つ警護の列の間を通り、館のホールへ入った。
長老、ここでは胆沢の王であるが、その前で、都のスタイルの礼を行い、エミシ達の列と対峙して座った。都の者達は、木簡を読み上げながら、まずは訪問の目的と滞在期間をつげ、みやげ物を献上したる。大型の木箱は百済からの仏像だろうか、うやうやしく運び込んでいた。
これらの作法は、明らかに外交そのものである。
この時代の奈良朝廷は伊治(宮城北部)から北の地域は、官位を与えて帰順した俘囚もいたが、基本的には蛮国、すなわち一種の外国とみなていた。都の者が、エミシ仲間の先導なく蝦夷のテリトリーに立ち入ると、事情の如何に関わらず略奪を受けた。この時点では、朝廷がそれを取り締まったり、抗議する術はなかった。この状況は、胆沢城ができるまで続いた。
聞けば都の者は、畿内の港(伊勢湾)から約30日の海路と陸路で多賀城まで到着したとのことである。大阪から多賀城までの所要日数30と、多賀城から胆沢までの所要日数30が同じなのは、道路や水路事情のせいではない。案内役のエミシを採用したり、胆沢にいたるまでの外交手続きが複雑なためなのである。入国・出国に不慣れなエミシを採用してしまうと生死に関わる問題になった。案内役になることができるエミシは、俘囚、つまり朝廷に帰順したエミシである。朝廷に税金を払い、しかもエミシの民にも人望がある者でないと案内役になれない。新顔の都の使いはこのような交渉に何日も要するのであった。今回の案内役、伊治と舞草エミシも、胆沢の民にとって信頼でき、歓迎できる者であった。
長老の館に食膳が運び込まれた。油灯ゆらめく中を、若いタツノら女性たちが、白麻に絹をかぶせた礼服をまとい、次々に使者の前に宴の準備を行った。都の者は、このセレモニーにより、宿泊寝食等が保証されたことを知るのであった。
「都のほうでは、騒動(いくさ)が起こったとの話を伺ったが」
長老の側近である警護隊軍長、伊佐西古(いさしこ)が問いただした。
「は。私どもが港を出た直後のようです。太政官殿が謀反を企て、
高野上皇(孝謙女帝)が、これを平定し終わったとのことです」
恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱である。
この年の9月、孝謙女帝の機嫌をそこねた藤原仲麻呂が、孝謙側にあった帝の象徴、御璽や駅鈴を武力で奪おうと試みて失敗し、ついには近江琵琶湖にて家族もろとも生涯を閉じたのであった。仲麻呂は淳仁天皇に謀反したわけでない。逆に、淳仁天皇の命令に背いた孝謙女帝へ、馬鹿まじめになっておしおきしようとしたことが、天皇への謀反行為にされたのである。仲麻呂にとっては、思わぬ展開だったであろう。
経緯を聞きながら、長老は、仲麻呂の律令制度に対する義理がたさに同情しながらも、思うところがあったのか、新しい帝、称徳天皇の即位を祝う酒を準備させた。
「それで、その道鏡という方は、新しい太政官に着任されたのですね」
「いや、固辞されたと伺っておりますが」
うーむ、巧妙な男だと長老は考えた。奥ゆかしい紳士振りを女帝にみせつけ、信頼を得ようとするタヌキのようなイメージを思い描いた。結局は藤原家の内紛劇のようであるが、藤原一族の勢力は健在のようである。すると問題は、帝の意志に影響を及ぼす道鏡の外交姿勢であるが、その部分が、長老には見えてこない。
「仲麻呂殿の係累については、いかがな処置であったのか」
立ち入った質問だ。ある程度噂は耳にしていたが、こうした質問にも、都の特使らは、信義をもって応えた。
「都に在住した一族は、もはや生存していないと思います。しかし
多賀城の勝猟(かつかり)鎮守将軍は、帝の命により留任されて
おります」
「・・ほう?」
少し前に、多賀城を改修した終えた藤原朝狩(あさかり)将軍は、東海道節度使に異動していた。その後、やはり仲麻呂の子息の勝猟が着任した。朝狩は恵美押勝の乱に連座し処刑されたが、勝猟は留任?・・・
長老の頭には、百済足人、小野竹浪、百済王三忠、田中多太麻呂、大伴益立の名前と、陸奥国大国造の道嶋嶋足の名前が浮かび、誰かが蝦夷政策をそのまま維持することを進言したものがいると推測した。仲麻呂政権における対エミシの姿勢や計画は、継承したままである。
胆沢のリーダー達は相談した。この都の特使は、仲麻呂政権の命令のままで訪問したであろう。とすると、うわさに聞いた伊治城建設の攪乱を回避するため、その牽制を目的とした柔軟化外交団であろう。
だからいつもと違い献上品が多く、礼儀もうやうやしい。徹頭徹尾のサービスぶりである。税金である庸調督促の話題も、微妙に避けている。彼らは目的は、おそらく胆沢の民の監視である。しばらく逗留し我々の対応を観察するであろう。彼らが、対エミシとしてどう出るのか、逆に監視してみようと話がまとまった。長老は都の者に、この冬は、胆沢で過ごすように、と勧めた。
都の者の代表は道嶋三山と名乗った。伺ったら、宮城県牡鹿出身の丸子氏、海道エミシと縁が深い渡来人の末裔であった。長老は、案内役であった伊治エミシに声をかけた。
「伊治の方々も、お役目ご苦労でしたな。そちらの方は、名はなんと
申すのじゃ」
「は。アザマロともうします」
「お若いようじゃの。はははは・・・」
伊治公呰麻呂と胆沢のエミシとの運命的な出会いであった。アザマロは、伊治城建設プロジェクトの現地側のリーダーに内定していた。外交役としての自己紹介を兼ねて胆沢へ訪れたのであった。
長期間の逗留が決定した後、アザマロは別の申し入れを行った。かねてからのあこがれであった資源の宝庫、カネイシへの入り口へ来たのである。長老にその旨をつたえ、カネイシへの道の案内役を懇願した。そこで紹介されたのが、アテルイであった。
胆沢の地に奈良平城京の者が訪れたのは、1年ぶりであろうか。アテルイがその黒烏帽子と白装束の20人ほどの者を見かけたのは、枯葉の舞う夕暮れであった。
先頭には伊治のエミシと、舞草のエミシが数名立ち、多賀城からのおよそ30日の旅路を案内してきたのである。舞草(一関)からは水路で北上してきた。胆沢の川の桟橋はに、都の旗をつけた船が停泊した。
長老から呼び出しをうけたアテルイは、部族の若者らと共に館の警護に立った。
すでに1児を出産した妻タツノは、義母イレイらとともに、食料の調達やもてなしを行った。館の中には、この地のリーダー達が待機していた。その中に、アテルイの父、サイヒもいる。
歓迎のたいまつの列に都の者が到着した時は、もはや夜半になっていた。11月の胆沢の夜は、雪はまだ積もっていないが寒さが厳しい。警護隊長とともに立った長老側近のひとりが、冷気の中に白いと息を長く伸ばしながら歓迎の口上をのべ、一行は、アテルイらが立つ警護の列の間を通り、館のホールへ入った。
長老、ここでは胆沢の王であるが、その前で、都のスタイルの礼を行い、エミシ達の列と対峙して座った。都の者達は、木簡を読み上げながら、まずは訪問の目的と滞在期間をつげ、みやげ物を献上したる。大型の木箱は百済からの仏像だろうか、うやうやしく運び込んでいた。
これらの作法は、明らかに外交そのものである。
この時代の奈良朝廷は伊治(宮城北部)から北の地域は、官位を与えて帰順した俘囚もいたが、基本的には蛮国、すなわち一種の外国とみなていた。都の者が、エミシ仲間の先導なく蝦夷のテリトリーに立ち入ると、事情の如何に関わらず略奪を受けた。この時点では、朝廷がそれを取り締まったり、抗議する術はなかった。この状況は、胆沢城ができるまで続いた。
聞けば都の者は、畿内の港(伊勢湾)から約30日の海路と陸路で多賀城まで到着したとのことである。大阪から多賀城までの所要日数30と、多賀城から胆沢までの所要日数30が同じなのは、道路や水路事情のせいではない。案内役のエミシを採用したり、胆沢にいたるまでの外交手続きが複雑なためなのである。入国・出国に不慣れなエミシを採用してしまうと生死に関わる問題になった。案内役になることができるエミシは、俘囚、つまり朝廷に帰順したエミシである。朝廷に税金を払い、しかもエミシの民にも人望がある者でないと案内役になれない。新顔の都の使いはこのような交渉に何日も要するのであった。今回の案内役、伊治と舞草エミシも、胆沢の民にとって信頼でき、歓迎できる者であった。
長老の館に食膳が運び込まれた。油灯ゆらめく中を、若いタツノら女性たちが、白麻に絹をかぶせた礼服をまとい、次々に使者の前に宴の準備を行った。都の者は、このセレモニーにより、宿泊寝食等が保証されたことを知るのであった。
「都のほうでは、騒動(いくさ)が起こったとの話を伺ったが」
長老の側近である警護隊軍長、伊佐西古(いさしこ)が問いただした。
「は。私どもが港を出た直後のようです。太政官殿が謀反を企て、
高野上皇(孝謙女帝)が、これを平定し終わったとのことです」
恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱である。
この年の9月、孝謙女帝の機嫌をそこねた藤原仲麻呂が、孝謙側にあった帝の象徴、御璽や駅鈴を武力で奪おうと試みて失敗し、ついには近江琵琶湖にて家族もろとも生涯を閉じたのであった。仲麻呂は淳仁天皇に謀反したわけでない。逆に、淳仁天皇の命令に背いた孝謙女帝へ、馬鹿まじめになっておしおきしようとしたことが、天皇への謀反行為にされたのである。仲麻呂にとっては、思わぬ展開だったであろう。
経緯を聞きながら、長老は、仲麻呂の律令制度に対する義理がたさに同情しながらも、思うところがあったのか、新しい帝、称徳天皇の即位を祝う酒を準備させた。
「それで、その道鏡という方は、新しい太政官に着任されたのですね」
「いや、固辞されたと伺っておりますが」
うーむ、巧妙な男だと長老は考えた。奥ゆかしい紳士振りを女帝にみせつけ、信頼を得ようとするタヌキのようなイメージを思い描いた。結局は藤原家の内紛劇のようであるが、藤原一族の勢力は健在のようである。すると問題は、帝の意志に影響を及ぼす道鏡の外交姿勢であるが、その部分が、長老には見えてこない。
「仲麻呂殿の係累については、いかがな処置であったのか」
立ち入った質問だ。ある程度噂は耳にしていたが、こうした質問にも、都の特使らは、信義をもって応えた。
「都に在住した一族は、もはや生存していないと思います。しかし
多賀城の勝猟(かつかり)鎮守将軍は、帝の命により留任されて
おります」
「・・ほう?」
少し前に、多賀城を改修した終えた藤原朝狩(あさかり)将軍は、東海道節度使に異動していた。その後、やはり仲麻呂の子息の勝猟が着任した。朝狩は恵美押勝の乱に連座し処刑されたが、勝猟は留任?・・・
長老の頭には、百済足人、小野竹浪、百済王三忠、田中多太麻呂、大伴益立の名前と、陸奥国大国造の道嶋嶋足の名前が浮かび、誰かが蝦夷政策をそのまま維持することを進言したものがいると推測した。仲麻呂政権における対エミシの姿勢や計画は、継承したままである。
胆沢のリーダー達は相談した。この都の特使は、仲麻呂政権の命令のままで訪問したであろう。とすると、うわさに聞いた伊治城建設の攪乱を回避するため、その牽制を目的とした柔軟化外交団であろう。
だからいつもと違い献上品が多く、礼儀もうやうやしい。徹頭徹尾のサービスぶりである。税金である庸調督促の話題も、微妙に避けている。彼らは目的は、おそらく胆沢の民の監視である。しばらく逗留し我々の対応を観察するであろう。彼らが、対エミシとしてどう出るのか、逆に監視してみようと話がまとまった。長老は都の者に、この冬は、胆沢で過ごすように、と勧めた。
都の者の代表は道嶋三山と名乗った。伺ったら、宮城県牡鹿出身の丸子氏、海道エミシと縁が深い渡来人の末裔であった。長老は、案内役であった伊治エミシに声をかけた。
「伊治の方々も、お役目ご苦労でしたな。そちらの方は、名はなんと
申すのじゃ」
「は。アザマロともうします」
「お若いようじゃの。はははは・・・」
伊治公呰麻呂と胆沢のエミシとの運命的な出会いであった。アザマロは、伊治城建設プロジェクトの現地側のリーダーに内定していた。外交役としての自己紹介を兼ねて胆沢へ訪れたのであった。
長期間の逗留が決定した後、アザマロは別の申し入れを行った。かねてからのあこがれであった資源の宝庫、カネイシへの入り口へ来たのである。長老にその旨をつたえ、カネイシへの道の案内役を懇願した。そこで紹介されたのが、アテルイであった。
アテルイ物語9 イシカ・メノコ(地の女神)
若い女がいた。女は、自分がロウイというような名前で呼ばれていたことを思い出していた。母親の口が、そのパターンで動くときは、自分を呼んでいることを意味していた。
女は幼い頃から母親の顔ばかりみていた。顔のわずかな変化から、感情を読みとるようになった。世の中の知識は、口の動きだけで理解し、生活に不自由しなくなった。しかし、母が高齢出産で亡くなった8年前、このろうあ女は、村から追われて、現在の遠野市、サロベの山に住みついた。
ひとりで歩く山は恐ろしいところだった。少女の頃はならず者に幾度か襲われた。しかし男というものは、自分のものにしたいために、いろいろ必要品をくれる、という知恵を身につけた。サロベにたどり着き、山女の世界に入り、いろいろな掟を知った。このような女は密集して住み、皆、助け合っていた。だから、とりわけ不幸だと思ったことはない。里の女のように「出産機械」として生きることが嫌いな女もおり、自らの意志で山に住む者もいた。都から逃れてきた者もいた。漂流してきた者もいた。こういう女が何人かまとまると、様々な知恵も得、生活には不便はないのである。
山女の知恵の代表は薬学であろう。あらゆる疾病用の生薬や、また堕胎ができると信じられている岩石薬が研究されていた。どうしようもなく苦しい時やいさかいの特効薬である毒薬も使いこなした。今日でいう麻薬もあった。果実酒等の醸造や食品保存の技術もあった。西洋風にいえば、怪しげな薬を扱う魔女集団、というところか。彼女らは、鬼女と呼ばれた。
川から水を汲み上げて運んでいたその女は、うかつなことに、背後から肩をたたかれた。
耳が聞こえないので、常にまわりに注意を払い、人や獣の存在を察知できたはずの自信が足もとをすくい、恐怖のあまり腰をぺたんと落としてしまった。降り始めの浅い雪の上に座り込み、その腰の周りにはこぼれた桶の水がしみ込んだ。血の気が失せ、山女にしては珍しく白い顔が、さらに蒼白になった。
「はっはっは・・オレだよ、オレ」
アテルイが毛皮をまとい、知らない男と並んで立っている。
「さすがのお前も、たまには察知能力が衰えるのか?」
女は立ち上がりざま、右手につかんだ雪を、男に投げつけた。言葉にならないうなり声を聞いて、隣に立っていた男、アザマロは、この女の生い立ちや境遇をすべて察した。
愛しいアテルイ。女が抱きつく。アテルイはいつものように、肩を抱き、後ろに結わえた長い髪をなであげた。この男が自分のねぐらを、月に1度くらい訪れるようになって、もう4年になる。
「この女がホウニだ。この道沿いの部族連中に人気がある。覚えて
おいてくれ」
「おう、美形じゃないか」
「ホウニが、北のアラバキからせしめた獲物が、さっき話した刀さ。
オレが5年前、ここに来たときは、こいつの世話役が持っていた。
ほら、あそこさ」
小さな竪穴住居や洞窟の見える群落が、まばらな仮設キャンプ場のように川沿いに見えた。山道越えの旅館の代わりをはたす場であるが、世間から隔離された山女、山婆(やまんば)の世界である。現在のように宿泊客の安全の保障は皆無であり、殺人強盗の何が起こっても不思議のない区域である。
アテルイとアザマロは馬を引きながら、ホウニの小屋へと向かう。父サイヒは田夷長の身分だったが、アテルイは今でいえば、資産家の町長クラスの跡取り息子である。アテルイおぼっちゃまが来たことを知った山女どもがたちまち駆け寄り、おみやげねだりの笑顔を送る。
アテルイは、ひとりの老婆を呼んで、馬の鞍から、乾飯と塩をおろし、宿代として振る舞った。これらの約3割はホウニの権利であることを確認させた。ひとりの女だけに貢ぐと仲間から毒を盛られ、客も無事ではすまない。他の小屋にも何人か客が来ていた。ひょっとして弟のムネトか、と思ったが、馬がいないので近くのタタラ職人どもであろう。そんなことを考えながら、老婆には長旅用の馬を監督することを依頼した。
山の冬の夜は寒い。ホウニの小屋の前で、毛皮を羽織った若い女を三人、浅雪の中に並ばせた。アテルイはアザマロに目配せし、アザマロはひとりの手をとり引き寄せた。ふとん代わりである。あとの者は、ホウニの小屋に食物や酒を運び込んだ。女どもは、水洗いした体を熱くするするために、すでに薬を飲んでいた。
ホウニは、食事の準備をしながら、アテルイの口の動きを見ていた。
さっきから刀の話をしている。弟と来たときもそうだったが、男どもはなぜそんなに武器が好きなのか、理解できなかった。今日の男は、見慣れない入れ墨をしている。アテルイの口の動きから、ア・ザ・・・アザマロという名前であることを知った。
「実はオレも、ドウバ採掘場を見たことがないのだ。冶金作業がだ
いぶ楽な石なのだが」
アテルイが、アザマロの質問に答えていた。
「オレの聞いた話では、胆沢の北、ワガと、東海岸のカネイシにある
とのことだ。今回はぜひカネイシに行きたい。長年の夢だった」
「東海岸なら願ってもない。オレの母や祖父が生まれたところだ。
それにこの方面のアラバキなら、ほとんど知っている」
アテルイは、この山女キャンプ地に3日間滞在し、付近のたたら部落や、知人のアラハバキを紹介することを告げた。
「ありがたい。恩に着るよ」
アザマロは、だいぶ酸っぱいが、美酒に酔い始めながら、こんなに順調に願いがかなう自分の幸運さを喜んだ。この酒は、ヒタカミの山女どもが、ぶどうや木の実を口に含んで、発酵貯蔵したものだろう。
山の夜は、冷え込みが厳しい。いつしか雪が降り始めていた。酒にほてったアテルイを、老婆が調達した柔らかい乾し藁布団の中にもぐらせ、ホウニは久しぶりの幸せを満喫し感激にひたっていた。このまま朝がこなければいい、と、ホウニはアテルイの腕の中でまどろんでいた。
若い女がいた。女は、自分がロウイというような名前で呼ばれていたことを思い出していた。母親の口が、そのパターンで動くときは、自分を呼んでいることを意味していた。
女は幼い頃から母親の顔ばかりみていた。顔のわずかな変化から、感情を読みとるようになった。世の中の知識は、口の動きだけで理解し、生活に不自由しなくなった。しかし、母が高齢出産で亡くなった8年前、このろうあ女は、村から追われて、現在の遠野市、サロベの山に住みついた。
ひとりで歩く山は恐ろしいところだった。少女の頃はならず者に幾度か襲われた。しかし男というものは、自分のものにしたいために、いろいろ必要品をくれる、という知恵を身につけた。サロベにたどり着き、山女の世界に入り、いろいろな掟を知った。このような女は密集して住み、皆、助け合っていた。だから、とりわけ不幸だと思ったことはない。里の女のように「出産機械」として生きることが嫌いな女もおり、自らの意志で山に住む者もいた。都から逃れてきた者もいた。漂流してきた者もいた。こういう女が何人かまとまると、様々な知恵も得、生活には不便はないのである。
山女の知恵の代表は薬学であろう。あらゆる疾病用の生薬や、また堕胎ができると信じられている岩石薬が研究されていた。どうしようもなく苦しい時やいさかいの特効薬である毒薬も使いこなした。今日でいう麻薬もあった。果実酒等の醸造や食品保存の技術もあった。西洋風にいえば、怪しげな薬を扱う魔女集団、というところか。彼女らは、鬼女と呼ばれた。
川から水を汲み上げて運んでいたその女は、うかつなことに、背後から肩をたたかれた。
耳が聞こえないので、常にまわりに注意を払い、人や獣の存在を察知できたはずの自信が足もとをすくい、恐怖のあまり腰をぺたんと落としてしまった。降り始めの浅い雪の上に座り込み、その腰の周りにはこぼれた桶の水がしみ込んだ。血の気が失せ、山女にしては珍しく白い顔が、さらに蒼白になった。
「はっはっは・・オレだよ、オレ」
アテルイが毛皮をまとい、知らない男と並んで立っている。
「さすがのお前も、たまには察知能力が衰えるのか?」
女は立ち上がりざま、右手につかんだ雪を、男に投げつけた。言葉にならないうなり声を聞いて、隣に立っていた男、アザマロは、この女の生い立ちや境遇をすべて察した。
愛しいアテルイ。女が抱きつく。アテルイはいつものように、肩を抱き、後ろに結わえた長い髪をなであげた。この男が自分のねぐらを、月に1度くらい訪れるようになって、もう4年になる。
「この女がホウニだ。この道沿いの部族連中に人気がある。覚えて
おいてくれ」
「おう、美形じゃないか」
「ホウニが、北のアラバキからせしめた獲物が、さっき話した刀さ。
オレが5年前、ここに来たときは、こいつの世話役が持っていた。
ほら、あそこさ」
小さな竪穴住居や洞窟の見える群落が、まばらな仮設キャンプ場のように川沿いに見えた。山道越えの旅館の代わりをはたす場であるが、世間から隔離された山女、山婆(やまんば)の世界である。現在のように宿泊客の安全の保障は皆無であり、殺人強盗の何が起こっても不思議のない区域である。
アテルイとアザマロは馬を引きながら、ホウニの小屋へと向かう。父サイヒは田夷長の身分だったが、アテルイは今でいえば、資産家の町長クラスの跡取り息子である。アテルイおぼっちゃまが来たことを知った山女どもがたちまち駆け寄り、おみやげねだりの笑顔を送る。
アテルイは、ひとりの老婆を呼んで、馬の鞍から、乾飯と塩をおろし、宿代として振る舞った。これらの約3割はホウニの権利であることを確認させた。ひとりの女だけに貢ぐと仲間から毒を盛られ、客も無事ではすまない。他の小屋にも何人か客が来ていた。ひょっとして弟のムネトか、と思ったが、馬がいないので近くのタタラ職人どもであろう。そんなことを考えながら、老婆には長旅用の馬を監督することを依頼した。
山の冬の夜は寒い。ホウニの小屋の前で、毛皮を羽織った若い女を三人、浅雪の中に並ばせた。アテルイはアザマロに目配せし、アザマロはひとりの手をとり引き寄せた。ふとん代わりである。あとの者は、ホウニの小屋に食物や酒を運び込んだ。女どもは、水洗いした体を熱くするするために、すでに薬を飲んでいた。
ホウニは、食事の準備をしながら、アテルイの口の動きを見ていた。
さっきから刀の話をしている。弟と来たときもそうだったが、男どもはなぜそんなに武器が好きなのか、理解できなかった。今日の男は、見慣れない入れ墨をしている。アテルイの口の動きから、ア・ザ・・・アザマロという名前であることを知った。
「実はオレも、ドウバ採掘場を見たことがないのだ。冶金作業がだ
いぶ楽な石なのだが」
アテルイが、アザマロの質問に答えていた。
「オレの聞いた話では、胆沢の北、ワガと、東海岸のカネイシにある
とのことだ。今回はぜひカネイシに行きたい。長年の夢だった」
「東海岸なら願ってもない。オレの母や祖父が生まれたところだ。
それにこの方面のアラバキなら、ほとんど知っている」
アテルイは、この山女キャンプ地に3日間滞在し、付近のたたら部落や、知人のアラハバキを紹介することを告げた。
「ありがたい。恩に着るよ」
アザマロは、だいぶ酸っぱいが、美酒に酔い始めながら、こんなに順調に願いがかなう自分の幸運さを喜んだ。この酒は、ヒタカミの山女どもが、ぶどうや木の実を口に含んで、発酵貯蔵したものだろう。
山の夜は、冷え込みが厳しい。いつしか雪が降り始めていた。酒にほてったアテルイを、老婆が調達した柔らかい乾し藁布団の中にもぐらせ、ホウニは久しぶりの幸せを満喫し感激にひたっていた。このまま朝がこなければいい、と、ホウニはアテルイの腕の中でまどろんでいた。
アテルイ物語10 寒流のまろうど
カネイシの道に入った頃は雪が多かった。その雪も、急に少なくなってきた。海岸が近くにせまっていることを、アザマロは推測した。
雪の深い峠には、小柄な松木が立ち並び、幾筋もの山道がつけられていた。
川沿いの細い道を抜け、松材を高く積み上げていた地区を通り、海がやっと見える場所にでると、眼下には密集した竪穴集落が広がっていた。集落の中央には高楼の館がみえた。カネイシの地である。
馬で向かうアテルイの進路をふさぐように、駆けつけた5人の若者が取り囲んだ。武器を携えた警備の者であった。しかし長老の孫、アテルイであることがわかると、若者は先導して、中央にあった高楼の館へ案内された。
「アテルイか。しばらくだのぉ」
長老が歓迎の宴を準備した。同行していたアザマロも、伊治からの土産を献上し、宿泊の恩義に謝意を述べた。
「ウクハウは、どうしておりますか?」
アテルイが訪ねた。こういう場面で真っ先に駆けつけてくるはずの長老の息子、年齢のあまり違わない叔父、ウクハウの姿がない。
「おお、そうじゃったな。
ウクハウは、いま海じゃよ。都に向かっておる」
「すると・・
道嶋殿に呼び出されたのですね。よかったですね」
「ほっほっほ。よかったかどうかはしらんがな。
なにしろ桃生柵が近くにできてしまったからのぉ。つきあいじゃ」
宮城県北の桃生(ものう、現石巻市)の柵は、付近に住む海道エミシの管理のために作られた。
奈良平城京のエリート官僚となった道嶋(牡鹿連)嶋足は、この地の出身であった。
道嶋嶋足は、藤原仲麻呂時代にはそれほどぱっとしなかったが、孝謙改め称徳女帝になってからは、恵美押勝の乱の功労者である道嶋嶋足を重用した。この経緯で、桃生付近の海道沿いの実力者が都に呼び集められていた。カネイシのウクハウも、その招聘された一人であった。
この頃のアテルイは、中央官庁の登用が、父サイヒの期待に応える出世の道である、と信じていた。だから、親戚で友人である宇漢迷公宇屈波宇(ウカメノキミウクハウ)が一歩先んじたことに、少し嫉妬を感じていた。
しかしカネイシの長老は、その進路に迷いがあり、疑心暗鬼の様子であった。
「そうじゃそうじゃ、アテルイ、いいところにきた。お客がきている。
会ってくれまいか」
「お客」というのは、カネイシの地では外国人のことである。
長老が合図すると、侍女がどこかえ消えた。アテルイは、アザマロを長老に紹介し、伊治の話で盛り上がっていた。その最中に、奇異な格好をした5人が現れた。靺鞨国(まっかつ)の者のようだ。
「もう10日ぐらいの滞在になったか。わしはもう、言葉がようわか
らなくてのぉ」
そうか、ウクハウがいないんだった。他の連中も、どこかに出かけたな、とアテルイは考えた。
アテルイやウクハウのような、部族の跡取り候補は、幼い頃から徹底した教育をうけた。読み書き、そろばん(当時は九九算板)そして兵法などである。アテルイは、少しだけだったが渤海などの異国の言葉も話すことができた。いわゆる「山女との交流」の成果である。
本来なら、部族あげて投資したこのような頭脳人材は、外部に出すものではない。
蝦夷地広しといえども、現実に教育をうけられる若者は、数少なかったからである。道嶋嶋足に、ぜひにと願われて、ウクハウを朝廷に遣わしたカネイシの長老の悩みと迷いは、ここにあった。
さて、靺鞨(まっかつ)国の客人は、わずかに母国語で話しかける若者に、まずは感激し、早口で何かまくしたてた。アテルイは笑顔のままでじっと聞き、ゆっくり話すようにさとした。
ツガル(十三湊)にいったん停泊したこと、海峡を越えて陸地づたいに海流にのってここまで来たこと、すでに10人ほどの男女が死に、別れてきたこと・・・この厳寒の海を、よくぞ耐えて、カネイシまで来たものである。
アザマロにとっては、異国の人間を見るのは初めてである。律令では、異国の客人は政府の厳重な監視下におかれる。しかし奥蝦夷の地のカネイシは、胆沢と同様に、一種の独立国家になっており、朝廷と同様の客人の監視を、独自に行っていた。アザマロはその外交現場にいきなり参加した気分であった。話がすすみ、打ち解けた頃を見計らって、アザマロは、
「彼らは、漂流して、ここへたどり着いたのか」
と、アテルイに伺った。アテルイは微笑んで、
「いや、商売ですよ」
と答えた。
アザマロは、この1ヶ月間、普通なら部外者立入厳禁であるはずのアラハバキのタタラ部落へアテルイが平気で入っていくことを、不思議な気持ちでみていた。アザマロの常識では、こうしたことができるのは、この業界関係の者か、鉱石資源の所有者、また特殊技術を有している者などである。アザマロは伊治のタタラ長である。いつでも彼らと取引きできる背景がある、と自負していた。しかし単なる田夷のせがれのアテルイが、なぜこんなに間単に出入りできるのか?という疑問を、ずっと持っていた。アザマロは推測した。アテルイの秘密は異国との交易情報か?
アテルイは、異国人ひとりひとりの名前や年齢を聞き、紙に書き留めた。客人のひとりが合図すると、後ろに控えていた若い者が進み出て、胸の中からなにか紙みたいなものを取り出した。ここに自分たちを連れていってほしい、との願いであった。そこにカネイシ王へのみやげがある、と述べた。おそらく蜂蜜か、毛皮であろう、とアテルイは想像し、長老に説明した。客人は、夏になったら帰るが、それまでの宿泊や外出許可の依頼を長老に願い出た。長老はうなずき、共に宴に加わるように勧めた。慣れない席で、アザマロも宴に参加した。
カネイシに来てもう3日目である。アザマロはカネイシの道で過ごした3ヶ月間を思い出していた。そろそろ胆沢に逗留中の道嶋三山や真麻呂らと帰り支度をする時期である。あこがれのカネイシの地に着いて、いろいろ歩き回ったが、製鉄、冶金関連の施設が少ない現実に驚いていた。
「ドウバは、ここに豊富にある、と聞いたのだが。」
風が冷たい真冬のカネイシの海岸を歩きながら、アザマロはアテルイに問いかけた。アテルイは笑って、あるある。ここではないが、と、答えた。
露天ドウバは、実はすでに大量に掘り尽くされていた。歩いて見つかるようなものではない。それは今のカネイシの村ができるずっと以前の話である。アテルイはそう説明した。どうりでカネイシは普通の村である。人の噂は、アテにならないな、とアザマロは考えたが、そんな様子をみてアテルイは、
「ドウバは、いまは、かんな(鉄穴)堀りだ。ここもそうだが、ここ
から北方面の海岸線沿いが、すべてドウバで埋め尽くされている、
と聞いている」
「しかし煙が・・・」
タタラの煙が見えない、と言いたいのだろう?アテルイは、アザマロには笑顔を返しただけで、何も言わなかった。これはトップシークレットである。
不良な砂鉄ばかり扱う近江や畿内はじめ、伊治などの全国の製鉄業連中には信じられない光景であろう。ヒタカミのドウバの精錬作業には、それほど燃料はいらないし、時間もかからないのだ。せいぜいアラハバキの小さなキャンプがかすむ程度である。
3年前に道嶋達が、渤海の刀剣の素材確認をするために、カネイシに調査に来たときにも、道嶋嶋足は同じことを言っていた。ドウバはもはや枯渇し、この地では鉄素材の産出は難しい、と。ウクハウはとぼけて説明したようだが、たしかに一見、カネイシの近辺はそのように見える。道嶋や、アザマロ達にとっては、琵琶湖上空を曇らすような光景が、活気のある鉄製産地の常識だからだ。
実はヒタカミ山中から、ツガル、そして出羽のアラハバキ連中は、こうした事情を知らずに作業していた。逆に、アテルイやウクハウらは、この地の鉄生産品の対外的な競争力があることを見抜いていた。つまり、素材といい、燃料調達条件といい、労少なく品質のよいものを作れる環境条件だったのである。それはちょうど、日本工業生産品が、本来なら莫大な金を払って買う水や資材を、自然の恵みで、タダ同然に使っているような状況に似ている。
この事情をよく知っていたのが「客人」たちであった。時には厳寒の寒流の中を、命を賭して交易に来た。たまたまカネイシにはまっかつ国の商人が訪れていたが、このことは、新羅や唐と敵対関係にあった渤海国が、十三湊を通じヒタカミの地と秘密裏にすすめていた交易事業であった。
カネイシの道に入った頃は雪が多かった。その雪も、急に少なくなってきた。海岸が近くにせまっていることを、アザマロは推測した。
雪の深い峠には、小柄な松木が立ち並び、幾筋もの山道がつけられていた。
川沿いの細い道を抜け、松材を高く積み上げていた地区を通り、海がやっと見える場所にでると、眼下には密集した竪穴集落が広がっていた。集落の中央には高楼の館がみえた。カネイシの地である。
馬で向かうアテルイの進路をふさぐように、駆けつけた5人の若者が取り囲んだ。武器を携えた警備の者であった。しかし長老の孫、アテルイであることがわかると、若者は先導して、中央にあった高楼の館へ案内された。
「アテルイか。しばらくだのぉ」
長老が歓迎の宴を準備した。同行していたアザマロも、伊治からの土産を献上し、宿泊の恩義に謝意を述べた。
「ウクハウは、どうしておりますか?」
アテルイが訪ねた。こういう場面で真っ先に駆けつけてくるはずの長老の息子、年齢のあまり違わない叔父、ウクハウの姿がない。
「おお、そうじゃったな。
ウクハウは、いま海じゃよ。都に向かっておる」
「すると・・
道嶋殿に呼び出されたのですね。よかったですね」
「ほっほっほ。よかったかどうかはしらんがな。
なにしろ桃生柵が近くにできてしまったからのぉ。つきあいじゃ」
宮城県北の桃生(ものう、現石巻市)の柵は、付近に住む海道エミシの管理のために作られた。
奈良平城京のエリート官僚となった道嶋(牡鹿連)嶋足は、この地の出身であった。
道嶋嶋足は、藤原仲麻呂時代にはそれほどぱっとしなかったが、孝謙改め称徳女帝になってからは、恵美押勝の乱の功労者である道嶋嶋足を重用した。この経緯で、桃生付近の海道沿いの実力者が都に呼び集められていた。カネイシのウクハウも、その招聘された一人であった。
この頃のアテルイは、中央官庁の登用が、父サイヒの期待に応える出世の道である、と信じていた。だから、親戚で友人である宇漢迷公宇屈波宇(ウカメノキミウクハウ)が一歩先んじたことに、少し嫉妬を感じていた。
しかしカネイシの長老は、その進路に迷いがあり、疑心暗鬼の様子であった。
「そうじゃそうじゃ、アテルイ、いいところにきた。お客がきている。
会ってくれまいか」
「お客」というのは、カネイシの地では外国人のことである。
長老が合図すると、侍女がどこかえ消えた。アテルイは、アザマロを長老に紹介し、伊治の話で盛り上がっていた。その最中に、奇異な格好をした5人が現れた。靺鞨国(まっかつ)の者のようだ。
「もう10日ぐらいの滞在になったか。わしはもう、言葉がようわか
らなくてのぉ」
そうか、ウクハウがいないんだった。他の連中も、どこかに出かけたな、とアテルイは考えた。
アテルイやウクハウのような、部族の跡取り候補は、幼い頃から徹底した教育をうけた。読み書き、そろばん(当時は九九算板)そして兵法などである。アテルイは、少しだけだったが渤海などの異国の言葉も話すことができた。いわゆる「山女との交流」の成果である。
本来なら、部族あげて投資したこのような頭脳人材は、外部に出すものではない。
蝦夷地広しといえども、現実に教育をうけられる若者は、数少なかったからである。道嶋嶋足に、ぜひにと願われて、ウクハウを朝廷に遣わしたカネイシの長老の悩みと迷いは、ここにあった。
さて、靺鞨(まっかつ)国の客人は、わずかに母国語で話しかける若者に、まずは感激し、早口で何かまくしたてた。アテルイは笑顔のままでじっと聞き、ゆっくり話すようにさとした。
ツガル(十三湊)にいったん停泊したこと、海峡を越えて陸地づたいに海流にのってここまで来たこと、すでに10人ほどの男女が死に、別れてきたこと・・・この厳寒の海を、よくぞ耐えて、カネイシまで来たものである。
アザマロにとっては、異国の人間を見るのは初めてである。律令では、異国の客人は政府の厳重な監視下におかれる。しかし奥蝦夷の地のカネイシは、胆沢と同様に、一種の独立国家になっており、朝廷と同様の客人の監視を、独自に行っていた。アザマロはその外交現場にいきなり参加した気分であった。話がすすみ、打ち解けた頃を見計らって、アザマロは、
「彼らは、漂流して、ここへたどり着いたのか」
と、アテルイに伺った。アテルイは微笑んで、
「いや、商売ですよ」
と答えた。
アザマロは、この1ヶ月間、普通なら部外者立入厳禁であるはずのアラハバキのタタラ部落へアテルイが平気で入っていくことを、不思議な気持ちでみていた。アザマロの常識では、こうしたことができるのは、この業界関係の者か、鉱石資源の所有者、また特殊技術を有している者などである。アザマロは伊治のタタラ長である。いつでも彼らと取引きできる背景がある、と自負していた。しかし単なる田夷のせがれのアテルイが、なぜこんなに間単に出入りできるのか?という疑問を、ずっと持っていた。アザマロは推測した。アテルイの秘密は異国との交易情報か?
アテルイは、異国人ひとりひとりの名前や年齢を聞き、紙に書き留めた。客人のひとりが合図すると、後ろに控えていた若い者が進み出て、胸の中からなにか紙みたいなものを取り出した。ここに自分たちを連れていってほしい、との願いであった。そこにカネイシ王へのみやげがある、と述べた。おそらく蜂蜜か、毛皮であろう、とアテルイは想像し、長老に説明した。客人は、夏になったら帰るが、それまでの宿泊や外出許可の依頼を長老に願い出た。長老はうなずき、共に宴に加わるように勧めた。慣れない席で、アザマロも宴に参加した。
カネイシに来てもう3日目である。アザマロはカネイシの道で過ごした3ヶ月間を思い出していた。そろそろ胆沢に逗留中の道嶋三山や真麻呂らと帰り支度をする時期である。あこがれのカネイシの地に着いて、いろいろ歩き回ったが、製鉄、冶金関連の施設が少ない現実に驚いていた。
「ドウバは、ここに豊富にある、と聞いたのだが。」
風が冷たい真冬のカネイシの海岸を歩きながら、アザマロはアテルイに問いかけた。アテルイは笑って、あるある。ここではないが、と、答えた。
露天ドウバは、実はすでに大量に掘り尽くされていた。歩いて見つかるようなものではない。それは今のカネイシの村ができるずっと以前の話である。アテルイはそう説明した。どうりでカネイシは普通の村である。人の噂は、アテにならないな、とアザマロは考えたが、そんな様子をみてアテルイは、
「ドウバは、いまは、かんな(鉄穴)堀りだ。ここもそうだが、ここ
から北方面の海岸線沿いが、すべてドウバで埋め尽くされている、
と聞いている」
「しかし煙が・・・」
タタラの煙が見えない、と言いたいのだろう?アテルイは、アザマロには笑顔を返しただけで、何も言わなかった。これはトップシークレットである。
不良な砂鉄ばかり扱う近江や畿内はじめ、伊治などの全国の製鉄業連中には信じられない光景であろう。ヒタカミのドウバの精錬作業には、それほど燃料はいらないし、時間もかからないのだ。せいぜいアラハバキの小さなキャンプがかすむ程度である。
3年前に道嶋達が、渤海の刀剣の素材確認をするために、カネイシに調査に来たときにも、道嶋嶋足は同じことを言っていた。ドウバはもはや枯渇し、この地では鉄素材の産出は難しい、と。ウクハウはとぼけて説明したようだが、たしかに一見、カネイシの近辺はそのように見える。道嶋や、アザマロ達にとっては、琵琶湖上空を曇らすような光景が、活気のある鉄製産地の常識だからだ。
実はヒタカミ山中から、ツガル、そして出羽のアラハバキ連中は、こうした事情を知らずに作業していた。逆に、アテルイやウクハウらは、この地の鉄生産品の対外的な競争力があることを見抜いていた。つまり、素材といい、燃料調達条件といい、労少なく品質のよいものを作れる環境条件だったのである。それはちょうど、日本工業生産品が、本来なら莫大な金を払って買う水や資材を、自然の恵みで、タダ同然に使っているような状況に似ている。
この事情をよく知っていたのが「客人」たちであった。時には厳寒の寒流の中を、命を賭して交易に来た。たまたまカネイシにはまっかつ国の商人が訪れていたが、このことは、新羅や唐と敵対関係にあった渤海国が、十三湊を通じヒタカミの地と秘密裏にすすめていた交易事業であった。
アテルイ物語11 道嶋(牡鹿)嶋足
「無垢浄光陀羅尼、六度、相輪、罪障消滅、か・・・」
経蔵の薄暗い床に夥しく並べた檜製のモニュメント、七重の塔(一万節塔)を見守る背の高い男がいた。塔内部に日本では初めての墨印刷した紙、陀羅尼(だらに)経紙を封入し、塔の底には内裏の字が書き示されていた。これは親王への贈答品であることを示す。
道鏡大臣禅師の示唆で、天平神護と年号を変えた年の夏、奈良東大寺の西塔は、セミしぐれの中にあった。
塔の中は、真夏なのに意外と涼しい。男は陀羅尼経の紙片を手に取り、低い声で読んでいた。
霊験がますます高まってきた称徳天皇(前孝謙女帝)は、仏師に命じ、祈祷用の七重塔を試作させた。この年の暮れには、そのミニチュア版の三重塔の製造計画が出された。約30cm程度のその檜製の塔は、実際に畿内の寺に配布した個数にちなみ、百万塔と呼ばれた。完成した百万塔が真夏の西塔に所狭しと並べられていた。
この百万塔は、怨霊退散の祈願のために製造された。称徳女帝の親族であった恵美押勝、すなわち藤原仲麻呂一族を根絶やしにし、悪霊を恐れたアポロジャイズ施策のひとつであった。男はおびただしい数の百万塔を眺めまわし、怪しげな呪術の時代の幕開けを感じていた。
「道嶋殿、こちらにいらっしゃいますか」
西塔の真言院側の東入り口から声を掛けられて、真昼のまぶしく見える戸口に真っ黒な烏帽子姿のシルエットを見た。シルエットは中にすすみ、座して深々と礼を始めた。
「宇漢迷(うかめ。ウクハウ)か。
帝が、御出立か」
「はは。ただいま、工事検分終了した東塔から、弓削殿が参られます。
共に中門まで参りましょう、とのことです。
御支度を」
称徳女帝は父聖武の権威の象徴である東大寺にしばしば訪れるのが習わしになっていた。自らも出家し、尼寺である法華寺に足しげく通い、仏の世界にひたっていた。本日は、東大寺法華堂に新たに加わった四天王像を見に来たのである。
授刀府を廃止し、今年から新しく発足した近衛府の少将道嶋嶋足(みちしまのしまたり)、官名、牡鹿宿弥嶋足従四位相模守は、帝自身の要望により、いつも警護にあたっていた。30歳の半ばの、細面の柔和な顔立ちからは、恵美押勝の乱で仲麻呂の息子、藤原訓儒麻呂(くずまろ)の胸板を矢で射抜いたことなど、とても想像できなかった。
「牡鹿相模守殿、お待たせしましたな。内裏に戻りますので、よろし
くお供を願いたいのですが。」
従四位上弓削宿称浄人(ゆげのすくねきよと)が現れた。
彼は大臣禅師道鏡の弟で、道鏡の出身地河内者の中の出世頭である。従四位の地位は、嶋足と同じ位階である。
なお、四位とは、政界の特定分野のナンバー4の高級官僚で、嶋足の立場、近衛府授刀少将は、現在でいえば防衛庁次官である。道嶋はもともと牡鹿郡司(仙台付近)の七位であった。地方出身者は普通、よくても六位どまりであったが、嶋足のように四位まで出世することは、よほどの功績に恵まれたためで、大変珍しい。
この事情は、弓削浄人も同様であった。浄人は道鏡の補佐係である。政界の中で道鏡に不満をもつ者を摘発する係であり、特高警察を想像すればよい。つい先日も、道鏡の示唆により参議の粟田道麻呂や石川永年など何人かの有力者を自殺に追い込んだ。都では、いよいよ始まったか、という空気が流れた。百万塔の中で嶋足が背筋に感じた呪術による恐怖政治は、この後6年間続くのであった。、
弓削浄人は渡来貴族の出身ではない。このため、似たルーツや経歴をもっていた嶋足に気安く語りかけてきた。しかしこの好き嫌いの激しい男が、ささいな言葉じりをとらえて、罪人を何人もでっちあげたことを、嶋足は聞いており、用心に怠りはなかった。浄人は嶋足を褒めた。
「牡鹿殿は、いつもあざやかですなぁ。隙がなく、すばやい」
警護体制のことか、と、嶋足は考えた。約1km四方の東大寺境内すべての方面に、ウクハウ達が瞬時に、隙なく、しかも目立たずに衛兵を配備させている。浄人はどこを見てきたかしらないが、白蛇川沿いの彫像のように不動のまま立ち並ぶ選抜、訓練されたエミシの衛兵のことを言っているのだろう。
「はは、帝の御警護は、過ぎることはありませんので」
「はっははは、あいかわらず控えめですなぁ」
華やかに飾った牛車が、衛兵の見守る中、南大門から境内へ引き入れた。鏡池から手向山へ近衛兵が列をなして立ち並ぶ中、最初に近衛府大将藤原蔵下麻呂、次に頭から白い絹布を覆った袈裟姿の称徳天皇が歩いてきた。すぐ後ろには、女衛兵の正五位吉備朝臣由利(きびのあそんゆり)、そして、由利とほとんど並ぶかのように、もはや誰にもはばかることなく、これも袈裟姿の大臣禅師、道鏡が付き従っていた。
しかし嶋足にとっては、称徳天皇がすべてである。道鏡すら警護の対象である。中門でひざまずき、顔は正面に向けたまま、道鏡を含め各人の行動に注意を払っていた。帝に近づく者は、嶋足のひと声で近衛兵が反射的に迎撃態勢に入る。嶋足と由利は、帝の名においてその場で処刑できる強力な権限を有していた。いったん牛車が動き出すと、嶋足や由利の近衛府の責任者しか、車の脇に立つことを許されていない。
嶋足は、太政官道鏡すら信用しない女帝が、自分を頼りにしていることを十分承知していた。またその信頼感に一度も背いたことはなかった。道鏡が女帝の寝室で看護祈祷しているそばでも、由利や嶋足など近衛府の影が常にあった。警備の実務は、ウクハウなどの信頼できる、実直で有能な人材起用にも依っている。浄人が褒めるように、スキがなく素早いのは当然である。
帝の道中は短いものだった。貴族どもがこそこそおしゃべりしている中で、道ばたの石を寄せたり、市内の斥候など、周囲の警護を行うのは、ほとんどはエミシ出身者の仕事であった。彼らは疲れを知らず機敏に動き、朱雀門を通過するまでは、いちいち嶋足へ報告に来た。ウクハウもそのひとりであった。
警護の1日が終わった。ウクハウらは、嶋足宅へ慰労の宴に招かれていた。夕食を共にしながら、ウクハウは嶋足に問いかけた。
「秋には、帝は紀伊や河内に行幸されると伺いましたが」
嶋足は、出世した道鏡を故郷で錦を飾らせるイベントが今年中にある、と聞いていた。ウクハウは、その日程が迫っているので、嶋足がどうするか、と話を切り出したのである。
嶋足は、すでに行宮(あんぐう。旅行中の宿泊場所)を造営していることを右大臣藤原豊成(とよなり)から聞いていた。実弟の仲麻呂に追放された豊成にとって、道鏡は政界に返り咲きさせてもらった恩人である。この60歳に近い無能な右大臣豊成は、藤原嫡系のプライドも忘れ、道鏡賛美のイベントに全面協力しようとしていた。嶋足の脳裏に、弓削浄人の油断ならない顔がよぎった。
「今回は、辞退しようか、と考えているが・・・」
嶋足は、エミシを好意的に取り立ててくれる称徳天皇に命を懸ける覚悟はあった。しかし、結果的に道鏡を警護することになるイベントは、好まなかった。辞退の返事に、顔をしかめてウクハウは言った。
「では、百済王殿が、困るのではないでしょうか」
道嶋が断ると、百済王敬福がその役を負うことになる。百済王敬福は、やはり牡鹿出身で、嶋足らを抜擢した上司(従三位)である。この当時は65才の老齢になっており、大がかりな行事は辛いはずである。実際、百済王敬福はこの任務を最後に、亡くなった。
「百済王殿には、私から話をしておく。ウクハウは、わしと共に都に
いてもらいたい。河内への警護は、さらに故郷から人を呼んだらど
うか、と考えているのだが」
嶋足から、支援のための陸奥国エミシの衛士(えじ)徴集の計画を思いつくまま述べてみよ、と言われ、ウクハウはアテルイの顔を真っ先に思い浮かべた。しかし、口から出た言葉は、百済王の出身地を考慮して桃生や玉造の海道地域のエミシ、さらに鹿島、上総、上野のエミシの徴集案を述べた。嶋足は、部下のオーソドックスな計画に、同感の微笑を浮かべて、じっと聞いていた。
ウクハウは、説明をしながら、都の立場でみたエミシの序列や差別のようなものが歴然として存在することを、自ら語る口で知った。序列付けすることが都の仕事なのか。これが律令国家というものか・・・
道嶋殿はあこがれの上司である。信頼してついて行きたい。しかし、何かが違う、と、ウクハウは考えはじめた。脳裏にアテルイの顔や、異国交易の夢を語り合ったことが浮び、俺は都の人間になったんだ、と、つぶやいた。
「無垢浄光陀羅尼、六度、相輪、罪障消滅、か・・・」
経蔵の薄暗い床に夥しく並べた檜製のモニュメント、七重の塔(一万節塔)を見守る背の高い男がいた。塔内部に日本では初めての墨印刷した紙、陀羅尼(だらに)経紙を封入し、塔の底には内裏の字が書き示されていた。これは親王への贈答品であることを示す。
道鏡大臣禅師の示唆で、天平神護と年号を変えた年の夏、奈良東大寺の西塔は、セミしぐれの中にあった。
塔の中は、真夏なのに意外と涼しい。男は陀羅尼経の紙片を手に取り、低い声で読んでいた。
霊験がますます高まってきた称徳天皇(前孝謙女帝)は、仏師に命じ、祈祷用の七重塔を試作させた。この年の暮れには、そのミニチュア版の三重塔の製造計画が出された。約30cm程度のその檜製の塔は、実際に畿内の寺に配布した個数にちなみ、百万塔と呼ばれた。完成した百万塔が真夏の西塔に所狭しと並べられていた。
この百万塔は、怨霊退散の祈願のために製造された。称徳女帝の親族であった恵美押勝、すなわち藤原仲麻呂一族を根絶やしにし、悪霊を恐れたアポロジャイズ施策のひとつであった。男はおびただしい数の百万塔を眺めまわし、怪しげな呪術の時代の幕開けを感じていた。
「道嶋殿、こちらにいらっしゃいますか」
西塔の真言院側の東入り口から声を掛けられて、真昼のまぶしく見える戸口に真っ黒な烏帽子姿のシルエットを見た。シルエットは中にすすみ、座して深々と礼を始めた。
「宇漢迷(うかめ。ウクハウ)か。
帝が、御出立か」
「はは。ただいま、工事検分終了した東塔から、弓削殿が参られます。
共に中門まで参りましょう、とのことです。
御支度を」
称徳女帝は父聖武の権威の象徴である東大寺にしばしば訪れるのが習わしになっていた。自らも出家し、尼寺である法華寺に足しげく通い、仏の世界にひたっていた。本日は、東大寺法華堂に新たに加わった四天王像を見に来たのである。
授刀府を廃止し、今年から新しく発足した近衛府の少将道嶋嶋足(みちしまのしまたり)、官名、牡鹿宿弥嶋足従四位相模守は、帝自身の要望により、いつも警護にあたっていた。30歳の半ばの、細面の柔和な顔立ちからは、恵美押勝の乱で仲麻呂の息子、藤原訓儒麻呂(くずまろ)の胸板を矢で射抜いたことなど、とても想像できなかった。
「牡鹿相模守殿、お待たせしましたな。内裏に戻りますので、よろし
くお供を願いたいのですが。」
従四位上弓削宿称浄人(ゆげのすくねきよと)が現れた。
彼は大臣禅師道鏡の弟で、道鏡の出身地河内者の中の出世頭である。従四位の地位は、嶋足と同じ位階である。
なお、四位とは、政界の特定分野のナンバー4の高級官僚で、嶋足の立場、近衛府授刀少将は、現在でいえば防衛庁次官である。道嶋はもともと牡鹿郡司(仙台付近)の七位であった。地方出身者は普通、よくても六位どまりであったが、嶋足のように四位まで出世することは、よほどの功績に恵まれたためで、大変珍しい。
この事情は、弓削浄人も同様であった。浄人は道鏡の補佐係である。政界の中で道鏡に不満をもつ者を摘発する係であり、特高警察を想像すればよい。つい先日も、道鏡の示唆により参議の粟田道麻呂や石川永年など何人かの有力者を自殺に追い込んだ。都では、いよいよ始まったか、という空気が流れた。百万塔の中で嶋足が背筋に感じた呪術による恐怖政治は、この後6年間続くのであった。、
弓削浄人は渡来貴族の出身ではない。このため、似たルーツや経歴をもっていた嶋足に気安く語りかけてきた。しかしこの好き嫌いの激しい男が、ささいな言葉じりをとらえて、罪人を何人もでっちあげたことを、嶋足は聞いており、用心に怠りはなかった。浄人は嶋足を褒めた。
「牡鹿殿は、いつもあざやかですなぁ。隙がなく、すばやい」
警護体制のことか、と、嶋足は考えた。約1km四方の東大寺境内すべての方面に、ウクハウ達が瞬時に、隙なく、しかも目立たずに衛兵を配備させている。浄人はどこを見てきたかしらないが、白蛇川沿いの彫像のように不動のまま立ち並ぶ選抜、訓練されたエミシの衛兵のことを言っているのだろう。
「はは、帝の御警護は、過ぎることはありませんので」
「はっははは、あいかわらず控えめですなぁ」
華やかに飾った牛車が、衛兵の見守る中、南大門から境内へ引き入れた。鏡池から手向山へ近衛兵が列をなして立ち並ぶ中、最初に近衛府大将藤原蔵下麻呂、次に頭から白い絹布を覆った袈裟姿の称徳天皇が歩いてきた。すぐ後ろには、女衛兵の正五位吉備朝臣由利(きびのあそんゆり)、そして、由利とほとんど並ぶかのように、もはや誰にもはばかることなく、これも袈裟姿の大臣禅師、道鏡が付き従っていた。
しかし嶋足にとっては、称徳天皇がすべてである。道鏡すら警護の対象である。中門でひざまずき、顔は正面に向けたまま、道鏡を含め各人の行動に注意を払っていた。帝に近づく者は、嶋足のひと声で近衛兵が反射的に迎撃態勢に入る。嶋足と由利は、帝の名においてその場で処刑できる強力な権限を有していた。いったん牛車が動き出すと、嶋足や由利の近衛府の責任者しか、車の脇に立つことを許されていない。
嶋足は、太政官道鏡すら信用しない女帝が、自分を頼りにしていることを十分承知していた。またその信頼感に一度も背いたことはなかった。道鏡が女帝の寝室で看護祈祷しているそばでも、由利や嶋足など近衛府の影が常にあった。警備の実務は、ウクハウなどの信頼できる、実直で有能な人材起用にも依っている。浄人が褒めるように、スキがなく素早いのは当然である。
帝の道中は短いものだった。貴族どもがこそこそおしゃべりしている中で、道ばたの石を寄せたり、市内の斥候など、周囲の警護を行うのは、ほとんどはエミシ出身者の仕事であった。彼らは疲れを知らず機敏に動き、朱雀門を通過するまでは、いちいち嶋足へ報告に来た。ウクハウもそのひとりであった。
警護の1日が終わった。ウクハウらは、嶋足宅へ慰労の宴に招かれていた。夕食を共にしながら、ウクハウは嶋足に問いかけた。
「秋には、帝は紀伊や河内に行幸されると伺いましたが」
嶋足は、出世した道鏡を故郷で錦を飾らせるイベントが今年中にある、と聞いていた。ウクハウは、その日程が迫っているので、嶋足がどうするか、と話を切り出したのである。
嶋足は、すでに行宮(あんぐう。旅行中の宿泊場所)を造営していることを右大臣藤原豊成(とよなり)から聞いていた。実弟の仲麻呂に追放された豊成にとって、道鏡は政界に返り咲きさせてもらった恩人である。この60歳に近い無能な右大臣豊成は、藤原嫡系のプライドも忘れ、道鏡賛美のイベントに全面協力しようとしていた。嶋足の脳裏に、弓削浄人の油断ならない顔がよぎった。
「今回は、辞退しようか、と考えているが・・・」
嶋足は、エミシを好意的に取り立ててくれる称徳天皇に命を懸ける覚悟はあった。しかし、結果的に道鏡を警護することになるイベントは、好まなかった。辞退の返事に、顔をしかめてウクハウは言った。
「では、百済王殿が、困るのではないでしょうか」
道嶋が断ると、百済王敬福がその役を負うことになる。百済王敬福は、やはり牡鹿出身で、嶋足らを抜擢した上司(従三位)である。この当時は65才の老齢になっており、大がかりな行事は辛いはずである。実際、百済王敬福はこの任務を最後に、亡くなった。
「百済王殿には、私から話をしておく。ウクハウは、わしと共に都に
いてもらいたい。河内への警護は、さらに故郷から人を呼んだらど
うか、と考えているのだが」
嶋足から、支援のための陸奥国エミシの衛士(えじ)徴集の計画を思いつくまま述べてみよ、と言われ、ウクハウはアテルイの顔を真っ先に思い浮かべた。しかし、口から出た言葉は、百済王の出身地を考慮して桃生や玉造の海道地域のエミシ、さらに鹿島、上総、上野のエミシの徴集案を述べた。嶋足は、部下のオーソドックスな計画に、同感の微笑を浮かべて、じっと聞いていた。
ウクハウは、説明をしながら、都の立場でみたエミシの序列や差別のようなものが歴然として存在することを、自ら語る口で知った。序列付けすることが都の仕事なのか。これが律令国家というものか・・・
道嶋殿はあこがれの上司である。信頼してついて行きたい。しかし、何かが違う、と、ウクハウは考えはじめた。脳裏にアテルイの顔や、異国交易の夢を語り合ったことが浮び、俺は都の人間になったんだ、と、つぶやいた。
アテルイ物語12 伊治城(エゾ城)
8月末の紺碧の空から、真夏の乾ききった土に陽光が垂直に注ぎ、かげろうがゆらめいていた。
かつて、たたら製鉄エンジニアであった伊治公呰麻呂、外従六位下地方官のアザマロは、いまは建造中の伊治城の南門高楼の見張台に立ち、北東方向に白く輝く夏雲を眺めていた。
ここしばらく雨がなく、作業が順調に進んでいるのも、この8月に神護景雲という年号に改元したからか、と、アザマロは考えていた。七色の虹が雲に映ったことに感動した称徳女帝が、太上大臣兼法王となった道鏡の勧めにより、その2か月後に改元を行ったのである。
現在の宮城県築館町、伊治郡は、舞草や胆沢のエミシ族と隣り合わせの地であり、出羽山道の関所でもある。ここに奈良朝廷の最前線基地、伊治城(エゾ城と発音。イジやコレハルはあとで呼ばれた地名)を建設開始したのが767年の初夏であった。着工してわずか1か月であったが、工事は8割完成した。
東西約700mを土塀でぐるりと囲んだ城内には、広場と政庁、兵士用の竪穴住居、工場及び簡易宿舎があり、城の外は、生活用水と防衛を兼ねた幅15mの掘が取り囲んでいる。
こんな大型土木工事が予想外に急ピッチで進んだのは、多賀城の官吏の人選はもちろんだが、桃生や雄勝の柵の工事の時のようなゲリラ攻撃や工夫の逃亡反乱が少なかったからである。道嶋三山らが予め胆沢に出向き、きちんと挨拶を行った甲斐があった。また約1万人の仕丁(現場作業員、工員)の監督のために、現地のエミシを大量に抜擢した気遣いの効果もあったであろう。
南門見張り台から見渡せば、北方向には栗駒山の水を湛えた清流エゾ川(現在の迫川)、西に伊治城内を通りアザマロの故郷鳴子の山々を貫き雄勝(横手市)につながる細長い出羽・秋田山道が見える。
真南には、墾田した広々としたエゾ沼平野に散在する水田と、ここ1年のうちに鹿島、上野、信濃から集まった多数の浮浪人の竪穴住居(柵戸)があり、さらにその屋根越し遠方には、エゾ沼(現在の伊豆沼)の湖水が光っていた。エゾ沼平野には、桃生城や玉造、色麻柵へと続く烽火高楼が見え、エゾ水門(伊治水門。石巻市)と多賀城への道を示していた。
その東側の迫川土塁の作業を行っていた仕丁(雑戸)の間をぬって、都の装束姿の男が、アザマロの立っていた南門へと近づき、馬から降りた。
陽射しの中で汗をぬぐい、男は高楼に向かって声を掛けた。
「アザマロ殿。また安積団の長の苦言なのだが」
吉弥侯部真麻呂、エミシ出身の土木技術者、外従五位のキミコベサネマロであった。キミコベは、族長クラスの呼称である。烽火高楼台の建築現場でまたトラブルが生じたな、と、アザマロは想像した。サネマロはアザマロに近づきながら言った。
「出羽のエミシを、やはり安積や白河団から分離して、北側の掘を
担当するのがよいと考えるのだが、どう思いますかな」
記録では伊治城は、9000名の仕丁が参加した築城事業であった。
そのうち秋田県横手から酒田付近までの俘囚約700人が、徭役で駆り出されていた。この出羽グループが、関東方面から来た浮浪人グループ、つまり鹿島、安積、白河団の連中と仲が悪い。
これは太政官令で、エミシとの交流が禁じられていたことも背景にあるが、あからさまな人種差別もあった。
つまり関東の浮浪人達は、牡鹿郡の海道エミシ(仙台付近の住民)には、この築城プロジェクトのリーダー、道嶋三山の出身地とあって一目おいているのだが、最近帰順した出羽エミシに対しては、野蛮人のように扱い、ことあるごとに馬鹿にしていた。
アザマロは答えた。
「わかりました。それなら、北の護岸工事へ移しましょう」
「おお。では、その旨を道嶋(三山)殿に伝えませんか。現場には
明日、私から指示しておきますので」
「ところで今回は、どんな事件が?」
「いや、ささいなことです。怪我をした安積団の二人は、後方(玉造)
の作業へ移します。大丈夫です、無位の浮浪者でした」
そうか、二人の力夫の怪我で済んだか、とアザマロは思った。
1万の見知らぬ浮浪者やエミシ同士が集まって、トラブルが少ない事がむしろ不思議なくらいである。
1週間前にはあやうく数百人規模の騒ぎになるところだった。喧嘩はどうでもいいが、一度険悪な状態になると工事が最低5日間止まり、こちらが深刻である。サネマロやアザマロは、工事の遅れにつながる険悪な状況に機敏に対応し手当てする義務がある。
しかしあの時は、二人の若者が、双方の間に立ち、憤りを見事に抑えた。この現場をたまたまアザマロがみていた。ムネトとモレという若者で、出羽の連中をよく知っている者だった。その後、アザマロは二人を呼び出し、城郭の北川のエゾ川の護岸取水工事をまかせた。監督役にふさわしい働きぶりだった。
陽光が全身を刺す暑い午後であった。セミの柵の周囲を取り囲んでいた。城郭内の平坦にならした土に、くっきりと2つの影を並べて、アザマロとサネマロが、南門から政務所に向かって歩いた。
左右の仕丁の簡易宿泊所からは、6000人分の糞尿の匂いが乾いた空気を伝わった。城郭内へ生活水路の導入すべきことを話しながら、中央にそびえる政務所まで400メートルの道を歩いて行った。
城郭の北壁の付近では、仕丁達の夕食の支度を始める大勢の女達があわただしく動き始めていた。その脇の鍛冶場からは、土建用の道具を鍛える音が絶え間なく聞こえた。窯場には木炭や燃料を運び込む人夫の動きが見えた。城郭内には、着工と同時にこのような製造部門が稼動していた。
城郭の中央に建つ政務所は、6本の掘っ立て柱に支えられた2階にある。見た目は立派な波多板で造られた家屋だが、砂盤腐葉土の上に基礎を入れず柱を入れたので、腐食や沈下で20年はもたない。
多賀城と違い、伊治城をこんなふうに簡略に造営したのは、臨時前線基地として早急に完成しなければならなかったからである。
外と違って、暗い政務室の中には、筆写担当官が壁に向かって座っていた。
奥のほうには、四人の都の装束の烏帽子の者がいた。そこに座っていた道嶋三山が、入り口の来訪者に声をかけた。
「おお、真麻呂殿と呰麻呂殿か。いまちょうど、築城工事の報告の奏
上文を書いているところであった。共に加わっていただければあり
がたいが」
四人の烏帽子は、今回の事業の成功は何によるものか、褒章者の評価について話し合っていた。エミシや仕丁達のトラブルもなく、賊地の最前線にしては奇跡的に、短期間かつ低予算で国家プロジェクトを成功させたのである。
実はこの伊治柵の築城が、道鏡時代に唯一自慢できる事業であった。このレポートは、1か月後には朝廷へ届き、法力による実績を求めていた称徳女帝や道鏡を歓喜させることになった。その結果、工事関係者全員が異例の褒賞にあずかり、蝦夷経営はうまくいっているとの認識が、貴族の間に広まることになった。
サネマロが座して一礼をし、道嶋三山に答えた。
「はは、かしこまりました。しかし、なにせ若輩の故、行き届かない
と存じますので、田中殿、石川殿、大伴殿にお願いできればと存じ
ます」
サネマロは、奥に座している上司の名前をあげ、自分は、作業割り当ての変更認可のために来たことを告げた。道嶋三山は、実質的な現場監督であるサネマロとアザマロの提案を了承した。道嶋は、アザマロに尋ねた。
「そういえば、呰麻呂殿、あの護岸個所で指揮している髭の若者、何
といいましたか」
「ムネトと、聞いておりましたが」
「おお、そうでした。出羽の者でしたね」
「いや、詳しくは知りませんが、髭の下の刺青は胆沢か志和のようで
す。尋ねてみましょうか」
工事の仕丁のほとんどは関東の浮浪者で、出所不明であった。出羽の雄勝エミシも帰順したばかりであり、ほとんどは無名の者である。道嶋三山は、ムネトもモレも出羽雄勝出身であると思っていた。実際、彼らは出羽の山の中から直接、自進雇夫(バイト作業員)として伊治へ来たからである。
ムネトがアテルイの弟であることはアザマロは知らない。
まして、モレが伝説的なエミシの雄、奥蝦夷の山道宣撫使の和我君計安塁(わがのきみけあるい)の孫であることなどは全く知らなかった。
ひげを顔中にたくわえた大男、胆沢のムネトは、自分が出羽エミシだろうと、和我、志和、阿倍族だと思われても、全然構わないと考えていた。実際、それらの地をすべて歩いていたし、よく知っていたからである。ムネトは、朝廷に帰順した父サイヒの息子が築城に協力することは当然ではないか、と考えていた。その経緯があったので親友である和我の御曹司だったモレを説得して、築城実習体験のために伊治へ来ていたのである。
ムネトやモレのようなエリートのエミシは、幼い頃からの鍛え方が違う。
説得力があり、長年培った自信がある。浮浪者やエミシの間で喧嘩の調停や工事の監督指導で頭角を現すのは、当然であった。
8月末の紺碧の空から、真夏の乾ききった土に陽光が垂直に注ぎ、かげろうがゆらめいていた。
かつて、たたら製鉄エンジニアであった伊治公呰麻呂、外従六位下地方官のアザマロは、いまは建造中の伊治城の南門高楼の見張台に立ち、北東方向に白く輝く夏雲を眺めていた。
ここしばらく雨がなく、作業が順調に進んでいるのも、この8月に神護景雲という年号に改元したからか、と、アザマロは考えていた。七色の虹が雲に映ったことに感動した称徳女帝が、太上大臣兼法王となった道鏡の勧めにより、その2か月後に改元を行ったのである。
現在の宮城県築館町、伊治郡は、舞草や胆沢のエミシ族と隣り合わせの地であり、出羽山道の関所でもある。ここに奈良朝廷の最前線基地、伊治城(エゾ城と発音。イジやコレハルはあとで呼ばれた地名)を建設開始したのが767年の初夏であった。着工してわずか1か月であったが、工事は8割完成した。
東西約700mを土塀でぐるりと囲んだ城内には、広場と政庁、兵士用の竪穴住居、工場及び簡易宿舎があり、城の外は、生活用水と防衛を兼ねた幅15mの掘が取り囲んでいる。
こんな大型土木工事が予想外に急ピッチで進んだのは、多賀城の官吏の人選はもちろんだが、桃生や雄勝の柵の工事の時のようなゲリラ攻撃や工夫の逃亡反乱が少なかったからである。道嶋三山らが予め胆沢に出向き、きちんと挨拶を行った甲斐があった。また約1万人の仕丁(現場作業員、工員)の監督のために、現地のエミシを大量に抜擢した気遣いの効果もあったであろう。
南門見張り台から見渡せば、北方向には栗駒山の水を湛えた清流エゾ川(現在の迫川)、西に伊治城内を通りアザマロの故郷鳴子の山々を貫き雄勝(横手市)につながる細長い出羽・秋田山道が見える。
真南には、墾田した広々としたエゾ沼平野に散在する水田と、ここ1年のうちに鹿島、上野、信濃から集まった多数の浮浪人の竪穴住居(柵戸)があり、さらにその屋根越し遠方には、エゾ沼(現在の伊豆沼)の湖水が光っていた。エゾ沼平野には、桃生城や玉造、色麻柵へと続く烽火高楼が見え、エゾ水門(伊治水門。石巻市)と多賀城への道を示していた。
その東側の迫川土塁の作業を行っていた仕丁(雑戸)の間をぬって、都の装束姿の男が、アザマロの立っていた南門へと近づき、馬から降りた。
陽射しの中で汗をぬぐい、男は高楼に向かって声を掛けた。
「アザマロ殿。また安積団の長の苦言なのだが」
吉弥侯部真麻呂、エミシ出身の土木技術者、外従五位のキミコベサネマロであった。キミコベは、族長クラスの呼称である。烽火高楼台の建築現場でまたトラブルが生じたな、と、アザマロは想像した。サネマロはアザマロに近づきながら言った。
「出羽のエミシを、やはり安積や白河団から分離して、北側の掘を
担当するのがよいと考えるのだが、どう思いますかな」
記録では伊治城は、9000名の仕丁が参加した築城事業であった。
そのうち秋田県横手から酒田付近までの俘囚約700人が、徭役で駆り出されていた。この出羽グループが、関東方面から来た浮浪人グループ、つまり鹿島、安積、白河団の連中と仲が悪い。
これは太政官令で、エミシとの交流が禁じられていたことも背景にあるが、あからさまな人種差別もあった。
つまり関東の浮浪人達は、牡鹿郡の海道エミシ(仙台付近の住民)には、この築城プロジェクトのリーダー、道嶋三山の出身地とあって一目おいているのだが、最近帰順した出羽エミシに対しては、野蛮人のように扱い、ことあるごとに馬鹿にしていた。
アザマロは答えた。
「わかりました。それなら、北の護岸工事へ移しましょう」
「おお。では、その旨を道嶋(三山)殿に伝えませんか。現場には
明日、私から指示しておきますので」
「ところで今回は、どんな事件が?」
「いや、ささいなことです。怪我をした安積団の二人は、後方(玉造)
の作業へ移します。大丈夫です、無位の浮浪者でした」
そうか、二人の力夫の怪我で済んだか、とアザマロは思った。
1万の見知らぬ浮浪者やエミシ同士が集まって、トラブルが少ない事がむしろ不思議なくらいである。
1週間前にはあやうく数百人規模の騒ぎになるところだった。喧嘩はどうでもいいが、一度険悪な状態になると工事が最低5日間止まり、こちらが深刻である。サネマロやアザマロは、工事の遅れにつながる険悪な状況に機敏に対応し手当てする義務がある。
しかしあの時は、二人の若者が、双方の間に立ち、憤りを見事に抑えた。この現場をたまたまアザマロがみていた。ムネトとモレという若者で、出羽の連中をよく知っている者だった。その後、アザマロは二人を呼び出し、城郭の北川のエゾ川の護岸取水工事をまかせた。監督役にふさわしい働きぶりだった。
陽光が全身を刺す暑い午後であった。セミの柵の周囲を取り囲んでいた。城郭内の平坦にならした土に、くっきりと2つの影を並べて、アザマロとサネマロが、南門から政務所に向かって歩いた。
左右の仕丁の簡易宿泊所からは、6000人分の糞尿の匂いが乾いた空気を伝わった。城郭内へ生活水路の導入すべきことを話しながら、中央にそびえる政務所まで400メートルの道を歩いて行った。
城郭の北壁の付近では、仕丁達の夕食の支度を始める大勢の女達があわただしく動き始めていた。その脇の鍛冶場からは、土建用の道具を鍛える音が絶え間なく聞こえた。窯場には木炭や燃料を運び込む人夫の動きが見えた。城郭内には、着工と同時にこのような製造部門が稼動していた。
城郭の中央に建つ政務所は、6本の掘っ立て柱に支えられた2階にある。見た目は立派な波多板で造られた家屋だが、砂盤腐葉土の上に基礎を入れず柱を入れたので、腐食や沈下で20年はもたない。
多賀城と違い、伊治城をこんなふうに簡略に造営したのは、臨時前線基地として早急に完成しなければならなかったからである。
外と違って、暗い政務室の中には、筆写担当官が壁に向かって座っていた。
奥のほうには、四人の都の装束の烏帽子の者がいた。そこに座っていた道嶋三山が、入り口の来訪者に声をかけた。
「おお、真麻呂殿と呰麻呂殿か。いまちょうど、築城工事の報告の奏
上文を書いているところであった。共に加わっていただければあり
がたいが」
四人の烏帽子は、今回の事業の成功は何によるものか、褒章者の評価について話し合っていた。エミシや仕丁達のトラブルもなく、賊地の最前線にしては奇跡的に、短期間かつ低予算で国家プロジェクトを成功させたのである。
実はこの伊治柵の築城が、道鏡時代に唯一自慢できる事業であった。このレポートは、1か月後には朝廷へ届き、法力による実績を求めていた称徳女帝や道鏡を歓喜させることになった。その結果、工事関係者全員が異例の褒賞にあずかり、蝦夷経営はうまくいっているとの認識が、貴族の間に広まることになった。
サネマロが座して一礼をし、道嶋三山に答えた。
「はは、かしこまりました。しかし、なにせ若輩の故、行き届かない
と存じますので、田中殿、石川殿、大伴殿にお願いできればと存じ
ます」
サネマロは、奥に座している上司の名前をあげ、自分は、作業割り当ての変更認可のために来たことを告げた。道嶋三山は、実質的な現場監督であるサネマロとアザマロの提案を了承した。道嶋は、アザマロに尋ねた。
「そういえば、呰麻呂殿、あの護岸個所で指揮している髭の若者、何
といいましたか」
「ムネトと、聞いておりましたが」
「おお、そうでした。出羽の者でしたね」
「いや、詳しくは知りませんが、髭の下の刺青は胆沢か志和のようで
す。尋ねてみましょうか」
工事の仕丁のほとんどは関東の浮浪者で、出所不明であった。出羽の雄勝エミシも帰順したばかりであり、ほとんどは無名の者である。道嶋三山は、ムネトもモレも出羽雄勝出身であると思っていた。実際、彼らは出羽の山の中から直接、自進雇夫(バイト作業員)として伊治へ来たからである。
ムネトがアテルイの弟であることはアザマロは知らない。
まして、モレが伝説的なエミシの雄、奥蝦夷の山道宣撫使の和我君計安塁(わがのきみけあるい)の孫であることなどは全く知らなかった。
ひげを顔中にたくわえた大男、胆沢のムネトは、自分が出羽エミシだろうと、和我、志和、阿倍族だと思われても、全然構わないと考えていた。実際、それらの地をすべて歩いていたし、よく知っていたからである。ムネトは、朝廷に帰順した父サイヒの息子が築城に協力することは当然ではないか、と考えていた。その経緯があったので親友である和我の御曹司だったモレを説得して、築城実習体験のために伊治へ来ていたのである。
ムネトやモレのようなエリートのエミシは、幼い頃からの鍛え方が違う。
説得力があり、長年培った自信がある。浮浪者やエミシの間で喧嘩の調停や工事の監督指導で頭角を現すのは、当然であった。
アテルイ物語13 モレとムネト
「出羽の連中は・・・」
アテルイの弟、ムネトは、米と稗をまぜたかゆをすすりながら、塩漬けの山芋を口に運ぶ。
残暑である。夕方になっても温度が下がらず、額からあごひげに汗が流れた。婢(女奴隷)がせわしく動き、大男ムネトの前に汁を運ぶ。
「田を心配しているのさ。この農繁期に駆り出されたからな」
ムネトは、あぐらの膝頭と同じ肩幅の体格で堂々と座り、隣に座ったモレに考えを述べていた。
出羽の雄勝(現横手市)といえば、延々と草原や水田が広がる東北きっての大耕作地帯、大曲平野がある。ムネトは、この時期の出羽のようすが、手に取るように想像できた。
いかにも豪傑のムネトに比べれば、モレはきゃしゃな若者である。
モレは、カネイシとならぶ製鉄の地、和我(和賀、現在の北上・花巻地域)に生まれ育ちながら、幼い頃から力仕事はせず、もっぱら祖父の計安塁(けあるい)のもとで、書に親しむ毎日であった。
しかし、鷹のようなモレの眼は、隙のない性格であることを想像させた。モレは、自分の意見を十分に理解し、あるときは批判してくれるムネトの豊富な体験を高く評価していた。
「ふむ。背景はそうだが、南の連中(浮浪人)のいわれのない蔑視が、
もっと直接的な原因ではないのかな」
そういう見方もあるのか、とムネトは驚いて、モレの顔を見る。
モレは続けて言う。
「出羽は少なくとも、ヒタカミや和我より開けている。客(異国人)
の出入りも多かった。それだけ誇れるなにか背景があるからだ。
関東も今の出羽の足元に及ばないだろう。出羽人たちは誇り高い。
しかし奈良の連中は、位階で人心をしばり、階級の高低で人を判断
するようにしむけた。
あの浮浪人たちは、もとは渡来人なのだろうな。位階ほしさで、
なんでもやるようだ。しかし結局は、判断能力を帝の権威にあずけて
威張っているだけなんだ。
独自に産業を推進している出羽の連中は、そこが気に入らないのさ」
「それほど自信があるなら、なぜ、出羽は、奈良に帰順したのか」
ムネトが尋ねた。
「これさ、これ」
手を首にあてたモレ、つまりは軍事力であることを示した。
自給自足の共同体を作っても、侵略は途絶えることは無く、軍事技術で有利に立ったほうが勝つ、という現実か・・・、ムネトが思い巡らしているとき、後ろから人が近づいてきた。
「モレ様とムネト様と伺いました。私は十三湊(とさみなと)のクラ
マロと申します」
東日流(津軽)の十三湊といえば、当時のエミシの世界では、国際貿易港であった。文化といい物流の量といい、群を抜いた交易の実績があった。ムネトもモレも、突然の十三湊の名乗りでいささか緊張した。今晩、仕丁宿舎で一席設けたいので、同席いただきたいとの話であった。
暑い一日が終わり、夜になった。
伊治城の城郭内は、たいまつが夜通し灯っていた。たいまつの明かりは四方を囲む土壁を赤く浮き上がらせた。たいまつの炎の周囲には、おびただしい数の蛾や虫が舞い、虫の音や獣の遠吠えが聞こえた。
多賀城から派遣された軍毅の統制のもとで、東西南北の門兵は外敵の進入のに対して警護に怠りはなかった。城郭の外にも不浪人達の住居や簡易宿舎があるが、毎晩、喧嘩等が絶えず、城郭内までその音が聞こえた。
月明かりとたいまつの明かりの中で、五人の影が部屋の隅で動き、酒を酌み交わしはじめた。周りには工事で疲れきった仕丁が、思い思いの寝姿で転がっていた。若い婢がひとりいた。政務所から酒をせしめてきたようであった。
「多賀城の連中の計画は・・・」
十三湊のクラマロが話をはじめた。
「雄勝城の次に、能代の城を造ると伺っている。この伊治城は、その
前進基地だとの話を伺った。なぜ能代なのか、考えていただきたい」
まだ幼い顔の婢の娘が、父親ほどのクラマロに寄り添って、盃に酒を注ぎ足している。
クラマロは盃を皆に勧め、低い声で話を続けた。
「狙いは、十三湊だと思う。
十三湊をたたけば、奈良は、ヒタカミやアラハバキを攻めずとも、
一挙に陸奥の利権を手中にできるからだ。
幸い、ここに、和我殿、胆沢殿、阿倍殿が来ておられる。
意見をうかがいたい」
たまたま北東北の面子がそろったとはいえ、我々は部族の代表ではない。
こういう場では、本音を言うものではないことを、モレもムネトも承知していた。十三湊のクラマロも、もちろん期待はしていなかった。
「いくさをしようというのか」
血の気の多いムネトが押し殺した声で、問いただした。
「陸奥の国は、十三湊のことも少しはわかっている。しかし、この中
の誰か都へ行ったことがあるのか。朝廷がどのようなものか、奈良
の軍がどうなっているのか、誰か知っているのか」
モレといつも話していた話題をムネトが切り出してしまった。
なぜ陸奥ヒタカミは侵されるのだろうか。
そのひとつの原因に、侵す相手の研究をしていないことがある。陸奥エミシの関心は、せいぜい隣の部族とか、時々訪れる渤海や新羅の異国、また便利屋的な渡来人しかない。
遠い存在とはいえ恐るべき隣国、奈良朝廷については詳しいことを知らず、無視している状況であることを、ムネトは述べた。
「同感だ。そういう面でも蝦夷地は、出遅れてしまったのだ」
阿倍の若者が、ムネトの意見をフォローした。
ベースキャンプの民であるアラハバキの阿倍族もまた、異国の交易に夢中になり、富を集積した軍事国家体制の確立が遅れ、奈良の侵略を防ぎきれなかったことを認めた。
これは逆に考えれば、当時のエミシの連合社会は、それぞれ技術立国しており、交易は活発であり、新羅の攻撃の心配もなく非軍事の社会体制でうまくいっていた、ということである。
商売熱心ではあったが、その一方では、平和ボケになってしまった地域連合の状況であった。
「提案がある」
十三湊クラマロがいっそう低い声で、話しはじめた。
まばたきを止めた三人の眼がクラマロを見つめた。
「渤海国だ。
この国を新羅へ侵出させるべきと思う。この国と共に、日本海の
制海権を得れば、奈良朝廷への税負担が半減する。水軍の整備も
あわせて、この話を考えてくれまいか」
突然の提案に、モレは我が耳を疑った。
自分と同じ発想をする者がいたのである。水軍の整備。その通りである。
エミシ社会には連合軍のような組織がない。
いざとなれば、国際的な支援を依頼せざるをえない。例えば渤海国である。渤海国にとって十三湊は重要な交易拠点で義理がある。したがって渤海と蝦夷の連合水軍という方向が考えられる。水軍の面では、なんとか対抗できるかもしれない。
整備の立ち後れた陸戦では、遅かれ早かれ、ヒタカミや十三湊の利権は、朝廷の手に陥ちてしまうであろう・・・モレは、たいまつの炎の光の中で、まばたきもせず考え続けていた。沈黙のまま、夜が更けていった。
蒸し暑い夜が明けた。
伊治の朝は、あいかわらず晴天続きであった。
伊治城建築の監督であるアザマロは、起きてすぐ、政務所から仕丁宿舎に向かった。道嶋三山と吉弥侯部真麻呂(サネマロ)の推薦で、ムネトとモレの二人を、多賀城修繕工事の軍毅役にとりたてようと考えていた。名も知らぬエミシの抜擢人事である。
あの若い彼らも、きっと喜ぶであろうと想像して、仕丁宿舎に着いたが、モレとムネトの姿が今朝から見えないことを知らされた。
二人はクラマロとの密議を胸に秘め、お世話になったと仕丁仲間に言葉を残し、伊治を発ったあとであった。
「出羽の連中は・・・」
アテルイの弟、ムネトは、米と稗をまぜたかゆをすすりながら、塩漬けの山芋を口に運ぶ。
残暑である。夕方になっても温度が下がらず、額からあごひげに汗が流れた。婢(女奴隷)がせわしく動き、大男ムネトの前に汁を運ぶ。
「田を心配しているのさ。この農繁期に駆り出されたからな」
ムネトは、あぐらの膝頭と同じ肩幅の体格で堂々と座り、隣に座ったモレに考えを述べていた。
出羽の雄勝(現横手市)といえば、延々と草原や水田が広がる東北きっての大耕作地帯、大曲平野がある。ムネトは、この時期の出羽のようすが、手に取るように想像できた。
いかにも豪傑のムネトに比べれば、モレはきゃしゃな若者である。
モレは、カネイシとならぶ製鉄の地、和我(和賀、現在の北上・花巻地域)に生まれ育ちながら、幼い頃から力仕事はせず、もっぱら祖父の計安塁(けあるい)のもとで、書に親しむ毎日であった。
しかし、鷹のようなモレの眼は、隙のない性格であることを想像させた。モレは、自分の意見を十分に理解し、あるときは批判してくれるムネトの豊富な体験を高く評価していた。
「ふむ。背景はそうだが、南の連中(浮浪人)のいわれのない蔑視が、
もっと直接的な原因ではないのかな」
そういう見方もあるのか、とムネトは驚いて、モレの顔を見る。
モレは続けて言う。
「出羽は少なくとも、ヒタカミや和我より開けている。客(異国人)
の出入りも多かった。それだけ誇れるなにか背景があるからだ。
関東も今の出羽の足元に及ばないだろう。出羽人たちは誇り高い。
しかし奈良の連中は、位階で人心をしばり、階級の高低で人を判断
するようにしむけた。
あの浮浪人たちは、もとは渡来人なのだろうな。位階ほしさで、
なんでもやるようだ。しかし結局は、判断能力を帝の権威にあずけて
威張っているだけなんだ。
独自に産業を推進している出羽の連中は、そこが気に入らないのさ」
「それほど自信があるなら、なぜ、出羽は、奈良に帰順したのか」
ムネトが尋ねた。
「これさ、これ」
手を首にあてたモレ、つまりは軍事力であることを示した。
自給自足の共同体を作っても、侵略は途絶えることは無く、軍事技術で有利に立ったほうが勝つ、という現実か・・・、ムネトが思い巡らしているとき、後ろから人が近づいてきた。
「モレ様とムネト様と伺いました。私は十三湊(とさみなと)のクラ
マロと申します」
東日流(津軽)の十三湊といえば、当時のエミシの世界では、国際貿易港であった。文化といい物流の量といい、群を抜いた交易の実績があった。ムネトもモレも、突然の十三湊の名乗りでいささか緊張した。今晩、仕丁宿舎で一席設けたいので、同席いただきたいとの話であった。
暑い一日が終わり、夜になった。
伊治城の城郭内は、たいまつが夜通し灯っていた。たいまつの明かりは四方を囲む土壁を赤く浮き上がらせた。たいまつの炎の周囲には、おびただしい数の蛾や虫が舞い、虫の音や獣の遠吠えが聞こえた。
多賀城から派遣された軍毅の統制のもとで、東西南北の門兵は外敵の進入のに対して警護に怠りはなかった。城郭の外にも不浪人達の住居や簡易宿舎があるが、毎晩、喧嘩等が絶えず、城郭内までその音が聞こえた。
月明かりとたいまつの明かりの中で、五人の影が部屋の隅で動き、酒を酌み交わしはじめた。周りには工事で疲れきった仕丁が、思い思いの寝姿で転がっていた。若い婢がひとりいた。政務所から酒をせしめてきたようであった。
「多賀城の連中の計画は・・・」
十三湊のクラマロが話をはじめた。
「雄勝城の次に、能代の城を造ると伺っている。この伊治城は、その
前進基地だとの話を伺った。なぜ能代なのか、考えていただきたい」
まだ幼い顔の婢の娘が、父親ほどのクラマロに寄り添って、盃に酒を注ぎ足している。
クラマロは盃を皆に勧め、低い声で話を続けた。
「狙いは、十三湊だと思う。
十三湊をたたけば、奈良は、ヒタカミやアラハバキを攻めずとも、
一挙に陸奥の利権を手中にできるからだ。
幸い、ここに、和我殿、胆沢殿、阿倍殿が来ておられる。
意見をうかがいたい」
たまたま北東北の面子がそろったとはいえ、我々は部族の代表ではない。
こういう場では、本音を言うものではないことを、モレもムネトも承知していた。十三湊のクラマロも、もちろん期待はしていなかった。
「いくさをしようというのか」
血の気の多いムネトが押し殺した声で、問いただした。
「陸奥の国は、十三湊のことも少しはわかっている。しかし、この中
の誰か都へ行ったことがあるのか。朝廷がどのようなものか、奈良
の軍がどうなっているのか、誰か知っているのか」
モレといつも話していた話題をムネトが切り出してしまった。
なぜ陸奥ヒタカミは侵されるのだろうか。
そのひとつの原因に、侵す相手の研究をしていないことがある。陸奥エミシの関心は、せいぜい隣の部族とか、時々訪れる渤海や新羅の異国、また便利屋的な渡来人しかない。
遠い存在とはいえ恐るべき隣国、奈良朝廷については詳しいことを知らず、無視している状況であることを、ムネトは述べた。
「同感だ。そういう面でも蝦夷地は、出遅れてしまったのだ」
阿倍の若者が、ムネトの意見をフォローした。
ベースキャンプの民であるアラハバキの阿倍族もまた、異国の交易に夢中になり、富を集積した軍事国家体制の確立が遅れ、奈良の侵略を防ぎきれなかったことを認めた。
これは逆に考えれば、当時のエミシの連合社会は、それぞれ技術立国しており、交易は活発であり、新羅の攻撃の心配もなく非軍事の社会体制でうまくいっていた、ということである。
商売熱心ではあったが、その一方では、平和ボケになってしまった地域連合の状況であった。
「提案がある」
十三湊クラマロがいっそう低い声で、話しはじめた。
まばたきを止めた三人の眼がクラマロを見つめた。
「渤海国だ。
この国を新羅へ侵出させるべきと思う。この国と共に、日本海の
制海権を得れば、奈良朝廷への税負担が半減する。水軍の整備も
あわせて、この話を考えてくれまいか」
突然の提案に、モレは我が耳を疑った。
自分と同じ発想をする者がいたのである。水軍の整備。その通りである。
エミシ社会には連合軍のような組織がない。
いざとなれば、国際的な支援を依頼せざるをえない。例えば渤海国である。渤海国にとって十三湊は重要な交易拠点で義理がある。したがって渤海と蝦夷の連合水軍という方向が考えられる。水軍の面では、なんとか対抗できるかもしれない。
整備の立ち後れた陸戦では、遅かれ早かれ、ヒタカミや十三湊の利権は、朝廷の手に陥ちてしまうであろう・・・モレは、たいまつの炎の光の中で、まばたきもせず考え続けていた。沈黙のまま、夜が更けていった。
蒸し暑い夜が明けた。
伊治の朝は、あいかわらず晴天続きであった。
伊治城建築の監督であるアザマロは、起きてすぐ、政務所から仕丁宿舎に向かった。道嶋三山と吉弥侯部真麻呂(サネマロ)の推薦で、ムネトとモレの二人を、多賀城修繕工事の軍毅役にとりたてようと考えていた。名も知らぬエミシの抜擢人事である。
あの若い彼らも、きっと喜ぶであろうと想像して、仕丁宿舎に着いたが、モレとムネトの姿が今朝から見えないことを知らされた。
二人はクラマロとの密議を胸に秘め、お世話になったと仕丁仲間に言葉を残し、伊治を発ったあとであった。
アテルイ物語14 和我(和賀)の里
今の言葉でいえば、主要地方道と呼ぶのだろうか、舞草(一関)、胆沢を通り、和我(北上)、子波、阿倍、爾薩体(にさて)、平賀、都留岐(青森)へと続く蝦夷国のメインルートは、奥羽山脈の山のせりだした東側丘陵の形のままに曲がりくねっていた。その山道の両側は、決まってナラやトチの木が目立っていた。現在の国道4号線の位置からおよそ10km〜20km西側のところである。
今日の国道ように、北上川河畔付近の平地にまっすぐなな道路を造ることは、エミシの民にとって危険なことである。平地の直線道路は、見知らぬ外敵に狙われやすい。この当時のヒタカミ国の平地は、畑や水田、果樹林、建材用植林などの生産活動の場所であり、あぜ路のような細い作業道路しかなかった。この畑地森林地帯を貫いて、幅広い軍用道路が出現したのは、坂上田村麻呂が志波城を建造したときであった。
モレとムネトは、やや色付き始めた胆沢の山すその、やっと2頭の馬が通れる落葉樹の繁る路を、語り合いながら北上していた。並木の向こうには初秋の空が広がり、時折吹きぬけるそよ風に、萱の穂が揺れた。
小川の浅瀬で縄細工の網で魚取りしている童達に出会った。布肩衣(貫頭衣)で頭を丸まげに結わえた男子達は、好奇の目を二人に向けた。
川魚が竹串に3匹すつ貫かれ、玩具の弓で射落とした雀や尾長鳥も、藁袋の中でうごめいていた。まだ5、6歳の女の子は、同じくらいの大きさの赤ん坊を背中に負い、手にトチの実やドングリ、カラハナソウなど野草のつまった藁袋を持っていた。とんぼや小鳥が飛び交う林の下では、キノコや栃の実を集める老婆達が怯えた目でモレとムネトを見つめていた。その林から300mほど向こうに、雑穀を担ぐ人たちが見えた。彼らも作業の手を止め、馬で行くモレ達をじっと見、警戒していた。そろそろ和我の境界付近である。
「向こうに見える三人連れ、あれは兄貴ではないか」
ムネトが声を掛けた。モレは馬を止めた。曲がりくねった木立の向こうに見え隠れする、けら(藁製のレインコート)を纏った三人連れを眺めた。用心深いモレは無意識のうちに腰の刀を確認し、鞍の弓をいつでも取り出せるようにした。日高見の地を馬で旅をするエミシは、たいていは、自分らと似た身分の連中ではある。念を入れて、すぐ迎撃できるように身構えるのは、多民族国家の習い性である。モレは丸薬を口に入れた。杉と麻と山椒の実の混合した味が口内に広がる。エミシの使う興奮剤である。向こうの三人連れも視線をそらすことなく、スキのない攻撃態勢で近づいた。しかし途中でムネトとわかったのか、尾花の生い茂る道を、早足で駆けてきた。
「しばらくだな。どこへ行っていた」
アテルイが、ヒゲずらのムネトに尋ねた。
「出羽からエゾ沼(伊治)だ。自進雇夫になって城造りをしてきた」
「そうか。ではアザマロに会ったか」
「郡司の甥の監督か。世話になった」
アテルイは、共に旅をしている阿倍族、十三湊の者を紹介した。これから胆沢に帰るところで、ついさっき、和我の警護の者達と別れてきた、とアテルイは言った。ムネトも、友人を紹介した。
「こちらは、和我のモレだ。出羽からずっと旅をしている」
「弟が世話になりましたな。よろしく」
「いや、こちらこそ、舞草からここまでは、ムネト殿や胆沢の方々の
お世話で、旅を続けられました。はじめまして」
これからムネトと和我に戻るが、ぜひ皆さんもお立ち寄りいただければ、とモレがアテルイ達を誘った。アテルイも急ぐ旅ではなかったので、来た道を引き返すことにした。
馬5頭が連なり、ヒタカミ河と和我河の合流地点から、クオナイ(口内。仕掛けのある川の蝦夷語)の浅瀬を渡り、ススナイやヨコシナイ(現煤孫、横志田の地名。いずれも漁場の河の意味)というサケの遡上する河を横切り、和我の里(北上市江釣子付近)の部落へと入った。
夕暮れの和我の里は、あちこちの住居から炊事の煙がたち、こども達のはしゃぐ声がにぎやかであった。こども達は牛と馬のかいばを作り、二人組みで厩舎に運んでいた。農作業を終えた男達は泥の付着した早袖姿でたきぎを積み上げ、そのたびに山の神に拝礼していた。
一日の麻織作業を終え、頭に水かめを乗せた衣裳(きぬも)姿の娘は、片手に笹の葉の包みものを下げてきた。桔梗や熊笹(薬草)を採取してきたのであろう。村を幾筋も貫く用水路の脇に麻布の乾燥柵がずらり並び、その奥に立った鮮やかな赤色の襟を付けた若い女が、にこにこ近づいてきた。モレの妻であった。彼女は多くの女たちの指揮をしていたので、5人の若者はあいさつもそこそこに通り過ぎて行った。
見事に整地された大通り路の向こうに、小高く作った丘がある。その上に堂々とそびえる要塞のような館は、和我王の館である。その館へ馬を乗り入れたのは、たいまつが板塀を照らしはじめる夕暮れ時であった。
旅人たちは、和我の長にあいさつを申し上げ、宴を催した。和我の若者も何人か駆けつけた。
「出羽は、いかがでしたか」
アテルイもモレに尋ねた。出羽は現在の横手市の近辺である。そこにある雄勝城で、エミシの民と朝廷の間でいざこざがあったのである。
「雄勝城に帰順する者と背くものが半々というところでしょうか。い
まは、出羽の租や調は、比較的軽い状況ですが、いずれ、出挙(す
いこ。年利率50%で朝廷の稲を貸す制度)や、義倉(ぎそう。凶
作にそなえた穀物の無尽制度)で、がんじがらめになることを心配
していたようです。征服された民のさだめですが」
「背いた人たちは、その後どのように暮らしているのですか」
「帰順した人が多くおりました。しかしすぐに西方(九州地方のこと)
に送られるようですね。ええ、ご推察のように、林業と製鉄の技術
指導か兵士としてです。その他は山に逃げたようですね。子波族の
地にも、多数流れたようです。和我でも受け入れました。たたら作
業に就いております」
長老側近でなければ知らない情報がモレの口から紹介された。
「和我の鉄は、定評がありますからね」
十三湊(とさみなと)の者が口をはさんだ。和我の里では、「高殿たたら」による生産様式が、和我川上流(現土畑鉱山付近)に導入されており、天候に関係なく一定のペースで鉄素材を生産できたのである。モレは逆に、十三湊の者に尋ねた。
「十三湊の鉄の相場はいかがですか」
モレの関心は和我の主力交易品である鉄素材の状況である。和我の若者達も緊張した顔になる。十三湊の者はしかし、暗い顔で答えた。
「ふむ。正直な話、下がり加減になった。越後の連中の話だが、この
ところ朝廷改修や造都の熱が冷め、新羅侵略を計画していた仲麻呂
もいなくなった。しかし近江や出雲、越後はあいかわらず鉄を量産
し続けているようなので、陸奥の鉄がだぶついたようだ」
エミシの玄関十三湊には、越後等から鉄素材や木材また塩、魚介類の仲買人の来訪者が多い。この貿易港には、交易品の流通のみならず、村を追われた者や渡来人(当時は不浪人と呼んだ)がたどり着き、その後、当時の禁制品であった製鉄に従事することも多かった。アテルイは、このような者の組織化や開発、流通を行うことが本業であった。
「伊治で、十三湊のクラマロという者から、こんな話を聞いた」
ムネトが低い声で話しはじめた。奈良平城京による雄勝、伊治、桃生の囲い込みの狙いは、最終的に十三湊であり、その利権と交易ネットワークを手中にすることである。つまり、アテルイらの行っている権益を朝廷が奪取することである。
「百済殿や道嶋殿がむこうにいるから、つつぬけだな」
アテルイがため息まじりの返事をした。
エミシと呼ばれた陸奥国内に、ネットワークを組織し、工業技術立国の様相を整えつつあったアテルイも、軍事上では大きく遅れをとっていることを自覚していた。道嶋嶋足は、百済系の渡来人で、アテルイの祖父にもつながる尊敬するこの先輩である。しかしこういう状況では、情報がつつぬけになり場合によっては強大な敵となる。道嶋のもとに行ったウクハウはどうしているだろうか。アテルイは、ウクハウの純真な気性が奈良で通用しているのだろうか、と思い浮かべた。
ムネトが周囲をぐるりと睨み付けながら言葉を続けた。
「これは内密に願いたいのですが・・・」
阿弖良(あてら。後の大伴部阿弖良)ら和我の若者達は、当然とでもいうような厳しい目をムネトに向けた。ムネトは、大柄な髭顔のなかに、これは失礼、とでもいうような笑顔の細い目を浮かべて話す。
「高麗(こま。渤海国)と同盟を結び、越前付近までの制海権を得よ
うという提案がされているのです」
ウーム、という顔でアテルイは腕を組んだ。先日、十三湊で聞いた噂が、伊治まで広まっている。
「同病相憐れむ、の様相ですな」
寡黙な阿倍族の乙代(おとしろ)が、沈黙を破った。乙代は、後に朝廷軍に恐れられた千人力の太い腕を組んだまま、言葉を続けた。
「渤海国は出目は違うが、軍事的には新羅や唐からみて、エミシと同
じ立場である。新羅に侵略され追い出され、必死で防戦している状
況だ。エミシから提案すれば渤海は断ることはないだろう。しかし、
その後が問題だ」
渤海国は、再興を狙って奈良にも通じている。いまは亡き仲麻呂は、渤海と通じて、日本海の制海権を得ようとして新羅討伐の準備をしていた。その同盟関係にあった渤海を、エミシ側に通じさせると、逆に敵に情報がつつぬけになることを覚悟せねばなるまい。かえって危険である、との意見を述べた。
一同がまた黙った。秋の虫の音が館を取り巻いた。夜もふけて、館の人々は寝静まった。油灯のゆらめく中で、モレは、自分たちの運命がきびしい状況にあることを考えていた。
渤海同盟は、計画ではなく、十三湊ではすでに開始し行動していることであろう。エミシの戦線布告の意思表示が、既に奈良朝廷に知られたものと認識しなければならない。奈良も当然動き始めているだろう。
モレの思考は、閉じた目の中で激しく動いた。和我は独自性を保ちながら朝廷に中途半端に帰順している。しかしいずれ雄勝のように全面統治の状態になるであろう。和我の鉱山やヒタカミへの塩運送ルート等の権益も、そっくり朝廷に奪取されることは時間の問題である。和我一族の未来は、奈良貴族連中の蔑視の中で生き、隷属の立場になるであろう。
何か手は打てないものか。モレは声を低くして話しはじめた。
「十三湊の権益は、和我のみならず、エミシ全体の死活問題である。
これは異論はない。しかしその権益保護ために、どこかの部族が楯
にならざるを得ない。その最前線は、南方は胆沢、西方は和我であ
ろう。ここに北方から戦力投入をしていただきたい。
その代わりに・・・」
モレは部族らの安全を、十三湊で保護するよう提案をした。和我、胆沢にある主力工業生産基地や要人を、十三湊やその交易ルート上に移し、そこを兵站基地にし、最前線である胆沢へ、エミシ連合軍を派遣する案である。
和我の里の夜は深まり、誰も言葉を交わすことがなかった。皆、自分のこれからの運命を思い浮かべていた。朝廷の侵略に対して、あまりにも遅すぎた防衛戦略である。
アテルイは、真夜中の空に目をむけた。吸い込まれるような満天の星が輝いていた。これまで幸福に過ごしてきた妻タツノや子供たちの顔が浮んだ。アテルイは立ち上がった。
「それでいこう。胆沢の軍長、伊左西古には、俺から伝える」
道嶋のもとへ行ったウクハウに会いたい。会って都のことを聞きたい。
アテルイは初秋のしじまの夜空を眺め続けた。
今の言葉でいえば、主要地方道と呼ぶのだろうか、舞草(一関)、胆沢を通り、和我(北上)、子波、阿倍、爾薩体(にさて)、平賀、都留岐(青森)へと続く蝦夷国のメインルートは、奥羽山脈の山のせりだした東側丘陵の形のままに曲がりくねっていた。その山道の両側は、決まってナラやトチの木が目立っていた。現在の国道4号線の位置からおよそ10km〜20km西側のところである。
今日の国道ように、北上川河畔付近の平地にまっすぐなな道路を造ることは、エミシの民にとって危険なことである。平地の直線道路は、見知らぬ外敵に狙われやすい。この当時のヒタカミ国の平地は、畑や水田、果樹林、建材用植林などの生産活動の場所であり、あぜ路のような細い作業道路しかなかった。この畑地森林地帯を貫いて、幅広い軍用道路が出現したのは、坂上田村麻呂が志波城を建造したときであった。
モレとムネトは、やや色付き始めた胆沢の山すその、やっと2頭の馬が通れる落葉樹の繁る路を、語り合いながら北上していた。並木の向こうには初秋の空が広がり、時折吹きぬけるそよ風に、萱の穂が揺れた。
小川の浅瀬で縄細工の網で魚取りしている童達に出会った。布肩衣(貫頭衣)で頭を丸まげに結わえた男子達は、好奇の目を二人に向けた。
川魚が竹串に3匹すつ貫かれ、玩具の弓で射落とした雀や尾長鳥も、藁袋の中でうごめいていた。まだ5、6歳の女の子は、同じくらいの大きさの赤ん坊を背中に負い、手にトチの実やドングリ、カラハナソウなど野草のつまった藁袋を持っていた。とんぼや小鳥が飛び交う林の下では、キノコや栃の実を集める老婆達が怯えた目でモレとムネトを見つめていた。その林から300mほど向こうに、雑穀を担ぐ人たちが見えた。彼らも作業の手を止め、馬で行くモレ達をじっと見、警戒していた。そろそろ和我の境界付近である。
「向こうに見える三人連れ、あれは兄貴ではないか」
ムネトが声を掛けた。モレは馬を止めた。曲がりくねった木立の向こうに見え隠れする、けら(藁製のレインコート)を纏った三人連れを眺めた。用心深いモレは無意識のうちに腰の刀を確認し、鞍の弓をいつでも取り出せるようにした。日高見の地を馬で旅をするエミシは、たいていは、自分らと似た身分の連中ではある。念を入れて、すぐ迎撃できるように身構えるのは、多民族国家の習い性である。モレは丸薬を口に入れた。杉と麻と山椒の実の混合した味が口内に広がる。エミシの使う興奮剤である。向こうの三人連れも視線をそらすことなく、スキのない攻撃態勢で近づいた。しかし途中でムネトとわかったのか、尾花の生い茂る道を、早足で駆けてきた。
「しばらくだな。どこへ行っていた」
アテルイが、ヒゲずらのムネトに尋ねた。
「出羽からエゾ沼(伊治)だ。自進雇夫になって城造りをしてきた」
「そうか。ではアザマロに会ったか」
「郡司の甥の監督か。世話になった」
アテルイは、共に旅をしている阿倍族、十三湊の者を紹介した。これから胆沢に帰るところで、ついさっき、和我の警護の者達と別れてきた、とアテルイは言った。ムネトも、友人を紹介した。
「こちらは、和我のモレだ。出羽からずっと旅をしている」
「弟が世話になりましたな。よろしく」
「いや、こちらこそ、舞草からここまでは、ムネト殿や胆沢の方々の
お世話で、旅を続けられました。はじめまして」
これからムネトと和我に戻るが、ぜひ皆さんもお立ち寄りいただければ、とモレがアテルイ達を誘った。アテルイも急ぐ旅ではなかったので、来た道を引き返すことにした。
馬5頭が連なり、ヒタカミ河と和我河の合流地点から、クオナイ(口内。仕掛けのある川の蝦夷語)の浅瀬を渡り、ススナイやヨコシナイ(現煤孫、横志田の地名。いずれも漁場の河の意味)というサケの遡上する河を横切り、和我の里(北上市江釣子付近)の部落へと入った。
夕暮れの和我の里は、あちこちの住居から炊事の煙がたち、こども達のはしゃぐ声がにぎやかであった。こども達は牛と馬のかいばを作り、二人組みで厩舎に運んでいた。農作業を終えた男達は泥の付着した早袖姿でたきぎを積み上げ、そのたびに山の神に拝礼していた。
一日の麻織作業を終え、頭に水かめを乗せた衣裳(きぬも)姿の娘は、片手に笹の葉の包みものを下げてきた。桔梗や熊笹(薬草)を採取してきたのであろう。村を幾筋も貫く用水路の脇に麻布の乾燥柵がずらり並び、その奥に立った鮮やかな赤色の襟を付けた若い女が、にこにこ近づいてきた。モレの妻であった。彼女は多くの女たちの指揮をしていたので、5人の若者はあいさつもそこそこに通り過ぎて行った。
見事に整地された大通り路の向こうに、小高く作った丘がある。その上に堂々とそびえる要塞のような館は、和我王の館である。その館へ馬を乗り入れたのは、たいまつが板塀を照らしはじめる夕暮れ時であった。
旅人たちは、和我の長にあいさつを申し上げ、宴を催した。和我の若者も何人か駆けつけた。
「出羽は、いかがでしたか」
アテルイもモレに尋ねた。出羽は現在の横手市の近辺である。そこにある雄勝城で、エミシの民と朝廷の間でいざこざがあったのである。
「雄勝城に帰順する者と背くものが半々というところでしょうか。い
まは、出羽の租や調は、比較的軽い状況ですが、いずれ、出挙(す
いこ。年利率50%で朝廷の稲を貸す制度)や、義倉(ぎそう。凶
作にそなえた穀物の無尽制度)で、がんじがらめになることを心配
していたようです。征服された民のさだめですが」
「背いた人たちは、その後どのように暮らしているのですか」
「帰順した人が多くおりました。しかしすぐに西方(九州地方のこと)
に送られるようですね。ええ、ご推察のように、林業と製鉄の技術
指導か兵士としてです。その他は山に逃げたようですね。子波族の
地にも、多数流れたようです。和我でも受け入れました。たたら作
業に就いております」
長老側近でなければ知らない情報がモレの口から紹介された。
「和我の鉄は、定評がありますからね」
十三湊(とさみなと)の者が口をはさんだ。和我の里では、「高殿たたら」による生産様式が、和我川上流(現土畑鉱山付近)に導入されており、天候に関係なく一定のペースで鉄素材を生産できたのである。モレは逆に、十三湊の者に尋ねた。
「十三湊の鉄の相場はいかがですか」
モレの関心は和我の主力交易品である鉄素材の状況である。和我の若者達も緊張した顔になる。十三湊の者はしかし、暗い顔で答えた。
「ふむ。正直な話、下がり加減になった。越後の連中の話だが、この
ところ朝廷改修や造都の熱が冷め、新羅侵略を計画していた仲麻呂
もいなくなった。しかし近江や出雲、越後はあいかわらず鉄を量産
し続けているようなので、陸奥の鉄がだぶついたようだ」
エミシの玄関十三湊には、越後等から鉄素材や木材また塩、魚介類の仲買人の来訪者が多い。この貿易港には、交易品の流通のみならず、村を追われた者や渡来人(当時は不浪人と呼んだ)がたどり着き、その後、当時の禁制品であった製鉄に従事することも多かった。アテルイは、このような者の組織化や開発、流通を行うことが本業であった。
「伊治で、十三湊のクラマロという者から、こんな話を聞いた」
ムネトが低い声で話しはじめた。奈良平城京による雄勝、伊治、桃生の囲い込みの狙いは、最終的に十三湊であり、その利権と交易ネットワークを手中にすることである。つまり、アテルイらの行っている権益を朝廷が奪取することである。
「百済殿や道嶋殿がむこうにいるから、つつぬけだな」
アテルイがため息まじりの返事をした。
エミシと呼ばれた陸奥国内に、ネットワークを組織し、工業技術立国の様相を整えつつあったアテルイも、軍事上では大きく遅れをとっていることを自覚していた。道嶋嶋足は、百済系の渡来人で、アテルイの祖父にもつながる尊敬するこの先輩である。しかしこういう状況では、情報がつつぬけになり場合によっては強大な敵となる。道嶋のもとに行ったウクハウはどうしているだろうか。アテルイは、ウクハウの純真な気性が奈良で通用しているのだろうか、と思い浮かべた。
ムネトが周囲をぐるりと睨み付けながら言葉を続けた。
「これは内密に願いたいのですが・・・」
阿弖良(あてら。後の大伴部阿弖良)ら和我の若者達は、当然とでもいうような厳しい目をムネトに向けた。ムネトは、大柄な髭顔のなかに、これは失礼、とでもいうような笑顔の細い目を浮かべて話す。
「高麗(こま。渤海国)と同盟を結び、越前付近までの制海権を得よ
うという提案がされているのです」
ウーム、という顔でアテルイは腕を組んだ。先日、十三湊で聞いた噂が、伊治まで広まっている。
「同病相憐れむ、の様相ですな」
寡黙な阿倍族の乙代(おとしろ)が、沈黙を破った。乙代は、後に朝廷軍に恐れられた千人力の太い腕を組んだまま、言葉を続けた。
「渤海国は出目は違うが、軍事的には新羅や唐からみて、エミシと同
じ立場である。新羅に侵略され追い出され、必死で防戦している状
況だ。エミシから提案すれば渤海は断ることはないだろう。しかし、
その後が問題だ」
渤海国は、再興を狙って奈良にも通じている。いまは亡き仲麻呂は、渤海と通じて、日本海の制海権を得ようとして新羅討伐の準備をしていた。その同盟関係にあった渤海を、エミシ側に通じさせると、逆に敵に情報がつつぬけになることを覚悟せねばなるまい。かえって危険である、との意見を述べた。
一同がまた黙った。秋の虫の音が館を取り巻いた。夜もふけて、館の人々は寝静まった。油灯のゆらめく中で、モレは、自分たちの運命がきびしい状況にあることを考えていた。
渤海同盟は、計画ではなく、十三湊ではすでに開始し行動していることであろう。エミシの戦線布告の意思表示が、既に奈良朝廷に知られたものと認識しなければならない。奈良も当然動き始めているだろう。
モレの思考は、閉じた目の中で激しく動いた。和我は独自性を保ちながら朝廷に中途半端に帰順している。しかしいずれ雄勝のように全面統治の状態になるであろう。和我の鉱山やヒタカミへの塩運送ルート等の権益も、そっくり朝廷に奪取されることは時間の問題である。和我一族の未来は、奈良貴族連中の蔑視の中で生き、隷属の立場になるであろう。
何か手は打てないものか。モレは声を低くして話しはじめた。
「十三湊の権益は、和我のみならず、エミシ全体の死活問題である。
これは異論はない。しかしその権益保護ために、どこかの部族が楯
にならざるを得ない。その最前線は、南方は胆沢、西方は和我であ
ろう。ここに北方から戦力投入をしていただきたい。
その代わりに・・・」
モレは部族らの安全を、十三湊で保護するよう提案をした。和我、胆沢にある主力工業生産基地や要人を、十三湊やその交易ルート上に移し、そこを兵站基地にし、最前線である胆沢へ、エミシ連合軍を派遣する案である。
和我の里の夜は深まり、誰も言葉を交わすことがなかった。皆、自分のこれからの運命を思い浮かべていた。朝廷の侵略に対して、あまりにも遅すぎた防衛戦略である。
アテルイは、真夜中の空に目をむけた。吸い込まれるような満天の星が輝いていた。これまで幸福に過ごしてきた妻タツノや子供たちの顔が浮んだ。アテルイは立ち上がった。
「それでいこう。胆沢の軍長、伊左西古には、俺から伝える」
道嶋のもとへ行ったウクハウに会いたい。会って都のことを聞きたい。
アテルイは初秋のしじまの夜空を眺め続けた。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
蝦夷(えみし) 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
蝦夷(えみし)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人
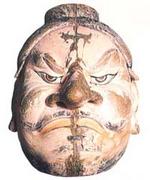





![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)


![饒速日 [ニギハヤヒ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/68/50/3876850_10s.gif)













