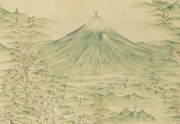|
|
|
|
コメント(181)
隕石から作った榎本武揚の「流星刀」、4年ぶり公開へ…「最も刃紋の美しい刀」と代々伝えられる
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240608-OYT1T50042/
幕末・明治期の政治家、榎本武揚が 隕石 を材料に作らせた日本刀「流星刀」が22日、榎本が1876年に建てた北海道小樽市稲穂の龍宮神社で公開される。子孫から2017年に奉納され、所蔵する名刀で、公開は4年ぶり2回目となる。
富山県で発見された「白萩隕鉄」を1895年に買い取った榎本は3年後、刀工の岡吉国宗に長短計5振りの刀を作らせ、流星刀と名付けた。
これらのうち、1振りは当時の皇太子(大正天皇)に献上され、1振りは戦時中に紛失、2振りはそれぞれ東京農業大学、富山市天文台(後に同市科学博物館が収蔵)に寄贈された。
龍宮神社が所蔵する短刀1振り(刃渡り19.7cm)は「最も刃紋の美しい刀」として120年近くにわたり、代々榎本家に伝えられてきたものだという。
4年前には、霊刀の御利益でコロナ禍を健康で乗り切ってほしいとの思いから初公開されたが、今回は今年が「 辰 年」ということで、再び拝観できる機会を設けたという。
本間公祐宮司は「今年は神社におまつりしている龍の神が最も強くなる年。強い霊力を持った刀に皆さんの希望を祈願してほしい」と話している。
公開は社殿内で午前10時〜午後3時。拝観無料。
こーゆー時にその地元の良さを感じますがやはり羨ましいですね。
利根川以北の移動は覚悟が必要ですね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240608-OYT1T50042/
幕末・明治期の政治家、榎本武揚が 隕石 を材料に作らせた日本刀「流星刀」が22日、榎本が1876年に建てた北海道小樽市稲穂の龍宮神社で公開される。子孫から2017年に奉納され、所蔵する名刀で、公開は4年ぶり2回目となる。
富山県で発見された「白萩隕鉄」を1895年に買い取った榎本は3年後、刀工の岡吉国宗に長短計5振りの刀を作らせ、流星刀と名付けた。
これらのうち、1振りは当時の皇太子(大正天皇)に献上され、1振りは戦時中に紛失、2振りはそれぞれ東京農業大学、富山市天文台(後に同市科学博物館が収蔵)に寄贈された。
龍宮神社が所蔵する短刀1振り(刃渡り19.7cm)は「最も刃紋の美しい刀」として120年近くにわたり、代々榎本家に伝えられてきたものだという。
4年前には、霊刀の御利益でコロナ禍を健康で乗り切ってほしいとの思いから初公開されたが、今回は今年が「 辰 年」ということで、再び拝観できる機会を設けたという。
本間公祐宮司は「今年は神社におまつりしている龍の神が最も強くなる年。強い霊力を持った刀に皆さんの希望を祈願してほしい」と話している。
公開は社殿内で午前10時〜午後3時。拝観無料。
こーゆー時にその地元の良さを感じますがやはり羨ましいですね。
利根川以北の移動は覚悟が必要ですね。
>>[149]
「根拠」とのことですがそんな小難しいものなんてありませんよ。
かえるーさんが書いてますように便乗商法の歴史系雑誌や小説、他に民放が大河ドラマに沿った内容の番組の放送といった一般向けの視点でもかまいません。
かえるーさんとは別の視点でなら歴史専門書においても徳川家康、今川氏真、武田勝頼、織田信長、豊臣秀吉、関ヶ原の戦いに焦点をあてた本の発刊も多かったですね。
幅広くそういうものはいいのですが、NHKが大河ドラマを宣伝しているにすぎない英雄達の選択と歴史探偵をあげるのはそれは違うように感じたに過ぎません。
私は「これって時代が古いから文献や遺跡が発見されにくいからですかね?」と趣旨を明確に書きましたが、ここに注目してくれてたらと思いました。
「根拠」とのことですがそんな小難しいものなんてありませんよ。
かえるーさんが書いてますように便乗商法の歴史系雑誌や小説、他に民放が大河ドラマに沿った内容の番組の放送といった一般向けの視点でもかまいません。
かえるーさんとは別の視点でなら歴史専門書においても徳川家康、今川氏真、武田勝頼、織田信長、豊臣秀吉、関ヶ原の戦いに焦点をあてた本の発刊も多かったですね。
幅広くそういうものはいいのですが、NHKが大河ドラマを宣伝しているにすぎない英雄達の選択と歴史探偵をあげるのはそれは違うように感じたに過ぎません。
私は「これって時代が古いから文献や遺跡が発見されにくいからですかね?」と趣旨を明確に書きましたが、ここに注目してくれてたらと思いました。
>>[155]
新しい文献が出てきたわけではありません。
元々、寿桂尼についてはその解釈にいくつかの無理があったのですが義元は寿桂尼の子という揺るがない常識(思い込み)をついに取っ払ったという感じです。
ただ、それで解決というわけにもいきませんので理論的な解釈で整合性を取っている作業の段階です。
義元の実母が誰かについて言及している文献でも出てきたらありがたいところですね。
雪斎は別格としても今川氏と姻戚関係という点で優遇されたのは伊勢氏以外で思いつかないのが現状。
まあ、大河ドラマ「おんな城主直虎」の時でも築山殿の実母の出自の解釈が井伊氏という説もアリ?とするなら寿桂尼の一件もそこまで今までの常識に固執する必要も無いのかと。
新しい文献が出てきたわけではありません。
元々、寿桂尼についてはその解釈にいくつかの無理があったのですが義元は寿桂尼の子という揺るがない常識(思い込み)をついに取っ払ったという感じです。
ただ、それで解決というわけにもいきませんので理論的な解釈で整合性を取っている作業の段階です。
義元の実母が誰かについて言及している文献でも出てきたらありがたいところですね。
雪斎は別格としても今川氏と姻戚関係という点で優遇されたのは伊勢氏以外で思いつかないのが現状。
まあ、大河ドラマ「おんな城主直虎」の時でも築山殿の実母の出自の解釈が井伊氏という説もアリ?とするなら寿桂尼の一件もそこまで今までの常識に固執する必要も無いのかと。
>>[159]
「福島氏」の可能性は難しいですね。
玄広恵探を担ぎ上げた福島氏はこれにこだわる理由が無くなってしまいます。
同じ母親という解釈なら雪斎と共に今川義元を担げばいいだけですからね。
姉妹が今川氏親の側室の可能性もありますけどそこまでしてまで家督を争うのもどうなんでしょうね。
雪斎との主導権争いも考えられなくもないですがわざわざ今川家を二分して争うのもどうなのかとも思います。
逆に今川義元が勝利した後の朝比奈氏は三浦氏と共に重臣として活躍していますから朝比奈氏のほうに説得力があります。
どっちにしても何か根拠を示す書状が発見されないことには思い付きで終わってしまいますので文書発見に期待したいです。
「福島氏」の可能性は難しいですね。
玄広恵探を担ぎ上げた福島氏はこれにこだわる理由が無くなってしまいます。
同じ母親という解釈なら雪斎と共に今川義元を担げばいいだけですからね。
姉妹が今川氏親の側室の可能性もありますけどそこまでしてまで家督を争うのもどうなんでしょうね。
雪斎との主導権争いも考えられなくもないですがわざわざ今川家を二分して争うのもどうなのかとも思います。
逆に今川義元が勝利した後の朝比奈氏は三浦氏と共に重臣として活躍していますから朝比奈氏のほうに説得力があります。
どっちにしても何か根拠を示す書状が発見されないことには思い付きで終わってしまいますので文書発見に期待したいです。
>>[161]
>「福島氏」の可能性は難しいですね。
更に言うなれば、福島氏が寿桂尼を拘束する必要も無いですしね。
寿桂尼が今川義元の実母だから人質としての利用価値があったと解釈されていますからこれが否定されてしまうとこの理論は根底から崩壊。
そもそも本当に福島氏が寿桂尼を拘束したのか?
当然、最初の疑問に立ち返るわけですね。
結局は寿桂尼と福島氏の接触は、今川家の象徴として存在する寿桂尼と今川家重臣として存在する福島氏が手を結んだと見た方が説得力が生まれます。
さくらねこさんのご指摘の通り、今川義元は福島氏を今川家中から排除することに成功したので福島氏が実母の可能性はほぼ無いでしょう。
そこで気になるのは更にこの後に続く親北条氏反武田氏外交路線の転換。
一般的には北条氏と結ぶ今川義元が武田氏との関係を修復し更には取り込みを図り三国同盟を画策するも北条氏綱がこれを嫌い敵対という流ですが、今一度の再考の余地がありそうな気がしないでもないです。
>「福島氏」の可能性は難しいですね。
更に言うなれば、福島氏が寿桂尼を拘束する必要も無いですしね。
寿桂尼が今川義元の実母だから人質としての利用価値があったと解釈されていますからこれが否定されてしまうとこの理論は根底から崩壊。
そもそも本当に福島氏が寿桂尼を拘束したのか?
当然、最初の疑問に立ち返るわけですね。
結局は寿桂尼と福島氏の接触は、今川家の象徴として存在する寿桂尼と今川家重臣として存在する福島氏が手を結んだと見た方が説得力が生まれます。
さくらねこさんのご指摘の通り、今川義元は福島氏を今川家中から排除することに成功したので福島氏が実母の可能性はほぼ無いでしょう。
そこで気になるのは更にこの後に続く親北条氏反武田氏外交路線の転換。
一般的には北条氏と結ぶ今川義元が武田氏との関係を修復し更には取り込みを図り三国同盟を画策するも北条氏綱がこれを嫌い敵対という流ですが、今一度の再考の余地がありそうな気がしないでもないです。
>>[168]
今の人は歴史的事実を現代の価値観で咀嚼しちゃう傾向がありますからね。
批判は自身の思考の狭量さを露呈ることになりますから気を付けないといけませんね。
音楽で何故ダメなのかを言うなればこれは学問とは掛け離れた価値観、子供への影響力の強いが故に物事の分別が付かない人は何が悪いのか分からないがために避けるべきなのかと。
映画で例えると分かり易いですが、表現の自由は良いとしても年齢制限が掛かりますよね。
音楽にも品性を欠いたものに年齢制限を掛けたらいいのですがその点を考慮せずに垂れ流しなので問題化してしまったと見るべきでしょう。
まあ、今時の人には理解し難い“配慮”を欠いた顛末と言えますね。
こんな感じで偉そうに書いてみました。
個人についてというよりも時代の感覚が麻痺しているのかな?
今の人は歴史的事実を現代の価値観で咀嚼しちゃう傾向がありますからね。
批判は自身の思考の狭量さを露呈ることになりますから気を付けないといけませんね。
音楽で何故ダメなのかを言うなればこれは学問とは掛け離れた価値観、子供への影響力の強いが故に物事の分別が付かない人は何が悪いのか分からないがために避けるべきなのかと。
映画で例えると分かり易いですが、表現の自由は良いとしても年齢制限が掛かりますよね。
音楽にも品性を欠いたものに年齢制限を掛けたらいいのですがその点を考慮せずに垂れ流しなので問題化してしまったと見るべきでしょう。
まあ、今時の人には理解し難い“配慮”を欠いた顛末と言えますね。
こんな感じで偉そうに書いてみました。
個人についてというよりも時代の感覚が麻痺しているのかな?
>>[170]
彼はクイズが得意ではありますが多分それだけしかないのかと思います。
彼は世界史の専門家ではなくあくまでもクイズとして強いだけですから回答は出来ても単語をパーツにして論文を書くには知識の限界、というかそうした訓練すらしていない様に思います。
時代や世界を明確にイメージすることが苦手なタイプなのかもしれませんね。
言うなれば世界史の話を論理立てて講義するのは厳しいでところでしょう。
多分、一般常識の視点でしか表現できないという感じでしょうか。
仰る通り「脊髄反射」ではありませんが思い付きを口にするのは得意そうですね。
まあ、お年寄りでもありますからそれが普通というところでもありますが。
彼はクイズが得意ではありますが多分それだけしかないのかと思います。
彼は世界史の専門家ではなくあくまでもクイズとして強いだけですから回答は出来ても単語をパーツにして論文を書くには知識の限界、というかそうした訓練すらしていない様に思います。
時代や世界を明確にイメージすることが苦手なタイプなのかもしれませんね。
言うなれば世界史の話を論理立てて講義するのは厳しいでところでしょう。
多分、一般常識の視点でしか表現できないという感じでしょうか。
仰る通り「脊髄反射」ではありませんが思い付きを口にするのは得意そうですね。
まあ、お年寄りでもありますからそれが普通というところでもありますが。
>>[178]
ご存知の通り私は城跡や古戦場、他に桜巡りなどの景勝地巡りをしていますのでこの手の倒木はよく見かけます。
今年も栃沢のシダレザクラを見に行った時も朽ちた音も無く落下した枝が直撃してかなり痛い思いをしました。
大木は勿論ですが1m級の枝でも朽ちている分、鈍器で殴られるくらいの破壊力はありますので当たり所が悪ければ即死でしょうね。
お金を払って入場する施設は管理が行き届いていますし観光客が多く集まる景勝地でも市町村やボランティアが整備していますから問題はほぼ無いですけどマイナーな場所や人が踏み入れない穴場はよくあるお話なので要注意ですね。
城跡でも埼玉県の天神山城なんかはかなり危険で動けない状況になったら確実にあの世へ行けます。
神社でも静岡県の浅間神社で大規模な倒木を見かけましたが人が多いところなので数日後には数十個に分けて解体されていくつかはイスとして利用されていましたけど。
仕事で毎日山に入っている人でも闇雲に奥深く立ち入ったりしないらしいです。
一年に一度程度の私の様な遊び感覚で山に踏み入れるタイプは特に慎重にですね。
まあ、結局は痛い思いをしないと学習はしないのですが。
今は老齢化や人手不足で10年前と違いますから頻繁に起きているという印象ですね。
ご存知の通り私は城跡や古戦場、他に桜巡りなどの景勝地巡りをしていますのでこの手の倒木はよく見かけます。
今年も栃沢のシダレザクラを見に行った時も朽ちた音も無く落下した枝が直撃してかなり痛い思いをしました。
大木は勿論ですが1m級の枝でも朽ちている分、鈍器で殴られるくらいの破壊力はありますので当たり所が悪ければ即死でしょうね。
お金を払って入場する施設は管理が行き届いていますし観光客が多く集まる景勝地でも市町村やボランティアが整備していますから問題はほぼ無いですけどマイナーな場所や人が踏み入れない穴場はよくあるお話なので要注意ですね。
城跡でも埼玉県の天神山城なんかはかなり危険で動けない状況になったら確実にあの世へ行けます。
神社でも静岡県の浅間神社で大規模な倒木を見かけましたが人が多いところなので数日後には数十個に分けて解体されていくつかはイスとして利用されていましたけど。
仕事で毎日山に入っている人でも闇雲に奥深く立ち入ったりしないらしいです。
一年に一度程度の私の様な遊び感覚で山に踏み入れるタイプは特に慎重にですね。
まあ、結局は痛い思いをしないと学習はしないのですが。
今は老齢化や人手不足で10年前と違いますから頻繁に起きているという印象ですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
-日本史- 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-