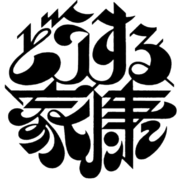|
|
|
|
コメント(15)
面白かったよ。
四天王の演出とか、中入り戦術とか、堀を掘り進める意図とか、突然の直政の母の回想とか(私はどうしても脳内で貫地谷しほりに変換するけど(直虎民なので))、井伊直政と本多正信の共通点をふたりで話し合う所とか。石川数正出奔前夜って感じの描写とか、信雄の小物っぷり描写とか。
見所たくさん。
「弱く 臆病であった このわしがなぜ ここまで やってこられたのか…。
今川義元に学び 織田信長に鍛えられ武田信玄から兵法を学び取ったからじゃ。
そして何より 良き家臣たちの恵まれたからである」
↑
このセリフとか良かった。
何よりも予告で、上総広常…じゃなく真田昌幸の出演とか。
と、さんざん褒めた。(にこっ)
そしてこの画像を貼る。
大きくして読んでみて。笑
↓
「何故、積み重ねてこなかったのか」
四天王の演出とか、中入り戦術とか、堀を掘り進める意図とか、突然の直政の母の回想とか(私はどうしても脳内で貫地谷しほりに変換するけど(直虎民なので))、井伊直政と本多正信の共通点をふたりで話し合う所とか。石川数正出奔前夜って感じの描写とか、信雄の小物っぷり描写とか。
見所たくさん。
「弱く 臆病であった このわしがなぜ ここまで やってこられたのか…。
今川義元に学び 織田信長に鍛えられ武田信玄から兵法を学び取ったからじゃ。
そして何より 良き家臣たちの恵まれたからである」
↑
このセリフとか良かった。
何よりも予告で、上総広常…じゃなく真田昌幸の出演とか。
と、さんざん褒めた。(にこっ)
そしてこの画像を貼る。
大きくして読んでみて。笑
↓
「何故、積み重ねてこなかったのか」
まあ仕方がないんですけど、セットだから、鍬を打ち込んでも刺さらないし、土がえぐれない
しかし私が畑で汗だくになって土を掘っても顔にも腕にも土はつかんよ やりすぎ
やりすぎ
で、平八郎が川を挟んで秀吉と対峙したのは、やっぱ撮影できなかったよね CGの限界
CGの限界 仕方がない
仕方がない
途中から、この戦は日露戦争に似てるのかもしれないなぁと思ってました
来たものを全力で追い払って、めっちゃ達成感があったんだけど、本隊は全く傷ついていなくて、戦後の交渉でなんでやねん状態に陥る…
直政のお母さんはなんで能衣装みたいな装束だったのかしらん?井伊家の格の高さを表しているのかな そんで直政も牛若丸みたいな着物だし
そんで直政も牛若丸みたいな着物だし
でも、ムロ秀吉のやなやつ感とか、池田さんと森さんの雰囲気とか、いい感じに楽しめました
そう、普通の大河ドラマです
特に文句のない
それでいい
しかし私が畑で汗だくになって土を掘っても顔にも腕にも土はつかんよ
で、平八郎が川を挟んで秀吉と対峙したのは、やっぱ撮影できなかったよね
途中から、この戦は日露戦争に似てるのかもしれないなぁと思ってました
来たものを全力で追い払って、めっちゃ達成感があったんだけど、本隊は全く傷ついていなくて、戦後の交渉でなんでやねん状態に陥る…
直政のお母さんはなんで能衣装みたいな装束だったのかしらん?井伊家の格の高さを表しているのかな
でも、ムロ秀吉のやなやつ感とか、池田さんと森さんの雰囲気とか、いい感じに楽しめました
そう、普通の大河ドラマです
特に文句のない
それでいい
>>[3]
>しかし私が畑で汗だくになって土を掘っても顔にも腕にも土はつかんよ
いや、軍勢が隠れるくらいだから数mの堀だよ。3m〜8mの深さがあったらしい。
畑のような平面を掘るのとは違う。だから土だらけにはなってもおかしくはない。
直政のお母さんの衣装の謎。
ありゃ何ぞ? 能だ。
どうしてどうしてこうなった。(NHK教育の「マルチスコープ」より)
あちこち検索してみた。
まずあの女優さんは、中島亜梨沙さんという人で、真田丸で昌幸が通い詰める遊女・吉野太夫役の人。
で、ここに行き付いた。
https://note.com/good_clover342/n/n12c88683e67c
=================
先日放送された大河ドラマ「どうする家康」
で井伊直政の回想シーンで直政の母・奥山ひよ
の衣装が気になった。
能楽を少々かじったことのある身としては
おっ!となった。
これはおそらく「唐織」だな。
唐織とは能楽で女性を演じるときよく身につける能装束である。
赤色の入った唐織はとくに若い女性を現す。
代表的な演目だと「熊野(ゆや)」がある。
熊野という女性が主人公で、田舎の娘でありながらその美貌で平宗盛の寵愛を受け都で暮らしていたが、ある日、母が病で危篤と知り帰りたいと宗盛に懇願するも許されず…という話だ。
この能「熊野」と今回のドラマの装束がそっくりだと思った。もっとも勘違いかもしれないが…。
さらに共通点というと、熊野の故郷が遠江であること。
井伊直政の出生地も遠江である。
そう考えると、ドラマも興味深いものになる
熊野は母と娘の物語で
ドラマでは母と息子の物語である。
お前は悪童だけど母に似て顔だけはいい、
と直政にいう母ひよ
嬉しそうにいうが顔はどこか悲しげだ。
暗がりでも分かる赤色の装束は
井伊直政がやがて「井伊の赤鬼」と呼ばれることから井伊家のイメージカラーともとれるが
それだけではない気がする。
じつは能「熊野」もまた一見煌びやかな装束を纏う美女の熊野の悲しみを魅せる演目でもあるからだ。
母として、息子の出世を喜びたいのと
息子が死ぬかもしれない不安がドラマでは明るい装束と暗い部屋で表現されているのかもしれない。
白粉を塗った顔もまさしく暗い部屋で能面のように浮き上がっている。
滝と樹々を鏡板に見立てた能舞台のようだ
SNSを見てると、こんなシーンいらないというのをちらほら見かけたが、
この母子のシーンはいわば能楽でいう「中入り」だったのではないかと思う。
(ドラマでも「中入り」というのが合戦の戦術の名称としてでてくるがこれとは別)
前半で堀を掘るだけの泥だらけの井伊直政含めた徳川四天王が
後半で華々しく甲冑姿で合戦を狂い舞い踊る
後半を視聴者に印象づけるための
いっときの静寂、間を演出づける
「中入り」だったのではないだろうか。
>しかし私が畑で汗だくになって土を掘っても顔にも腕にも土はつかんよ
いや、軍勢が隠れるくらいだから数mの堀だよ。3m〜8mの深さがあったらしい。
畑のような平面を掘るのとは違う。だから土だらけにはなってもおかしくはない。
直政のお母さんの衣装の謎。
ありゃ何ぞ? 能だ。
どうしてどうしてこうなった。(NHK教育の「マルチスコープ」より)
あちこち検索してみた。
まずあの女優さんは、中島亜梨沙さんという人で、真田丸で昌幸が通い詰める遊女・吉野太夫役の人。
で、ここに行き付いた。
https://note.com/good_clover342/n/n12c88683e67c
=================
先日放送された大河ドラマ「どうする家康」
で井伊直政の回想シーンで直政の母・奥山ひよ
の衣装が気になった。
能楽を少々かじったことのある身としては
おっ!となった。
これはおそらく「唐織」だな。
唐織とは能楽で女性を演じるときよく身につける能装束である。
赤色の入った唐織はとくに若い女性を現す。
代表的な演目だと「熊野(ゆや)」がある。
熊野という女性が主人公で、田舎の娘でありながらその美貌で平宗盛の寵愛を受け都で暮らしていたが、ある日、母が病で危篤と知り帰りたいと宗盛に懇願するも許されず…という話だ。
この能「熊野」と今回のドラマの装束がそっくりだと思った。もっとも勘違いかもしれないが…。
さらに共通点というと、熊野の故郷が遠江であること。
井伊直政の出生地も遠江である。
そう考えると、ドラマも興味深いものになる
熊野は母と娘の物語で
ドラマでは母と息子の物語である。
お前は悪童だけど母に似て顔だけはいい、
と直政にいう母ひよ
嬉しそうにいうが顔はどこか悲しげだ。
暗がりでも分かる赤色の装束は
井伊直政がやがて「井伊の赤鬼」と呼ばれることから井伊家のイメージカラーともとれるが
それだけではない気がする。
じつは能「熊野」もまた一見煌びやかな装束を纏う美女の熊野の悲しみを魅せる演目でもあるからだ。
母として、息子の出世を喜びたいのと
息子が死ぬかもしれない不安がドラマでは明るい装束と暗い部屋で表現されているのかもしれない。
白粉を塗った顔もまさしく暗い部屋で能面のように浮き上がっている。
滝と樹々を鏡板に見立てた能舞台のようだ
SNSを見てると、こんなシーンいらないというのをちらほら見かけたが、
この母子のシーンはいわば能楽でいう「中入り」だったのではないかと思う。
(ドラマでも「中入り」というのが合戦の戦術の名称としてでてくるがこれとは別)
前半で堀を掘るだけの泥だらけの井伊直政含めた徳川四天王が
後半で華々しく甲冑姿で合戦を狂い舞い踊る
後半を視聴者に印象づけるための
いっときの静寂、間を演出づける
「中入り」だったのではないだろうか。
>>[8]
能衣装の件、なるほどです
で、土の話です
例えば秀吉が、石垣を作る場所を区分けして、チームで競わせたという話は有名ですが、徳川軍ではこの大工事をどうやったのか、もう少しこう、なるほどなぁと思わせて欲しかったのです。
平八郎も小平太も長政も、作業をやってるようでやってないのに、ただ雑兵の肩を叩いて「やれよ 」って言うだけとか、掛け声をかけるだけとか、学芸会並みじゃないですか
」って言うだけとか、掛け声をかけるだけとか、学芸会並みじゃないですか
もう少し、どんな体制を組んで、組織だってやっていたのかとか、描いて欲しかったんですよ。
彼らの下に、各部の責任者がいて、その人達が意気込んでやっているような描写があれば、小平太たちの顔に土なんかいらないんです
能衣装の件、なるほどです
で、土の話です
例えば秀吉が、石垣を作る場所を区分けして、チームで競わせたという話は有名ですが、徳川軍ではこの大工事をどうやったのか、もう少しこう、なるほどなぁと思わせて欲しかったのです。
平八郎も小平太も長政も、作業をやってるようでやってないのに、ただ雑兵の肩を叩いて「やれよ
もう少し、どんな体制を組んで、組織だってやっていたのかとか、描いて欲しかったんですよ。
彼らの下に、各部の責任者がいて、その人達が意気込んでやっているような描写があれば、小平太たちの顔に土なんかいらないんです
>>[9]
>もう少しこう、なるほどなぁと思わせて欲しかったのです。
私はこの場面、全然違和感なかったです。
戦いの戦術とかどれも拾ってたら尺が足りないですし、ドラマの焦点がぼけるし、「〇〇の戦いに勝利しました」で済まされる所をあそこまで描いたら、あとは脳内変換だと。
>平八郎も小平太も長政も、作業をやってるようでやってないのに、ただ雑兵の肩を叩いて「やれよ」って言うだけとか、掛け声をかけるだけとか
実際の所、平八郎も小平太も作業現場に出てたかは分かりません。
上に立つものは雑兵と一緒に働くと全体が見えなくなりますので。
ただこの5日で仕上げた大がかりな堀の作成は、ほぼいくさです。雑兵の間に入って声をかけていくってのは、雑兵の士気にも関わりますし、かなりアリだと思っています。
私はかなり丁寧な描写と感じましたので。
それよりも軍師官兵衛で、秀吉が「さすが官兵衛」だけでどんどん事が運んだ時の不満たるや。
その「軍師」っぷりが観たかったのに。(何年も前の不満 笑)
私が「お。なかなか良いな」と思っている所。
小平太と正信のキャラがかぶっていない所なんです。
ふたりとも武の人ではなく智の人です。
平八郎は小平太に「おまえいつの間にこんな戦術をまとめられるように」と言われ
小平太は「武ではどんなに頑張ってもおまえにはかなわない。だったら脳を鍛えるしかなかろう」と言ったこと。
小平太は武でも努力するけど智の人。
正信は、武はまったく不参加だけど智の人。
でもね、その智の部分がふたりはかぶっていない描き方なんですよ。
正信は戦略家なんです。
小平太は戦術が的確なんです。
戦略と戦術は違っていて、戦略はすごく大きな「我々はどうしたらいいか」なんです。
戦術は、そのための具体的な策。
今回そのあたりの描き分けられて良かったと思いました。
>もう少しこう、なるほどなぁと思わせて欲しかったのです。
私はこの場面、全然違和感なかったです。
戦いの戦術とかどれも拾ってたら尺が足りないですし、ドラマの焦点がぼけるし、「〇〇の戦いに勝利しました」で済まされる所をあそこまで描いたら、あとは脳内変換だと。
>平八郎も小平太も長政も、作業をやってるようでやってないのに、ただ雑兵の肩を叩いて「やれよ」って言うだけとか、掛け声をかけるだけとか
実際の所、平八郎も小平太も作業現場に出てたかは分かりません。
上に立つものは雑兵と一緒に働くと全体が見えなくなりますので。
ただこの5日で仕上げた大がかりな堀の作成は、ほぼいくさです。雑兵の間に入って声をかけていくってのは、雑兵の士気にも関わりますし、かなりアリだと思っています。
私はかなり丁寧な描写と感じましたので。
それよりも軍師官兵衛で、秀吉が「さすが官兵衛」だけでどんどん事が運んだ時の不満たるや。
その「軍師」っぷりが観たかったのに。(何年も前の不満 笑)
私が「お。なかなか良いな」と思っている所。
小平太と正信のキャラがかぶっていない所なんです。
ふたりとも武の人ではなく智の人です。
平八郎は小平太に「おまえいつの間にこんな戦術をまとめられるように」と言われ
小平太は「武ではどんなに頑張ってもおまえにはかなわない。だったら脳を鍛えるしかなかろう」と言ったこと。
小平太は武でも努力するけど智の人。
正信は、武はまったく不参加だけど智の人。
でもね、その智の部分がふたりはかぶっていない描き方なんですよ。
正信は戦略家なんです。
小平太は戦術が的確なんです。
戦略と戦術は違っていて、戦略はすごく大きな「我々はどうしたらいいか」なんです。
戦術は、そのための具体的な策。
今回そのあたりの描き分けられて良かったと思いました。
>>[10]
そうですかー、文句なしですか
確かに、官兵衛の軍師ぶりも、竹中半兵衛との違いも、もう少し見たかったし、
長谷川麒麟光秀の、実は良い領主だったところとか、部下とのあれこれとか、めっちゃくちゃに働かされて疲弊していたところとか、もっとやってほしかった(贅沢、、、コロナだったからしょうがない)
江とか篤姫とか八重の桜とか直虎とかは、意外とその主人公本人の細かながんばりがしっかり見られて、あとの人物や歴史の流れの説明とかでごまかされたりはしていなかったのが私としては好感でした。
今回、徳川の家臣団は、しっかりと描かれていていいですよね
小平太の杉野さんは、よく似合ってると思います
なぜ頑なに本多作左衛門を出さないのかはプリプリですが
そうですかー、文句なしですか
確かに、官兵衛の軍師ぶりも、竹中半兵衛との違いも、もう少し見たかったし、
長谷川麒麟光秀の、実は良い領主だったところとか、部下とのあれこれとか、めっちゃくちゃに働かされて疲弊していたところとか、もっとやってほしかった(贅沢、、、コロナだったからしょうがない)
江とか篤姫とか八重の桜とか直虎とかは、意外とその主人公本人の細かながんばりがしっかり見られて、あとの人物や歴史の流れの説明とかでごまかされたりはしていなかったのが私としては好感でした。
今回、徳川の家臣団は、しっかりと描かれていていいですよね
小平太の杉野さんは、よく似合ってると思います
なぜ頑なに本多作左衛門を出さないのかはプリプリですが
2回目視聴。
この32回「小牧長久手の激闘」は、今までで一番バランスが良く、これ1回で1篇の映画を観てるようだった。
2回目なので余裕を持って、石川数正に注目して観てみた。
終始、他と比べてずっと表情は重く、意見は皆と真逆の「和睦」推し。
それは勝利後も変わらず。
まさに出奔前夜だ。
皆と違うのは、前回数正だけがひとり秀吉の元に赴いて、秀吉の権勢を目の当たりにしていること。
徳川四天王。
こう呼ばれるようになったのはこの戦いの頃からだった模様。
今回、それぞれに見所を用意し、華麗に紹介している。そして正信も時々触れている。
数正は蚊帳の外感というか居場所はない?感? 自らの限界感?
忠勝、平八郎、直政。みんな成長してきている。
そうして軍を盛り上げ、精神的にも皆の支柱となっている酒井忠次左衛門尉。
たしかに数正の居場所はなくなってきている。
今回は家康方勝利の話だし、四天王爆誕的な明るい話題なのだけれど、言い換えれば「光」の話なのだけれど、それだけじゃなく、そこに数正という「影」の存在がある。
そのコントラストが、1篇のお話としてみても完成度が高いなと思った。
数正だけがたぶん大局的に物事を見ている。
目先の戦いに勝利した織田信雄=徳川軍だけれど、大局的にみれば秀吉はまた攻めてくるし、コテンパンにやっつけてしまった以上、和議は結べない。だとしたら徳川に勝ち目はない。
数正的にはそういう思考なのだろうが、その事に誰も気が付いていない。
本多正信と井伊直正の話。
「我らふたりとも、かつては殿の命を狙った者。なんで許されたんだろうね?」
このふたりは気が付いてないかもだけど、理由がある。
二人とも「民の代弁者」であったからだ。家康は自分に非があると認識していたからだ。
そのあたりが他の三英傑と違う。
信長は独善的で、自分の命を火縄銃で狙った善住坊を鋸(のこぎり)引きで残酷に殺したし。(黄金の日日)
秀吉はコンプレックスの塊で、捨(すて)が生まれて壁に悪口を書かれた時に門番の親兄弟、さらに隣近所の住人まで磔(はりつけ)にしろと実行させた。(真田丸)
家康にはそういう狂気はない。
この32回「小牧長久手の激闘」は、今までで一番バランスが良く、これ1回で1篇の映画を観てるようだった。
2回目なので余裕を持って、石川数正に注目して観てみた。
終始、他と比べてずっと表情は重く、意見は皆と真逆の「和睦」推し。
それは勝利後も変わらず。
まさに出奔前夜だ。
皆と違うのは、前回数正だけがひとり秀吉の元に赴いて、秀吉の権勢を目の当たりにしていること。
徳川四天王。
こう呼ばれるようになったのはこの戦いの頃からだった模様。
今回、それぞれに見所を用意し、華麗に紹介している。そして正信も時々触れている。
数正は蚊帳の外感というか居場所はない?感? 自らの限界感?
忠勝、平八郎、直政。みんな成長してきている。
そうして軍を盛り上げ、精神的にも皆の支柱となっている酒井忠次左衛門尉。
たしかに数正の居場所はなくなってきている。
今回は家康方勝利の話だし、四天王爆誕的な明るい話題なのだけれど、言い換えれば「光」の話なのだけれど、それだけじゃなく、そこに数正という「影」の存在がある。
そのコントラストが、1篇のお話としてみても完成度が高いなと思った。
数正だけがたぶん大局的に物事を見ている。
目先の戦いに勝利した織田信雄=徳川軍だけれど、大局的にみれば秀吉はまた攻めてくるし、コテンパンにやっつけてしまった以上、和議は結べない。だとしたら徳川に勝ち目はない。
数正的にはそういう思考なのだろうが、その事に誰も気が付いていない。
本多正信と井伊直正の話。
「我らふたりとも、かつては殿の命を狙った者。なんで許されたんだろうね?」
このふたりは気が付いてないかもだけど、理由がある。
二人とも「民の代弁者」であったからだ。家康は自分に非があると認識していたからだ。
そのあたりが他の三英傑と違う。
信長は独善的で、自分の命を火縄銃で狙った善住坊を鋸(のこぎり)引きで残酷に殺したし。(黄金の日日)
秀吉はコンプレックスの塊で、捨(すて)が生まれて壁に悪口を書かれた時に門番の親兄弟、さらに隣近所の住人まで磔(はりつけ)にしろと実行させた。(真田丸)
家康にはそういう狂気はない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
「どうする家康」感想コミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
「どうする家康」感想コミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90069人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208326人
- 3位
- 酒好き
- 170699人