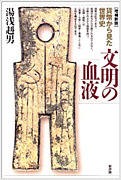|
|
|
|
コメント(33)
■世界の一体化(Wikipedia日本語版)
世界の一体化(せかいのいったいか)では、世界の歴史において、交通や通信の発達などによって、諸地域間の分業システム(近代世界システム)が形成され、固定化され、また幾度か再編されたその全過程をあらわす。
歴史事象としては、16世紀の大航海時代以降本格化し、現在もなお進行中である。
主として歴史学上および歴史教育における概念であり、とりわけ日本における世界史教育では平成11年以降学習指導要領のなかで基軸となる観点のひとつとして盛り込まれた。
「世界の一体化」前史としてのモンゴル帝国 [編集]
「世界史A」新学習指導要領では、前近代を「諸地域世界と交流圏」として扱うこととするのは、上述のとおりであるが、そのなかで諸地域相互の交流を促進し、「世界の一体化」につながるような交流圏の成立に寄与したのがモンゴル帝国であった。
すなわち、13世紀、ユーラシア大陸ではモンゴル人が、東アジアから東ヨーロッパ、イスラーム世界を覆う空前の大帝国を建設し、それにより各地で勢力の交替が起こったのである。
モンゴルによる征服は人びとに恐怖の記憶を刻んだが、その一方で「タタールの平和(パクス・タタリカ)」という言葉に表現されるように、モンゴル人によってユーラシアと北アフリカの諸地域が政治的、経済的にたがいに結びつけられ、国際色豊かな統治体制とそれに支えられた遠隔地商業など東西交流が、その宗教的寛容も相まって空前の繁栄ぶりを呈した。
情報技術が整備され、世界紙幣がつくられ、ジャムチ(駅伝制)が各地を結んだ。
杉山正明、岡田英弘らを主とする中央ユーラシア史の研究者からは、この13、14世紀の大モンゴル時代を世界史におけるひとつの分水嶺ととらえ、「近代」につながる諸要素を指摘する声があがっている[21][22]。
杉山らは、モンゴル帝国自身が陸上だけでなく海上の帝国の面もそなえて海上ルートのシステム化をも推進した結果、以後の陸上国家は単なる陸上国家ではなくなったのであり、また、16世紀に隆盛をほこったロシア帝国、オスマン帝国、ムガル帝国、明朝などの大規模国家(ユーラシア近世帝国)はモンゴル帝国およびその地方政権の後継国家としての性格を有し、いわゆる「大航海時代」もモンゴル時代を前提にしなければ理解しにくいことを指摘しており、比較文明史の湯浅赳男、世界システム論の山下範久らの論者もこの観点に着目した所論を展開している[10][14]。
また、堺屋太一など、モンゴルが世界史に果たした役割を重視する知識人も少なくない。『堺屋太一が解くチンギス・ハンの世界』などがそれに該当する[23]。堺屋は、このなかで、大量報復思想、信仰の自由、「世界」の3つを「ジンギス・カンの三大発明」と呼称し、従来の統治体制にない3つの思想と手段だとして高く評価している。
13、14世紀のヨーロッパでは、西欧世界が十字軍や東方植民、イベリア半島でのレコンキスタなどによる膨張運動が展開され、これらはいずれもイスラーム世界に対するモンゴルの衝撃と深いかかわりを有していた。
そして、そのなかで特に地中海沿岸やバルト海沿岸、および両者をつなぐ内陸部に顕著な都市の発達がみられ、王権の伸張という新しい歴史の動きを生んでいた。
そしてまた、ポストモンゴル時代の遊牧民は、近世以後も諸帝国をむすびつける役割を果たした。
杉山は、「ポスト・モンゴル時代」のティムール帝国はじめ一連のモンゴル国家、明代モンゴルから「最後の遊牧王国」ドゥッラーニー朝(アフガニスタン)までの流れを清、オスマン、ムガルとともに「第五の波」と称している[21]。
モンゴルによって生じたグローバリゼーションの芽は、16世紀以降の「世界の一体化」と深く呼応していた。
大航海時代における海洋の時代をむかえるまで、ユーラシア内陸部では馬が一種の船の役割を果たし、古代から中世にかけて歴史的に形成されてきた諸世界を結びつけたのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%8C%96
世界の一体化(せかいのいったいか)では、世界の歴史において、交通や通信の発達などによって、諸地域間の分業システム(近代世界システム)が形成され、固定化され、また幾度か再編されたその全過程をあらわす。
歴史事象としては、16世紀の大航海時代以降本格化し、現在もなお進行中である。
主として歴史学上および歴史教育における概念であり、とりわけ日本における世界史教育では平成11年以降学習指導要領のなかで基軸となる観点のひとつとして盛り込まれた。
「世界の一体化」前史としてのモンゴル帝国 [編集]
「世界史A」新学習指導要領では、前近代を「諸地域世界と交流圏」として扱うこととするのは、上述のとおりであるが、そのなかで諸地域相互の交流を促進し、「世界の一体化」につながるような交流圏の成立に寄与したのがモンゴル帝国であった。
すなわち、13世紀、ユーラシア大陸ではモンゴル人が、東アジアから東ヨーロッパ、イスラーム世界を覆う空前の大帝国を建設し、それにより各地で勢力の交替が起こったのである。
モンゴルによる征服は人びとに恐怖の記憶を刻んだが、その一方で「タタールの平和(パクス・タタリカ)」という言葉に表現されるように、モンゴル人によってユーラシアと北アフリカの諸地域が政治的、経済的にたがいに結びつけられ、国際色豊かな統治体制とそれに支えられた遠隔地商業など東西交流が、その宗教的寛容も相まって空前の繁栄ぶりを呈した。
情報技術が整備され、世界紙幣がつくられ、ジャムチ(駅伝制)が各地を結んだ。
杉山正明、岡田英弘らを主とする中央ユーラシア史の研究者からは、この13、14世紀の大モンゴル時代を世界史におけるひとつの分水嶺ととらえ、「近代」につながる諸要素を指摘する声があがっている[21][22]。
杉山らは、モンゴル帝国自身が陸上だけでなく海上の帝国の面もそなえて海上ルートのシステム化をも推進した結果、以後の陸上国家は単なる陸上国家ではなくなったのであり、また、16世紀に隆盛をほこったロシア帝国、オスマン帝国、ムガル帝国、明朝などの大規模国家(ユーラシア近世帝国)はモンゴル帝国およびその地方政権の後継国家としての性格を有し、いわゆる「大航海時代」もモンゴル時代を前提にしなければ理解しにくいことを指摘しており、比較文明史の湯浅赳男、世界システム論の山下範久らの論者もこの観点に着目した所論を展開している[10][14]。
また、堺屋太一など、モンゴルが世界史に果たした役割を重視する知識人も少なくない。『堺屋太一が解くチンギス・ハンの世界』などがそれに該当する[23]。堺屋は、このなかで、大量報復思想、信仰の自由、「世界」の3つを「ジンギス・カンの三大発明」と呼称し、従来の統治体制にない3つの思想と手段だとして高く評価している。
13、14世紀のヨーロッパでは、西欧世界が十字軍や東方植民、イベリア半島でのレコンキスタなどによる膨張運動が展開され、これらはいずれもイスラーム世界に対するモンゴルの衝撃と深いかかわりを有していた。
そして、そのなかで特に地中海沿岸やバルト海沿岸、および両者をつなぐ内陸部に顕著な都市の発達がみられ、王権の伸張という新しい歴史の動きを生んでいた。
そしてまた、ポストモンゴル時代の遊牧民は、近世以後も諸帝国をむすびつける役割を果たした。
杉山は、「ポスト・モンゴル時代」のティムール帝国はじめ一連のモンゴル国家、明代モンゴルから「最後の遊牧王国」ドゥッラーニー朝(アフガニスタン)までの流れを清、オスマン、ムガルとともに「第五の波」と称している[21]。
モンゴルによって生じたグローバリゼーションの芽は、16世紀以降の「世界の一体化」と深く呼応していた。
大航海時代における海洋の時代をむかえるまで、ユーラシア内陸部では馬が一種の船の役割を果たし、古代から中世にかけて歴史的に形成されてきた諸世界を結びつけたのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%8C%96
■インド人口史−史料と推計
この記事は、ペンシルバニア大学 のデュランドが1974年にまとめた「Historical Estimates of World Population: An Evaluation」という記事の中の、インド人口史に関する部分を抜き出して、数値の出典や、デュランドが記載していない19世紀以降の 数値を追記したものです。
社会学者アンドレ-グンダー・フランクの書籍「リオリエント(1998年)」や、湯浅赳男「文明の人口史」(1999年)などで引用されているインド史上の人口推計値には、 いったいどのような根拠があるのかを調べてみたものです。
http://heartland.geocities.jp/zae06141/history_of_indian_population.html
この記事は、ペンシルバニア大学 のデュランドが1974年にまとめた「Historical Estimates of World Population: An Evaluation」という記事の中の、インド人口史に関する部分を抜き出して、数値の出典や、デュランドが記載していない19世紀以降の 数値を追記したものです。
社会学者アンドレ-グンダー・フランクの書籍「リオリエント(1998年)」や、湯浅赳男「文明の人口史」(1999年)などで引用されているインド史上の人口推計値には、 いったいどのような根拠があるのかを調べてみたものです。
http://heartland.geocities.jp/zae06141/history_of_indian_population.html
■SHARISHARISHARI
http://sharisharishari.com/
Reread Cybernetics サイバネティクス再読
http://sharisharishari.com/2012/12/rereadcybernetics/
[pdf]第8章 情報,言語,社会
Contents
1 組織的な活動と情報伝達
2 社会の恒常性と情報伝達
3 社会科学と自然科学
ウェーバーの理論との関連性
文明を分析するためには、その文明の価値を対象化するばかりでなく、分析者の価値をも対象化することもまた必要であり、これを彼[ウェーバー]は<価値自由>とした。
そしてこの価値自由[…]は、自覚的に分析者の価値関心によって構成したところの<理念型>でなければならないとした。(湯浅赳男)
http://sharisharishari.com/wp-content/uploads/2012/07/Chapter-8.pdf
http://sharisharishari.com/
Reread Cybernetics サイバネティクス再読
http://sharisharishari.com/2012/12/rereadcybernetics/
[pdf]第8章 情報,言語,社会
Contents
1 組織的な活動と情報伝達
2 社会の恒常性と情報伝達
3 社会科学と自然科学
ウェーバーの理論との関連性
文明を分析するためには、その文明の価値を対象化するばかりでなく、分析者の価値をも対象化することもまた必要であり、これを彼[ウェーバー]は<価値自由>とした。
そしてこの価値自由[…]は、自覚的に分析者の価値関心によって構成したところの<理念型>でなければならないとした。(湯浅赳男)
http://sharisharishari.com/wp-content/uploads/2012/07/Chapter-8.pdf
■WEBマガジン「風」 連想出版
http://kaze.shinshomap.info/
新書マップ
http://shinshomap.info/search.php
http://bookshelf.shinshomap.info/
11. 食生活
フランス料理とワイン
『フランス料理を料理する : 文明の交差点としてのフランス料理』(湯浅赳男著、新書y)もまた、フランス料理の歴史と魅力を余すことなく紹介した力作である。
とくに、中華とフランス料理の違いについての考察が興味深い。
フランス料理は外交や文化交流の一コマとして世界に普及していったのに対し、中華料理は世界に分散した漢人労働者の食堂として普及した。
日本のサラリーマンが昼飯にはチャーハンやラーメンを食い、結婚式ではフランス料理を食べるのには、そのような背景があったのである。
中華とフランス料理では食材と調理法が違うという指摘もなるほどと思わせる。
内陸部が多い中華の高級食材の大半は乾物なのに対し、フランスでは地方でとれた新鮮な食材を使う。
さらに、中華の調理法は蒸籠が基本であるのに対し、フランスではオーブンを使い、これが両者の特徴に決定的な違いをもたらしているのだという。
著者はフランス料理が世界を席巻した強さの
(1)地方による食材の多様さ
(2)ブランド食材管理の厳しさ
(3)厳格な品質保証制度
(4)一流シェフによる調理法の情報公開
--の四つを挙げている。
それぞれに具体的な記述が豊富で、なるほどとうならせる。
ほかにも、レストラン誕生秘話、ロシア式サービス(一皿ずつのサービスをいう)にまつわる伝説など、逸話にも溢れている。
http://shinshomap.info/theme/french_cuisine_g.html
http://kaze.shinshomap.info/
新書マップ
http://shinshomap.info/search.php
http://bookshelf.shinshomap.info/
11. 食生活
フランス料理とワイン
『フランス料理を料理する : 文明の交差点としてのフランス料理』(湯浅赳男著、新書y)もまた、フランス料理の歴史と魅力を余すことなく紹介した力作である。
とくに、中華とフランス料理の違いについての考察が興味深い。
フランス料理は外交や文化交流の一コマとして世界に普及していったのに対し、中華料理は世界に分散した漢人労働者の食堂として普及した。
日本のサラリーマンが昼飯にはチャーハンやラーメンを食い、結婚式ではフランス料理を食べるのには、そのような背景があったのである。
中華とフランス料理では食材と調理法が違うという指摘もなるほどと思わせる。
内陸部が多い中華の高級食材の大半は乾物なのに対し、フランスでは地方でとれた新鮮な食材を使う。
さらに、中華の調理法は蒸籠が基本であるのに対し、フランスではオーブンを使い、これが両者の特徴に決定的な違いをもたらしているのだという。
著者はフランス料理が世界を席巻した強さの
(1)地方による食材の多様さ
(2)ブランド食材管理の厳しさ
(3)厳格な品質保証制度
(4)一流シェフによる調理法の情報公開
--の四つを挙げている。
それぞれに具体的な記述が豊富で、なるほどとうならせる。
ほかにも、レストラン誕生秘話、ロシア式サービス(一皿ずつのサービスをいう)にまつわる伝説など、逸話にも溢れている。
http://shinshomap.info/theme/french_cuisine_g.html
■COMMUNIO SANCTORUM
VERITAS LIBERABIT VOS―JOHN THE APOSTLE
前原 将太(まえはらしょうた)
専門領域:哲学、政治思想、キリスト教
「亜周辺と知識人―甦るウィットフォーゲル」 湯浅赳男
第1部 「亜周辺と知識人−甦るウィットフォーゲル」 湯浅赳男
第2部 『「東洋的専制主義」論の今日性―還ってきたウィットフォーゲル』を読む
http://akizukiseijin.wordpress.com/2008/11/05/%E3%80%8C%E4%BA%9C%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%A8%E7%9F%A5%E8%AD%98%E4%BA%BA%E2%80%95%E7%94%A6%E3%82%8B%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%80%8D-%E6%B9%AF/
VERITAS LIBERABIT VOS―JOHN THE APOSTLE
前原 将太(まえはらしょうた)
専門領域:哲学、政治思想、キリスト教
「亜周辺と知識人―甦るウィットフォーゲル」 湯浅赳男
第1部 「亜周辺と知識人−甦るウィットフォーゲル」 湯浅赳男
第2部 『「東洋的専制主義」論の今日性―還ってきたウィットフォーゲル』を読む
http://akizukiseijin.wordpress.com/2008/11/05/%E3%80%8C%E4%BA%9C%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%A8%E7%9F%A5%E8%AD%98%E4%BA%BA%E2%80%95%E7%94%A6%E3%82%8B%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%80%8D-%E6%B9%AF/
湯浅赳男-Wikipediaの改訂のための準備ノート:自然葉のブログ 2014/7/10
山口県岩国市生まれ。1953年東京大学文学部仏文学科卒業後、日本育英会(現・独立行政法人日本学生支援機構(JASSO(ジャッソ))に就職、約9年勤務し、労働組合活動に熱中した。
その後退職して、東大大学院に入学、高橋幸八郎教授の下でフランス経済史を専攻、1966年東大大学院経済学研究科MC修了・満期退学。
新潟大学人文学部に勤務し、定年退官後に常磐大学に勤務するもその後退官し、現在は新潟大学名誉教授。
同時期学んだ学友に山之内靖、林道義らがいた。
いわゆる「大塚史学」の系譜(大塚久雄・高橋幸八郎・松田智雄・川島武宜・飯塚浩二ら)に連なっていたが、多様な分野に関心を持ち、現在は既成の学問領域にとらわれない創造的な研究・著述活動を行っている。
研究内容
「『東洋的専制主義』論の今日性」(新評論、2007年11月15日)において、湯浅は研究者としての問題意識は大学院での専攻の西洋経済史・フランス経済史であったが、生涯の知的探検のテーマは3つあったと「あとがき」で書いている。
第一の探検 トロツキズムの真相解明
第二の探検 ウィットフォーゲルの名誉回復
第三の探検 貨幣と権力との間の渓谷の探検
http://blogs.yahoo.co.jp/naturalleaf2006/12588507.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
湯浅赳男/環境と文明 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
湯浅赳男/環境と文明のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6476人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19253人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208309人